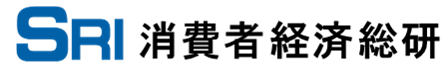アベノミクス成果,評価とは?3本の矢の効果も簡単に総括|消費者経済総研|2022/8/28
| アベノミクスとは? その成果・評価・結果を わかりやすく 総括・総決算し、簡単に解説。 3本の矢(金融緩和・財政政策・成長戦略) の特徴と成果・効果は? アベノミクスの結果は、成功・失敗? それらの理由をデータを基に、 効果なし・あり?を経済の専門家・評論家の 消費者経済総研・松田優幸が解説 今後の内閣の「経済課題」とは? 約20年間8つの歴代内閣では 【安倍内閣だけがGDPプラス成長】だった。 経済で見た安倍内閣は、優等生だった。 消費者経済総研は、 チーフ・コンサルタントの松田優幸を筆頭に、 消費・商業・経済の評論家・専門家として、 わかりやすい解説をお伝えしています。 |
■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 リモートでの出演・取材にも、対応しています。  消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸 ■最新更新日:2022年8月28日 本ページは修正・加筆等で、上書き更新されていく場合があります。 ■ご注意 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、 対応して下さい。また「免責事項」をお読みください |


- ■今回号のポイント
- ◆2012年~2016年の「実感なき景気回復」
2012年~2016年は、GDPも年収水準も上昇した
↓
しかし「年収上昇」を超える「物価上昇」となった
↓
そのため「実感なき景気回復」となってしまった
↓
しかし2017年~は、年収水準が物価水準を超えた
↓
つまり「実感できる景気回復」となったのだ
↓
※この件は、過去号「実感なき景気回復」を参照
◆安倍内閣は、経済優等生だった?
小泉内閣以降の約20年間での、
8つの歴代内閣を、経済で比較し、振り返る
↓
8内閣では、在任期間でGDPを
成長させたのは、安倍内閣(2次)だけだった
↓
2次安倍内閣での経済成長は、
折れ線グラフで見ても明確で、優等生だ
↓
人々の年収も、アベノミクス開始で、
下落から上昇へと、反転した
↓
失業率と、経済の犠牲者数等も、
高い相関性を、示しながら、減少へ
◆2度の消費増税は、余計だった?
しかし、2014年の消費増税で、
消費支出は急落し、経済にブレーキ
↓
せっかく好調だったアベノミクスは、
消費増税で、台無し に
↓
実は、安倍首相は、消費増税に消極的だった?
◆菅内閣以降の内閣の経済課題と、消費税
2021年秋以降の内閣では、
増税路線になる可能性も、消えてはいない。
↓
給付金等を、世の中に供給したほか、
コロナ対策で、政府は様々な支出をした
↓
2021年度は、前年度比
109兆円増の国債を発行した
↓
それを、増税で回収となれば、
再び、生活や経済への、重しになってしまう
↓
ベストな政策は、何か?
(以降は続編で解説予定)
◆本ページの構成は?
本ページは、下記の「2段構成」としている。
前半:アベノミクス 3本の矢 の内容の解説
後半:アベノミクスの成果・評価(成功?or失敗?)
すぐに、「後半の成果・評価」を、見たい場合は、
上の青線・下線部のクリックで移動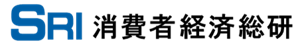
- ■アベノミクスとは ?
- -この項ではわかりやすく簡単に解説する-
アベノミクスとは、
第2次安倍内閣(2012年12月~)の経済政策。
アベノミクスのネーミングは、
安倍前首相の苗字「アベ」に、
経済の英語「エコノミクス」をかけた造語。
1980年代の米国の大統領レーガンの経済政策は
「レーガノミクス」と言われていた。
これにちなんだネーミング。
アベノミクスの目標は、
「デフレからの脱却」と「富の拡大」
この目標を実現する具体的な経済政策が
「3本の矢」である。
「3本の矢」とは、
①金融政策、②財政政策、③成長戦略の3つだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆① 1本目の矢は「金融政策」
日本は、デフレ(物価下落)の状態にあった
↓
下落で、マイナスが、さらなるマイナスを、呼ぶ
↓
会社の売上額も、社員の給料も下がる
↓
そこで「金融緩和」をする※
↓
世の中のお金の量が、増える(量的な金融緩和)
↓
お金が増えると、物の値段が上がる(解説参照)
↓
デフレマインドが払拭へ(マイナス→プラスへ)
↓
モノの値段、会社の売上額、社員の給料も、上がる
※「金融緩和」の具体例は「国債購入」
日銀が、民間銀行等から、国債を買う
↓
民間銀行等には、その売却代金が入る
↓
お金が「日銀→民間へ移動」する
↓
民間部門(世の中)のお金が、増える
↓
これが金融緩和策のうちの「量的緩和策」だ
↓
金融緩和は、他に「低金利策」もある(後述)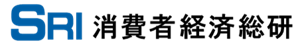
◆② 2本目の矢 「財政政策」を 積極財政へ
*「積極財政」とは?
積極財政では、政府が積極的に、財政支出を増やす
↓
政府が、多くのお金を、支出して、景気拡大させる
*「政府の需要 つまり 政府の支出」とは?
民間需要(=会社の需要+消費者の需要)が弱い
↓
需要が弱く「需要<供給」なので、経済拡大しない
↓
よって、会社の売上も、社員の給料も、上がらない
↓
民間需要が弱いなら、政府が需要を積極的に増やす
↓
政府が需要を増やすとは、政府の支出を増やすこと
↓
「民間需要+政府需要」 →「民間需要+政府需要」へ
↓
「政府需要」が増え、「需要>供給」になる
↓
政府が、経済対策予算で自らお金使って需要を創出
※「財政政策」の具体例は「国土強靭化の工事」
財政支出では、国の予算で「公共事業」などを行う
↓
その1つの例が、インフラを強靭化する工事だ
↓
防災水準が向上する他、お金が「政府→民間へ移動」
↓
受託企業の売上や、その社員の給料が増える
↓
その企業は、取引先への発注額が、増える
↓
その取引先企業の売上や、社員の給料が増える
↓
その社員は、増えた給料で、個人消費を増やす
↓
広く世の中へ、経済効果が循環し広がる
公共事業と聞くと、ダムや博物館などの
無駄なコンクリートや、ハコモノが、連想される。
賢い支出(ワイズ・スペンディング)が、必須だ。
下記の内容が、その例だ。
・教育、福祉、脱炭素、デジタル化などの費用に使う
・(工事なら)豪雨被害を救う「防災・強靭化の工事」
-- 消費者 経済 総研 --
◆③ 3本目の矢「成長戦略」
規制や余計なルールで、新ビジネスが生まれない
↓
規制緩和で、民間企業・個人が、活躍し実力を発揮へ
↓
自由度が増えれば、ビジネス活動が活発になる
※「成長戦略」の具体例は「様々色々」
「成長戦略」は、働き方改革や電力自由化・・・多数
↓
経済成長につながりそうなことを、様々立案した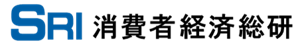
- ■金融緩和が最大の特徴?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆アベノミクスの最大の特徴は?
上記の①②③の3本の矢は、
経済学では、基本的な内容だ。
諸外国でも、似たようなことが、行われている。
アベノミクスでの特徴で、効果的だったのは、
1本目の「①金融政策」を大胆に実施したこと。
それが成果に、つなっがったのは、
「安倍首相が2013年に、日銀総裁に
黒田氏を指名し黒田氏が長年、総裁を務めた」
これが大きい。
「黒田バズーカ砲」「異次元規模の緩和」
などの言葉も生まれた。
とにもかくにも、大胆で徹底的に、
金融緩和を実施したのが特徴だ。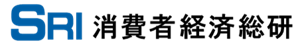
- ■金融緩和の内容は?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆そもそも、「金融緩和策」とは何か?
A 金利を、下げること(低金利策)
B お金の量を、増やすこと(量的緩和策)
上記の2つの手法がある。
そもそも、なぜ、金融緩和策を、するのか?
金融緩和策のメリットは何か?
A 金利下げや、B お金の量の増加で、どうなるか?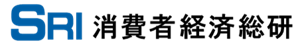
- ■A 低金利 政策 とは?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆A 金利を下げると、どうなる?
例え話で解説する(金額などは仮の数値)
自動車メーカーが、工場の増設を、検討する。
工場増設の費用は、100億円だ。
100億円を、銀行から借金する。
金利10%なら、1年で10億円の利子を負担する。
金利が1%なら、1年で1億円の利子を、負担する。
金利が低いと、企業は工場を、増設しやすい。
工場が増設されれば、車の生産台数が増える。
その増えたクルマを、海外へ輸出する。
こうして、その企業の売上は、増える。
金利を下げれば、経済は拡大する
-- 消費者 経済 総研 --
◆需要サイドは?
前項の自動車メーカーの例え話は、供給サイドだ。
需要サイドでは、どうか?
同じく、例え話で、解説する。
パワーカップルが、1億円の
マンションの購入を、検討している。
住宅ローンの金利が、8%ならば、
1年で、800万円もの金利を、負担する。
金利が0.5%ならば、50万円だ。
1年間で、上記のように、大きな差が出る。
30年間のローンなら、とても大きな差になる。
(※経年で、元本が減れば、支払利子の額も減少する)
低金利は、企業だけでなく、消費者も恩恵がある。
金利が下がれば、
マンション買おうとする人が、増える。
「金利ダウン → マンション需要はアップ」だ。
マンション売上UP
↓
不動産会社の売上UP
↓
関連業界 (家具、家電、引越し等の業界)の売上もUP
↓
不動産業界や、関連業界の、景気が良くなる
↓
様々な業界の「社員の給料もUP」へ
消費拡大すれば、景気も給料もUPする。
-- 消費者 経済 総研 --
◆低金利は、企業にも、消費者にも、プラス
この例え話では、低金利で、
自動車業界、不動産業界・関連業界にプラスだ。
一方、企業だけでなく、消費者にも、恩恵がある。
消費者による住宅、家具・家電の消費に、プラスだ。
そして、消費が拡大すれば、景気も給料もUPする。
-- 消費者 経済 総研 --
◆逆に、「 金利を上げる 」と、どうなるか?
逆に、「 金利を上げた 」場合を、解説する
↓
金利が上がれば、住宅ローンの総支払額が、増える
↓
マンションを、買おうとする人が、減る
↓
「金利アップ → マンション需要は、ダウン」だ
↓
マンション売上は、減る
↓
不動産会社の売上が、減る
↓
関連業界(家具、家電、引越し等)の売上も、減る
↓
不動産業界や、関連業界への、「需要」が、減る
↓
需要が減れば、「値下がり」が、起きる
↓
こうして、金利引き上げで、物価は下がる
インフレが、過熱している時は、
金利を上げて、値下げを、誘導するのだ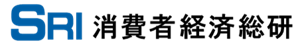
- ■低金利 政策 のやり方とは?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆どうやって金利を下げる?
「金利を、上げ下げ」 するのは、日銀の仕事だ。
日銀の政策金利の目標の値は、下記の通りだ。
・短期金利は、-0.1%(マイナス金利政策)で、
・長期金利は、 0.0%(ゼロ金利政策)だ。
長期金利を、下げるには、どうするか?
↓
日銀が、金融市場で、長期の国債を、たくさん買う
↓
すると、国債が、品薄になる
↓
国債が品薄になると、C:国債の価格は、上がる
↓
A:国債金利 = B:国債の利息の額 ÷ C:国債の価格
↓
C:国債の価格が上がれば、上式の分母が大きくなる
↓
Cの分母が大きくなれば、Aの金利は下がる
-- 消費者 経済 総研 --
◆長期金利を、ゼロ金利水準に維持する方法
市場参加者の動向で、長期金利がUPしたら?
↓
日銀が、市場に介入し、金利を下げるのだ
↓
このやり方を、「指値オペ」などと言う
↓
「指値オペ」の解説は、本ページの下段に掲載中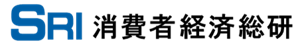
- ■B 量的緩和 政策 とは?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆B お金の量を増やすと、どうなる?
金利が下がっても、融資する資金が不足だと、
自動車メーカーは、借金できない。
借金できなければ、工場の増設ができない。
また、住宅ローンにおいて、融資資金が不足だと、
住宅購入者は、ローンを利用できない。
ローン組めなければ、住宅が買えない人が増える。
そこで「金利を下げる」だけではなく、
「お金の量も、増やす」のだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆量的緩和策は、どうやるのか?
量的緩和策は、
既述の通り「国債の購入」などにより実施される。
民間銀行が保有する国債を、日銀が購入する
↓
すると、購入代金が、日銀→民間銀行に渡る
↓
日銀の国債購入の増加で、民間銀行のお金が増える
↓
民間銀行の「融資用のお金」が増える
↓
これが、量的緩和策の流れだ
-- 消費者 経済 総研 --
◆デフレ・スパイラル からも 脱却?
お金の量が増えれば、物価は上昇方向へ向かう。
量的緩和策は、デフレ脱却効果もある。
-- 消費者 経済 総研 --
◆ミカンの例で、簡単3分解説
インフレ・デフレは、なぜ起こる?発生のメカニズム
「カネの量 > モノの量 」だと、インフレになる。
マネーサプライ(通貨の供給量)が増加すると、
「カネ>モノ」になり、物価が上昇する。
「ミカン」の例えで、簡単に3分で解説する。
例えば、、、
八百屋さんが、「1個100円のミカン」を、
10個売っている、とする。
近所の10人が、100円で1個づつ、買うとする。
◆「カネの量↑> モノの量 」 のケースは?
世の中のお金が、増えたら、どうなる?
近所の人が裕福になったと、八百屋さんは知った。
そこで、ミカン1個を、120円に値上げした。
値上げしても、買い手が裕福になったので売れた。
→カネが増えると、物価上昇(インフレ)になる。
◆「カネの量↓< モノの量 」 のケースでは?
逆に、近所の人のお金が、減ったら、どうなる?
不景気で、お客さんのお財布が、寂しくなった。
いつも通りの100円では、売れ行きが、良くない。
時間がたつと、ミカンは腐ってしまう。
八百屋さんは、「早く売りたい」と考える。
そこで、1個80円に、値下げした。
→カネが減ると、物価下落(デフレ)になる。
◆「 カネの量 >モノの量↓」のケースでは?
モノが減ったら、どうなる?
不作で、入荷が減って、5個しか、在庫がない。
5個×100円=500円の売上では、
八百屋さんは、生活できない。
なので、八百屋さんは、値上げを試みる。
逆に、買い手側の立場では、どうか?
近所の人は、数が少ないから、すぐ売り切れちゃう
と懸念し、高値でも、買う人は、いる。
→モノが減ると、物価上昇(インフレ)になる。
◆「 カネの量 <モノの量↑」のケースでは?
逆に、モノが増えたら、どうなる?
豊作で、20個も入荷し、在庫がある。
たくさんのミカンがあり、時間がたつと腐る。
八百屋さんは、「早く売りたい」と考える。
そこで1個50円に値下げした。
そうしたら、いつも通りの1000円を、売り上げた。
(50円×10人×2個=1000円)
→ モノが増えると、物価下落(デフレ)になる。
こうして「カネの量」「モノの量」の
バランスで、物価の上昇・下落が、決まる。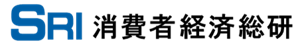
- ■A+Bの2つの「金融緩和策」
- -- 消費者 経済 総研 --
◆2つの「金融緩和策」で、経済を立て直しへ
A 低金利策 (ゼロ金利・マイナス金利策)
B 量的緩和策 (お金の量を増やす)
金融緩和策(低金利策+量的緩和策)すれば、
景気は拡大するのだ。
金融緩和で、企業にも消費者にもプラスで、
景気も拡大へ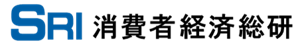
- ■低金利を、維持するには、指値オペ?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆低金利を、維持するために、指値オペ?
国債は、様々な主体が、市場で、売買取引している
国債の売り>国債の買いと、売り側が強いと?
↓
C:国債の価格は、下がってしまう
↓
A:国債金利 = B:国債の利息の額 ÷ C:国債の価格
↓
C:国債の価格が下がれば、上式の分母が小さくなる
↓
Cの分母が小さくなれば、A分子の金利は上がる
↓
日銀は長期金利を政策目標を、ゼロ金利としている
↓
しかし誤差範囲(±0.25%)までは、許容する
↓
国債金利が0%より上がっても、0.25%までとする
↓
0.25%超に、なりそうな時は、日銀は市場に介入
↓
国債を無制限に大量に、日銀が購入する
↓
大量購入で国債が品薄になり、C:国債の価格UP
↓
A:国債金利 = B:国債の利息の額 ÷ C:国債の価格
↓
C:国債の価格が上がれば、上式の分母が大きくなる
↓
Cの分母が大きくなれば、Aの金利は下がる
-- 消費者 経済 総研 --
◆2022年に、オペが実行された?
2022年は、年初から、金利は上昇してしまった。
2022年2月11日は、10年国債は0.25%を超えた。
ゼロ金利政策の誘導範囲の+0.25%を超えたのだ。
日銀は、金利を下げる方向に、動き出す。
その下げる手法に「国債購入オペ」がある。
日銀は、国債購入オペを、
2022年2月14日に実施すると、公表した。
その公表日は、2月10日だった。
その時点では、まだ0.25%に、至ってない。
しかし日銀は0.25%突破すると、よんだのだろう。
「国債買入オペ」とは、
日銀が行うオペレーション(公開市場操作)の一つ。
長期国債の購入量を、増額することだ。
価格は、需要と供給のバランスできまる。
需要>供給 ならば、価格上昇で、
需要<供給ならば、価格下落だ。
日銀が国債の購入を増やすと、どうなるか?
需要>供給となり、国債の価格は、上昇する。
金利 = 利子(分子) ÷ 国債の価格(分母)だ。
価格(分母)が上昇すると、金利は低下する。
日銀の国債買入が増えれば、国債の価格は上昇だ。
分母の国債価格の上昇は、金利低下となる。
これで上昇した国債金利を、下げることができる。
ゼロ金利政策の上限+0.25%より、
「上の金利にはしない」との日銀の意思表明だ。
なお、国債買入オペには、
「利回り入札方式」と「固定利回り方式」の2種ある。
「利回り入札方式」では、
高い金利(低い価格)のオファーから買う競争入札。
「固定利回り方式」は、
日銀が指定する金利で、買入れをする。
これを、「指し値オペ」ともいう。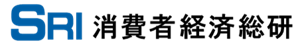
- ■経済成長した 唯一の内閣 とは ?
- ◆はじめに
まずはじめに、成果・効果の評価の前に
消費者経済総研は、特定の政党・内閣に、
肯定・否定の姿勢をとっていない。
政党や政権ではなく、
あくまで「政策」にフォーカスしている。
-- 消費者 経済 総研 --
◆8の内閣の中では?
2次安倍内閣は、最長の内閣となった。
その前の長期の内閣は、小泉内閣で5年5か月。
歴代内閣を、小泉内閣以降の約20年間で振り返る。
本稿では「経済」に着目する。
小泉内閣以降は、
安倍内閣(1次)、福田内閣、麻生内閣、
鳩山内閣、菅内閣、野田内閣、安倍内閣(2次)と、
8つの内閣があった。
経済指標では、まずは、
GDP(国内総生産)で見てみる。
各首相が、着任した時から退任する時までの間に、
GDPがどれだけ成長したかを注目する。
上記の8内閣では、在任期間で、
GDPを成長させたのは、安倍内閣(2次)だけ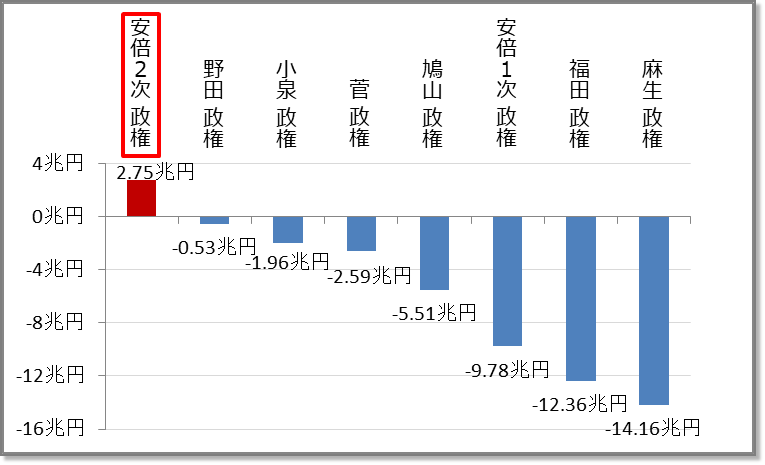
※出典:内閣府 国内総生産 四半期 名目原系列(初稿時点)
※内閣期間
左から、内閣名:内閣の始期~終期 | 四半期GDPの始期~終期の割り当て期
1Q:1~3月、2Q:4~6月、3Q:7~9月、4Q:10~12月
小泉内閣 :2001/4/26~2006/9/26|2001/2Q~2006/3Q
1次安倍内閣 :2006/9/26~2007/9/26|2006/4Q~2007/3Q
福田内閣 :2007/9/26~2008/9/24|2007/4Q~2008/3Q
麻生内閣 :2008/9/24~2009/9/16|2008/4Q~2009/3Q
鳩山内閣 :2009/9/16~2010/6/08|2009/4Q~2010/2Q
菅内閣 :2010/6/8~2011/9/02|2010/3Q~2011/3Q
野田内閣 :2011/9/2~2012/12/26|2011/4Q~2012/4Q
2次安倍内閣 :2012/12/26~2012/9/14|2013/1Q~2020/2Q
※四半期GDPの額(単位:兆円)
始期の額~終期の額。右は、終期額と始期額の差
小泉内閣 :130.09 ~ 128.13 - 1.96
安倍1次内閣 :139.16 ~ 129.39 - 9.78
福田内閣 :138.75 ~ 126.39 -12.36
麻生内閣 :133.67 ~ 119.51 -14.16
鳩山内閣 :128.92 ~ 123.41 - 5.51
菅内閣 :124.11 ~ 121.52 - 2.59
野田内閣 :128.90 ~ 128.37 - 0.53
安倍2次内閣 :123.29 ~ 126.04 2.75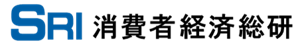
- ■ グラフで見る安倍内閣の経済成長
- 折れ線グラフで見ても、経済成長は明確。
2次安倍内閣のGDPでは、成果・効果ありである。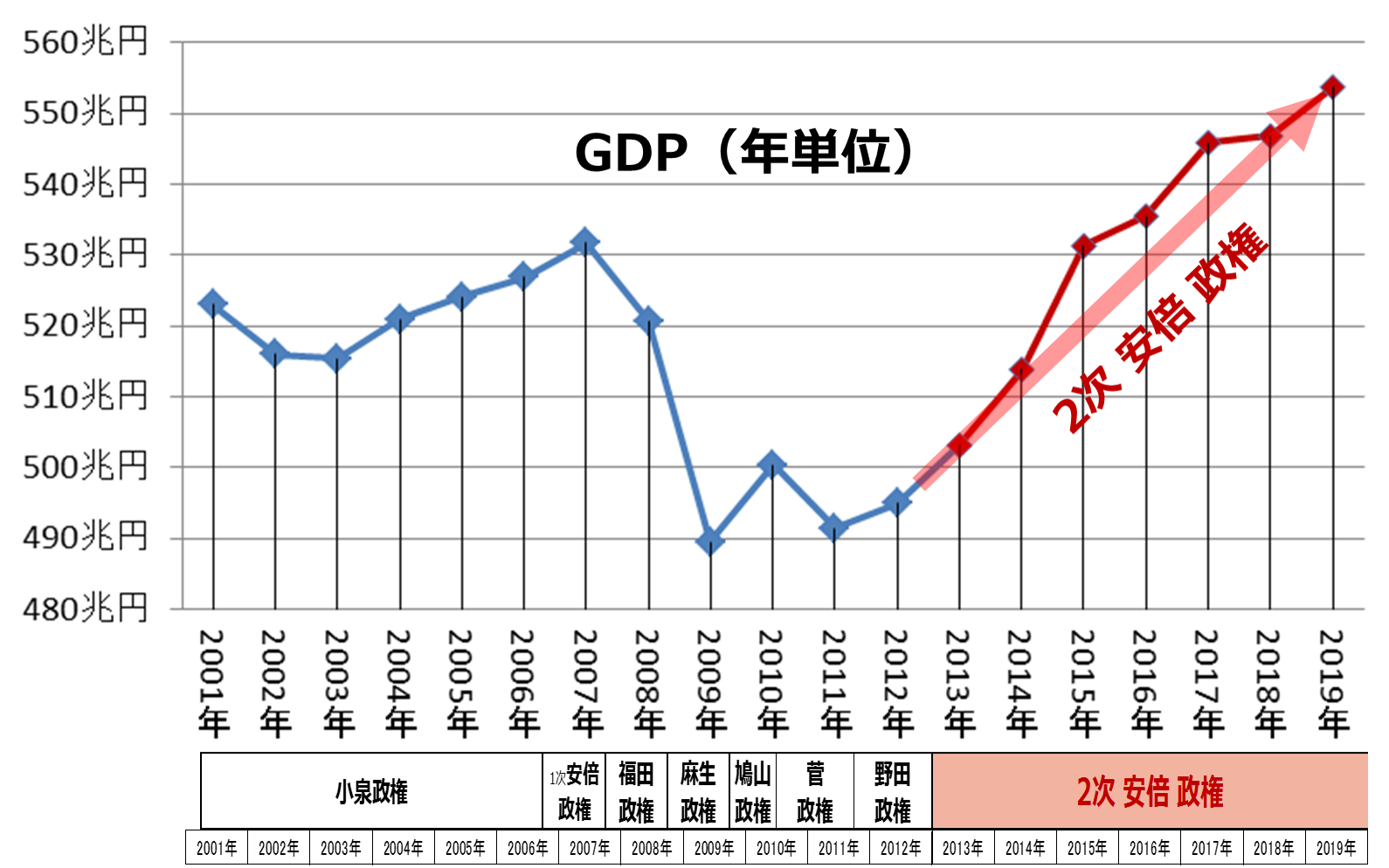
※出典:内閣府 国内総生産 名目暦年
※前項のGDPは四半期単位の額で、
このグラフは、年単位(暦年)の値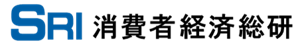
- ■ 国民の年収は?
- 2次安倍内閣では、人々の年収も上昇した。
平成元年からの長期トレンドで見てみる。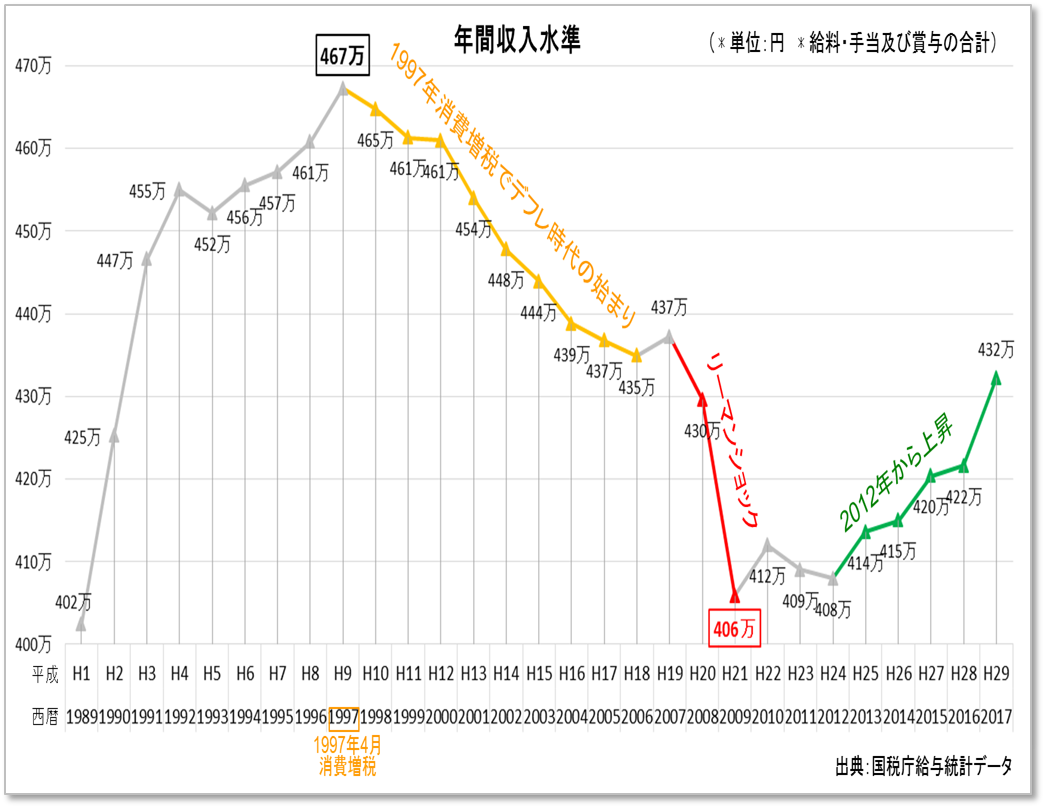
1989年(H1)から1997年(H9)まで、
年収水準は、上昇した。
1997年(H9)の4月に、消費税率が3%→5%
に増税の「消費増税ショック」があった。
これにより、9年間にわたり下落に転じた。
デフレ時代の始まりである。
その後、2007年(H19)に、米国の金融商品等の
価格上昇を伴う好景気があった。
日本国内景気も恩恵を受け、年収も反転上昇した。
しかしリーマンショックで、再度下落した。
その下落幅は、平成時代で、最大となった。
H24年(2012年)12月26日に、安倍内閣が誕生。
のちに「アベノミクス」が始まる。
長く続いたデフレ基調のダウントレンドは
終了し、年収水準は上昇を続けた。
こうして、2次安倍内閣では、
人々の年収は、下落から反転し、上昇した。
-- 消費者 経済 総研 --
◆実質年収では?
物価変動の影響を除いた「実質年収」でも、
アベノミクスで、上昇している。
*00年代は?
その前の、21世紀の00年代では、どうか?
下図のように、下落トレンドである。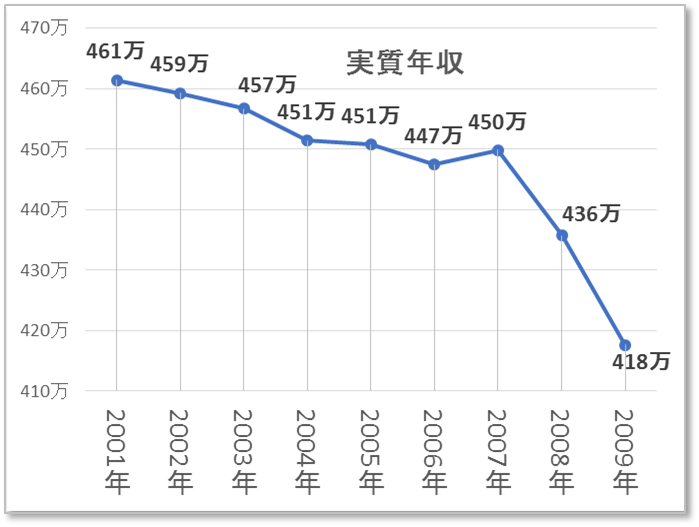
*アベノミクス前半は?
アベノミクスの前半の2012年~2016年は、
実質年収は、下図の通り、低迷していた。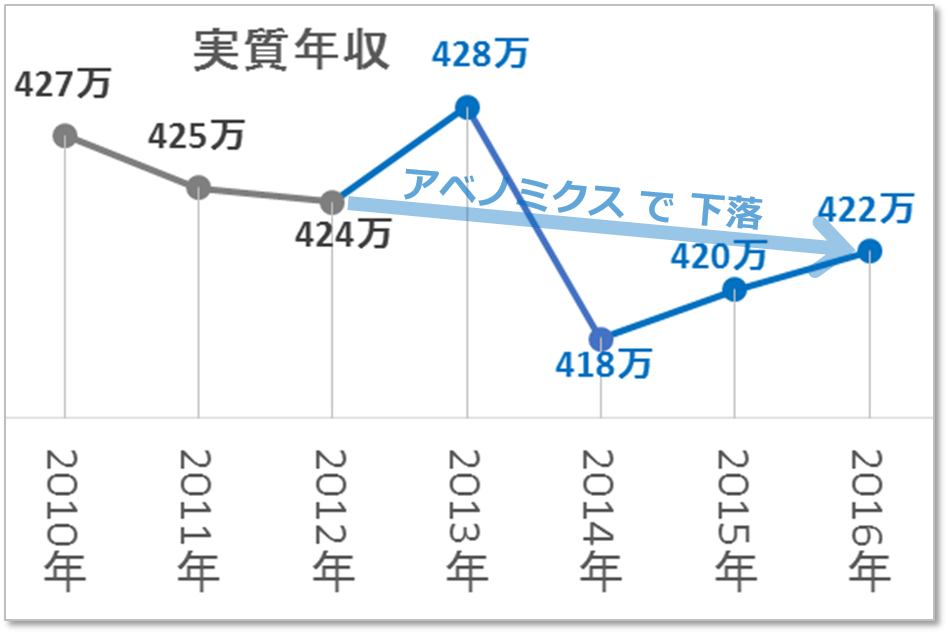
この期間2012~2016年のGDPは、拡大を続け
日本の景気は回復していった。
しかし実質年収は、上図のように下落した。
よって「実感なき景気回復」である。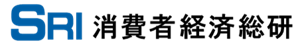
*アベノミクスの後半は?
しかし、2017年からは、実質年収は
アベノミクス開始時よりも、高い水準になった。
(2012年:424万円 → 2018年:435万円)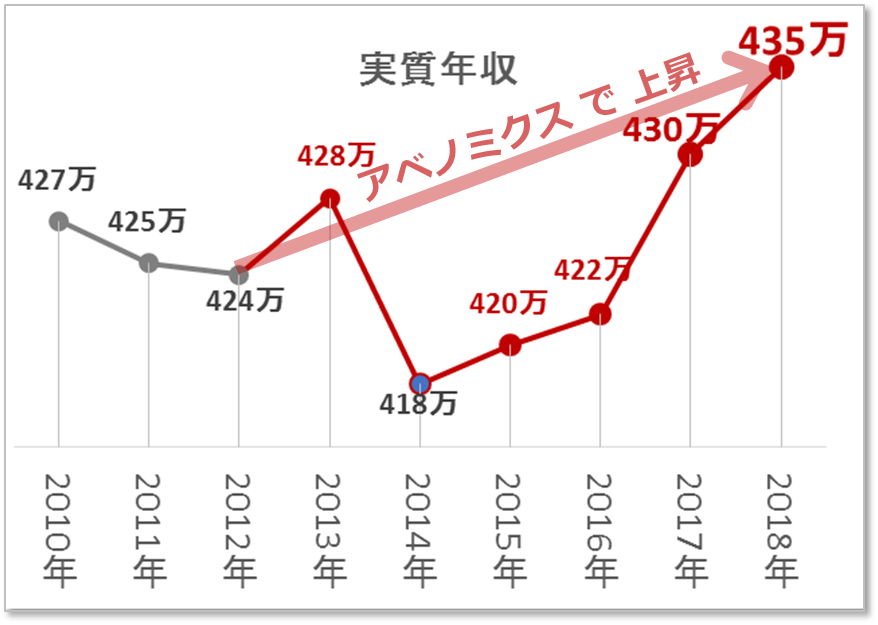
上記グラフから、2017年には、
年収が、物価水準を超えて上昇した。
つまり2017年から
「実感ある景気回復」になった。
*この期間で、下落は1回
2014年以外は、順調に上昇したが、
2014年だけ下落した。
その原因は何か?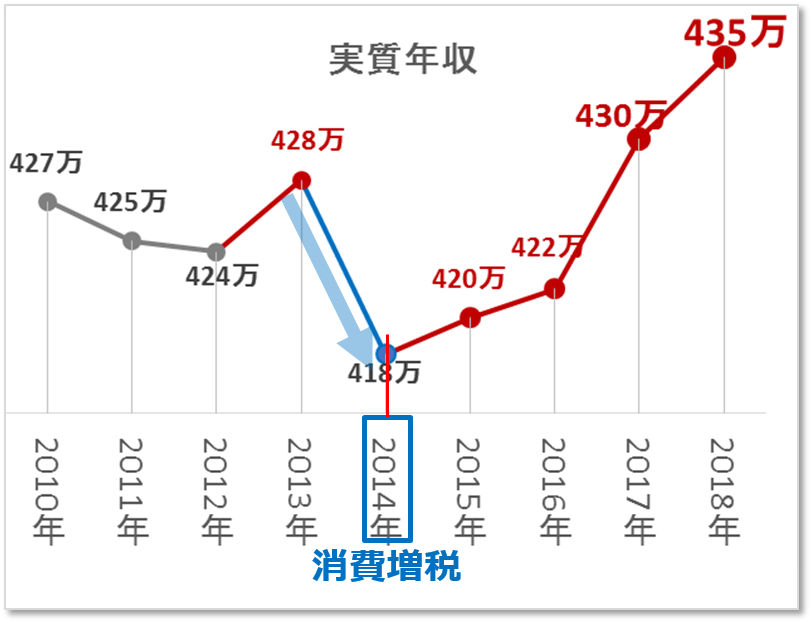
2014年の急落は、消費増税の影響である。
ここでも「消費増税は余計」だとわかる。
※実質年収の計算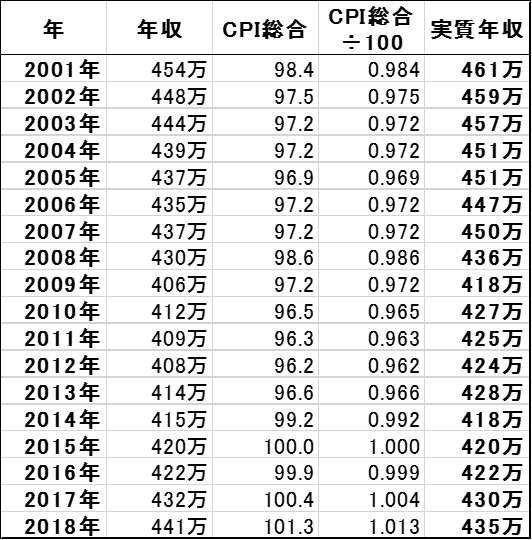
※実質年収 = 年収 ÷(CPI総合÷100)
※出典
・年収:国税庁民間給与実態統計調査結果
・CPI総合:総務省統計局 消費者物価指数
- ご注意 -
※年収や賃金データには、
上記の「国税庁 民間給与実態統計」以外に、
「厚生労働省 毎月勤労統計」もある。
しかし後者は、連続性の喪失問題や、
不正の発覚など、信頼性が無いため、採用できない。
よって本稿では「国税庁データ」を採用している。
※「毎月勤労統計」の諸問題とは、
・勤労統計の2004~2011年のデータは、
紛失・廃棄され、正確な実質賃金は不明である点。
・また2018年1月から調査方式が変更され、
それ以前と以後の実質賃金の比較が、できない点。
※アベノミクス期間の実質年収は、
「国税庁 民間給与実態統計」ではプラスで、
一方「毎月勤労統計」では、マイナスである。
※アベノミクスの批判論では、
上記のとおり、信頼性もなく、連続比較もできない
「毎月勤労統計」を、エビデンスとして
アベノミクス批判が、なされる試みが多すぎる。
賃金トレンドを把握するには、注意が必要だ。
※なお、両者の違いは
賃金関連統計の比較検証 総務省統計委員会の比較表(14P)を参照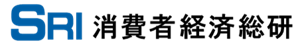
- ■失業率や、経済犠牲者数は?
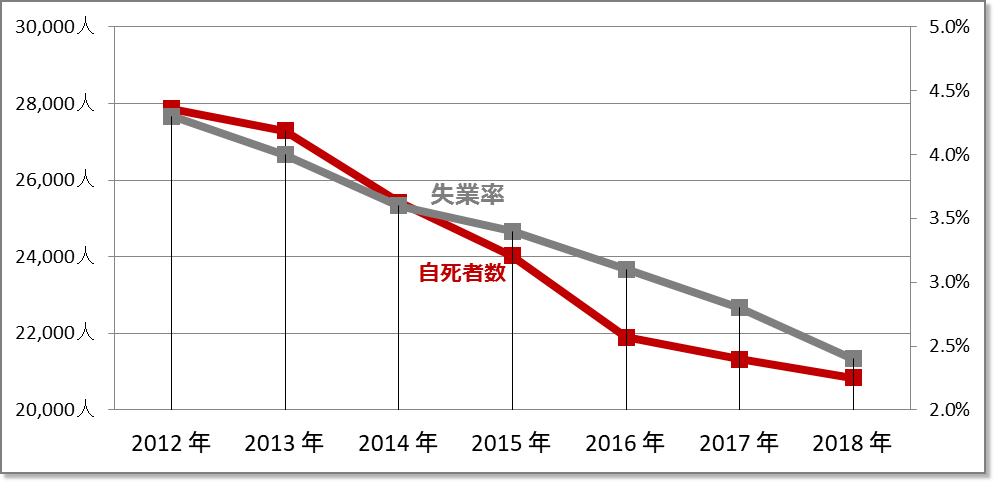
第2次安倍政権は、2012年に誕生した。
アベノミクスで、失業率は、減少していった。
同様に、自ら命を絶つ人数も、減少していった。
後述するが1997年の消費増税で、
失業率・自から絶つ人数は、共に上昇した。
しかし、アベノミクスでは、両方減少した。
アベノミクス6年間での「失業率」「自絶数」は
「相関係数0.97」と、高い相関関係が示された。
※失業率 出典:総務省統計局 労働力調査
長期時系列データ 完全失業率 総数
2012年4.3% 2013年4.0% 2014年3.6% 2015年3.4% 2016年3.1% 2017年2.8% 2018年2.4%
※自から断つ数 出典:厚生労働省
参考統計資料[警察庁統計]
2012年27,858人 2013年27,283人 2014年25,427人 2015年24,025人 2016年21,897人
2017年21,321人 2018年20,840人
-- 消費者 経済 総研 --
◆1997年の消費増税では?
安倍内閣の前の時期だが、参考までに
「1997年の消費増税ショック」の影響も見る。
下記のグラフの通り、失業率が増加すると、
自ら絶つ数も、増えてしまった。
1998年は、前年の2.4万人→3.3万人へ急増した。
1994~1998年で見ると
「失業率」と「自ら絶つ数」は、相関性が高い。
相関係数を分析すると「0.95」である。
1.0に近く、かなり高い相関性が、認められる。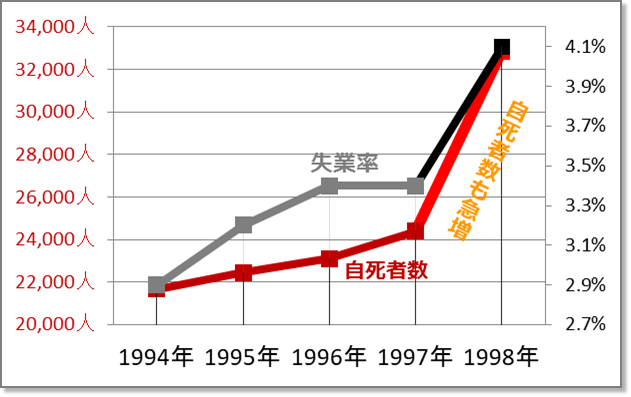
※失業率 出典:総務省統計局 労働力調査
長期時系列データ 完全失業率 総数
1994年2.9% 1995年3.2% 1996年3.4% 1997年3.4% 1998年4.1%
※自ら断つ数 出典:厚生労働省
参考統計資料[警察庁統計]
1994年21,679人 1995年22,445人 1996年23,104人 1997年24,391人 1998年32,863人
- ■ アベノミクスも、消費増税で、台無し
- GDPの概略内訳は、
・約60%が個人消費等、
・約25%が公共支出・投資、
・約15%が企業の設備投資だ。
つまり、経済のメイン・エンジンは「個人消費」
そこで、GDPの内訳の個別項目の中の
「消費支出」に、注目してみる。
2008年度のリーマンショックで、
消費支出は下落したが、その後、反転上昇した。
2013年度からアベノミクスが、始まった。
下図の「緑の➡」が、アベノミクス効果である。
黄色矢印よりも、伸び率はアップしている。
つまりアベノミクスで、消費支出は、加速した。
しかし、2014年の消費増税で、急落した。
アベノミクスは、消費増税で、台無しとなった。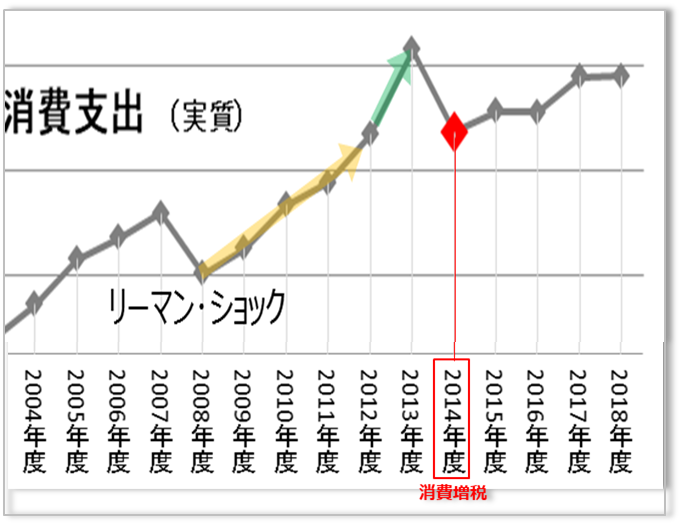
安倍内閣は、2014年と2019年と、
2回も消費増税を実施した。
この消費増税がなければ、かなりの好景気が、
実現されていた可能性がある。
経済成長が高まれば、
税率がそのままでも、税収は増える。
これを「自然増収」と言う。
経済成長が進展すれば、
税率を上げなくても、税収は増えるのだ。
約20年間の8の内閣のGDP増加額の比較から、
安倍内閣の経済政策は、トップの優等生だった。
一方マイナス評価は、2度にわたる消費増税だ。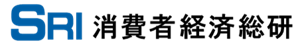
- ■ 次の内閣での「経済政策の課題」 とは ?
- ◆安倍前首相は、消費増税に、消極的だった?
安倍首相は、消費増税には、もともと消極的だった。
2次安倍内閣では、
消費増税を、繰り返し延期したのが、その証拠だ。
ならば、消費増税をやらなければ、よかったのだ。
この点は、菅内閣以降の課題となる。
-- 消費者 経済 総研 --
◆次の菅首相は?
菅首相は、就任直前に消費増税を肯定した。
(後日、この肯定発言は修正)
増税路線になる可能性は、消えてはいない。
今後の首相が、菅氏以外になった場合も
消費増税の可能性がある。
2020年度は、コロナ禍への経済対策等で、
対前年度比109兆円増の国債発行をした。
コロナ危機への救済で、給付金等が、支給された。
それを、増税で回収となれば、
再び、国民生活や経済への、重しとなる。
- ■「東京新聞」が、消費者経済総研・松田優幸を取材
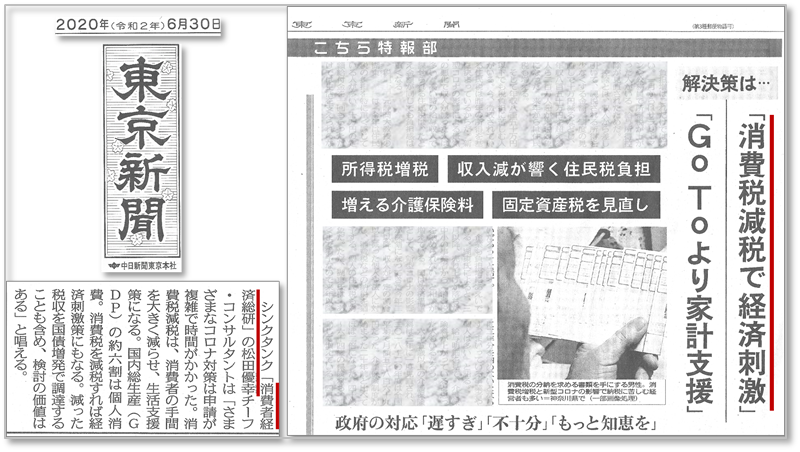
準全国紙の 東京新聞(2020年6月30日)から、
筆者(松田)が、取材を受け、
消費税の減税に関する内容が掲載されました。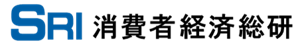
- ■続編や関連ページは?
- ◆続編のページは?
アベノミクスは消費増税で台無しになった。
では、消費税を減税したら、どうなる?
消費税の減税効果の下記ページもご覧頂きたい。
「消費税|減税の効果・メリット,増税の影響・デメリット」
◆関連ページは?
本稿では「実感なき景気回復」「実感ある景気回復」
が登場した。
「実感なき景気回復」と「物価と賃金」の関係の
詳細解説の下記ページも、ご覧頂きたい。
「実感なき景気回復とは?|わかりやすく3分解説」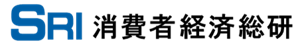
| ■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので、 「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆である事を念頭に置いて下さい。 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、 対応して下さい。また「免責事項 」をお読みください。 ■引用 真っ暗なトンネルの中から出ようとするとき、 出口が見えないと大変不安です。 しかし「出口は1km先」などの情報があれば、 真っ暗なトンネルの中でも、希望の気持ちを持てます。 また、コロナ禍では、マイナスの情報が飛び交い、 過度に悲観してしまう人もいます。 不安で苦しんでいる人に、出口(アフターコロナ)という プラス情報も発信することで、 人々の笑顔に貢献したく思います。 つきましては、皆さまに、本ページの引用や、 URLの紹介などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件をご覧下さい。 |
- 【著作者 プロフィール】
- ■松田 優幸 経歴
(消費者経済|チーフ・コンサルタント)
◆1986年 私立 武蔵高校 卒業
◆1991年 慶応大学 経済学部 卒業
*経済学部4年間で、下記を専攻
・マクロ経済学(GDP、失業率、物価、投資、貿易等)
・ミクロ経済学(家計、消費者、企業、生産者、市場)
・労働経済
*経済学科 高山研究室の2年間 にて、
・貿易経済学・環境経済学を研究
◆慶応大学を卒業後、東急不動産(株)、
東急(株)、(株)リテール エステートで勤務
*1991年、東急不動産に新卒入社し、
途中、親会社の東急(株)に、逆出向※
※親会社とは、広義・慣用句での親会社
*2005年、消費・商業・経済のコンサルティング
会社のリテールエステートに移籍
*東急グループでは、
消費経済の最前線である店舗・商業施設等を担当。
各種施設の企画開発・運営、店舗指導、接客等で、
消費の現場の最前線に立つ
*リテールエステートでは、
全国の消費経済の現場を調査・分析。
その数は、受託調査+自主調査で多岐にわたる。
商業コンサルとして、店舗企業・約5000社を、
リサーチ・分析したデータベースも構築
◆25年間の間「個人投資家」としても、活動中
株式の投資家として、
マクロ経済(金利、GDP、物価、貿易、為替)の分析や
ミクロ経済(企業動向、決算、市場)の分析にも、
注力している。
◆近年は、
消費・経済・商業・店舗・ヒットトレンド等で、
番組出演、執筆・寄稿、セミナー・講演で活動
◆現 在は、
消費者経済総研 チーフ・コンサルタント
兼、(株)リテール エステート リテール事業部長
◆資格は、
ファイナンシャル・プランナーほか
■当総研について
◆研究所概要
*名 称 : 消費者経済総研
*所在地 : 東京都新宿区新宿6-29-20
*代表者 : 松田優子
*U R L : https://retail-e.com/souken.html
*事業内容: 消費・商業・経済の、
調査・分析・予測のシンクタンク
◆会社概要
「消費者経済総研」は、
株式会社リテールエステート内の研究部署です。
従来の「(株)リテールエステート リテール事業部
消費者経済研究室」を分離・改称し設立
*会社名:株式会社リテールエステート
*所在地:東京都新宿区新宿6-29-20
*代表者:松田優子
*設立 :2000 年(平成12年)
*事業内容:商業・消費・経済のコンサルティング
■松田優幸が登壇のセミナーの様子
- ご案内・ご注意事項
- *消費者経済総研のサイト内の
情報の無断転載は禁止です。
*NET上へ「引用掲載」する場合は、
①出典明記
②当総研サイトの「該当ページに、リンク」を貼る。
上記の①②の2つを同時に満たす場合は、
事前許可も事後連絡も不要で、引用できます。
①②を同時に満たせば、引用する
文字数・情報量の制限は、特にありません。
(もっと言いますと、
①②を同時に満したうえで、拡散は歓迎です)
*テレビ局等のメディアの方は、
取材対応での情報提供となりますので、
ご連絡下さい。
*本サイト内の情報は、正確性、完全性、有効性等は、保証されません。本サイトの情報に基づき損害が生じても、当方は一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。
- 取材等のご依頼 ご連絡お待ちしています
- メール: toiawase★s-souken.jp(★をアットマークに変えて下さい)
電 話: 03-3462-7997 (離席中が続く場合は、メール活用願います)
- チーフ・コンサルタント 松田優幸
-