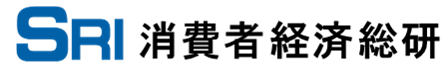【賃上げ 収入UP方法 ベスト10】安い低い日本の賃金給与を上げるには?|消費者経済総研|2022/7/24
■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 リモートでの出演・取材にも、対応しています  消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸 ■最新稿:2022年7月24日 本ページは、修正・加筆等で、 上書き更新されていく場合があります。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆であることを念頭に置いて下さい。 本ページ内容に関しては、自らの責任において対応して下さい。 また「免責事項」をお読みください ■引用 皆さまに、本ページの引用や、 リンク設定などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件 をご覧下さい。 |
- ■連載シリーズ|ニッポン爆上げ作戦
- 【連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦】は、
下記の 全3部で、構成 (予定)
第1部:収 入 爆上げ 作戦
第2部:景 気 爆上げ 作戦
第3部:生産性 爆上げ 作戦
▼第1部は 「 ニッポン 賃金収入 爆上げ 」
「賃金」のほか、「賃金以外の総収入」も上げる。
▼第2部は 「 ニッポン 景気 爆上げ 」
日本の「経済全体」 を UPする。
「消費者も、企業も、株主も」 潤う、全体の底上げ。
経済全体をUPし、GDP成長を、高める。
▼第3部は 「 ニッポン 生産性 爆上げ 」
生産性をUPし、ビジネスでの利益をUP
企業の生産性を上げ、企業の利益を上げる。
ビジネス改善の手法を、提言
-- 消費者 経済 総研 --
◆消費者・働き手も、企業も、株主も?
【連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦】は、
企業も、株主も、消費者・働き手も、潤う提言だ。
つまり 「 働き手の 賃金UP 」 だけではない。
企業の 売上UP
↓
企業の 利益UP
↓
働き手の 賃金UP + 株主への配当UP・株価UP
↓
個人消費UP (GDPは、6割が個人消費)
↓
GDPのUP
↓
ニッポン全体がUP
このように、各主体、そして全体が、好循環で、潤う
「ニッポン 爆上げ 作戦」である。
この連載シリーズは、政策提言でもある。

- ■【 爆上 作戦| 賃金 編 】
- -- 消費者 経済 総研 --
◆第1部は、賃金収入 UP 編
日本の「消費者」の多くは、「働き手」でもある。
しかし、働き手の賃金が、上がらない。
第1部は「私たちの収入UP」の手法を、提言する。
-- 消費者 経済 総研 --
◆今回更新は、「 第1部の第4回目 」
賃上げ・収入UPの政策案を、
ランキング形式で、ベスト10を発表

- ■収入爆上げ の方法 ベスト10
- ランキング形式で、賃金収入UP策 ベスト10 提言
収入UPの効果の「高さ・容易さ・早さ」を、
総合的に勘案し、順位付けをした。
賃金や収入を、上げるには、
下記の10の方策・方法を、提言する。
◆2位 雇用条件の 交渉促進
◆3位 副業の促進
◆4位 1億 総株主
◆5位 アメ版|賃上げ税制の 強化
◆6位 ムチ版|賃上げ税制
◆7位 ボーナスへシフト
◆8位 解雇規制 の 緩和
◆9位 公務員の 賃金水準UP
◆10位 最低賃金UP
そして1位は?
◆1位 働き手が 〇〇〇〇?
「1位」 は、本ページの 一番下に、記載。
まずは、2位~10位を、掲載・提言する。

- ■2位 賃上げの 交渉促進
- -- 消費者 経済 総研 --
◆賃上げの 交渉促進 とは?
① 「 個人 での 交渉 」 の活性化
② 「 団体 での 交渉 」 の活性化
上記2件を、提言する。
-- 消費者 経済 総研 --
◆現状と課題は?
「交渉で、賃上げする。 この意識が、低すぎる」
これが、日本人の課題だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆賃金交渉|外国人は積極的、日本人は消極的?
「賃金の交渉」 に、関する国際調査がある。(出典後掲)
調査の対象国は、
日本+海外4か国(米・中・仏・デンマーク)だ。
この国際比較の調査からは、
「日本人の 賃金交渉は、消極的」なのが、顕著だ。
まずは、入社時・入社後での賃金交渉を、見てみる。
-- 消費者 経済 総研 --
◆入社時(転職時)の賃金要望は?
入社時に「会社からの提示額で合意」した割合は?
・中国は、11%しかいない
・海外4か国の中で、最多の米国でも28%だけだ
・日本人は、62%もいる
日本人の転職の賃金は、会社の言いなりが、多い
-- 消費者 経済 総研 --
◆入社の「後」の 賃金交渉は?
前項は、「入社時」の賃金交渉だった。
では、「 入社後 」 では、どうか?
同じく、日本+海外4か国での調査結果だ。
「入社後に、賃上げを、求めた事は無い」の割合は?
・日本人は、求めた事は無いが、71%もいる
・中国は5%だけだ。 多い方の米国でも29%だ
入社の前も後も、日本人の賃金交渉は、消極的
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本人は、賃金意識 低い?
「賃金の決定要因は、何か?」 との調査項目もある。
賃金の決定要因は、「わからない」と回答したのは?
・日本人は、33%で、最も多い
・他の4か国は、1%~14%しかない
そもそも、賃金決定への意識が、日本人は低い
-- 消費者 経済 総研 --
前項までで、日本人の特徴は、下記だった。
・入社する前の 賃金交渉に 消極的
・入社した後の 賃金交渉に 消極的
・そもそも 賃金決定に、関心薄い
続いて日本の賃金交渉を、下記の順で、見ていく。
① 「 個人交渉 」
② 「 団体交渉 」
-- 消費者 経済 総研 --
◆ ① 日本は、「個人交渉」が、少ない?
▼「 給料上げて 」 とは、言えないニッポン人
日本のサラリーマンは、賃金に不満があっても、
会社や上司への賃上げ交渉は、やりにくい。
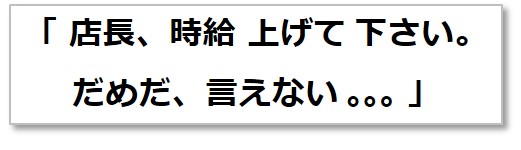
乃木坂46の齋藤 飛鳥さんのバイトルのCMだ。
※画像出典+公式CM動画:
乃木坂46、DAIGO主演!バイトルcm
「営業さん、交渉する」篇バイトル公式チャンネル
▼個人交渉|日本+海外4か国 の調査では?
「個人での個別交渉が、賃金を決めるか?」
との設問での回答は、どうか?
・「個別交渉で賃金決定」は、日本は20%だけだ
・他の4か国では、56%~65%もいる
-- 消費者 経済 総研 --
◆② 日本は、「団体交渉」も 低迷?
前項は、「① 個人交渉」 についてだった。
続いて、「② 団体交渉」 を、解説する。
▼日本+海外4か国 の調査では?
「労働組合での団体交渉が、賃金を決めるか?」
との設問での回答は、どうか?
・労組団交で賃金決定は、日本は20%だけ
・他の4か国では、29%~51%もいる
※ここまでの「日本+海外4か国調査」の出典は、
Works Report 2020 5カ国リレーション調査 データ集
▼米国の スタバや、GAFAの 労働組合は?
アメリカでは、労組の結成へ向けた動きが、ある。
「スターバックス社」では、労組結成が続いている。
GAFAでも、アマゾン社や、アップル社では、
現在、組合の結成が、目指されている。
※出典:CNN|労組結成目指すNYアップル...スタバやアマゾンに追随
▼日本の労組の組織率は、低下?
「団体交渉」は、「労働組合」という組織で行われる。
下図の通り、日本の労組の組織率は、低下した。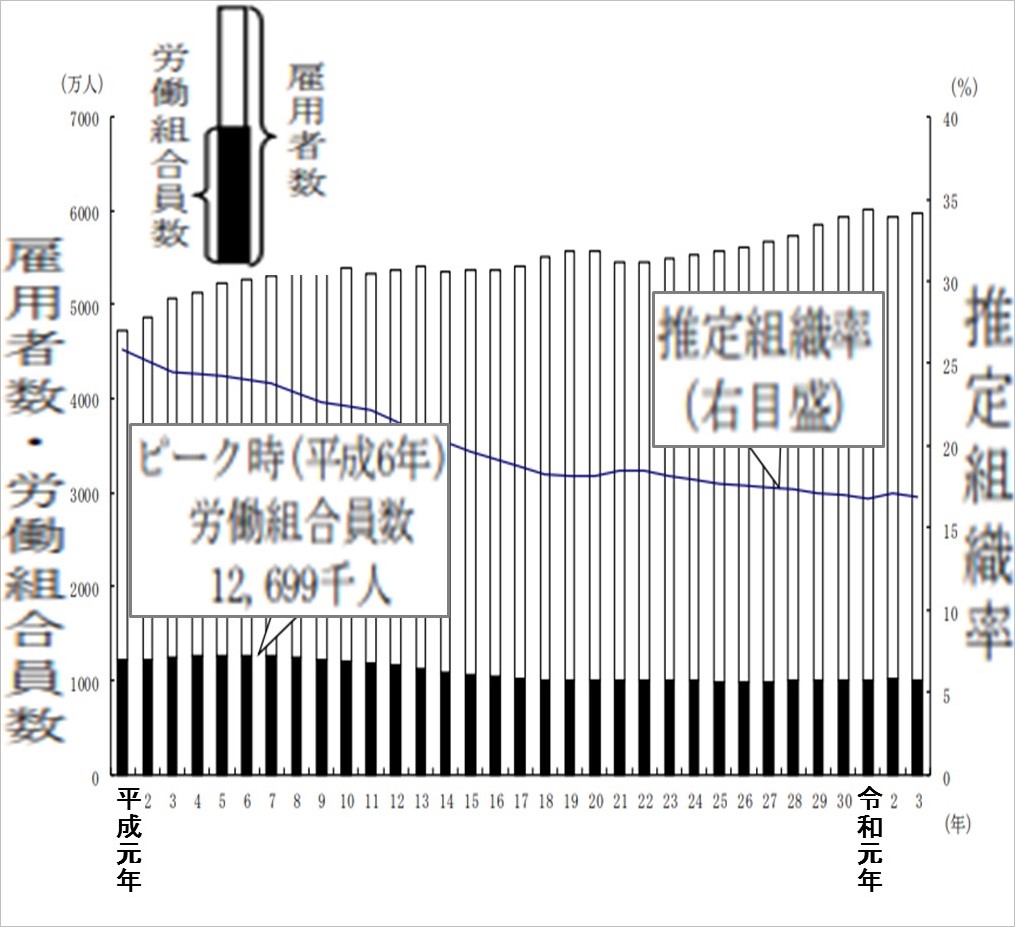 ※出典: 厚生労働省|令和3年労働組合基礎調査の概況
※出典: 厚生労働省|令和3年労働組合基礎調査の概況
▼日本のユニークな賃金交渉 「官製春闘」とは?
「賃上げ → 消費拡大 → 景気拡大」
この流れを、政府も、当然に意識している。
日本の春闘では、総理大臣が、
経済界・経営陣へ「賃上げの要請」を、続けてきた。
7年連続で、安倍元首相が、賃上げ要請を続けた。
※出典:日経新聞電子版| 2019/12/26|
首相が7年連続賃上げ要請...
政府も、「賃上げすべき」との意思は、強いのだ。
これは「官製春闘」と言われた。
既述の通り、労組の組織率は、低下した。
春闘での団体交渉も、低迷傾向だ。
その「低迷分を、首相が補っている」とも見える。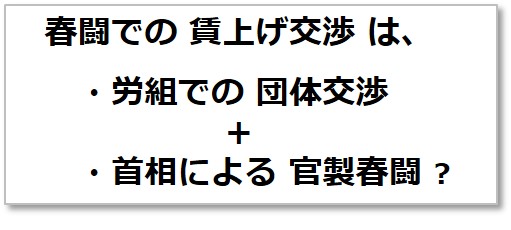
岸田首相も、トヨタ自動車の豊田社長との面談で、
賃上げへの話を、している。
-- 消費者 経済 総研 --
◆積極的に、賃金交渉を
▼まずは「個人交渉」を
我慢していても、黙っていても、賃金はUPしない。
「店長、時給 上げて下さい 」 のCMのように、
交渉することは、賃上げに、つながる。
しかし、社員1人で、交渉するのは、やりにくい。
エンゼルス球団と、大谷選手の代理人バレロ氏が、
契約の延長について、交渉をしたと、報じられた。
個人交渉を、「代理人」で、行うことも、考えられる。
しかし、日本では、どうだろうか?
会社の上司や人事部への賃金交渉を、
弁護士に頼むのは、現実的ではないだろう。
自分で自ら交渉する方が、現実的だろう。
交渉は、自分ひとりでも、十分できる。
既述の通り、海外では「個人交渉は積極的」だ。
「日本人だけ できない」では、無いはずだ。
▼労組での団体交渉を
前項で、交渉は個人で、できると述べた。
とは言え、団体の方が、心強いだろう。
個人での交渉の他に、労組での団体交渉がある。
組織的な団体交渉を、積極化するのも、選択肢だ。
「賃上交渉は、誰かが、やるだろう」ではなく、
自ら賃上げに参加する意識を、持つことも大切だ。
米国では、スタバ、アマゾン社、アップル社が、
労組結成へ動いた。
日本でも、社員が自ら、動くことも重要だ。
▼新しいスタイルの団体交渉は、いかが?
「春闘」とは 、「春季闘争」の略である。
最近は、「春季生活闘争」と言う。
「闘争」との言葉を、
令和の若手サラリーマンは、どう思うだろうか?
ハチマキを頭に巻いてのスタイルを、
想像する人も、いるだろう。
「闘争」というより「交渉」や「協議」の方が、
若手社員の賛同を、得やすい気がする。
「仲間の社員と一緒に、賃金UPをしよう」 という
スタイルの方が、若手の心を、掴むのではないか?
ちなみに、下記リンク先に、
米国スターバックスの労組の写真がある。
※産経ニュース|米スタバで初の労組結成
-- 消費者 経済 総研 --
◆まとめ|賃上げの 交渉促進を
日本人の特徴は、下記だった。
・入社する前の 賃金交渉に 消極的
・入社した後の 賃金交渉に 消極的
外国人は、賃上げ交渉に、積極的だった。
日本人も、積極的に、なろう。
① 「 個人 での 交渉 」 の活性化
② 「 団体 での 交渉 」 の活性化
上記2件を、提言する。

- ■3位 なぜ 副業の促進 ?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆なぜ 副業の促進 なのか?
本ページのテーマは、
「日本人の 賃金・収入を 上げる方法 」 である。
収入は 「 賃金 + その他収入 」 だ。
「副業促進」は、その他収入のUPだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆現状と課題は?
▼現状は?
副業・兼業を認めてない企業は、85%(2014年)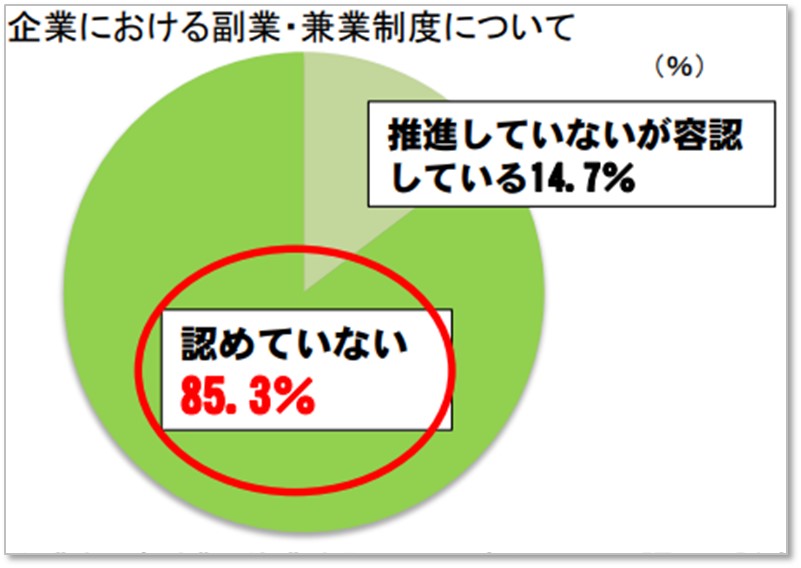 ※出典:厚生労働省|副業・兼業の現状と課題
※出典:厚生労働省|副業・兼業の現状と課題
2017年に、政府は「副業の促進」を、うたい始めた。
(※働き方改革 実行計画 2017年3月)
政府は、副業に下記の利点を、認めている。
・新たな技術の開発
・オープンイノベーションや起業の手段
・第2の人生の準備
2022年は、政府は「副業を加速する」策を示した。
その副業加速の方策とは、何か?
「企業に、副業条件を、公表させる」 方針である。
副業制限する場合は、理由等を開示するよう促す。
この方策で、働き手は、副業のしやすさが、わかる。
副業のしやすさで、就職先の選択ができるのだ。
※:出典: 2022/6/24|日経新聞電子版|副業...解禁加速へ企業に要請
▼ 課題 ① は?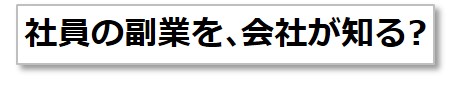
副業していることが、会社に知られる。
これも、副業での課題である。
副業が、認められている企業では、どうか?
容認されても、上司・同僚の目や空気が、気になる。
どうやって、企業は副業に、気付くのか?
副業で収入を得た場合は、税の申告が必要になる。
住民税は、自治体へ申告する。
所得税は、一定の額以上で、税務署へ確定申告だ。
※本稿記載内容に関わらず、自分の申告や納税が、
どうなるかは、税理士、税務署、自治体などに
自ら確認するなどで、自らの責任で対応が必要だ。
「副業容認かつ副業の告知不要」の企業であっても
税の申告で、企業が社員の副業を、知る事がある。
▼ 課題 ② は?
副業は促進されるが、副業の制限は法的にできる。
促進のアクセルを踏むが、ブレーキが残っている。
-- 消費者 経済 総研 --
◆課題への解決策の 提言は?
▼ ① 会社に知られる への 解決策は?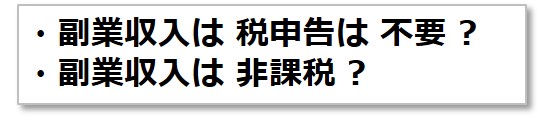
税申告で、副業が会社に知られるのが課題だった。
そこで税制優遇や、申告手続きの優遇を提言する。
副業収入が一定額までは、下記2点とするのだ。
・副業での収入の 税の申告は、不要
・副業での収入は、非課税
税の申告不要であれば、会社が知る機会は、減る。
非課税枠は、副業促進の大きな後押しになる。
▼ ② 副業の法的なブレーキ への 解決策は?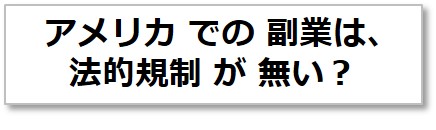
副業を一段と促進する「ルール整備」を、提言する。
副業促進のためには、制限の緩和が必要だ。
ガイドラインや法整備の議論が、期待される。
米国では、どうか?
米国では、副業への法的な規制は無い。
そもそも日本も、「副業制限を緩和」ではなく、
「副業の制限なし」でもよいのだ。
制限なしで、副業原因で不祥事が発生した場合は、
個別の刑事罰や民事賠償で、対応する。
とは言え、日本の現実的な制度としては、どうか?
自社の秘密情報のライバルへの漏洩懸念がある。
ライバル企業での副業禁止は、要求されるだろう。
▼結論は、下記の法整備を、提言
・副業禁止の就業規則は、無効
・禁止は、「ライバル企業での副業」 のみ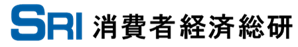
▼「 意識面 」 での課題への 解決策は?
政府広報(意識改革プロモーション)を提言する
政府は、副業のさらなる普及を、目指している。
ならば、政府の広報活動の強化を、期待したい。
副業容認の企業であっても、副業者は、
上司・周囲の目や、空気を、気にしてしまう。
「副業は、良いことだ。 どんどんやろう。 」
という雰囲気を、醸成するのだ。
「 ワクチン接種 しましょう 」
「 黙食や マスク着用の 徹底を 」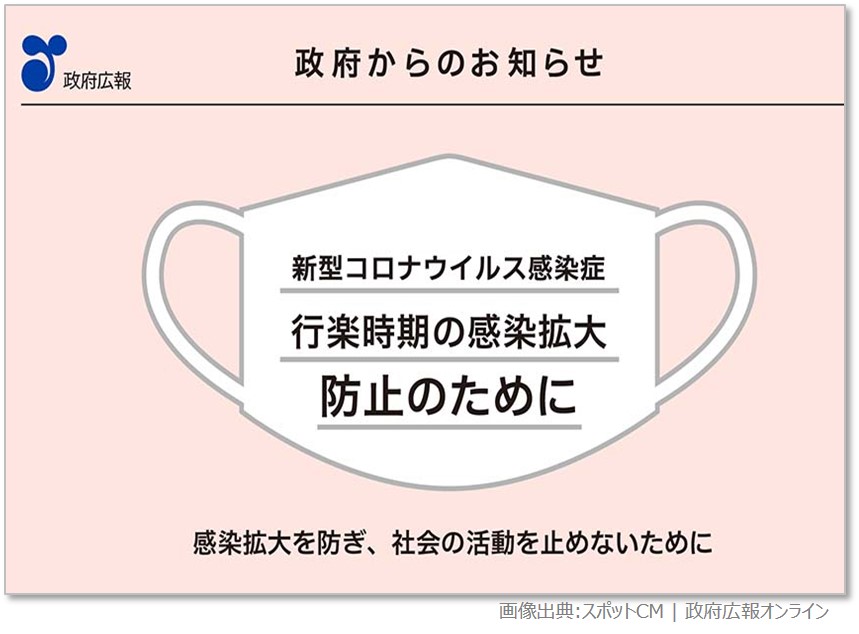
コロナ禍では、
上記等の政府広報のテレビCMが、流された。
※動画:スポットCM | 政府広報オンライン
政策の推進では、
CM等の政府広報の積極活用も、効果的だ。
日本は、同調傾向が強く、周囲の目を気にする。
雰囲気の醸成は、実は重要である。
-- 消費者 経済 総研 --
◆提言策のデメリットと、その対応は?
副業促進で、働き手の新視点・選択肢が、増える。
それにより、下記のデメリットが、考えられる。
・本業の勤務先での、意欲・忠誠心の低下。
・副業開始をきっかけに、本業企業の離職が増加。
本業の勤務先が、副業者の離職を、懸念するなら、
自社の賃金などの雇用条件を、改善すればよい。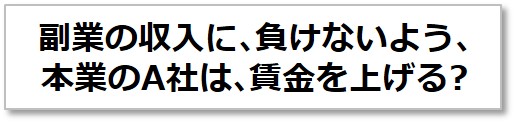
副業促進は、企業の賃上げを、促す側面もある。
1つの企業に忠誠心を示すのは、昭和で終わりだ。
令和では、精神姿勢を、評価するのではない。
業績や仕事の成果を、評価すべきだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆追記( 副業の 契約の種類は?)
▼契約の種類は?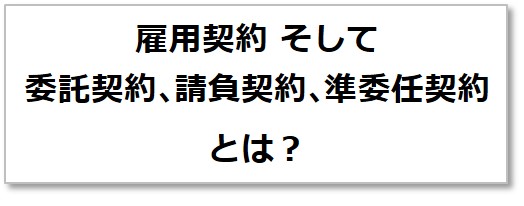
働く際の契約は、どのような契約が、あるか?
通常のサラリーマンは、「雇用契約」が大半だろう。
「雇用契約」 以外の契約は、何があるか?
他者の仕事を、引き受けた場合には
「委託契約」がある。
なお、委託契約は、法律用語では無い。
「請負契約」、「準委任契約」等が、法的な用語だ。
▼本業の勤務先と、副業先の 契約の組合せは?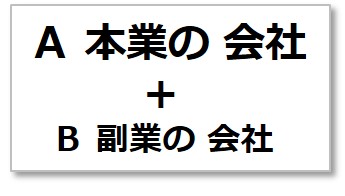 本業の勤務先(A社) + 副業先(B社) の2社で、
本業の勤務先(A社) + 副業先(B社) の2社で、
Xさんが、兼業した場合は、どうなるか?
なお契約は両方とも「雇用契約」とする。
その場合、現制度では、どうすべきか?
「A社での労働時間」 + 「B社での労働時間」
この2つを、合算する必要が、あるのだ。
つまりB社は、
A社でのXさんの労働時間を、把握する必要がある。
その上で、残業代の計算を、するのだ。
この現行の制度は、とてもとても、煩雑である。
現ガイドラインの合算規定は、読むだけで疲れる。
(厚労省は 合算 ではなく通算と言う)
厚生労働省|副業・兼業の促進に関するガイドライン
他社での労働状況の把握とは、難題である。
こんなに面倒だと、どうなるか?
Xさんは、「副業を、あきらめる」 かもしれない。
A社もB社も「副業禁止を、選択」するかもしれない。
現制度は、副業の促進に対して、ブレーキになる。
▼解決策は?
A社は、A社での労働だけを、管理する。
B社は、B社での労働だけを、管理する。
自社内だけを、管理するように、すべきだ。
現制度は、「過剰な制度」に、なっている。
▼「 アキ活 」 の勧め とは?
AB2社とも「雇用契約」だから、面倒なことになる。
ならば、下記の組み合せの方が、良いだろう。
・本業A社 :雇用契約
・副業B社 :委託契約
ホームページの作成、写真撮影、イラスト作成、
専門知識でのアドバイス業務・・などなど
これらの副業は、概ね委託契約に、なるだろう。
雇用契約ではない委託契約の方が、スムーズだ。
これは、まさに「アキ活」である。
消費者 経済 総研は、「アキ活」を、提唱してきた。 (画像:熊本県民テレビ)
(画像:熊本県民テレビ)
「アキ活 とは?」 を、ご覧頂きたい。

- ■4位 1億 総株主 へ
- -- 消費者 経済 総研 --
※注意:投資・貯蓄等は、自らの判断と自己責任
であり、当方は一切責任を負わない。
-- 消費者 経済 総研 --
◆1億 総 株主 とは?
① 日銀保有の株(ETF)を、国民へ配布
② NISA、iDeCo等の さらなる普及
③ 金融教育の拡充(義務教育で)
④ 貯蓄から投資へ の政府広報
上記4件を、提言する。
株式投資の日本国民への普及促進が提言だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆現状と課題は?
▼老後 2千万円 不足問題
老後2千万円の不足問題とは、
・老後の生活費は、年金だけでは不足
・毎月5万円不足し、30年では2千万円も不足
上記の問題を、金融庁が報告し、話題になった。
※出典:2019年6月3日|金融庁|高齢社会における資産形成・管理
▼老後不安が、生み出す 悪循環 とは?
年金では2千万円不足なら、国民は老後が不安だ。
老後が不安だから、貯蓄に励んでしまう。
お金が貯蓄に回ってしまい、消費が活性化しない。
約6割が個人消費であるGDPも、伸び悩む。
経済が活性化しないから、賃金も伸びない。
不安 → 貯蓄 → 経済低迷 → 賃金低迷 → 不足
この悪循環が、生まれる。
企業は、将来リスクに備え、内部留保を増やした。
別稿の通り、内部留保は、貯蓄的な意味がある。
企業も消費者も、将来のリスクに、備えている。
お金を、ため込んでしまい、使わない。
賃金が低迷なら、老後2千万円問題は解消しない。
将来の不安も、解消しない。
▼貯金しても、お金は増えない?
貯金しても、利息はゼロに近い。
貯金しても、お金は、ほとんど増えない。
家計の金融資産の内訳は?
上・日本:現金預金54%、 株式等は10%
下・米国:現金預金13%、 株式等は38%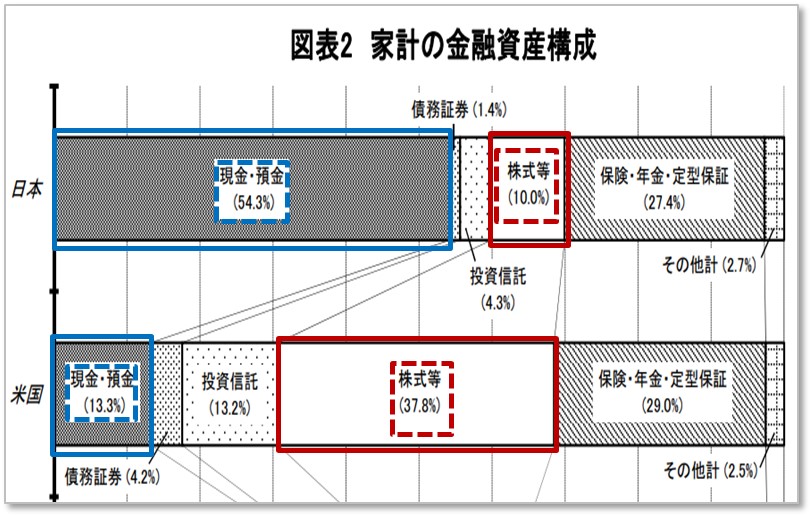
※出典:日銀|資金循環の日米欧比較
日本人の リスク回避マインドが、課題だ
-- 消費者 経済 総研 --
◆課題への解決策は?
▼賃金以外の収入をUPへ
賃金が低迷なら、賃金以外の収入を、増やすのだ。
貯金しても増えないなら、株式投資をするのだ。
賃金低迷なら、賃金以外の収入を、増やす
「貯蓄から投資へ」 の移行で、お金を増やす
-- 消費者 経済 総研 --
◆解決策のデメリットと、その対応は?
当然ながら、株は元本保証ではない。
株の下落で、損をすることがある。
日本人は、損失が嫌だから、株式投資を避ける。
だが、日本人は、株のリスクを、過大に捉えている。
▼「長期投資」 と、「指数投資」 なら、安心?
まず大切なのは「短期視点 ではなく長期の視点へ」
次に大切なのは「個別銘柄 ではなく全体指数」だ。
短期の売買ではなく、長期保有ではどうか?
長期では、高い確率で、資産を大きく増やせる。
また、個別銘柄ではなく、市場の指数ではどうか?
個別銘柄投資とは、個別の企業の株を買うことだ。
個別銘柄は、原因不明の乱高下する場合がある。
企業が倒産し、「株が紙くず」になる事もある。
日経平均に連動するETFへ、投資するのだ
※ETFとは、上場している投資信託のこと。
※投資信託とは、様々な個別銘柄が混ざったファンド
下図を見て頂きたい。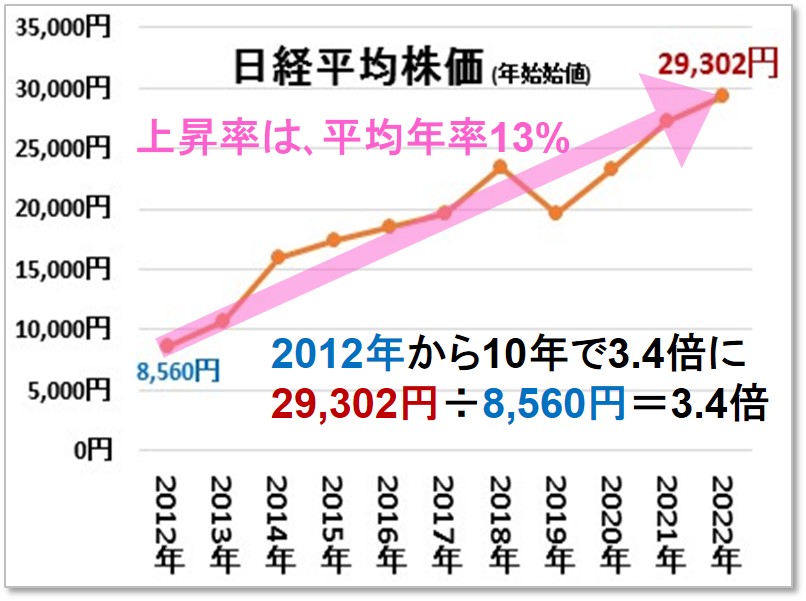
下がる年もあるが、長期では、大きく上昇した。
2012年から10年で「3.4倍」にもなった。
(2022年29,302円 ÷ 2012年8,560円 = 3.4倍)
日本株ではなく、米国株の指数では、どうか?
下図は、米国のナスダック総合指数の推移だ。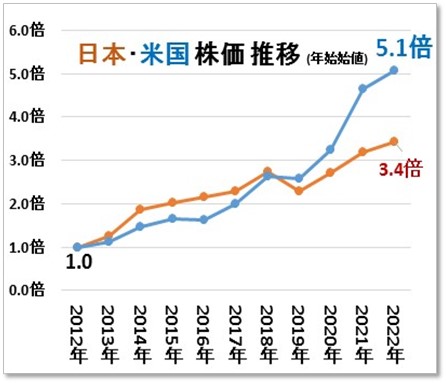
10年間で、日経平均株価は3.4倍だが、
米国ナスダックは、「5.1倍」にもなった。
・個別銘柄ではなく、市場全体へ連動するETF
・「短期」 ではなく 「長期」
上記の2つの視点で、大きく資産を増やすのだ
▼貯金と比べたら、どうか?
10年間の伸び率は、
日経平均は3.4倍、ナスダックは5.1倍だった。
600万円を、日経平均に、投資したら、
10年間で、2,054万円 になる。
(600万×3.4倍=2054万)
ナスダックなら、3,036万円になる。
50歳で、600万円の株投資をすれば、
60歳で、2000万円超に、なった計算だ。
「老後の 2千万円 不足」 へ対応できる。
一方、10年間の「貯金」では、どうか?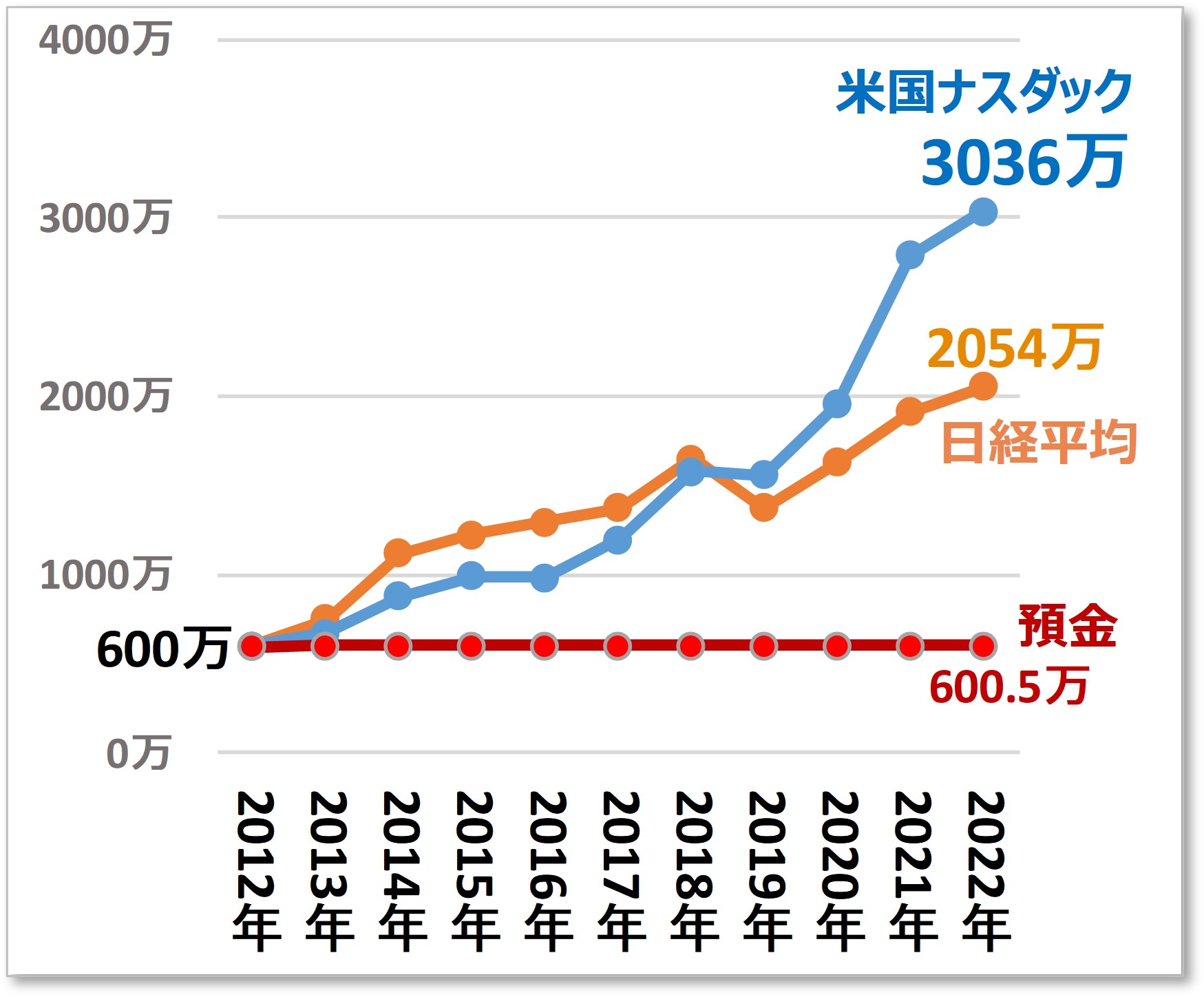
600万円 → 600.5万円 で、約千円しか増えない。
※貯金600.5万円は、下記金利で、複利計算
12~15年:0.02%、16年:0.005%、17~21年:0.001%
※出典:日銀|統計別検索
▼政府広報 と 金融教育 とは?
別稿の通り、コロナ禍では、
政府広報のテレビCMが、流された。
「資産所得の増加 」 の政策の推進では、
CM等の政府広報を、積極活用するのも、効果的だ。
日本は、同調傾向が、強い。
周囲の人が株をやれば、影響を受け、関心を持つ。
雰囲気の醸成は、実は重要である。
米国では、随分前から、
株式投資等を、教育の中に、取り入れていた。
日本でも、早期・大幅な金融教育の充実が、必要だ。
筆者(松田)は、高校生の時、
古文と漢文の科目は、好きだった。
得点(偏差値)も、全科目の中で、高かった。
だが古文漢文を勉強して良かったと、感じたのは、
社会人になって以降、約30年間、無かった。
金融・投資教育の方が、役に立っていただろう。
-- 消費者 経済 総研 --
◆日銀保有のETFの 国民への配布 とは?
日銀は、金融政策の1手段として、株を買ってきた。
日銀が、市場で株を買うと、お金は、どう動くか?
株の購入代金が、市場つまり民間部門へ移動する。
それにより、民間部門のお金の量が、増える。
つまり、「 量的緩和の金融政策 」だ。
※株の購入を「質的緩和」に、日銀は分類するが、
国債の購入と同じく、量的緩和の利点がある。
※「量的緩和策 や 金融緩和策 とは?」を参照
日銀は、平等のため、特定の個別銘柄を、買わない。
日経平均やTOPIX等に連動するETFを買った。
※ETFとは、上場してる投資信託のこと。
※投資信託とは、様々な個別銘柄が混ざったファンド
日本は、まだデフレ脱却を、していない。
よって日銀は、金融緩和策を、継続中だ。
デフレ脱却時には、金融緩和を、終えるだろう。
その時は、緩和政策で買ったETFを、民間へ戻す。
そこで、提言するのは、「ETFの国民への配布」だ。
日本人は、株売買の経験が、無い人は多い。
日経平均等のETFを、日銀が無料で、配ることは、
国民が、金融投資に馴染む 絶好のチャンスだ。
「 国民へ株の配布なんて、変なこと 言っている 」
と思うかもしれない。
だが海外では、香港で、事例がある。
それによって、香港の人々は、
資産も増え、投資の知識も、増えたのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆NISA、iDeCo等のさらなる普及・促進
ETFの国民への配布は、先々の検討事項だ。
まずはNISA、iDeCo等のさらなる普及促進が先だ。
NISA、iDeCoのメリットは、税制優遇だ。
その税制優遇の上限の大幅緩和を、提言する。
税制優遇を、徹底拡充し「株をやると、得だ!」
との認識を、国民全般に広げるのが良い。
-- 消費者 経済 総研 --
◆「1億 総株主 作戦」のまとめ
賃金以外の収入を増やす 「1億 総株主 作戦」
日本人の株保有率は低い。 これを海外並みに改善
① 日銀保有の株(ETF)を、国民へ配布
② NISA、iDeCo等の さらなる普及
③ 金融教育の拡充(義務教育で)
④ 貯蓄から投資へ の政府広報
個別銘柄 ではなく、指数(日経平均、ナスダック等)へ投資
短期 ではなく、長期の投資を

- ■5位 アメ版|賃上げ税制の 強化
- -- 消費者 経済 総研 --
◆賃上げ税制の 強化|アメ版 とは?
賃上げすると、法人税が減るから、賃金UPへ
「賃上げした企業への減税」 の制度は、既にある。
その既存の制度を、大幅に拡充する。
賃上げでの 「減税額の増大」 等の改善策を提言
-- 消費者 経済 総研 --
◆現在の課題は?
現行の賃上げ税制は、どういう内容か?
「 1.5% 以上の 給与UP 」 をすれば、
「 給与の増加額×15% 」の額が、法人税から減る。
※2.5%以上給与増なら、増加額×30%など上乗せあり
※本来は、「給与」ではなく「給与等」である。
同様に「法人税額」ではなく「法人税額等」である。
他にも「等」が付くのがあり、「等」が連発するが、
読みやすさのため、「等」を省略している。
今の税制でも、一定の効果が、期待される。
しかし、現行の制度では、不十分だ。
▼赤字企業は、対象外
中小企業では、約7割が、赤字決算である。
つまり、そもそも、法人税ゼロの企業が、多いのだ。
▼黒字企業でも、効果薄い
現在の「賃上げ税制」で、
賃上げをする経営者は、限定的だろう。
下記の「単純化した計算モデル」では、
賃上げは、得ではなく、損になる。
実際の法人税額の計算は複雑だ。
上記は、思いっきり単純化した計算である。
賃上げ前の税引き後利益は、3.85
賃上げ後(現制度)の再最終利益は、3.57
賃上げ税制優遇を受けても3.85→3.57と減る。
3.85と同じ再最終利益になるには、
(12)の控除率が、76%も必要だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆課題への解決策の 提言は?
賃金UPの意欲を、増やすために、
「 税制優遇の パーセントの 大幅UP 」を提言
▼現行の税制は?
・減税条件:1.5 % 以上の 給与の増加
・減 税 額:給与の増加額 × 15%
※2.5%以上給与増なら、増加額×30%など上乗せあり
▼新しい提言は?
青字の%を、15%から、大幅に上げるのが提言だ。
減税メリットが増えるので、賃上げ促進になる。
▼赤字企業は、どうする?
A減税条件:1.5 % 以上の 給与の増加
B減 税 額:給与の増加額 × 15%
上記が黒字企業への優遇策だった。
赤字企業には、
Aを満たしたら、B売上×〇%の助成等を提言。
-- 消費者 経済 総研 --
◆新しい提言の デメリットは?
賃上げが進む → 法人税の減税が進む → 税収減
新しい提言での減税強化では、国の税収が減る。
よって、国の財政負担が、増加する。
※本連載では、新たな政策の採用で
政府の支出が、増える提言が、複数ある。
つまり、財政の赤字は、増加する。
しかし、それは問題にならない。
「 財政赤字の増加は、問題ではない 理由 」 は、
本ページの下段に、まとめて掲載する。

- ■6位 ムチ版|賃上げ税制 とは?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆賃上げ税制|ムチ版 とは?
「会社の貯金」である「内部留保」に、課税する。
内部留保を増やすと、損だから、賃上げに使う。
内部留保への課税で、賃上げを促す提言である。
前項の賃上げ税制では、どうだったか?
前項の賃上げ税制は、賃上げすれば、税金が得だ。
つまり 「アメとムチ」 での 「アメ」 に該当する。
一方、この項での提言は、どうか?
内部留保へ課税は、「ムチ」 版だ。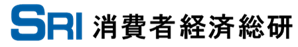
◆内部留保 とは?
内部留保とは、「企業の貯金」のようなものである。
※「 内部留保 = 企業の貯金 」とは言い切れないが、
簡単解説においては、この理解でよい。
企業の「税引き前の利益」から、
「法人税等」を、引いた後が、「純利益」だ。
純利益は、最終利益である。
最終の純利益を、どう処分するか?
純利益は、株主への配当や、内部留保になるのだ。
「内部留保」は、会計用語では「利益剰余金」だ。
それは、経費・税金・配当等を、引いた後の残額で、
「企業の貯金」の性格を持つ。
下図のように、内部留保は、増大を続けてきた。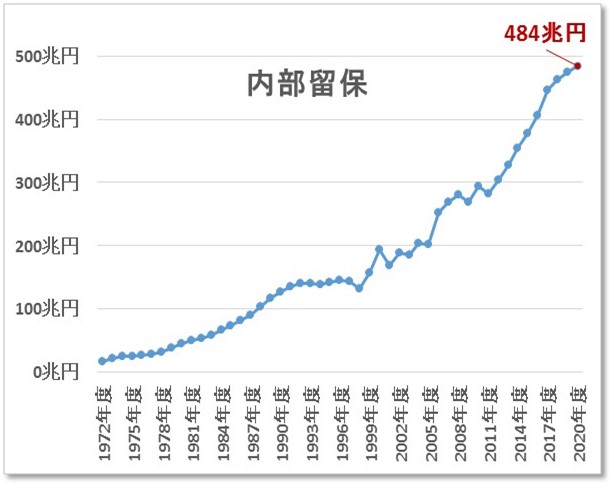 ※金融業・保険業を除く
※金融業・保険業を除く
※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成
※出典: 政府統計総合窓口|法人企業統計調査
金融業、保険業以外の業種(原数値)
-- 消費者 経済 総研 --
◆内部留保 増えた理由は、将来不安?
平成元年以降の日本は、下記の経済危機があった。
平成バブル崩壊、リーマンショック、大震災など。
今後、新たな経済ショックが起きたら、
弱い日本経済では、克服するのは、楽ではない。
日本の経営者は、将来に不安を、感じているのだ。
企業は、危機への備えで、内部留保を貯めたのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆現在の課題は?
内部留保は、増えたが、賃金は、増えていない。
-- 消費者 経済 総研 --
◆課題への解決策の 提言は?
内部留保を、賃上げに使う税制にする。
そこで、「内部留保」に、課税する。
内部留保が多いと、課税されて損するから、
「賃上げに使う 誘導税制 」とする。
「内部留保が多いと、損だ」となれば、何に使うか?
必ずしも、賃上げに使うとは、限らない。
使い道は、「株主への配当」等に、回る可能性もある
そこで、課税は、
内部留保の額 × 税率 ではなく、
( 内部留保の額 - 賃上げ額 ) × 税率 とする。
-- 消費者 経済 総研 --
◆解決策のデメリットと、その対応は?
企業の税負担の増加には、反対意見が出やすい。
企業の負担増は、ムチだ。
一方、前の項では、「ムチ」ではなく「アメ」だった。
「アメ型の賃上げ税制強化」 の方が、導入しやすい。
一方で、「 ムチ型 」 は、国の税収増になる。
よって、国の財政の健全化に、つながる。
▼ムチ型:
メリット は 、 増税なので、国の税収が増加。
デメリットは、企業増税なので、反対されやすい。
▼アメ型:
メリット は 、 減税なので、反対されにくい。
デメリットは、国の財政負担が、増加。
財政の負担増は、クリアできるので、
アメ型の方を、上位として評価する。
「財政の負担増はクリア」 の理由は、
下段掲載の「財政赤字の増加への評価と対策」参照

- ■7位 ボーナス へ シフト
- -- 消費者 経済 総研 --
◆ボーナス へ シフト とは?
賃上げは、賞与(ボーナス)に、フォーカスする。
その普及促進のために、税制優遇を提言する。
-- 消費者 経済 総研 --
◆現状と課題は?
▼現状は?
春闘での賃上げ交渉は、
「ベア+定昇のUP」に、数値目標が設定される。
「ベア+定昇のUP」は、生活の安定・底上げになる。
※「ベア+定昇 とは?」を参照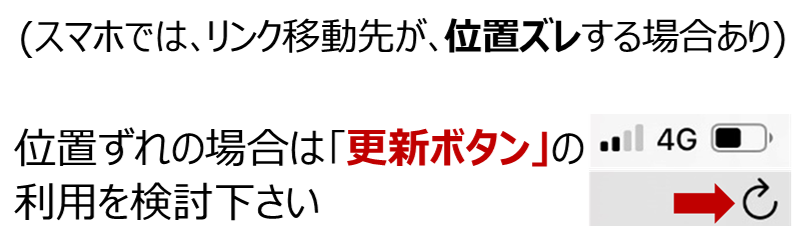
しかし、ベア等は、支払う側の経営者にとっては、
長期の賃金水準UPになり、長期の固定費のUPだ。
低迷する経済ゆえ、日本の経営者は、慎重姿勢だ。
よって、既述の通り、内部留保を、増やしてきた。
▼課題は?
ベア等 (ベア+定昇UP)は、
企業の負担水準を、長期に高めるのが課題だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆解決策は?
そこで、ベア等ではなく、ボーナス等に注目だ。
ボーナス等の一時金の方が、支払いやすい。
「今年は儲かったから、ボーナスを多くしよう」
「税制改正で、ボーナス増やすと、税金が楽になる」
このように、経営者を誘導するのだ。
春闘方針も含め、大いに検討の価値があるだう。
ベア等よりもボーナス等で、賃上げ要求した方が、
働き手の総収入は、大きくなる可能性がある。
▼具体的には?
下記の現制度に加え、ボーナスUPは、さらに減税
別稿に「賃上げ税制の 強化|アメとムチ」がある。
給与UPした企業は、法人税が減税される。
上記の現行の減税制度に、下記を加えるのだ。
「ボーナス増額」した部分の減税額を、大きくする。
月給UPでも、条件満たせば、減税だが、
「ボーナスUP ならば、さらに減税」を、提言する。
-- 消費者 経済 総研 --
◆解決策のデメリットと、その対応は?
ボーナスは一時金なので、安定しないのが欠点だ。
不安定でも 「ボーナス重視で、収入総額のUP」
との目的への、理解促進が必要だ。
「賃金を もらう側 」 の視点だけではなく、
「賃金を 払う側 」 の視点を、持つと良い。
払いやすい形なら、多くもらえる可能性がある。

- ■8位 解雇規制 の 緩和
- -- 消費者 経済 総研 --
◆解雇規制 の 緩和 とは?
解雇されにくい方が、働き手は安心だ。
しかし解雇規制によって、逆に賃金低迷を招く。
そこで、解雇規制の緩和を、提言する。
-- 消費者 経済 総研 --
◆現状と課題は?
雇用期間を、仮に、40年間(20~60歳)とする。
また年間賃金を、平均400万円とする。
総額は、1.6億円だ。 (400万円×40年=1.6億円)
解雇ができないと、40年も雇い続けることになる。
20歳で新卒採用した雇用契約は、
「1.6億円を、支払う約束の契約」 とも言えるのだ。
終身雇用ならば、働き手は安心する。
だが、かえって収入を、減らすことになる。
これを、経済学の用語では、
「合成の誤謬」(ごうせい の ごびゅう)と言う。
1視点で得するが、全体視点では損を、意味する。
経営者は、長期間の賃金の支払いを懸念し、
「なるべく 安めの賃金 」 にしようと、考えるのだ。
▼「働かない おじさん社員」 とは?
昔から、「働かない おじさん社員」は、いた。
昭和なら、
社内で新聞を、読んでいる時間が長い
タバコを吸ったり、コーヒー飲んでる回数多い
平成~令和なら、
パソコンで、仕事と無関係のサイトを、見ている
働かないおじさん社員に、高い給与を支払う分、
業績に貢献している若手社員への給与が減る。
働かないおじさん社員は、新たな職へ移った方が、
本人も、経営者も、若手社員にも、プラスだろう。
年齢に応じて、自分にマッチする仕事はあるのだ。
▼採用した社員が、ミスマッチ社員だったら?
ミスマッチ社員を、高い賃金で採用しても、
解雇が容易なら、リスクではない。
解雇ができないなら、ミスマッチ社員に対して、
定年までの長期間、賃金を支払い続ける事になる。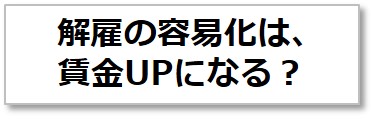
解雇が容易なら、高い賃金の提示が、しやすい。
諸外国を比較した、データの検証では、
失業しやすい国では、賃金が高いことが解る。
解雇の容易化は、働き手の賃金UPになるのだ。
失業と賃金の相関など、
裏付けとなるデータは、海外に様々ある。
-- 消費者 経済 総研 --
◆解決策のデメリットと、その対応は?
規制緩和で、働き手は、クビになる場合がある。
そこで、セーフティーネットの拡充を、するのだ。
次の職場で働き始めるまでの、
手当や、職業訓練・職業教育を、充実させるのだ。

- ■9位 公務員の 賃金UP
- -- 消費者 経済 総研 --
◆公務員の 賃金UP とは?
公務員の賃金水準を、民間より高くする案だ。
すると、高い賃金の役所への就職ニーズが高まる。
その分、民間企業への就職ニーズが、下がる。
その対抗策として、民間企業が、賃金を上げる。
これを意図的・政策的に、実施することで、
民間の賃金UPを、促すという手法だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆現状と課題は?
現状の公務員の賃金決定は、「民間準拠方式」だ。
公務員の給与は、民間企業の従業員の給与に、
均衡させることで、決定しようとする。
現状、公務員の方が「高い賃金・高い人気」でない。
公務員の賃上げで、民間賃金水準も、上げるのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆解決策のデメリットと、その対応は?
「役人天国だ」 のような批判を、招く可能性がある。
それに対しては、「目的は、民間の賃金UP」
との趣旨の広報の徹底が必要。

- ■10位 最低賃金UP
- -- 消費者 経済 総研 --
◆具体策は?
最低賃金の上昇率の、UPと加速化
-- 消費者 経済 総研 --
◆現状と課題は?
日本の最低賃金は、先進国で、低水準か?
いや、実は、低くはない。
▼日本の最低賃金、2番目に低い?
日本の最低賃金の「額」は、
下表の先進国の中では、米国の次で、2番目に低い。
▼平均賃金は、1番低い?
しかし、日本はそもそも、賃金水準が低い。
下表の先進国の中で、1番低い。
▼「賃金の指数」では、日本は高い方?
A 最低賃金 ÷ B 平均賃金 の指数では、どうか?
この指数では、日本は、3番目に高いのだ。
「平均賃金」との比較では、日本は低くないのだ。
A:時期は2020年1月。単位は円(同時点の為替レート)
B:US dollars, 2021 or latest available
※下記出典から、消費者経済総研が、図を作成
※出典: OECD|平均賃金 (Average wage)
※出典:日銀|最低賃金の国際比較
▼最低賃金UPは、強制の賃上げ?
最低賃金は「最低賃金法」という法律が定める。
法令による「強制的な賃上げ」との側面もある。
日本の賃金が、上がらないなら、強制賃上げだ。
最低賃金の引き上げの加速が、賃金UP策となる。
-- 消費者 経済 総研 --
◆解決策のデメリットと、対応は?
最低賃金UPのペースが速いと、どうなるか?
経営者は「採用数の抑制」へ、向かう可能性がある。
また最低賃金UPは、低所得層の底上げになるが、
中間層以上の賃金が、上がるかは疑問だ。
世界中で最低賃金UPの効果検証論文は様々ある。
効果の有無や効果の程度は、論文によって様々だ。
よって、収入UP策としては、下位の10位とした。

- ■1位 働き手が 自ら転職
- -- 消費者 経済 総研 --
◆働き手が 自ら転職 とは?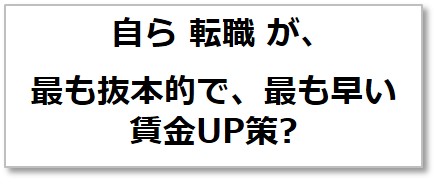
政府+民間で、転職を促進する意識改革の
プロモーションの実施を、提言する。
ここまで「私たちの収入UP」の提言を、述べてきた。
新たな政策の導入には、反対が、付きものだ。
法整備などの時間も、かかるだろう。
最も抜本的で、最も早い 賃金UP策は、
「 好条件へ 自ら 転職する 」 である。
-- 消費者 経済 総研 --
◆現状と課題は?
米国人は、「積極的に転職」する。
一方、日本人は、転職へ消極的である。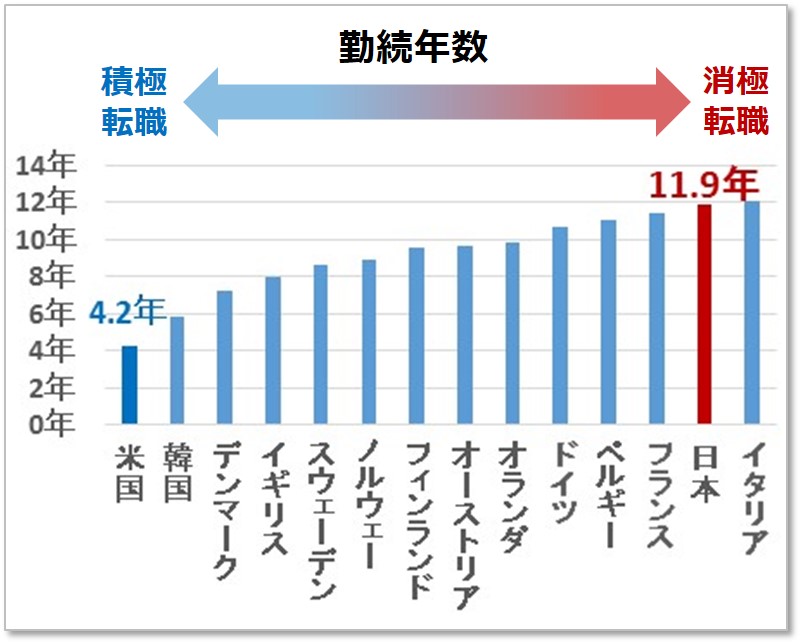 ※出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構
※出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構
データブック国際労働比較2018(全文)|JILPT
上図で、勤続年数が、長いことは、
「転職が少ない 」 ことを、意味する
▼転職には、不安はない?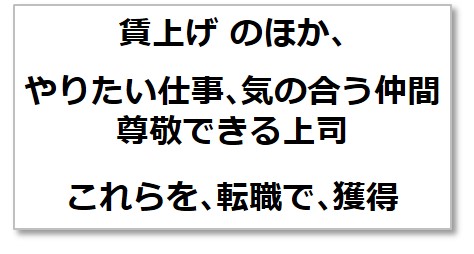
転職に、不安に感じる人も、いるだろう。
しかし、1度、転職を経験すれば、
2回目以降は、なんら不安はない。
例えば、初めての一人での海外旅行は不安もある。
しかし2回目の海外一人旅では、不安は消える。
転職も、同じようなものだ。
「苦労が美徳 」 「 我慢が美徳 」 は、嘘だ。
転職後に、輝いた人を、たくさん知っている。
メリットは、賃金UPだけ ではない。
賃上げに加えて、下記も手に入るチャンスだ。
気の合う仲間、尊敬できる上司、やりたい仕事
-- 消費者 経済 総研 --
◆解決策のデメリットと、対応は?
転職で賃金UPしても、ミスマッチの場合がある。
事前のリサーチを、怠っては、いけない。
事前リサーチしても、ミスマッチは、ありえる。
上司や同僚などと、「そりが 合わない 」 などだ。
ミスマッチな転職を防ぐため、事前調査も重要だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆10の方策を、振り返って
「賃上げ税制の強化」 「解雇規制 の 緩和」
「公務員の 賃金水準UP」 「最低賃金UP」
これらの賃上げ策は、法改正を、伴うものも多い。
法改正が、あっても、
「小幅な改善」に、留まる事も、あるだろう。
また、法改正は、時間もかかる。
賃上げ・収入UPは、
政府頼みよりも、自分のチカラで、獲得する。
これが何よりも、最善の方法である。

- ■ 財政赤字の増加 への評価・対策
- 上段の提言で、財政赤字が、増加する政策もある。
赤字の増加は、国の借金の増加を、意味する。
しかし、それは問題にならない。
理由は、下の青文字リンクのページで解説中だ。
「次世代への、借金の先送りは、ダメ」
「日本は借金大国なので、増税が必要だ」
「日本の財政支出を、減らす必要がある」
上記のフレーズが、しばしば聞かれる。
しかしいずれも、問題視する必要はない。
なぜ「先送りはダメ」等のフレーズを言うのか?
その理由は、下記3つの、いずれかだ。
[1] そう言った方が、自分が、得をする
[2] そう言わざるを得ない立場にある
[3] 単純に情報不足
[3]は、知識の習得で解消する。
[1]と[2]は、ポジショントーク だ。
消費者経済総研は、財務を預る役所でもなく、
特定政党の支援を、する立場でもない。
つまり、当方のポジションは、ニュートラルだ。
「わかりやすく解説する」との立場に、いるだけだ。
※なお「ポジショントークは直ちにNG」
というわけではない。
先送りダメと言う人は、「だいぶ減った」と感じる。
知識の習得(情報の共有・伸展)が、進んだのだろう。
筆者(松田)は、35年以上前に、慶応大学 経済学部
に入学以来、経済を研究している。
しかし下記①②③は、経済学の知識なしでも、
わかるような簡単解説としている。
国の借金の解説では、筆者の解説が、
「日本で2番目にわかりやすい」と思っている。
①そもそも、日本は借金大国ではない
②借金増加しても、相手は身内だから問題ない
③日本は脱デフレ未完だから、借金増加は好都合

| ■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので、 「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆である事を念頭に置いて下さい。 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、 対応して下さい。また「免責事項 」をお読みください。 ■引用 真っ暗なトンネルの中から出ようとするとき、 出口が見えないと大変不安です。 しかし「出口は1km先」などの情報があれば、 真っ暗なトンネルの中でも、希望の気持ちを持てます。 また、コロナ禍では、マイナスの情報が飛び交い、 過度に悲観してしまう人もいます。 不安で苦しんでいる人に、出口(アフターコロナ)という プラス情報も発信することで、 人々の笑顔に貢献したく思います。 つきましては、皆さまに、本ページの引用や、 URLの紹介などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件をご覧下さい。 |
- 【著作者 プロフィール】
- ■松田 優幸 経歴
(消費者経済|チーフ・コンサルタント)
◆1986年 私立 武蔵高校 卒業
◆1991年 慶応大学 経済学部 卒業
*経済学部4年間で、下記を専攻
・マクロ経済学(GDP、失業率、物価、投資、貿易等)
・ミクロ経済学(家計、消費者、企業、生産者、市場)
・労働経済
*経済学科 高山研究室の2年間 にて、
・貿易経済学・環境経済学を研究
◆慶応大学を卒業後、東急不動産(株)、
東急(株)、(株)リテール エステートで勤務
*1991年、東急不動産に新卒入社し、
途中、親会社の東急(株)に、逆出向※
※親会社とは、広義・慣用句での親会社
*2005年、消費・商業・経済のコンサルティング
会社のリテールエステートに移籍
*東急グループでは、
消費経済の最前線である店舗・商業施設等を担当。
各種施設の企画開発・運営、店舗指導、接客等で、
消費の現場の最前線に立つ
*リテールエステートでは、
全国の消費経済の現場を調査・分析。
その数は、受託調査+自主調査で多岐にわたる。
商業コンサルとして、店舗企業・約5000社を、
リサーチ・分析したデータベースも構築
◆26年間の間「個人投資家」としても、活動中
株式の投資家として、
マクロ経済(金利、GDP、物価、貿易、為替)の分析や
ミクロ経済(企業動向、決算、市場)の分析にも、
注力している。
◆近年は、
消費・経済・商業・店舗・ヒットトレンド等で、
番組出演、執筆・寄稿、セミナー・講演で活動
◆現 在は、
消費者経済総研 チーフ・コンサルタント
兼、(株)リテール エステート リテール事業部長
◆資格は、
ファイナンシャル・プランナーほか
■当総研について
◆研究所概要
*名 称 : 消費者経済総研
*所在地 : 東京都新宿区新宿6-29-20
*代表者 : 松田優子
*U R L : https://retail-e.com/souken.html
*事業内容: 消費・商業・経済の、
調査・分析・予測のシンクタンク
◆会社概要
「消費者経済総研」は、
株式会社リテールエステート内の研究部署です。
従来の「(株)リテールエステート リテール事業部
消費者経済研究室」を分離・改称し設立
*会社名:株式会社リテールエステート
*所在地:東京都新宿区新宿6-29-20
*代表者:松田優子
*設立 :2000 年(平成12年)
*事業内容:商業・消費・経済のコンサルティング
■松田優幸が登壇のセミナーの様子
- ご案内・ご注意事項
- *消費者経済総研のサイト内の
情報の無断転載は禁止です。
*NET上へ「引用掲載」する場合は、
①出典明記
②当総研サイトの「該当ページに、リンク」を貼る。
上記の①②の2つを同時に満たす場合は、
事前許可も事後連絡も不要で、引用できます。
①②を同時に満たせば、引用する
文字数・情報量の制限は、特にありません。
(もっと言いますと、
①②を同時に満したうえで、拡散は歓迎です)
*テレビ局等のメディアの方は、
取材対応での情報提供となりますので、
ご連絡下さい。
*本サイト内の情報は、正確性、完全性、有効性等は、保証されません。本サイトの情報に基づき損害が生じても、当方は一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。
- 取材等のご依頼 ご連絡お待ちしています
- メール: toiawase★s-souken.jp
(★をアットマークに変えて下さい)
電 話: 03-3462-7997
(離席中が続く場合は、メール活用願います)
- チーフ・コンサルタント 松田優幸
- 松田優幸の経歴のページは「概要・経歴」をご覧下さい。