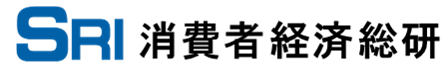[Vol.4日銀次期総裁人事] 植田和男氏 政策 どんな人(ハト,リフレ,タカ)?利上げどうなる?株価,金利は〇〇へ?|消費者経済総研|2023/2/23
■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 リモートでの出演・取材にも、対応しています  消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸 ■最新稿:2023年2月23日 本ページは、修正・加筆等で、 上書き更新されていく場合があります。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆であることを念頭に置いて下さい。 本ページ内容に関しては、自らの責任において対応して下さい。 また「免責事項」をお読みください ■引用 皆さまに、本ページの引用や、 リンク設定などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件 をご覧下さい。 |
- ■日銀 解説|筆者(松田)のTV出演
- 日銀に関する解説・提言でのTV出演実績。
「フジテレビ・めざまし8」に、
「消費者 経済 総研」の 筆者(松田)が生放送に出演。
「日銀 黒田総裁の値上げ許容」 発言等を、解説。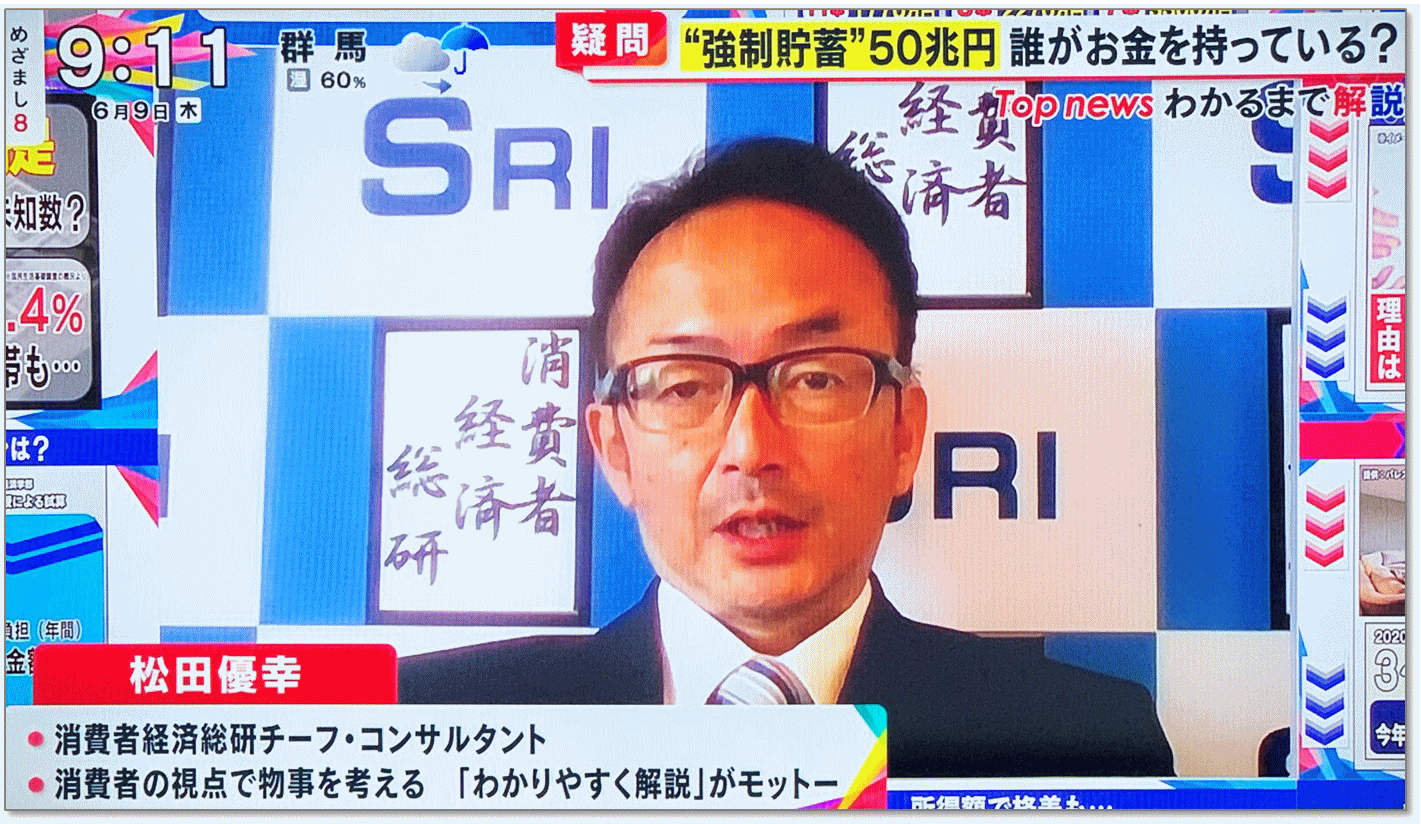
2022年 6月9日 放送 画像出典:フジテレビ
- ■本ページの目次
- 青文字・下線部をクリックし、その場所に移動
- ◆Vol.1 (2023年2月4日)
- どうなる? 今後の 日銀と日本
- ◆ Vol.2 (2023年2月5日)
- 続編Vol.2 利上げの利点,為替影響
- ◆Vol.3 (2023年2月11日)
- 植田和男氏 は、どんな人(ハト,リフレ,タカ)?
- ◆Vol.4 (2023年2月23日)
- 2/24 植田和男氏 は、国会で何を語る?
2/19 NHK 日曜討論が、〇〇だった?
この次に、記載中。
- ■ Vol.4植田氏は 何を 語る?
NHK 日曜討論が、〇〇? - 2月24日(金) 午前の衆議院の理事会で、
植田氏からの「所信の聴取」と、「質疑」が行われる。
日銀の新・総裁の植田氏は、24日に何を語るか?
「金融緩和の変更」を、語るのか?
筆者(松田)、は植田氏が語る内容を、予想した。
予想内容は、下段に記載した。
その話の前に、注目のNHK日曜討論の
日銀テーマの放送内容に、言及したい。

- ■2/19(日)NHK日曜討論とは?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆2/19(日) NHK・日曜討論が、面白かった?
「日銀新体制へ 金融緩和の行方は」のテーマで、
2/19(日)朝9時~10時のNHK・日曜討論が話題だ。
筆者(松田)は、放送開始から、約24時間分の
ツイッターの「#日曜討論」の投稿を、読んでみた。
「 面白かった 」
「 これぞ、討論の番組だ 」
等の投稿も、多かった。
-- 消費者 経済 総研 --
◆日曜討論での発言内容は?
日銀OBの4人が、登壇した。
その中では、岩田氏の発言に、注目して欲しい。
岩田氏は、日銀の前・副総裁だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆なぜ、4人の中で、岩田氏に、注目なのか?
民放の討論とは違い、NHKの討論番組は穏やかだ。
しかし、今回の放送は、違った。
遠慮なく、真実を、強く、はっきり発言されていた。
「 歯に 衣着せぬ 物言い 」 だった。
その代表格が、岩田氏だった。
岩田氏は、正しい金融政策を、しっかり解説した。
金融関係者のポジショントークに、苦言も呈した。
また、そのポジション・トーク以外にも、
「 日銀は、やばい、大変だ! 」
「 国の借金は、多すぎで、大変だ! 」
上記のように、騒ぐ人を、批判した。
このNHKの番組は、1週間程度の間は、見られる。
下の方に、そのNHKの公式URLを記載したので、
あとで、視聴して頂きたい。
-- 消費者 経済 総研 --
◆岩田氏の 発言内容は、何か?
日本は、値上げラッシュが続いた。
CPI(消費者物価指数)の上昇率は、4%になった。
だがこれは、コロナ禍と戦争という、
一時的で、特殊な要因による上昇だ。
2023年の日本のCPIの上昇率は、落ち着くだろう。
日本は、コスト・プッシュのインフレであって、
需要牽引型(デマンド・プル)のインフレではない。
岩田氏の発言でも、
CPI上昇率は、長期的・継続的・安定的な2%
ではない前提に、たっている。
-- 消費者 経済 総研 --
◆岩田氏の コメント内容は?(抜粋要約・校正あり)
ここから、NHKの日曜討論での、
岩田氏のコメントの一部を、紹介する。
▼「日銀が、国債を、買いすぎ」の問題は?
「日銀が、債務超過になったら、大変だ 」 と言うが、
債務超過は、全く問題にならない。
オーストラリアや、イスラエル、チェコの中銀は、
債務超過になったが、何の問題も、起きていない。
債務超過だと、騒ぐのは、
日銀と普通の銀行を混同した、とんでもない話だ。
こんな話は、消滅してほしい。
▼「 2%の 物価安定目標 」 に、達しないのは?
日本で、低インフレが、続くのは、
「 増税したせい」 だ。
▼国の借金や、日銀の国債大量保有の問題は?
国債残高が、何兆円もあり、多すぎで問題だとか、
国債の半分を日銀保有なのはNGと騒ぐ人がいる。
このような、数字だけで、人々を驚かすのは、
もう、やめて欲しい。
財政政策の副作用は、CPIと国債金利で判断する。
今の日本は、物価も金利も、低いから、問題ない。
▼金融政策ではなく、財政政策を?
アベノミクスは、3本の矢ではなく、
1本目の矢(金融緩和)だけで、やってきた。
2本目の矢は、「積極財政」どころか、
「緊縮財政」 (消費税の増税)を、やってしまった。
インフレ率が低いのは、増税(緊縮財政)のせいだ。
それを、無くせば、2%目標に近づく。
国の借金(国債残高)や、日銀の国債大量保有の値
だけで、騒いでいる人には、
CPIと金利の値を、しっかりと、見て欲しい。
日本の経済は、需要不足が、たくさんある。
増税を、やったら、2%にならない。
2%達成のためには、
財政政策の方を、しっかり積極財政しないとだめ。
そうすれば、GDPも上がるし、税収も増える。
増税が先だと、景気は、落ちてしまう。
▼緩和からの出口戦略を、いつ、やるのか?
CPIが2%UPになれば、出口戦略を考えればよい。
そこまでは、国債購入を、継続すればよい。
今は、CPIも低いし、金利も、暴騰してない。
CPIが2%UPになるまでは、金融緩和を継続だ。
▼ポジショントークで騒ぐのは、やめて欲しい?
「 数字が大きいから、 大変だ、 大変だ 」 と、
議論するのは、いいかげん、やめて欲しい。
CPIの2%UPの見通しが、まだ、たたない中で、
YCCを、早期に見直ししたら、危険だ。
早期の見直をしたら、デフレに逆戻りしてしまう。
「 大変な事が、起こる 」とか「 大変だ! 大変だ」
と言う事が、大好きな人が、多すぎる。
※YCC(イールドカーブコントロール) とは、
下記ページの ■Vol.2と■Vol.3 で、解説中。
[日銀|利上げではない・利上げしない理由]
▼〇〇さん(登壇者の1人)に対して、
「 国債マーケットが、混乱した 」と、
〇〇さんは盛んに、そんなことばかり言っている。
※なお、〇〇さんは、登壇者4人の内の1人で、
メガバンク・グループの 100%子会社の 研究員
YCCやると、債券価格が、あまり動かない。
だから、債券売買で、儲けようとする人が、
儲からないので、文句を、言っている。
「 儲かる・儲からない 」 のために、
金融政策を、やってるんじゃない。
国民のために、やっているのだ。
雇用等のために、日銀は、仕事をしているのだ。
銀行が、YCCに、反対しているのは、
「 利ザヤが、稼げない 」 からだ。
▼ご注意
当初は番組での発言を、そのまま活字にしてみた。
しかし、生放送での発言内容そのままを、
活字にしても、意味が、伝わらなかった。
よって、上記のコメントは、
抜粋要約の上に、加筆等の校正等を、加えてある
そのままの発言内容は、NHK公式にて、
視聴して確認して頂きたい。
そのURLは、本ページの最下段の
「■関連ページ」に、記載してある。
-- 消費者 経済 総研 --
◆植田氏は、24日、金融緩和の変更を、語るか?
筆者(松田)は、下記だと予想する。
・金融緩和の政策は、当面、変更しない。
・緩和策の副作用が、あることは、認める。
・副作用は、検証していくが、早期の修正はしない。
-- 消費者 経済 総研 --
◆緩和を見直し?
「大規模な金融緩和を、見直しへ?」をはじめ、
下記のような様々な言葉が、世の中に、増えた。
金融緩和の 見直し、変更、修正 や、
出口戦略、緩和終了 などの様々な、言葉がある。

- ■緩和, 見直し, 引き締め とは?
-
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:そもそも、「緩和」とは、何か?
「緩和」の言葉は、ピンとこないが、
具体的には何か?
- ↓
A:「金融緩和」の具体的な手法は、様々あるが、
メインは、 「 利下げ・低金利策 」 だ。
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:緩和策の見直しとは? - ↓
A:前項の逆で、見直しは、「 利上げ 」だ。
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:低金利と言うが、今は、何%なのか?
- ↓
A:現在の日銀が、誘導する目標は、
長期金利は、0% (±0.5%)で、
短期金利は、-0.1% だ。
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:長期の金利も、短期の金利も、低くするのは、
世界で、共通か?
- ↓
A:違う。先進国の中では、日銀の独自の政策だ。
米国・中銀のFRBは、短期を、上げ下げした。
FRBは、長期の金利は、操作していない。
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:長期の金利を、操作する国は、無いのか? - ↓
オーストラリアの中銀は、コロナ禍で、
長期の金利も、引き下げたが、やめてしまった。
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:長期金利を操作するのは、副作用があるか?
- ↓
そうだ。 副作用がある。
日銀は10年物国債を、
ゼロ% ( -0.25% ~ +0.25% )に、した。
そこで、YC(イールドカーブ)が、歪んでしまった。
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:YCや、YCの歪みとは、何か?
YCの歪みで、困る人は、だれか?
- ↓
下記の別ページで、解説中だ。
あとで、そこを、読んでいただきたい。
[日銀|利上げではない・利上げしない理由]
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:植田氏は、緩和継続だと、予想した理由は? - ↓
緩和をやめる=メインは、利上げだ。
弱い日本の経済で、利上げしたら、危険だ。
学者出身として、データを元に、判断するだろう。
利上げすべき、経済データは、見当たらない。
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:利上げのメリット・デメリットは?
利上げしたら、どうなる?
- ↓
本ページの下記記載のVol.1+2で、解説中だ。
あとで、Vol.1+2を、読んでいただきたい。
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:黒田総裁は、
他国がやらない長期操作を、なぜやったのか?
- ↓
黒田氏の方針は、「大胆」 「大規模」 「徹底的」 だ。
やれる手段は、なんでもやるのだ。
その中で、YCC(イールドカーブコントロール)は、
副作用が、指摘されている。
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:植田氏は、YCCを、どうする? - ↓
植田氏の考えは、黒田氏と、大枠で一緒だ。
つまり緩和継続だ。
ただし、YCCの副作用を、気にしているので、
どこかのタイミングで、修正する可能性がある。
黒田氏も、22年12月に、YCCを微修正決定した。
(これを事実上の利上げという人がいるが、
それは間違いだ。 間違いである根拠は、
[日銀|利上げではない・利上げしない理由]
の Vol.2 を、参照
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:植田氏も、微修正を、さらにやるか? - ↓
やらないと、筆者(松田)は、予想している。
「YCCは、微修正は向かない」と言っているからだ
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:では、YCCは、廃止か? - ↓
その可能性はある。
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:いつ、YCCを、廃止するか? - ↓
今年の前半だと、予想する市場参加者も多い。
だが、筆者(松田)は、もっと後だと思う。
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:YCC撤廃とは、利上げのことか? - ↓
意味が違う。
副作用が、あるので、他国がやらないのを、
日本も、やめるという位置づけだ。
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:緩和策は、利下げで、 引き締め策は、利上げ
とのことだったが、それ以外は?
- ↓
「 量的緩和 」だ。
量的緩和策は、金融緩和策の中の、ひとつだ。
市中の「 お金の量を、増やす政策 」 である。
下記の流れの効果を、狙うのが、量的緩和だ。
日銀が、市中・民間銀行から、国債をたくさん買う
↓
国債の購入代金を、日銀は、民間銀行等へ渡す
↓
これで、市中の民間銀行のお金が、増えた
↓
増えたお金で、企業や消費者への融資を、増やす
↓
融資を受けた企業は、工場の新設などに使う
↓
工場が増えたので、その会社の売上が、増える
住宅ローンの融資を受けた人が、住宅を買う
↓
不動産会社や関連業界の売上が増える
↓
様々な取引業界の売上が増える
↓
様々な企業の社員の賃金の原資が増える
↓
賃金が増えれば、消費も増えて、お店の売上がUP
↓
景気は好循環で、拡大する
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:量的緩和を、もっと、わかりやすく、知りたい。
何かの例え話で、教えて欲しい。
- ↓
「低金利策」は、
「値下げ」を、イメージして欲しい。
100円のミカン1個を、90円に値下げすれば、
八百屋さんの、売れ残りが、減る。
「量的緩和策」は、
「在庫仕入れの増加」を、イメージして欲しい。
ミカンを、値下げしたら、すぐに、売り切れた。
そこで農家から、ミカンの仕入れ量を、増やした。
上記を、銀行に、当てはめると?
「低金利策」で、
住宅ローンが人気化し、借りる人が、増えた。
人気になったので、銀行のお金の在庫が、減った。
ローンを、借りたいのに、借りれない人が、出た。
「量的緩和策」で、
銀行の住宅ローン用のお金の在庫が、増えた。
住宅ローンの貸し出しが、増えて、
マンションの売り上げが、増えた。
不動産の業界を始め、
関連の取引業界の売上も増えた。
こうして、景気が良くなった。
※上記は理解促進のための「たとえ話」であることに留意
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:量的緩和の効果は、あったか? - ↓
効果は、少しあったが、最初の少しだけだ。
企業売上がUPでも、賃金より内部留保に回った。
賃金が増えた消費者も、貯金してしまい、
消費は、あまり増えない。
日銀が供給するお金(ベースマネー)は、凄く増えた。
だが、その先のステップである、
民間銀行から、企業や消費者へのお金の量
(マネーストック)は、それほどは、増えなかった。
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:日銀がお金を増やしても、
なぜ民間は、お金を、動かさないのか?
- ↓
デフレ思考・マイナス思考 だからだ。
デフレは、物価下落だ。
急いで、買い物するよりも、
後で買った方が、値段が、下がるのでお得だ。
つまり 「 貯金 」 してしまう。
貯金すれば、消費者の消費需要は、伸びない。
「 需要が不足 」 の状態に、なったのだ。
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:需要不足の解決策は何か? - ↓
政府部門の公共支出・公共投資を、増やすのだ。
この財政政策を、「 積極財政 」という。
民間の不足した需要を、政府の需要で補うのだ。
だが、ここで、下記を言う人が、出てくる。
「 政府が、お金を、多く使うのは、けしからん!」
こうして、積極財政ではなく、緊縮財政になり、
日本の経済は低迷を続ける。
G7(先進七か国)は、政府の支出を、増やしてきた。
残念ながら、日本は、そうではない。
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:外国の政府が、支出を、増やした証拠は?
- ↓
別ページで、
G7の政府支出の増加のグラフを、掲載してある。
下記のページを、参照頂きたい。
弱い日本経済,停滞の景気を良くするには?
上のページの中の「MMT 4|高圧経済8|爆上げ12」
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:ならば「日銀」や「金融政策」の話より、
「財政政策」の方が、重要ではないか?
- ↓
その通りだ。
既述の通り、NHK討論での岩田氏も、
財政政策が、積極財政でなく、
消極財政だから、ダメと指摘した。
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:利上げしたら、日本の経済は、
さらに低迷との話だった。
だが、最近、やたらと、「緩和見直し」と聞く。
なぜか?
- ↓
利上げを、望む陣営が、いるからだ。
既述の通り、NHK討論での岩田氏も、
債券トレーダーや、銀行利ザヤに、言及した。
筆者(松田)も、以前から、指摘している。
それを、本ページの中段 Vol.2で、解説中だ。
あとで、そこを、読んでいただきたい。

- -- 消費者 経済 総研 --
- ■Vol.3 植田氏の 経歴は?
植田 和男 氏 (71歳)は、
共立女子大 教授 ・ 東大 名誉教授で、
経済学者 (マクロ経済学、金融論)
▼学歴
筑波大附属 駒場高校 卒
東京大学の 理学部・経済学部 卒後、同 大学院進学
最終学歴は、
1980年のマサチューセッツ工科大学博士課程修了
▼職歴
卒後、複数の大学の経済学部等で、教鞭を振るう。
1998年~2005年は、日銀の審議委員を、務めた。
その他、様々な職歴あり。
※出典: 植田和男 - Wikipedia

- ■植田和男 氏 は、どんな人?
- 植田氏は、どんな人か? ハト派、タカ派か?
結論を先に言うと、「植田氏は、ハト派」であろう。
-- 消費者 経済 総研 --
◆金利での 「 ハト派 」 と 「 タカ派 」 とは?
「ハト派」 は、 金融緩和・利下げ 寄りの人
「タカ派」 は、 金融引締め・利上げ 寄りの人
なお、リフレ派は、ハト派と、ほぼ同じ意味。
-- 消費者 経済 総研 --
◆ハト派の根拠は?
一部報道で、「 植田氏は、タカ派 側 」 とされたが、
「タカ派より」ではなく、「ハト派」だろう。
その根拠を、解説していく。
-- 消費者 経済 総研 --
◆2000年8月では?
日銀の審議委員だった植田氏は、
2000年8月のゼロ金利政策の解除の議案に、
反対票を投じた。
上記は、利上げではなく、ゼロ金利を続けるべき
との意見で、「ハト派」の根拠だ。
※出典:日本銀行|金融政策決定会合議事要旨(2000年 8月11日開催分)|
-- 消費者 経済 総研 --
◆2022年7月では、どうか?
前項の情報は、23年前の話であって、古い。
では、最近では、どうか?
2022年7月に、植田氏は、下記のように述べた。
▼黒田総裁の政策を肯定
「2022年6月の日銀の会合での
政策据え置きの判断は、至極当然だ。」
黒田総裁の金融緩和の継続を、
当然だと、評価したのだ。
ハト派の黒田路線を、肯定した。
「 植田氏は、ハト派 」 であろう。
▼黒田政策への肯定の根拠は?
「金利引き上げを、急ぐことは、
経済やインフレ率に、マイナスの影響を及ぼす」
上記の通り、黒田政策への肯定の根拠として、
「 利上げは、経済にマイナス 」 と述べた。
▼低金利→円安→物価高 に、対しては?
低金利で、円安になった。
円安によって、物価高になった。
物価高というデメリットを、回避すべく、
利上げをすべきか、については、どうか?
「利上げで、円安に、ブレーキをかければ、
金利・為替両面から、景気を悪化させ、
インフレ目標達成も、一段と遠のく」
上記のように述べた。
その理由として、下記の見解を示した。
「円安は、好調な企業決算が、示すように、
日本経済にプラス。」
「プラスが少ない層 (低所得者)には、
食料・エネルギー価格上昇で、悪影響(物価高) 」
「これ(低所得者の悪影響)は、分配の問題だ。
財政で、低所得層への支援が、適切だ。」
つまりこの内容は、下記を意味する。
筆者(松田)も、過去号で、同内容の解説をしてきた。
円安は、企業が儲かり、日本の経済にはプラス
↓
一方、円安での物価高で、低所得者の暮らしには損
↓
円安で増えたお金を、低所得者へ分配すべき
※上記の「」内のコメントは、
下記出展から抜粋要約した。 原文は、下記を参照。
※出典:日本経済新聞|2022年7月|
植田和男氏「日本、拙速な引き締め避けよ」
-- 消費者 経済 総研 --
◆2023年1月10日の発言では?
2023年1月10日の夜には、下記を発言した。
「金融政策は、景気と物価の現状と、
見通しに、基いて、運営すべき。
その観点から、現在の日銀の政策は、適切。
「現状では、金融緩和の継続が、必要」
現在の日銀政策は適切で、緩和継続が必要
という事は、黒田路線を、肯定している。
ハト派の黒田総裁を、肯定した。
つまり、植田氏は、ハト派であろう。
※上記の「」内のコメントは、
下記出展から抜粋要約した。 原文は、下記を参照。
※出典:NHK|首相が日銀総裁起用意向の植田氏“現状は金融緩和継続が重要”
-- 消費者 経済 総研 --
◆緩和の副作用にも、目配り?
植田氏は、金融緩和の副作用にも、言及している。
「日銀の当面の選択肢は、副作用に目配りしつつ、
粘り強く、現行の緩和策を続け、
物価の上昇を、待つことしかない」
※出典:日経新聞| 2018年8月20日

- ■金融の市場は、どう反応したか?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆ドル円は?
円高が、一気に進んだが、円安方向へ戻した。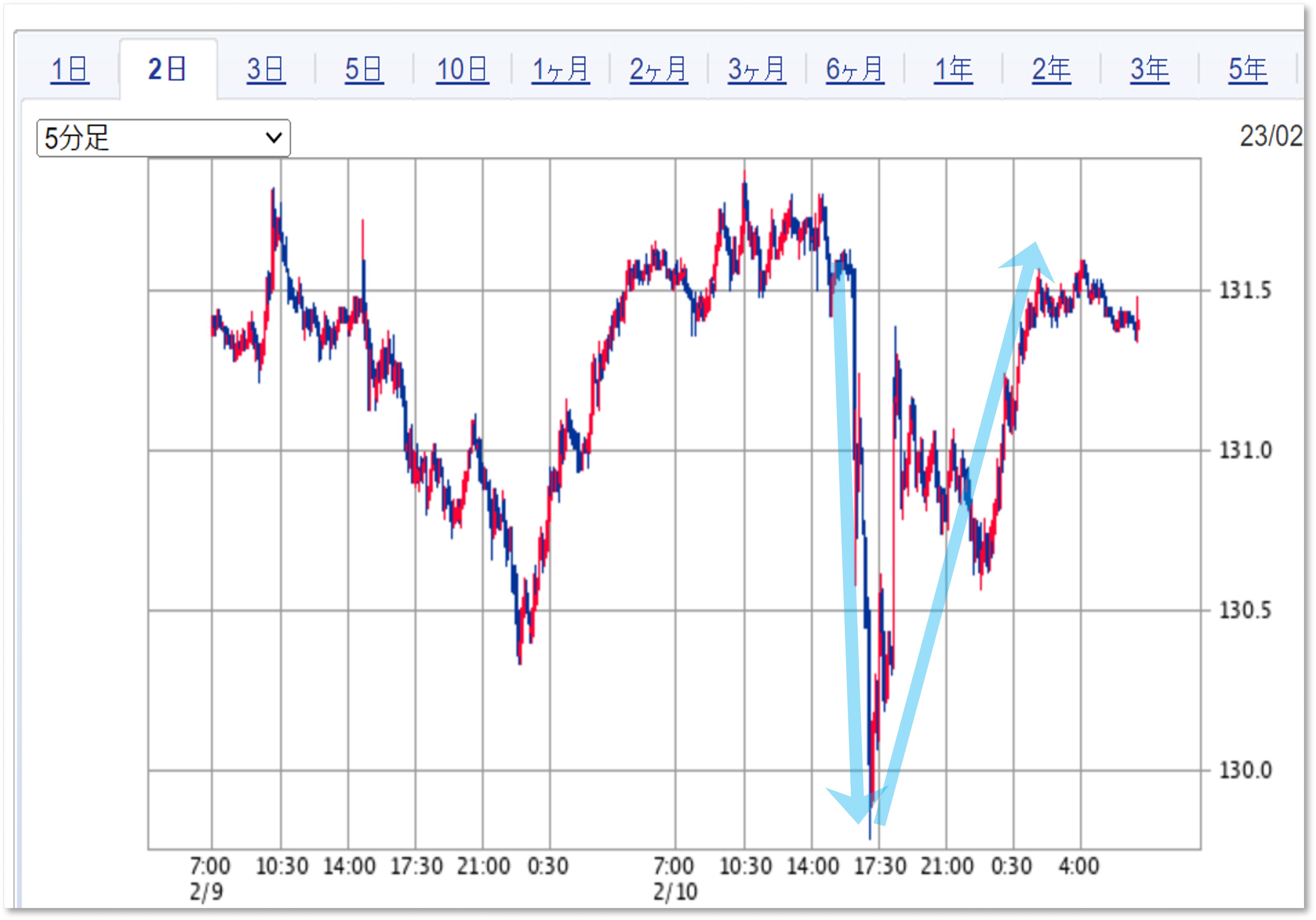 ※出典:マーケット|SBI証券
※出典:マーケット|SBI証券
-- 消費者 経済 総研 --
◆日経平均株価は?
「植田氏が次期総裁へ」は、10日夕方に、伝わった。
15時を過ぎていたので、先物価格では、どうか?
株価は、急落したが、すぐに戻した。
その後は、若干の下水準で推移。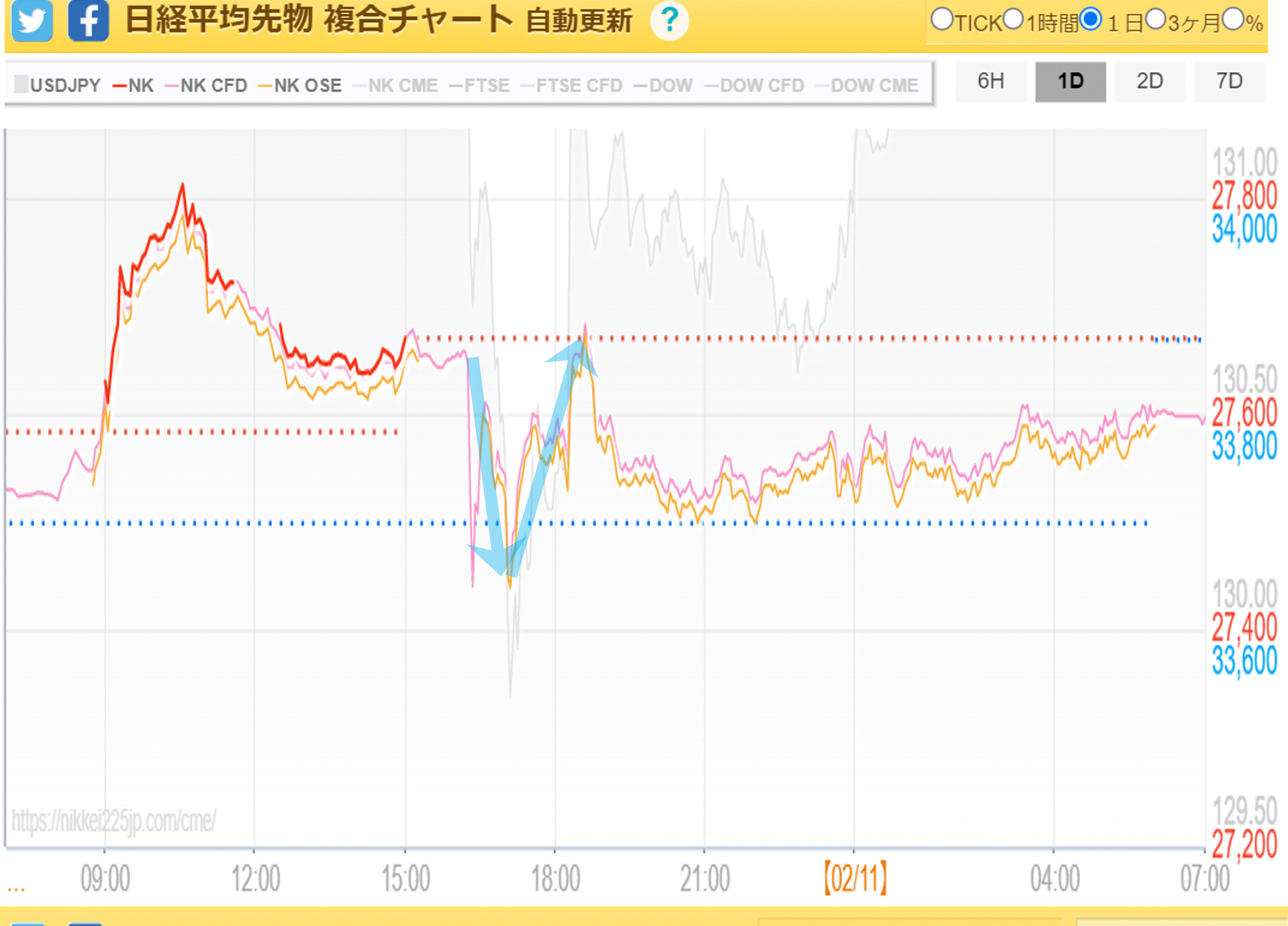 ※出典:nikkei225jp.com日経平均先物 CME SGX 大取 夜間 リアルタイム チャート
※出典:nikkei225jp.com日経平均先物 CME SGX 大取 夜間 リアルタイム チャート
-- 消費者 経済 総研 --
◆急落から、戻すとは?
「ハト派の雨宮氏」が、次期総裁だと、
市場は、予想していたのだろう。
それ以外の人物の名前が、伝わったので、
「ハト派ではない?」との見解で、
急落したのではないか?
その後、「ハト派だろう」との理解から、
戻したのではないか?

- ■金融緩和は、効果実感できない?
- 黒田路線(金融緩和)は、効果実感できない?
黒田路線の金融緩和でも、賃金は低迷中だ。
「金融緩和のプラス効果が、実感できない」
という人も、いるだろう。
マクロ経済の政策は、下記の3ジャンルだ。
①金融緩和の政策(ホップ)
↓
②財政拡大の政策(ステップ)
↓
③成長戦略の政策(ジャンプ)
-- 消費者 経済 総研 --
◆①金融緩和の 効果は?
金融緩和での金利低下で、ローン金利が、下がり、
消費者が、マンションやクルマを、買いやすくなる。
資金調達の金利も下がり、
企業も、借金して新規の設備投資が、しやすくなる。
だが、日本の経済が、元気不足なので、
企業の新規投資や、消費者の需要が、伸び悩む。
伸び悩む理由は、「日本は、需要不足」だからだ。
そこで、その需要不足を、政府支出で、埋めるのだ。
それが、②の財政拡大の政策(ステップ)である。
だが日本は、財政拡大が、不十分なので、低迷だ。
財政拡大とは、政府の支出・投資を、増やすことだ。
それが、不十分だから、日本は低迷なのだ。
財政支出の拡大のためには、財源が必要だ。
主な財源は、「増税」か、「国債の増発」だ。
増税なんかしたら、更なる低迷が、待っている。
失われた20年のスタートは、1997年の増税だ。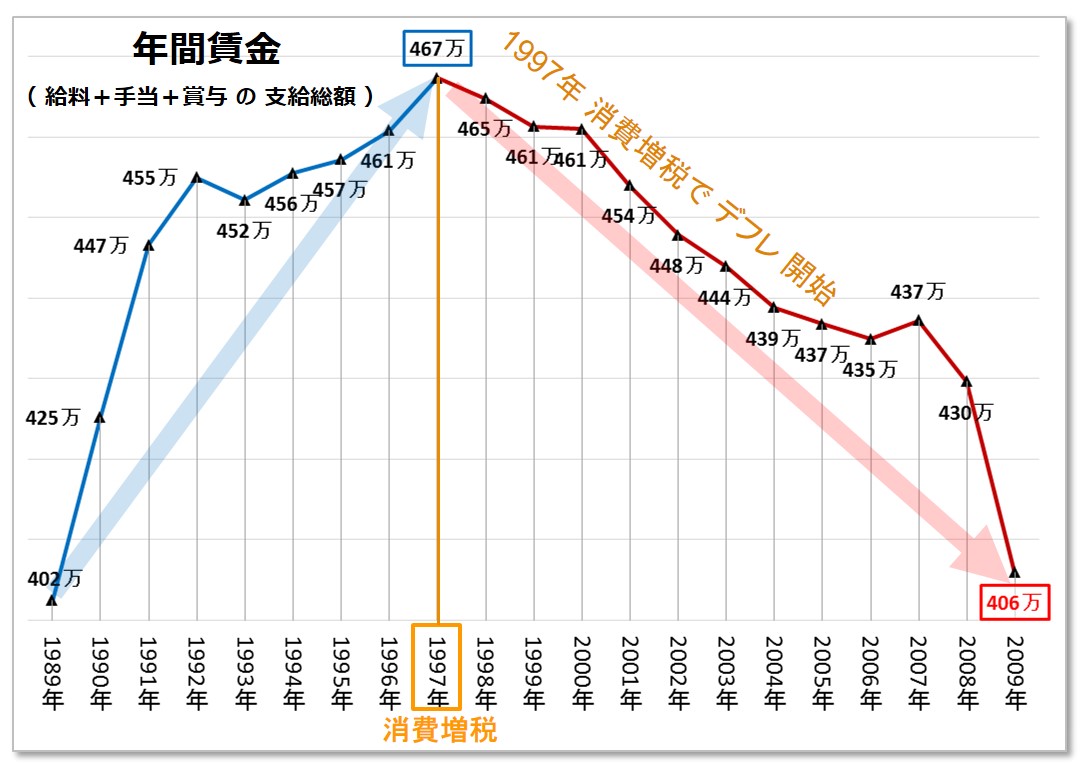
増税は、NGである。
すると、財源は、
国債の増発、つまり国の借金の増加だ。
ここで、「借金は、けしからん!」
という意見が、出てきてしまう。
日本は、借金大国ではないし、
今後、さらに借金が、増えても問題ない。
この件は、下記の別ページを参照頂きたい。
「なぜ日本借金大国は嘘」
借金増やして、財源増やして、政府支出を増やす。
これで、経済成長と賃金UPが、実現する。
先進諸国は、それを十分に、やっているが、
日本だけが、不足している。
借金増やすことは、賃金UPの原資だ。
次項のグラフを、見れば、一目瞭然だ。

- ■先進七ヵ国は、どうか?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆先進諸国は、借金増加?
国債の増発は、日本、米国だけではない。
つまり先進諸国は、国の借金を、増加させている。
-- 消費者 経済 総研 --先進7か国は、
・政府予算の財源は、国債等
↓
・国の借金も、増加させた
◆先進7国の 借金は?
G7(先進7ヵ国)の 借金は、どう増えたか?
↓
2005年を100とした場合の、2020年の増加率だ
↓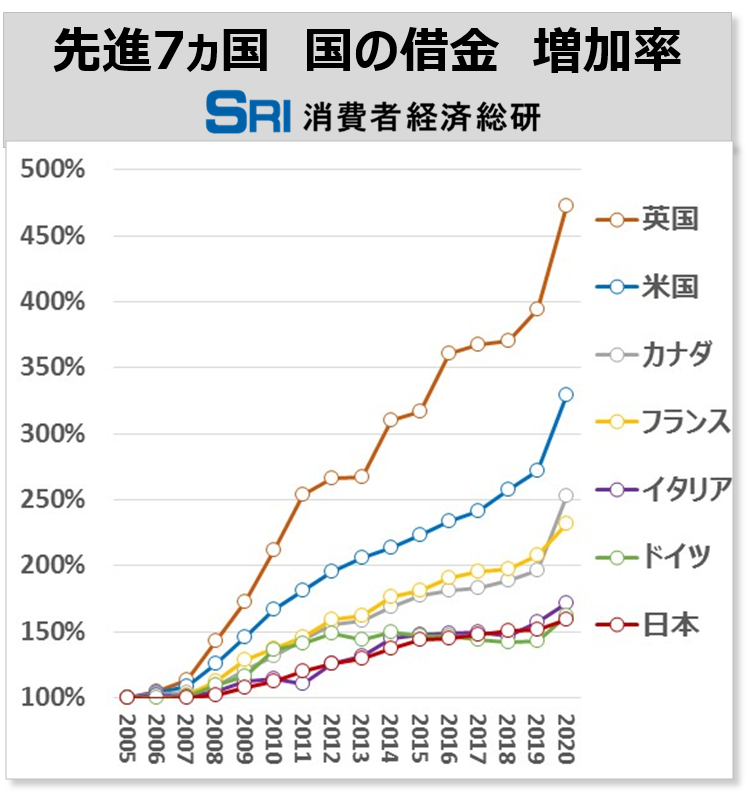 ↓
↓
英 国 473%
米 国 329%
カナダ 253%
フランス 232%
イタリア 172%
ドイツ 162%
日 本 159%
↓
日本が、最も借金残高の増加が、少ない
-- 消費者 経済 総研 --
※上のグラフの対象は、Liabilities
(IPSGS(年金等)ある場合は、それを除く)
※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成
※出典 :IMF | Balance Sheet-IMF DataGBR:2020年3,052 ÷ 2005年646 =473%
USA:2020年27,757 ÷ 2005年8,435 =329%
CAN:2020年2,988 ÷ 2005年1,183 =253%
FRA:2020年3,370 ÷ 2005年1,451 =232%
ITA:2020年3,050 ÷ 2005年1,773 =172%
DEU:2020年2,649 ÷ 2005年1,638 =162%
JPN:2020年1,311,292 ÷ 2005年823,067= 159%
(Unit: Domestic currency. Scale: Billions)
◆日本の 借金の増加 は、少なすぎる?
「 国の借金の増加 」 は、先進諸国では共通だ。
日本では、「 国の借金は ダメ 」と、言う人がいる。
国の借金は、問題ないのだ。
それどころこか、日本の借金増加は、少なすぎる
日本の 借金の増加 は、
少なすぎる
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本だけが低迷 その原因は?
先進7か国の賃金推移 (2005年を100)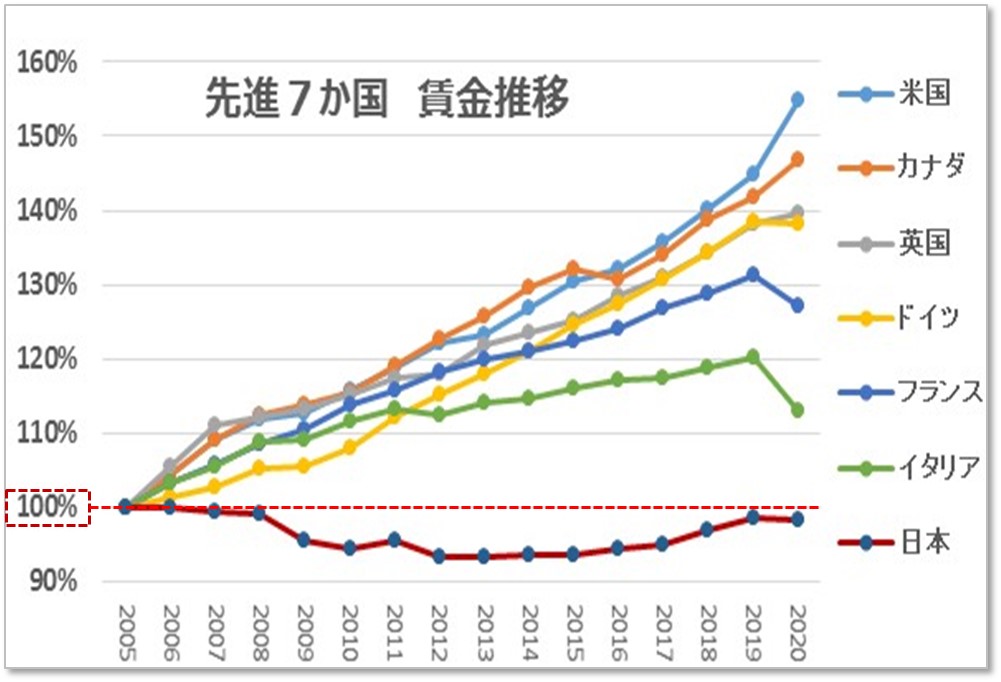 ※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成
※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成
※出典:OECD|Average annual wages
良く知られた事だが、日本の賃金は、低迷中だ。
「借金増加率」と、「賃金推移」 の相関を見てみる。
賃金UP率の上位3か国では、どうか?
1位の米国、2位のカナダ、3位の英国は、
借金増加率と、賃金UP率 の相関は極めて高い。
上位3か国の借金・賃金の相関係数は、どうか?
上の2図(2005年~2020年)の相関係数は、下記だ。
・米 国 0.99
・カナダ 0.97
・英 国 0.97
相関係数は、「 ゼロ ~ 1まで 」の値で、表される
全く相関が無いが「ゼロ」だ
完全に相関するのが「1」だ。
一般に、「相関係数」は、下記が目安とされる
* 0.7~1.0 → 強い相関がある
* 0.4~0.7 → 相関あり
* 0.2~0.4 → 弱いが相関あり
* 0 ~0.2 → ほぼ相関なし
先進諸国は、日本よりも、借金を、増やしてきた。
日本の借金の増加率は、低いのだ。
外国は、借金を増やして、政府財源を増やした。
借金増は、景気UPと、国民の便益UPのためだ。
日本低迷の理由の1つは、借金増が少ないからだ。
日本経済が弱いから、借金を増やした のではない。
借金増加が少ないから、日本経済が低迷したのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本は、外国のマネを、すべき?
日本の賃金伸び率は、
先進国の7か国の中で、ビリの7位だ。
ビリなら、1位~6位の国の方法を、真似するのだ。
つまり、国の借金をもっと、大胆に増やすのだ。
増税なんかしたら、日本の賃金は低迷のままだ。
世間の常識とは違うが、これが「真実」である。
この真実に、与党も野党も、気づき始めた。
国民民主党、れいわ新選組は、
これを、早くから、気づいていた。
自民党も、遅まきながら、気づき始めた。
与党・野党が、借金肯定へ変化した様子は、
下記の別ページを、ご覧頂きたい。
「諸外国と、日本の政治家」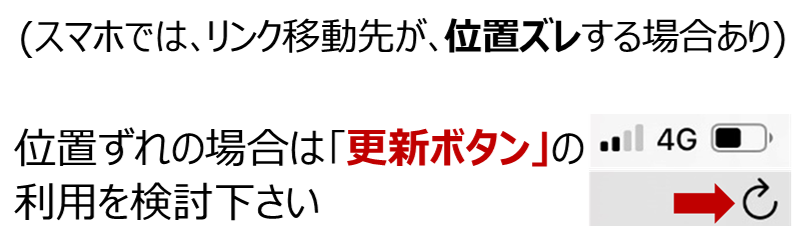
日本が低迷から、脱出するために、
このページ内容は、広がって欲しい。
ぜひ、このページへリンク設定、をお願いしたい。
日本は、外国よりも、
・借金増加が、少なすぎる
・政府の支出が、少なすぎる
借金と支出が、少なすぎるのが、
日本低迷の 原因の1つだ
-- 消費者 経済 総研 --
◆利上げしたら、どうなる?
「金融緩和・低金利」と「金融引き締め・利上げ」の
それぞれのメリット・デメリットは?
下記の過去号で、解説してある。

- ■Vol.1どうなる?今後の日銀と日本
- 日銀の黒田総裁が、4月8日に、任期満了となる。
「 次の日銀総裁は、誰? 〇〇さんか? 」 と、
日本そして海外からも、注目を集めている。
交代後の新総裁しだいで、
日本は、〇〇になるリスクがある。
★では、ここで問題:
〇〇のリスクとは、何か?
↓
答えは、本ページで、後述
-- 消費者 経済 総研 --
◆日銀総裁は、誰が、決める?
★では、ここで問題:
総裁を決める 任命権者は、〇〇?
内閣は、総裁に最適任と考えられる者を、選定し、
衆参両院の同意を得て、任命する。
決めるのは、内閣だ。
つまり、内閣総理大臣の岸田氏は、任命に関わる。
岸田首相が、自身の意向を、
どの程度、反映させるかは、あまり見えてこない。
※任命権者 出典:日本銀行法第23条|
総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
※参考:日本銀行総裁の任命基準に関する質問に対する答弁書
-- 消費者 経済 総研 --
◆次の後任総裁は、いつ、決まる?
★ここで問題:
次の総裁の候補の氏名が、
出るのは、いつか?
後任人事を、2月10日に、政府が国会に提示する
との、一部報道があった。
2月7日追記:「来週(2月13日~17日)に、
国会に提示する方向で調整している」と報道。
※出典:Reuters|政府、日銀の正副総裁案を来週国会に提示へ
-- 消費者 経済 総研 --
◆岸田首相の得意・不得意は?
★ここで問題:
岸田首相の 得意は、 □□
岸田首相の 不得意は、 〇〇
岸田氏の過去の外務大臣のキャリアは、立派だ。
在職期間は、戦後の外務大臣としては、歴代2位で、
専任の外務大臣としては、歴代最長だ。
得意な外交では、手腕を発揮できる。
だが、金融経済の手腕には、懸念点がある。
日銀総裁の選定は、今後の日本に、
多大な影響を及ぼす、重要な決定だ。
どうなるか、心配である。
※外務大臣キャリア 出典:岸田文雄 - Wikipedia

- ■次期総裁の候補は?
- 次期総裁の話をする前に、
現在の総裁の黒田氏の政策を、振り返っておく。
-- 消費者 経済 総研 --
◆黒田総裁は、どういう政策だった?
★ここで問題:
黒田総裁の政策の 特徴は、 何か?
「 黒田バズーカ砲 」 「 異次元の金融緩和 」
などの言葉でも、表現された。
前例のないレベルの「 大胆な 金融緩和 」だ。
大胆で徹底的に、金融緩和を実施したのが特徴だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆次期総裁は、誰が、なる?
★ここで問題:
次期総裁の 候補者の名前は、〇〇?
次期総裁が、誰になるかは、大きな関心ごとだ。
次期総裁の候補には、複数人の氏名が、噂される。
その中でも、下記3人が有力だと、されている。
・雨宮 正佳 氏 (あまみや まさよし)
・中曽 宏 氏 (なかそ ひろし)
・山口 広秀 氏 (やまぐち ひろひで)
-- 消費者 経済 総研 --
◆黒田総裁と次期総裁
黒田氏の特徴は、とことん徹底した金融緩和策だ。
具体的な緩和策の1つに、「 低金利政策 」 がある。
黒田総裁の退任後は、どうなるか?
次期総裁は、金利を、上げるのか?
-- 消費者 経済 総研 --
◆雨宮氏、中曽氏、山口氏のスタンスは?
雨宮氏、中曽氏、山口氏
ハト派 ← → タカ派
上記のように言われる。
金利での 「 ハト派 」 と 「 タカ派 」 とは?
「ハト派」 は、 金融緩和・利下げ 寄りの人
「タカ派」 は、 金融引締め・利上げ 寄りの人
黒田氏は、 強い ハト派 (利下げ側) だった。
ハト派・雨宮氏は、黒田路線を、概ね踏襲しそうだ。
雨宮氏ではなく、
タカ派の候補が、総裁になったら、何が起きるか?
利上げ、つまり、政策金利の引き上げが、
実施される可能性がある。

- ■利上げしたら、どうなる?
★問題:利上げしたら、日本は、〇〇になる?
↓
消費者、企業、経済へのダメージになる
-- 消費者 経済 総研 --
◆消費者への影響|住宅ローンでは?
★ここで問題:
30年住宅ローンで、金利が、1%UPしたら
負担額は、 いくら増える?
パワーカップルが、1億円のマンションを、
フルローンで、購入するケースでは、どうか?
変動型の住宅ローンの金利は、どのくらいか?
黒田総裁の体制での最近では、0.4% 程度だ。
前任の白川総裁の時代の平均は、1.4% 程度だ。
1億円の住宅ローンの金利が、
0.4%ならば、1年で、40万円の利子を、負担する。
金利が、1.4%ならば、
1年で、140万円もの利子を、負担する。
1年間で、上記のように、100万円差が出る。
30年間のローンなら、とても大きな差になる。
満期30年で、元利均等払いでの、
支払う利子の合計は、どうか?
0.4%で、 632万円 の利子
↓
1.4%で、2,315万円 の利子
後者は、1,683万円もの利子の負担が、増加する。
なお、1億円ではなく、5千万円ならば、
半分の842万円の利子の負担増加だ。
(もちろん、この利子以外に、元本返済が、別途ある)
利上げは、
住宅ローンの負担を、
大きく増やす
-- 消費者 経済 総研 --
◆マンション以外でも、消費者へダメージ?
★ここで問題:
マンションの業界以外に、
自動車の業界では、 どうか?
マイカーローンも、利上げでは、利子が増える。
↓
ローンでのクルマ購入では、負担は増えてしまう。
利上げは、
消費者へ、ダメージを、与える
-- 消費者 経済 総研 --
◆利上げは、企業にも、ダメージ?
前項は、消費者へのダメージだった。
★では、ここで問題:
消費者 以外に、
企業へのダメージも、あるか?
金利が上がれば、
マンションを、買おうとする人が、減る。
マンションの売上ダウン
↓
不動産会社の売上ダウン
↓
関連業界 (家具、家電、引越等の業界)の売上も減少
↓
部材業界 (鉄、コンクリ、内装、設備)の売上も減少
↓
不動産業界、関連業界、部材業界の、利益が減る
↓
様々な業界に、広く、ダメージが及ぶ
利上げのダメージは、
消費者だけ ではなく、
企業にも およぶ利上げすれば、
関連する業界の売上・利益も、減少
-- 消費者 経済 総研 --
◆自動車の業界では、どうか?
マイカーローンも、金利UPで、負担増になる。
↓
クルマを買う人が、減る
↓
自動車会社の売上は、ダウン
↓
関連業界 (部品・資材・原材料の業界)の売上も減少
↓
自動車業界や関連業界の、利益が減る
↓
様々な業界に、広く、ダメージが及ぶ
利上げ すれば、
様々な業界に、ダメージ
-- 消費者 経済 総研 --
◆企業の利益が、減ると?
前項で、利上げで、企業の利益は減少と解説した。
★ここで問題:
企業の利益が、減ると、
私たちの賃金は、 どうなる?
利上げで、様々な業界に、広く、ダメージが及ぶ
↓
各業界の利益減少で、各業界の賃金の原資が減る
利上げで、
私たちの 賃金の原資 も、
減って しまう
-- 消費者 経済 総研 --
◆個人投資家 ( 株主 ) への影響は ?
★ここで問題:
利上げすると、株価は、〇〇になる?
利上げをすれば、国債から貰える利息は、増える
↓
金融商品の中で、国債等の利付商品が、人気になる
↓
相対的に、株式投資の魅力が、下がる
↓
つまり、利上げをすれば、株価は、下落する
↓
個人投資家の株主への、ダメージになる
利上げで、
株価下落し、
個人投資家へ、ダメージになる
-- 消費者 経済 総研 --
◆学生や、親御さんには?
★ここで問題:
大学生で、 奨学金ローンを、
利用する人の 割合は?
↓
約半数が、利用する。
※出典:奨学金を受けている学生の割合はどれくらい?
|公益財団法人 生命保険文化センター
利上げで、
学生さんや、親御さんの
負担が、増える。
-- 消費者 経済 総研 --
◆利上げで、 企業の 設備投資は ?
★ここで問題:
利上げを、すると、
企業の 新規の 設備投資は、 どうなる ?
例え話で解説する (金額などは仮の数値)
自動車メーカーが、工場の増設をするケースでは?
工場が、増設されれば、車の生産台数が、増える。
その増えたクルマを、海外へ輸出する。
その企業の売上は、増える。
工場増設の費用は、100億円だとする。
100億円を、銀行から借金する。
金利が1%なら、1年で1億円の利子を、負担する。
金利が2%なら、1年で2億円の利子を、負担する。
金利上昇では、企業は工場を、増設しにくくなる。
金利が上がれば、経済拡大へ、ブレーキだ。
利上げ すれば、
企業の 設備投資を 抑制し、
経済拡大へ、 ブレーキになる
-- 消費者 経済 総研 --
◆設備投資を、しなくても、 ダメージ?
★ここで問題:
新増設の 設備投資を、しなくても、
利上げは、企業のコストへ、影響する?
新設・増設ではなくても、
既に借り入れた借金の利子が、増えてしまう。
支払利子は、企業のコストだ。
コストUPになれば、賃金の支払い原資が減る。
設備投資 しなくても、
企業のコストは UPする
利益が減ると、
賃金の原資が、 減ってしまう
-- 消費者 経済 総研 --
◆賃貸住宅にも?
既述の通り、
利上げすれば、住宅ローンの負担が、増える。
★ここで問題:
自分は、 「 賃貸派 」 だから、関係ない?
違う。 賃貸住宅にも、利上げは、影響してくる。
不動産の業界は、借入の依存度が、高い。
不動産企業は、収入(売上金)を、受け取る前に、
土地代金の支払い、建設工事金の支払が発生する。
つまり、先行投資額が、大きいので、
借金の依存度が、高くなる。
利上げで、借金の支払利子というコストが増える。
利上げは、コスト・プッシュ なのである。
コストが増えた分、それを回収すべく、
収入(売上金)である家賃を、上げる圧力が、かかる。
利上げ→コストプッシュ→家賃の値上げへ
利上げ
↓
コストプッシュ
↓
家賃の値上げへ

- ■利上げの デメリットは?|まとめ
- ★ここで問題:
ここまでの 「 まとめ 」 として、
利上げすると、 どうなる ?
-- 消費者 経済 総研 --
◆国民への ダメージは?
・消費者には、住宅や車等の購入で、ダメージ
・奨学金ローン利用の学生・親御さんに、ダメージ
・個人投資家には、株価下落のダメージ
-- 消費者 経済 総研 --
◆企業への ダメージは ?
・消費者の買物が減り、 企業の売上・利益が減る
・企業の設備投資が減り、売上UPの機会が減る
・新増設でなくても、既存の借金の利払いが増える
-- 消費者 経済 総研 --
◆働き手への ダメージは ?
・企業の利益減少で、私たちの賃金の原資が減る
・企業売上UPの機会の減少で、賃上げ機会を減らす
利上げをすれば、
消費者 にも、 ダメージ
企 業 にも、 ダメージ
働き手 にも、 ダメージ
景気も悪化へ。

- ■Vol.2 利上げの利点,為替影響
- -- 消費者 経済 総研 --
◆前回号 Vol.1 (本ページ上段に記載)は?
前回号 Vol.1で、
利上げしたら、消費者・企業・働き手のいずれにも、
ダメージを与えることを、解説した。
利上げは、デメリット多いことも、わかった。
前回号 Vol.1で、
利上げは、
デメリットが、多かった
-- 消費者 経済 総研 --
◆今回号 Vol.2は?
利上げに メリット あるか?
利上げに 誘導する 陣営の 狙いは?
今回号(続編 Vol.2)では、下記を解説していく。
・利上げしたら、為替(ドル円)は、どうなる?
・円安と円高 どちらが、望ましいか?
・利上げの メリットは、〇〇?
・「日銀の政策が変わる」 と言う陣営の狙いは〇〇?
・「金融緩和を修正せよ」 と言う陣営の狙いは〇〇?

- ■為替への影響は?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆利上げ すると、 為替は、 どうなる ?
★ここで問題:
日本の金利が、 上がると、
ドル円は、 どうなる ?
日本で、利上げすると
↓
日本国債は、貰える利息が増えて、魅力度が上がる
↓
日本の国債を、買う人が、増える。
↓
外国人が、日本の国債を買うには、日本の円が必要
↓
外国の通貨を売り、日本円を買う人が、増える
↓
こうして、円高になる。
↓
利上げすると、為替は、円高へ
利上げすると、為替は、円高へ
-- 消費者 経済 総研 --
◆円安と円高 どちらが?
★ここで問題:
円安と円高、 どちらが 儲かる ?
円高(1ドル103円)の時は、どうか?
↓
外国人が、1ドル払って、日本の商品を買うと?
↓
日本人は、1ドルを、手に入れる
↓
日本円に交換し、103円のお金を、手にする
↓
円安(1ドル151円)の時は、どうか?
↓
日本人は、151円の日本円を、手にする
↓
同じ1ドルの販売で、円高では103円だけだが、
円安なら、151円も、貰える
↓
日本の輸出企業では、どうか?
↓
円安なら、日本の輸出企業は、儲かるのだ
円安で、日本の輸出企業は、儲かる
-- 消費者 経済 総研 --
◆円安で、どのくらい、儲かったか?
★ここで問題:
円安で、 日本の企業 は、
どのくらい、 儲かったか ?
円安効果もあって、2021年4~2022年3月の期は、
トヨタ自動車は、「 過去 最高利益 」を、出した。
2021年4月~2022年3月の期は、
上場企業の 約3割 もが、最高益を出した。
最高益が3割にも至ったのは、30年ぶりだ。※1
理由は、主に「 円安効果 」だ。
その後も、2022年4~6月期・法人企業統計では、
「 全産業の 経常利益の額は、過去最高 」 だ。
(金融・保険除く)※2
※1出典:日本経済新聞 電子版|2022年5月14日
※2出典:日本経済新聞 電子版|2022年9月1日
円安で、企業は、過去最高の儲けに、なったのだ。
円安で、企業は、過去最高の儲け
-- 消費者 経済 総研 --
◆利上げ → 円高 では?
★ここで問題:
「 利上げ → 円高 」に、
なったら、 どうなる ?
円高では、前項の円安の時とは、逆の現象になる。
「利上げ→円高」で、企業の利益は、減る。
企業利益の減少で、賃金の原資が、減ってしまう。
利上げ→円高で、
企業の儲けは、減る。
つまり、私たちの賃金の
原資が、減ってしまう。

- ■利上げの メリットは?
- 前項まで、利上げのデメリットを、解説してきた。
利上げは、デメリットが、多かった。
★ここで問題:
では、利上げで、デメリットではなく、
メリットは、 あるか ?
-- 消費者 経済 総研 --
◆普通預金の 利息は ?
★ここで問題:
普通預金の 「金利」 は、 何% か?
今の黒田体制と、前の白川体制での 差は?
黒田総裁の体制での最近では、 0.001% 程度だ。
前任・白川総裁の時代の平均は、0.06% 程度だ。
1,000万円の普通預金なら、
0.001%では、1年で、100円の利息を、貰える。
金利が、0.06%ならば、
1年で、6千円の金利を、利息を、貰える。
1年間で、5,900円の差しかない。
利上げになっても、普通預金からの受取利息は、
たいして増えないだろう。
※出典:日銀|主要時系列統計データ表
※参考:平均貯蓄額1,077万円|厚生労働省
利上げ になっても、
普預金からの 受取利息は、
たいして 増えない
-- 消費者 経済 総研 --
◆利上げ→円高→物価の影響は?
本ページで既述の通り、
低金利→円安で、 円安は、輸出に有利だった。
また、利上げすると、 「為替は、円高へ」だった。
円高では、貿易は、どうか?
★ここで問題:
円高は、 輸入に、有利か ?
円高は、 輸入物価を、下げるか ?
円安(1ドル151円)の時は、どうか?
↓
1ドルの商品の輸入では、151円も払う必要がある
↓
輸入物価がUPし、国内の物価も上がる
↓
消費者の支払いが、増える
円高(1ドル103円)になれば、どうか?
↓
外国の1ドルの商品を、103円で輸入できる
↓
輸入物価が下がり、国内の物価も下がる
低金利 → 円安 → 物価高 が、 デメリットで、
利上げ → 円高 → 物価安 が、 メリットだ。
低金利→円安→物価高 :デメリット
利上げ→円高→物価安 :メリット
-- 消費者 経済 総研 --
◆利上げのメリットを、まとめると?
本ページでは、上段~中段で、
利上げは、デメリットが様々あると、解説した。
続いて、利上げのメリットも、解説した。
★ここで問題:
「まとめ」として、
利上げの メリット 2つは ?
① 預貯金の利息が、少し増える
(前例では、1,000万円なら、5,900円だけ増えた)
② 円高で、輸入物価が低下し、物価安
-- 消費者 経済 総研 --
◆円安は、メリット・デメリットどっち?
★ここで問題:
日本は、全体では、
円安と円高 どっちが、お得 ?
円安で、日本の企業は、最高に、儲かった。
企業の儲けが増えたので、賃金UPの原資も増えた
後は、2023年の春闘以降で、
企業の儲けを、賃金UPへ、しっかり回すことだ。
円安での輸出では、外国から貰うお金が、増えた。
円高では、外国から貰うお金が、減ってしまう。
円安では、外国から貰うお金が、増
円高では、外国から貰うお金が、減
「 値上げラッシュは嫌だから、円高にすべき 」
という意見もある。
これは、 「 物価が下がる = デフレの期待 」 だ。
しかし、これでは、
「 マイナス思考・デフレ脳 」 に、戻ってしまう。
失われた20年は、デフレの20年だ。
マイナスがマイナスを生む悪循環の、
デフレ・スパイラルは、下記だ。
企業の売上と利益が、下がる
↓
賃金が、下がる
↓
消費者の買い物が、減る
↓
企業の売り上げが、減る
↓
賃金が、下がる
↓
この「悪循環」を繰り返すのが、デフレスパイラル
★ここで問題:
悪循環ではなく、「 好循環 」 とは?
企業の売上と利益が、増える
↓
賃金が、上がる
↓
消費者の買い物が、増える
↓
企業の売上げが、増える
↓
賃金が、上がる
↓
これを繰り返すのが、「 好循環 」 だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本と、諸外国の 違いは ?
外国は、プラスが、プラスを生む 「 好循環 」だ。
日本は、どうか?
マイナスがマイナスを生む 「 悪循環 」の時は多い。
先進国の中で、日本だけが、「悪循環」傾向にある。
日本も、「好循環」へ、移行すべきなのだ。
「円高で、物価ダウン」を、期待したら、
悪循環から、抜け出せない。
「円高で、物価安」を、期待したら、
悪循環から、抜け出せない。
-- 消費者 経済 総研 --
◆円安が有利|別のロジックでは?
「モノの貿易収支」 に、サービス収支、所得収支も、
合計した「経常収支」では、日本は黒字なので、
「円安有利」は、変わらない。
経常収支から、「再投資分」を除外しても、黒字だ。
「金融収支」も黒字で、「円安有利」は、変わらない。
本件は、下記ページも参照されたい
悪い円安論は 嘘? 悪い円安,良い円安とは?

- ■日銀の政策が変更へ?
日銀の極端な政策は、まもなく、修正すべき
日銀の緩和策は、正常化(出口)へ、向かうべき
上記の言説が、増えた。 その理由は、何か?
① 日銀批判で、目立ちたいから?
② 単なる知識不足?
③ ポジショントークや、セールストーク?
-- 消費者 経済 総研 --
◆批判した方が、目立つ?
「 日銀政策は、そのままでよい 」
または
「 日銀政策は、やばい。 修正せよ 」
前者の「 日銀政策は、そのままでよい 」 のテーマで
評論家が、執筆しても、目立たない。
「 日銀政策は、やばい。 修正せよ 」
の方が、目立つ。
目立てば、アクセス数などの増加に、寄与する。
-- 消費者 経済 総研 --
◆金利が、高い方が、有利な業種は?
金利上昇で、有利になる業界が、ある。
銀行や、生命保険の業界だ。
既述の通り、利上げ局面でも、
普通預金の金利は、あまり上がらない。
一方で、貸出しの方の住宅ローン金利は、
それよりも、上昇幅が大きい。
①運用収益:住宅ローン金利等の上昇幅
②調達費用:普通預金 金利等の上昇幅
利上げ局面では、上昇幅は、① > ② だ。
つまり利上げで、銀行等は、利幅が、向上する。
-- 消費者 経済 総研 --
◆金融・経済の 評論家の 肩書は?
金融・経済のジャンルで、言説を発する、
評論家、アナリスト、エコノミストの所属は?
金融機関やその子会社に、所属する人も多い。
経済評論家には、中立客観の発言する人もいるが、
自社や自分に、有利な発言する人もいるだろう。
これを、「 ポジション・トーク 」 という。
※なお、ポジショントークだからと言って、
直ちにNGではない。

- ■どーする? 岸田首相?
- 既述の通り、岸田首相は、
外交においては、素晴らしいキャリアを持つ。
だが、経済政策の手腕は、不透明だ。
(というより、大変心配だ。
マクロ経済学の知見が、不十分だと、思われる)
岸田首相には、
日銀総裁人事を、ぜひ適切に、判断して頂きたい。
「 聞く力 」 の岸田首相には、
ぜひ、中立客観で有益な話を、聞いて頂きたい。
「聞く相手」を、間違えないで、頂きたい。
利上げしたら、日本は、衰退だ。
日銀総裁人事は、極めて重要な決定事項だ。
利上げしたら、日本は、衰退だ。
日銀総裁人事は、
極めて重要な 決定事項だ。

- ■関連ページ
- NHK 日曜討論 日銀新体制へ 金融緩和の行方は
2/19(日) 午前9:00-午前10:00

| ■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので、 「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆である事を念頭に置いて下さい。 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、 対応して下さい。また「免責事項 」をお読みください。 ■引用 真っ暗なトンネルの中から出ようとするとき、 出口が見えないと大変不安です。 しかし「出口は1km先」などの情報があれば、 真っ暗なトンネルの中でも、希望の気持ちを持てます。 また、コロナ禍では、マイナスの情報が飛び交い、 過度に悲観してしまう人もいます。 不安で苦しんでいる人に、出口(アフターコロナ)という プラス情報も発信することで、 人々の笑顔に貢献したく思います。 つきましては、皆さまに、本ページの引用や、 URLの紹介などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件をご覧下さい。 |
- 【著作者 プロフィール】
- ■松田 優幸 経歴
(消費者経済|チーフ・コンサルタント)
◆1986年 私立 武蔵高校 卒業
◆1991年 慶応大学 経済学部 卒業
*経済学部4年間で、下記を専攻
・マクロ経済学(GDP、失業率、物価、投資、貿易等)
・ミクロ経済学(家計、消費者、企業、生産者、市場)
・労働経済
*経済学科 高山研究室の2年間 にて、
・貿易経済学・環境経済学を研究
◆慶応大学を卒業後、東急不動産(株)、
東急(株)、(株)リテール エステートで勤務
*1991年、東急不動産に新卒入社し、
途中、親会社の東急(株)に、逆出向※
※親会社とは、広義・慣用句での親会社
*2005年、消費・商業・経済のコンサルティング
会社のリテールエステートに移籍
*東急グループでは、
消費経済の最前線である店舗・商業施設等を担当。
各種施設の企画開発・運営、店舗指導、接客等で、
消費の現場の最前線に立つ
*リテールエステートでは、
全国の消費経済の現場を調査・分析。
その数は、受託調査+自主調査で多岐にわたる。
商業コンサルとして、店舗企業・約5000社を、
リサーチ・分析したデータベースも構築
◆26年間の間「個人投資家」としても、活動中
株式の投資家として、
マクロ経済(金利、GDP、物価、貿易、為替)の分析や
ミクロ経済(企業動向、決算、市場)の分析にも、
注力している。
◆近年は、
消費・経済・商業・店舗・ヒットトレンド等で、
番組出演、執筆・寄稿、セミナー・講演で活動
◆現 在は、
消費者経済総研 チーフ・コンサルタント
兼、(株)リテール エステート リテール事業部長
◆資格は、
ファイナンシャル・プランナーほか
■当総研について
◆研究所概要
*名 称 : 消費者経済総研
*所在地 : 東京都新宿区新宿6-29-20
*代表者 : 松田優子
*U R L : https://retail-e.com/souken.html
*事業内容: 消費・商業・経済の、
調査・分析・予測のシンクタンク
◆会社概要
「消費者経済総研」は、
株式会社リテールエステート内の研究部署です。
従来の「(株)リテールエステート リテール事業部
消費者経済研究室」を分離・改称し設立
*会社名:株式会社リテールエステート
*所在地:東京都新宿区新宿6-29-20
*代表者:松田優子
*設立 :2000 年(平成12年)
*事業内容:商業・消費・経済のコンサルティング
■松田優幸が登壇のセミナーの様子
- ご案内・ご注意事項
- *消費者経済総研のサイト内の
情報の無断転載は禁止です。
*NET上へ「引用掲載」する場合は、
①出典明記
②当総研サイトの「該当ページに、リンク」を貼る。
上記の①②の2つを同時に満たす場合は、
事前許可も事後連絡も不要で、引用できます。
①②を同時に満たせば、引用する
文字数・情報量の制限は、特にありません。
(もっと言いますと、
①②を同時に満したうえで、拡散は歓迎です)
*テレビ局等のメディアの方は、
取材対応での情報提供となりますので、
ご連絡下さい。
*本サイト内の情報は、正確性、完全性、有効性等は、保証されません。本サイトの情報に基づき損害が生じても、当方は一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。
- 取材等のご依頼 ご連絡お待ちしています
- メール: toiawase★s-souken.jp
(★をアットマークに変えて下さい)
電 話: 03-3462-7997
(離席中が続く場合は、メール活用願います)
- チーフ・コンサルタント 松田優幸
- 松田優幸の経歴のページは「概要・経歴」をご覧下さい。