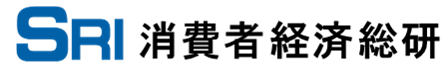GDPとは?内訳の見方や名目,実質,季節調整,年率換算,デフレーター等を簡単解説|消費者経済総研|2023年11月19日
■Q:ページのレイアウトが、崩れる?
■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 下記の電話・メールで、ご連絡下さい。 この連絡先は、メディア関係者様と、 企業・団体・法人様向けです。 一般個人の方には、対応いたしかねます。 ◆電 話:03-3462-7997 ◆メール:toiawase★s-souken.jp (★を、アットマークに、変えて下さい) ■リモートでも リモートでの出演・取材にも、対応しています  消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆であることを念頭に置いて下さい。 本ページ内容に関しては、自らの責任において対応して下さい。 また「免責事項」をお読みください ■引用 皆さまに、本ページの引用や、 リンク設定などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件 をご覧下さい。 |

- ■GDPのマスコミ報道は、
「誤報」ではないが、「誤解」 を招く? - 日本の最新の2023年7-9月のGDPの報道は、
「 誤報 」 ではないが、「 誤解 」 を招く?
新聞社等のマスコミ各社は、下記と報じた。
GDPは、2.1%のマイナス成長
だが、消費者 経済 総研は、下記と報じる。
GDPは、6.4%のプラス成長
・マスコミ報道は:
日本経済の回復に、急ブレーキ
最大の要因は、個人消費の落ち込み
・消費者 経済 総研 は:
7-9月GDPは、1995年以降で、最大の高成長へ
個人消費は、引き続き堅調
「マスコミ」と、「 消費者 経済 総研 」 の報じ方は、
まるで違う。
正反対だ。
マスコミ報道は、「 誤報 」 では、ない。
だが、「 誤解 」 を生む報道だ。
長年に渡り、「この報道の仕方」が、されている。
今回号は、「GDP の正しい見方」を解説する。
勘違いを排除し、正しい見方を、
消費者 経済 総研 が、徹底解説する。

- ■7~9月のGDPが、 11月15日発表
- -- 消費者 経済 総研 --
◆マスコミ報道では、年率 マイナス 2.1 %
日本の最新GDPの、2023年7~9月期分が、
11月16日(水)に、発表された。
GDP成長率は、年率▼2.1%のマイナスと、
マスコミが、報じた。
-2.1%は、「 年率換算・実質 」 の値である。
年率ではなく、「 前期比 」では、-0.5% だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆勘違いするな
★ここで、あなたに、問いかけ
年率マイナス2.1%だった。
「 やはり、日本経済は、落ちたのか?! 」
と、思ったか?
↓
それは、勘違いだ。 理由を解説していく。
-- 消費者 経済 総研 --
◆マスコミ報道では?
新聞社などのマスコミ各社の報道では、
下記の様に、報じられた。(抜粋)
▼各社に 共通する 表現は?
「 年率換算で 2.1% 減った 」
「 3四半期ぶりの マイナス成長 」
このくだりは、各社共通している。
▼原因に関する 各社の コメントは?
・輸出の伸びも、力強さを欠いた
・物価高を受けた個人消費の不振..
景気回復に急ブレーキ..
・国内需要の弱さが目立つ
・個人消費は振るわない
・日本経済の回復に急ブレーキ
最大の要因は個人消費の落ち込み
・物価高の影響で食料品の消費が減
上記の様に、マスコミ各社は、コメントした。
-- 消費者 経済 総研 --
◆消費者 経済 総研 の報じ方は?
消費者 経済 総研 が、報じる内容は、下記だ。
「 GDPは、+6.4 % の成長と、好調だ 」
「 7-9月では、比較可能な95年からの
28年間で、最大の増加率だ 」
「 なお、個人消費は、+2.8 % だった 」
▼マスコミと、消費者 経済 総研 の比較
マスコミ報道: GDPは、2.1%のマイナス
消費者経済総研: GDPは、6.4%のプラス
まるで、違う。
★ここで、あなたに、問いかけ
違う出典データを、用いれば、結果も違う。
では、マスコミと、消費者 経済 総研 では、
違う出典データを、使っているか?
あなたは、1分間、想像して頂きたい。
↓
マスコミも、当総研も、同じ出典を、使っている。
発表元は、内閣府 経済社会総合研究所で、共通だ。
★ここで、あなたに、問いかけ
GDP伸び率の値は、まるで違う。
同じ出典を、元にしたのに、
なぜ、こんなに、大きな差が、出たのか?
あなたは、1分間、考えて頂きたい。
↓
この理由を、解説していきたい。

- ■世間に、はびこる 変なGDPの見方
- GDPは、
余計な操作を、した後の値で、報道されてきた。
これらの余計な操作によって、どうなるか?
おかしな値に、化けるし、わかりにくくなる。
長年にわたり、世間では、GDPが
おかしな値で、伝わってしまっているのだ。
マスコミ各社も、その方法で伝えている。
そこで、消費者 経済 総研 は、
「 GDPの 正しい見方 」 を、解説する。
-- 消費者 経済 総研 --
◆ 「 余計な 4つの 操作 」 で、おかしくなる?
GDPは、余計な操作で、おかしな値にされている。
その余計な操作は、4つもある。
★その4操作とは何か?
あなたは、1分間、考えて頂きたい。
↓
それは、下記の4操作だ。
① 前期比 で見る
② 実質 に変える
③ 季節調整 をする
④ 年率換算 をする

- ■① 前期比で見る とは ?
- 一度、GDPの話から、企業の業績の話に移す。
大半の企業では、年度のはじめ頃に、
12か月間の年間計画を、作成する。
売上・費用・利益の計画は、その計画のメインだ。
★ここで、あなたに、問いかけ
企業の今年の売上の達成状況は、
何と、比較するか?
あなたは、1分間、考えて頂きたい。
↓
下記で、比較することが、多いだろう。
「 昨年の実績 」 と 「 今年の実績 」
▼例として 年間では?
昨年度の売上:100億円
↓
今年度の売上:106億円 ( 前年度比 +6% )
▼月別では?
昨年10月の売上:8億円
↓
今年10月の売上:8.5億円 ( 前年・同月比 +6% )
最新の10月の売上の伸び率を、見る時は、
前年の同月 ( 22年10月 ) と、比較する。
今年の前の月 ( 23年9月 ) との比較ではない。
12ヶ月前の 「 前年・同月比 」 で、比較する。
-- 消費者 経済 総研 --
◆店舗の業界では、どうか?
店舗や、商業施設・百貨店の業界では、
「 前月は、サクタイが凄く良かったよ 」などと言う。
「 昨対 (サクタイ) 」 は、前年・同月比のことだ。
店舗の業界は、当然に「昨対」を、採用している。
今月10月の売上を、1か月前の9月と比較しない。
★それは、なぜか?
↓
12月と1月での話が、がわかりやすいので、
それを解説する。
-- 消費者 経済 総研 --
◆12月は?
店舗業界の売上では、
12月が、1年のうちで、最大になることが、多い。
★ここで、あなたに、問いかけ
なぜ、12月の売上が、高いか?
あなたは、1分間、考えて頂きたい。
↓
12月は、お歳暮の商戦、Xmas商戦などで、
物販の売上が、大幅増加する。
また、忘年会、Xmasディナーなどで、
飲食店の売上が、大幅増加する。
また、11月と12月の「 日数の比較 」では、どうか?
営業日数は、11月は30日間で、12月は31日間だ。
営業日数だけでも、12月の方が、約3%も有利だ。
よって、12月を、前月(11月)と、比較すれば、
12月の方が、高いに決まっているのだ。
22年12月を、同年の11月と、比較 → ×
22年12月を、前年の12月と、比較 → 〇
12月の売上成績は、1年前の12月と比較する。
これが、本来すべき比較で、当然のことだ。
▼マイナスが、プラスに、化ける?
例として、
ある店舗が、下記の売上成績だったとする。
21年 12月:100万円
22年 11月: 80万円
22年 12月: 90万円
「 前年・同期比 」では、22年12月は、
マイナス10%だ。 ( 90万円 ÷ 100万円 )
一方で、「 前期比 」では、22年12月は、
プラス12.5% だ。 ( 90万円 ÷ 80万円 )
本来、比較すべき「前年・同期比」は、-10%だ。
だが、「前期比」にすることで、+12.5%になる。
正解の-10%が、+12.5% に、化けてしまう。
マイナスが、プラスに、化ける。
よって、「前期比」で、判断してはダメだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆株式市場での 企業の利益の 伸び率は?
前項は、売上進捗に関する、社内での見方だった。
では、「 社外への 公式の発表 」 では、どうか?
★ここで、あなたに、問いかけ
株式市場では、どうか?
上場企業の業績の伸び率は、
何と何で、比較するか?
あなたは、1分間、考えて頂きたい。
↓
もちろん、「 前期比 」 ではなく、「 前年・同期比 」 だ。
▼7-9月の増益率は、いつと、比較するか?
23年11月14日までに、
企業の7~9月期の決算報告が、続いた。
増益率、つまり、利益が、どれだけ増えたか?
これが、大きな関心事である。
上場企業の決算発表では、
去年の7~9月期と、今年の7~9月期で比較する。
「 前年・同期比 」 だ。 当たり前のことである。
A:今年の 4~6月期
B:今年の 7~9月期
AとBとでの比較は、しない。
つまり、「 前期比 」 では、比較しない。
正解は、
「 前期比ではなく、前年比で見る 」
-- 消費者 経済 総研 --
◆GDPの報道では?
★ここで、あなたに、問いかけ
マスコミが報じた GDP伸び率は、
何と、何で、比較したか?
あなたは、1分間、考えて頂きたい。
↓
「 前期比 」 だ。
前年・同期比 ではない。
「前期比」で報じるから、誤解を呼ぶ。
前期比の報道で、
誤報ではないが、大きな誤解を呼ぶ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆新NISA カブ活の初心者
まもなく、新NISAが、始まる。
カブ活デビュー する人も、増えるだろう。
カブ活 = 株式投資活動
今年、既にデビューした人も、多い模様だ。
カブ活デビューしたての初心者の方が、
下記の報道を、聞いたら、どう思うだろうか?
「 GDPがマイナスへ。 日本の景気にブレーキ 」
すると、下記の様に、考える初心者が、
いるかもしれない。
「 日本の景気が、悪くなったのか。 残念だ。
「 株を、買ったばかりだけど、売ってしまおう 」
「 前期比 」 での報道は、
誤報ではないが、誤解を生む。
-- 消費者 経済 総研 --
◆前期比・前年同期比の データ比較
+ 6.4% :消費者経済総研が、報じる 前年・同期比
- 2.1% :各マスコミが、報じた 前期比
GDP報道は、まるで違う姿になる。

- ■② 「 実質 」 に変える とは ?
- GDP 余計な4操作は、既述の通り、下記だ。
① 前期比 で見る
② 実質 に変える
③ 季節調整 をする
④ 年率換算 をする
◆ ② 実質 に変える とは?
続いて、②の 「 実質 に変える 」 を、解説する。
-- 消費者 経済 総研 --
◆消費者 経済 総研の見方は?
消費者経済総研が、伝えるGDPは、+6.4%だ。
この+6.4%は、名目GDPの伸び率だ。
だが、マスコミ各社は、
「 名目 」 ではなく、 「 実質 」 で、報道した。
-- 消費者 経済 総研 --
◆名目GDPと、実質GDPの 違い とは?
「 名目値 」 とは、
実際の取引での価格に基づき、算出された値だ。
「 実質値 」 とは、
物価の上昇・下落分を、取り除いた値だ。
▼名目は、実際の値 実質は、操作された値
名目GDPを、実質GDPに直すメリットは、小さい。
名目では、実際のお金の流れが土台だ。
肌感覚での経済規模は、
「 実質 」 よりも、「 名目 」 の方が、近いのだ。
「実質」よりも「名目」の方が、実態を把握
-- 消費者 経済 総研 --
◆上場企業では?
店舗系の上場企業は、販売成績を、毎月発表する。
★上場する店舗系の企業の、売上成績の発表は、
名目売上か? 実質売上か?
あなたは、1分間、考えて頂きたい。
↓
当然に、名目売上だ。
伸び率も、
「 当月の名目売上 」 ÷ 「 前年同月の名目売上 」 だ。
▼上場企業の決算発表は?
22年7~9月期の売上:300億円
↓
23年7~9月期の売上:306億円
この場合は、企業売上は、300→306億円と、
2%成長と、決算発表される。
つまり名目の値で、決算発表される。 当然のことだ。
なお、23年7-9月期のインフレ率は、3.2%だ。
もし、インフレ分を、除外して、実質にしたら?
↓
名目売上306億円は、実質売上297億円になる。
「 実質売上 」 で、発表したら、マイナスとなる。
そんな発表をする企業を、見た事がない。
「 実質売上297億円で、マイナス成長 」
のような決算発表は、されない。
人々は、第1に、名目の値で、判断する。
無理して、実質にすると、おかしくなる。
名目データを踏まえた上で、更なる深掘り分析を、
したい人が、実質値の評価を、試みればよい。
企業の 売上発表も、決算発表も、
実質ではなく、名目で発表

- ■③ 「 季節調整 」 をする とは?
- GDPの 余計な4操作は、既述の通り、下記だ。
① 前期比 で見る
② 実質 に変える
③ 季節調整 をする
④ 年率換算 をする
続いて、③の 「 季節調整 」 を、解説する。
-- 消費者 経済 総研 --
◆「季節調整」 を する理由 とは ?
GDPの発表では、
1-3月、4-6月、7-9月、10-12月 の 4つの期 がある。
GDPの値は、季節によって、水準が変わる。
10-12月が、大きな額になる。
GDPの過半を占めるのは、個人消費だ。
個人消費が、年末商戦で、増えるからだ。
「季節調整」で、この変動を排除し、調整している。
1-3月、4-6月、7-9月、10-12月の4つの期を、
季節調整で、同水準で比較しようとしている。
下記が、2022年の四半期ごとのGDPの値だ。
調整前 → 季節調整の後
1-3月: 550兆円 → 553兆円(増加)
4-6月: 551兆円 → 558兆円(増加)
7-9月: 540兆円 → 554兆円(増加)
10-12: 586兆円 → 561兆円(減少)
※この時点で、四半期→12ヶ月換算の操作も、されている
既述の通り、12月は、消費額が、多い。
GDPの額も、10〜12月期が、多い。
この季節差を、補正計算を、しているのだ。
10〜12月期は、減らす調整をし、
その他の期は、増やす調整をしている。
季節変動があるなら、わざわざ違う季節で
比較しなければよいのだ。
冬のGDPと、同じ年の秋のGDPを、
比較すると、冬のGDPの方が、高くなる。
それなら、今年の冬のGDPと、去年の冬のGDPで、
比較すれば、良いのだ。
▼正しい見方は、下記のABで、比較
A 今年の冬のGDP
B 去年の冬のGDP
▼おかしな見方は、下記のCDで、調整比較
C 今年の冬のGDP
D 今年の秋のGDP

- ■④ 「 年率換算 」 とは?
- 続いて、おかしな操作の、4つ目の 「 年率換算 」 だ。
年率換算では、
4半期(3か月)を、1年分(12か月)に、変換する。
3ヶ月分を、12ヶ月分では、4倍も違う。
なおGDPの年率換算では、4倍ではなく、4乗する。
-- 消費者 経済 総研 --
◆マスコミ報道は、前期比-0.5%、年率-2.1%
▼前期比 -0.5% とは?
マスコミ報道では、
7-9月は、 4-6月と比べて、「 0.5% 減 」 だった。
その計算は、下記の通りだ。
7-9月 : 555兆円 ÷ 4-6月 : 558兆円
= 99.46% ( 0.54 % 減 )
今回発表のGDPの7-9月期(3つの操作後)は、
マイナス0.54%だ。
▼年率 -2.1% とは?
マスコミ報道では、下記だった。
・前 期 比 :マイナス 0.5 %
・年率換算:マイナス 2.1 %
前項の前期比-0.54%は、99.46%でもある。
( 99.46% = 100% ― 0.54% )
それを、4乗すると?
99.46% × 99.46% × 99.46% × 99.46%
= 97.87%
4乗して、年率に換算したら、97.87%になった。
97.87%は、マイナス2.13%でもある。
( 97.87%= 100% ― 2.13% )
▼余計な 4乗 とは?
7~9月の3か月の伸び率を、わざわざ、4乗して、
年率(12か月分)に、直す意味は、ない。
4乗すると、
時期によっては、極端に大きな値へ、化けてしまう。
2020年は、その 「 大化け した 年 」 だった。
2020年GDPの異常な大化けは、本ページ下段参照。

- ■消費者 経済 総研 の報じ方は?
- 消費者 経済 総研 が、報じるGDPは、下記だ。
2022年 → 2023年
1-3月: 138兆円 → 143兆円( 4.0 % UP )
4-6月: 138兆円 → 145兆円( 5.2 % UP )
7-9月: 135兆円 → 144兆円( 6.4 % UP )
名目の前年・同期比である。
7-9月は、 6.4 % UPだ。
※計算:単位 10億円
7-9月 143,546 ÷ 4-6月 134,924 =106.4%
上記の4.0%UP・5.2%UPも、10億円単位計算で、
兆円未満の数字を含んだ値で、計算した%である。
こうして、2023年「7-9月期」のGDP成長率は、
名目・昨年同期比6.4%なのに、-2.1%へ化けた。
-- 消費者 経済 総研 --
◆まとめ
マスコミ各社は、下記と報じた。
GDPは、2.1%のマイナス成長
消費者 経済 総研は、下記と報じる。
GDPは、6.4%のプラス成長
マスコミ報道は:
日本経済の回復に、急ブレーキ
最大の要因は、個人消費の落ち込み
消費者 経済 総研 は:
7-9月GDPは、
1995年以降の28年間で、最大の高成長へ
個人消費は、引き続き堅調
日本の経済は、
数十年ぶりの高成長
各社のGDP報道と、
消費者 経済 総研のGDPは、まるで違う
-- 消費者 経済 総研 --
◆消費者 経済 総研 からの 提言
こうして、多くの人が、GDPを、誤解している。
日本の7-9月GDPは、比較可能な1995年からの
28年間で、最大の成長率だ。
失われた30年から、脱却できるチャンスなのだ。
2023年は、海外の投資家が、
「 生まれ変わる シン日本 」 に、投資を増やした。
そこで、23年の日本株は、稀に見る高騰になった。
▼日本経済を、世界へ、アピールしよう
日本のGDPは、高い成長率になった
↓
世界に、「名目GDP・前年比」を、アピールしよう。
↓
世界が気づけば、日本への投資が、一段と加速する。
↓
日本に、お金が、どんどん集まる
↓
あなたのお金も、私のお金も、増えるのだ
GDPを、「 名目・前年比 」 で、見るように、
日本政府は、世界へ向けて、アピールを、すべきだ。
◆追伸
繰り返しだが、
マスコミ報道のマイナス成長は、誤報ではない。
プラスなのに、マイナスに見える4操作方式は、
世界最大の経済大国の「 米国方式 」だからだ。
その米国方式に、日本は、準拠しているのだ。
だが、同じく経済大国の中国は、前年比方式だ。
「 前年比 方式 」 で、国際基準を、統一するように、
働きかけを、すれば良い。
6.4%もの 高成長の 日本を、
ぜひ、世界に 発信すべきだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆本ページの下段続編は?
下記の★については、
次項の2020・2021解説版を、ご覧頂きたい。
★ そもそも GDP とは?
★ GDPの 内訳 とは?
★ GDPの 長期推移 は?
★ 2020年のGDPが、4操作で、大化け とは?
★ 余計な4操作をやる理由とは?
★ GDPデフレーター とは?
次の「 目次 」 の中の ★ マークが、該当部分。
該当箇所へ、ジャンプ移動するには、
大見出し■の行を、クリック。

- ■目次|2021・2021解説版
- ※青色部のクリックで、その該当部分へ、移動
- ■GDP最新の21年4-6月が8月16日公表
- ◆1次速報は、年率1.3%、前期比0.3
◆名目GDPは?
◆世間にはびこる「変なGDPの見方」 - ■20年のコロナ・ショックの時は?
- ◆2020年4-6月期のGDPは?
◆2020年7-9月期のGDPは? - ■余計な操作で、おかしな値とは?
- ■そもそもGDPとは何か?
- ★注目の指標GDPとは?
★GDPの内訳とは?
★内閣府が公表する「内訳の詳細」は?
★GDPの長期推移とは? - ■世間の見方が、おかしいとは?
- ◆余計な4つの操作 とは?
◆余計な4操作で公表する理由は、何か?
- ■消費者経済総研の正しい見方とは?
- ◆「名目GDP」の実額は?
◆2020年の名目の成長率(昨年同期比)は? - ■世間と、消費者経済総研の違いは?
- ◆実額は?
★20年GDP成長率は、4操作で大化け?
◆どちらが、よいか? - ■GDP計算式と、余計な操作とは?
- ◆「季節調整」をする理由とは?
◆年率換算 とは?
◆「年率換算の謎」の答え とは?
◆「前年比ではなく、前期比で見る」 - ■余計な操作をする理由は?
- ★余計な4操作後の値で公表する理由は、何か?
◆年率換算は、昭和では?
◆名目GDPと、実質GDPの違いとは?
◆昭和は「実質」が、成長を把握しやすかった
◆近年は、名目の方が、実感に近い
◆海外では? - ■GDPデフレーター とは?
- ◆「消費者物価指数」「企業物価指数」とは?
★デフレータ、CPI、CGPIの関係は?
★GDPデフレータが、事後的な指数 とは?
- ■まとめ
- ■関連ページは?

- ■GDP最新の21年4-6月が8月16日公表
- ■ GDP21年4-6月が8月16日公表
- ◆1次速報は、年率1.3%、前期比0.3%
日本の最新GDPの、2021年4~6月期分が、
8月16日(月) AM 8:50に、公表された。
年率のGDP成長率は、1.3%のプラスとなった。
これは「年率」の値である。
年率換算の前の4-6月期の前期比は、0.3%だ。
0.3%は「前年比」ではなく「前期比」である。
さらに「季節調整」をした後の値だ。
また、物価変動の影響を除いた「実質」の値である。
◆名目GDPは?
名目GDPは、物価影響を除く前の「素の値」である。
名目の方が、実体・実感に近いのだ。
「名目」GDP公表値は、前期比0.1%、年率0.2%だ。
4-6月期の3ヶ月分が、0.1%で、
年率(12か月分)では、0.2%なのは、なぜか?
ところで名目の実額は、いくらか? (単位:十億円)
2020年4-6月期:126,581
2021年4-6月期:135,107
素の値である名目GDPの実額は、昨年比+6.7%だ。
(135,107 ÷ 126,581 = 1.067)
名目GDPの昨年比の成長率は、プラス6.7%なのに、
公表値が、0.1%や0.2%の値なのは、なぜか?
また、実質の公表値が0.3%や1.3%なのは、なぜか?
◆世間にはびこる「変なGDPの見方」
GDPは、名目を実質にする加工のほか、
様々な操作で、おかしな値で発表されてきた。
長年にわたり、世間では、GDPが
おかしな値で伝わってしまっているのだ。
本稿では、GDPの正しい見方を解説する。

- ■ 20年のコロナ・ショックの時は?
- 2020年4月7日に、最初の緊急事態宣言が出た。
4-6月は、激しく経済活動が、低下した時期だ。
GDP 4-6月期は、-29% 成長 と発表された。
その次の期はどうなったか?
GDP 7-9月期は、+21% 成長 と発表された。
このようにGDP成長率は、激変の値が伝わった。
はたして2割、3割も激変したのか?
コロナ・ショックで変動が大きかった昨年の
4-6月期と、7-9月期に注目していく。
-- 消費者 経済 総研 --
◆20年4-6月期のGDPは?
2020年「4-6月期」の実質GDP成長率は、
前期比・年率マイナス28.6%だった。
「約3割も、日本経済は、落ちたのか?!」
と、思われたかもしれない。
→それは、勘違いだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆20年7-9月期のGDPは?
続いて7~9月期はどうだったか?
「7-9月期」の実質GDP成長率は、
前期比・年率プラス22.9%だった。
「約23%もプラス?!
早くも、経済が大幅に、回復した?」
と思われたかもしれない。
→それも、勘違いだ。

- ■ 余計な操作で、おかしな値とは?
- GDPは下記4操作で、おかしな値にされている。
① 年率換算で、3か月分を、12か月分にする
② 前年比ではなく、前期比で見る
③ 季節調整をする
④ 名目を実質に変える
これらの余計な操作によって、どうなるか?
おかしな値に化けるし、わかりにくくなる。
発表主体の政府(内閣府)も、伝える各総研も、
その方法で伝えている。
そこで、消費者経済総研は、
GDPを正しく把握する方法を、解説する。

- ■ そもそもGDPとは何か?
- ◆注目の指標のGDPとは?
大手の機関投資家の金融トレーダー達に
「重要な経済の指標とは?」とアンケートしてみた。
日銀短観やGDPが、1位か2位になることが多い。
※「日銀短観」とは、下記過去号を参照
日銀短観とは|最新はいつ公表?DIの見方や意味は?
私(松田)は、慶応大・経済学部で経済を研究した。
GDPは、経済学では、早い段階で登場する。
経済の重要な指標だ。
GDPを経済学的に説明すると、わかりにくくなる。
ここでは、簡単にわかりやすく説明していく。
日本のGDPとは、
一言で言うと「日本の経済活動の規模」だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆GDPの内訳とは?
「GDP」とは、単純化すると、
下記の4つの金額を、足し算した合計の金額だ。
[1] 「個人消費等」
+
[2] 「政府の支出等」
+
[3] 「企業の設備投資」
+
[4] 「貿易」
この内訳の割合は、下記の通りだ。
GDP(100%)=
[1] 57%:個人消費等
+
[2] 27%:政府の支出等
+
[3] 16%:企業の設備投資
+
[4] 0%:貿易
※パーセントの値は2020年暦年名目GDP
2021年8月10日時点での値、小数点以下は四捨五入
日本ではGDPの約6割が「消費」等である。
なお米国では、その値は約7割である。
「消費」は経済の主人公である。
*貿易が0%とは?
「貿易・純輸出」=「輸出」-「輸入」
「貿易」とは、
「輸出」から「輸入」を差し引いた「純輸出」だ。
*輸出・輸入の推移は?
輸出と輸入は、近年は同水準で推移している。
よって「純輸出」は、近年は小さい額になっている。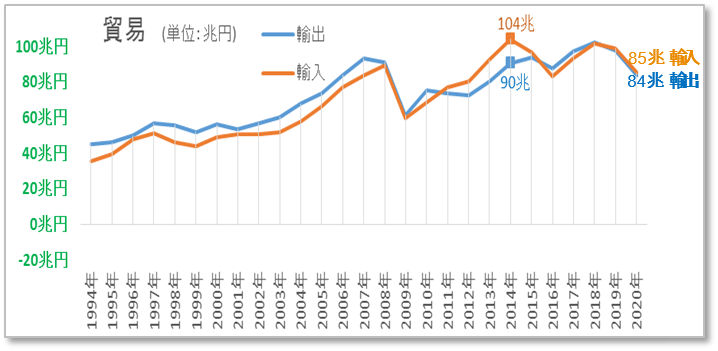
*純輸出(輸出-輸入)は?
「純輸出の額」「純輸出の率」を下図で加えた。
※「純輸出の率」=「純輸出の額」÷「GDPの額」
「純輸出の率」は、1%未満で、存在感がない。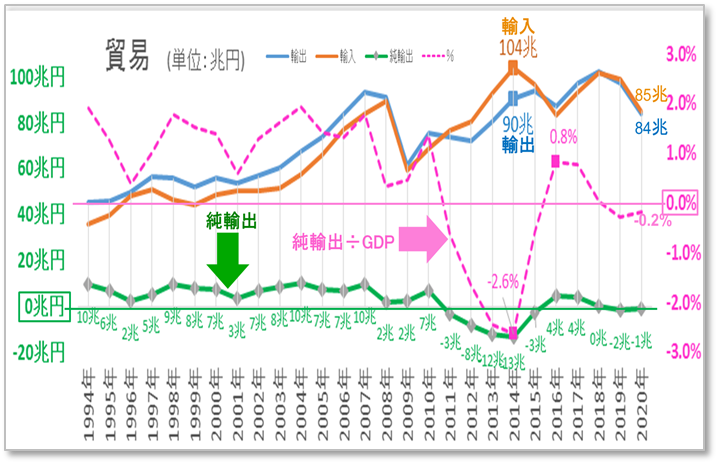
経済活動が活発なら、輸出も輸入も多くなる。
しかし輸出と輸入が多くても、同じ値ならどうか?
輸出-輸入=0なら、GDP計算式では純輸出は0だ。
「GDP成長率の値は良いが、実は経済は悪い」
ということが起こることがある。
この点は、GDPの求め方の統計上の欠点でもある。
このGDP統計の欠点の解説は下記過去号参照
3分でわかる|中身は悪い?GDP|2019年1~3月期
-- 消費者 経済 総研 --
◆内閣府が公表する「内訳の詳細」は?
[1] 個人消費等
[2] 政府の支出等
[3] 企業の設備投資
[4] 貿易
前項では、上の4項目に、単純化した。
内閣府発表の構成要素では、下記8項目となる。
① 53.5%:民間最終消費支出
② 3.7%:民間住宅
③ 21.1%:政府最終消費支出
④ 5.6%:公的固定資本形成
⑤ 0.0%:公的在庫変動
⑥ 16.0%:民間企業設備
⑦ 0.2%:民間在庫変動
⑧ -0.2%:財貨・サービス純輸出
*8項目→4項目の集約の対比は、下記の通りだ。
[1] 個人消費等 = ①+②
[2] 政府の支出等 = ③+④+⑤
[3] 企業の設備投資= ⑥+⑦
[4] 貿 易 = ⑧
※パーセントの値は2020年・暦年名目GDP
(2021年8月10日時点での値)
なお、内閣府が発表するGDPの値は、
1次速報、2次速報・・・と更新が続くことに注意。
2021年8月10日時点の最新の値は、
内閣府名目暦年を参照
-- 消費者 経済 総研 --
◆GDPの長期推移とは?
※単位は兆円|名目GDP|暦年ベース
※出典:内閣府 名目 暦年(2021年8月10日時点)

- ■世間の見方が、おかしいとは?
- ◆余計な4つの操作 とは?
① 実際の額の「名目」ではなく、物価影響除く「実質」
② 季節によって変える「季節調整」
③「前年同期比」ではなく「前期比」
④ 3ヵ月分を12か月分にする「年率換算」
「実質」「季節調整」「前期比」「年率換算」
この4つの余計な操作で、おかしくなる。
-- 消費者 経済 総研 --
◆余計な4操作後の値で公表する理由は、何か?
「今まで、そうしてきた」からで、
また「皆が、4操作のまま扱う」からだ。
日本の同調傾向である。
昭和時代の傾向とあわせて、この詳細は後述する。

- ■消費者経済総研の正しい見方とは?
- ◆「名目GDP」の実額は?
下記は、操作をする前の「名目GDPの原データ」。
青が2019年、赤は2020年。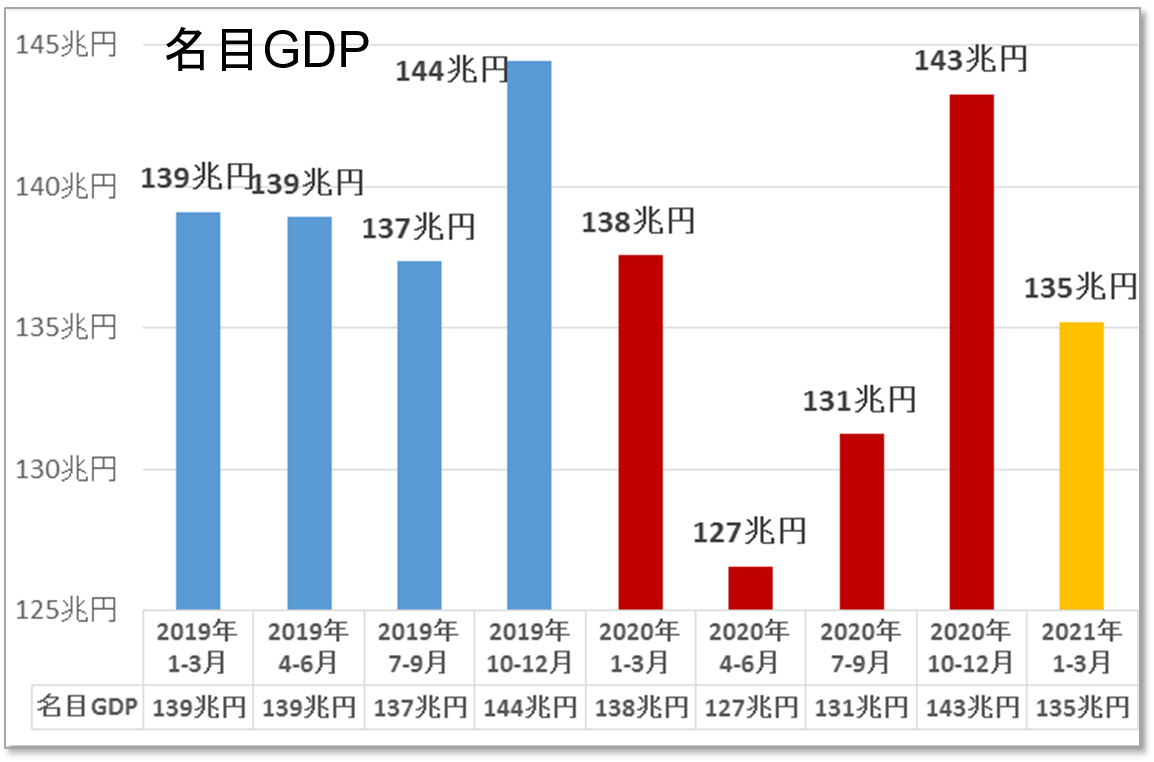
-- 消費者 経済 総研 --
◆2020年の名目の成長率(昨年同期比)は?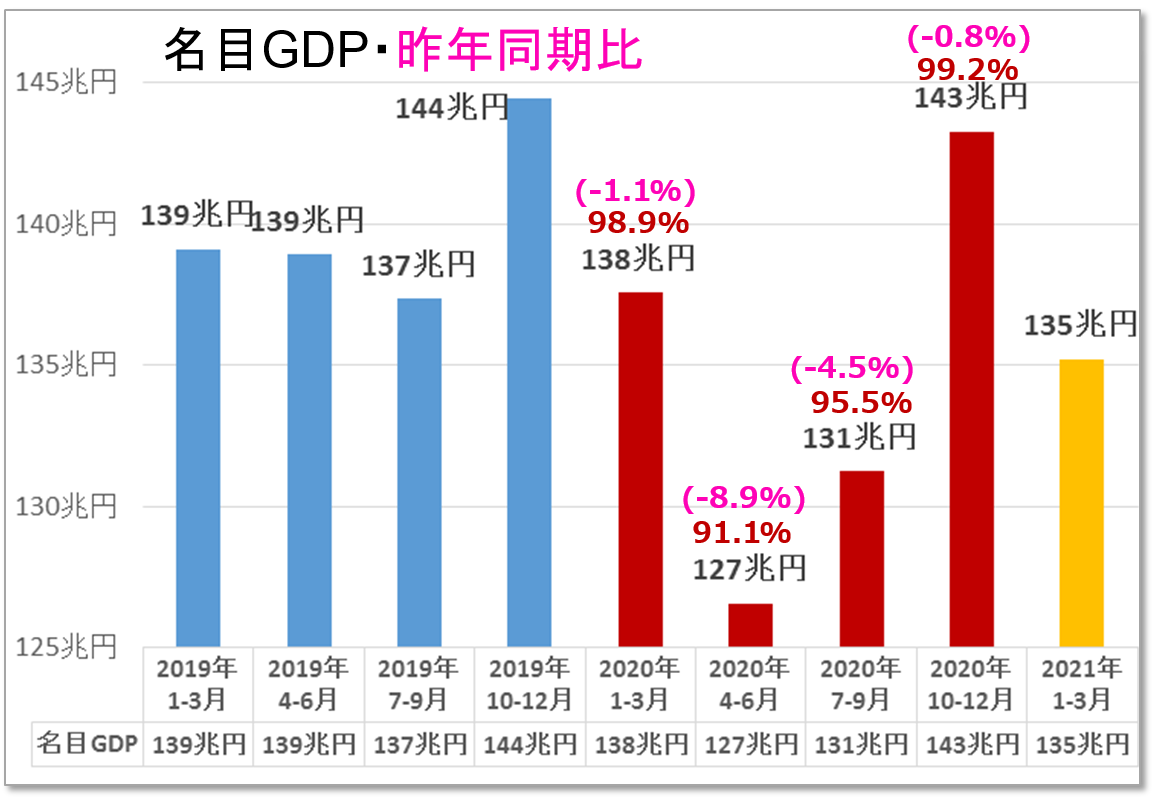
*1-3月は、-1.1%
*4-6月は、-8.9%
*7-9月は、-4.5%
*10-12月は、-0.8%
※出典:内閣府国内総生産四半期名目原系列

- ■世間と、消費者経済総研の違いは?
- 引き続き、2020年の4-6月期、7-9月期に注目する。
◆実額は?
まずは、GDPの実額(名目)を見ていく
*4-6月:139兆円(2019年) → 127兆円(2020年)
→ 8.9%の減少
*7-9月:137兆円(2019年) → 131兆円(2020年)
→ 4.5%の減少
-- 消費者 経済 総研 --
★20年GDP成長率 4操作で、大化?
左が公表と報道 → 右が消費者経済総研
4-6月期 : -28.6% → -8.9%
7-9月期 : +22.9% → -4.5%
※左:実質・季節調整後・前期比・年率換算後
※右:名目・前年同期比
-- 消費者 経済 総研 --
◆どちらが、よいか?
一般のGDP報道より、消費者経済総研の方が、
経済の実態が、把握できるのだ。

- ■GDP計算式と、余計な操作とは?
- 「操作」という言葉を使ったが、
小細工しているわけではなく、計算過程の調整だ。
余計な操作とは、下記4つである
①「名目」ではなく「実質」
② 「季節調整」
③「前年同期比」ではなく「前期比」
④ 3か月分を12か月分にする「年率換算」
「実質」「季節調整」「前期比」「年率換算」
「実質」の操作は、後述とし、
まずは「季節調整」から解説する。
-- 消費者 経済 総研 --
◆「季節調整」をする理由とは?
1-3月、4-6月、7-9月、10-12月の4つの期がある。
GDPは、10-12月が、大きな額になる。
GDPの過半を占めるのは、個人消費だ。
個人消費が、年末商戦で増えるからだ。
「季節調整」で、この変動を排除し調整している。
1-3月、4-6月、7-9月、10-12月の4つの期は、
季節調整で、同水準で比較しようとしている。
下記が、2020年の季節調整後の値だ。
1-3月期: 544兆円
4-6月期: 500兆円( 91.9%| -8.1%)
7-9月期: 527兆円(105.3%| +5.3%)
※カッコ内は、前期比
-- 消費者 経済 総研 --
◆年率換算 とは?
4半期(3か月)を、1年分(12か月)に、変換している。
「4-6月期122.291兆円」÷「1-3月期137.294兆円」
=89.1%(10.9%減)
2020年4-6月期の実質GDPは、前期比-10.9%だ。
年率換算後の最終的な公表値では、-28.6%だ。
4~6月の3か月を、わざわざ、4倍して、
年率(12か月分)に直す意味は、ない。
確認のため、3か月分の-10.9%を4倍にしてみる。
すると、-10.9% × 4 = -43.6%だ。
しかし、発表された値は、28.6%だ。
43.6%と28.6%では、大きなズレがある。
これは、なぜか?
-- 消費者 経済 総研 --
◆「年率換算の謎」の答え とは?
*4倍ではなく、4乗 とは?
年率換算は、
季節調整後の値を用いて、次式で算出される。
年率成長率= (当期の値÷前期の値)の4乗-1
「GDPを、年率換算で、4倍にしている」
とよく世間では言われている。
正確には、「4倍」ではなく「4乗」である。
前期比「1割」の成長の場合で、
4倍のときは、1 + 0.1×4 = 1.4
4乗のときは、1.1 ^ 4 = 1.4641
このように、4倍と4乗は、値が違う。
*年率換算の計算をしてみると?
年率成長率= (当期の値÷前期の値)の4乗-1
この式に、GDPの値を入れてみる。
500.232兆円(当期:4-6月期)
÷ 544.231兆円(前期:1-3月期)
= 0.919154029
0.919154029の4乗は、-0.286238399
→ 28.6%
こうして、2020年「4-6月期」の成長率は、
名目・昨年同期比では-8.9%なのが、
-28.6%へと、大きく化けたのだ。
続く「7-9月期」は、どうか?
名目昨年同期比-4.5%が、
+22.9%に、化けたのだ。
7-9月期では、-マイナス成長が、プラス成長へ
化けてしまっている。
マイナスがプラスに化ける理由は、次で解説。
-- 消費者 経済 総研 --
◆「前年比ではなく、前期比で見る」
季節変動があるなら、わざわざ違う季節で
比較しなければよいのだ。
店舗や商業施設の業界の売上指標では、どうか?
当然に「昨対(サクタイ)」を採用している。
昨対とは、昨年同月比や、昨年同期比の事だ。
12月は、1年のうち最大売上になることが、多い。
なので12月を前月(11月)と比較すれば、
12月は、上がるに決まっているのだ。
12月の売上成績は、1年前の12月と比較する。
これが、本来すべき比較で、当然のことだ。
*計算例で見ると?
ある店舗が次の売上成績だったとする。
通常は年末商戦で12月は売上が高い。
2019年12月:100万円
2020年11月: 80万円
2020年12月: 90万円
前年同期比では、2020年12月はマイナス10%だ。
(90万円÷100万円)
前期比では、2020年12月はプラス12.5%だ。
(90万円÷80万円)
本来比較すべき前年同期比は、-10%が、
前期比にすることで、+12.5%になってしまう。
マイナスをプラスに化けさせる。
こんな計算式のGDPが、世の中に公表されるのだ。
さらに、各総研がその内容で、伝えているのだ。

- ■余計な操作をする理由は?
- ◆余計な操作後の値で公表する理由は、何か?
「今まで、そうしてきた」からで、
また「皆が、4操作のまま扱う」からだ。
日本の同調傾向である。
-- 消費者 経済 総研 --
◆年率換算は、昭和では?
余計な年率換算は、下記の様な成長拡大が続く
昭和の高度成長の時代の名残りだろう。
「当期3か月間の成長率は、
翌期も翌々期も、翌々々期も同率で拡大を続け
マイナスにならないし、減速すらもない」
しかし令和の時代、こういう時代ではない。
前記→当期が「+」でも、当期→翌期が「-」に
なるのは、頻出している。
2021年1-3月期までの2年間(全8期)では、
半分の4期が、前期比マイナス成長である。
高度成長の昭和と、令和時代は、全く違う
またインフレ率は、
昭和は高かったが、令和はそうではない。
この件は、次項で解説していく。
-- 消費者 経済 総研 --
◆名目GDPと、実質GDPの違いとは?
「名目値」とは、
実際に市場で取引されている価格に基づいて
推計された値だ。
「実質値」とは、
物価の上昇・下落分を、取り除いた値だ。
名目値から、インフレ率を割り引いたのが実質値。
-- 消費者 経済 総研 --
◆昭和は「実質」が、成長を把握しやすかった
日本も高度成長時代は、インフレ率が高かった。
1974年では、総合卸売物価は、31%も上昇した。
消費者物価指数は、23%も上昇した。
昭和の高成長や高インフレの時代では、
GDPは、実質の方が、実態をとらえやすかった。
例えば、仮に、実質GDPの水準が、
昨年も100で、今年も100で、横ばいだとする。
GDPは、横ばいで成長していない。
しかし物価が2割上昇し
「名目GDPが120」になったとする。
この場合は、20の物価上昇を除くことで、
経済成長して無いという実態を、把握できる。
昔は、インフレの度合いが、大きかった。
名目値は、実態より大きく乖離する事が多かった。
つまり昭和の時代のGDP成長率は、
インフレを除いた実質で把握するのが良かった。
-- 消費者 経済 総研 --
◆近年は、名目の方が、実感に近い
一方、近年は、昭和ほどのインフレ水準にない。
よって、名目を実質に直すメリットは、小さい。
名目では、実際のお金の流れが土台だ。
つまり企業の入出金の実際の額や、
個人消費の実際の額がベースだ。
肌感覚での経済規模は、
「実質」よりも「名目」の方が、近いのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆海外では?
ところで、海外のGDPは、どうか?
中国は、前年同期比で公表・報道されている。
日本も前期比ではなく、前年同期比で見るべきだ。
-GDPは、前年同期比・名目ベースで見るべき-

- ■GDPデフレーター とは?
- GDPでは、インフレ率に相当するのが、
「デフレータ」と呼ばれる指数だ。
「実質GDP」 = 「名目GDP」 ÷ 「デフレーター」。
近年のデフレータの値は、下記の通りだ。
2018年:100.3%
2019年:101.0%
2020年:101.9%
なお「GDPデフレータ」と「CPI」は、違う。
-- 消費者 経済 総研 --
◆「消費者物価指数」「企業物価指数」とは?
*「CPI(消費者物価指数)」は、
Consumer Price Indexの略。
消費者が購入する商品・サービス価格の変動指標
*「CGPI(企業物価指数)」は、
Corporate Goods Price Indexの略。
企業間で取引される商品が対象の物価指数だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆デフレータ、CPI、CGPIの関係は?
CPIは、消費者物価指数は、家計消費が対象で、
CGPIは、企業物価指数は、企業間取引が対象だった。
GDPデフレーターは、
家計消費の動向、企業設備投資の動向も踏まえた
総合的な物価指標だ。
GDPデフレータは、CPI、CGPI等を単純には包括
してないが、概念的には包括すると理解してよい。
-- 消費者 経済 総研 --
◆GDPデフレータが、事後的な指数 とは?
先に、GDPデフレータがあって、
「名目GDP÷デフレーター」によって
「実質GDP」を算出するのではない。
デフレーターは、後で指数化されるのだ。
GDPデフレータは、
事後的計算によって、得られた指数だ。
ちなみに、事後的に算出することを、
「インプリシット方式」と言う。
※参考出典:
「日銀|金融政策の説明に使われている物価指数」
GDPデフレータは、
国内の経済活動全体の名目付加価値と、
実質付加価値の関係を表示する用途で作成されている。
これは価格を直接調査するものではなく、
加工によって得られる指数である。
具体的な作成方法をみると、
まず、品目毎の名目生産額を積み上げて、
名目国内総生産額を算出する。
次に、品目毎の名目生産額を、
対応する物価指数や関連の価格情報で、
割ることによって、品目毎の実質生産額を算出し、
これを足し上げていくことで、実質国内総生産を算出する。
最後に、集計された名目国内総生産を、実質国内総生産で
割ることによってGDPデフレータを算出する。

- ■ まとめ
- 左が公表と報道 → 右が消費者経済総研の方式
2020年 4-6月期 : -28.6% → -8.9%
2020年 7-9月期 : +22.9% → -4.5%
「実質」「季節調整」「前期比」「年率換算」
この4つの余計な操作で、おかしな数字になる。
よって、消費者経済総研の方式の
「名目」「昨年同期比」で見るのが良いのだ。

- ■続編や関連ページは?
- ◆続編は、下記ページをクリック
*GDP拡大でも「実感なき景気回復」の理由とは
「実感なき景気回復とは?|わかりやすく3分解説」
◆関連テーマは、下記ページをクリック
*「日銀短観」とは
「日銀短観とは|最新はいつ公表?DIの見方や意味は?」
*GDP統計の欠点とは
「3分でわかる|中身は悪い?GDP|2019年1~3月期」

| ■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので、 「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆である事を念頭に置いて下さい。 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、 対応して下さい。また「免責事項 」をお読みください。 ■引用 真っ暗なトンネルの中から出ようとするとき、 出口が見えないと大変不安です。 しかし「出口は1km先」などの情報があれば、 真っ暗なトンネルの中でも、希望の気持ちを持てます。 また、コロナ禍では、マイナスの情報が飛び交い、 過度に悲観してしまう人もいます。 不安で苦しんでいる人に、出口(アフターコロナ)という プラス情報も発信することで、 人々の笑顔に貢献したく思います。 つきましては、皆さまに、本ページの引用や、 URLの紹介などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件をご覧下さい。 |
- 【著作者 プロフィール】
- ■松田 優幸 経歴
(消費者経済|チーフ・コンサルタント)
◆1986年 私立 武蔵高校 卒業
◆1991年 慶応大学 経済学部 卒業
*経済学部4年間で、下記を専攻
・マクロ経済学(GDP、失業率、物価、投資、貿易等)
・ミクロ経済学(家計、消費者、企業、生産者、市場)
・労働経済
*経済学科 高山研究室の2年間 にて、
・貿易経済学・環境経済学を研究
◆慶応大学を卒業後、東急不動産(株)、
東急(株)、(株)リテール エステートで勤務
*1991年、東急不動産に新卒入社し、
途中、親会社の東急(株)に、逆出向※
※親会社とは、広義・慣用句での親会社
*2005年、消費・商業・経済のコンサルティング
会社のリテールエステートに移籍
*東急グループでは、
消費経済の最前線である店舗・商業施設等を担当。
各種施設の企画開発・運営、店舗指導、接客等で、
消費の現場の最前線に立つ
*リテールエステートでは、
全国の消費経済の現場を調査・分析。
その数は、受託調査+自主調査で多岐にわたる。
商業コンサルとして、店舗企業・約5000社を、
リサーチ・分析したデータベースも構築
◆25年間の間「個人投資家」としても、活動中
株式の投資家として、
マクロ経済(金利、GDP、物価、貿易、為替)の分析や
ミクロ経済(企業動向、決算、市場)の分析にも、
注力している。
◆近年は、
消費・経済・商業・店舗・ヒットトレンド等で、
番組出演、執筆・寄稿、セミナー・講演で活動
◆現 在は、
消費者経済総研 チーフ・コンサルタント
兼、(株)リテール エステート リテール事業部長
◆資格は、
ファイナンシャル・プランナーほか
■当総研について
◆研究所概要
*名 称 : 消費者経済総研
*所在地 : 東京都新宿区新宿6-29-20
*代表者 : 松田優子
*U R L : https://retail-e.com/souken.html
*事業内容: 消費・商業・経済の、
調査・分析・予測のシンクタンク
◆会社概要
「消費者経済総研」は、
株式会社リテールエステート内の研究部署です。
従来の「(株)リテールエステート リテール事業部
消費者経済研究室」を分離・改称し設立
*会社名:株式会社リテールエステート
*所在地:東京都新宿区新宿6-29-20
*代表者:松田優子
*設立 :2000 年(平成12年)
*事業内容:商業・消費・経済のコンサルティング
■松田優幸が登壇のセミナーの様子
- ご案内・ご注意事項
- *消費者経済総研のサイト内の
情報の無断転載は禁止です。
*NET上へ「引用掲載」する場合は、
①出典明記
②当総研サイトの「該当ページに、リンク」を貼る。
上記の①②の2つを同時に満たす場合は、
事前許可も事後連絡も不要で、引用できます。
①②を同時に満たせば、引用する
文字数・情報量の制限は、特にありません。
(もっと言いますと、
①②を同時に満したうえで、拡散は歓迎です)
*テレビ局等のメディアの方は、
取材対応での情報提供となりますので、
ご連絡下さい。
*本サイト内の情報は、正確性、完全性、有効性等は、保証されません。本サイトの情報に基づき損害が生じても、当方は一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。
- 取材等のご依頼 ご連絡お待ちしています
- メール: toiawase★s-souken.jp
(★をアットマークに変えて下さい)
電 話: 03-3462-7997
(離席中が続く場合は、メール活用願います)
- チーフ・コンサルタント 松田優幸
- 松田優幸の経歴のページは「概要・経歴」をご覧下さい。