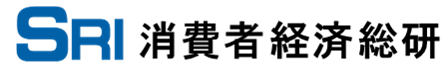【2023最新予測 日本 物価上昇率】推移,原因,計算方法もグラフでわかりやすく|消費者経済総研|2023年7月9日
■Q:ページのレイアウトが、崩れる?
■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 下記の電話・メールで、ご連絡下さい。 この連絡先は、メディア関係者様と、 企業・団体・法人様向けです。 一般個人の方には、対応いたしかねます。 ◆電 話:03-3462-7997 ◆メール:toiawase★s-souken.jp (★を、アットマークに、変えて下さい) ■TV リモート出演|筆者(松田)の物価予測 リモートでの出演・取材にも、対応しています 「消費者 経済 総研」の 筆者(松田)が、解説・提言 「フジテレビ・めざまし8」に、 「消費者 経済 総研」の 筆者(松田)が生放送に出演。 インフレ率(消費者物価指数)の見通しや、 日銀総裁の値上げ許容発現などを、解説。 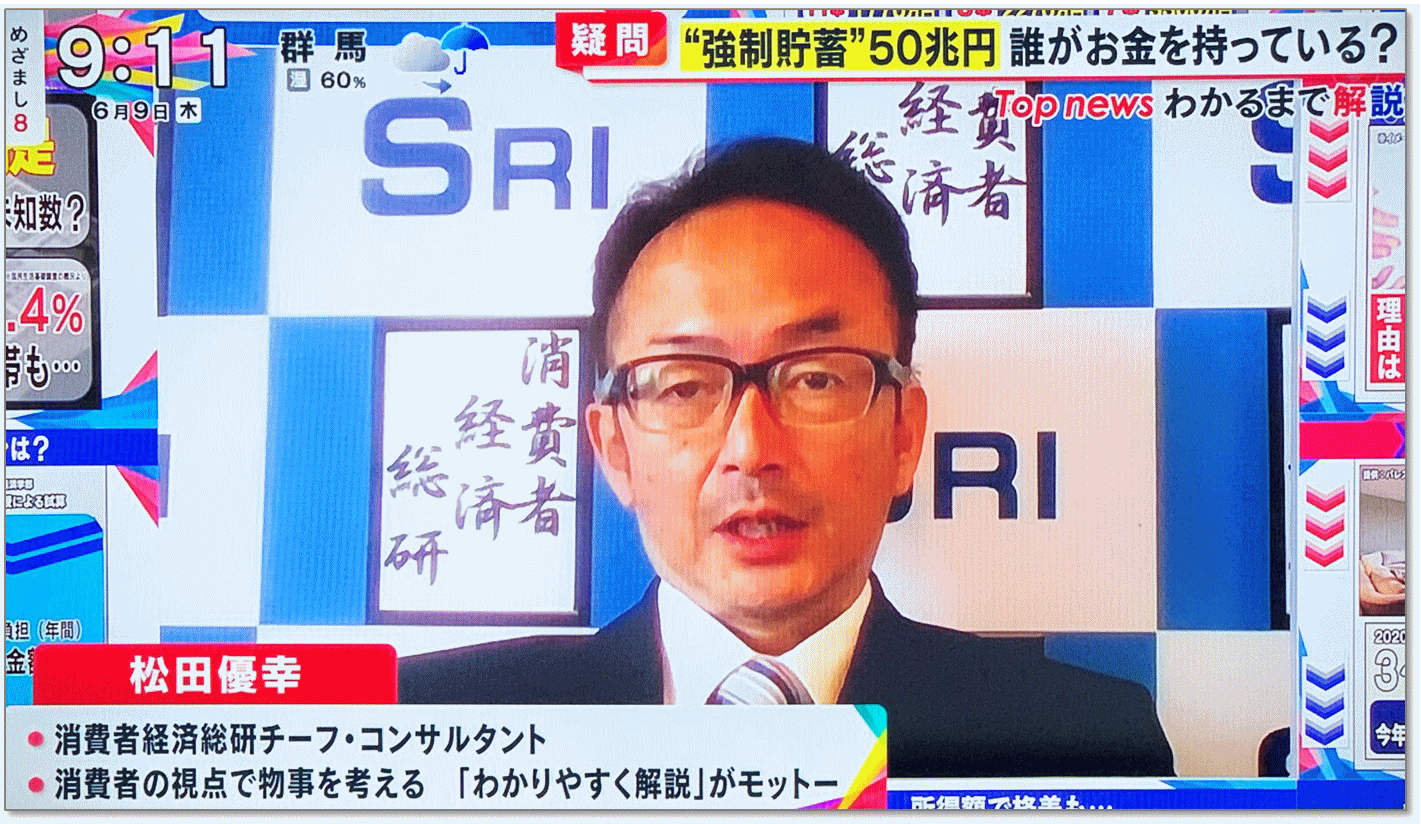 ※画像3枚出典:フジテレビ(2022年6月9日放送) ※画像3枚出典:フジテレビ(2022年6月9日放送)■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆であることを念頭に置いて下さい。 本ページ内容に関しては、自らの責任において対応して下さい。 また「免責事項」をお読みください ■引用 皆さまに、本ページの引用や、 リンク設定などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件 をご覧下さい。 |
- ■用語の定義は?
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:インフレ率と、物価上昇率の違いは?
↓
A:両者は、同じだと捉えてよい
-- 消費者 経済 総研 --
Q:インフレ率は、どの指標で、見るのか?
↓
A:消費者物価指数だ。 「 CPI 」とも言う※
※Consumer Price Indexの略
その他、「企業物価指数」がある。
企業間の取り引きでの物価指数だ。
企業の仕入れ価格などに、影響する
-- 消費者 経済 総研 --
Q:総合CPI、 コアCPI とは、何か?
↓
A:「 コアCPI 」 とは、「 総合CPI 」 から、
「 生鮮食品 」 の価格変動を、除いた CPI だ。
生鮮品は、天候によって、価格変動が激しい。
そこで、 「コアCPI 」 が、登場することも多い。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:本ページは、どの CPI か?
↓
A:「 総合CPI 」を、扱う。
消費者は、生鮮食品も購入する。
よって、生鮮品を除外するのは、意味がない
-- 消費者 経済 総研 --
Q:どんな時に、「コアCPI 」 を、使えばよいか?
↓
A:例えば、台風が来て、畑に被害が出た時等だ。
キャベツ、レタス、玉ネギ等の野菜が高騰した
場合は「 生鮮を除く コアCPI 」を見ればよい。
-- 消費者 経済 総研 --

- ■直近の実績と予測は?
- Q:インフレ率の 直近実績(5月) は?
↓
A:2023年5月の、昨年同月比の、
総合CPIは3.2%UP、コアCPIも3.2%UPだ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:インフレ率の 年間実績 (2022年度) は?
↓
A:2022年度の、年間平均は、
総合CPIは3.2%UP、コアCPIで3.0%UPだ
今後は、本ページでは、
特記ない限り、CPIは、「 総合 」 で表す。
-- 消費者 経済 総研 --

- ■2023 年度の 物価上昇率は?
- Q:2023年度は、物価上昇率は、どうなるか?
↓
日本の総合CPIの上昇率は、下記だと予測した。
・電気ガス代の支援が、継続の場合:2.7 %
・電気ガス代の支援が、終了の場合:3.1 %
22年度実績は、3.2%だったが、
支援終了なら、昨年度並みの、物価上昇となる。
「 電気ガス代支援 」 とは何か? に関しては、
本ページにて、後ほど、解説する。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:年度ではなく、 「 暦年 」 ではどうか?
↓
年度(2023年4月~翌年3月)は、上記の予測だが、
暦年(2023年1月~同年12月)では、下記の予測だ。
・電気ガス代の支援が、継続の場合: 3.0 %
・電気ガス代の支援が、終了の場合: 3.2%
なお、22年の暦年では、2.5%だった。
暦年では、22年よりも、
23年の方が、高い物価上昇となる。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:インフレのピークは、いつか?
↓
2023年1月の4.3%で、ピークアウトした。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:今まで、物価が上がった原因 は?
↓
天候不良、コロナ禍、原油高(戦争)、円安だ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:上記の影響は、残っているか?
↓
天候不良と、コロナ禍の影響は、ほぼ消えた。
原油高と、円安は、タイムラグを持って影響した。
物価上昇を、説明する要因として、
最近は、新たに、〇〇の影響が、大きい。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:その 「 新たな 〇〇 」 とは、何か?
↓
本ページで、わかりやすく解説していく
-- 消費者 経済 総研 --
Q:円安は、22年に、ピークアウトした。
だが、23年1月まで、物価上昇した理由は?
↓
輸入品が、最終商品として、消費者に届くまでに、
タイムラグがあるからだ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:原油価格は、もっと前にピークアウトした。
なのに、CPIが上昇したのは、なぜか?
↓
原油価格も、数か月遅れて、CPIに波及する
-- 消費者 経済 総研 --
Q:原油高も円安も、遅れてCPIへ影響か?
↓
そうだ。 原油高は、9ヶ月のタイムラグ、
円安は、3か月のタイムラグが見られた。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「消費者 経済 総研」の予測の計算根拠は?
↓
消費者 経済 総研による、日本のCPI上昇率の
予測の計算式と根拠を、下段に、後述してある

- ■CPI 海外は?
- 「Q&A」 でも、解説していく。
「Q」 の問いかけに対して、
あなたは、「答えA」 を、考えて頂きたい。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:海外のCPIは、どうなっているか?
↓
A:
諸外国は、日本よりも早く、ピークアウトした。
上昇率(前年同月比)のピーク時期は、下記の通りだ。
米国:2022年7月
韓国:2022年8月
中国:2022年10月
英国:2022年11月
-- 消費者 経済 総研 --
Q:日本のCPIのピークアウトが、遅い理由は?
↓
A:
日本は、値上げに躊躇した企業が多かった。
値上げするタイミングが、遅れたのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
次の項からの詳細解説編を、お読み頂きたい。

- ■インフレの原因は?
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:近年の日本のインフレの原因は、何か?
↓
A:天候不良、コロナ禍、原油高、円安、戦争だ
Q:その中でも、影響が大きいのは、何か?
主な要因として 「2つ 」を、挙げて欲しい。
↓
A:① 「 原油高 」 と、 ② 「 円安 」 だ。
まずは、①原油価格を、見ていく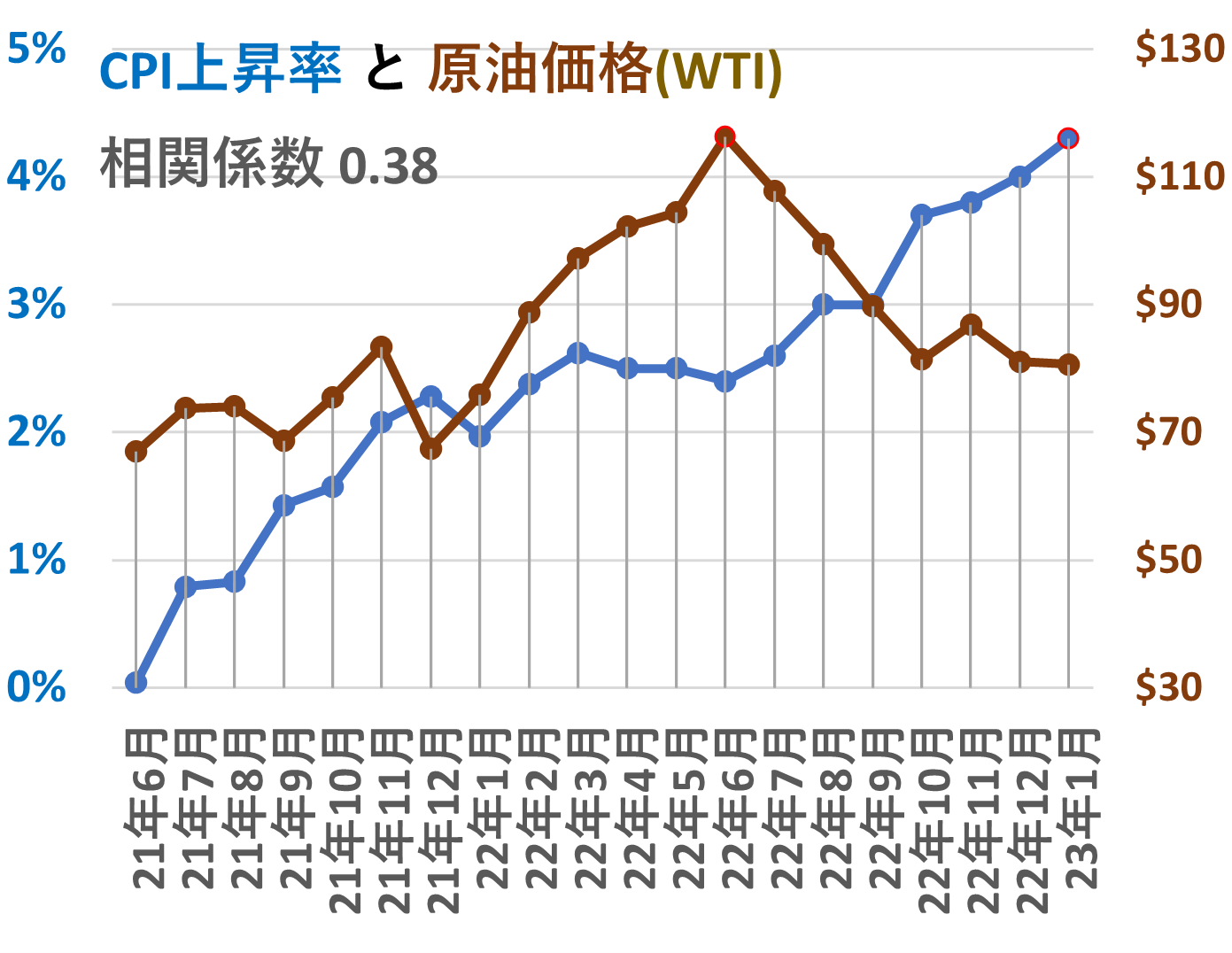 ※左軸の%は、前年同月比のCPIの上昇率で、以下同じ
※左軸の%は、前年同月比のCPIの上昇率で、以下同じ
※CPIの上昇率を、単に「CPI」と表記する箇所がある
※注意:21年4月~22年3月の間だけは、携帯料金の
値下げ効果を、排除した後のCPIとしている。
本ページでの「21年度のCPI」は、以下同じ。
Q:上のグラフでは「CPI上昇率」と「原油価格」は、
相関しているようには、見えないのは、なぜか?
↓
A:相関が見えないのは、タイムラグのせいだ。
下図のように、原油の線を、9月分右へずらすと、
原油価格と、CPIは、相関性が高い
↓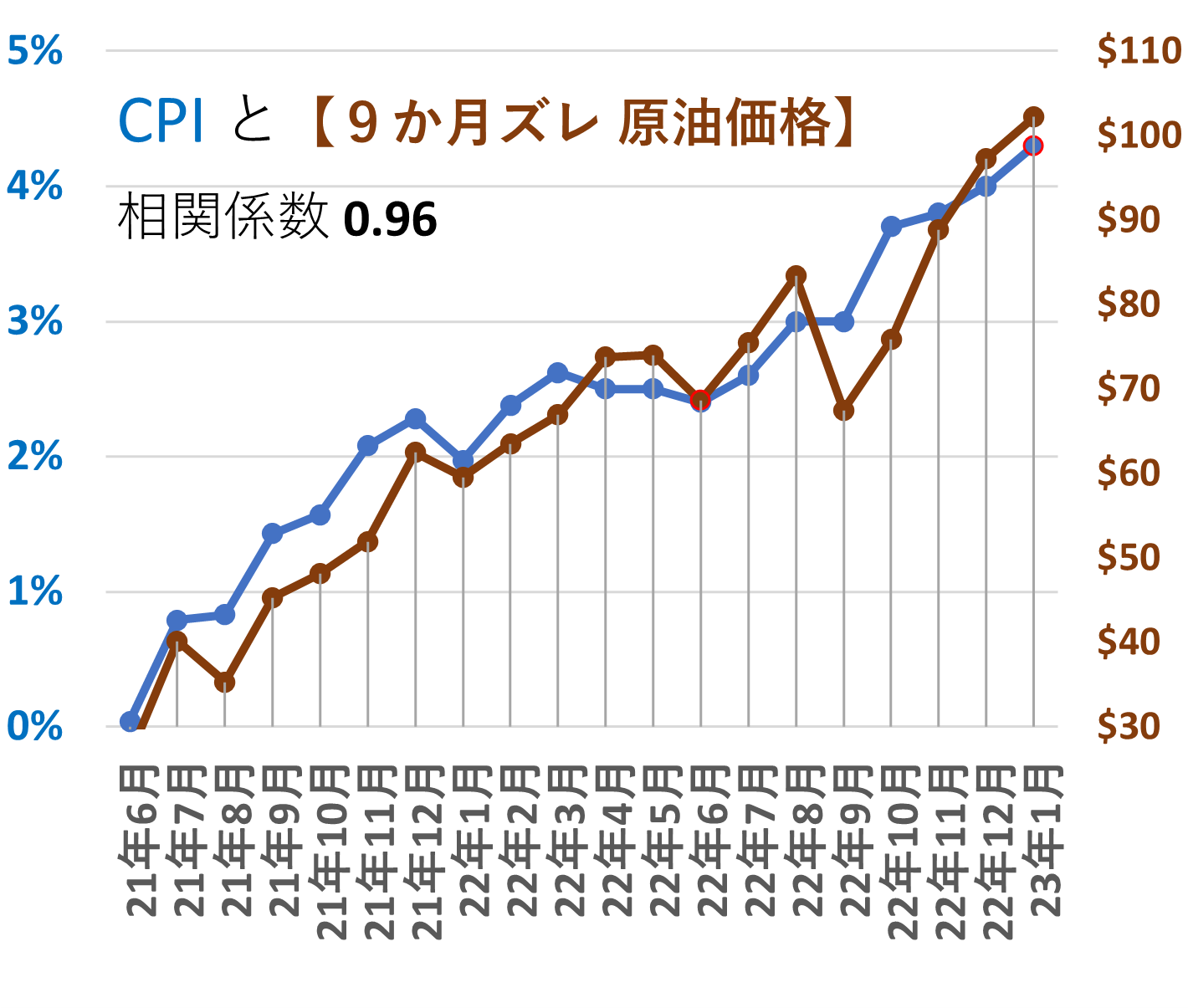 ※原油価格は、WTIの1バレルあたり。 単位はドル
※原油価格は、WTIの1バレルあたり。 単位はドル
※原油価格は、各月の月初の値
原油価格と、日本のCPIの相関は、極めて高い
上図での2つの相関係数は、「0.96」だ
相関係数は、「 ゼロ ~ 1まで 」の値で、表される
全く相関が無いが、「 ゼロ 」 だ
完全に相関するのが、 「1」 だ。
一般に、「相関係数」は、下記が目安とされる
* 0.7~1.0 → 強い相関がある
* 0.4~0.7 → 相関あり
* 0.2~0.4 → 弱いが相関あり
* 0 ~0.2 → ほぼ相関なし

- ■原油は、物価に、大きな影響?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆原油価格と、電気料金の関係は?
原油価格UP → 発電コストUP → 電気代UPだ
↓
石油は、発電のための、資源のひとつだ
↓
だが発電用の資源は、石油よりも、天然ガスが多い
↓
天然ガスの価格は、原油価格と、連動する仕組みだ
↓
よって原油価格の上昇で、天然ガス価格も、上がる
↓
こうして、電気代は、上がっていくのだ
↓
電気を、使わない消費者は、いないだろう
↓
原油高は、幅広く日本の消費者へ、影響する
-- 消費者 経済 総研 --
◆企業の電気代も、上昇?
電気代UPは、消費者に影響するだけ、ではない
↓
企業の工場では、電気を大量に、消費する
↓
企業のコストも、UPするのだ
-- 消費者 経済 総研 --
◆原油高で、企業の運搬費が、上昇?
企業が、運搬する際の手段は、何か?
↓
船便、航空便、陸運(トラックなど)だ
↓
企業は、製品を生産する前に、部品を仕入れる
↓
その部品は、「運搬」して、仕入れる
↓
その後、完成したら、それを「運搬」して、販売する
↓
運搬に、重油・ジェット燃料・ガソリンが、使われる
↓
重油・ジェット燃料・ガソリンの原料は、原油だ
↓
原油価格が、高騰すると?
↓
原油高 → 燃料費UP → 運搬費UP になる
↓
よって運搬費UPで、商品価格がUPする
-- 消費者 経済 総研 --
◆原油価格と、原材料費の関係は?
原油からは、様々な製品が、作られる。
↓
ビニール、プラスチック、ゴムなども、そうだ
↓
衣料やスニーカーの原材料も、石油由来が多い
↓
スーパーで買った食品の容器も、石油由来だ
↓
自宅の内装の壁クロスも、ビニールの物も多い
↓
様々な家庭用品のプラスチック部分も、そうだ
↓
こうして、とても広範囲に、石油が使われている
↓
運搬費UPの他、「様々な製品のコスト高」になる
↓
こうして原油高は、様々な経路を通じ、物価へ影響
-- 消費者 経済 総研 --
◆原油価格UP → 遅れて 物価UP?
Q:原油価格がUPしたら、
直ちに、物価UPするのか?
↓
A:すぐではなく、月日をかけて、CPIへ影響する。
下記の流れが、あるからだ
原油が、タンカーで、日本に入港する
↓
その後、工場などに、移動する
↓
最終製品の前に、中間財1 → 中間財2 ・・・がある
↓
最終的に、消費者が買う時は、数か月経過している
↓
前出のグラフは、9か月のラグが見られた

- ■続いて「円安」も、影響する?
- 物価上昇の主な原因は、
「 ① 原油高 」 と、 「 ②円安 」 だった。
前項では、「 ① 原油高 」 を、解説したが、
ここからは、「 ② 円安 」 を、解説していく。
Q:「 円安で、物価上昇 」 を、
単純化した話で、理解したい
↓
A:下記の例で、解説していく
・円高:1ドル 100円
・円安:1ドル 150円
円高なら、日本は、
1億ドルの商品の輸入では、100億円を、支払う
円安なら、日本は、
1億ドルの商品の輸入では、150億円も、支払う
同じ商品の輸入でも、
円安の方が、日本の支払額が、多い。
円安によって、輸入物価が上る。
言い換えると、
「 ドル円が円安 」 になると、「 CPI 」 は、上昇する。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:ドル円と、CPIの関係の推移は、どうか?
↓
A:下図が、最近のドル円・CPIのグラフだ。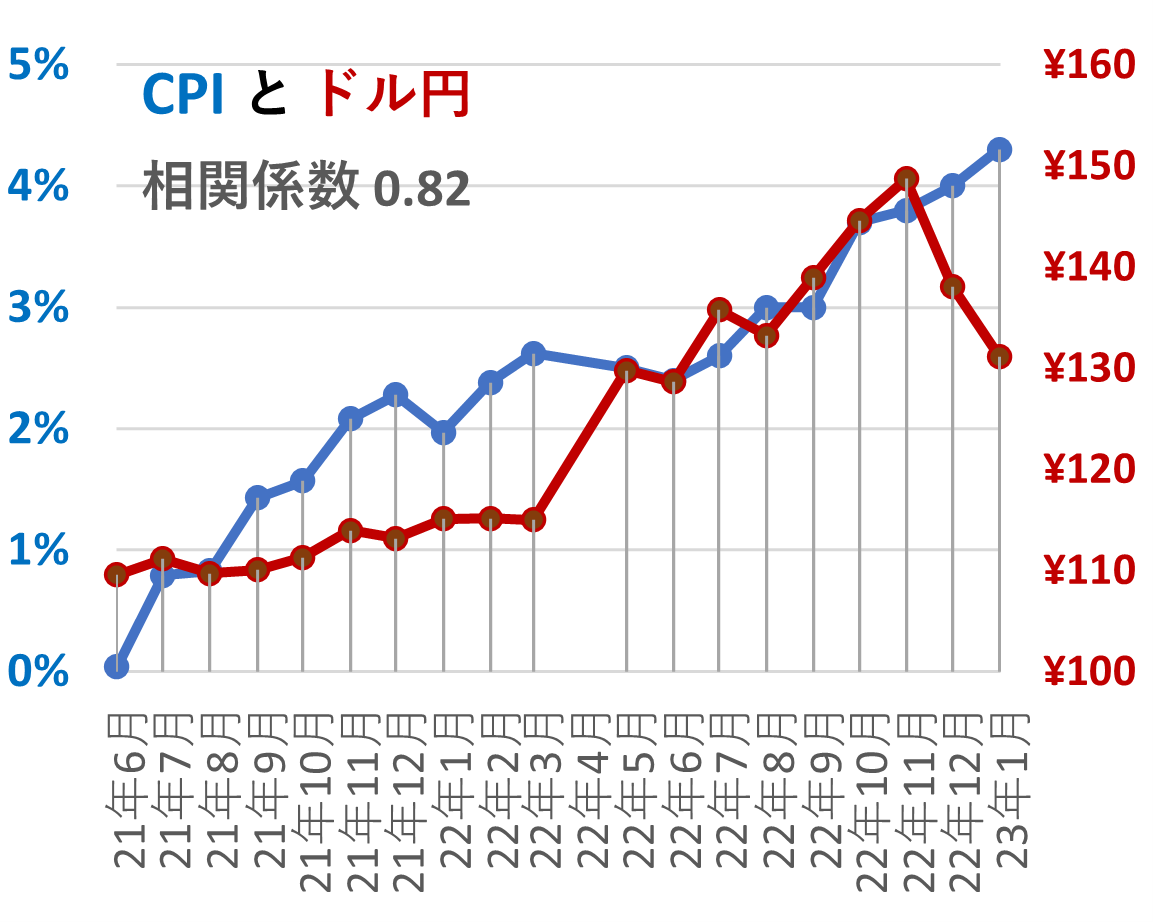
Q:上グラフでは、「CPI上昇率」と「ドル円」は、
相関は、さほど高くないは、なぜか?
↓
A:
相関が高くないのは、タイムラグのせいだ。
下図の様に、ドル円の線を、3月分右へずらすと、
ドル円と、CPIは、相関性が高くなる。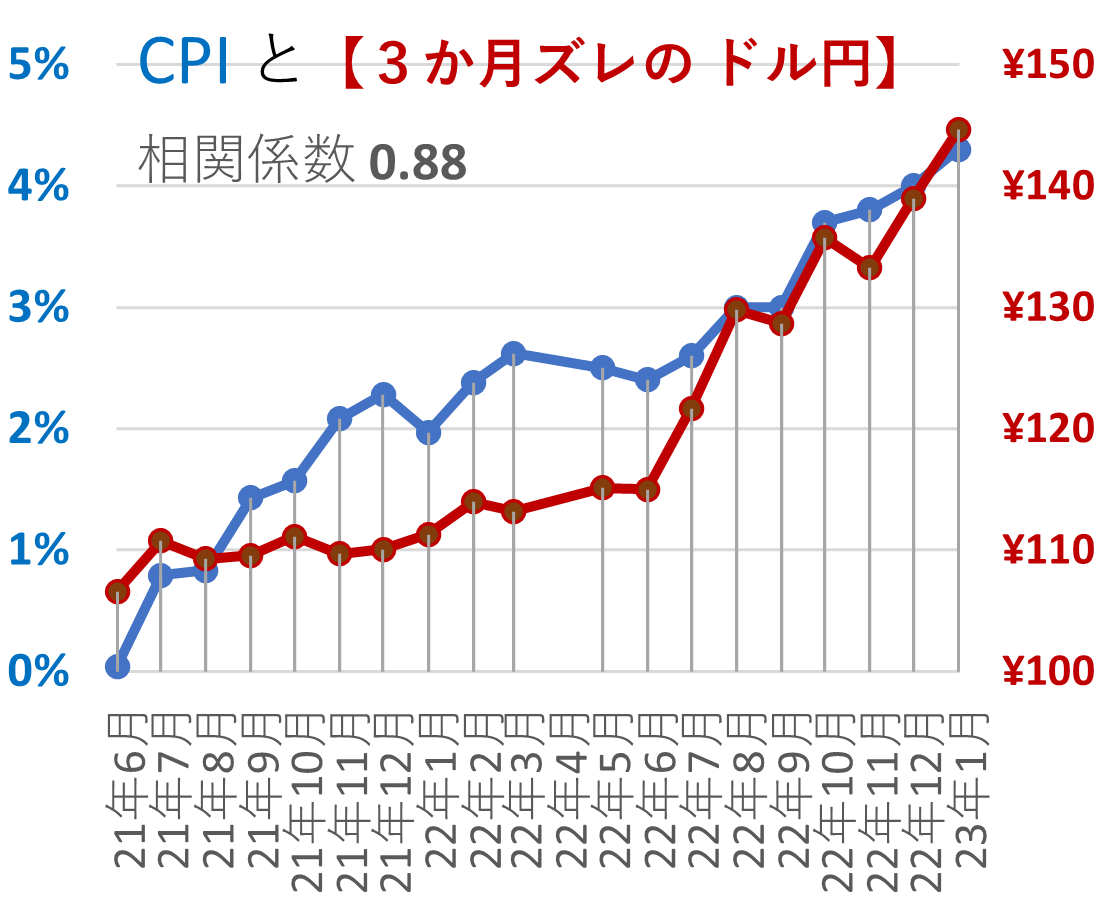
Q:円安の影響が、
遅れて出てくるのは、なぜか?
↓
A:下記のようなタイムラグが、あるからだ。
日本の港に来た、海外からの製品なども、
最終的に、店頭に並ぶのは、先となる
前項の原油でも、タイムラグが、見られた。
円安の影響は、3か月のタイムラグが、見られる。
-- 消費者 経済 総研 --
◆原油と、為替が、CPIへ影響
ここまでで、原油価格とドル円が、タイムラグを、
持ちながら、CPIに影響すると、わかった。
続いて、次項からは、
原油・ドル円の影響の度合いの変化を、解説する。

- ■原油とCPIの 相関は、薄れた?
- 「①原油高・②円安」 と、 「CPI」 は、
タイムラグを持ちながら、連動すると解説した。
だが最近は、その連動に、変化が見られる。
まずは、「①原油」から見ていく。
-- 消費者 経済 総研 --
◆CPIと原油の連動は、薄れた?
。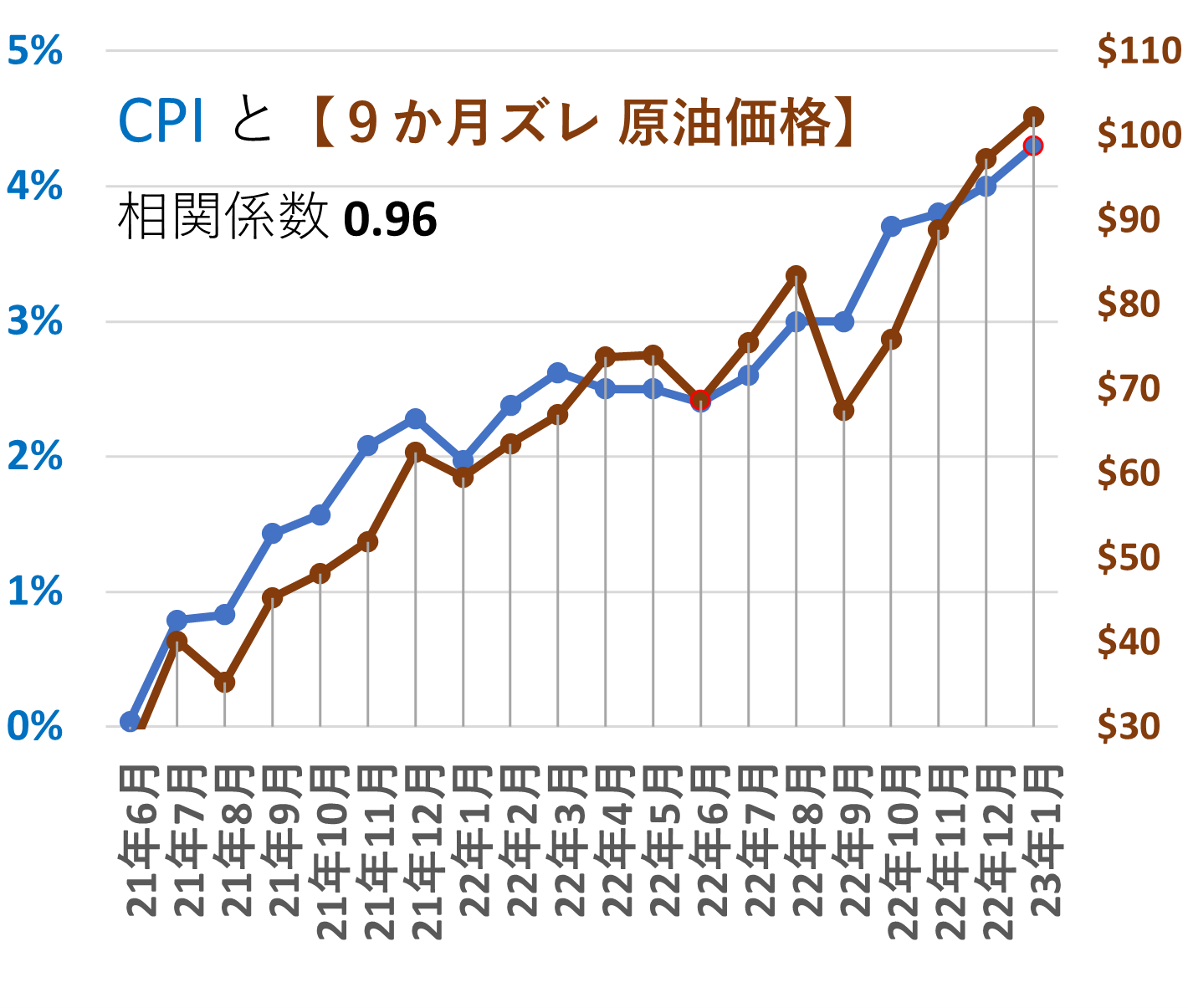
上のグラフでは、原油とCPIの相関は、高かった。
期間は、23年1月までだ。
期間を、23年5月まで、伸ばすと、どうか?
下のグラフだが、2月から、連動性は低下する。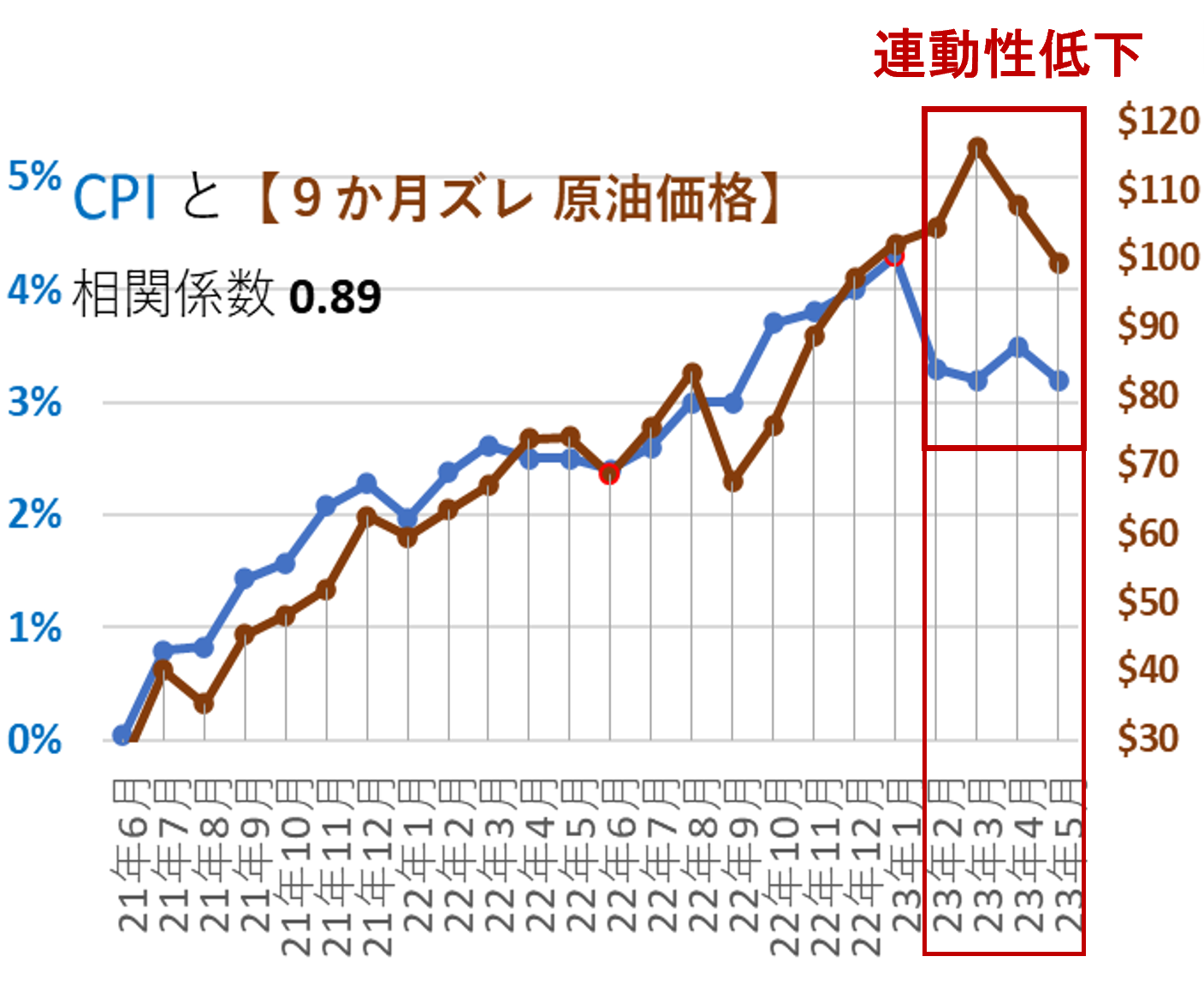
上図で、23年の
「1月まで」と、「2月から」で、変化が見られる。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:23年の 「1月まで」 と、「2月から」 で、
相関係数を、比較すると、どうか?
↓
A:「 CPI 」 と 「 原油価格 」 の相関係数は、
下記のように、低下した。
・21年6月~23年1月は、0.96
↓
・23年の 2月~5月では、-0.01
-- 消費者 経済 総研 --
◆2月から、変わった?
下のグラフは、CPIの実績の推移だ。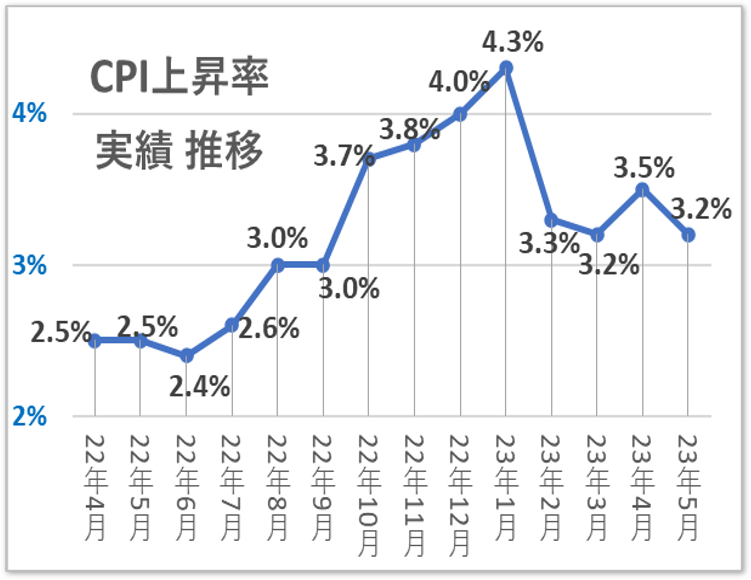
1月まで上昇し、2月から下落した。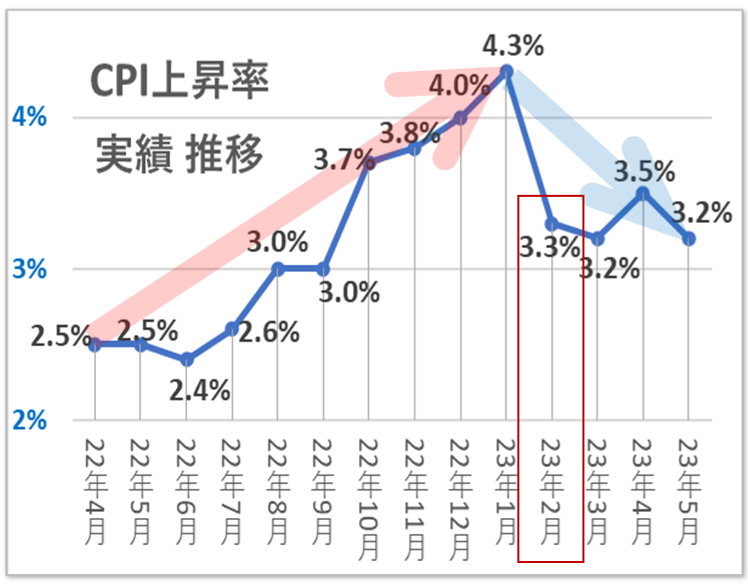
Q:上図で、「 2月 」 から、CPIが、急落した。
その原因は、何か?
↓
A:電気代・ガス代の支援が、始まったからだ。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:電気代・ガス代の支援とは何か?
↓
A:経産省・資源エネルギー庁の負担軽減策で、
名称は「 電気・ガス価格 激変緩和 対策事業 」 だ
この支援は、23年1月~9月まで、行われる。
CPIに、反映されるのは、翌月になる。
よって、2月~10月までのCPIに、影響する。
下のグラフは、CPIの実績の推移だ。
23年2月から、急落したのがわかる。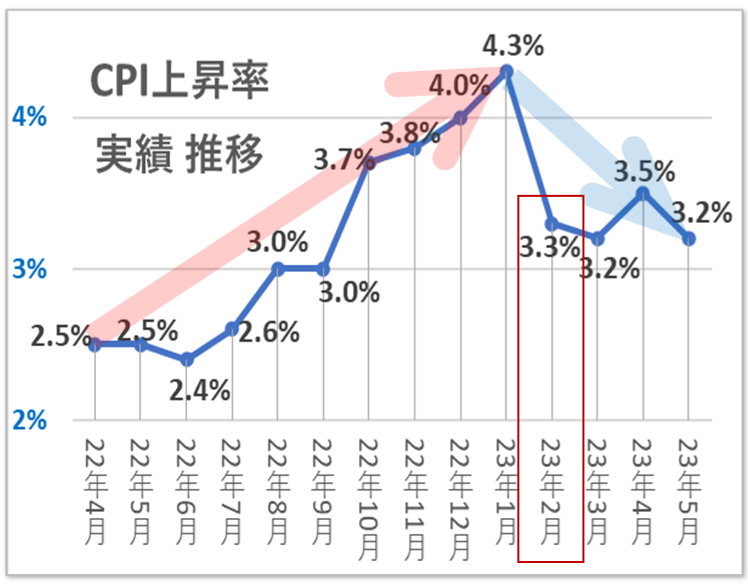
-- 消費者 経済 総研 --
Q:電気ガス代の支援が、
「 なかった場合 」 では、どうか?
↓
A:
支援ありと、支援なかった場合の比較が、
下のグラフだ。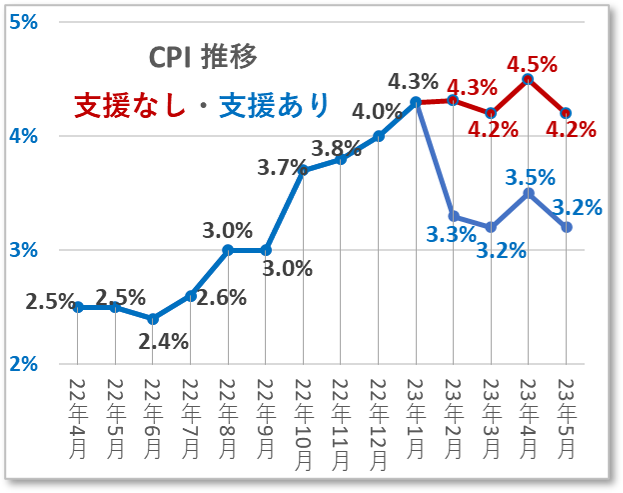
支援ありと、支援なしの差は、1.0%だ。
電気ガス支援で、CPIを、1.0%押し下げたのだ。
23年4月は、3.5%だったが、
支援がなければ、4.5%だった。
もし4.5%なら、ピークの1月の4.3%を超え、
物価上昇が、進んでいたのだ。
支援なし:4.5% → 支援あり:3.5%で、
1%の負担軽減は、大きいのだ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「 原油価格と、CPI 」 の話に、戻る。
23年の2月~5月だけに、
集中した方が、見やすいだろう。
そうすると、どんなグラフ・相関になるか?
↓
A:下のグラフのようになる。
この期間の相関係数は、-0.01で、
CPIと原油の相関は、見られない。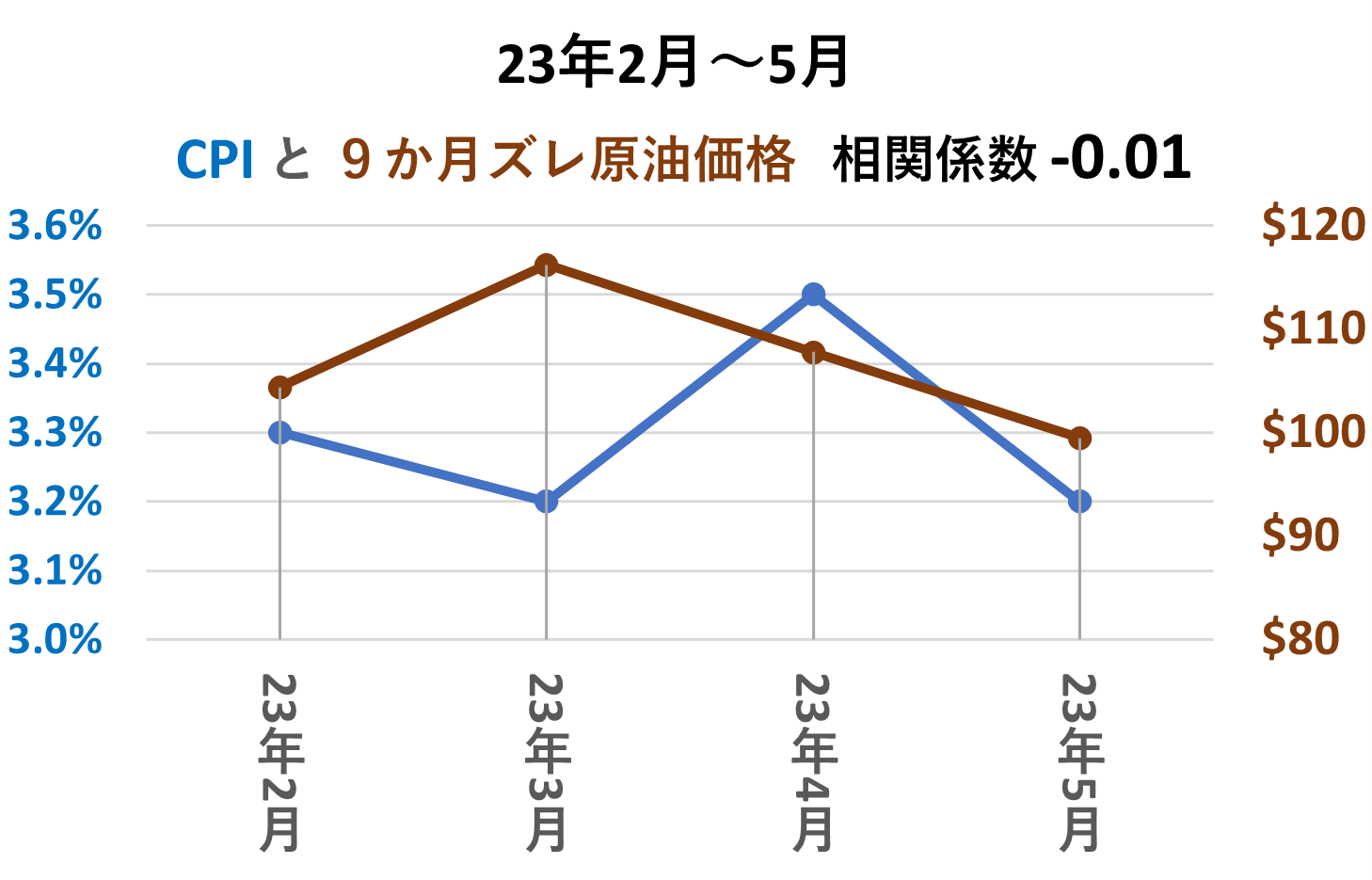
-- 消費者 経済 総研 --
Q:では、電気ガス支援が、
相関を下げた のではないか?
その支援の影響を排除すれば、
「 原油価格と、CPI 」 は、高い相関か?
↓
A:
違う。 支援を排除しても、相関は低いままだ。
23年2月からは、
電気ガス支援ありの現状で、-0.01
電気ガス支援なしだとしたら、-0.01
支援ありでも、支援なしでも、相関は見られない。
つまり、連動性が、低下した原因は、
電気ガス支援ではない。
23年2月からは、
電気ガス支援でも、原油価格でも、
CPIを説明できなくなった。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「 ①原油 」 では、
説明できなくなったのは、わかった。
では、「 ②ドル円 」なら、説明できるか?
↓
A:ドル円とCPIの関係(23年2月から)を、
次項で見ていく。

- ■ドル円とCPIの相関は、薄れた?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆2月以降は、「②ドル円」の相関も、薄れた?
前項では「 原油とCPI 」 の連動の低下を解説した。
では、 「 ドル円とCPI 」 では、どうか?
23年の2月~5月で見ると、「ドル円とCPI」では、
相関係数は-0.16で、相関は見られない。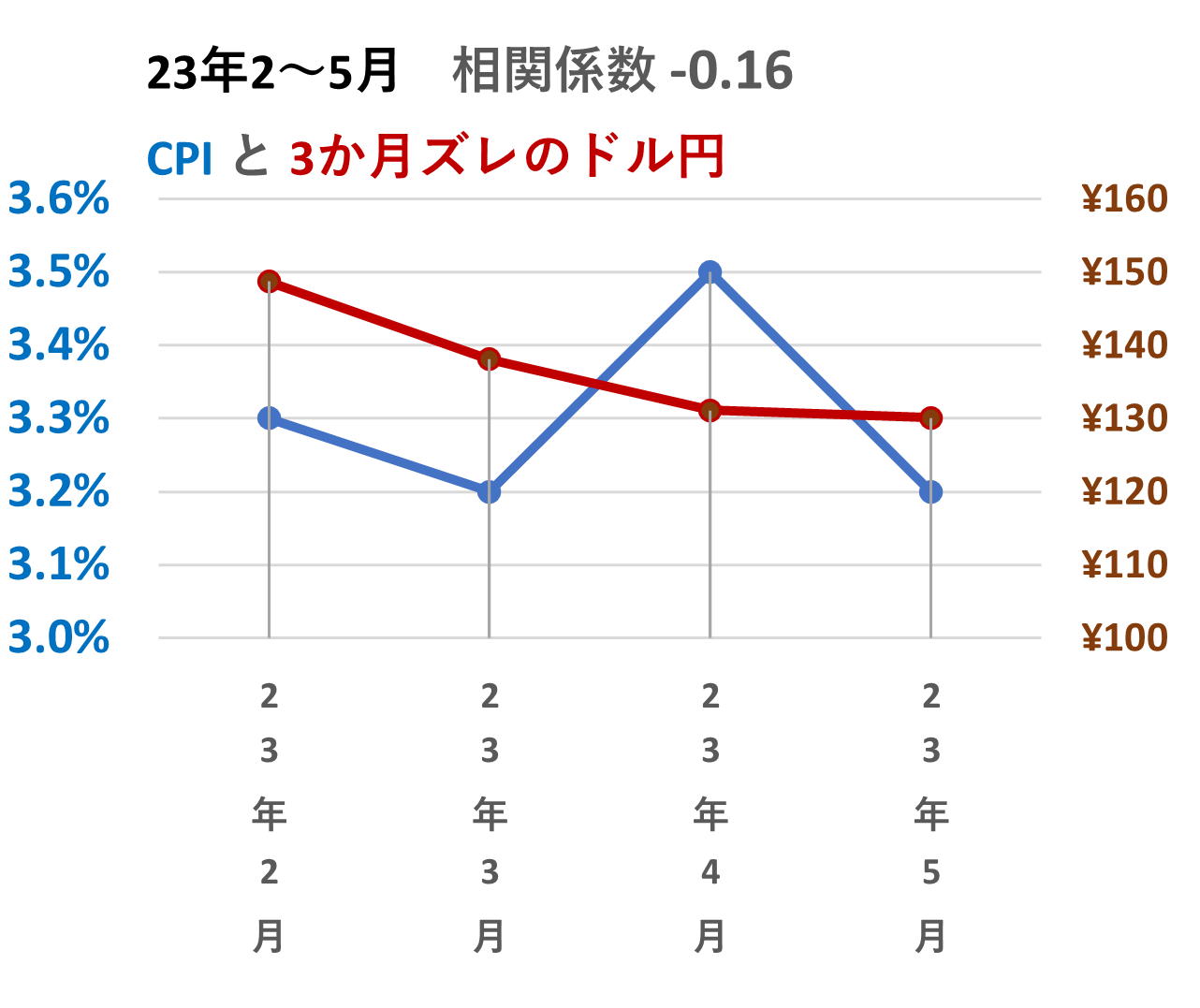
「 電気ガス支援が、無し 」 とした場合も、
相関係数は-0.16で、相関は見られない。
23年2月からは、
原油では、CPIを説明できないと前項で解説した。
同様に本稿でも、
ドル円でも、説明できないとわかった。
23年2月からは、
原油でもドル円でも、CPIを説明できない。
Q:では、何が要因となったか?
↓
A:〇〇が、大きく影響している。
次項で、解説していく。

- ■相関低下の原因は?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆最近は、CPIを決めるのは、〇〇?
本来は、物価は、
原油価格や、ドル円で、決まるはずだった。
最近の物価は、原油やドル円では、説明できない。
そこで、登場する説明変数は、
「 食品 値上げ数」 だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆「 食品の値上 」 が、強く影響した?
最近は「 食品の 値上げ ラッシュ」 が、続いている。
下のグラフは、
毎月の月別の、「 値上食品の 品目数 」 の推移だ。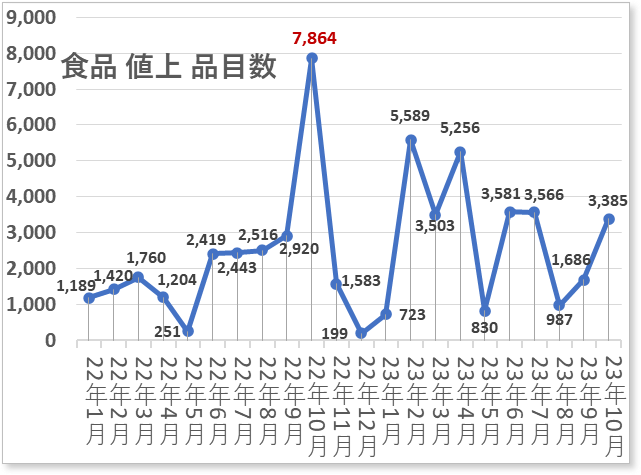
下のグラフは、上図に、「累計」を加えた図だ。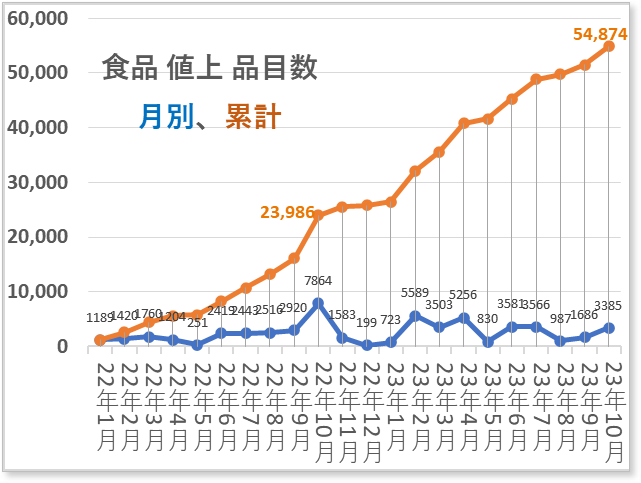 ※上図2つの出典:
※上図2つの出典:
帝国データバンク|食品主要195社価格改定動向調査|2023年7月
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「 食品値上 」 と 「 CPI指数 」 は、
どの程度、連動するか?
↓
A:下のグラフのように、相関係数は0.96で
相関は、とても高い。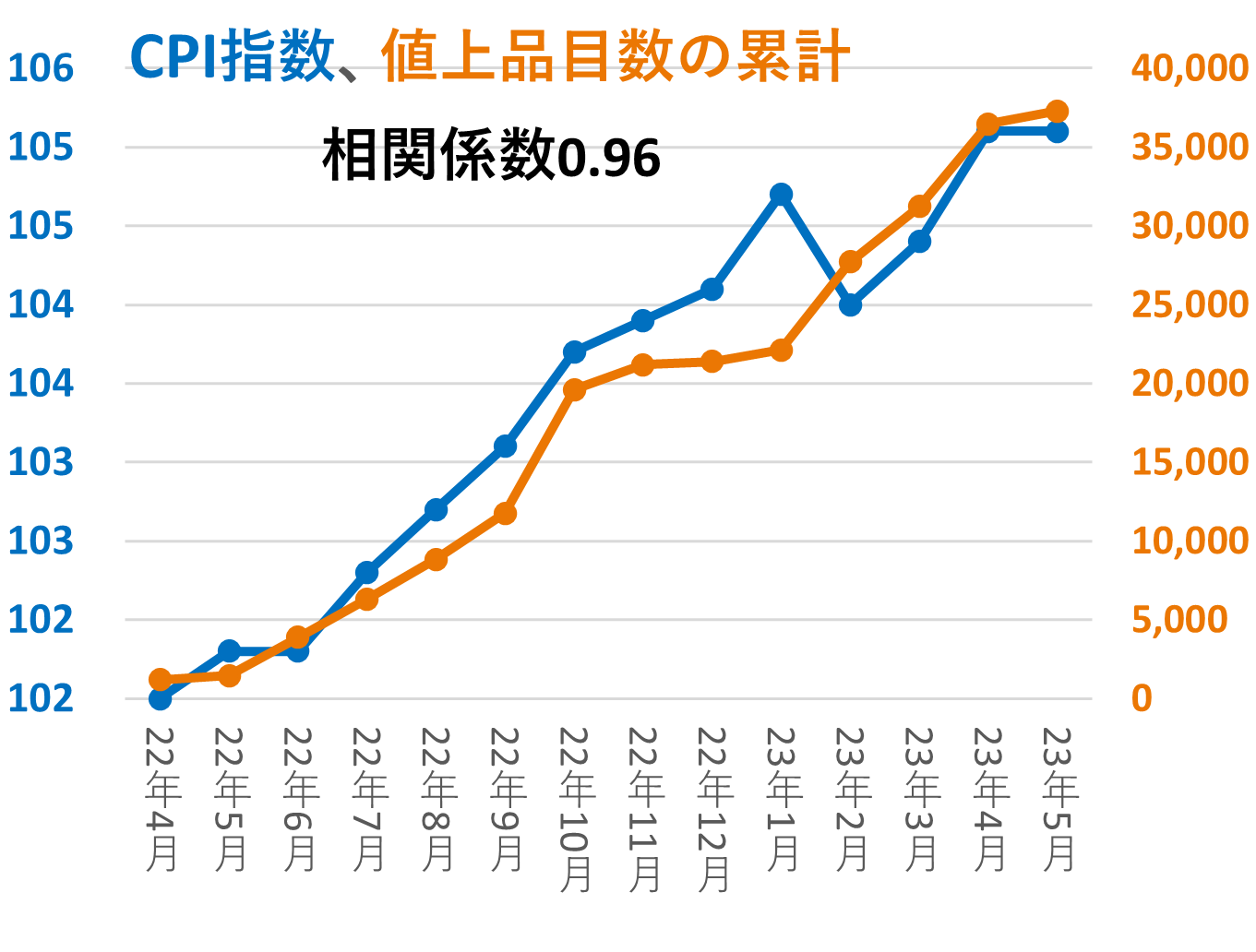
-- 消費者 経済 総研 --
Q:上図は、22年4月からだが、
変化が見られた23年2月からでは、どうか?
↓
A:23年2月~5月では、CPI指数と値上数累計は、
相関係数は、ほぼ1.00で、完全相関に近い。※
※相関係数は、0.99704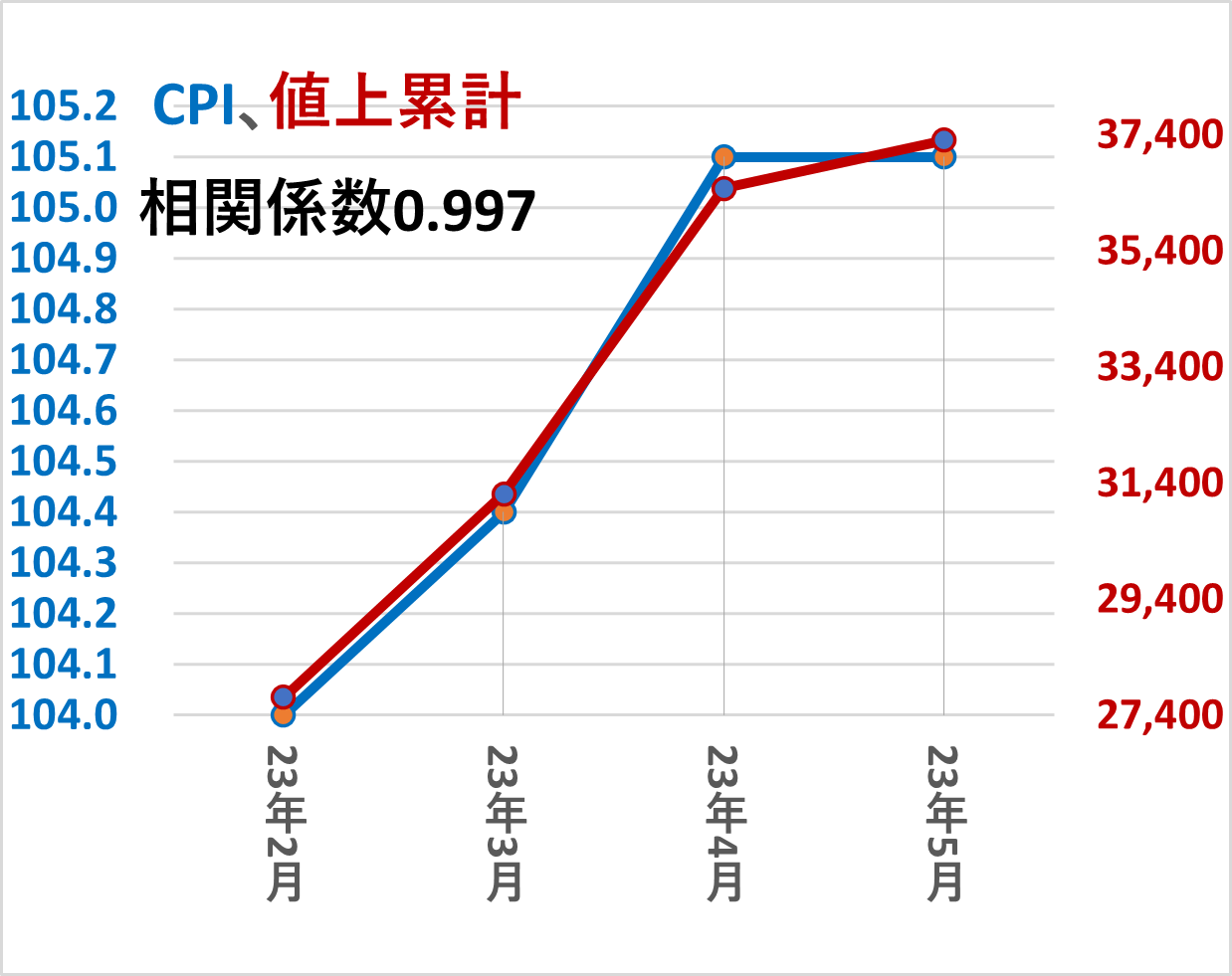
-- 消費者 経済 総研 --
Q:ところで、「 CPI 指数 」とは、何か?
↓
A:
前項までは、CPIの推移を、見る際は、
「 前年 同月比 」 のパーセントで、見てきた。
例えば、翌年が、2% 物価上昇し、
翌々年が、前年比 3% 上昇したら、下記の通りだ。
翌年 の CPI 上昇率 : 2%
翌々年のCPI上昇率 : 3%
翌年 の CPI 指数 : 102.00
翌々年のCPI指数 : 105.06 (= 102 × 1.03 )
CPIを発表する総務省は、
基準年の2020年を100として、CPI指数を表す。
-- 消費者 経済 総研 --
◆CPI予測に、値上品目数を
高い相関関係から、
第1に、「値上品目数の累計」から、CPIを予測した。
その後、電気料金等の変動を、加味した。
具体的には、
電気ガス支援の影響や、電力会社の6月の値上げ、
電気代(燃料調整費)の変動予測を加味し、算出した。
▼① 値上の品目数から、CPIを予測
下のグラフのように、
値上数は、22年10月に、ピークアウトした。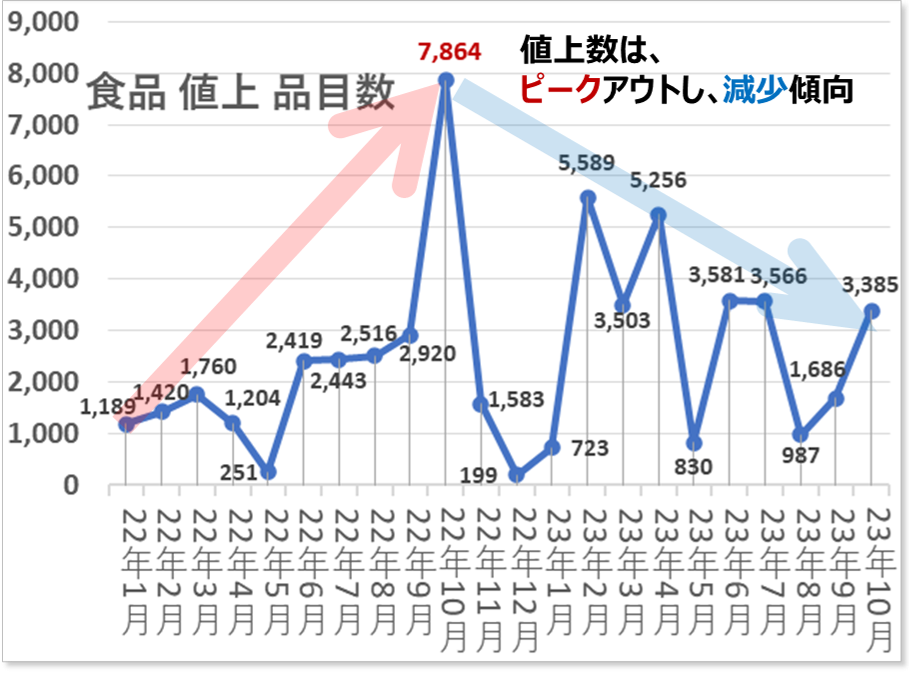
23年10月までの値上数の減少推移から、
23年11月~24年3月の月別の値上数を、予測した。
これが、予測の手順の①番目で、
その後、下記②③④の手順で、予測した。
① 値上品目数から、月別のCPIを、予測
↓
② 電気ガス支援の影響を加減
↓
③ 電力会社の23年6月からの値上を、加算
↓
④ 電気代(燃料調整費)の変動予測を加味
( 原油価格から予測 )
-- 消費者 経済 総研 --
Q:では、①~④で、CPIの予測は、どうか?
↓
A:予測の結果が、下のグラフだ。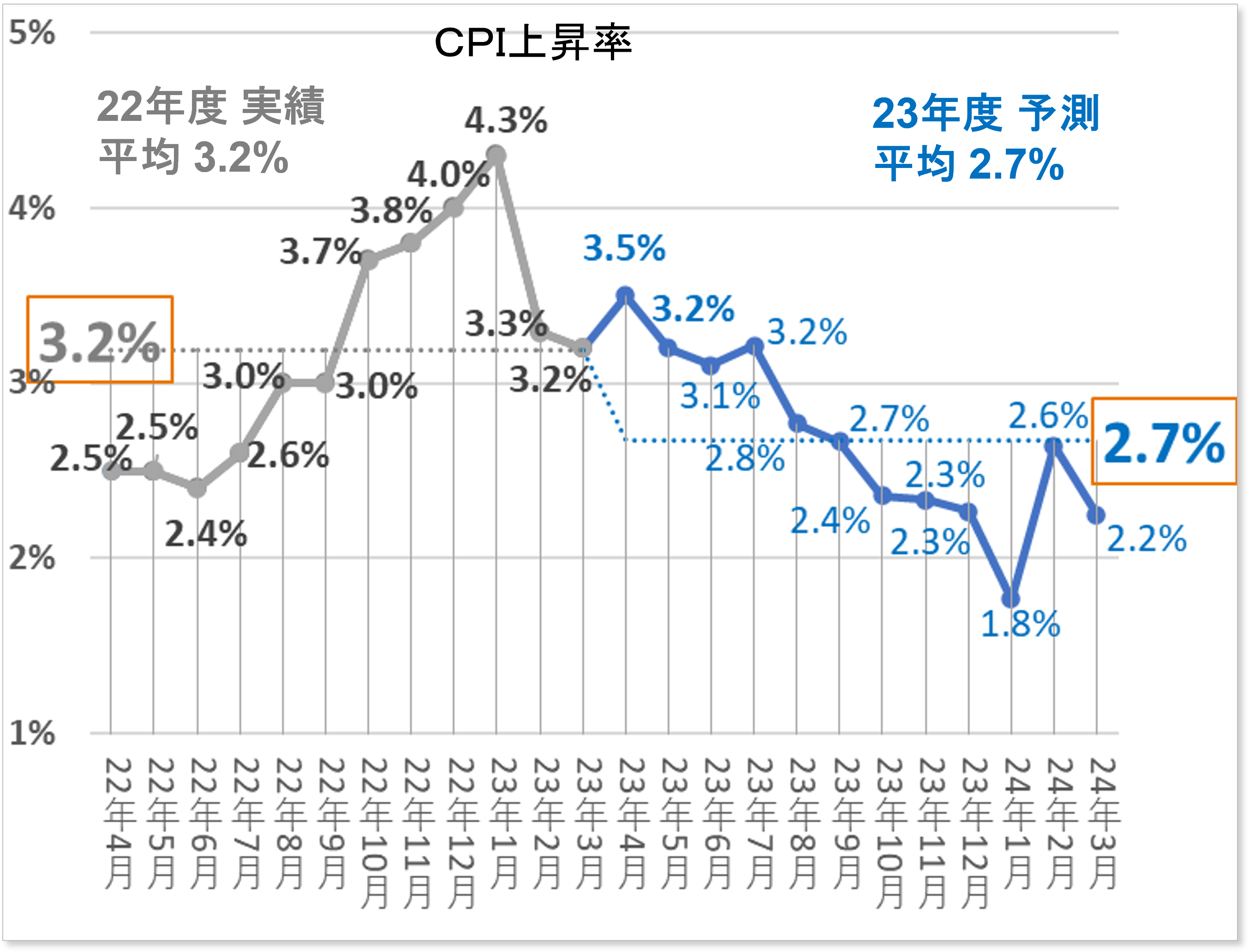
22年度のCPI上昇率は、3.2%だった。
23年度のCPI上昇率は、2.7%となった。
但し、 「 電気ガス支援が、24年3月まで継続する 」
との前提での予測だ。
現状では、電気ガス支援は、
23年9月までの予定となっている。
消費者 経済 総研は、電気ガス支援は、
延長される可能性が、高いと見ている。
その理由は後述する。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:では、電気ガス支援が、
予定通り、終了したら、どうなる?
↓
A:下のグラフの赤線のように、なるだろう。
赤線が、電気ガス支援が、終了した場合で、
青線が、電気ガス支援が、継続した場合だ。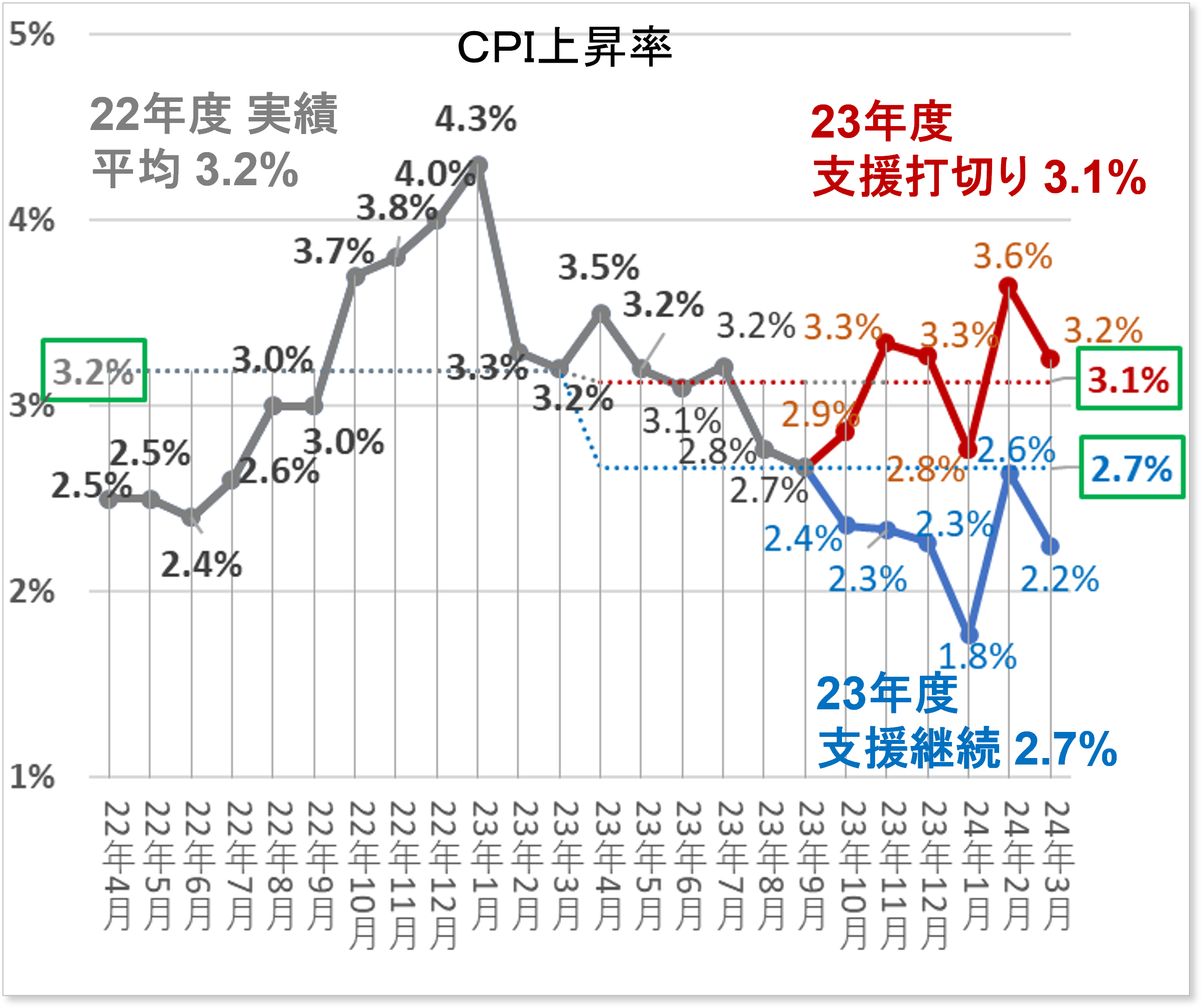
緑色の四角い枠は、年度(12ヶ月分)の平均値だ。
支援が打切りになったら、23年度は22年度並みに
物価上昇率が、高くなってしまう。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:CPI上昇率のまとめは?
↓
A:
・22年度 実績 :3.2%
・23年度予測:支援終了:3.1%
・23年度予測:支援継続:2.7%
-- 消費者 経済 総研 --
Q:電気ガス支援は、
延長されると、予測した理由は?
↓
A:
23年度の賃金のベースアップ率は、2.12%だ。
賃金UP率が、2.1%で、物価UP率が3.1%では、
消費者の生活は苦しい。
岸田内閣は、
解散・総選挙を、意識しているとされる。
生活負担を感じされる状況は、避けたいだろう。
※ベア出典:連合|2023春季生活闘争第7回(最終)回答集計結果

- ■関連テーマは?
- 前項までが、CPI上昇率の予測だった。
続いて、関連テーマとして、
「 値上げは、 悪か、善か? 」 を、解説したい。
また「 2023 賃金 予測 」のページもご覧頂きたい。
物価上昇 > 賃金上昇 ならば、苦しいが、
物価上昇 < 賃金上昇 ならば、よい。
前項で、「ベースアップ」の話をしたが、
「ベースアップ」と「定期昇給」の違いも解説中だ。
その関連ページのリンク集が、
本ページの下段に、あるので、ご覧頂きたい。

- ■値上げは、 悪か、善か?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆消費者物価へ、価格転嫁すべき?
▼米国は、企業物価UP→最終商品価格へ転嫁
日米のインフレへの初期対応を、比較したい
↓
企業物価が、高騰した
↓
米国企業は、最終商品への価格転嫁を、進めた
↓
この価格転嫁は、当然のことである
↓
企業物価には遅行するが、消費者物価も上昇した
↓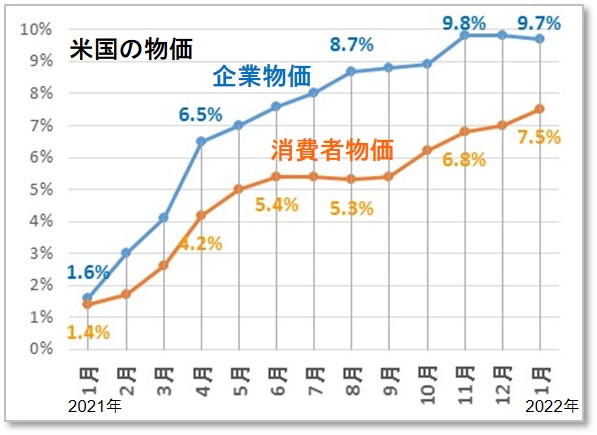
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本は、どうした?
企業物価の上昇で、日本の企業は、どうしたか?
↓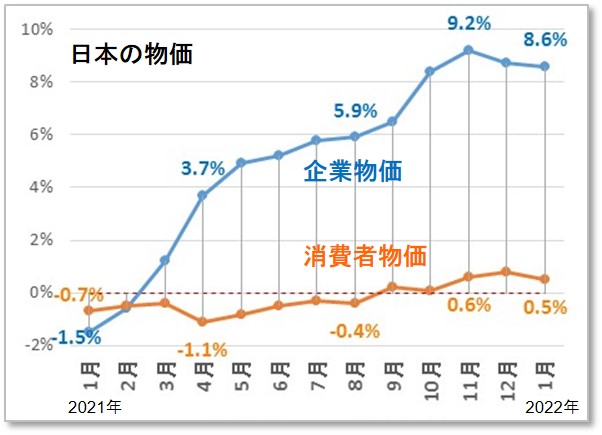 ↓
↓
消費者へ売る商品の価格への転嫁は、遅かった
↓
よって消費者物価の上昇率は、小さかった
↓
売値(販売価格) - コスト(原価) = 粗利益 だ
↓
コストUPしたのに、売値が、少ししかUPしない
↓
これでは、企業の粗利益が、減ってしまう
↓
企業の粗利益は、社員の賃金の原資だ
↓
粗利益が減れば、社員の賃金の原資が減る
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本もようやく値上げへ?
高騰した企業物価を消費者物価へ転嫁しないと?
↓
赤字転落する企業も、増えるだろう
↓
値上げを、自社だけ行うと、どうなる?
↓
消費者から、割高と判断され、売上は落ちる
↓
しかし日本も、値上げラッシュを、始めた
↓
他社が値上げなら、自社も値上げとなる
↓
日本は外国よりは遅れて、インフレが進行した

- ■良いインフレか? 悪いインフレか?
- ここまでの話で、最近のインフレは、
「悪いインフレ」だとわかる。
賃金が増えない中での物価上昇は、悪いインフレ
賃金UP >物価UP→ 良いインフレ のイメージ図
↓
物価UP >賃金UP → 悪いインフレのイメージ図
↓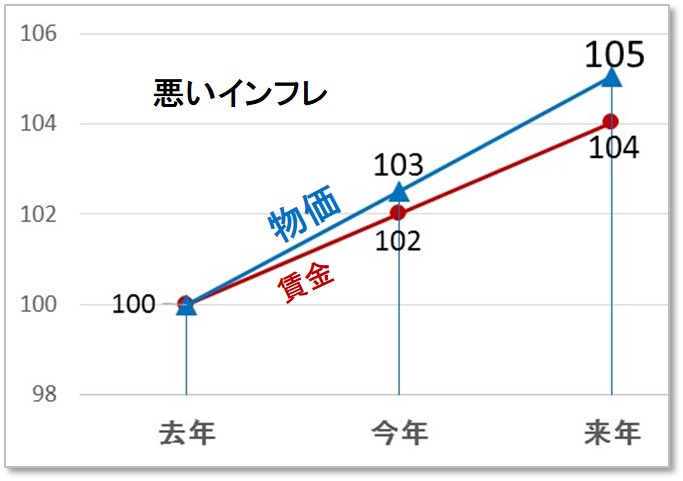
-- 消費者 経済 総研 --
◆価格転嫁が、進まない場合は?
最終商品への価格転嫁が、進まない場合は?
↓
企業の粗利益が、減る
↓
賃金の原資が、減ってしまう
↓
「賃金の減少」を、招きなねない、悪いインフレだ
-- 消費者 経済 総研 --
◆価格転嫁が、進む場合は?
最終商品への価格転嫁が、進んだ場合は?
↓
最終商品の価格が、上昇
↓
消費者物価が、上昇
↓
賃金が上がらず、物価だけ上がったら?
↓
価格転嫁しても、悪いインフレだ
↓
では、どうすべきなのか?
-- 消費者 経済 総研 --
◆通常の好景気では?
通常の好景気ならば、企業の売上も利益も、増える
↓
利益が増えれば、賃金も増やせる
↓
賃金が増えたら、消費支出が拡大する
↓
消費拡大で、需要増加となり、物価も適正に上がる
↓
企業は、販売価格・販売数量が上昇で、売上UPだ
↓
プラスが、プラスを生む「好循環」である
↓
プラスの好循環では、
企業の売上・利益も、社員の給料も、物価も、UPだ
↓
この好循環での物価上昇は、良いインフレである
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本の解決策は?
では「プラスの好循環」のためには、どうすべきか?
↓
日本の消費者は、「値上げを許容」するのだ
↓
これで、日本企業の売上と粗利益が、増える
↓
「粗利益」の増加は、「賃金の原資」の増加だ
↓
そして企業は、「賃金をUP」させるのだ
↓
しかし企業は、最終利益を内部留保に、回している
↓
政府が「賃上げを促す税制を、強化」するのだ
↓
これをしなければ、日本だけが、低迷のままだ
これをしないと、悪いインフレのままだ。
消費者も、節約を考えるよりも、
収入を増やす事を、考えるのだ。
節約をすると、回り巡って、
自分たちの収入を、減らしてしまう。
これを経済学では 「 合成の誤謬 」 という。
※合成の誤謬( ごうせいの ごびゅう )とは、
ミクロの視点では、正しいことでも、
それが合成されたマクロの世界では、
必ずしも意図しない結果が生じることを
指す経済学の用語
(※出典:wikipedia)
では、2023年の日本人の年収は、どうなるか?
連載シリーズ・2023年度 経済予測は、
「 年収の予測 」 なども、投稿済みだ。
年収は、月給+残業代+ボーナス+その他の計
物価UP率 と、賃金UP率 は、どっちが、大きいか?
下記の関連ページを、ご覧頂きたい。
- ■関連ページは?
- ◆物価UP率と賃金UP率は、どっちが大きい?
- ◆2023年日本の賃金アップ率,引上げ額の予測
- ◆節約ではなく、収入UPの方法 とは?
- ◆第1部 賃上げ・収入UP方法ベスト10(政策提言)
- ◆インフレ、物価、日銀
- ◆[簡単]インフレ,デフレ,ハイパーインフレとは
◆悪いインフレとは?|日本の値上げの原因理由
◆最近の悪い円安とは?|円安円高のメリットデメリット
◆悪い円安論 は 嘘?|悪い円安,良い円安とは?
◆Vol.1 ウクライナ情勢の日本への間接影響
◆Vol.2 続編 ウクライナ情勢の日本への直接影響
- ◆値上げラッシュ|商品 一覧
- ◆2021年4月からの値上げ・値下げとは?
◆なぜ値上げラッシュ?値上げ食品一覧・原因理由
◆2022年4月から値上げ一覧,原因理由も
◆2022年10月から値上げ一覧,原因理由も
◆2023年2月 値上げ一覧、 値上げ いつまで続く?

| ■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので、 「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆である事を念頭に置いて下さい。 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、 対応して下さい。また「免責事項 」をお読みください。 ■引用 真っ暗なトンネルの中から出ようとするとき、 出口が見えないと大変不安です。 しかし「出口は1km先」などの情報があれば、 真っ暗なトンネルの中でも、希望の気持ちを持てます。 また、コロナ禍では、マイナスの情報が飛び交い、 過度に悲観してしまう人もいます。 不安で苦しんでいる人に、出口(アフターコロナ)という プラス情報も発信することで、 人々の笑顔に貢献したく思います。 つきましては、皆さまに、本ページの引用や、 URLの紹介などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件をご覧下さい。 |
- 【著作者 プロフィール】
- ■松田 優幸 経歴
(消費者経済|チーフ・コンサルタント)
◆1986年 私立 武蔵高校 卒業
◆1991年 慶応大学 経済学部 卒業
*経済学部4年間で、下記を専攻
・マクロ経済学(GDP、失業率、物価、投資、貿易等)
・ミクロ経済学(家計、消費者、企業、生産者、市場)
・労働経済
*経済学科 高山研究室の2年間 にて、
・貿易経済学・環境経済学を研究
◆慶応大学を卒業後、東急不動産(株)、
東急(株)、(株)リテール エステートで勤務
*1991年、東急不動産に新卒入社し、
途中、親会社の東急(株)に、逆出向※
※親会社とは、広義・慣用句での親会社
*2005年、消費・商業・経済のコンサルティング
会社のリテールエステートに移籍
*東急グループでは、
消費経済の最前線である店舗・商業施設等を担当。
各種施設の企画開発・運営、店舗指導、接客等で、
消費の現場の最前線に立つ
*リテールエステートでは、
全国の消費経済の現場を調査・分析。
その数は、受託調査+自主調査で多岐にわたる。
商業コンサルとして、店舗企業・約5000社を、
リサーチ・分析したデータベースも構築
◆26年間の間「個人投資家」としても、活動中
株式の投資家として、
マクロ経済(金利、GDP、物価、貿易、為替)の分析や
ミクロ経済(企業動向、決算、市場)の分析にも、
注力している。
◆近年は、
消費・経済・商業・店舗・ヒットトレンド等で、
番組出演、執筆・寄稿、セミナー・講演で活動
◆現 在は、
消費者経済総研 チーフ・コンサルタント
兼、(株)リテール エステート リテール事業部長
◆資格は、
ファイナンシャル・プランナーほか
■当総研について
◆研究所概要
*名 称 : 消費者経済総研
*所在地 : 東京都新宿区新宿6-29-20
*代表者 : 松田優子
*U R L : https://retail-e.com/souken.html
*事業内容: 消費・商業・経済の、
調査・分析・予測のシンクタンク
◆会社概要
「消費者経済総研」は、
株式会社リテールエステート内の研究部署です。
従来の「(株)リテールエステート リテール事業部
消費者経済研究室」を分離・改称し設立
*会社名:株式会社リテールエステート
*所在地:東京都新宿区新宿6-29-20
*代表者:松田優子
*設立 :2000 年(平成12年)
*事業内容:商業・消費・経済のコンサルティング
■松田優幸が登壇のセミナーの様子
- ご案内・ご注意事項
- *消費者経済総研のサイト内の
情報の無断転載は禁止です。
*NET上へ「引用掲載」する場合は、
①出典明記
②当総研サイトの「該当ページに、リンク」を貼る。
上記の①②の2つを同時に満たす場合は、
事前許可も事後連絡も不要で、引用できます。
①②を同時に満たせば、引用する
文字数・情報量の制限は、特にありません。
(もっと言いますと、
①②を同時に満したうえで、拡散は歓迎です)
*テレビ局等のメディアの方は、
取材対応での情報提供となりますので、
ご連絡下さい。
*本サイト内の情報は、正確性、完全性、有効性等は、保証されません。本サイトの情報に基づき損害が生じても、当方は一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。
- 取材等のご依頼 ご連絡お待ちしています
- メール: toiawase★s-souken.jp
(★をアットマークに変えて下さい)
電 話: 03-3462-7997
(離席中が続く場合は、メール活用願います)
- チーフ・コンサルタント 松田優幸
- 松田優幸の経歴のページは「概要・経歴」をご覧下さい。