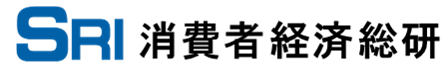[日銀|利上げできない・しない理由] いつ利上げ?円安の利点,欠点,影響は?|消費者経済総研|2023年11月5日
■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 リモートでの出演・取材にも、対応しています  消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸 ■最終更新日:2023年11月05日 datemodified":"2023-11-05 本ページは、修正・加筆等で、 上書き更新されていく場合があります。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆であることを念頭に置いて下さい。 本ページ内容に関しては、自らの責任において対応して下さい。 また「免責事項」をお読みください ■引用 皆さまに、本ページの引用や、 リンク設定などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件 をご覧下さい。 |
- ■日銀 解説|筆者(松田)のTV出演
- 日銀に関する解説・提言でのTV出演実績。
「フジテレビ・めざまし8」に、
「消費者 経済 総研」の 筆者(松田)が生放送に出演。
「日銀 黒田総裁の 値上げ許容」 発言等を、解説。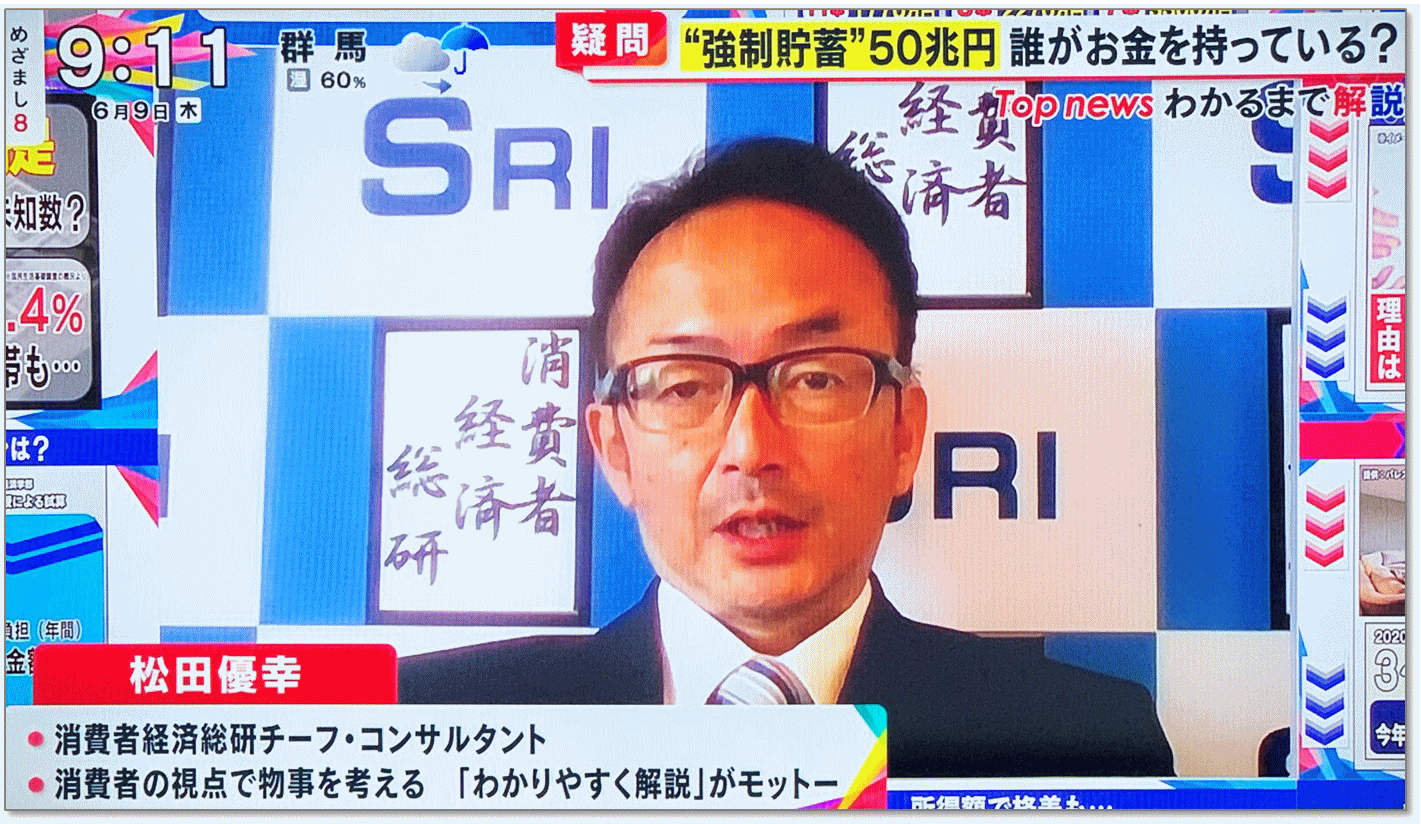
2022年 6月9日 放送 画像出典:フジテレビ
- ■ はじめに 「 利上げ しない 理由 」
- -- 消費者 経済 総研 --
◆日銀が、利上げぜす、緩和継続する 理由とは?
なぜ日銀は、利上げを、しないのか?
▼低迷脱却を、邪魔しないため
・低金利の継続:景気を刺激し、景気を下支えする
・金利の引上げ:経済を冷やし、景気の過熱を防ぐ
今の日本は、
「 失われた 30年 」 からの脱却のチャンスにある。
ここで、利上げを、すると、
その脱却の力を、失わせてしまう。
▼物価高だが、金利が原因ではない
2023年は、物価上昇率は、2%超だ。
だが、景気過熱 ( 需要 > 供給 ) が、原因ではない。
戦争由来の 「 原油高 」 の影響が、大きい。
つまり、海外原因の 「 コスト牽引 」 のインフレだ。
日銀が利上げしても、
停戦にならないし、原油価格は低下しない。
▼日銀が、利上げを、するには?
「 利上げをする 」 には、具体的には、下記が必要だ。
▼A インフレが、
コスト牽引ではなく、需要牽引 になること。
▼B インフレ率が、
持続的・安定的に、2% になること。
▼C 賃金UPを、伴う物価上昇であること。
賃金上昇率 X%> 物価上昇率 2%に、
なるのが、目標だ。
例えば、賃金上昇率 3% > 物価上昇率 2% とか
▼ ①: A Bのインフレでは?
現在は、CPI の上昇率は、2%超だが、
需要牽引 ではなく、コスト牽引 なので、だめだ。
なお、日銀は、下記の呼び方を、している。
コスト牽引 の力を → 「 第1の力 」
需要牽引 の力を → 「 第2の力 」
第1の力(コスト牽引)ではなく、
第2の力(需要牽引)で、2%超に、なる必要がある。
▼ ②: C の賃金では?
来年度の賃金水準は、まだ不明だから、
日銀は、政策変更できない。
上記の①②両方の理由から、緩和は継続が、正解だ。
私(松田)と、植田総裁の考えは、同じだ。
「 総裁と同じだと、威張りたい 」 のではない。
マクロ経済学の視点では、
現在の政策の継続が、当然だからだ。
マクロ経済学の主な政策は、下記2点だ。
「 雇用 」 と 「 物価 」 だ。
ア 雇用を、よくする事 (失業減、賃金UP3%等)
イ 物価を、適切な水準に、安定させること(2%)
今、金利を上げたら、、
ア 雇用には、マイナスに、働き、
イ 物価2%達成に、マイナスに、なってしまう。
利上げ、つまり、緩和修正などしたら、
経済を、ダメにしてしまう。
「 利上げ → 経済へ、ダメージ 」 のメカニズムは、
下記の別ページに、移動して、ご覧頂きたい。
( 移動後に、「 ダメージ 」で、ページ内検索 )
「 日銀次期総裁 植田和男氏 政策 」
- ■Vol.7 10/30の 日銀会合
日銀の微調整は、不要だった?
日銀の会合の結果の発表が、10/31 (火)にあった。
結果は、下記だった。
「 粘り強く、緩和を、継続する 」
具体的には、下記を継続だ。
・短期の 政策金利を、 マイナス0.1%
・長期の 政策金利を、 0%程度
▼微調整は?
基本方針は、緩和継続だったが、「微調整」があった。
長期の政策金利の水準は、0% 程度 だが、
その 「 程度 」 が、下記のように、変更になった。
変更前:変動幅の上限は、 1%
↓
変更後:変動幅の上限は、 1%をメド
▼ 「 メド 」 が 付いた理由は?
今回は、「上限は、1%をメド」と、「メド」が付いた。
前回の会合では、厳格に1%までに、抑えるとした。
今回は、「1%を多少超えることも、許容」となった。
★1%超を、許容した理由は、何か?
あなたは、1分間、考えて頂きたい。
↓
厳格に1%までに抑えると、副作用が大きいからだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆副作用とは?
1%までに抑える副作用を、解説していく。
その前に、債券(社債と国債)を見ていく。
▼借金 と 社債
企業の資金調達の中で、
「 お金を 借りる 」 方法として、下記がある。
① 銀行から、借金する
② 社債を、発行する
「 ① 銀行から借金 」 するは、
イメージしやすいので、説明不要であろう。
▼②の社債 とは?
社債とは、企業が発行する債券だ。
この債券は、借用証書を、意味する。
「 企業A社は、Bさんから、〇〇円を借りた。
〇〇年後に、返済する。
それまでの間、〇〇%の利子を払う 」
社債は、上記の内容が、定められた債券だ。
「①の借金」の場合は、
A社と銀行とでの、1対1での関係が多い。
その銀行に、主導権が握られることは、多いだろう。
社債では、
お金を借りるA社が、主体的に、下記を決められる。
・返済期間:〇〇年
・利子率:〇〇%
・集めたい額:〇〇円
①借金の場合は、「お金を、貸す・借りる」の関係だ。
②社債の場合も、同じだ。
だが、②社債では、
社債という債券を、企業A社が、販売する。
お金の貸し手は、それを買う。
▼例えば、過去のソフトバンクの社債では
・返済期間 : 7年
・利 子 率 : 2.03%
・集める額 : 4000億円
・一口単位 : 100万円
Bさんは、ソフトバンク社債を、
100万円で買って、同社へ100万円を、渡す。
Bさんは、100万円を、同社へ貸した状態になる。
この社債を買った人は、金融市場で、
返済期間の途中でも、売却することができる。
ソフトバンクの社債の募集ページ(過去事例)は、
わかりやすい内容に、なっている。
▼YCCの副作用とは?
YCCとは、
イールド・カーブ・コントロールの略語。
長期の金利の操作と、短期の金利の操作のことだ。
だが、最近は、
長期(10年物)の国債の金利を、下げることに、
限定して使われることが増えた。
既述の通り、日銀は、下記の金利誘導をしている。
・短期の政策金利を、マイナス0.1%
・長期の政策金利を、0%程度
▼長期の政策金利を、下げる
長期金利の代表的な10年物国債の金利を、
日銀が、意図的に、下げている。
この日銀の政策で、10年国債の金利が下がる。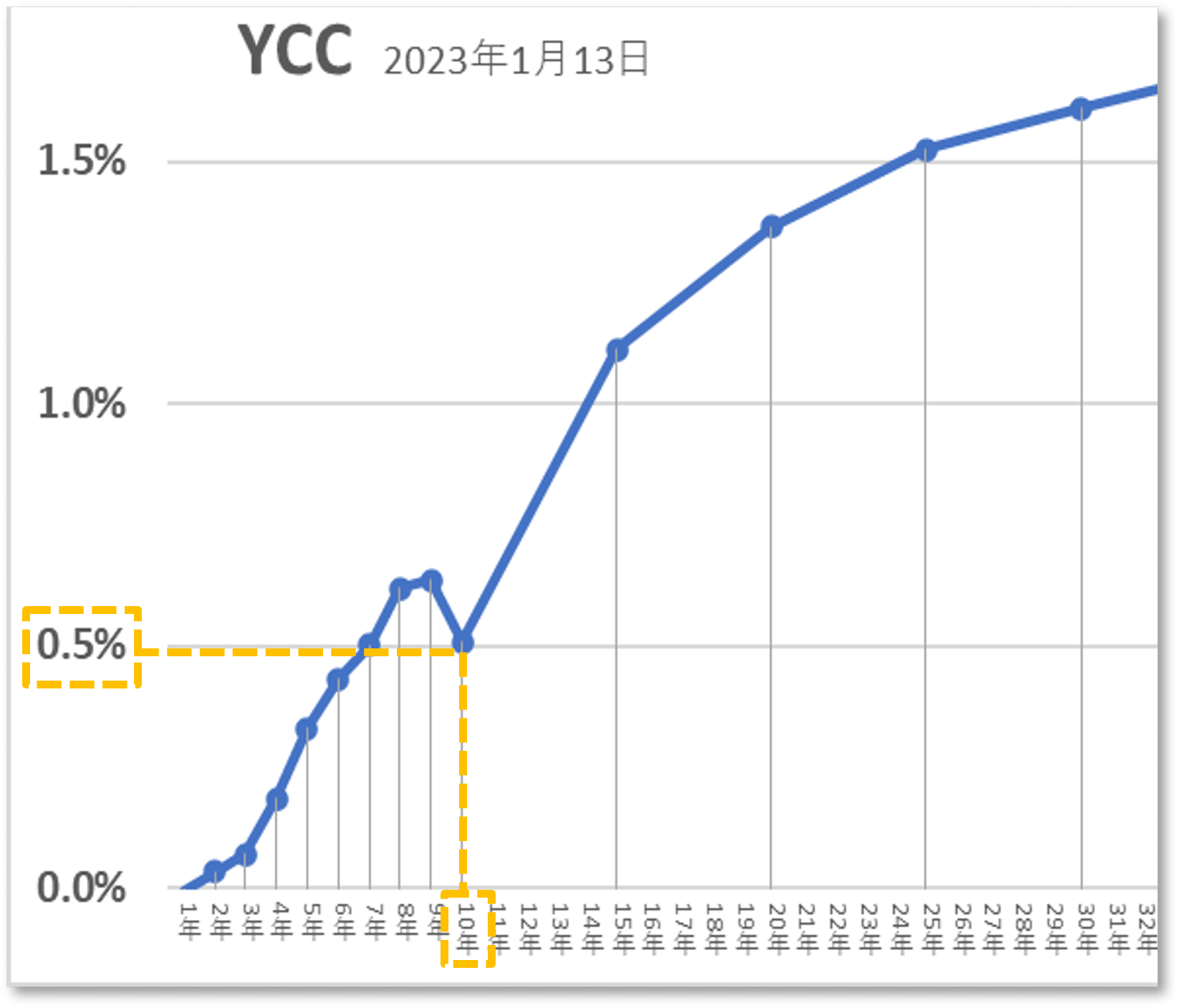
-- 消費者 経済 総研 --
Q:前項は、「 YCC 」だった。
では、「 YC 」 イールドカーブとは、何か?
↓
A:
・イールド = 金利
・カーブ = グラフの図の中の「曲線」
下図の青線が、イールドカーブ(金利曲線)だ。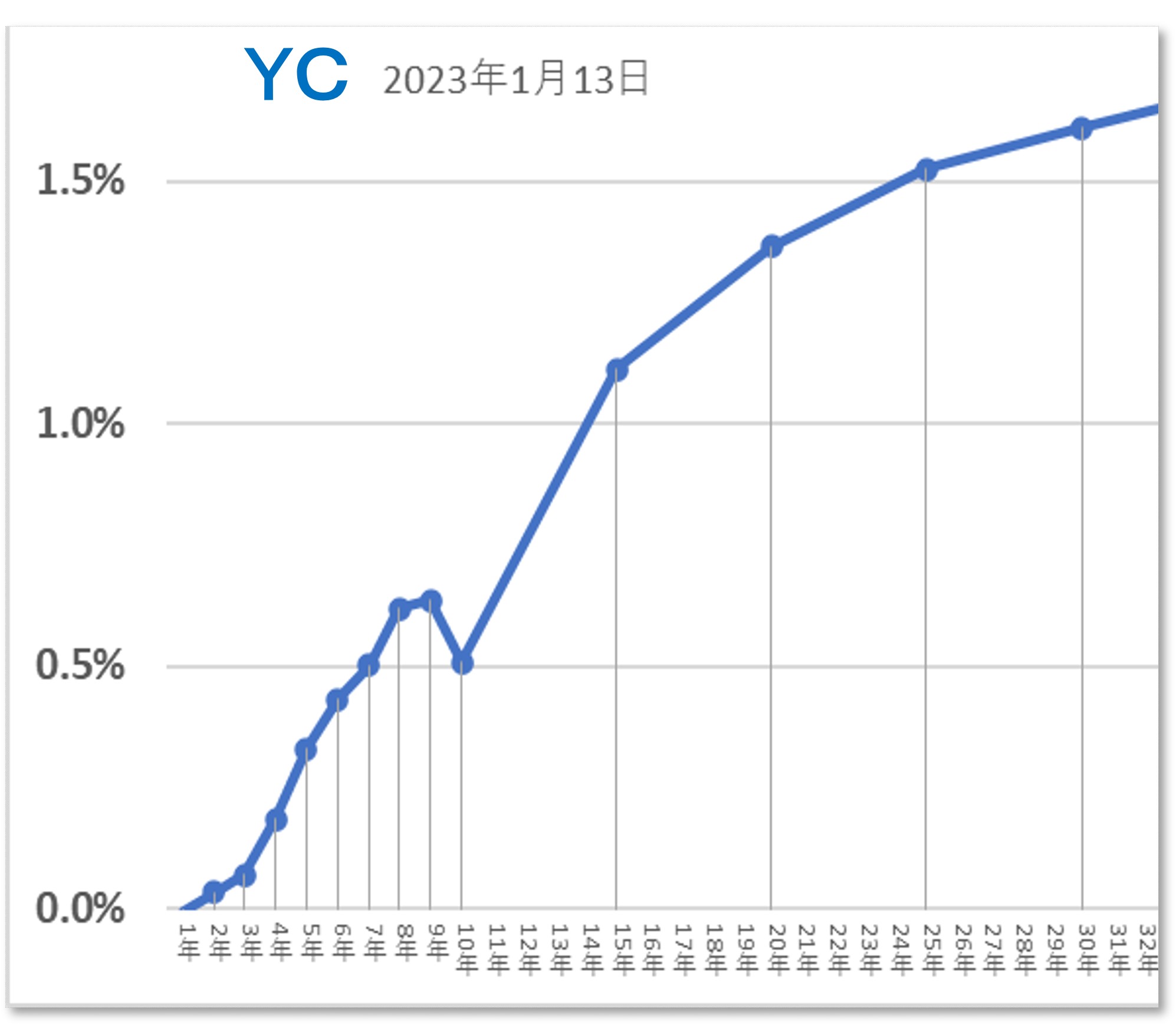
短期の金利よりも、長期の金利の方が、
利回りが高い。
その理由の簡単な理解は、下記だ。
短期:
1年で返してもらえるなら、金利が低くてもいいや
長期:
返済が20年後なのは、心配だ。
金利が低いなら、貸さない。
こうして、
短期よりも、長期の方が、金利が高くなる。
「YC」 ではなく、 「 YCC 」の最後のCは、
コントロールのCだ。
金利(イールド)の曲線(カーブ)を、
操作(コントロール)することだ。
下図の通り、
10年限の金利が、引き下げられていた。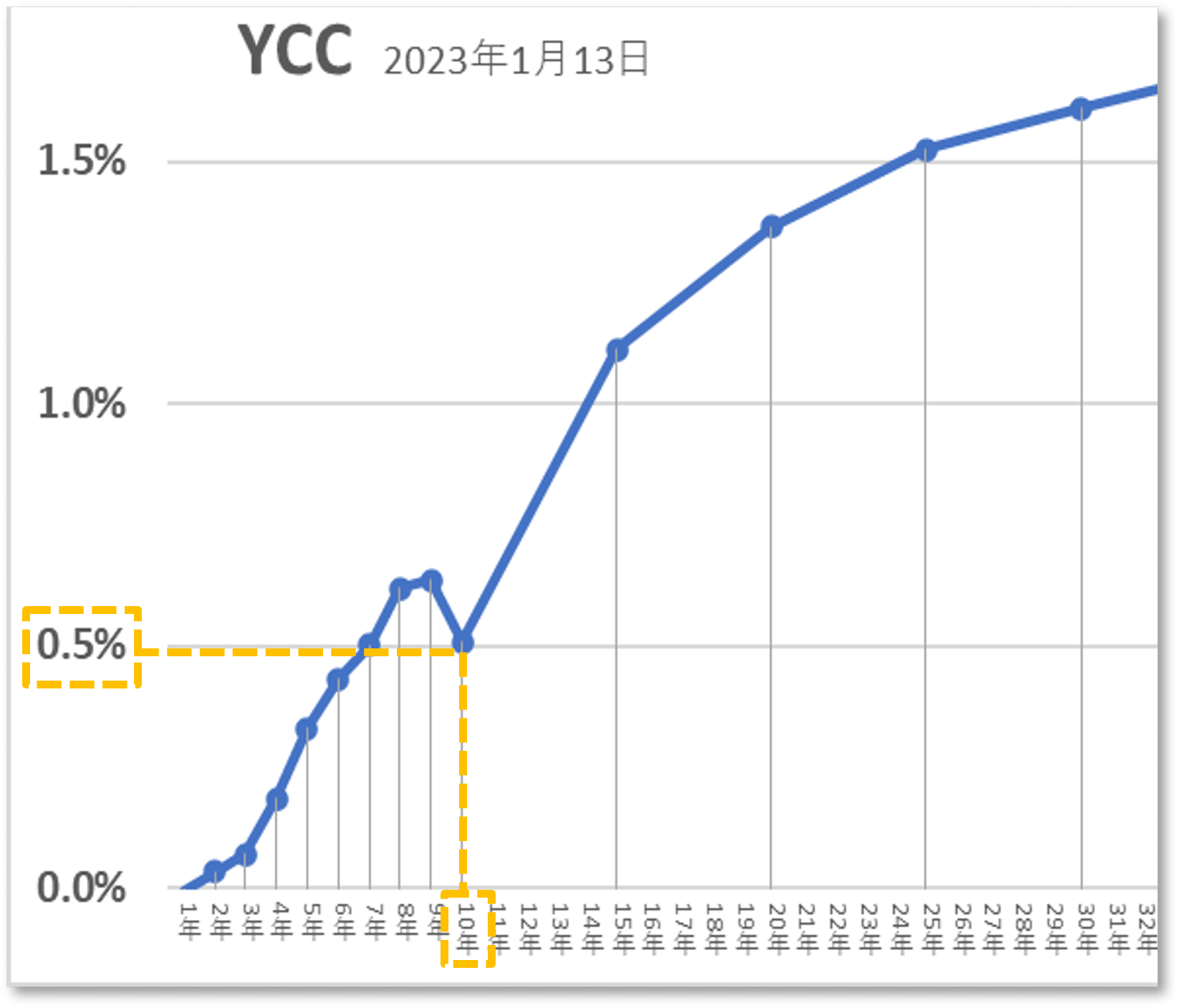 ※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成
※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成
※出典:財務省|国債金利情報
黒田体制での10年金利の誘導目標は、
ゼロ% ( ±0.5% ) だった。
つまり、「 -0.5% から+0.5%まで 」 だ
変動幅が、 ±0.5% の範囲内に、収まるように、
日銀が、金利を操作した結果が、上図の歪みだ。
-- 消費者 経済 総研 --
▼国債と社債の関係
国債の金利は、社債の金利の基準になる。
国債金利のうち、10年国債だけが不自然に低いと、
10年物の社債を、扱う人は混乱する。
10年金利が、不自然な金利になるのが、
副作用の1つだ。
社債の発行が、やりにくくなり、
社債の機能が、低下する
これが 「 社債市場の 機能度の 低下 」
と言う副作用だ。
▼社債以外に、国債も
前項は、社債における副作用だった。
YCCは、国債にも、副作用がある。
日銀が、10年国債金利を、無理やり下げることで、
民間の金融機関は、取引が、やりにくくなる。
10年国債が、思い通りの額や利率での取引が、
できない場合があるからだ。
民間の金融機関で、国債を扱う人も、困るのだ。
これが、「 国債市場の 機能度の 低下 」である。
社債と国債をあわせて、
「 債券市場の機能度の低下 」という副作用だ。
「副作用=機能度の低下」は、
下図の通り、機能度は悪化していた。
下図は、日銀の 機能度 判断DI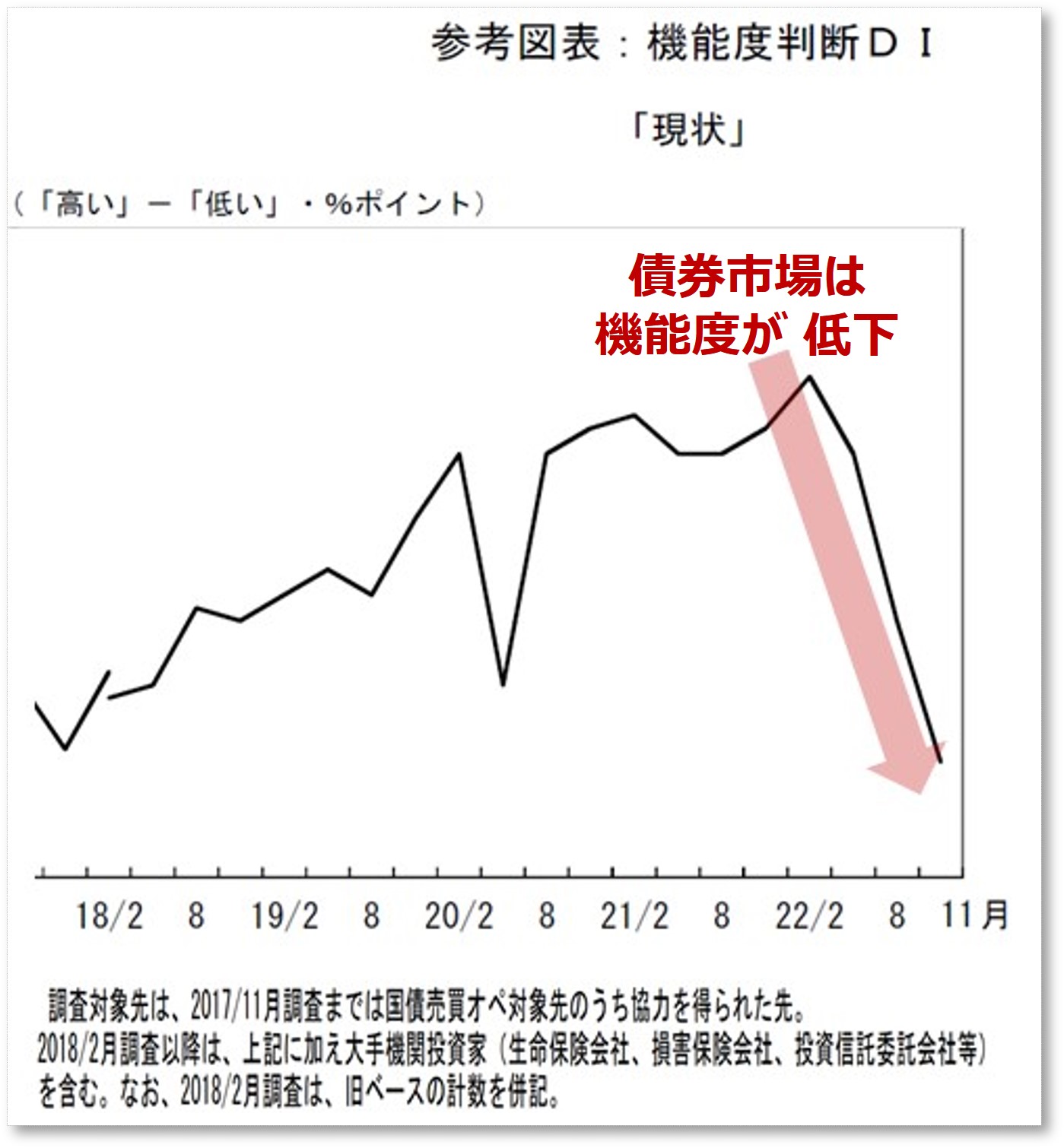 ※図は、下記日銀資料から不要部分を削除し抜粋した
※図は、下記日銀資料から不要部分を削除し抜粋した
※出典:日銀|債券市場サーベイ(2022年11月調査)
そこで、黒田総裁体制の終盤から、
YCCの変動幅を広げて、YCの歪みを小さくした。
▼利上げか?
2022年12月に、黒田体制の日銀は、
10年国債の金利を、 0.25% → 0.5% に、広げた。
「 利上げだ 」 「 金融緩和の出口 」 と言われた。
だが、それは違う。
利上げではない。緩和は、継続している。
これは、単なる副作用の排除だ。
▼副作用大きいなら、やめれば?
植田総裁は、総裁に着任する前から、
YCCの副作用を、懸念していた。
もちろん、前任の黒田総裁も、そうだった。
では、YCCのメリット・デメリットは?
メリットは、金利水準の低下だ、
デメリットは、既述の副作用だ。
メリットと、デメリットは、どちらが、大きいか?
▼諸外国は?
アメリカも、かなり前には、YCCを、やっていた。
1940〜1951年のことだ。
だが、今は、やっていない。
近年では、オーストラリアの中銀が、やっていた。
だが、デメリットがあるので、やめてしまった。
最近の世界標準は、「 長期金利の操作 」 なしの
「 短期金利の操作 」 がメインだ。
▼では、なぜ日本だけ?
デフレ脱却のために、前任の黒田総裁は、
とことん金融緩和を、やることとした。
「大胆な緩和」や、「異次元の金融緩和」と言われた。
▼大胆、 異次元 とは?
大胆、異次元、つまり、
「 やれる事は、なんでも、やる 」 ということだ。
黒田前総裁は、
副作用・デメリットの懸念があっても、トライした。
▼非・伝統手法 とは?
「 伝統的 手法 」 とは、他の国の中央銀行が、
今までやってきた、標準的な金融政策のことだ。
「非・伝統的 手法」とは、
他の中銀が、あまり採用しなかった政策の事だ。
黒田前総裁は、「 伝統的手法 」に加えて、
「 非・伝統的手法 」 にも、トライしたのだ。
YCCは、「 非・伝統的手法 」 の1つだ。
▼他にも、「非・伝統的手法」が、ある?
日銀は、金融政策として、「 株の購入 」もしている。
購入しているのは、正確には、株その物 ではなく、
上場している株のファンドのETFだ。
過去号で、筆者(松田)は、カブ活デビューには、
日経平均ETFが良い、との話をした。
※ 「 カブ活 」 とは、株式投資の活動のこと。
日銀は、その日経平均ETFを、買っている。
▼日銀が、ETFを買う メリットは?
日銀がETFを買えば、
その購入代金が、株式市場に行く。
日銀(公的セクター)から、市場(民間セクター)へ
これで、民間セクターのお金が増える。
日銀が買うETFは、誰が売るか?
民間の個人投資家が、売った分も、含まれる。
個人投資家のお金が増える
↓
個人(消費者)が、買い物を増やせる
↓
買い物の需要が増える
↓
需要増→物価UPで、デフレ脱却に寄与する
中央銀行がETFを買うというこのやり方は、
日銀独自の手法だ。
これも、非・伝統手法だ。
株式市場は、本来、
民間セクターによる自由な売買市場であるべきだ。
公的セクターが、介入すべきではない。
だが、公的セクターの日銀の介入で、
株価が支えられるのは、日本の投資家にプラスだ。
日銀のETF購入に、反対する人は少ない。
また、その購入による副作用は、目立っていない。
よって、ETF購入は、あまり問題視されていない。
日銀の 緩和政策 には、
株 ( 正確には ETF ) の購入 もある
これを、「 質的 緩和策 」 という。
この質的緩和策には、副作用は顕在化してない
▼予想が、はずれる日銀
日銀の物価予想は、3ヵ月に一度、発表される。
発表のたびに、その予想値を、変更した。
つまり、日銀の物価予想は、毎回ハズレているのだ。
日銀会合の会見では、
「 不確実性 」 の言葉が、多発している。
予測が当たらない事を、「不確実性が高い」とする。
中央銀行は、将来予想をするが、予想屋ではない。
金融政策は、直近の経済データを元に、立案する。
直近データが中心だが、将来見通しも、考慮する。
でも、重要なのは、
「 直近データ 」 > 「 将来予想データ 」 だ。
よって、中銀は、「 予想は 得意ではない 」 のだ。
なお米国の中銀FRBも、予想を外してきている。
▼今回の微調整は、不要だった?
前回・9月の日銀会合では、下記の微調整があった。
10年金利の変動幅は、
±0.5%とし、 念のための「 外枠 ±1% 」を設けた。
「 外枠の1% 」 には、達しないと、日銀は見ていた。
だが、日本の10年国債金利は、上昇を続けた。
日本の国債金利は、
10月26日(木)には、0.89%まで、上昇した。
-- 消費者 経済 総研 --
★日本の国債金利が、上昇した理由は、〇〇だ。
〇〇とは、何か?
借金大国・日本の 財政の破綻の懸念か?
あなたは、1分間、考えて頂きたい。
↓
違う。 財政破綻の懸念ではない。
日本の金利は、
米国の金利につられて、上がっただけだ。
日銀が設定した、変動幅の許容上限は、±1%だ。
10月26日に、0.89%まで上昇し、1%に接近した。
日銀は、1%を超えたら、1%以下に、厳格に下げる。
すると、既述の通りの副作用が発生する。
その副作用は、「債券市場の機能度の低下」だった。
だが、筆者(松田)は、
「 1%超えは、無い 」 と見立てていた。
▼アメリカの金利は?
米国の10年物の市場金利は、上昇を続けた。
23年9月から、上昇ピッチが、加速した。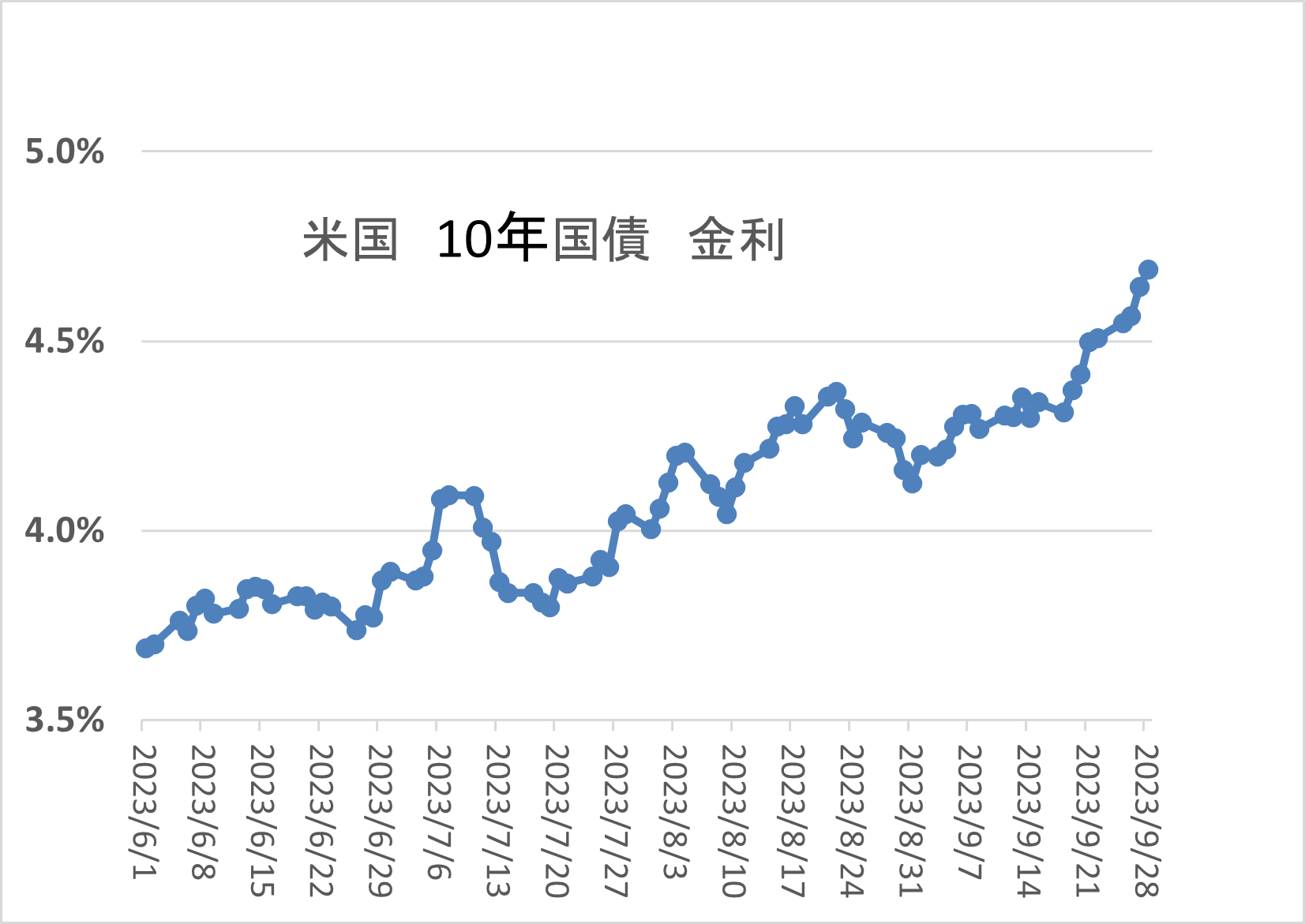
上昇が加速した理由は、
米国FRBが、タカ派 の姿勢を、強めたからだ。
だが、筆者(松田)は、5%に、タッチしたら、
反転下落すると、予測していた。
国債ショートポジション(空売り)が、溜っていた。
よって、踏み上げ反転すると、読んだからだ。
また、「5%は、心理的 節目ライン」でもあるからだ。
筆者(松田)の予測通り、
米国の10年市場金利は、反転下落した。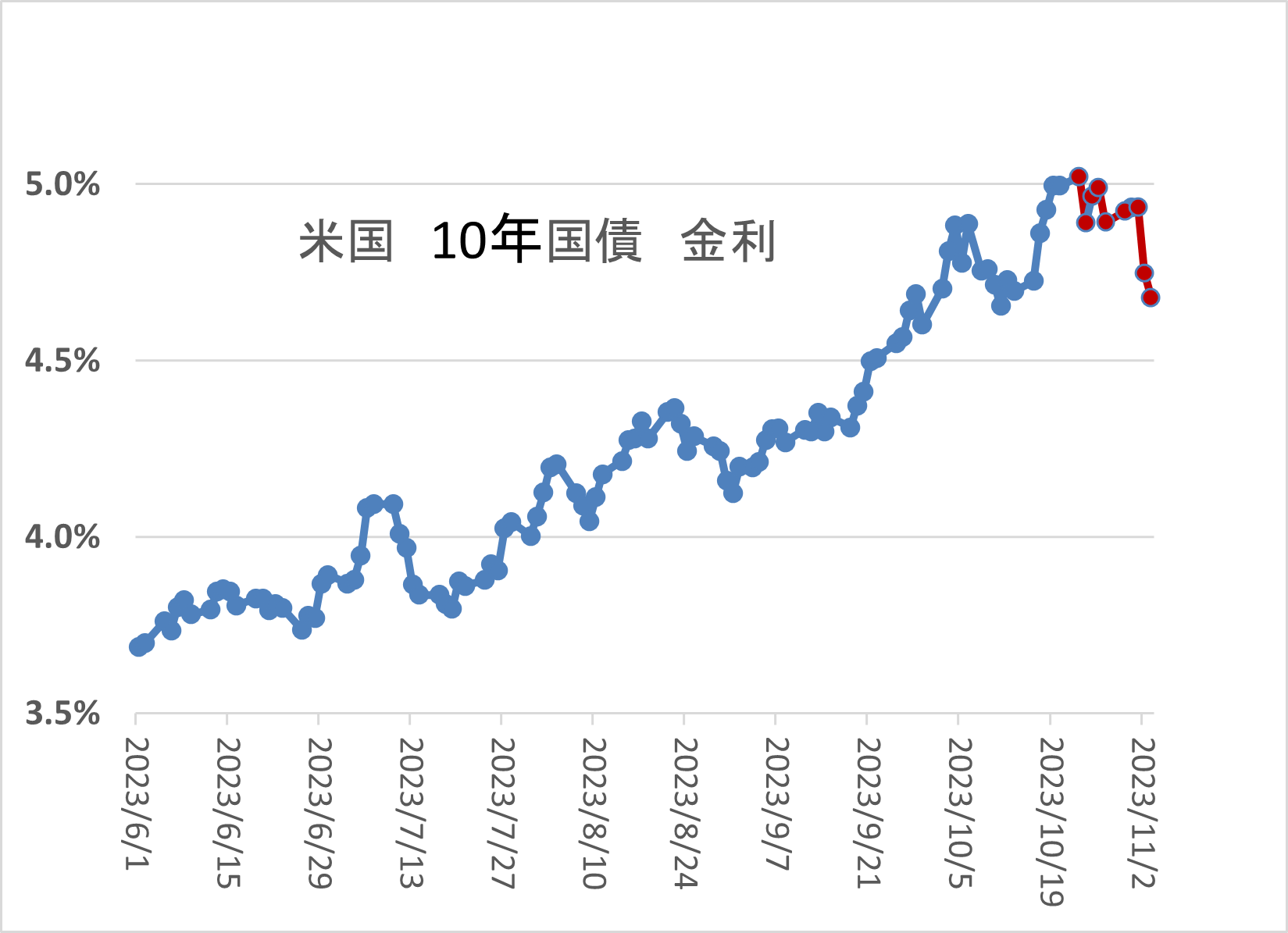
▼日本の市場金利は?
日本の国債金利は、
10月26日(木)には、0.89%まで、上昇した。
米国金利が反転下落すると、予想していたので、
日本の金利も、反転下落すると、私は予想していた。
日本の金利も、つられて、1%に達せず、下落した。
筆者(松田)の予想通りだった。
「 日本の10年金利が、 1%を超える 」 と、
日銀は、予想していたのだろう。
だから、日銀は、
変動幅の上限を、下記の様に、変更したのだろう。
変更前:変動幅の上限は、1%
↓
変更後:変動幅の上限は、1%をメド
( 1%超も、容認 )
日本の10年市場金利は、1%にタッチしなかった。
日銀は「1%超も容認」を、しなくてよかったのだ。
「 必要のない 微調整 」 を、日銀は実施したのだ。
▼筆者(松田) 会合前に、日銀政策を予想
既述の通り、筆者(松田)は、日本は、1%に至らず、
米国金利と共に、反転下落と予測していた。
よって、筆者(松田)の10月29日の事前の予測は、
「 10月の日銀会合では、変更なし 」 だった。
だが、日銀は、「 1%を 突破する 」 と思い、
変動幅の枠を、拡大してしまったのだ。
その時、その時の、経済環境で、最新の判断にする
というアップデートは、もちろん良い。
だが、変更・修正を、繰り返すと、
日銀の信頼性を、下げてしまう。
▼時間軸政策 ( フォワード・ガイダンス )
非・伝統的な金融政策には、「時間軸政策」もある。
時間軸政策 ( フォワード・ガイダンス )とは、
将来に向かって、政策を継続すると、宣言する事だ。
これにより、市場参加者が、
日銀政策への信頼・安定性を、感じる事ができる。
現在~将来にわたる時間軸で、
政策の効果を高め、安定化させる効果があるのだ。
簡単に言うと、下記だ。
「 ころころ、変わらないから、安心して 」
日銀が、コロコロ変えると、
市場は、「 また 今後も 変わる 」と、考えてしまう。
日銀が、政策方針を、打ち出しても、
市場は、それを信頼せず、別の思惑で動いてしまう。
つまり、「 日銀が考える 政策方針 」 とは別に、
「 市場は、違う考え・行動 」 を、とってしまう。
日銀が低金利政策を、継続しても、
「 コロコロ変わるから、次回は利上げか? 」
などの日銀の方針とは、違う動きが、出てしまう。
日銀:低金利を、継続させたい
市場:金利上昇側の行動
日銀の考えとは、別の行動を招く懸念がある。
繰り返しになるが、日本は、1%に達する前に、
反転下落なのだから、微修正すら不要だった。
会合前の10月29日での、
筆者(松田)の予測は、下記だった。
日本の金利は1%に達せず、反転下落するから、
変動幅の枠の拡大は不要
よって、微修正すらなく、
前回の9月会合と同じ。
▼日銀よりも、FRBに注目を
日銀よりも、FRBの方が重要だ。
カブ活を、やっている人なら、知っている。
円安の原因は、日米の金利差だ。
日本の金利が、変動しても、その変動幅は小さい。
米国FRBは、政策金利を、
0%から、5.25%までと、大幅に引き上げた。
円安は、日米の金利差で、決まる。
円安になったのは、「日銀のせい」と言う人がいる。
違う。 円安の原因は、「米国FRBの利上げ」だ。
そもそも、円安は悪い事ではなく、日本にプラスだ。
日銀の計量分析では、
「円安は日本にプラス」 との検証結果が、出ている。
「 内閣府 」 の計量分析でも、
円安は日本にプラスとの検証結果が、出ている。
計量分析なんて、面倒なこと言わなくても、
足し算・引き算、掛け算・割り算の単純計算でも、
円安は日本にプラスだとわかる。
「 円安は、日本にプラス 」 の解説は、
本ページ内に、掲載中なので、参照して頂きたい。
本稿の下段に、そのリンク先を、掲載してある。
円安は、日銀が原因ではなく、FRBが原因だ。
世間、特にメディアは、日銀に関心が寄りすぎだ。
筆者(松田)は、毎日、朝一番に、確認することは、
米国の金融経済のデータだ。
・株価 ( ナスダック、S&P500、ダウ )
・金利 ( 米国2年債、米国10年債 )
この2件を、最重視している。
カブ活やっている人ならば、同じだろう。
なお、その後に、
シカゴやシンガポールの日経先物の値を見る。
中央銀行の話では、日銀の動向よりも、
米国FRBの動向の方が、注目される。
▼カブ活で、詳しくなろう
カブ活をやれば、金融や、経済に、詳しくなる。
日本の世の中の金融経済に、関する言説が、
いかに、でたらめで、いい加減かを、知るだろう。
金融経済に詳しくなれば、誤解・誤報を見抜ける。
下記のvsでは、前者は、いずれも、誤解・誤報だ。
つまり、いずれも、後者が正解だ。
日銀の緩和政策は、けしからん
vs
日銀の緩和政策は、継続必要
国の借金 けしからん
vs
国の借金 問題なし
借金大国・日本は、 デフォルトや、破綻の懸念
vs
自国通貨建ての日本国債は、デフォルトしない
円安は 日本経済に マイナス
vs
円安は 日本経済に プラス
▼新NISA
新NISAを、きっかけに、
カブ活デビューする人は、急増するだろう。
カブ活すれば、金融経済の知識が増える。
日銀やFRBの会合を、
今まで以上に、関心を持って見る事になるだろう。
そして、「誤解・誤報が多い」と知るだろう。
-- 消費者 経済 総研 --
◆本ページの続きは?
次項から、
連載シリーズ・日銀の決定会合 Vol.1~Vol.6。
長文になるので、
「 知りたいこと 」 を、キーワード検索で、
ページ内検索を、お勧めする。
「円安は、日本にプラス」の件も、下段にある。
「 計量モデル 」 で、ページ内検索
計量分析ではなく、足し算などでの単純計算は、
「 簡単な計算 」 で、ページ内検索

- ■Vol.6 7/28の決定会合で〇〇に?
記者会見後に更新 → 翌日 再更新
- 2023年7月27~28日に、
日銀の政策決定会合が、行われた。
その会合の後に、〇〇が、発表された。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:過去も、日銀会合の後は、
「 誤解・誤報 」 が、飛び交っていた。
今回は、どうなったか?
↓
A:毎度おなじみの 「 会合後の 誤解・誤報 」 は、
今回もあった。
誤解・誤報のうち、「 誤解 」の方を先に述べたい。
▼深夜2時から、9時の取引開始では?
7/28深夜2時 日経新聞「0.5%超え容認案」報道
で、株式市場は、取引開始から、大幅安へ。
タカ派的姿勢を日銀が示すと、市場は予想した。
日銀が、タカ派姿勢ならば、下記3つが起きる。
① 市場金利には、上昇圧力
② 株価には、下落圧力
③ 為替は、円高圧力
※②③の理由は、「 日銀総裁 」 のページ内で、
②は「株価」、③は「為替」で、ページ内検索
▼昼の 日銀資料の 公表後は?
7/28昼に、「当面の金融政策運営について」
の資料が、日銀から公表された。
その資料から、
「 日銀は、ハト派では? 」 と、株価上昇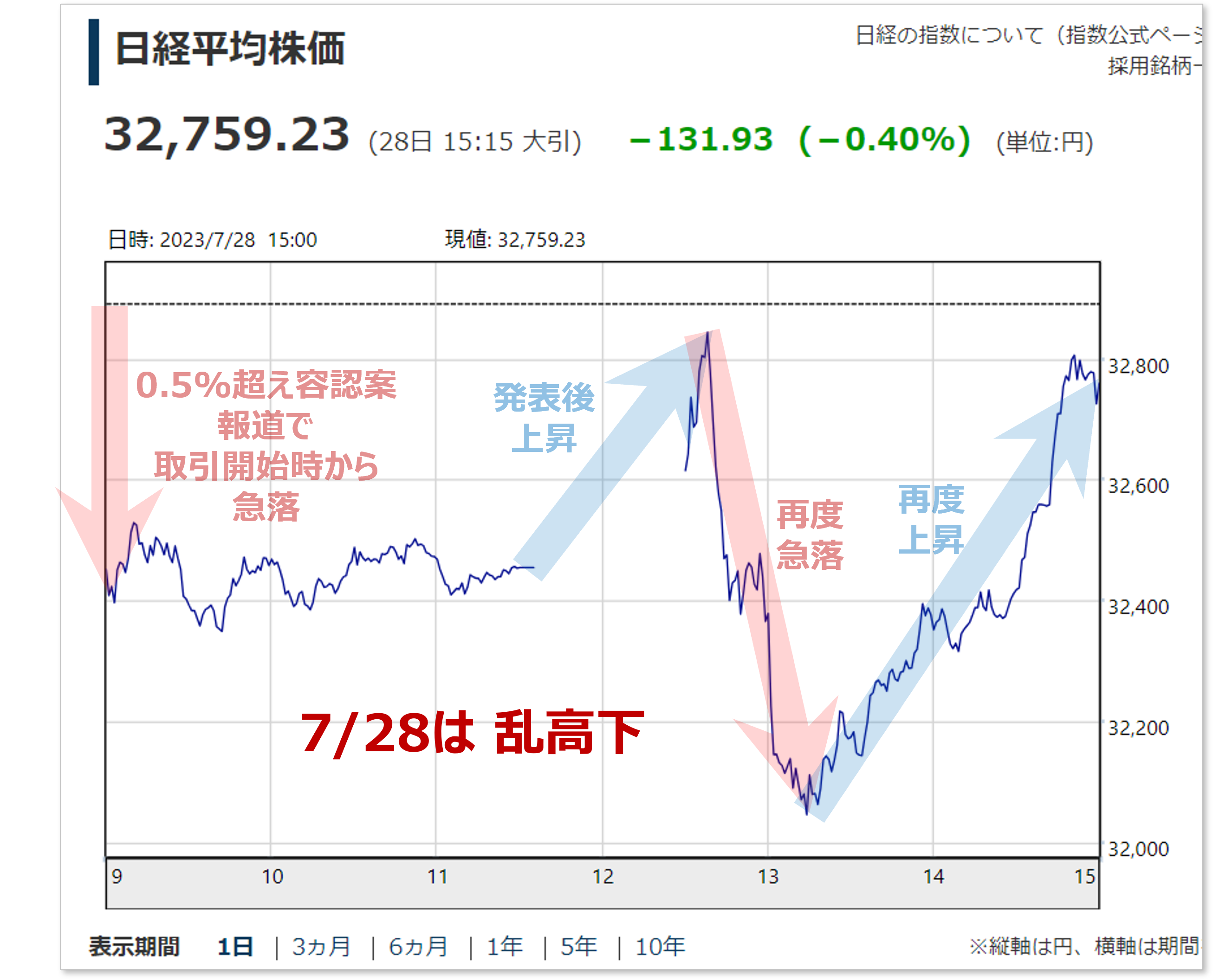 ※画像出典:日経平均株価:リアルタイム推移|日本経済新聞
※画像出典:日経平均株価:リアルタイム推移|日本経済新聞
▼15時の 取引終了 までは?
「日銀 タカ派よりだ」 いや 「日銀 ハト派よりだ」
日銀姿勢への解釈が、分かれ、乱高下となった。
こうして、誤解もあって、市場は混乱した。
▼15:30~の総裁会見・質疑応答の後では?
総裁会見・質疑応答で、
日銀の政策方針・姿勢は、明らかとなった。
それにもかかわらず、お約束の「誤報」はあった。
-- 消費者 経済 総研 --
◆何が誤解・誤報で、 何が正解なのか?
◇◇◇◇ は、 誤解・誤報で、
□□□□ が、 正しい解釈だ。
これらは、本稿の後半で、解説してある。
その前に、「そもそも〇〇 とは?」 を掲載する。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:そもそも、「 政策決定会合 」 とは、何か?
↓
A:金融政策の方針を、審議・決定する会合だ。
日銀にて、開催される。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:何が決まり、何が発表 されたのか?
↓
A:2023年7月28日(金)に、下記が実施された。
① 当面の金融政策の方針の発表
② 総裁の記者会見
③ 展望レポートの発表
※他にも発表文書等があるが、主な3件を列記した。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:上記の ①②③ の内容は、何か?
↓
A:
① 当面の金融政策の方針の発表
日銀決定会合で、決定された内容が、
公表された。 (4ページの資料にて)
② 総裁の記者会見
決定会合で、決まった方針を基に、質疑応答
③ 展望レポートの発表
今後の経済・物価の見通しが、11ページの
レポートで発表された。
展望レポートは、3ヵ月に1回、公表される。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「①金融政策の方針」は、具体的には、何か?
↓
A:今後の政策の金利を、どうするかだ。
金利を、上げるのか?下げるのか?維持か?
ということだ。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:どんな方針が、示されたのか?
↓
A:
・短期の政策金利:-0.1%のままで、変更なし
・長期の政策金利: 0%程度のままで、変更なし
・長期金利の変動幅:±0.5%のままで、変更なし
ここまでは、いずれも、事前予想通りの、
現状維持で、変更なしだ。
ただし、付加された補足内容がある。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:付加された補足内容とは、何か?
↓
A:
▼前回(6月の会合)
・長期金利の変動幅を「±0.5%程度」
・10年物国債の指値オペは、0.5%で実施
▼今回(7/28会合)
・長期金利の変動幅を「±0.5%程度」を目途とし、
より柔軟に運用
・10年物国債の指値オペは、1.0%で実施
-- 消費者 経済 総研 --
Q:この件を、日銀はどう説明したか?
↓
A:日銀は、下記の通り、説明している。
▼昼に公表された 「 当面の金融政策運営 」 では?
「柔軟化」によって、債券市場の機能への影響や、
金融市場のボラへの影響を、和らげる。
経済・物価の上振れが、続く際は、
実質金利の低下によって、緩和効果が強すぎる。
経済・物価が、下振れした際は、
長期金利が低下する事で、緩和効果が維持される。
※下記出典から、消費者経済総研が抜粋要約
※出典:日銀|当面の金融政策運営について
上記の日銀資料では、
誤解が、生まれるのは、しょうがない。
この少ない文字数の資料では、説明不足だ。
そこで、1時間の会見・質疑応答が重要だ。
▼その後の 会見 (15:30~16:30)では?
下段に、会見内容を、記載してある。
その前に、「そもそも 〇〇 とは?」 その2 として、
「 YC とは? 」 「 YCC とは? 」 を、記載しておく。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:そもそも、
イールドカーブ(YieldCurve)とは、何か?
↓
A:
・イールド = 金利
・カーブ = グラフの図の中の「曲線」
下図の青線が、イールドカーブ(金利曲線)だ。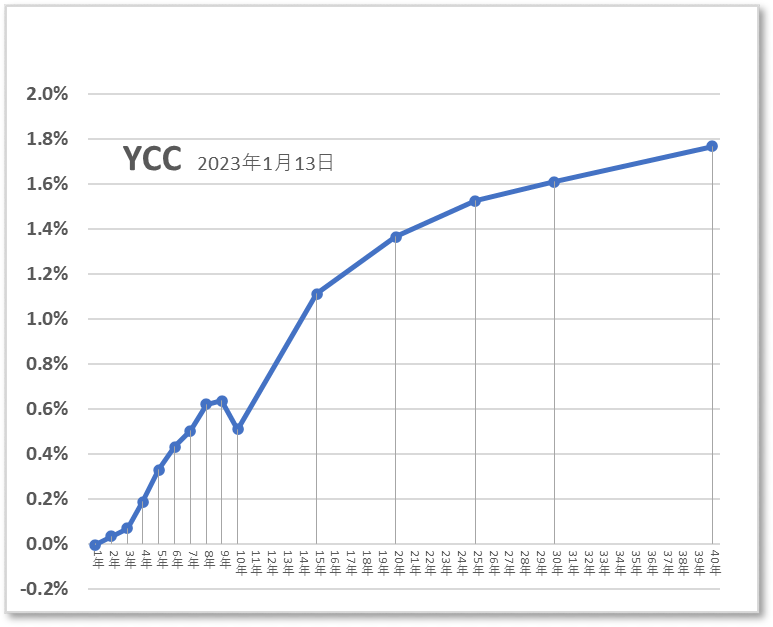
短期の金利よりも、長期の金利の方が、
利回りが高い。
その理由の簡単な理解は、下記だ。
短期:
1年で返してもらえるなら、金利が低くてもいいや
長期:
返済が20年後なのは、心配だ。
金利が低いなら、貸さない。
こうして、
短期よりも、長期の方が、金利が高くなる。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:YC ではなく、 「 YCC 」 とは何か?
↓
A:
Yield Curve Control
(イールドカーブ・コントロール)の略だ。
金利(イールド)の曲線(カーブ)を、
操作(コントロール)することだ。
▼日銀は、
「 YCC=長期金利と短期金利の操作 」としている。
▼世間は、
長期金利(10年金利)を、意図的に引き下げる事
だとして、言うケースが多い。
下図の通り、
10年限の金利が、引き下げられている。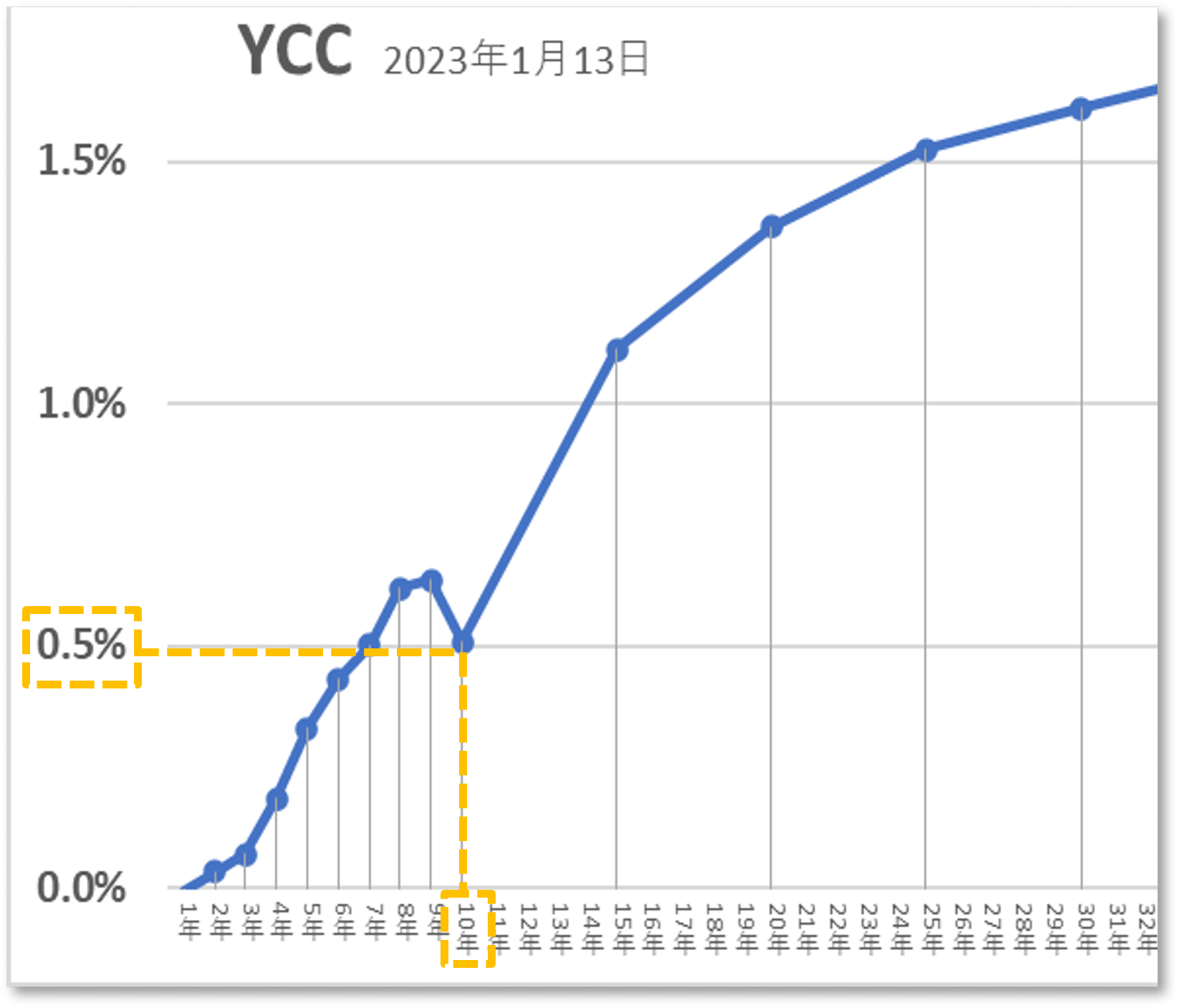 ※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成
※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成
※出典:財務省|国債金利情報
10年金利の誘導目標は、ゼロ% ( ±0.5% ) だ。
つまり、「 -0.5% から+0.5%まで 」 だ
変動幅が、 ±0.5% の範囲内に、収まるように、
日銀が、金利を操作した結果が、上図の歪みだ。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:YCCの 撤廃や修正 とは?
「 YCCの撤廃 」 とは、
この10年金利の引き下げ操作を、やめると言う事。
「 YCCの修正 」 とは、
変動幅を、±0.5%から、0.75%や1%へ拡大する事
-- 消費者 経済 総研 --
Q:今回は、YCCの修正なのか?
↓
A:
ここからは、7/28の15:30~の記者会見での
植田総裁の発言内容を記載する。
会見のライブ配信を見ながら、筆者(松田)が、
下記を速記した。 抜粋・要約・意訳である。
後日、議事録が掲出されたら、その議事録のリンク
を張るので、そちらを参照頂きたい
※追記:議事録|総裁定例記者会見
-- 消費者 経済 総研 --
◆植田氏の発言趣旨
10年金利の 「 上限キャップが、1% 」 については、
1%まで上がるとは、想定してないが、念のためだ。
▼YCC柔軟化のねらいは?
今回のYCCの柔軟化で、
物価の上方向・下方向の双方のリスクに対応する。
▼物価の下振れリスクは?
下方へのリスクが起きた際は、
YCCの機能が、自動的に発動する
(市場原理で、市場金利が低下するから)
下振れリスクは、現在のままで、効果を発揮する。
上振れリスクへの対処が、今回の柔軟化だ。
▼0.5%までの間と、0.5~1.0%の間での差は?
10年金利が、1%の所では、連続指値オペをやる。
キャップをはめ、1.0%を、超えないようにする。
0.5~1.0%の間では、
機動的に国債買入増、指値オペ、共担オペをやる。
投機筋への対処、スピード調整の意味もある。
▼柔軟化は、事前準備のため
今後の物価が、上振れするリスクに備えて、
あらかじめ事前の対策の準備が、 「柔軟化 」 だ。
後手になって、混乱や、副作用の増幅は、避けたい。
物価の上振れリスクが、顕在化した時に、
急に対策をやると、混乱してしまう。
急な対処は、
投機筋を呼び込み、益々、金利が上昇してしまう。
よって、対応の余地を、事前に広げたのだ。
今回の柔軟化は、「正常化への歩みだし」ではない。
YCCの持続性の維持や、投機の防止ためだ。
なお今回の柔軟化は、YCC修正かと言われれば、
そうだとも言える。
▼名目金利以外に、実質金利
( 実質金利 = 名目金利 - CPI上昇率 )
物価上昇局面では、
実質金利が低下し、緩和効果の効き目が強すぎる。
よって、その緩和効果は、余計に物価UPへ働く。
※上記の植田総裁発言は、
筆者(松田)の聞き取り速記による。
正確な発言内容は、後日掲出の議事録を参照。
※追記:議事録|総裁定例記者会見
-- 消費者 経済 総研 --
◆さらに わかりやすい 解説は?
上記の会見の内容でも、
わかりにくいと、感じる人も、多いだろう。
そこで、筆者(松田)による、
さらに わかりやすい解説を、後半下に記載した。
その前に、物価予想の変更を、記載する。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:短期金利、長期金利、長期金利の変動幅
の3点以外は、どうか?
↓
A:事前予想通り、
「 物価の見通しを 日銀が変更 」した
-- 消費者 経済 総研 --
Q:なぜ、日銀は物価見通しを、変えたのか?
↓
A:従来の日銀の物価見通しが、低すぎるからだ。
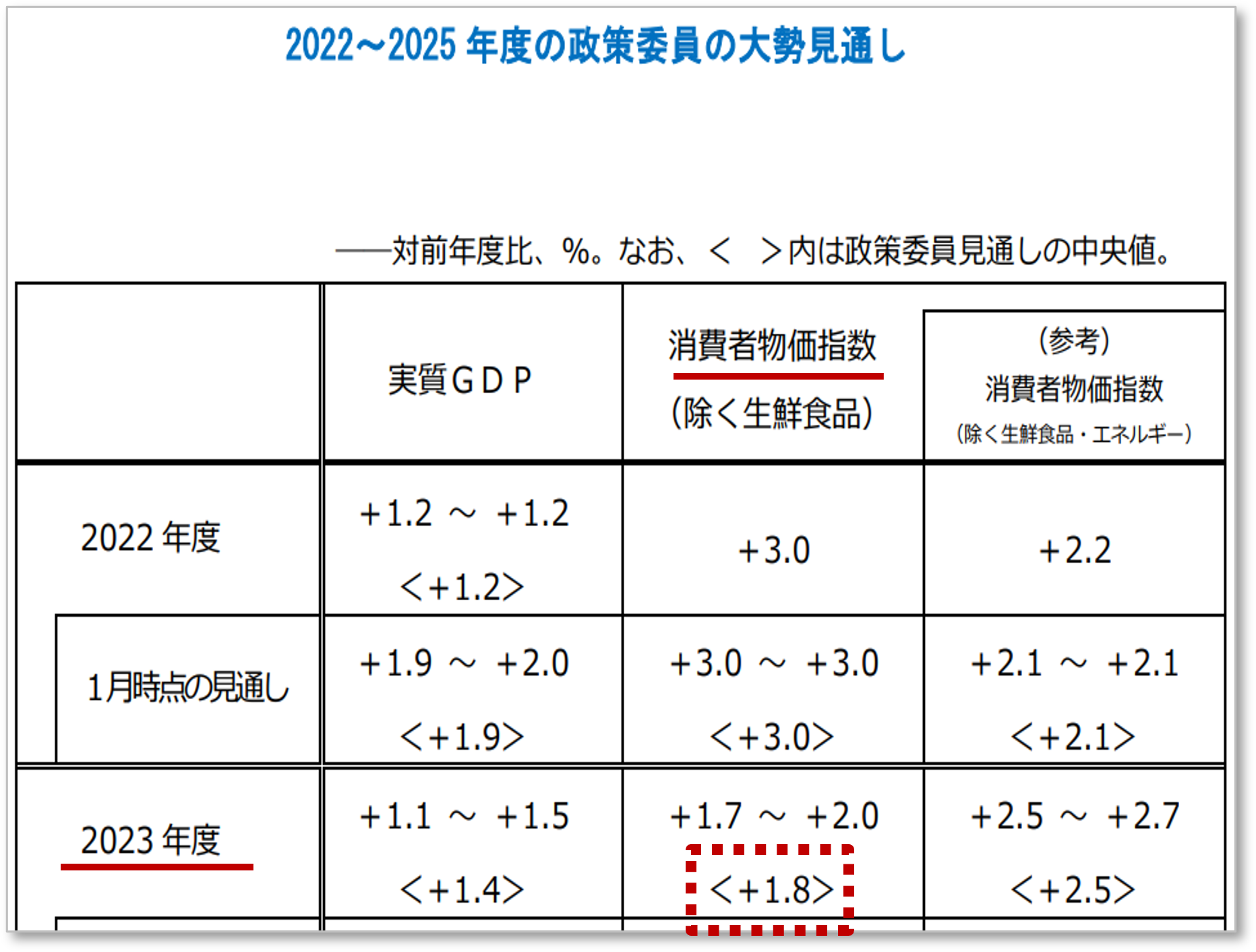 ※出典:日銀経済・物価情勢の展望2023 年 4 月
※出典:日銀経済・物価情勢の展望2023 年 4 月
23年度のコアCPIの日銀予想は、1.8%だ。
これは、低すぎるから、上方修正(2.5%へ)した。
なお、消費者 経済 総研は、先日に、
23年度のCPIの予想を出した。
その予測は、下記ページを、参照頂きたい。
【2023最新予測 日本 物価上昇率】
-- 消費者 経済 総研 --
Q:日銀のCPI予想が1.8%から、
2.5%へ、上方修正だな
すると、日銀が目標とする 2%を、超えた。
ならば、日銀は、金融緩和を、
やめるべき ではないか?
↓
A:
日銀は、まだ緩和をやめない。
消費者 経済 総研は、下記の流れだと考える。
コストプッシュ型インフレで、物価上昇
↓
原油高の落ち着きで、
エネルギー費や、様々な原材料の価格も落ち着く
↓
ひとたび、コストプッシュ型インフレは、収束
その後は?
需要 > 供給 の需要牽引型インフレになり
↓
継続的・安定的に、CPI上昇率が、2%超になったら
↓
そこで初めて、金融緩和策の修正だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆さらに わかりやすい 筆者(松田)の 解説
▼22年12月の 黒田総裁の 変動幅の拡大
22年12月の 変動幅の拡大のキーワードは、
〇〇〇〇〇?
2022年12月には、
黒田総裁による、下記の変動幅の拡大が、あった。
変更前:±0.25%
↓
変更前:±0.50%
22年12月の時も、
利上げではないし、引き締め策でもない。
目的は、「 副作用への対応 」 だった。
具体的には「 債券市場の 機能度の改善 」 だった。
下図の通り、機能度は悪化していた。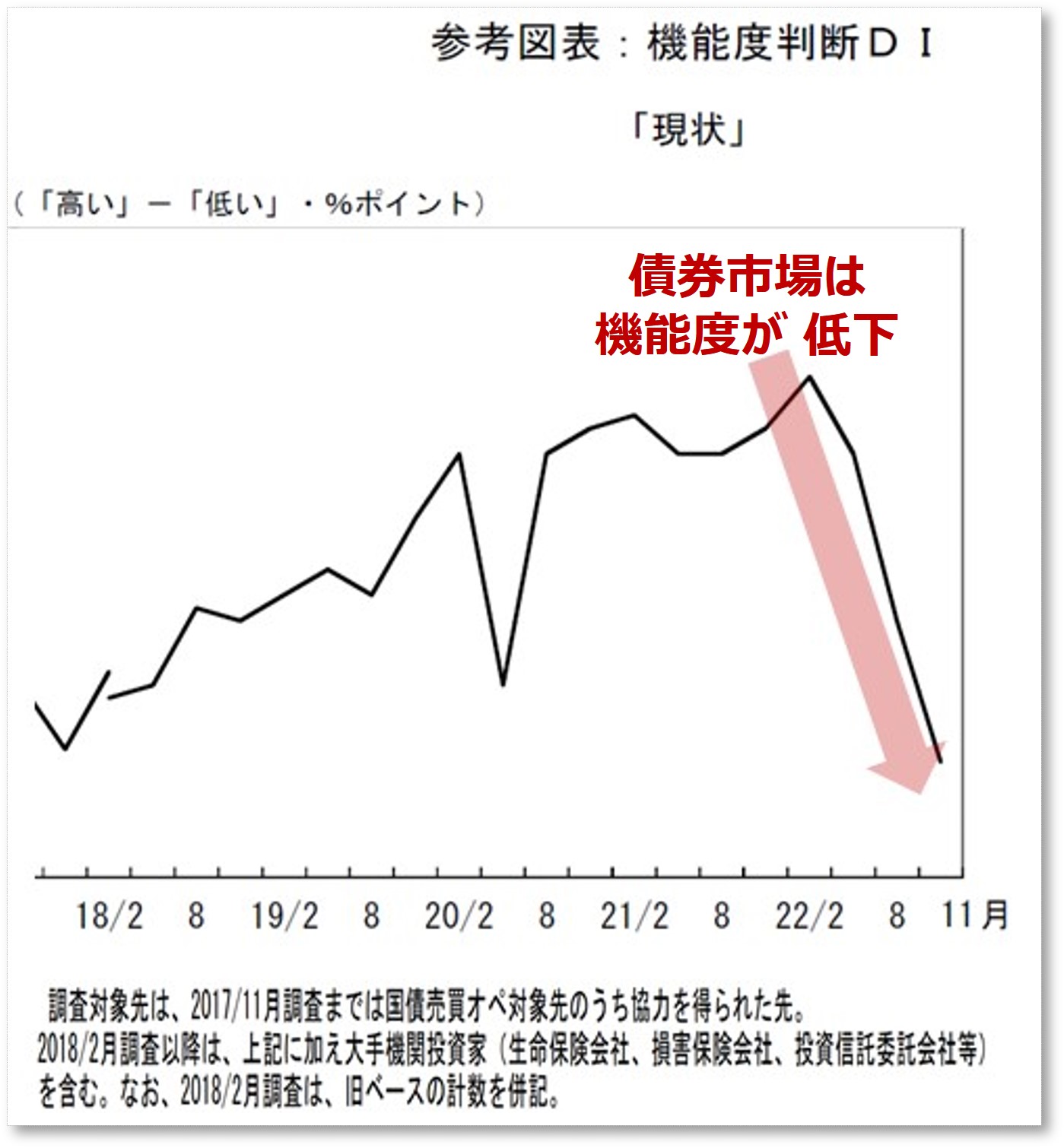 ※図は、下記日銀資料から不要部分を削除し抜粋した
※図は、下記日銀資料から不要部分を削除し抜粋した
※出典:日銀|債券市場サーベイ(2022年11月調査)
22年12月の変動幅の拡大時のキーワードは、
「機能度 改善」 だった
▼最近の機能度は?
7/28の会合後の公表資料でも、下記が語られた。
「 金利操作の柔軟化で、
債券市場の機能への影響を、和らげる 」
だが、最近の債券市場の機能度は、
下図の通り、改善傾向にある。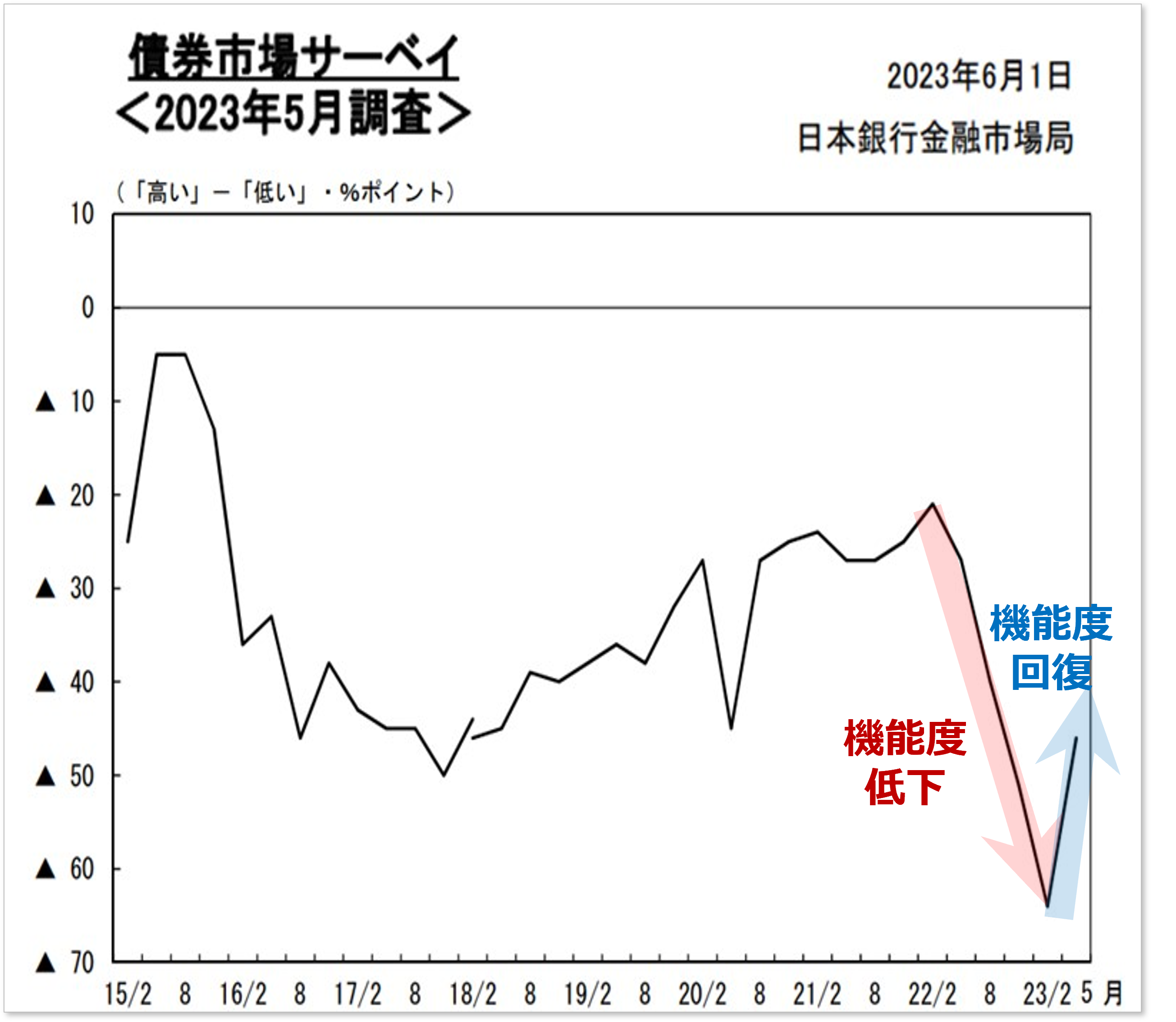 ※出典:日銀|債券市場サーベイ(2023年5月調査)
※出典:日銀|債券市場サーベイ(2023年5月調査)
改善傾向にあるので、7/28会合では、
債券市場への配慮は、強調や重視は、されてない。
その代りに、下記が重要キーワードだ。
① 不確実性
② 将来の リスクへの 対応
③ 投機筋
今回の日銀会合のキーワードは、上記の3つだ
植田総裁は、
①②③のワード(含む同義語)を、繰り返し、発言した。
▼誤解、そして、誤報
利上げでもない。 金融引き締めへ転換でもない。
正常化への一歩でも、ない。 緩和の修正でもない。
利上、引締め、正常化へ一歩、緩和修正は、誤報だ。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:上記の①②③のキーワードを、
わかりやすく、言い換えると?
↓
A:
① 不確実性 とは?
↓
日銀の予想が、外れた。
今後も、外れるかもしれない
② 将来のリスクへの対応 とは?
↓
今後の予想が、外れた場合の、事前の準備
③ 投機筋 とは?
↓
ヘッジ・ファンドによる、YCCアタック
-- 消費者 経済 総研 --
◆日銀の予想が、外れた?
既述の通り、日銀の物価予想は、外れた。
今後も、予想が外れるリスクがある。
23年度のCPI上昇率の予想は、1.8%だったので、
その予想が、外れるのは、ほぼ確実だ。
そこで、1.8%→2.5%へ、上方修正した。
年度別の日銀のCPI予想は、下記だ。
23年度 2.5%
24年度 1.9%
25年度 1.6%
上記の予想が、また外れるリスクを、
日銀は、懸念しているのだ。
▼予想どおりなら、緩和継続
上記の予想通りならば、金融の緩和策は、継続だ。
24年度も25年度も、2.0%を、下回るからだ。
安定的・持続的な 2%以上 になったら、
利上げ等で、緩和策を修正する。
▼23年度の 2% 超 は、コスト・プッシュ型
23年度は、2%超だが、
海外発のコストプッシュ型で、特殊なインフレだ。
「 需要が牽引 」 する通常のインフレではない。
コストプッシュの主な原因は、原油高だ。
日銀が利上げをしても、原油価格は下がらない。
よって、23年度は、金融緩和策を、継続する。
▼予想は、下側にも、上側にも、外れる?
上:予想よりも、物価が上昇する 上振れリスク
下:予想よりも、物価が上昇しない 下振れリスク
上・下 両方のリスクがある。
▼下振れリスクは、さほど懸念なし?
下振れした場合は、市場原理によって、
市場の金利は、自然に低下する。
だが、上振れの方は、やっかいなのだ。
〇〇〇が、やってくるからだ。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:〇〇〇とは、何か?
↓
A:投機筋(ヘッジ・ファンド)だ
物価が、予想以上に、上昇したら、
日銀は、変動幅の上限の拡大や、利上げを行う。
Q:予想が外れて、
あわてて、利上げ等をしたら、どうなる?
↓
A:
「 利上げ = 国債の価格の下落 」 が、
急速に大幅に進む。
国債価格は、下落トレンドになる。
国債市場が、下落トレンドにあると、皆が知れば、
国債のショート(カラ売り)が、増える。
短期的・投機的に、儲けを狙うヘッジファンドは、
そのトレンドに、参入してくる。
利上げ等のため、日銀が、国債売却を、続ける必要
があるなら、下落が約束された様な状態になる。
売りが売りを呼び、国債価格は、下落を続ける。
国債の価格と国債の金利は、逆数 ※ なので、
金利は、上昇を続ける。
日銀が適切だと、考える金利水準を、超えて、
高金利に、なってしまう。
※「 国債の 価格と金利は 逆 」 の理由の解説は、
本ページ内を「品薄」で検索し、該当箇所へ移動
予想外の物価高になって、慌てて、利上げ等をする
と、このような望まぬ状態に、なるのだ。
だからこそ、急に・慌てて、やるのではなく、
「 事前に、準備 」 しておくのだ。
これが、日銀が言うところの 「 柔軟化 」 策だ。
長期の政策金利は、ゼロ%(変動幅±0.5%)は、不変。
事前の準備の枠として、
その外側に、0.5~1.0%の枠を、用意したのだ。
「 何が何でも、0.5%まで 」 ではない
↓
「 柔軟化 」 だ。
▼それなら、±0.5%ではなく、±1%に、すれば?
上記の狙いがあるなら、
変動幅を、±0.5%ではなく、±1%に、でよいか?
±0.5%のままにしたのは、
下記の両方を、重視したと、考えられる。
A ゼロ金利での、金融緩和の継続
B 将来の予想外の 上振れへの準備
Bだけ考えるなら、±1%でよい。
だがそれは、 「 事実上の 利上げだ! 」 との
誤ったメッセージとして、理解される懸念がある。
日銀の金融政策は、緩和姿勢を、継続している。
その点は、変わらない。
本来の趣旨である「 金融緩和策の継続 」のために、
長期金利は、0%(変動幅±0.5%)を、継続したのだ。
▼市場金利が、0.5%を超えたら、どうする?
±0.5%を、±1%に、変えたわけではないので、
0.5%を市場金利が超えたら、日銀は行動を起こす。
具体的には、
国債買入の増加、指値オペ、共担オペを、やるのだ。
これらの手法(オペ)によって、
0.5%を超えた金利に、ブレーキをかけるのだ。
変動幅±0.5%の原則は、不変なのだ。
0.5%を超えたら、
日銀は、行動(各種オペ)を、発動する。
なので、1%まで上がるとは、日銀は想定してない。
「上限キャップ1%」は、想定しないが、念のためだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆7/28 日銀会合・総裁会見の キーワードは?
① 不確実性
↓
日銀の予想が、外れた。
今後も、外れるかもしれない
② 将来の リスク への対応
↓
今後の予想が、外れた場合のための、
事前の準備
③ 投機筋
↓
ヘッジ・ファンドによる、
YCCアタック
-- 消費者 経済 総研 --
◆「 金融緩和が 正常化へ 」 の言説が 増えた?
「 日銀の極端な政策は、まもなく、修正へ 」
「 日銀の緩和策は、正常化(出口)へ、向かうべき」
「 次の総裁では、緩和は終了へ。
黒田総裁は、その 地ならし をやる 」
2022年の後半あたりから、上記の言説が増えた。
誤解や、ポジション・トークが、増えたのだ。
Q:「 緩和策をやめて、正常化」 しない のは、
なぜか?
↓
A:
そもそも、「 正常化 」 の言葉が、おかしい。
今までが「 異常で、危険 」 ならば、正常化すべきだ。
だが、異常でもなければ、危険でもない。
黒田氏の政策は、「 大胆 」ではあったが、
繰り返すが、「 異常 」ではない。
後任の植田総裁も、黒田路線を継承しているのだ。
それは、マクロ経済学の視点からも、正しい。
次項から、
連載シリーズ・日銀の決定会合 Vol.1~Vol.5。
長文になるので、
「 知りたいこと 」 を、キーワード検索で、
ページ内検索を、お勧めする。

- ■Vol.5 最近の日銀は、〇〇を実施?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆22年12月~23年1月 日銀は〇〇を実施?
「 日銀は、事実上の利上げに、政策変更した 」
「 日銀は、金融緩和の政策を、修正した 」
上記は、間違いであることを、
過去号(Vol.1~Vol.4)で、解説してきた。
間違いであることは、日銀が発表した公式資料や、
黒田総裁の記者会見の議事録などで、証明された。
今回号(Vol.5)では、さらに証明していく。
22年12月~23年1月に、日銀が実施した実績を、
見れば、より明らかになる。
日銀の 「 政策方針の 表明・予定 」 以上に、
「 実施した実績 」 を見れば、より一層、証明される。
とことん、わかりやすい日銀の 解説をする。
とことん、わかりやすい
日銀の 解説
日銀解説なら 「 消費者 経済 総研 」

- ■22年12月の 日銀会合では?
- 22年12月の日銀会合後で、下記言説も伝わった。
「 事実上の利上げに、政策変更された 」
これは、誤解である。
その 「 誤解 」 は、日々、解消され、
「 YCCのゆがみを、修正 」と、表現は、変わった。
それでも、まだ、
「 事実上の 利上げ 」 との言説が、残っている。
日数が経過したのに、まだこう言っているのは、
もはや「誤解」ではなく「誤報」である。
「 事実上の 利上げ 」 は、
もはや「 誤解 」 ではなく 「 誤報 」
-- 消費者 経済 総研 --
◆国債を買えば、 国債の金利は、低下?
日銀が、国債を、たくさん買うと?
↓
国債が、品薄になる。
↓
国債が品薄になると、国債の価格は、上がる
↓
A 金利 = B 国債の利息額 ÷ C 国債の売買額
↓
「C 国債の額」が、上がれば、分母が大きくなる
↓
Cの分母が大きくなれば、「A 金利」は、下がる
国債を、買うと
↓
国債の価格は、上昇し
↓
金利は、低下
-- 消費者 経済 総研 --
◆22年12月会合での 決定内容は?
22年12月の会合で、決まったのは、下記2点だ。
① 「利上げ」ではなく、「YCCのゆがみ修正」
② 国債の買い入れの増加
既述の通り、国債を買えば、 金利は低下する。
②は、国債の買い入れの「増加」だ。
つまり、22年12月会合では、日銀は、従来よりも、
「金融緩和・利下げ」の策を、強化したのだ。
22年12月は、
利上げ どころか、
従来よりも、緩和・利下げを、強化

- ■1月は過去最大の緩和を、実施済み
- -- 消費者 経済 総研 --
◆23年1月は、「過去最大」の緩和策を、実施
「日銀は、利上げへ、変更した 」 のがウソなのは、
実績を、見ればわかる。
実績として、巨額の国債購入を、日銀は実施した。
日銀が、1月に買った国債の額は、23兆円を超えた。
1か月間の買入れ額としては、過去最大の規模だ。
過去最大の規模の
利下げ策を、実施した
国債買入れの増加は、金利低下への誘導策だ。
実施したのは、利上げでなく、利下げ強化だった。
23年1月に、実施したのは、
利上げではなく、利下げ強化だった
「利上げ」や「緩和の修正」は、ウソ
-- 消費者 経済 総研 --
◆23年1月会合での決定内容は?
2023年1月18日の日銀会合で、何が決まるか?
について、筆者(松田)の予想もVol.3で、記載した。
予想に対して、結果は、どうなったか?
ベースラインは、
金融政策は、「現状維持」で、予想通りだった。
オプションは、
「国債買入れの拡充」でなく「共通担保オペの拡充」
だった。
共通担保オペの拡充で、
金融緩和の手法を拡大

- ■「共通担保オペ」 とは?
- 共通担保オペ は、
「 共通担保 資金供給 オペレーション 」 の略。
簡単に言うと、
「日銀が民間銀行に、低金利で、お金を貸す政策」
-- 消費者 経済 総研 --
◆目的は、低金利への誘導?
共通担保オペでは、
相場の金利よりも、安い金利で、お金を貸す。
これで、金利の相場を、低い方へ、誘導できる。
つまり、金利を低下させる政策だ。
共通担保オペは、金利の低下策
-- 消費者 経済 総研 --
◆担保 とは?
「共通担保オペ」の、「 担保 」 とは、何か?
お金を貸す際に、日銀は担保を、要求する。
担保は、何でも良いわけではなく、
国債など、一定のものに、限られる。
-- 消費者 経済 総研 --
◆どう、拡充された?
「共通担保オペの拡充」とあるが、「拡充」とは何か?
貸付の「期間の選択肢が増えた」ことが、拡充だ。
下記のように、金利入札方式において、
貸付期間の選択肢が、増えた。
拡充前:貸し付け期間は、1年以内に、限定
↓
拡充後:貸し付け期間は、10年以内へ、拡大
-- 消費者 経済 総研 --
◆さっそく、1月23日に実施?
23年1月18日の日銀会合の後、
共通担保オペは、さっそく1月23日に、実施された。
拡充され選択肢が増えた「貸付期間5年」で、
実施された。
-- 消費者 経済 総研 --
◆金利の入札方式 とは?
このオペは、
日銀から民間銀行等への、お金の貸し出しだ。
1月23日では、1兆円の規模で、行われた。
お金を借りる側の民間銀行等は、
金利は、低い方が、お得だ。
お金を貸す側の日銀は、金利が高い方が、良い。
そこで、入札によって、
金利を競争させて、貸付先を決める。
借りる側の民間銀行等が、希望の金利を提示する。
そして、高い金利の方から、落札とする。
-- 消費者 経済 総研 --
◆共通担保オペの 入札結果は?
入札の結果は、0.145%だった。(落札平均の金利)
入札で提示される金利の値は、ばらつきがある。
落札された最低金利は、0.11%だ。
よって、0.11%未満の提示の入札は、不採用だ。
落札になった金利の平均は、0.145%だった。
-- 消費者 経済 総研 --
◆共通担保オペの 狙いは?
共通担保オペの狙いは、
民間の銀行等の、国債購入の機会の増加である。
民間銀行等が、相場より低い金利で、お金を借りる
↓
借りたお金を、何に、使うか?
↓
民間企業への融資を、増やす等がある
↓
企業の借入ニーズが、低いならば?
↓
国債を買って、国債が生む利息で、儲ける
↓
具体的には?
↓
日銀から貸付期間5年で、0.145%の金利で借りて
その金利よりも、高い金利の5年国債を買う
↓
1月24日の5年国債の終値は、0.181%だった
↓
支出は0.145%、収入0.181%なので簡単に儲かる
↓
民間の銀行等は、この制度に、参加意欲が生まれる
↓
民間銀行等による国債購入の増加が、期待できる
↓
国債の購入の増加で、国債価格に上昇の力が働く
↓
国債価格の上昇は、国債の金利低下
↓
金利を下げる力になる
-- 消費者 経済 総研 --
◆「共通担保オペ」のメリットは?
今までは、 「 日銀が、国債を買う 」 ことで、
金利低下を、図ってきた。
日銀は、それ以外の手法を、拡充したのだ。
国債の購入の増加
↓
国債の価格が上昇
↓
国債の金利が低下
上記のプロセスを、
日銀に加えて、民間銀行等でも、行うのだ。
金利相場の低下へ貢献する主体が、増える。
利下げ手法のメニューを、増やせたのがメリット。

- ■修正・終了は、ポジショントーク?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆利上げしたら、日本経済は、困窮?
利上げは、
景気が過熱しすぎた時の、ブレーキとして使う。
これは経済学部の学生が、1年生で習うことだ。
日本の景気は、まだ低迷状態だ。
利上げというブレーキを、掛けたら、
低迷するに、決まっている。
日本の全体にマイナスでも、自分や自分の会社が、
得する発言は、ポジション・トークだ。
一部だけが、得をする利上げをして、
日本の国全体を、困窮させてはいけない。

- ■Vol.4修正へ 「地ならし」 は ウソ?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆「 金融緩和が 修正へ 」 の言説が 増えた?
「 日銀の極端な政策は、まもなく、修正へ 」
「 日銀の緩和策は、正常化(出口)へ、向かうべき」
「 次の総裁では、緩和は終了へ。
黒田総裁は、その 地ならし をやる 」
昨年の後半あたりから、上記の言説が増えた。
誤解や、ポジション・トークが、増えたのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆消費者経済総研が、日銀解説をする 理由は?
日本経済は、まだ、利上げできる状態にない。
利上げしたら、消費者、企業、働き手へダメージだ。
弱い日本の経済は、さらに弱体化してしまう。
「 利上げで → 弱体化 の理由・メカニズム 」 は、
下記ページを、参照頂きたい。
日銀次期総裁人事いつ決まる? 利上げしたら〇〇
弱体化を回避すべく、「 消費者 経済 総研 」は、
日銀政策を、シリーズで、連載している。
とことん、わかりやすい日銀の解説だ。
とことん、わかりやすい
日銀の 解説
日銀解説なら 「 消費者 経済 総研 」
日銀の金融政策に関する話は、
誤解、理解不足、デマ、ポジショントークが多い。
金利が上がった方が、得をする陣営は、
「 緩和策・低金利策を、修正すべき 」 と言う。
これを、「 ポジション・トーク 」 という。
※なお、ポジショントークだからと言って、
直ちにNGではない。
ポジショントーク以外に、
知識不足が、原因での「誤解」も、多い。
▼岸田内閣には、正しく、判断して頂きたい
別ページの過去号で、解説した通り、
岸田首相は、外交には素晴らしい経歴がある。
しかし、マクロ経済学の知見に、不足がある。
誤解に基づく言説や、ポジショントークが、
世の中に、増えると、どうか?
「 利上げが正解。 金融緩和の修正が正解 」
これを岸田首相が、世論だと思い、
誤った判断をしては困る。
※「次期総裁として、政府は雨宮氏へ打診」
との一部報道があった。
雨宮氏ならば、リスクは小さい。
しかし雨宮氏に、内定したわけではない。
雨宮氏で決定しなかった場合、
岸田内閣が、どのような判断をするか、懸念が残る。
また、日銀政府の共同声明にも、影響する懸念がある。
「 金融緩和を修正すべき 」 や 「 利上げすべき 」 は、
この重要な時期においては、迷惑な言説である。
-- 消費者 経済 総研 --
◆今回号のポイントは?
▼①利上げ ではなく、 クレーム対応 だった?
※YCC ( イールド・カーブ・コントロール ) は、
本ページの ■Vol.2と■Vol.3 で、解説中。
YCC の 微修正は、
「 事実上の利上げ 」 ではない。
次の総裁の利上げの「 事前の地ならし 」でもない。
「 債券市場の 機能低下 」に関するクレーム対応だ。
「債券市場の機能低下」 を、知らない人が多いから、
「事実上の 利上げ だ」との勝手な解釈が生まれた。
市場参加者(民間の機関投資家)のクレーム
(意見表明)の発言内容は、下段に記載してある。
▼②黒田氏は、地ならし なんか、頭の中にない
・次の総裁での政策修正への 地ならし
・利上げ開始への 事前の 地ならし
黒田総裁は、これらは、まるで頭の中にない。
それどころか、2,3年は、
金融緩和を継続すべきと、言っている。
世間の言説と、まるで正反対なのだ。
この①と②のエビデンス(証拠、根拠)を、解説する。

- ■12月会合も、1月会合も、緩和強化
- -- 消費者 経済 総研 --
◆22年12月会合も、緩和の強化?
2022年12月の日銀会合の直後から、
「 日銀が、金融引き締めへ、政策変更した 」
「 日銀が、事実上の利上げへ、修正した 」
このような誤解が、広がった。
それは、誤解で、正しくは、「 金融緩和の強化 」だ。
「金融緩和の強化」である証拠(エビデンス)を、
本ページの■Vol.2~4 で、解説してある。
-- 消費者 経済 総研 --
◆23年1月会合も、緩和の強化?
23年1月会合では、何が決まったか?
ベースライン(基本姿勢)は、変更なく、現状維持。
オプションは「共通担保オペ」で、利下げだった。
つまり、前回12月会合も、今回1月会合も、
利下げメニューの拡充での、金融緩和の強化だ。
「共通担保オペ」 については、Vol.5で解説中。
前々回12月会合も、 前回1月会合も
利下げ・金融緩和の強化 だった

- ■次期総裁への地ならし?
- 黒田総裁の任期は、2023年4月8日までだ。
最近は、下記の憶測が、言われることがある。
「 新しい総裁では、
金融緩和ではなく、引き締め側へ変更だ。
引き締めへ、急に、チェンジするのではなく、
その準備として、地ならしを、黒田氏は考えた。
そのために、0.25%分の利上げに、踏み切った。」
繰り返すが、22年12月以降も、
利上げを、してないし、 引き締めも、していない。
「次の総裁のための、準備的行為の地ならし」とも、
黒田総裁は、一言も、言っていない。
「地ならし」である根拠を、
筆者(松田)は、探してみたが、見当たらなかった。
逆に「地ならし ではない」の根拠は、下記の通りだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆次の総裁への 地ならし?
▼記者質問 (2023年1月会合の後)
「 次の総裁に、スムーズに渡したい、
とかの思いは、あったか? 」
▼黒田総裁回答
「 後任の方とか、何かを申し上げたり、
後任の人のために、とかは大変僭越で、
そういった考えは、ない。 」
「次の総裁への 地ならし」を、
黒田氏は、否定した
▼記者質問 (2022年9月26日大阪懇談会の後)
「 次期総裁での、政策変更の話だが、
次の体制になっても、利上げをせずに
大規模緩和を、維持して欲しい、という事か? 」
▼黒田総裁回答
「 私は、4 月までなので、その後について、
私が、今考えているという事はない。
その後の事は、その時の金融政策に関与する
総裁、副総裁、審議委員の方々の考え方による。」
上記のように、黒田総裁は、
次の総裁体制への地ならしは、考えていない。
-- 消費者 経済 総研 --
◆緩和策を、最後まで、変える意思なし
▼黒田総裁発言(2022年9月26日大阪懇談会の後)
「 2%の物価安定の目標は、先進国の殆ど全てが
採用してるので、変えようとは、思わない。 」
黒田総裁は、緩和策を、
最後まで、変える意思なし
-- 消費者 経済 総研 --
◆黒田氏は、任期満了後も、緩和すべきと言った
▼記者質問 (2022年9月会合の後)
「 総裁はフォワードガイダンス変更と利上げは、
当面は、必要ないと、言っている。
当面とは、3ヵ月とかでなく、長いスパンか? 」
※フォワードガイダンスとは、
金融政策の将来の方向性のこと
▼黒田総裁回答
「 その通りだ。
当面というのは、数か月の話ではなくて、
2~3 年の話だと、考えて頂いた方がよい。 」
上記の通り黒田氏は、
「 利上げは、2,3年不要 」と言ったのだ。
2,3年先とは、
黒田氏の退任後の、次の総裁の期間だ。
次の総裁で 緩和修正 どころか
次の総裁でも 利上げ不要 と述べた
「 地ならし 」 は、ウソ
▼黒田総裁発言(2022年9月26日大阪懇談会の後)
9/22日銀会合の後の、9/26大阪懇談会はどうか?
「 2023年度も、2024年度も、
当然に、金融緩和が続くと、私は考えている。
但し、私が任期後の政策を決める立場にない。 」
上記の通り、
自分が決める立場に無いと、断った上で、
黒田氏は、「任期満了後も、緩和継続だ」と言った。
つまり 「 次期総裁での 緩和修正の 地ならし 」
なんて事は、まるで頭の中にない。
次の総裁で緩和修正どころか次の総裁で緩和修正どころか
次の総裁でも緩和継続と述べた。
次の総裁でも緩和継続と述べた。
つまり、「地ならし」と、正反対なのだ。
「地ならし」とは、正反対だった
「地ならし」 は、 ウソ
上記の質疑内容は、下記議事録から抜粋要約した。
質疑内容の原文の文言は、下記を参照。
※日銀|総裁定例会見(9月22日)要旨
※日銀|総裁記者会見 要旨2022年9月26日 於大阪市
※日銀|総裁定例会見(1月18日)
-- 消費者 経済 総研 --
◆黒田総裁は、地ならしの考えはない
金融政策の変更は、2、3年必要なしとも発言した。
日銀の公表文書でも、黒田総裁の発言でも、
緩和政策の見直し、終了への出口の模索などは、
見当たらない。

- ■利上げでなく、債券市場の健全化?
- 22年12月の日銀会合で、10年国債の金利の
振れ幅を、±0.25 → ±0.5% へ拡大した。
繰り返すが、これは、利上げではなく、
債券市場の健全化のための、微調整だ。
▼国債の歪みは、社債へ悪影響利上げ ではない。
債券市場の健全化のための
微調整
社債は、資金調達のため、企業が発行する債券
↓
社債の金利の基準になるのは、国債の金利だ
↓
債券の市場機能が、低下すると
↓
企業の資金調達に、悪影響
▼YCの歪み 是正 → 企業金融の円滑化が目的
国債の金利のYC(イールドカーブ)が、歪むと
↓
社債の金利の基準が、はっきりしない
↓
企業の資金調達に、悪影響になる
↓
歪みを正して、企業金融を、円滑にする
↓
12月20日の日銀決定は、上記がポイント
↓
12月20日の日銀決定は、「 利上げ ではない 」
12月20日の日銀決定は、
利上げ ではなく、
イールドカーブの歪みの是正
▼黒田総裁発言(22年12月会合の後)
12/20の日銀会合の目的を、
黒田総裁は、下記の通り、しっかり説明している。
「 国債金利は、社債、貸出等の金利の基準となる。
債券の市場機能が、低下した状態が、続けば、
企業の起債など金融環境に、悪影響を及ぼす。
12月20日決定は、こうした情勢を踏まえた。
国債の金利は、社債、銀行貸出の基準だ。
イールドカーブの歪みが、続くと、基準が、
はっきりせず、市場に信用されなくなる。
企業金融全体に、非常にマイナスになる。
国債金利の基準になる所の歪みを正して、
緩和効果が企業金融に円滑に及ぶようにする。」
上記の質疑内容は、下記議事録から抜粋要約した。
質疑内容の原文の文言は、下記を参照。
※日銀|総裁定例会見(1月18日)
利上げ ではない。
債券市場の健全化のための
微調整
-- 消費者 経済 総研 --
◆債券市場の健全化は、誰が、要求した?
前項の通り、債券市場の機能が、低下している事実
があるのだ。 しかしこれを、知らない人が多い。
その機能低下という弊害を、是正するために、
YCCの微修正を、実施したのだ。
「債券市場の機能低下」を、知らない人が多いから、
「事実上の 利上げだ」との勝手な解釈が生まれた。
債券市場の 機能低下を
知らない人が 多いから、
勝手な解釈が 発生
債券市場の健全化を、誰が求めたか?
これも、知らない人が多い。
実際にアンケートや、グループインタビューで、
その機能低下への苦言を、日銀は把握をした。
いわば、クレーム対応で、
YCC微修正を、したようなことだ。
利上げも、緩和修正 でもない
地ならし でもない
市場参加者のクレーム対応
-- 消費者 経済 総研 --
◆アンケートでは?
下図は日銀が実施した
民間金融機関へのアンケートと、回答内容。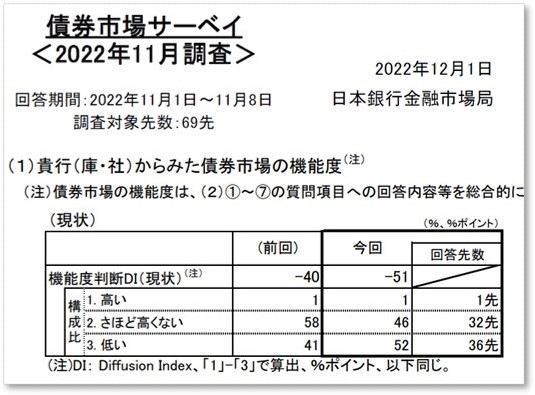
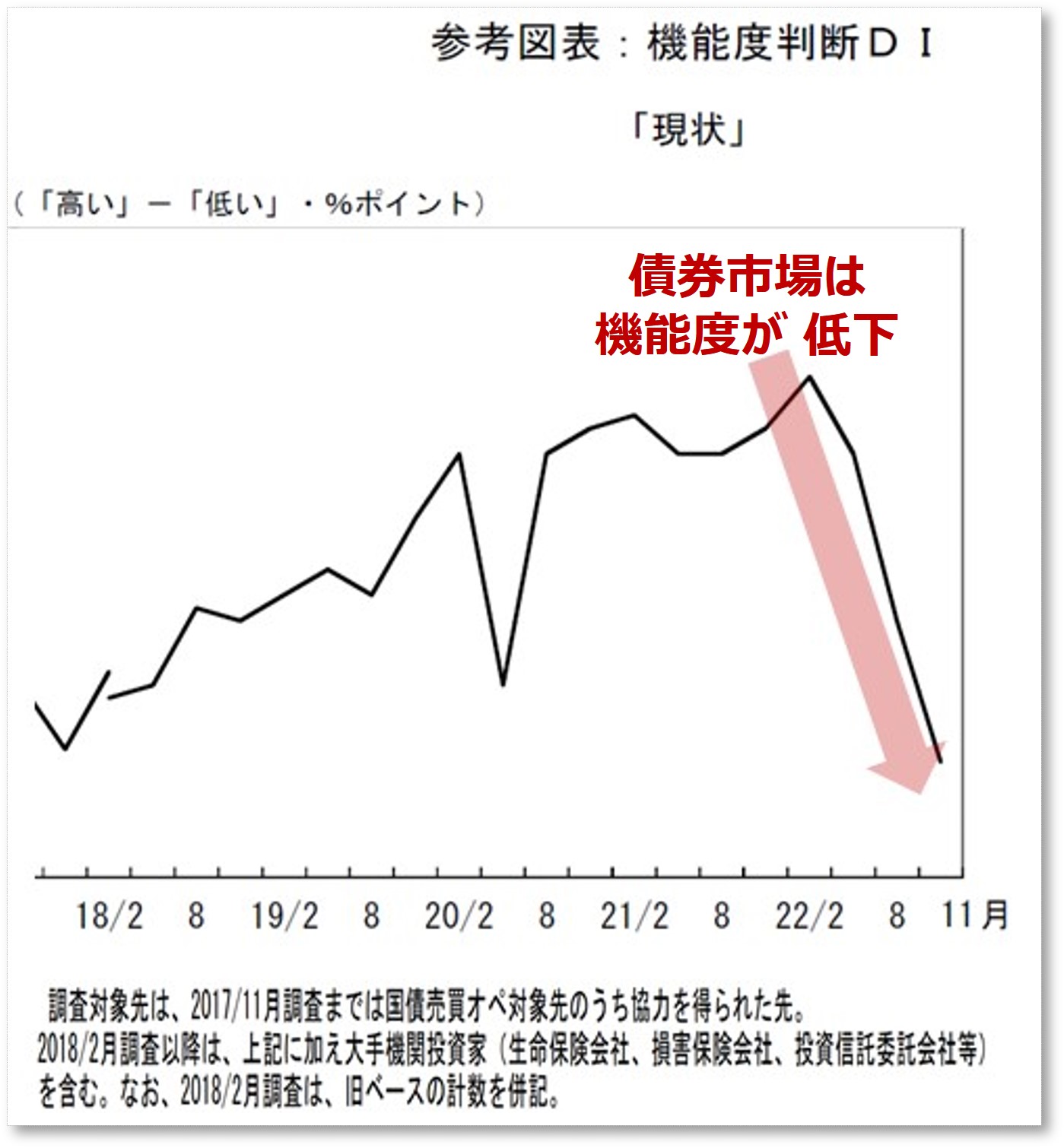
※図等は、下記日銀資料から不要部分を削除し抜粋した
※出典:債券市場サーベイ(2022年11月調査)
-- 消費者 経済 総研 --
◆グループ・インタビューでは?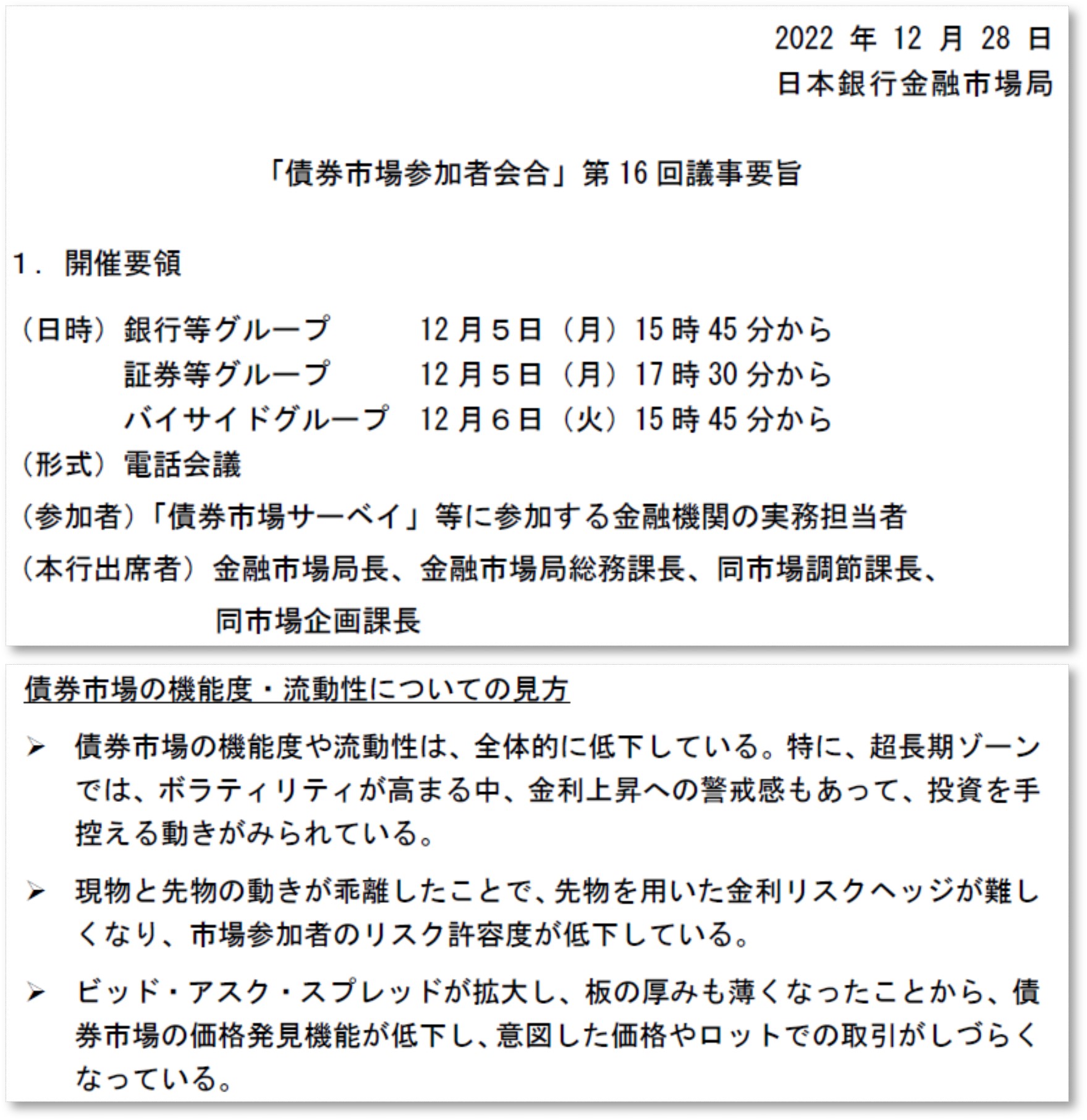
※上の資料は、下記日銀資料から抜粋した。
※出典:日銀第16回債券市場参加者会合・議事要旨

- ■修正・終了は、ポジショントーク?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆利上げしたら、日本経済は困窮?
利上げは、
景気が過熱しすぎた時の、ブレーキとして使う。
これは経済学部の学生が、1年生で習うことだ。
日本の景気は、まだ低迷状態だ。
「 利上げという ブレーキ 」 を、掛けたら、
日本の経済は、低迷するに、決まっている。
日本の全体にマイナスでも、自分や自分の会社が、
得する発言は、ポジション・トークだ。
一部だけが、得をする利上げをして、
日本の国全体を、困窮させてはいけない。

- ■Vol.3 2023/1/18の日銀会合
- -- 消費者 経済 総研 --
◆1月18日、〇〇が、決まってしまう?
日銀の金融政策決定会合(以下、日銀会合)が、
開催されている。
今回の日銀会合では、何が、決定されるのか?
-- 消費者 経済 総研 --
◆先に、国債の価格と、利回りの解説
先に、国債の「価格」と「金利」の解説を、しておく。
Q:国債価格が、UPすれば、 国債金利は、低下か?
↓
A:そうだ。 金利は低下だ。
国債価格UP → 金利低下 の仕組みは下記↓だ
日銀が、国債を、たくさん買うと?
↓
国債が、品薄になる。
↓
国債が品薄になると、国債の価格は、上がる
↓
A 金利 = B 国債の利息額 ÷ C 国債の売買額
↓
「C 国債の額」が、上がれば、分母が大きくなる
↓
Cの分母が大きくなれば、「A 金利」は、下がる
逆に、「 C 分母の 国債の額 」 が、小さくなれば、
「 A 金利 」 は、上がる。
※わかりやすく、たとえ話として、
仮に100万円で、1% だとした場合↓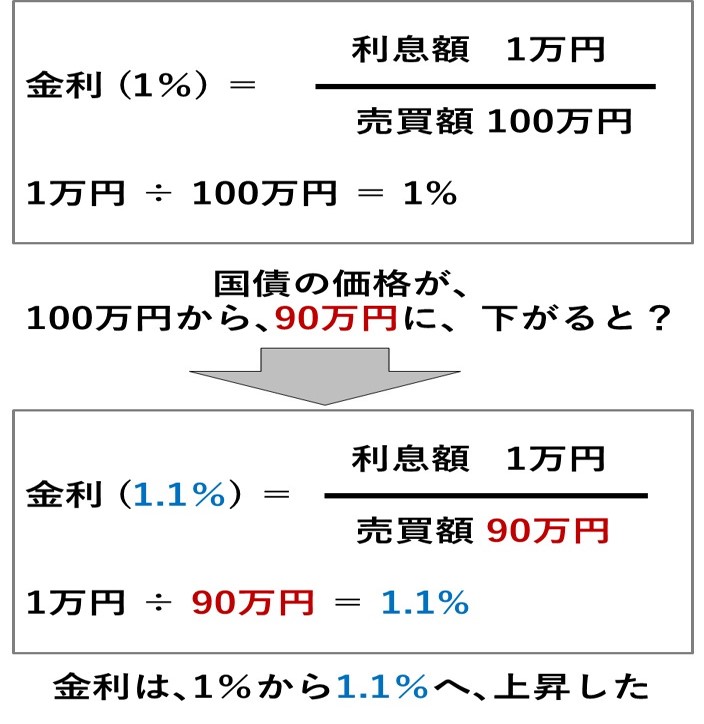
国債の「価格」が、下がると
↓
「金利」は、上がる国債の「価格」が、上がると
↓
「金利」は、下がる国債の
「 価格 」 と 「 金利 」 は、逆
-- 消費者 経済 総研 --
◆前回2022年12月の 日銀会合の 後は?
前回(昨年12月)の日銀会合で、
10年金利の変動幅が0.25%→0.5%へ拡大された
「 利上げ 」 との 「 誤解 」 が、広がった。
その 「 誤解 」 は、日々、解消され、
「 YCCのゆがみを、修正 」と表現は、変わった。
※YCCは、イールド・カーブ・コントロールの略
・イールド = 金利
・カーブ = グラフの図の中の「曲線」
・コントロール = 操作
YCCとは、金利の 曲線の 操作のこと。
YCCのグラフは、後述。
※日銀のYCC政策は、
様々な長期金利の内、10年限の国債を買って、
10年限の金利を、下げること。
「 利上げや、引き締めは、誤解 」と、
「 消費者 経済 総研 」は、昨年12月に連投してきた
「 利上げ 」 ではなく、
微修正(YCCの調整)であることを、解説した。
「 利上げ・金融引き締め 」 どころか、
国債の買入れ額を増額し、金融緩和の強化だった。
それらのエビデンス(証拠)を、掲載し、
消費者 経済 総研は、わかりやすく解説した。
これらの詳細は、
本ページの中段の記載分を、ご覧頂きたい。
-- 消費者 経済 総研 --
◆市場の反応は?
日銀の黒田総裁が、昨年12月の日銀会合で、
「 利上げ ではない 」と、繰り返し、説明した。
それにもかかわらず、市場参加者は、
誤解から、国債を売った人も、いただろう。
誤解じゃなくて、
「 思惑 」 から、国債を売った人も、いただろう。
時間の経過と共に、誤解は、解消される。
誤解が無くなっても、得する方の売買をする。
国債を売買するプロの機関投資家の目的は、何か?
「 儲ける こと 」 だ。
儲けを目的にしている投資家は、何を考えるか?
国債金利の誤解を、正そう!
日本の財政の健全化に、役立てよう!
このようなことは、考えてない。
「儲ける」ことが目的だ。 それが彼らの仕事だ。
大資金を動かす為替、株、国債のトレーダー達と、
筆者(松田)は、飲み会で、相場談義をしてきた。
彼らの使命は、「儲ける」ことである。
誤解だろうが、思惑だろうが、
市場の値動きに沿って、自分が得する売買をする。
「 金利が上昇・国債価格は下落 」の流れがあれば、
国債を売る。
こうして日本国債の相場は、
10年限以外の国債も、金利上昇となった。
-- 消費者 経済 総研 --
◆「事実上の利上げ」の言葉が、独り歩き?
2022年12月20日からは、
「 事実上の 利上げ 」 の言葉が、独り歩きした。
市場金利が、上昇に向かう流れが、あれば、
国債価格は、下落に向かう流れになる。
下落傾向の国債を、早めに売れば、
利益確定や、損失の回避になる。
カラ売りを仕掛ければ、儲けのチャンスが増える。
最近は、海外投資家による、
日本国債の空売りが、盛んだ。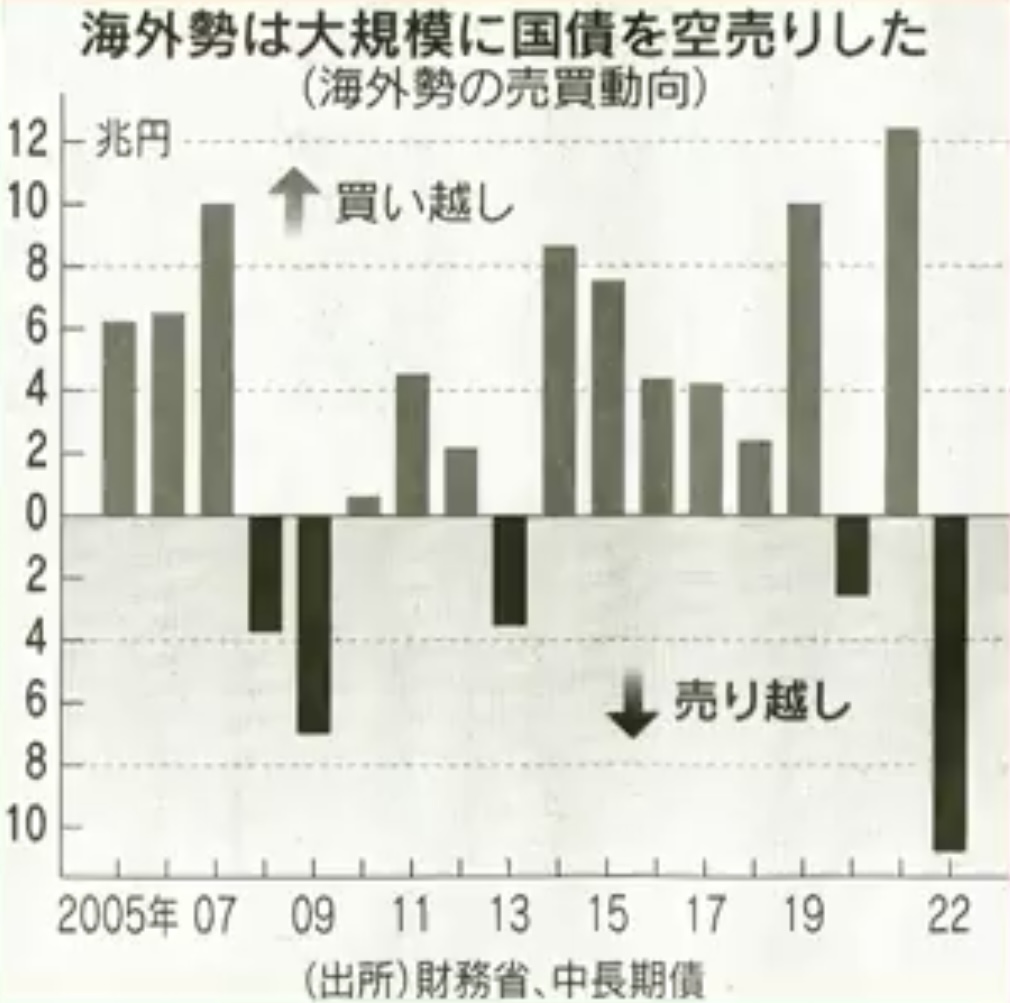 (画像出展:日本経済新聞)
(画像出展:日本経済新聞)
-- 消費者 経済 総研 --
◆イールドカーブのゆがみを、直したかった?
長期金利を、引き下げる、日銀の政策では、
10年限の国債の金利を、引き下げてきた。
10年限の金利だけ、不自然に凹んだ。
日銀は、その「ゆがみの是正」を、目指した。
縦軸は、金利。 横軸は、国債の年限。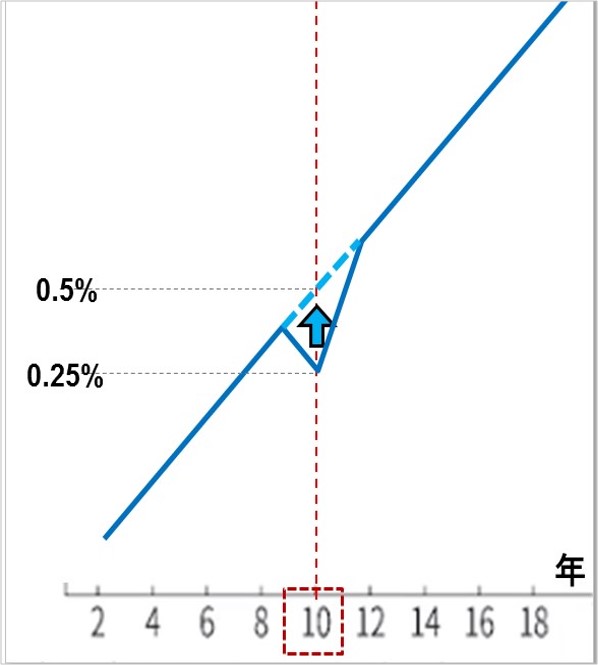
10年限の金利の振れ幅の上限を、
0.25%→0.5%に、昨年12月の会合で、拡大した。
-- 消費者 経済 総研 --
◆YC(イールドカーブ)は、どう変化した?
前回の日銀会合(2022年12月20日)から、
今回(2023年1月17日)の間では、どう変化した?
YCの 「 ゆがみ 」 は、小さくするところが、
かえって、大きくなってしまった。
下のYC(イールドカーブ)のグラフをご覧頂きたい
縦軸は金利。横軸は、日本国債の年限。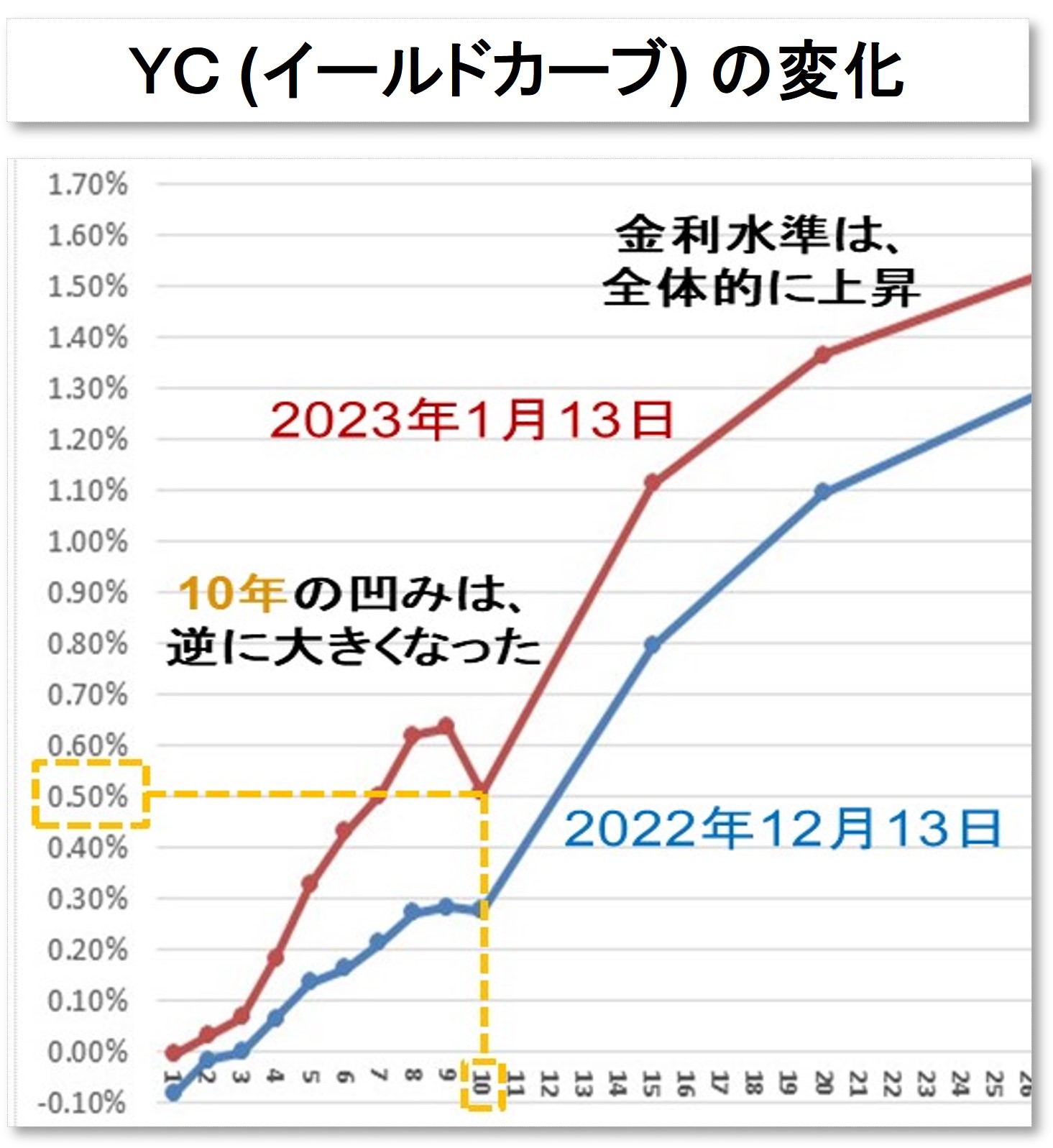
上図は、昨年12月13日 →今年1月13日の変化。
10年限の金利は、0.25%分、上昇しだが、
8年限の金利は、0.33%分も、上昇した。
10年の上昇幅よりも、大きな上昇の年限がある。
こうして歪みは、逆に大きく、なってしまった。
ゆがみ修正が、昨年12/20日の日銀の目的だった。
それが、裏目に、出てしまったのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆なぜ、ゆがみは、大きくなったか?
10年金利の上限の、0.25%→0.5%への、拡大が、
「金利相場は上昇」との解釈に、なったからだ。
最初は「誤解」で、 その後は「思惑」で動いた。
10年は、0.25%→0.5%と、0.25%拡大したが、
それ以上に、拡大した年限が、あるからだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆今回の 日銀会合で、何が決まる?
日銀会合が、開催されている。
12月18日に、内容が明らかに、なってくるだろう。
何が、決定されるのか?
A 国債買入れ強化で、金利上昇の抑制の強化
B 現状維持で、特段の決定なし
C 10年の許容振れ幅を、拡大(0.5%→0.75%など)
D YCC 政策の停止
上記4パターンのうち、どれか?
昨年12月の日銀会合では、
Cで、歪み補正をし、Aで金利の抑制を図った。
しかしながら、Cは逆効果と、なってしまった。
ゆがみの修正どころか、歪みは、大きくなった。
昨年12月のやり方を、今回の1月でもやれば、
逆効果を、拡大させてしまうリスクがある。
Cを再びやるのは、日銀も躊躇するだろう。
Aを強化するのは、ありえる。
しかし、12月20日から、Aを強化したが、
「外国ヘッジファンド vs 日銀」で、日銀は苦戦中だ
大穴は、Dの 「 YCCの停止 」 だ。
YCC政策は、副作用があるので、
諸外国では、あまり採用されない。
米国の中銀FRBは、
コロナでも、YCCの採用を、見送った。
オーストラリア中銀は、コロナでYCCを採用した。
豪中銀は、すでに、YCCを停止したが、
「YCCによって、混乱を招いた」と、反省している。
YCCで、いじれば、いじるほど、混乱し、歪むならば
やめてしまおうと、日銀も考える かもしれない。
2023年の半ばには、
世界の金利相場も、下落に向かうだろう。
Bの現状維持でも、金利は、自然に低下するから、
待っている、という選択も、あるかもしれない。
C の10年の許容振れ幅を、
拡大(0.5%→0.75%等)は、ないだろう。
同じことを、繰り返してしまうからだ。
大穴は、YCCの停止だ。
今回の会合の決定事項は、
「現状維持」をベースに、
買入れ増が、オプションだろう。

- ■Vol.2 2022/12/20の日銀会合
- 2022年12月19、20日に、日銀政策会合があった。
日本の金融政策を、決定する会議だ。
重要な会議である。
筆者(松田)は、日銀公表の資料も、読んだ。
資料公表の後での「黒田総裁の 記者会見」も、
筆者(松田)は、議事録で、読んだ。
今回は、12/20の日銀の政策決定会合を、解説する。
筆者(松田)は、35年以上前に、慶応大学 経済学部
に入学以来、経済を研究している。
しかし本ページは、経済学の知識なしでも
わかるような簡単解説としている。
経済の解説では、筆者の解説は、
「とことんわかりやすい」と思っている。
各Q&Aを、さらに掘り下げて、知りたい場合は、
本ページの下段のリンク先を、ご覧頂きたい。

- ■利上げでも 引き締めでも ない?
- 12/20日銀決定は、利上げ・引き締めではない。
逆に、「 金融緩和 」 だった。
その理由は 皆が知らない 〇〇だから?
-- 消費者 経済 総研 --
Q:12/20の日銀会合で、何が、決まったのか?
「 利上げと、 金融引き締め 」 が、決定か?
↓
A:違う。 利上げ決定 ではない。
また、引き締め決定 でもない。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:ということは、世間は、誤解しているのか?
↓
A:そうだ。 世間は、誤解している。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:では、何が、決まったのか?
↓
A:「金融の引き締め」 ではなく、「金融緩和」 だ。
緩和つまり、国債購入の増加が、決定された。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「国債購入の増加 = 金融緩和」 の仕組みは?
↓
A:国債購入を増やせば、国債への需要がUPする
よって、国債の価格は、UPする
日銀が、国債購入を、増やすと
↓
国債の価格は、上昇へ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:国債価格がUPすれば、国債金利は低下か?
↓
A:そうだ。 金利は低下だ。
国債価格UP→金利低下の仕組みは、下記↓だ
日銀が、国債を、たくさん買うと?
↓
国債が、品薄になる。
↓
国債が品薄になると、国債の価格は、上がる
↓
A 金利 = B 国債の利息額 ÷ C 国債の売買額
↓
「C 国債の額」が、上がれば、分母が大きくなる
↓
Cの分母が大きくなれば、「A 金利」は、下がる
国債の価格上昇で、
↓
金利は低下
-- 消費者 経済 総研 --
Q:中銀が保有する、国債の量の増 or 減で、
金融の 「緩和」 or 「引き締め」 なのだな?
↓
A:そうだ。 整理すると、下記の通りだ。
①国債の買入れは、金融の「 緩和 」
②国債の買入れの増加は、金融の「 緩和強化」
③国債の保有量の減少は、金融の「 引き締め 」
-- 消費者 経済 総研 --
Q:国債買入れの増加で、金利低下を図るのは、
金融の緩和の姿勢だな?
↓
A:そうだ。 日銀は金融緩和を再度、強調した
利上げ でもない
金融の 引き締め でもない
金融の緩和 だった
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「 日銀が、金融緩和を強化 」 の根拠は?
↓
A:黒田総裁は、買入れ増加と、記者発表した※
国債購入の増加は、金融緩和の強化だ。
※黒田総裁の12/20記者会見の内容は、下記↓
(..は、中略箇所を示す。)
「国債買入れ額を 大幅に増やしつつ..
各年限において、機動的に、
買入れ額の 更なる増額..を実施します。」
※出典:日銀|総裁定例会見(12月20日)
国債の 買い入れ額の 増額は
金融の緩和の強化利上げ でも ない
金融の 引き締め でもない
金融の緩和 なのだ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:なるほど。
だが「 10年国債 0.25% 利上げ 」との報道は?
↓
A:10年国債の金利は、0%が、目標だ。
それは12/20会合の 前・後で、変更なしだ。
10年国債の上下の変動幅は、変更になった。
次の通りの変更だ.
・変更前:± 0.25%
↓
・変更後:± 0.5%
-- 消費者 経済 総研 --
Q:+0.25% から +0.5%へ変更と、同時に、
-0.25% から -0.5%へ変更でもあるか?
↓
A:そうだ。 上側だけでなく、下側にも振れる。
振れ幅の許容範囲を、増やしただけだ
10年の政策金利は、ゼロ%のままで、不変だ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:だが、10年国債の市場金利は、上昇したぞ。
利上げでは、ないのか?
↓
A:10年物だけ、無理して、金利を下げてきた。
それを、正常化方向へ、戻しただけだ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:10年国債だけ、不自然に低金利だったのか?
↓
A:そうだ。 下図の通りだ
国債金利を、10年物だけ、低下させてきた。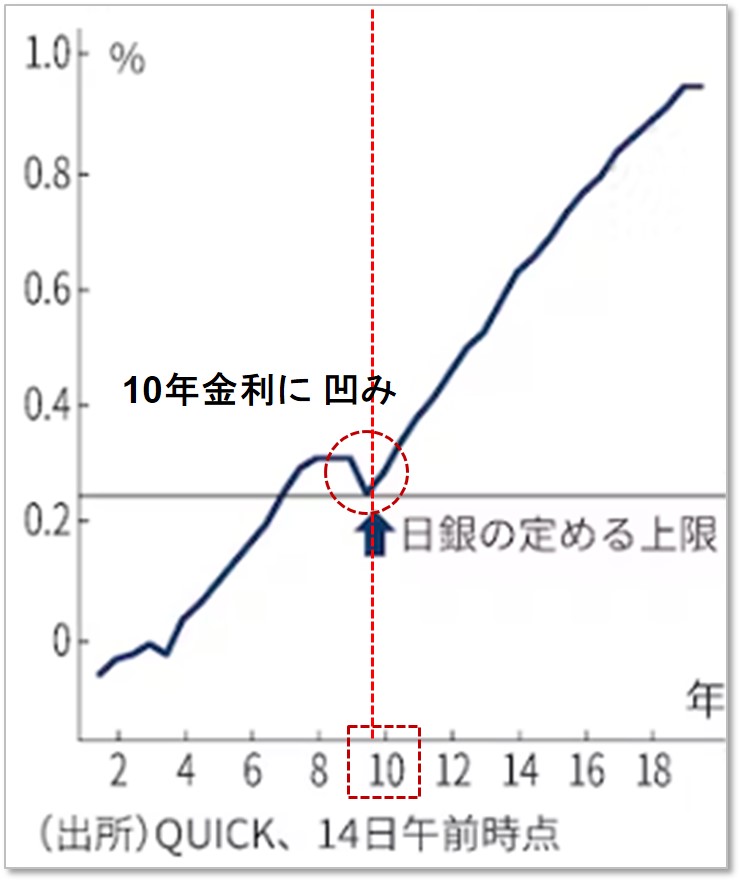
※下記出典に、赤線赤枠挿入
※出典:日本経済新聞|国債利回り乱れる秩序..
-- 消費者 経済 総研 --
Q:10年国債の金利だけが、特別なのは、なぜか?
↓
A:日銀の金融政策での、長期金利の誘導対象は、
10年国債のみを、対象としている。
10年国債を、日銀が買うことで、
10年国債の金利を、低水準に抑えてきた。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:上図で、10年の金利だけ、低く凹んでいる。
この歪みを、日銀は、是正したいのか?
↓
A:そうだ。 下記の黒田総裁の発言が根拠だ。
なおイールドカーブとは、上図の曲線の事だ。
「イールドカーブの形状がやや歪んだ形になって、
それが..企業金融等にもマイナスの影響を
与える恐れがある..ので、
このタイミングでその是正を図り、
市場機能の改善を図った..
イールドカーブの歪みの10年のところを是正」
-- 消費者 経済 総研 --
Q:イールドカーブの曲線は、どうなるか?
↓
A:下図は、10年金利の凹み 是正のイメージ図だ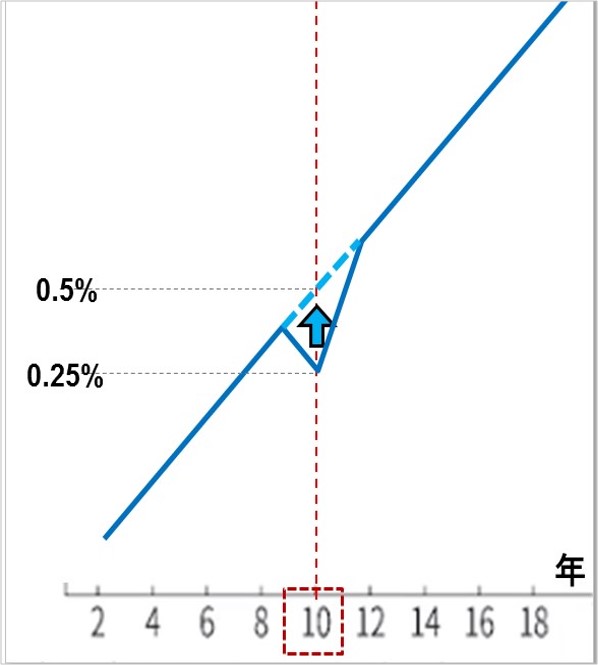
-- 消費者 経済 総研 --
Q:つまり、凹んだ10年を、引き上げ、
10年以外は、金利上昇を 抑えるのか?
↓
A:そうだ。
イールドカーブ(グラフの曲線)の歪みを、
綺麗にし、是正したいのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:10年の年限以外は、金利動向は、どうか?
↓
A:金利相場は、2022年は上昇トレンドだった。
よって、10年の年限以外は、国債購入増加で、
上昇を抑えるのだろう。 下はそのイメージ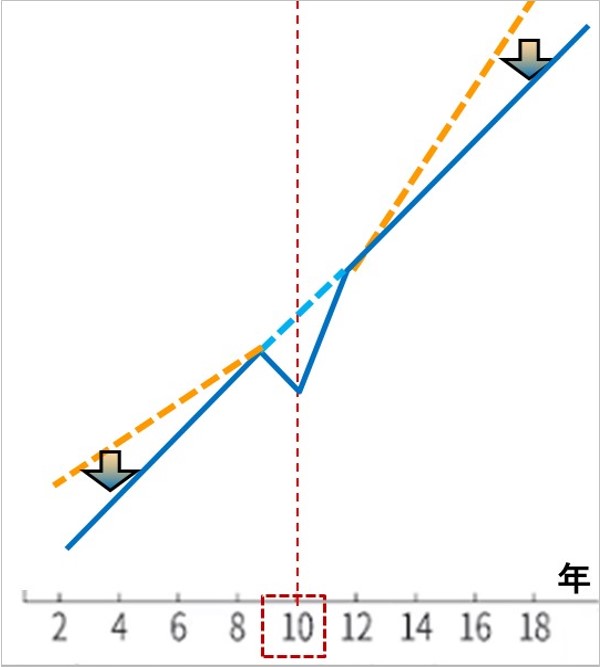
-- 消費者 経済 総研 --
Q:10年国債金利だけ、正常化(上昇)させて、
10年以外は、緩和 ということか?
↓
A:そうだ。 10年以外の国債の購入増加で、
10年以外は、金利低下を、図るのだろう。
そうすれば、上図のイールドカーブは、
凹みの無い、なだらかな線になる。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:日銀は、国債購入を、どのくらい増やすのか?
↓
A:下のように、月間7 .3兆円→9兆円 に、増やす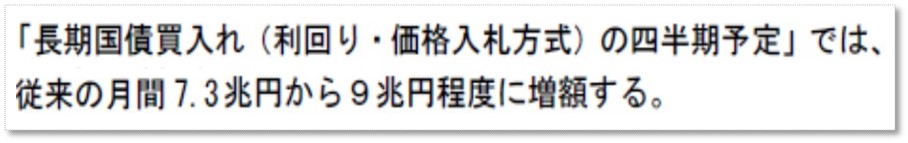 ※出典:日銀資料に改行補正
※出典:日銀資料に改行補正
-- 消費者 経済 総研 --
Q:年限別では、どのくらい増やすのか?
↓
A:下表のように、額や、回数を、増やす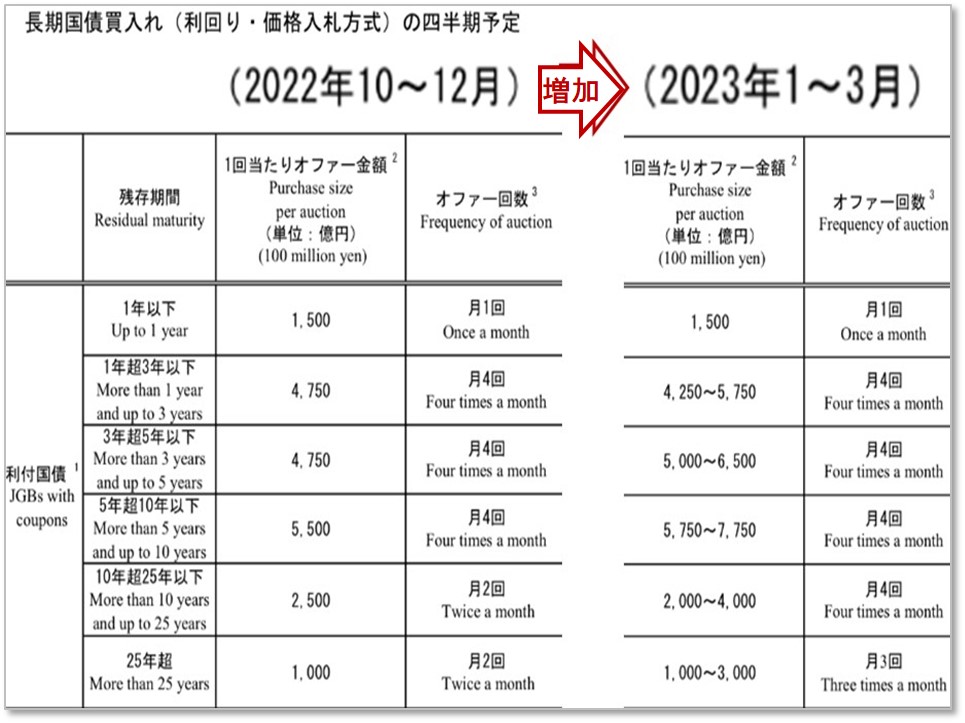 ※出典:日銀
※出典:日銀
-- 消費者 経済 総研 --
Q:10年超の年限が、購入の伸び率が高そうだな?
↓
A:そうだ。
上の表の伸び率を、下図で、見やすくしてみた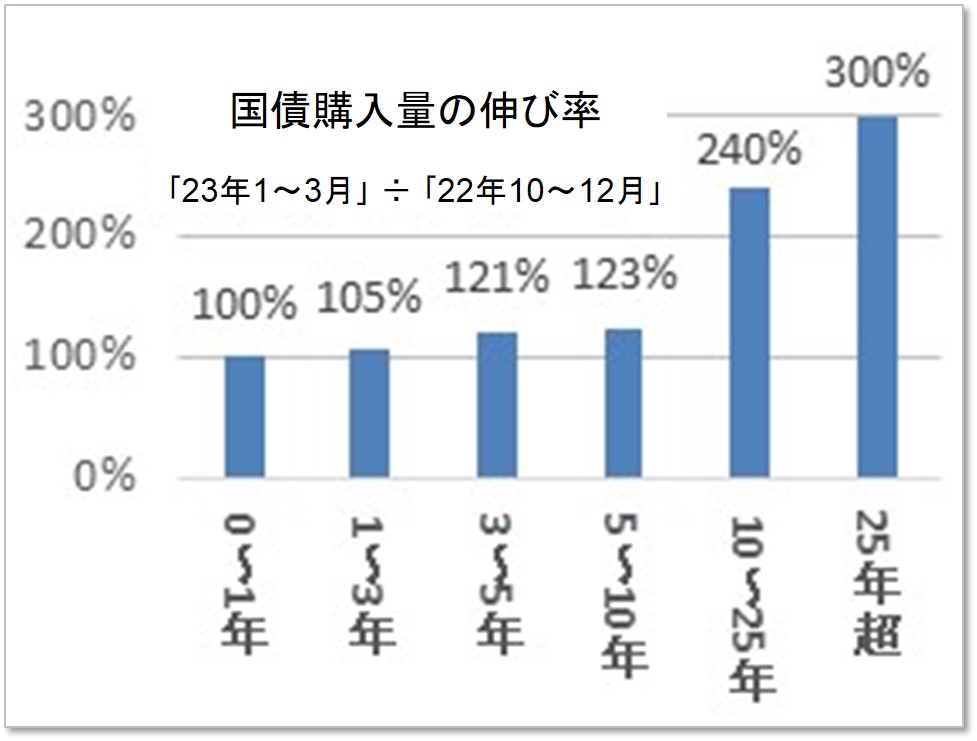 ※幅がある金額は、中央値を採用
※幅がある金額は、中央値を採用
-- 消費者 経済 総研 --
Q:10年金利を、0.5%にしたら、
直線のイールドカーブは、どうなるか?
↓
A:下図の緑の線に、なる。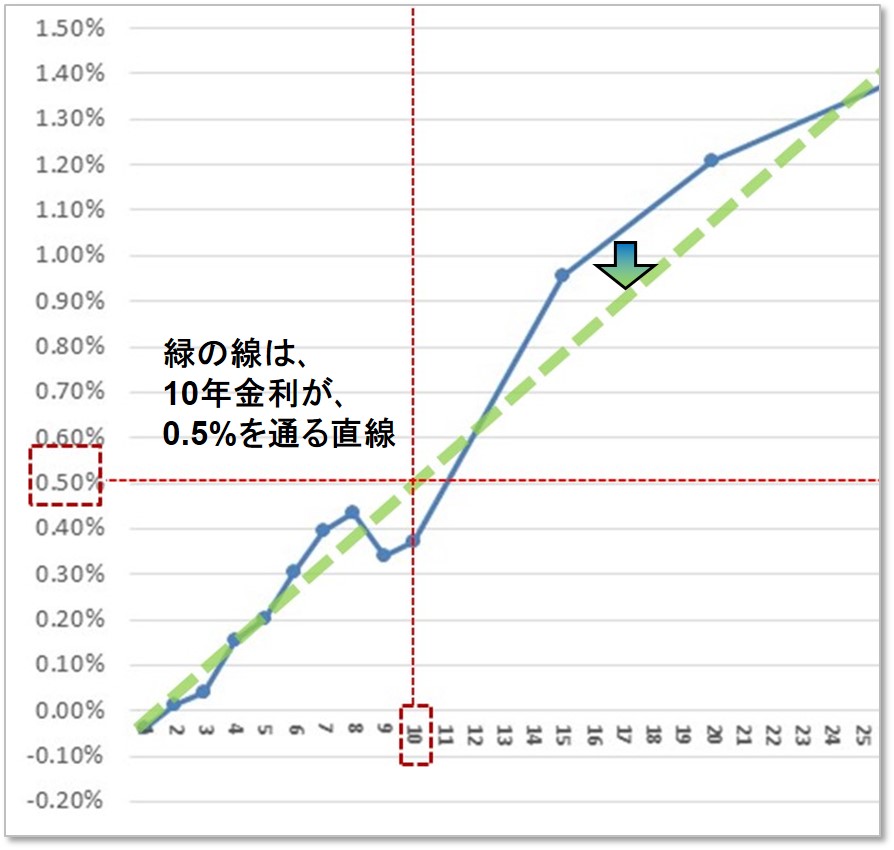 ※青線は、2022年12月23日時点の日本国債金利
※青線は、2022年12月23日時点の日本国債金利
-- 消費者 経済 総研 --
Q:10年超の金利、つまり上図の右側は、
緑の線より、実際の金利の方が、高いな
↓
A:10年超の国債購入の伸び率が、高いのは、
10年超の金利の低下を、
狙っているのではないか?
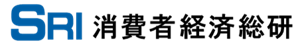
Vol.3 2022年12月27日 更新分
◆日銀は、実際に利下げした「事実と実績」
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「10年債以外は、利下げする」 のは、本当か?
↓
A:本当だ。 日銀は利下げを、既に、実施済みだ。
2022年12月20日から、実施した。
(※利下げは、金利上昇抑制との見方もある)
-- 消費者 経済 総研 --
Q:どのような手法で、やったのか?
↓
A:強力な利下げ手法の「指値オペ」が実施された
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「 指値オペ 」 と「 国債買入れ 」 の違いは?
↓
A:「国債買入れ」は、買入れの予算額分 だけ買う。
「 指値オペ 」は、 無制限に、国債を買う。
よって、指値オペの方が、強力だ。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:強力な「指値オペ」を、やるほど、
日銀は、「本気の金利抑制」なのか?
↓
A:そうだ。
かつてやったことの無い年限でも、実施した。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:どの年限の国債で、やったのか?
↓
A:2年(短期債)、5年(中期債)、20年(超長期債)だ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:その内容の日銀資料は、あるのか?
↓
A:ある。 下記だ。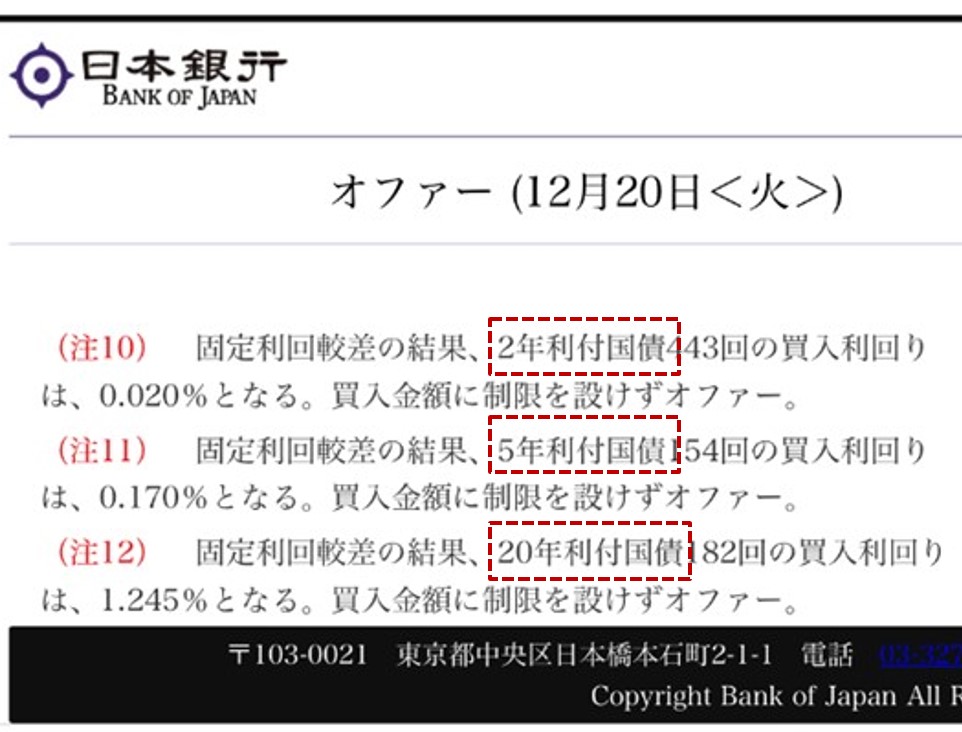
-- 消費者 経済 総研 --
Q:この資料は、プロ(機関投資家)向けだな。
もう少し、わかりやすい情報は、無いか?
↓
A:では、日経新聞の記事を、紹介する
日経新聞電子版|2022年12月20日|
日銀、5年債や20年債で指し値オペ実施 超長期は初
(..は中略箇所を示す。)
日銀は12/20に、2年、5年、20年の..国債を対象に..
無制限に買い入れる「指し値オペ」を実施..
超長期国債を対象とした指し値オペの実施は
初めてで、中期債は16年に実施したことがある。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「実施は初めて」だから、相当本気だな?
↓
A:そうだ。 前例ない事に着手するほど、
日銀は、本気で、利下げ(金利上昇抑制)だ。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:これで、どのように、金利は下がったのか?
↓
A:12月20日の指値オペ(5年国債)では
下図の通り、金利は下落した。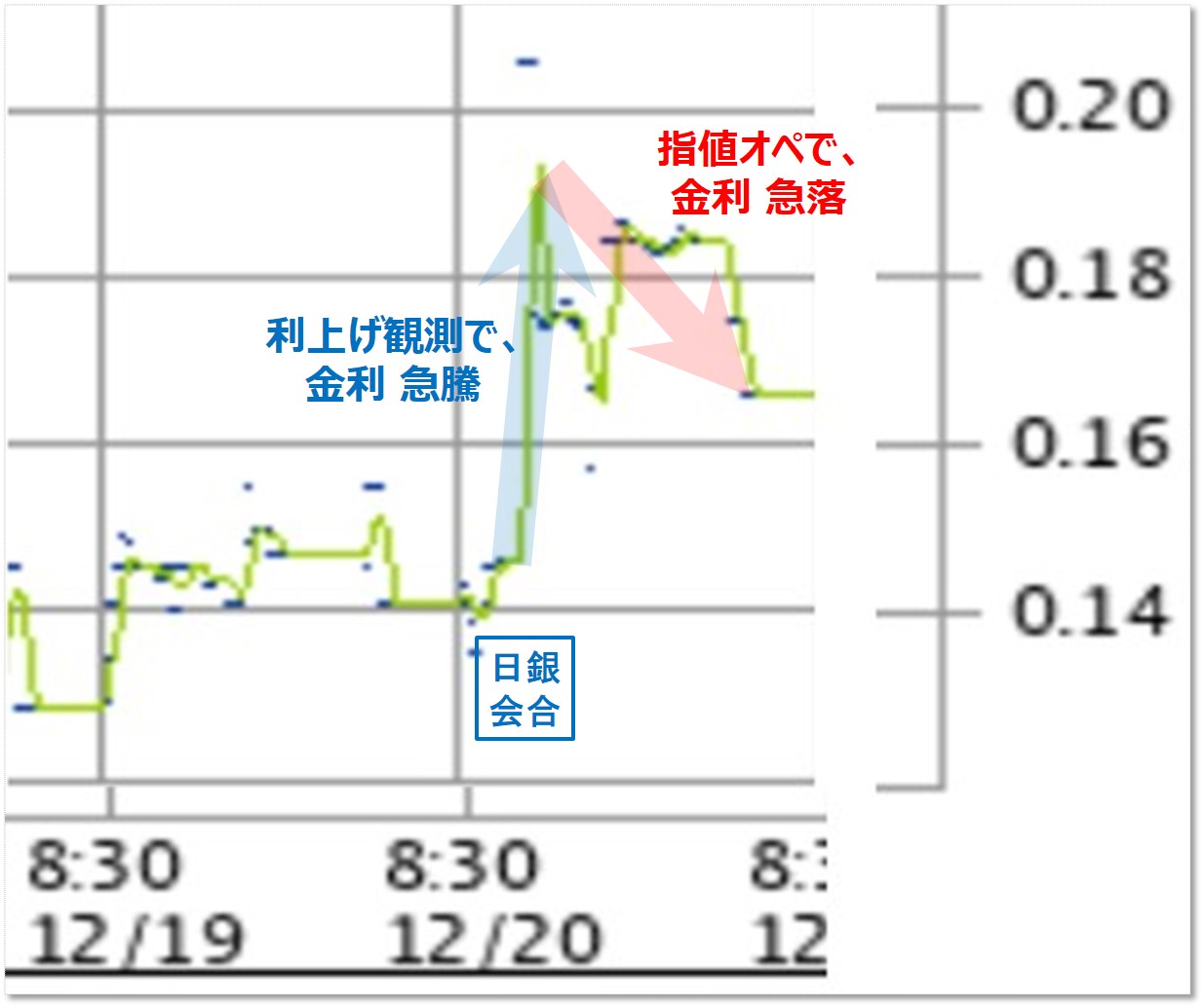 ※下記出典に矢印等を加入
※下記出典に矢印等を加入
※出典: マーケット|SBI証券|日本国債5年
-- 消費者 経済 総研 --
Q: 12月20日の日銀会合の後、
日銀の黒田総裁は、どう言っているか?
↓
A:12月26日に、経団連で、講演した。
下記のように、発言した。
「国債買入れの月間予定額を、
従来の7.3 兆円から9兆円程度に増加する事で、
低水準のイールドカーブを維持します。..
10年以外の各年限においても、機動的に買入れ額
の更なる増額や指値オペを..する事としました。
これらの措置によって、
低水準のイールドカーブを維持しつつ、
より円滑なカーブの形成を促す..。
実際、決定後の金融市場調節のもとで、
歪みが生じていた10年物金利は上昇しましたが、
それ以外の年限の上昇は抑えられています。」
※(..は中略箇所を示す。)
※出典:日銀|日本経済団体連合会審議員会における講演
※「利下げ」と、「上昇を抑える」
日銀は、国債買入れの増加と、指値オペで、
「金利上昇を、抑える」としている。
つまり表現としては、「金利上昇を、抑える」だ。
この項では、「利下げ」と表記している個所がある。
過去の同程度の金利水準で、
20年債の指値オペは、実施されなかった。
だが今回は「20年債の指値オペ」があったので、
この点では「積極的な利下げ姿勢」と見える。
「利下げ」との表記もしたが、「金利上昇を抑える」
との見え方もある。
◆日銀は、社債市場を、正常化したい?
-- 消費者 経済 総研 --
Q:企業への融資は、借金以外に、社債もあるな。
↓
A:そうだ。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「借金」と「社債」 の違いは?
↓
A:例として、100万円の社債が、
10年、0.9%だとして、話をする。
企業が100万円の社債を、金利0.9%で販売する
↓
購入者は、100万円の購入代金を、企業へ払う
↓
これで、企業は100万円を、借りた状態になる
↓
同時に、購入者は企業へ100万円を貸した状態
↓
購入者(貸し手)は、年9千円の利息が、もらえる
↓
満期10年後、借り手(企業)は貸し手(購入者)へ、
100万円を、払って、返済完了になる
なお、社債は、満期期限の10年を待たずとも、
その社債を、市場で売却し、中途換金できる。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:社債は、個人でも、購入できるか?
↓
A:できる。 先日のソフトバンクの
個人向け社債は、大人気だった。
※期間:約7年、利率2.84%の第58回社債は、
大好評につき完売した。
※出典: SBI証券|
ソフトバンクグループ第58回無担保社債
-- 消費者 経済 総研 --
Q:10年国債が、不自然に、低金利であるが、
そのデメリットは、何か?
↓
A:国債金利は、社債の金利の相場の基礎である
10年国債の金利が、不自然に低いなら、
10年社債の金利も、不自然に低くなる。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:社債は、10年期限が、多いのか?
↓
A:企業が、社債を発行し、お金を借りる際の
期間の平均は、約10年だ。※
10年金利が、不自然に低金利なら、
10年で、お金を貸す者が、減ってしまう。
※出典:日本経済新聞|2017/1/13|社債長期化..平均年限9.9年
-- 消費者 経済 総研 --
Q:10年以外の国債の購入増加で、
10年以外は、金利低下を図る件は、
黒田総裁は、どう説明したか?
↓
A:この件は、黒田総裁は、下記で説明した。
「今回の見直しは
10年金利の変動幅を拡大するだけではなくて、
国債買入れの大幅な増額..機動的な追加買入れ..
の実施..によって..
整合的なイールドカーブの形成を促す..」
「より円滑にイールドカーブが形成されれば、
各年限間の金利の相対関係.市場機能は改善する」
「国債の買入れも増額し..指値オペを
10 年物のみならず他の年限でも
必要があればやる」
-- 消費者 経済 総研 --
Q:不自然な国債金利が、
社債金利に、影響する事は、どう説明された?
↓
A:黒田総裁は、下記の通り説明した。
「国債金利は、
社債や貸出等の金利の基準となるものですので、
こうした状態が続けば、企業の起債など
金融環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
本日の決定は、こうした情勢を踏まえたものです。」
「歪んだ形が続くと、..国債の金利.が.
社債とか銀行の貸出の基準になっていますので、
基準がはっきりしないというか、
マーケットに信用されないということになると、
企業金融全体にとって非常にマイナスになります..
国債という金利の..基準になるところが
歪んだ形になっているものを正して、
..企業金融に緩和の効果がスムーズ円滑に..する」
(総裁発言の ..は、中略箇所を示す。)
-- 消費者 経済 総研 --
Q:社債への悪影響の裏付けは、あるのか?
↓
A:アンケートなどでも、悪影響が指摘された。
下記↓が、黒田総裁の説明だ。
「10年の社債を避けるとか、色々な影響が..ある。
国債・社債等の債券市場の機能度、
これが色々なアンケート調査でも相当低下して
いるというデータが出ており..
われわれの検討でも国債のイールドカーブの
歪みというものが、様々な影響を与えている」
-- 消費者 経済 総研 --
Qそれでも、利上げに見えるが、どうなのか?
↓
A:黒田総裁は、「利上げ ではない」と、
繰り返し、説明している。
しつこいから、いらだった下記の回答もある。
「金利を..引き上げようとか、引き締めようとか、
そういう..意図は全くないということは、
重ねて申し上げられます。」
(総裁発言の ..は、中略箇所を示す。)
-- 消費者 経済 総研 --
Q:だいたい、わかった。
ここまでの内容の根拠を、見たい。
↓
A:日銀の記者会見の議事録が、わかりやすい。
下段の◆に、掲載しておく。
黒田総裁は、 「 利上げ ではない 」と、
繰り返し、強調している。
今回変更は、「 企業金融の円滑化 」だと、
ちゃんと、説明している。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:結論として、日銀の企業金融の円滑化とは、
既述の通り、10年債券の金利の正常化だな?
↓
A:そうだ。 10年社債の市場が、正常化すれば、
企業は、10年期限の資金調達がしやすくなる。
今までは、10年社債が、不自然に低金利だが、
正常金利なら、お金を貸す者が増えるからだ。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:それにしても、世の中の金融経済の情報は、
誤解や、間違いが、多いな。
↓
A:そうだ。 ポジショントーク、プロパガンダ
知識不足での誤情報が多い。
有名な経済学者でも、そういう場合もある。
消費者 経済 総研 は、経済の真実を、
今後も、わかりやすく解説していきたい
- 中立・客観 の ポジションで 解説 -
- 当総研は、ポジショントークを、やらない -
- とことん わかりやすい 経済解説 -
-- 消費者 経済 総研 --
◆日銀政策決定会合の内容の出典:
日銀|総裁定例会見(12月20日)

- ■Vol.1 2022/6/21投稿 日銀会合
- 6月15、16日(水~木)に、米国で、FOMCが、あった。
6月16、17日(木~金)に、日銀の政策会合があった。
日本の金融政策を、決定する会議だ。
重要な会議である。
筆者(松田)は、6/17(金)日銀公表の資料も読んだ。
資料公表の後での「黒田総裁の 記者会見」も、
筆者(松田)は、ライブ中継で、見ていた。
ここからは、
6/17の日銀の政策決定会合を、解説する。
筆者(松田)は、35年以上前に、慶応大学 経済学部
に入学以来、経済を研究している。
しかし本ページは、経済学の知識なしでも
わかるような簡単解説としている。
経済の解説では、筆者の解説は、
「とことん わかりやすい」と思っている。
各Q&Aを、さらに掘り下げて、知りたい場合は、
本ページの下段のリンク先を、ご覧頂きたい。

- ■日銀とは?|日銀の政策は変更?
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:そもそも「日銀」は、会社か? 役所か?
↓
日銀は「会社」である。しかも上場している会社だ。
結局は、買わなかったが、筆者(松田)は、
日銀の株(出資証券)の購入を、検討した事もあった。
※「日銀は会社」の詳細は、ページ下段を、ご覧頂きたい
-- 消費者 経済 総研 --
Q:最近は、黒田総裁が、批判されている。
その理由は、何か?
↓
A:6月6日の講演会で、黒田総裁が、
「家計の値上げ許容が改善」と言ったからだ。
この発言は「消費者への配慮が欠けている」
と、筆者(松田)も思う
-- 消費者 経済 総研 --
Q:6/17に「日銀の政策会合」が、開催された。
批判を受けて、政策は、どう変更されたのか?
↓
A:政策の変更は、無い。 低金利政策が継続だ

- ■日銀は 「円安はプラス」 と考える?
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:円安が進んだ。 円安は、日本にマイナスでは?
↓
A:違う。日銀は下記の見解だ。
「 円安は、日本の経済全体には、プラス 」
-- 消費者 経済 総研 --
Q:円安で、「輸入物価UP」なので、マイナスでは?
↓
A:違う。 「円安で、輸出額UP」なので、プラスだ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:円安と、輸出・輸入の「損と得」の関係は?
↓
A:輸出には、円安が 得 だ
輸入には、円安が 損 だ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「円安で得」したのは、どこか?
↓
A:例えば、トヨタ自動車だ。
円安効果もあって、21年4~22年3月の期は、
トヨタ自動車は「過去 最高利益」を出した。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:コロナ禍で最高益なのは、トヨタだけでは?
↓
A:違う。 21年4~22年3月の期は、
上場企業の 約3割 もが、最高益を出した。
最高益が3割にも至ったのは、30年ぶり(出典後掲)
理由は、主に「 円安効果 」だ。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:企業には、「円安はプラス」という事だな?
↓
A:そうだ。
日本の上場企業は、輸出型の製造業が多い。
多くの上場企業には「円安は、強い追い風」で
上場企業は、円安で、儲かったのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:上場企業には 「円安が得」は、わかった。
では、一般の消費者には、円安は、どうなのか?
↓
A:消費者の視点での円安は、下段で解説する

- ■輸出はプラス、輸入はマイナスか?
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:最近は、輸出と輸入 どちらが多い?
↓
A:21年8月から、モノの貿易は、
輸入の方が、輸出より多い。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:では「輸入の損」と「輸出の得」どちらが大きい
↓
A:最近は、輸入 > 輸出 なので、
「輸入の損> 輸出の得」だ。
よって、円安は損だ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:貿易赤字だから、円安は、「損」ということか?
↓
A:そうだ。
なお、貿易黒字なら、円安は、「得」だ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:最近は貿易赤字だから、「円安は悪い」のでは?
↓
A:違う。
それでも円安は、日本全体には、プラスだ。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:全体でプラスとは、どういうことか?
↓
A:「モノの貿易」だけ見ても、不十分だからだ
次項で、解説していく

- ■貿易収支と、経常収支の 違いは?
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:[1]モノの貿易以外に、何があるのか?
↓
A:[2]サービスの貿易や、[3]所得収支がある
-- 消費者 経済 総研 --
Q:[1] のモノ貿易 だけでなく、
[1]+[2]+[3] の全体では、どうなのか?
↓
A:[1]+[2]+[3]を、「経常収支」という。
経常収支では、黒字なのだ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「モノの貿易」は、赤字だが、
広範・全体の貿易では、黒字ということか?
↓
A:そうだ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:では全体で黒字なら、円安は日本に有利か?
↓
A:そうだ。 円安は日本全体に、プラスだ。
つまり、日銀の見解は、正しいのだ

- ■海外シフトで、「直接投資」に注目?
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:前項の [3] の 「所得収支」 とは何か?
↓
A:直接投資収益などだ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「直接投資収益」とは何か?
↓
A:海外の子会社の儲けが、
日本国内の親会社へ回る配当金などだ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:近年は「直接投資」の言葉を、聞く事が増えた。
それは、なぜか?
↓
A:日本企業の工場が「海外シフト」したからだ。
海外で生産した商品が、海外で販売される。
その海外での儲けの行き先が、どうなるかだ。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:海外の子会社の儲けは、
「海外で再投資」 される分も、あるのか?
↓
A:ある
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「海外で、再投資するので、
海外での儲けは、日本に戻らない」
上のコメントを、聞いたことがある。
ならば、海外での儲けは、
円に変換されないから、円安メリットなしか?
↓
A:違う。 円安メリットは、引き続きある。
「経常収支」から「再投資分」を、引いても、
「経常収支」は、黒字だからだ
下段に掲載中の「再投資・経常収支」の
額・グラフを、ご覧頂きたい

- ■円安がプラス との 試算・計算は?
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:「円安が、日本全体に プラス」を、
言葉での説明に加え、計算・数値で理解したい
↓
A:① 日銀の 計量モデルでの試算や、
② 内閣府の 経済社会総合研究所の試算でも、
「円安は、全体にプラス」との結果が出ている。
下段に、この2つのリンク先を、掲載してある
-- 消費者 経済 総研 --
Q:上のの2つの計量モデル(①②)よりも、
簡単・単純な計算式は、あるか?
A:1分でわかる計算式を、別ページに掲載中だ。
本ページの下段のリンク先を、ご覧頂きたい

- ■日銀は、円安の為替を、どうする?
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:6/17の「記者会見」で、黒田総裁は、
円安と為替に関して、何を語ったか?
↓
A:筆者(松田)は、会見のライブ中継を、見ていた。
(ちなみに、地上波ではなく、ネット配信だ。
ネット配信では、複数の東京キーTV局が中継する)
(ドル円などの)為替の動向には、
「注視する」との回答が、続いた。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:為替に、「注視」ではなく、「介入」しないのか?
↓
A:日銀は、ドル円等の為替に、介入しない。
為替は、「政府の仕事」である。
為替は、中央銀行の仕事ではない のだ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:では、中央銀行の仕事は、何か?
↓
A:米国の中銀であるFRBの仕事は、
「物価の安定と、雇用の安定」だ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:日本では、どうか?
↓
A:日本の中銀の日銀の仕事は「物価の安定」だ。
日本での「雇用の安定」は、政府の仕事である。
日銀の役割は、法律で定められている。
その根拠法は、本ページ下段を、ご覧頂きたい

- ■日銀が、金利を上げない 理由とは?
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:米国の中央銀行のFRBは、どうした?
↓
A:3回目の利上げを、6/16(木)に、発表した。
0.75%もの金利を、上げた
-- 消費者 経済 総研 --
Q:諸外国が、続々利上げを、している。
なぜ日銀は、利上げを、しないのか?
↓
A:日本経済は、諸外国より弱い。
利上げをしたら、景気は、ますます低迷する
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「利上げで景気低迷」の具体例を、知りたい
↓
A:例えば、住宅だ。
金利UPで、住宅ローンの支払いが、増える
支払総額が増え、住宅の売上が、低迷する
-- 消費者 経済 総研 --
Q:その低迷の影響は、住宅業界だけか?
↓
A:違う。
施工業界、引越し業界、家電・家具の
業界など、様々な業界に、影響する。
それらの業界が、仕入れる原材料や部材の
各業界にも、波及する。
様々な業界へ、影響するのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:住宅関連の業界の話は、理解できた。
他にも、利上げの影響の業界は、あるか?
↓
A:自動車の業界も、そうだ。
マイカーローンの金利が上がれば、
自動車の業界も、影響を受ける。
住宅のケースと同じく、
自動車に関する様々な業界の売上に影響する
-- 消費者 経済 総研 --
Q:利上げで、業界の売上が、低迷したらどうか?
↓
A:会社の利益が、減ってしまう。
利益が減れば「給料を減らす」きっかけとなる
-- 消費者 経済 総研 --
Q:日本で、利上げを求める声もあるが、どうか?
↓
A:企業業績も、給料も、下がる きっかけになる。
大企業だけでなく、消費者も、損をしてしまう
-- 消費者 経済 総研 --
Q:企業の売上の低下+消費者の賃金の低下
のきっかけ以外に、他にデメリットはあるか?
↓
A:住宅ローンが、上昇する。
金額が大きいから、消費者ダメージは大きい
-- 消費者 経済 総研 --
Q:利上げが、景気を冷ますのは、理解した。
では、諸外国が利上げしたのは、なぜか?
↓
A:インフレ対策だ。
諸外国は、インフレに、襲われている
金利が上がれば、住宅への需要は、減少する。
高騰した住宅価格を、冷やし、
さらに追って、様々な物価が、冷やされていく
-- 消費者 経済 総研 --
Q:日本も、値上げラッシュが、続いている。
日本も、物価上昇なのに、なぜ、利上げしない?
↓
A:たしかに日本も、値上げ傾向にあるが、
まだ、懸念水準のインフレではない。
物価上昇率は、米国は8%台、英国は9%台だ。
日本は、2%台でしかない。
※下図は2022年4月だが、米国の5月は8.6%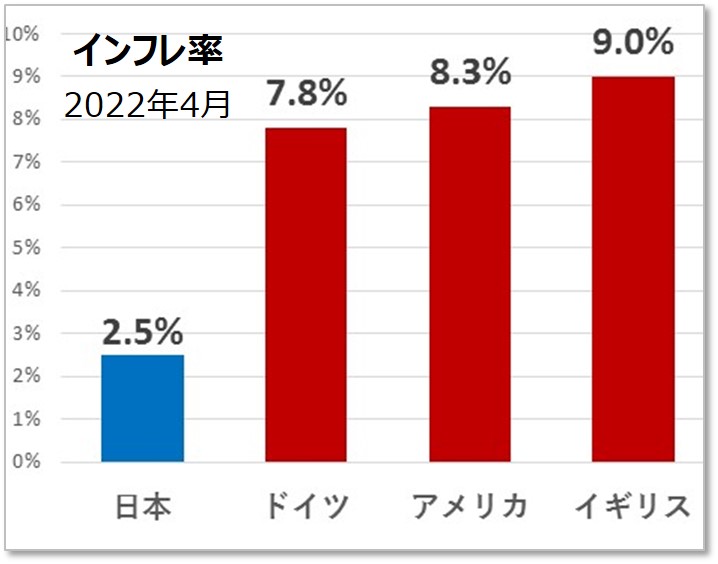
-- 消費者 経済 総研 --
Q:日銀は、意地でも、利上げしないのか?
↓
A:違う。
利上げしないのは、意地ではない。
日銀には、「金融政策の基準」がある。
基準に達するまでは、利上げしない だけだ。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:その基準とは、何か?
↓
A:日銀の基準を、別ページに掲載している。
本ページの下段のリンク先を、ご覧頂きたい

- ■全体がプラスでも、消費者は?
- -- 消費者 経済 総研 --
Q:円安は「全体にプラス」 なのは、理解した。
しかし消費者は、値上げラッシュで、つらい。
消費者には、やはり「円安は悪」だ
↓
A:違う。
消費者に対して、悪いのは、円安ではない。
悪いのは、「円安」ではなく、「〇〇」だ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:その「悪い 〇〇」とは、何か?
↓
A:別ページに掲載している。
本ページの下段のリンク先を、ご覧頂きたい

- ■リンク、詳細情報、根拠は?
- -- 消費者 経済 総研 --
Q1:日銀は、役所ではなく、「上場の会社」とは?
↓
日銀は、役所ではないから、
日銀の役員・職員は、公務員ではない。
※だが、公共性高いので、「みなし公務員」の扱い。
上場している市場は、ジャスダック市場だったが、
2022年度からは、プライム市場になった。
結局は、買わなかったが、筆者(松田)は、
日銀の株(出資証券)の購入を、検討した事もあった。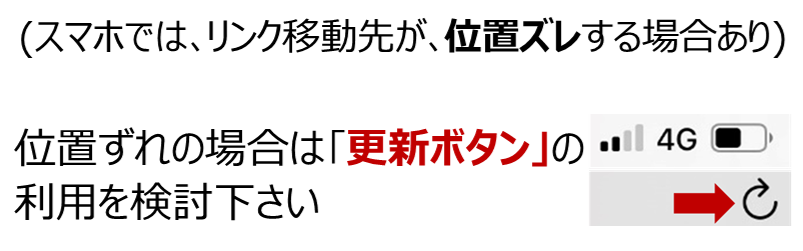
- 詳しくは、下記をご覧頂きたい
- ◆日銀は、上場会社|政府と日銀は、親子の関係?
-- 消費者 経済 総研 --
Q2:「上場企業の 約3割 もが、最高益」の出典は?
↓
「資源高や円安が追い風となり、
2022年3月期に最高益となった企業の比率は、
30%と約30年ぶりの高水準。」
※出典:日本経済新聞 電子版|2022年5月14日
-- 消費者 経済 総研 --
Q3:6/17(金)の日銀の政策会合のポイントは?
↓
短期金利:-0.1%のマイナス金利のまま
長期金利:10 年物国債金利が、ゼロ%程度のまま
従来通りで、変更なしだ。
下が、その会合のポイントになる部分だ
「日銀公式サイト|当面の金融政策運営について」
-- 消費者 経済 総研 --
Q4:日本の中銀である日銀の役割の「根拠法」は?
↓
日本での「雇用の安定」は、政府の仕事で、
日銀の仕事は「物価の安定」
※日本銀行法 第二条
日本銀行は、...物価の安定を図ることを通じて
国民経済の健全な発展に資することをもって、
その理念とする。
(...は省略箇所。 以下同じ)
-- 消費者 経済 総研 --
Q5:「為替介入は政府の仕事」の根拠法は?
↓
外国為替及び外国貿易法7条、
特別会計に関する法律77条
日本銀行法 36条,40条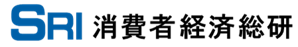 Q6:「経常収支が、黒字なら、日本にプラス」を、
Q6:「経常収支が、黒字なら、日本にプラス」を、
計算や数値で、理解するリンク先は?
↓
① 日銀のVar計量モデルは、次の結果が出た。
「円安はGDP・GNIに、統計的に有意にプラス」
② 内閣府の経済社会総合研究所の試算でも、
「円安は、GDPにプラス」との結果が出ている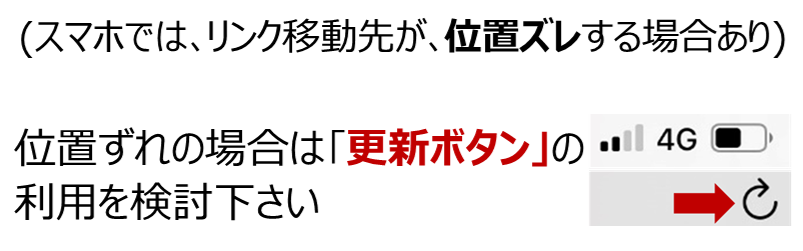
- 詳しくは、下記をご覧頂きたい
②は、内閣府HP直リンクで、14p目を参照 - ◆①日銀|Var計量モデル|悪い円安は嘘?
◆② 内閣府|日本経済 マクロ計量 モデル(14P)
-- 消費者 経済 総研 --
Q7:この2つの計量モデルよりも、簡単な計算は?
↓
別のページに、簡単な計算を、掲載してある。
- 詳しくは、下記をご覧頂きたい
- ◆円安・円高|輸出・輸入の計算例
-- 消費者 経済 総研 --
Q8:[1]+[2]+[3]の「経常収支」の中身を
もう少し詳しく知りたい
↓
- 詳しくは、下記をご覧頂きたい
- ◆経常収支・貿易収支|ドル円予測|
-- 消費者 経済 総研 --
Q9:経常収支 と 再投資収益 の関係は?
↓
日本企業の海外シフトで、海外での儲けが増えた。
海外で儲けたお金を、
海外で再投資する分が、「再投資収益」だ。
海外シフトで、「再投資収益」は、大幅増加した。
1996年→2021年の間で、7.5倍の規模になった。
一方、「経常収支」は、96~21年で、2倍の伸びだ。
しかし、海外シフトが進んでも、
経常収支 > 再投資収益 である。
つまり、経常収支は、再投資分を引いても、黒字だ。
黒字なので、「円安は日本に有利」だ。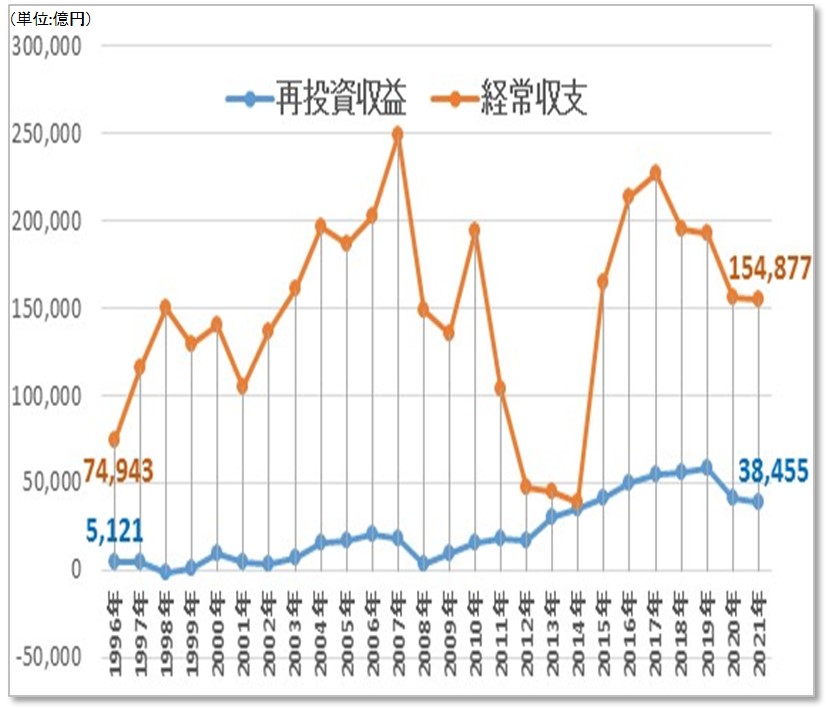 ※下記出典から消費者 経済 総研がグラフ作成
※下記出典から消費者 経済 総研がグラフ作成
※出典:財務省|国際収支総括|第一次所得収支
-- 消費者 経済 総研 --
Q10:日銀には、金融政策の基準があり、
基準に達するまでは、利上げしない
とのことだった。その基準とは、何か?
↓
物価上昇率が、「安定的に 2%超」だ
- 詳しくは、下記をご覧頂きたい
- ◆日本の金利は? 安定的に2%超|ドル円予測|
-- 消費者 経済 総研 --
Q11:消費者に対して、悪いのは、円安ではない。
悪いのは、「円安」ではなく、「〇〇」だ
その「悪い 〇〇」とは、何か?
↓
- 詳しくは、下記をご覧頂きたい
- ◆悪い円安論は 嘘? |悪い円安,良い円安とは?
-- 消費者 経済 総研 --
Q12:日本の物価上昇は、どこまで、進むか?
その予測の値は?
↓
- 詳しくは、下記をご覧頂きたい
- ◆2022年 経済予測|日本の物価の見通し・予測
-- 消費者 経済 総研 --
Q13:日本人の給料は、2022年は、どうなるか?
その予測の値は?
↓
- 詳しくは、下記をご覧頂きたい
- ◆2022年 経済予測|日本の賃金の見通し・予測
-- 消費者 経済 総研 --
Q14:円安は、どこまで、進むか?
その予測の値は、
↓
- 詳しくは、下記をご覧頂きたい
- ◆2022年 経済予測|為替(ドル円)の見通し
-- 消費者 経済 総研 --
Q15:その他、「経済テーマ」のページを読みたい
↓
- 下記のリンク先の「一覧」から、ご覧頂きたい
- ◆経済テーマのページ一覧表

| ■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので、 「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆である事を念頭に置いて下さい。 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、 対応して下さい。また「免責事項 」をお読みください。 ■引用 真っ暗なトンネルの中から出ようとするとき、 出口が見えないと大変不安です。 しかし「出口は1km先」などの情報があれば、 真っ暗なトンネルの中でも、希望の気持ちを持てます。 また、コロナ禍では、マイナスの情報が飛び交い、 過度に悲観してしまう人もいます。 不安で苦しんでいる人に、出口(アフターコロナ)という プラス情報も発信することで、 人々の笑顔に貢献したく思います。 つきましては、皆さまに、本ページの引用や、 URLの紹介などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件をご覧下さい。 |
- 【著作者 プロフィール】
- ■松田 優幸 経歴
(消費者経済|チーフ・コンサルタント)
◆1986年 私立 武蔵高校 卒業
◆1991年 慶応大学 経済学部 卒業
*経済学部4年間で、下記を専攻
・マクロ経済学(GDP、失業率、物価、投資、貿易等)
・ミクロ経済学(家計、消費者、企業、生産者、市場)
・労働経済
*経済学科 高山研究室の2年間 にて、
・貿易経済学・環境経済学を研究
◆慶応大学を卒業後、東急不動産(株)、
東急(株)、(株)リテール エステートで勤務
*1991年、東急不動産に新卒入社し、
途中、親会社の東急(株)に、逆出向※
※親会社とは、広義・慣用句での親会社
*2005年、消費・商業・経済のコンサルティング
会社のリテールエステートに移籍
*東急グループでは、
消費経済の最前線である店舗・商業施設等を担当。
各種施設の企画開発・運営、店舗指導、接客等で、
消費の現場の最前線に立つ
*リテールエステートでは、
全国の消費経済の現場を調査・分析。
その数は、受託調査+自主調査で多岐にわたる。
商業コンサルとして、店舗企業・約5000社を、
リサーチ・分析したデータベースも構築
◆26年間の間「個人投資家」としても、活動中
株式の投資家として、
マクロ経済(金利、GDP、物価、貿易、為替)の分析や
ミクロ経済(企業動向、決算、市場)の分析にも、
注力している。
◆近年は、
消費・経済・商業・店舗・ヒットトレンド等で、
番組出演、執筆・寄稿、セミナー・講演で活動
◆現 在は、
消費者経済総研 チーフ・コンサルタント
兼、(株)リテール エステート リテール事業部長
◆資格は、
ファイナンシャル・プランナーほか
■当総研について
◆研究所概要
*名 称 : 消費者経済総研
*所在地 : 東京都新宿区新宿6-29-20
*代表者 : 松田優子
*U R L : https://retail-e.com/souken.html
*事業内容: 消費・商業・経済の、
調査・分析・予測のシンクタンク
◆会社概要
「消費者経済総研」は、
株式会社リテールエステート内の研究部署です。
従来の「(株)リテールエステート リテール事業部
消費者経済研究室」を分離・改称し設立
*会社名:株式会社リテールエステート
*所在地:東京都新宿区新宿6-29-20
*代表者:松田優子
*設立 :2000 年(平成12年)
*事業内容:商業・消費・経済のコンサルティング
■松田優幸が登壇のセミナーの様子
- ご案内・ご注意事項
- *消費者経済総研のサイト内の
情報の無断転載は禁止です。
*NET上へ「引用掲載」する場合は、
①出典明記
②当総研サイトの「該当ページに、リンク」を貼る。
上記の①②の2つを同時に満たす場合は、
事前許可も事後連絡も不要で、引用できます。
①②を同時に満たせば、引用する
文字数・情報量の制限は、特にありません。
(もっと言いますと、
①②を同時に満したうえで、拡散は歓迎です)
*テレビ局等のメディアの方は、
取材対応での情報提供となりますので、
ご連絡下さい。
*本サイト内の情報は、正確性、完全性、有効性等は、保証されません。本サイトの情報に基づき損害が生じても、当方は一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。
- 取材等のご依頼 ご連絡お待ちしています
- メール: toiawase★s-souken.jp
(★をアットマークに変えて下さい)
電 話: 03-3462-7997
(離席中が続く場合は、メール活用願います)
- チーフ・コンサルタント 松田優幸
- 松田優幸の経歴のページは「概要・経歴」をご覧下さい。