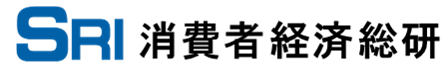財政政策の解説 弱い日本経済,停滞の景気を良くするには?成長に必要な政策,問題点の解決策|消費者経済総研
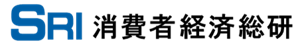
■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 リモートでの出演・取材にも、対応しています  消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆であることを念頭に置いて下さい。 本ページ内容に関しては、自らの責任において対応して下さい。 また「免責事項」をお読みください ■引用 皆さまに、本ページの引用や、 リンク設定などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件 をご覧下さい。 |
- ■連載シリーズ|ニッポン爆上げ作戦
- 【連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦】は、
下記の 全3部で、構成
第1部:収 入 爆上げ 作戦
第2部:景 気 爆上げ 作戦
第3部:生産性 爆上げ 作戦
▼第1部は 「 ニッポン賃金収入爆上げ 」
「賃金」のほか、「賃金以外の総収入」も上げる。
賃金・収入UPの 政策 全10選を発表済み
下記ページで、ご覧頂きたい
【 賃上げ 収入 UP 方法 ベスト10 】
▼第2部は 「 ニッポン景気爆上げ 」
日本の「経済全体」 を UPする。
「消費者も、企業も、株主も」 潤う、全体の底上げ。
経済全体をUPし、GDP成長を、高める。
▼第3部は 「 ニッポン 生産性 爆上げ 」
生産性をUPし、ビジネスでの利益をUP
企業の生産性を上げ、企業の利益を上げる。
ビジネス改善の手法を、提言
※第3部は、今後連載予定
-- 消費者 経済 総研 --
◆消費者・働き手も、企業も、株主も?
【連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦】は、
企業も、株主も、消費者・働き手も、潤う提言だ。
つまり 「 働き手の 賃金UP 」 だけではない。
企業の 売上UP
↓
企業の 利益UP
↓
働き手の 賃金UP + 株主への配当UP・株価UP
↓
個人消費UP (GDPは、6割が個人消費)
↓
GDPのUP
↓
ニッポン全体がUP
このように、各主体、そして全体が、好循環で、潤う
「ニッポン 爆上げ 作戦」である。
この連載シリーズは、政策提言でもある。

- ■【 爆上 作戦| 景気 編 】
- -- 消費者 経済 総研 --
◆第2部は、景気 UP 編
低成長が続く日本経済
そこで第2部は、景気UP編として、
「GDP拡大・企業売上UP・賃上げ」の政策案を、
消費者 経済 総研が、提言する。
-- 消費者 経済 総研 --
◆「高圧経済」へ向けた 「積極財政」
第2部の1~15回は、「高圧経済」へ向けた
「積極財政」という「財政政策」の強化を提言
▼経済政策の中で、「財政政策」が重要?
[1] 金融政策
[2] 財政政策
[3] 成長戦略
上記の3つが、主な経済政策だ。
「アベノミクスの3本の矢」の3ジャンルでもある。
耳に残るネーミングだから、
アベノミクスは、日本で、よく話題に上がった。
だが、経済政策の上記の 3つのジャンルは、
日本独自ではない。
各国で、この3ジャンルの政策運営が、なされる。
先進国での、共通する経済政策の内容だ。
さて、日本でも、値上げラッシュが、続いた。
日銀総裁の「強制貯蓄・値上許容」の発言もあった。
物価上昇の一因である「円安」も、話題になった。
こうした背景から [1]金融政策 が、話題になる。
しかし金融政策には、変更はない。
変更無いのに、金融政策や日銀の話題が多すぎる。
今の日本で、重要なのは、[2] 財政政策 だ
とても重要なのに、注目度が、低すぎる
連載シリーズ|ニッポン爆上げの第2部は、
「その大変重要な 財政政策」 から、始めた。
-- 消費者 経済 総研 --

- ■その1 なぜ「高圧経済」なのか?
- 2022年 8月 7日に 投稿
Vol.5 (第2部の高圧経済の 1回目)
高圧経済・積極財政 の 内容 と メリット
-- 消費者 経済 総研 --
◆「 高圧経済 」 の提言 とは?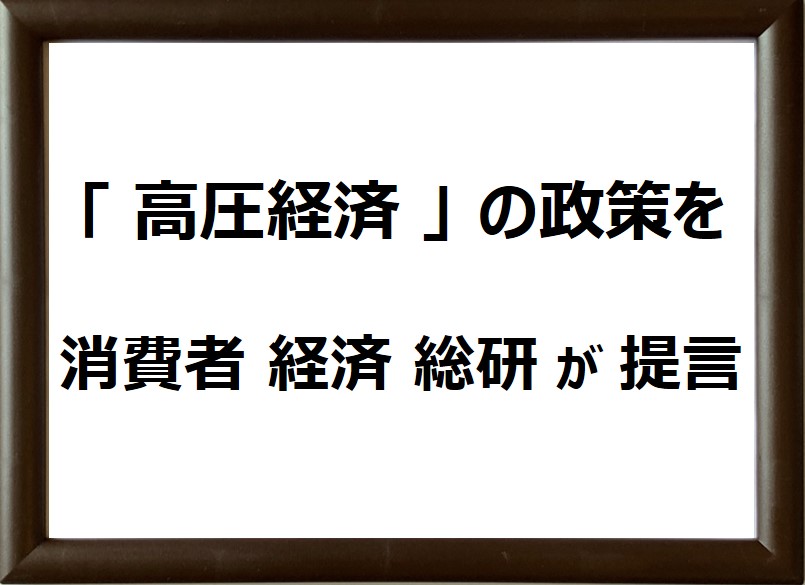
「 経済の 高圧化 」 で、
GDP拡大、企業売上UP、賃金UPの好循環をつくる。
この好循環の政策を、消費者 経済 総研 が、提言。
具体的には、積極財政で、成長分野等へ投資等だ。
「 高圧経済 」 の 政策を
消費者 経済 総研 が 提言
-- 消費者 経済 総研 --
◆「高圧経済」 で 需要を増やす とは?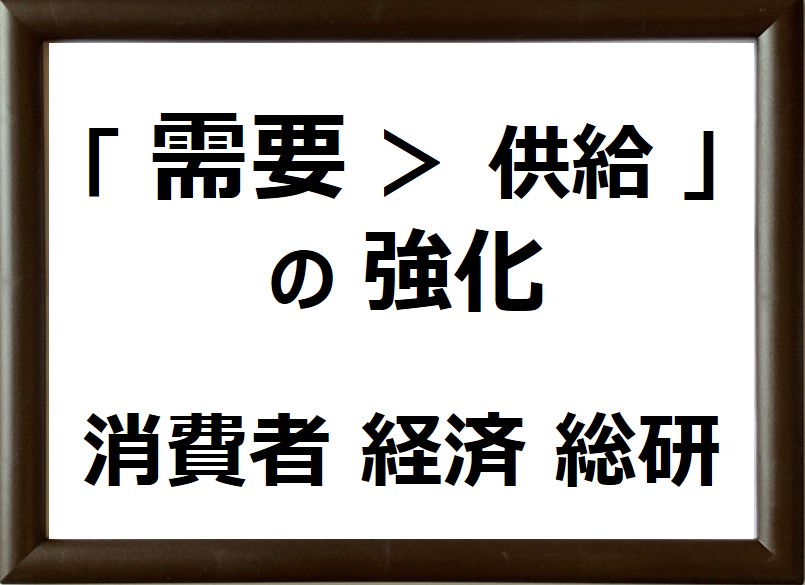
「 高圧経済 」 とは、
「 需要の圧力が、高い経済 」 の状態のこと。
一言で言うと、「 需要> 供給 」 の強化 だ。
政策で意図的に、「需要」を、増やすのだ。
「需要> 供給 」 を 強化 する
▼プラス が プラスを 生む 好循環?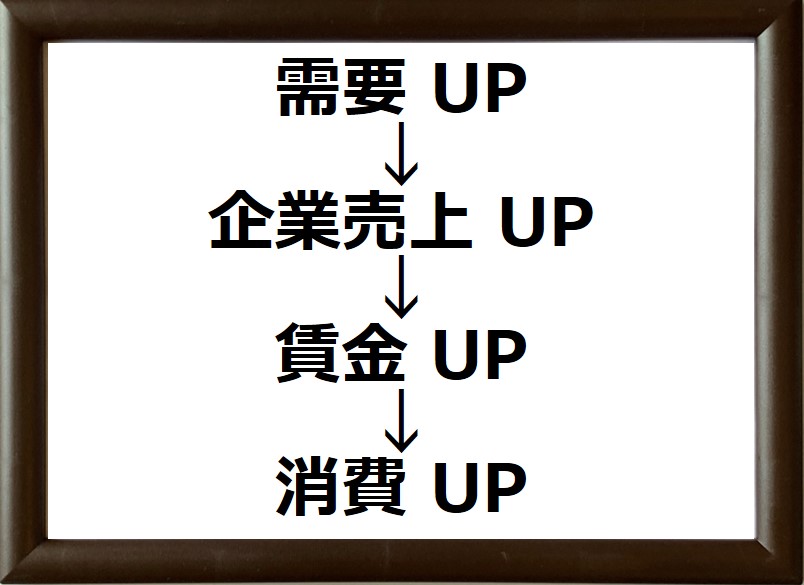
モノ・サービスへの「需要が、増えたら」、どうなる?
↓
モノ・サービスを、供給する企業は、売上がUPする
↓
企業の売上のほか、利益も、増える
↓
利益が増えれば、「賃金UP」の余地が、増える
↓
賃金がUPすれば、消費者に、余裕が生まれる
↓
余裕ができた消費者は、消費を増やす
↓
消費が増えれば、企業の売上は、さらに増加する
↓
企業の売上UPが続けば、さらに賃金UPできる
↓
さらに余裕ができた消費者は、更に消費を増やす
↓
こうして「増加→増加が続く 好循環」が、できる
需要UP → 企業売上UP
→ 賃金UP → 消費UP
「需要> 供給 」 の高圧経済で
プラスが プラスを 生む 好循環へ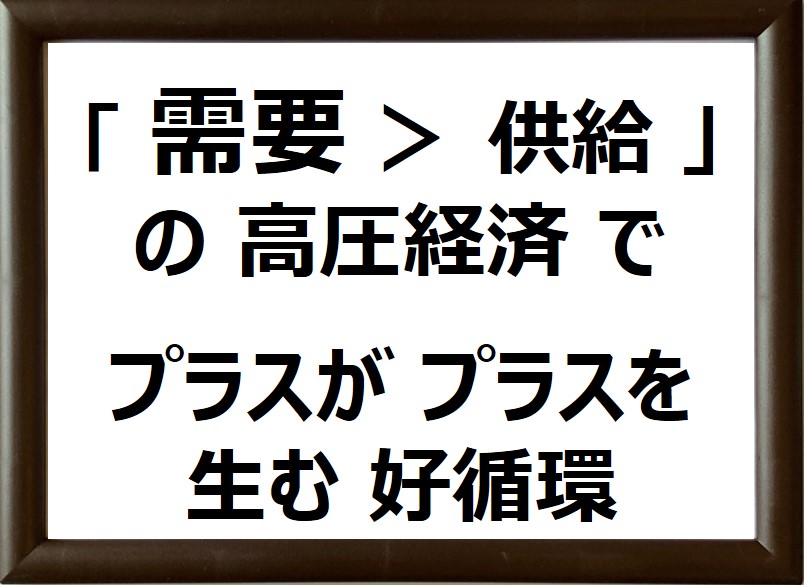
▼GDPは、どうなる?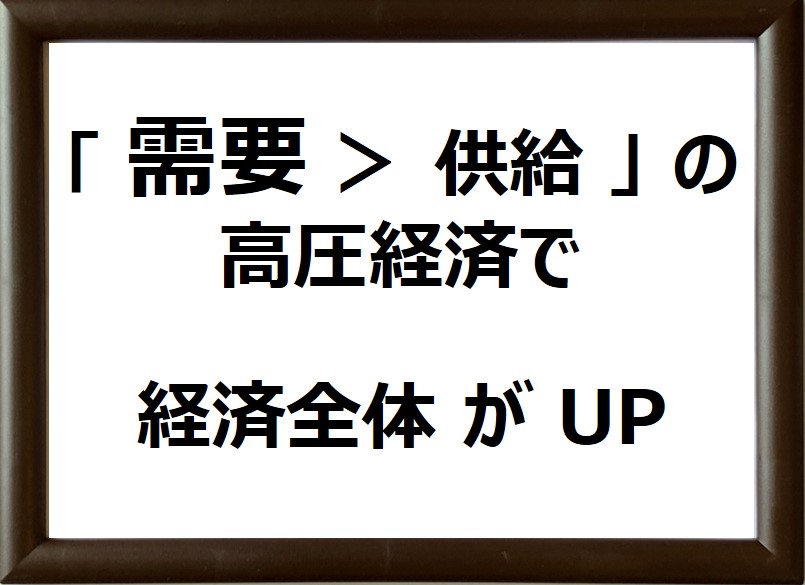
前述の好循環で、「需要UP → 消費UP」があった
↓
個人消費は、GDPの約6割を、しめる
↓
つまり、GDPのメイン・エンジンは、個人消費だ
↓
「消費」が増加すれば、「GDP」も拡大する
↓
賃金UP、企業売上UP、さらに GDPのUP へ
↓
こうして、経済全体が、UPする
「需要> 供給 」 の高圧経済で
経済全体 が UP
-- 消費者 経済 総研 --
◆現状 と 課題 は?
「 供給 >需要」 が
日本の課題?
日本の「需給」 の現状は、どうか?
↓
残念だが、「需要>供給」 ではなく 「供給>需要」だ
↓
需要が弱いのが、日本の課題なのだ
▼需給ギャップとは?
需給ギャップは 、
潜在GDPと 実際のGDP の差?
「需給ギャップ」とは、何か?
↓
需給ギャップは、「GDPギャップ」とも言われる
↓
需給ギャップとは、「潜在GDP」-「実際のGDP」だ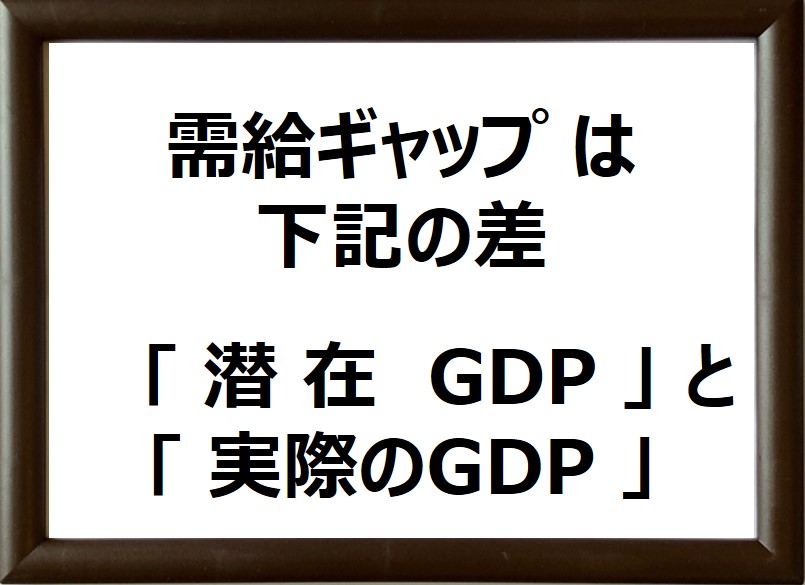
▼「潜在GDP」とは、何か?
↓
潜在的に持っている供給能力でのGDPのことだ。
↓
わかりにくいが、具体的には、どういうことか?
▼「潜在GDP」 の 具体的な 内容は?
・働き手が、フルに仕事に、参加する
・工場などの機械・設備が、フル稼働する
「 潜在GDP 」 は、
フル稼働で、生産・供給された場合のGDPの規模だ
▼需給ギャップは、マイナス?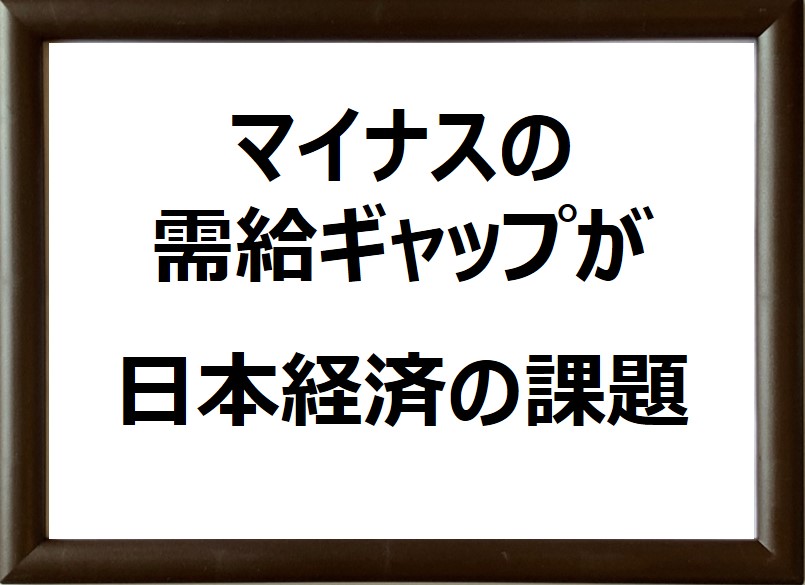
需給ギャップ(潜在GDP-実際のGDP)は、いくらか?
↓
最近は、20兆円前後のマイナスで、推移している。
↓
潜在GDPと、実際のGDPは、どのくらいの金額か?
↓
時期によって、値は異なるが、概数は下記の通りだ
↓
潜在GDP558兆 -GDP537兆 = 需給ギャップ 21兆
↓
558兆円も供給できるが、需要が537兆円しかない
↓
「供給」よりも、「需要」が、21兆円分、弱いのだ
↓
マイナスの需給ギャップが、日本経済の課題だ
マイナスの 需給ギャップが、
日本経済の 課題
▼需給ギャップ 21兆円の 計算は?
2021年のGDPギャップ(-3.7%) ※1 と、
2021年の実質GDPから、潜在GDPを算出
GDPギャップ=(実際GDP-潜在GDP)/潜在GDP ※2
(単位:10億円、GDPは実質GDPベース)
実際GDP:536,771、潜在GDP:557,394
実際GDP - 潜在GDP = -20,624
※1出典: 月例経済報告|内閣府|
GDPギャップ、潜在成長率(令和4年6月24日更新)
※2出典:内閣府|GDPギャップ/潜在GDPの改定について
▼需要が弱いのは、民間部門か?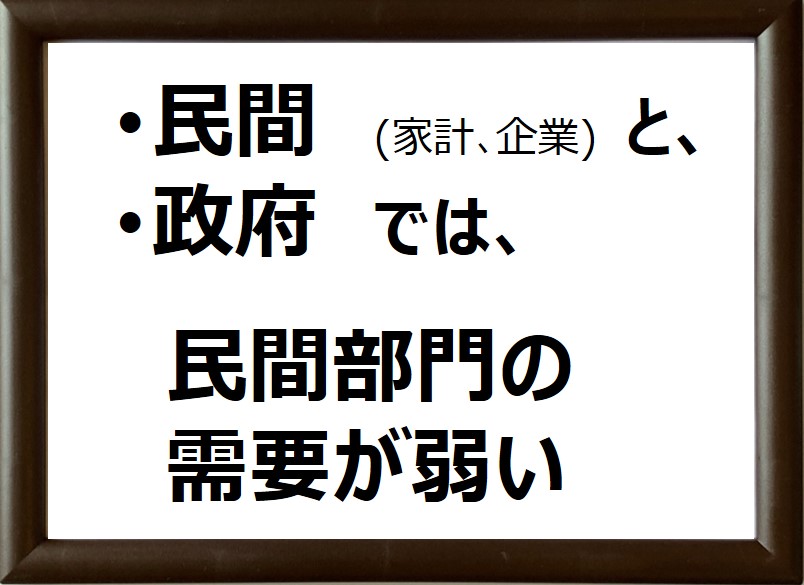
「民間部門」 と 「政府部門」を、見ていく
↓
「民間部門」の経済活動の主体は、どこか?
↓
「家計」 と 「企業」 だ。
↓
民間部門(①家計、③企業)、②政府の3つに別ける
↓
家計、企業、政府の 「3件の経済規模」は、どうか?
↓
GDPの中身・内訳で、見てみよう
↓
下記が、近年のGDPの内訳の概数だ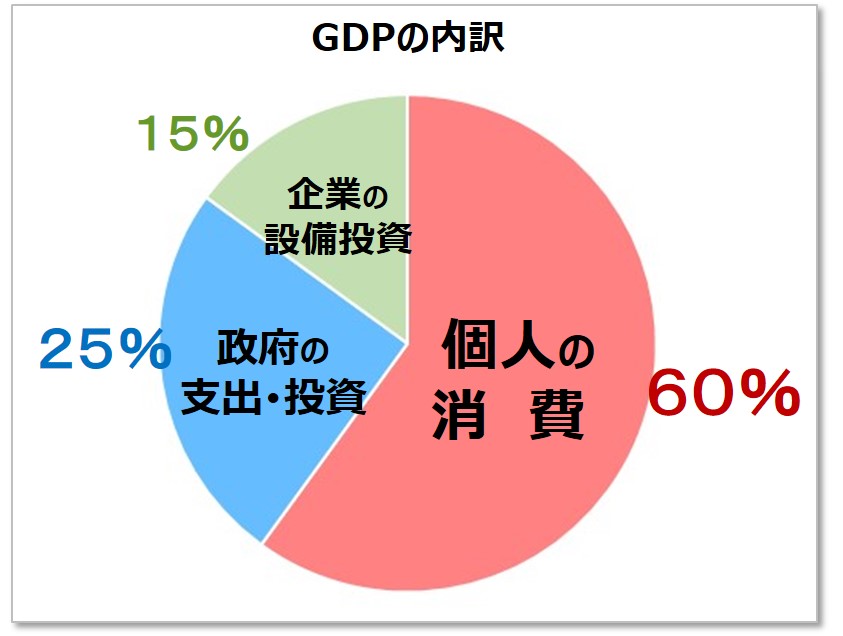
[1] 約 60% : 個人の消費 (家計部門)
[2] 約 25% : 政府の支出・投資 (政府部門)
[3] 約 15% : 企業の設備投資 (企業部門)
[1]+[2] (個人消費+企業投資)が、
日本の民間部門の需要だ
この民間需要は、いまだ、弱さがみられる。
民間(家計、企業)と、政府では、
民間部門の需要が、弱い
▼GDPの 政府部門の 詳細は?
※本稿では、「政府の支出」+「政府の投資」を、
「政府支出」と、略している箇所がある。
GDP統計では、政府部門に、下記の項目がある。
① 政府 最終 消費支出
② 公的 固定資本 形成
③ 公的 在庫変動
本稿では、下記の略称としている。
①を、政府の支出
②を、政府の投資
② (政府の投資) の具体例は、
道路やダム建設などの公共投資・公共事業だ。
① (政府の支出) の わかりやすい具体例は、
〇〇ポイント付与、〇〇補助金などだ。
① (政府の支出) は、他にも様々あるが、
「公共投資以外の政府の出費」と考えた方が早い。
③(公的 在庫変動)は、調整項目であるし、
数値も小さいので、ここでは深入りしないでよい。
※参考文献: Kobe University Repository : Kernel|
近年の政府最終消費支出の動向と民間消費
▼政府の 支出と投資の 大きさは?
政府部門の支出の規模は、
2021年GDP(名目542兆円)を、100%とした場合、
① 政府 最終 消費支出: 21% (116兆円)
② 公的 固定資本 形成: 6% ( 30兆円)
(③の公的在庫変動は、ゼロに近い)
2021年の ①+②は、27%( 21% + 6% )だ。
2019年までの①+②は、25%の年が、多かった。
2020年からコロナ禍で、民間部門が低迷した。
よって民間部門の割合が落ち、
政府部門の割合が、25%→27%へ、上がった。
-- 消費者 経済 総研 --
◆課題への解決策 とは?
▼政府支出UPで、高圧経済へ?
現状の日本は、「 供給 > 低い需要 」 だった
↓
つまり、日本経済は 「低圧状態」 なのだ
↓
「低圧経済」→「高圧経済」 にするには、どうする?
↓
「政府部門の支出・投資」で、高圧にするのだ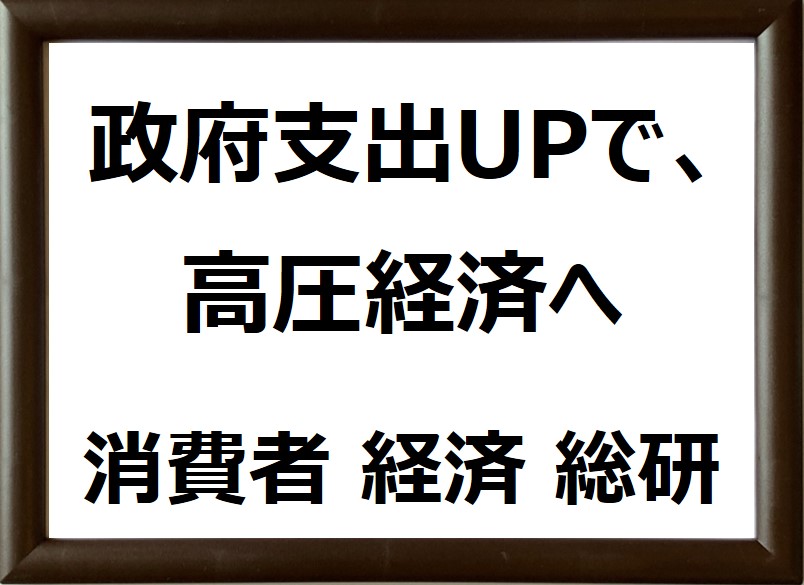
▼言葉を変えて、わかりやすく解説する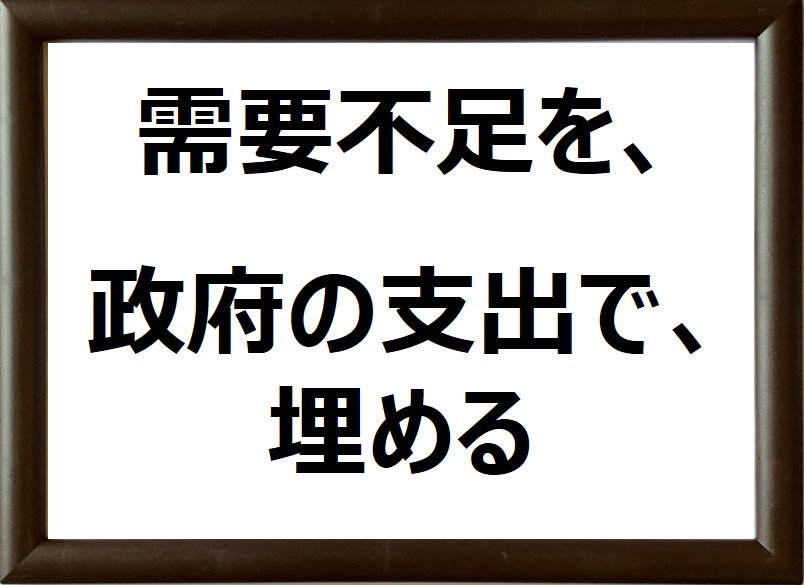
現状は、民間部門の需要(個人消費+企業投資)が弱い
↓
「 供給 > 需要 」で、需要が20兆円不足している
↓
需要不足の解消には、どうするか?
↓
不足分を 「政府の支出の拡大」 で、埋めるのだ
需要不足を、
政府の支出の拡大で、埋める
▼積極財政とは?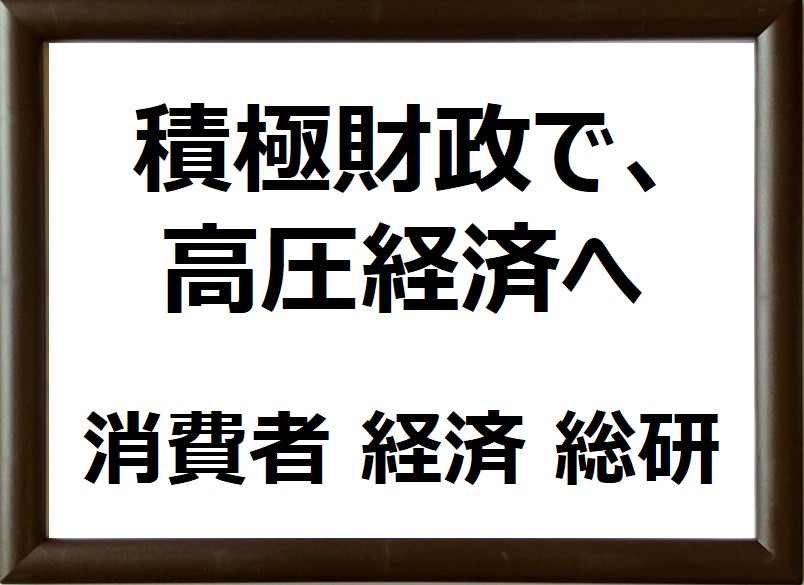
「積極財政」とは、
政府が積極的に、財政支出を、増やすこと。
↓
前項で、「政府支出の拡大」を、述べた
↓
政府が多くのお金を使って、景気拡大させるのだ
↓
不足している需要に、政府の需要を加えるのだ
積極財政で、高圧経済へ
▼「積極財政」の具体例は?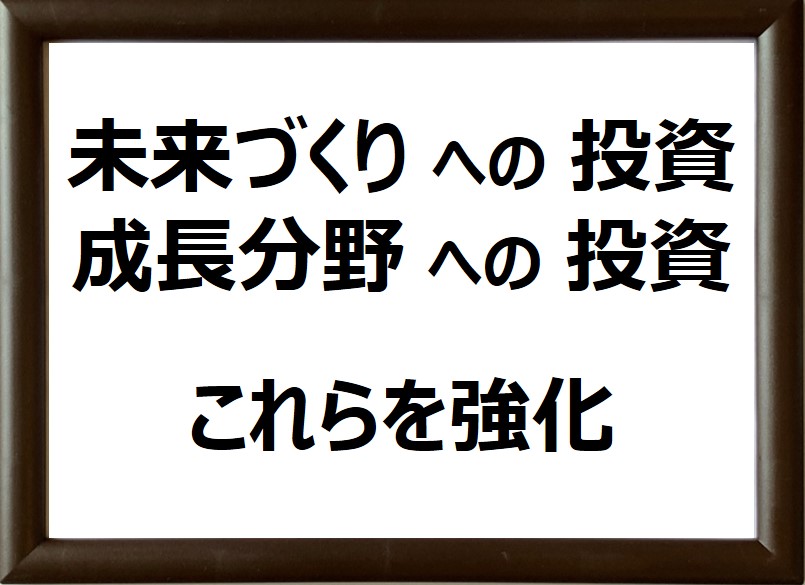
国の予算で「公共事業」などを行っている
↓
その1つの例が、インフラを強靭化する工事だ
↓
防災水準が向上する他、お金が政府→民間へ移動
↓
受託企業の売上や、その社員の給料が、増える
↓
その企業は、仕入先への発注額が、増える
↓
その仕入先企業の、売上・社員の給料が、増える
↓
各社の社員は、増えた給料で、個人消費を増やす
↓
広く世の中へ、経済効果が、循環し広がる
↓
公共事業の対象は、ダムや博物館などか?
↓
コンクリートや、ハコモノが、連想されてしまう
↓
賢い支出(ワイズ・スペンディング)が、必須だ
↓
下記の内容が、その例だ。
▼未来投資
脱炭素化、デジタル化など への 投資
▼人の投資
教育、福祉など
▼クールジャパン等
外人向け観光、アニメ等のカルチャー、和食等
▼防災、経済の安全保障
豪雨被害を救う「防災・強靭化の工事」
半導体、蓄電池など
未来づくり への投資や、
成長分野 への投資を 強化
▼政府支出の増大で、プラスの好循環へ?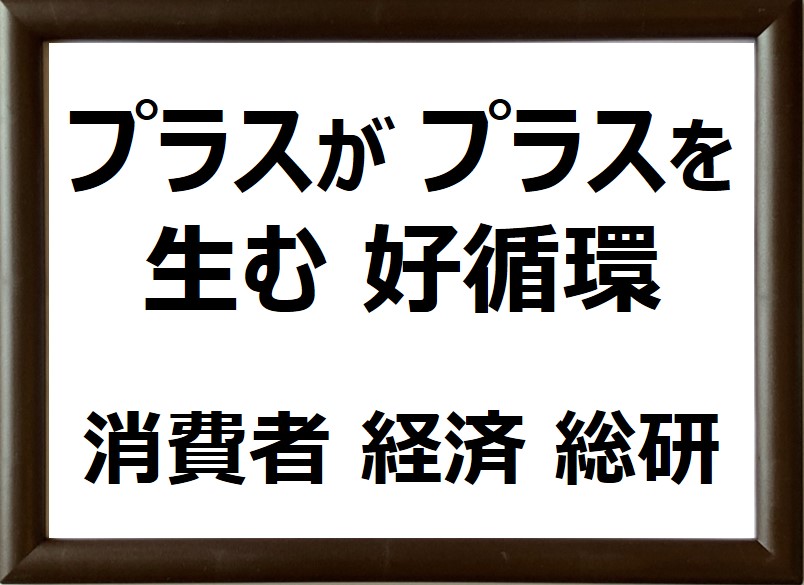
既述の通り、需要が20兆円も、不足している
↓
政府が、20兆円を、超える支出をする
↓
これで需要不足を、埋めることができる
↓
政府から事業を、受託する企業は、売上がUPする
↓
企業売上が増えれば、同社の社員の給料が増える
↓
また、その企業は、取引先への発注額が、増える
↓
その取引先の企業の売上や、社員の給料が増える
↓
その社員は、増えた給料で、個人消費を増やす
↓
消費が増えれば、企業の売上は、さらに増加する
↓
企業の売上UPが続けば、さらに賃金UPできる
↓
さらに余裕ができた消費者は、更に消費を増やす
↓
個人消費は、GDPの約6割を、しめる
↓
GDPのメイン・エンジンは、個人消費だ
↓
「消費」が増加すれば、「GDP」も拡大する
↓
賃金UP、企業売上UP、さらに GDPのUP へ
↓
広く世の中へ、経済効果が、循環し広がる
↓
こうして「増加→増加が続く 好循環」が、できる
プラスがプラスを 生む 好循環 へ
政府の積極財政で、「 需要 > 供給 」へ
そして高圧経済で、経済全体が、UPする
-- 消費者 経済 総研 --
◆財政政策は、重要?
物価上昇の一因である「円安」が、話題になった。
こうした背景から [1]金融政策が、話題になった。
しかし金融政策には、変更はない。
変更無いのに、金融政策や日銀の話題が多すぎる。
今の日本で、重要なのは、[2] 財政政策 だ
とても重要なのに、注目度が、低すぎる
連載シリーズ|ニッポン爆上げの第2部は、
「その大変重要な 財政政策」 から、始めた。
-- 消費者 経済 総研 --
◆「高圧経済」 の 「デメリット」は?
本ページで、「高圧経済」のメリットを解説した。
メリットが、あっても、
デメリットの方が、大きければ、無意味だ。
デメリットは、次回号の続編で、解説する
-- 消費者 経済 総研 --
◆「高圧経済」 の 「財源」は?
「高圧経済」政策は、政府の支出を大幅に増やす。
では、政府の支出の「財源」は、どうなるのか?
「 財源 」 は、次回号の続編で、解説する

- ■関連ページは?
- ▼今回の第2部は 「 ニッポン 景気 爆上げ 」
▼前回の第1部は 「 ニッポン 賃金収入 爆上げ 」
「賃金」のほか、「賃金以外の総収入」も上げる
賃金・収入UPの 政策 全10選を、発表済み
下記ページで、ご覧頂きたい
【 賃上げ 収入 UP 方法 ベスト10 】

- ■「高圧経済」 政策 その2
- 2022年 8月 12日(金)に 新規投稿
Vol.6 (第2部の高圧経済の 2回目)
高圧経済・積極財政の 財源とデメリット
「連載シリーズ|ニッポン 爆上げ作戦」の6回目は、
「高圧経済」の「その2」である。
前回は「高圧経済」の政策内容・メリットを述べた。
今回は、高圧経済の「財源」と「デメリット」だ。
まず先に、「前回号の概略」を、簡単に掲載する。
-- 消費者 経済 総研 --
◆「 高圧経済 」 の政策 とは?(概略 振り返り)
前回号の高圧経済の政策を、簡単に振り返る
↓
日本には、21兆円の需要不足がある
↓
政府の支出を増やして、その需要不足を埋める
↓
つまり 「 積極財政 」 の強化 である
↓
積極財政によって、需要の圧力が強い経済にする
↓
需要の増大で、企業の売上は増え、企業が潤う
↓
賃金UPの余地が、拡大する
↓
個人消費も拡大し、GDPも拡大する
↓
こうしてプラスがプラスを生む好循環の経済に
↓
以上が概略だ。 詳細は「なぜ高圧経済なのか」参照
-- 消費者 経済 総研 --
◆財源は、増税か?
「高圧経済」のために、「積極財政」が必要だった
↓
積極財政で、政府の支出が、増える
↓
政府支出の増加の際の、財源は、何か?
↓
「 増税」 または 「 国の借金の増加 」 である
-- 消費者 経済 総研 --
◆財源が 「増税」 なら、どうなる?
「増税」を実行したら、日本は、どうなる?
↓
法人税の増税は、企業へ、ダメージになる
↓
消費税の増税は、消費者へ、ダメージになる
↓
所得税の増税は、働き手へ、ダメージになる
↓
高圧経済の政策は、各主体を潤すのが目的だった
↓
消費者・働き手も企業も、潤う好循環が、目的だった
↓
増税は、この「好循環作戦」を、台無しにする
財源が、増税では、台無しになる
-- 消費者 経済 総研 --
◆「 行って 来い 」 になる?
民間から集めた税金で、民間へ支出したら?
「 行って 来い 」 になる?
「 財源が 増税 」では、次の課題もある
↓
日本の需要の不足額は、21兆円だった
↓
政府が、21兆円を支出して、不足分を埋める
↓
21兆円の財源が「増税」の場合の流れを、見ていく
↓
政府が、民間から21兆円を、税金として徴収する
↓
つまり、21兆円が、民間部門から、政府部門へ移る
↓
増税で得たその21兆円は、どうなるか?
↓
政府が、その21兆円を、公共事業等で支出する
↓
よって、21兆円が、政府部門から、民間部門へ移る
↓
民間から徴税した21兆円は、民間へ戻るのだ
↓
つまり 「行って 来い」 に、なってしまう
21兆円増税:民間 → 21兆円 → 政府へ移動
21兆円支出:政府 → 21兆円 → 民間へ移動
-- 消費者 経済 総研 --
◆財源が 「増税」では、意味なし?
需要不足の21兆円を、政府が支出して埋める
↓
これで、需給ギャップ(GDPギャップ)は、解消か?
↓
違う。 需給ギャップは、残ってしまう
↓
民間部門の需要が、「増税で、21兆円 減る」からだ
↓
「 消費税や所得税 」 での増税の場合は、どうか?
↓
消費者の財布からは、21兆円が、減る
↓
個人消費の需要の原資が、21兆円減るのだ
↓
増税方式では、「高圧経済」は、実現しない。
↓
「 行って 来い 」 になり、プラス・マイナス ゼロだ
増税したら、民間部門のお金が、減る
民間のお金が、減れば、民間の需要が、減る
-- 消費者 経済 総研 --
◆「徴税+政府支出」で、今まで 低迷?
「 財源が徴税+政府支出 」 なら、どうか?
↓
乗数効果※が、効果的に、機能すればよい
↓
しかし日本の経済が、低迷しているという事は?
↓
「今までの徴税→政府投資」は、効果が薄い証拠だ
「 徴税 → 政府投資が、上出来 」ならば、
日本の経済は、低迷していない
※乗数効果とは
1兆円の公共投資を、実施した場合、
仮に、乗数の値が 「1.2」ならば、
名目GDPは、1.2兆円 増加 することになる。
政府の投資額 1兆円 × 1.2 = 経済効果1.2兆円
※参考:Wikipedia|乗数効果
-- 消費者 経済 総研 --
◆増税以外の 解決策は?
▼増税せず、財政赤字 でよい?
前項の通り、「財源が増税」では、効果が疑問だ
↓
では、「増税なし」なら、どうなる?
↓
政府支出は増えるから、財政赤字が増える。
↓
財政赤字が増えると、どうなるか?
↓
国の借金が、さらに増える
財政の赤字は、国の借金を、増やす?
増税ではなく、借金増加が、財源?
▼国の借金は、問題ではない?
では、国の借金の増加は、問題か?
↓
国の借金は、問題ではない
↓
国の「借金は悪」ではないのだ
政府の 支出の増加の 財源は、
増税ではなく、借金(国債)でよい
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本は、借金大国 ではない?
わかりやすい理解のため
1人2役の対話方式を、交えながら解説していく
▼日本は、資産大国?
日本は「世界1の借金大国」と、言われるが、嘘か?
↓
それは、嘘だ。 日本は、借金大国 ではない
↓
日本は、「資産大国」でもあるからだ
↓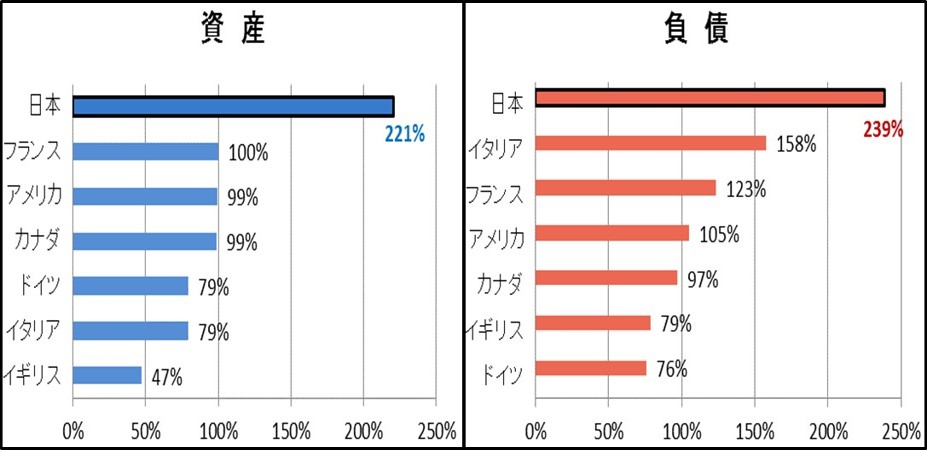 上の「負債」から「資産」を引いた「純負債」では?
上の「負債」から「資産」を引いた「純負債」では?※%の値は、対GDP比
※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成
※出典:IMF| Fiscal Monitor Managing Public Wealth, October 2018
↓
G7(先進七か国)の平均よりも、日本は少ない
↓
G7では、日本は、借金に関し、優等生の側にいる
↓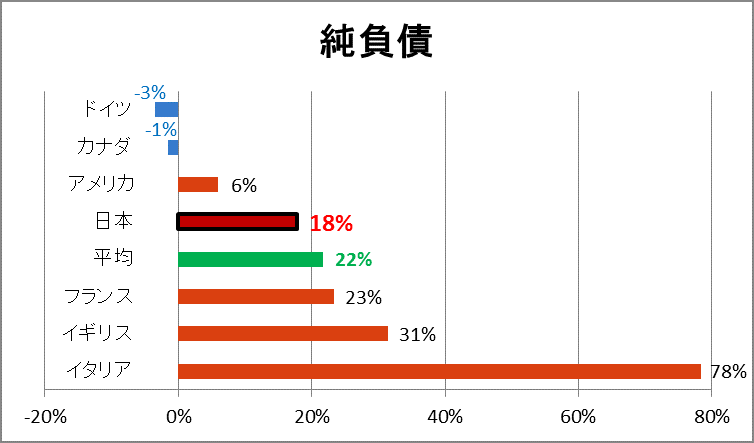 借金つまり「負債の部」だけ見ても、しょうがない
借金つまり「負債の部」だけ見ても、しょうがない※%の値は、対GDP比
※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成
※出典:IMF| Fiscal Monitor Managing Public Wealth, October 2018
↓
財産つまり「資産の部」を、見る必要がある
↓
日本は 「 資産大国 」 でもあるのだ
↓
企業人の多くが、貸借対照表を、知っているはずだ
↓
学生でも、理解できる内容だ
▼民間企業の貸借対照表(バランスシート)は?
日本を代表する民間企業に、トヨタ自動車がある
↓
トヨタ自動車の負債の額は、41兆円もある
1つの企業群だけで、41兆円の負債は、問題か?
↓
何ら問題ではない。 資産が68兆円もある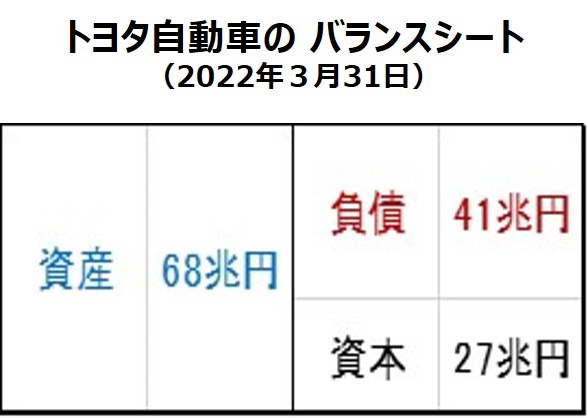 ※金額は連結決算
※金額は連結決算
※出典:トヨタ自動車|2022年3月期 決算要旨|7p-8p
バランスシートの右側だけ見ても、しょうがない
↓
左の資産の部と、右の負債の部の、両方見るのだ
右の負債だけ 見ても、意味なし
左の資産も見て、左右の両方を、見るのだ
▼今後の 借金増加も ok?
わかりやすい理解のため
1人2役の対話方式を、交えながら解説していく
日本が、「借金大国ではない」 ことは、理解した
↓
だが、今後の政府支出の増加で、借金がまた増える
↓
今後の、さらなる借金の増加は、NGか?
↓
今後の借金の増加も、問題ない
↓
国の借金の最大の相手は、「身内の日銀」だからだ
国の借金の 最大相手は、
「 身内の日銀 」 だから、問題ない
▼身内の借金は、他人は、関係ない?
例として、家庭内のケースで、考えてみる
↓
母親に、息子が、マッサージをした
↓
お礼に、小遣いとして千円を、母から息子に払う
↓
千円が、「後払い」なら、どうなる?
↓
息子は千円を貸し、母は千円を借金した事になる
↓
貸し・借りが、発生したが、家庭全体では、どうか?
↓
家計の資産・負債の合計は、増加も減少もしない。
↓
「身内の貸し借り」では、家計は破綻しない
「身内の 親子の 貸し借り 」 では、
家計は、破綻しない
▼身内ではなく、他人の場合は?
家庭内の親子の貸し・借りは、他人には、関係ない
↓
他人である外部のマッサージ師の場合は、どうか?
↓
外部のマッサージ師が来て、施術をした場合は?
↓
当然に、代金の支払い義務がある
↓
身内での貸し・借りが、問題なくても、
他人への支払義務は、チャラにできない
↓
アルゼンチンやギリシャの借金問題は?
↓
2つの国は、外国からの借金が、返せなかった
↓
よって、問題になった
↓
日本政府の身内(日銀)からの借金の分は、問題ない
アルゼンチン や ギリシャは、
身内ではなく、
他人である外国から、借金で問題
▼日銀の親会社は、日本政府?
そもそも「日銀」は、会社か? 役所か?
↓
日銀は「会社」である。しかも上場している会社だ
↓
日銀の筆頭株主は、日本政府だ※
↓
日銀の株の過半(55%)を、政府が保有する※
↓
政府が親会社で、日銀が子会社 という関係だ
↓
日銀は、プライム市場に、上場している※
↓
つまり普通の人も、日銀の株を、買えるのだ。
↓
結局は、買わなかったが、筆者(松田)は、
日銀の株(出資証券)の購入を、検討した事もあった
※日銀の場合、正確な名称は「株式」ではなく「出資証券」
※筆頭株主は、筆頭口主のこと
※以前はジャスダックで、22年度からは、プライム市場
※日銀は株式会社ではなく「認可法人」であり、
通常の株式会社とは異なる部分がある
日銀・政府の関係を、より知りたい場合は、
本ページ下段記載のリンク先を、参照頂きたい
日銀は、政府の 子会社
日本政府は、日銀の 親会社
▼まだ、理解不充分?
ここまで、国の借金は「問題なさそう」とわかった
↓
しかしまだ、ぼんやりとした理解に、とどまる
↓
日銀・政府の関係、他人・身内の借金など、
もう少し、納得したいが、詳しい解説は、あるか?
↓
本ページでは、字数の関係で、部分的な解説のみだ
↓
より詳しい解説は、別ページに特集してある
↓
本ページの下段のリンク先から、読んで頂きたい
-- 消費者 経済 総研 --
◆財源は、借金でよいか?
高圧経済の財源は、借金で、よさそうだな?
↓
そうだ。 借金の増加でよい
↓
借金で政府予算を増やして、民間へ発注だな?
↓
そうだ。 民間企業の受注つまり売上が、増える
↓
企業の売上UP、社員の賃金UP、景気UPだな?
↓
そうだ。 冒頭に既述の通り、好循環になるのだ
↓
政府の借金で、民間部門のお金の量が増えるのだ
政府の借金の 増加で、
民間のお金が、増える
-- 消費者 経済 総研 --
◆借金増加の デメリットは?
▼過剰なインフレならば、デメリットか?
「財源は、増税より、借金が良い」 のは、わかった
↓
一方で、デメリットの有無も、知りたい
↓
借金増加で、民間部門のマネーの量が、増えるか?
↓
そうだ。 増える
↓
「民間部門のお金が増える」ことのデメリットは?
↓
インフレ圧力だ
↓
「お金が増えると、インフレ」の仕組みは、何か?
↓
わかりやすい解説を、別ページに掲載してある
↓
本ページの下段のリンク先から、読んで頂きたい
高圧経済で、マネーの量が、増える
そのデメリットは、インフレ圧力?
▼悪性インフレの 心配ない ?
22年は、日本も、物価が上がったが、大丈夫か?
↓
大丈夫だ。 日本は、まだ「デフレ脱却は未完」だ
↓
最近の日本の物価高は、一時的なのだ
↓
なぜ、一時的なのか?
↓
天候不良、コロナ、戦争が、原因だからだ
インフレは、一時的
日本は、デフレ脱却未完
▼円安は、ピークアウト したか?
物価上昇は一時的な原因(天候、コロナ、戦争)と理解した
↓
だが「円安」でも、輸入価格UPで、物価上昇になる
↓
「 円安で 物価高 」 は、続くか?
↓
円安は、ピークアウトしたので、懸念は減少した
↓
なぜ、円安は、落ち着いたのか?
↓
米国景気が失速し、景気後退の懸念があるからだ
↓
景気後退(リセッション) 懸念とは、具体的には?
↓
米国のGDPは、2期連続マイナスに、なったのだ
↓
よって、ドルが強いドル高のトレンドは、終わった
↓
ドル高が終わったことは、円安も終わったのだ
円安は、既に ピークアウト
▼インフレは、日本に好都合?
日本は、「デフレ脱却 未完」なのは、理解した
↓
デフレ脱却が未完なら、インフレ圧力は、良いか?
↓
そうだ。 インフレ圧力は、逆に好都合なのだ
↓
「低迷→離陸→好循環」 になるまで、高圧をかける
↓
これが、高圧経済である
↓
望まぬインフレになる迄、政府支出を続けられる
↓
「望まぬインフレが 続く」 のは、当分先の話だ
↓
では、どの程度のインフレまで、続けるのか?
↓
少なくとも物価上昇が、安定的に「2%」になる迄だ
↓
2022年6月は、2.4%の物価上昇になった
↓
既に、2%を超えたが、どうなのか?
↓
2.4%は、原油や食品の 一時的な高騰を、含む
↓
既述の通り、「悪天候、コロナ、戦争」で、高騰した
↓
その一時的な要因を除くと、まだ低い物価水準だ
↓
「食料とエネルギー」 を除くと、下図の通り、低い
↓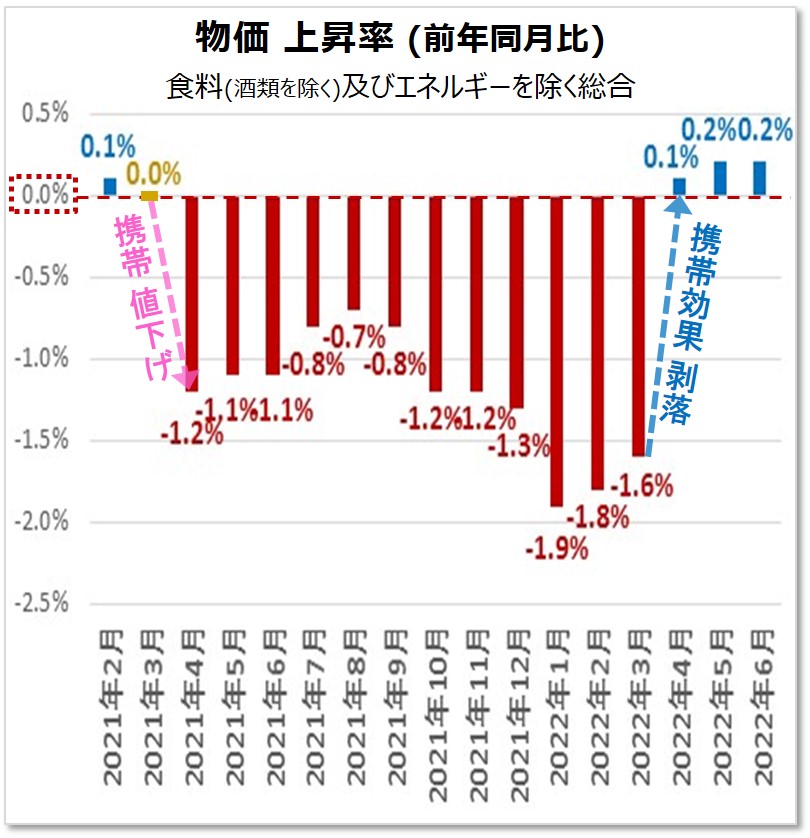 ※出典:政府統計の総合窓口|
※出典:政府統計の総合窓口|
消費者物価指数2020年基準消費者物価指数 2022年6月
↓
2022年4月から、プラスになった理由は、何か?
↓
菅 前首相による 「携帯料金の引下げ」 の変動だ
↓
2021年4月から、その効果で、物価は下落した
↓
そこから、12か月が経過した月が、2022年4月だ
↓
2022年4月に、その下駄(水準下落)が、剥落した
↓
22年4月の「プラス化」は、インフレ圧力ではない
↓
携帯料金の下駄(水準下落)が、剥落しただけだ
日本は、デフレ脱却 未完 のまま
▼2%の 物価目標 とは?
「2%目標」をよく聞くが、なぜ、「2%」なのか?
↓
1%や、3%では、駄目なのか?
↓
「目標は、2%である理由」を、別頁に掲載してある
↓
本ページの下段のリンク先から、読んで頂きたい
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本で 借金が批判される 理由 とは?
なぜ、財政赤字と借金は、日本で批判されるのか?
↓
下記のいずれかだ
[1] そう言った方が、自分が、得をする
[2] そう言わざるを 得ない立場にある
[3] 単純に 情報不足
[3]は、知識の習得で解消する。
[1]と[2]は、ポジショントーク だ。
消費者経済総研は、財務を預る役所でもなく、
特定政党の支援を、する立場でもない。
つまり、当方のポジションは、ニュートラルだ。
「わかりやすく解説する」との立場に、いるだけだ。
※なお「ポジショントークは直ちにNG」
というわけではない。
借金ダメと言う人は、「だいぶ減った」と感じる。
知識の習得(情報の共有・伸展)が、進んだのだろう。
筆者(松田)は、35年以上前に、慶応大学 経済学部
に入学以来、経済を研究している。
しかし本稿は、経済学の知識なしでも
わかるような簡単解説としている。
日本の借金の解説では、筆者の解説は、
「とことん わかりやすい」と思っている。
下段の 「リンク集」 から、
そのわかりやすい解説を、ご覧頂きたい
「日本は、借金大国」は、嘘
▼海外も 日本も 変化?
諸外国は、「 財政赤字 も 借金増加 も 」 容認だ
↓
日本も2019年から急速に、借金容認へ動き始めた
↓
野党では、国民民主も、れいわ新選組も、容認派だ
↓
そしてついに20年から、自民党も容認へ動き出す
↓
野党だけでなく、なぜ自民党までもが借金容認か?
↓
続編の次回号で、徹底解説する
外国は、財政赤字 も 借金増加 も 容認
日本も、2019年から、借金容認へ
-- 消費者 経済 総研 --
◆次回号は?
次回号の 「 自民党も 急速に 変化!? 」 とは?
ついに自民党も、2020年に、〇〇が 発足
続いて 2021年には、◇◇が 設立
翌2022年には、□□が 消滅した
そのきっかけは、令和元年(2019)の●●だった?
-- 消費者 経済 総研 --
◆リンク集
本ページで登場したリンク先での詳細解説
下記の過去号を、ご覧頂きたい。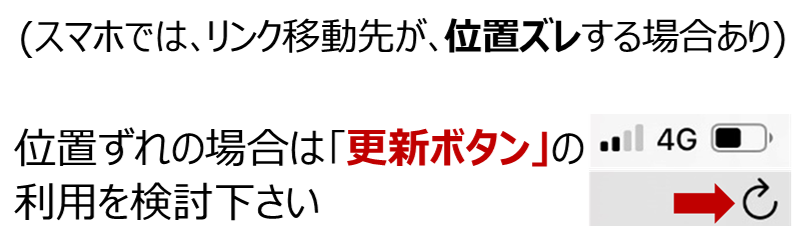
▼「お金が増えると、インフレ」の仕組み とは?
【簡単】インフレ|ミカンの例で、簡単3分解説
▼日本 借金大国 嘘
日本 借金大国 嘘 Vol.1 バランスシート 編
▼政府と日銀の詳細は
日本 借金大国 嘘 Vol.2 日銀・政府 編
▼2%目標 なのは なぜか?
なぜ、2%なのか?

- ■「高圧経済」 政策 その3
- 2022年 8月 20日 (土) に 投稿
Vol.7 (第2部の高圧経済の 3回目)
海外も、自民党 も 野党も、借金を肯定へ
・外国は、借金を大幅に、増加
・外国は、日本よりも、借金増加した
・下記↓の通り、日本の 借金増加は少ない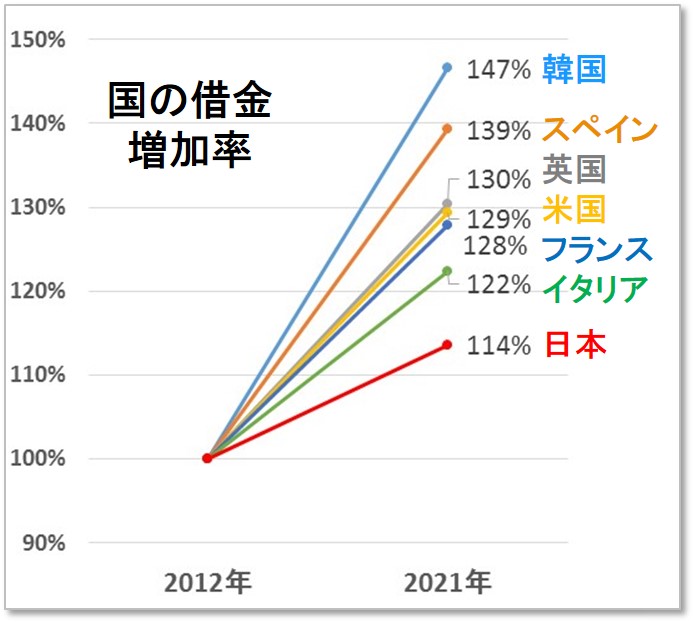
%の値は「債務残高÷GDP」の伸び率で、12年を100とした21年の値
※IMFレポートから、「 消費者 経済 総研 」が、グラフ作成
自民党 が 財政革命 へ
自民党 の 財政革命 が、
令和時代に 始まった?
国の借金増加を、自民党も、賛成へ?
自民党 の 議連 は、
下記が、全て誤りと、掲載した
・日本の財政は 破綻寸前
・国民一人 900万円の 借金
・国債は、必ず返済が、必要
※本件の詳細は後述
「連載シリーズ|ニッポン 爆上げ作戦」の7回目は、
「 高圧経済 」 の 「 その3 」 である。
その1は、高圧経済の 「政策内容」 と 「メリット」
その2は、高圧経済の 「 財源 」 と 「デメリット」
-- 消費者 経済 総研 --
◆今回号(その3)は?
外国は、積極財政 → 財政赤字 → 国の借金増加
令和は、「 自民党 の 財政革命 」の時代
国の借金増加 自民党も、野党も、賛成へ
令和に、自民党 の 財政革命 か?
自民も、野党も、国の借金 賛成へ?
-- 消費者 経済 総研 --
◆「 財政赤字 」 と、 「 国の借金 」 の関係は?
政府の税収が、仮に 「100兆円」 だとする
↓
政府の支出が、仮に 「110兆円」 だとする
↓
この場合、「 10兆円の 財政赤字 」 だ
( ▼10兆円 = 100兆 - 110兆 )
↓
この不足分の10兆円を、借金で、まかなう
↓
つまり、積極財政で、政府支出を増やすと?
↓
税収が不変なら、財政赤字と借金が、増える
積極財政 では、どうなる?
・政府の支出が、増える
↓
・財政赤字が、増える
↓
・国の借金が、増える
-- 消費者 経済 総研 --
◆海外は、「借金」を、増やしている?
日本では、「 国の借金への批判 」 が多い
↓
では諸外国は、借金を、減らしているのか?
↓
違う。 先進国は、軒並み、国の借金を増やしている
↓
なぜ、先進諸外国は、借金が増えたのか?
↓
先進国は、財政赤字の国が、多いからだ
↓
先進国は、なぜ、赤字にしてまで、支出拡大なのか?
↓
「 需要 > 供給 」 で、景気UPに、貢献するためだ
海外は、赤字でも、政府支出 拡大
「 需要 > 供給 」 で、景気UPに
-- 消費者 経済 総研 --
◆海外は、「政府の支出」を、増やす?
先進7か国は、政府支出 拡大
日本は、7か国で、最低水準
諸外国は、政府の支出を、増やしている
↓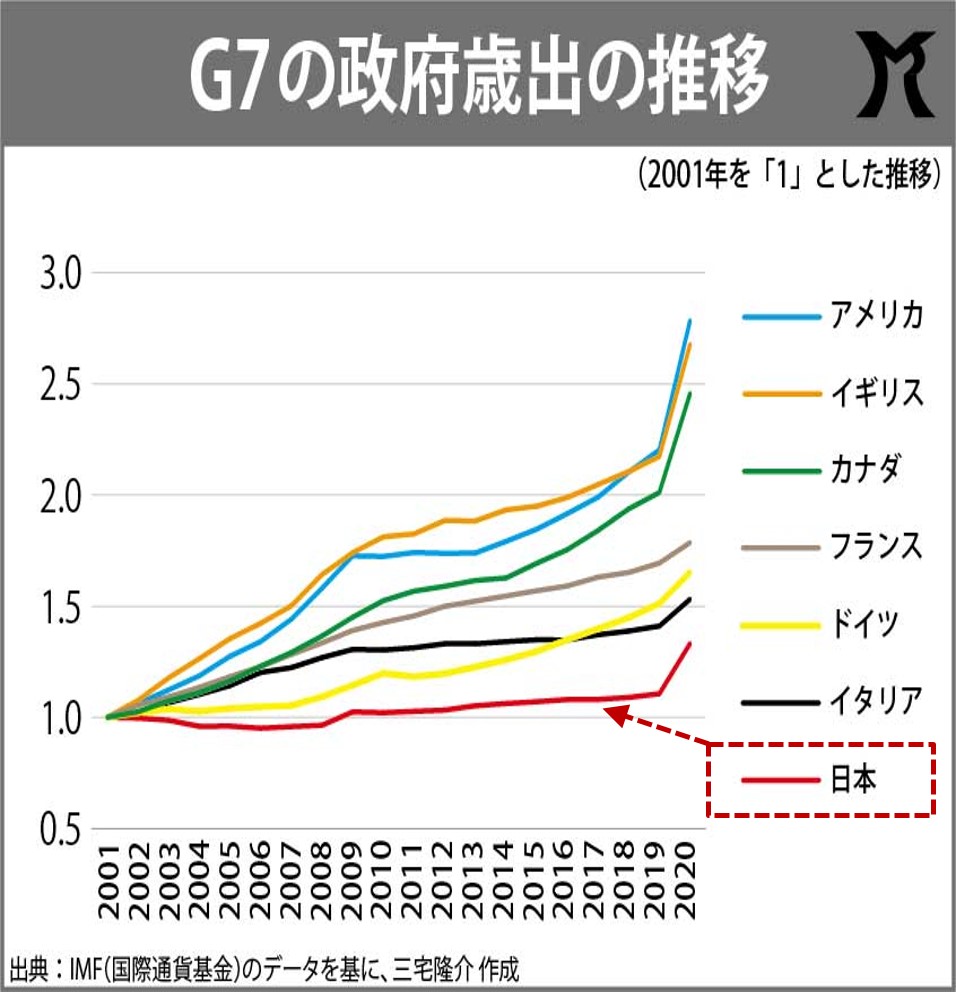 -- 消費者 経済 総研 --
-- 消費者 経済 総研 --※グラフ出典:川崎市議会議員 三宅隆介氏|
政府債務残高が増えたのは、政府がおカネを使わないからだ
◆日本は、消極財政?
上のグラフからは、何が、わかるか?
↓
日本は、政府支出の増額幅が、小さすぎる
↓
日本は、「積極財政」ではなく、「消極財政」なのだ
↓
これでは、日本のGDPは、低迷してしまう
外国は、積極財政
日本は、積極財政 ではない から、
日本の企業売上も、賃金も、低迷だ
-- 消費者 経済 総研 --
◆海外は、国の借金を、どうしている?
借金が増えているのは、日本だけではない外国は、借金を大幅に、増加
外国は、日本よりも、借金増加した
↓
諸外国も、国の借金を、当然に増やしている
↓
2012年~2021年の間で、どのくらい増えたか?
↓
「 借金残高 ÷ GDP 」 の借金指数で、見ていく
↓
日本の2012年を100とした場合、2021年は?
↓
2012年:100 → 2021年:114と、14 pt 増えた
↓
では、諸外国は、どうか?
↓
下図の通りだ
↓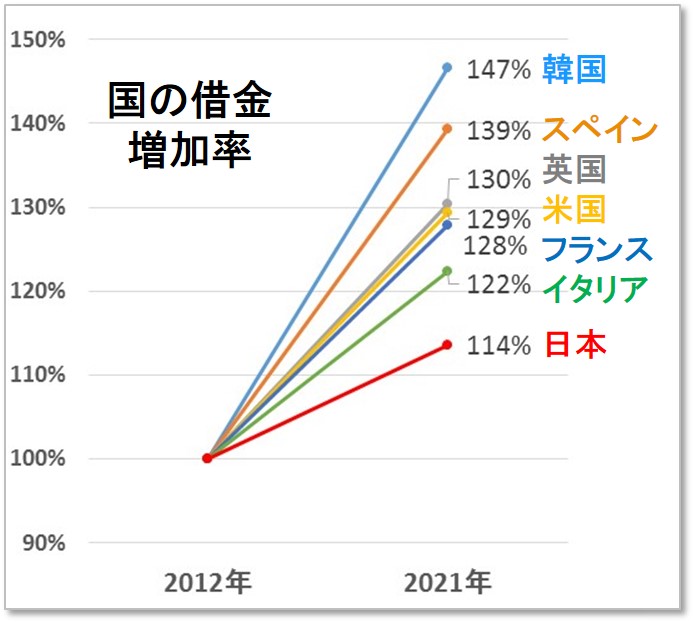
※%の値は、 ①÷②
① 21年の債務残高÷GDP ② 12年の債務残高÷GDP日本の借金の増え方は、少ないのだ※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成
※出典:IMF|Strengthening the Credibility of Public Finances
IMF Fiscal Monitor
↓
一方で外国は、日本よりも、借金を増やした
外国は、借金を大幅に、増加
外国は、日本よりも、借金増加した
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本 低迷の 理由は?
なぜ、日本経済は、低迷するのか?
↓
日本の「政府支出と借金増加」が、少ないからだ
↓
既述の通り、先進国・諸外国と、比較すれば明白だ
-- 消費者 経済 総研 --
- ◆日本で 借金が批判される 理由 とは?
- なぜ、財政赤字と借金は、日本で批判されるのか?
↓
下記のいずれかだ
[1] そう言った方が、自分が、得をする
[2] そう言わざるを 得ない立場にある
[3] 単純に 情報不足
[3]は、知識の習得で解消する。
[1]と[2]は、ポジショントーク だ。
消費者経済総研は、財務を預る役所でもなく、
特定政党の支援を、する立場でもない。
つまり、当方のポジションは、中立・客観 だ。
「わかりやすく解説する」との立場に、いるだけだ。
※なお「ポジショントークは直ちにNG」
というわけではない。
借金はダメ と言う人は、「だいぶ減った」と感じる。
知識の習得(情報の共有・伸展)が、進んだのだろう。
筆者(松田)は、35年以上前に、慶応大学 経済学部
に入学以来、経済を研究している。
しかし本稿は、経済学の知識なしでも
わかるような簡単解説としている。
日本の借金の解説では、筆者の解説は、
「とことん わかりやすい」と思っている。
下段の 「リンク集」 から、
そのわかりやすい解説を、ご覧頂きたい
「日本は、借金大国」は、嘘
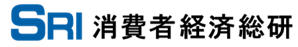
-- 消費者 経済 総研 --
◆諸外国と、日本の政治家
諸外国は、政府支出を、増やした
↓
諸外国は、財政赤字を、増やした
↓
諸外国は、国の借金を、増やした
↓
一方で、日本では、どうか?
↓
「赤字はダメ 」 「 借金は、ダメ 」 と言われる
↓
日本の政治家は、「赤字と借金」を、どう考えるか?
わかりやすい理解のため
1人2役の対話方式を、交えながら解説していく
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本の国会では、借金は、悪か? 善か?
日本の国の予算は、国会で決められる
↓
国会議員は皆が、「借金は悪」と、考えているのか?
↓
違う。 「借金は、良い」 は、主張されている
↓
「借金は良い」は、誰が、言うのか?
▼自民党は?
自民党の大物議員も、「借金を肯定」している
↓
それは、だれか?
↓
著名人では、安倍元首相、高市氏などだ※
自民党 大物議員は 借金肯定
▼野党は、どうか?
与党に借金の肯定が増えても、野党は借金反対か?
↓
違う。 国民民主や、れいわ新撰組も、借金肯定派だ
野党にも 借金の肯定派 あり
▼政党別では、どうか?
借金へのスタンスは、政党別の違いは、どうか?
↓
2022年の参院選の公約等からは、下図であろう
↓ ※消費者 経済 総研が、上図を作成
※消費者 経済 総研が、上図を作成
▼自民党内の温度差は?
同じ自民党の中でも、スタンスは違うのか?
↓
そうだ。 かなり違う
↓
故安倍元首相や、高市氏は、「肯定側」だ
↓
岸田首相や、麻生元首相は、「消極側」だ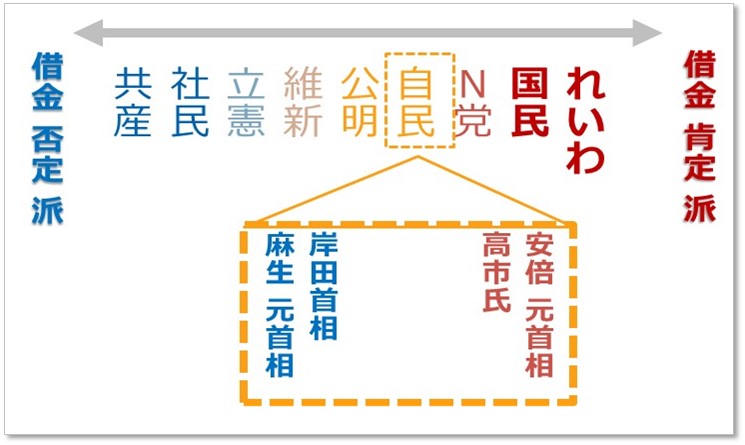 ※消費者 経済 総研が、上図を作成
※消費者 経済 総研が、上図を作成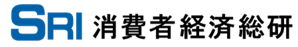
政策 本部 vs 健全化 本部 とは?
※肯定側には、
高市政調会長の直轄の「財政政策 検討本部 」がある。
安倍元首相が、最高顧問を務めていた。
この組織については、下段で、後述する。
※消極側には、
岸田 総裁直属の「 財政健全化 推進本部 」がある
麻生元首相が、最高顧問を務める※安倍氏、高市氏をはじめ肯定派であっても、
「借金は善」のような明確な表現は避けて、
回りくどいが、借金は悪ではない趣旨を言っている。
▼借金の 「 肯定派 」 が、増えた?
政治家は、借金の 「 肯定派 」 が、増えたのか?
↓
そうだ。 与党も野党も、肯定派が、近年増加した
-- 消費者 経済 総研 --
◆自民党は、どう増えたのか?
自民党は、近年は、どのように変化したか?
↓
令和時代から、自民党の借金の肯定派が、急増だ
自民党で 借金の肯定派が 急増
▼2020年 の 自民党は?
20年に「日本の未来を考える勉強会」が発足した
↓
「日本の未来を考える勉強会」 の性格は?
↓
財政赤字容認、消費税減税などの積極財政派だ
↓
自民党に、他の動きは、あるか?
▼2021年 の 自民党は?
21年に「財政政策 検討本部」を、自民党内に設立
↓
「 財政政策 検討本部 」 の性格は?
↓
「積極財政」を、提言する組織だ
↓
誰がメンバーか?
↓
故安倍元首相、高市氏などだ※
※財政政策検討本部
本部長:西田昌司氏、幹事長:城内みのる氏
元最高顧問:安倍元首相、役員:高市早苗氏
自民党に、他の動きは、あるか?
▼2022年 の 自民党は?
常識が、全て誤り だと 確信?
22年は、財政黒字の目標年度の記載を、消した
↓
どこで、消したのか?
↓
経済財政の基本方針である 「 骨太の方針 」 だ
↓
また22年は、下記の議員連盟が、設立された
↓
「 責任ある 積極財政を 推進する 議員連盟 」
↓
文字通り、「積極財政の推進派」である
↓
この連盟は、かなり強いメッセージを、出している
↓
下記が、その抜粋だ
※...は省略箇所を示す(以下同じ)。「 日本の財政は 破綻寸前 」
「...国民一人当たり 900万円の 借金がある」
「 国債は 必ず...返済しなければ ならない 」
これらの常識が、
全て誤りであることを...確信。
※上の赤字化・大文字化、下の赤枠化は、筆者による
※出典:ご挨拶|責任ある積極財政を推進する議員連盟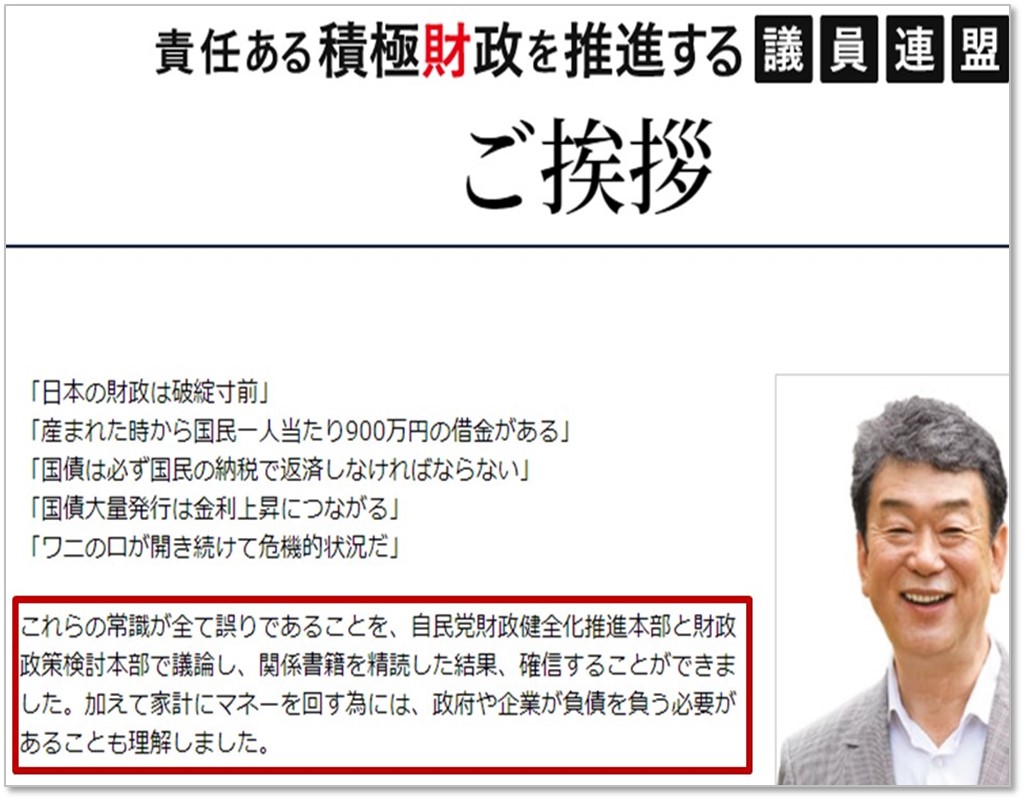
常識が、全て誤り だと 確信
-- 消費者 経済 総研 --
◆令和の自民党 積極派 が 急増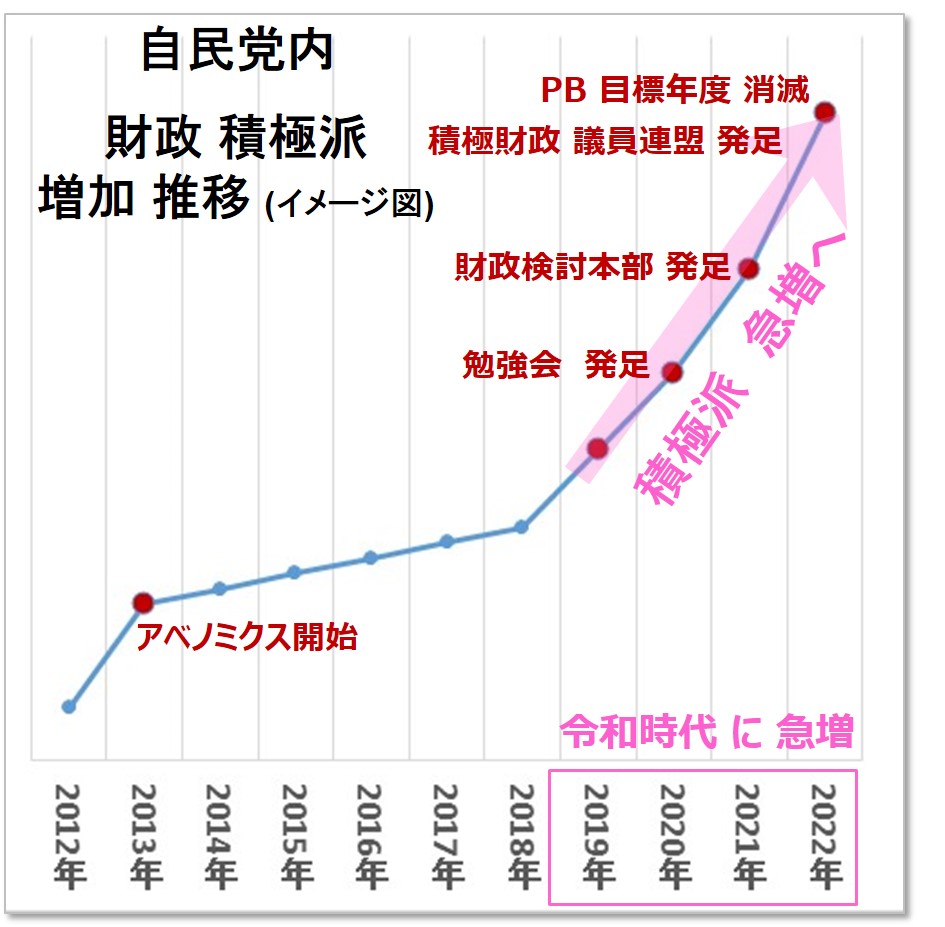
-- 消費者 経済 総研 --
◆「 野党 」 の変化は?
与党ではなく、野党の方は、どうか?
↓
れいわ新選組は、マクロ経済学の理解が深い
↓
国民民主党も、経済政策の水準が高い
↓
この2つの党は、借金肯定の政党だ
↓
2021年、立憲民主も党内に、変化が見られる
↓
原口氏が「日本の未来を創る勉強会」を立ち上げた
↓
この会は、「積極財政」等を、考える勉強会だ
↓
日本維新の会も、21年→22年で変化した
↓
維新の会の公約は、青字部分が、22年に加わった
中央銀行をもつ国家と
地方自治体は異なることを前提に...
過度なインフレを招かない範囲で
積極的な財政出動・金融緩和を行います。
※出典:維新マニュフェスト|
2021年版 14P|2022年版 9P
大阪市や大阪府は、地方自治体だ
↓
地方自治体は、通貨発行が、できない(お金を作れない)
↓
地方自治体ではなく、国レベルでは、どうか?
↓
政府は硬貨を、中央銀行(日銀)は紙幣を、発行する
↓
お金の発行は、自治体は、できないが、国はできる
↓
自治体は節約姿勢で、国は積極姿勢を、示唆する
↓
維新は、国政では、積極財政の姿勢を、強めた
▼与党も野党も 「借金 問題なし」 に気付いた?
与党も野党も「借金は問題なし」に、気付いたのか?「 借金は 問題なし 」 と、
与党も 野党も 気付いた?
↓
そうだろう。 「借金は問題なし」 が、徐々に進む
↓
徐々にではなく、抜本的に、進めればよいのでは?
↓
与党も野党も、今までの発言を、急には変えにくい
↓
「 ばつが悪い 」 ということか?
↓
そういうことだろう。
↓
しかし、議論・整理をして、早く改善して頂きたい
-- 消費者 経済 総研 --
◆借金 肯定派 vs 否定派 どちらが多い?
自民党も、借金の肯定派が、増えた
↓
そこで、肯定派と否定派と、どちらが多いのか?
▼若手は?
自民党の若手では、肯定・否定は半々くらいだろう
↓
しかし借金の肯定派は、急速に増加している
↓
やがて自民党若手は、肯定派が過半になるだろう
※参考:責任ある積極財政を推進する議員連盟
|会員一覧|会員数 85人 ↓|
▼ベテランは?
自民党の 「 ベテラン 」 は、どうか?
↓
長年にわたり「財政黒字の目標」を、うたってきた
↓
長年の主張を、あっさり変更するのは、できるか?
↓
さずがに、「 あっさり変更 」 は、バツが悪いだろう
▼若手 vs ベテラン ?
過去の党の経緯・歴史に、若手は影響受けにくい
↓
ベテランが高齢になり、いずれは引退する
↓
否定派が多いベテラン割合が、減っていくだろう
↓
よって、年月を経て、肯定派が増えていく
-- 消費者 経済 総研 --年月を経て、肯定派が 増えていく
◆自民党も、やがて、「積極派が主流」に?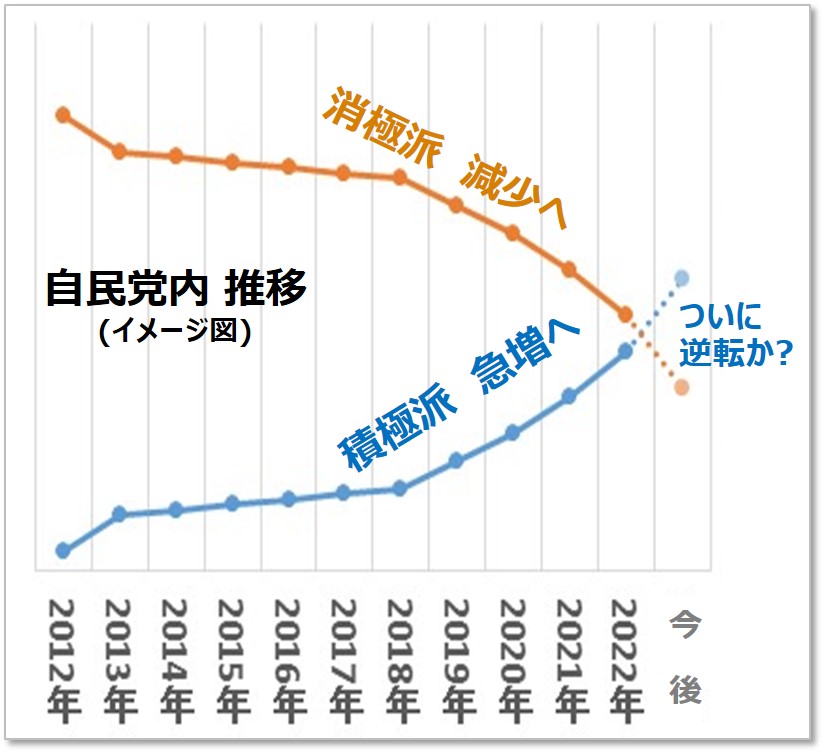
自民党も、やがて、「 積極派が 主流 」 になるか?
↓
そうなれば、今後の日本の経済は、明るい
↓
ようやく、低迷から、脱出できるのだ
▼安倍元首相は?
安倍氏は、消費税の増税を、回避できなかった
↓
しかし党の経緯に関わらず、積極財政 派だった
↓
ベテランでも、積極派に転じる議員も、出るだろう
▼岸田首相は?
岸田首相の経済政策のスタンスは、どうなのか?
↓
財政健全化推進本部は、岸田総裁の直轄の組織だ
↓
よって、積極派ではなく、緊縮派であろう
↓
2021年総裁選から「聞く力」を、アピールしている
↓
ぜひ「積極財政・高圧経済」論を、聞いて頂きたい
↓
そして高圧化で、日本経済を元気に、して頂きたい
↓
本稿は、消費者 経済 総研からの政策提言でもある
↓
自民党の財政革命で、日本も、ようやく成長加速へ
自民党 の 財政革命 で、
日本も、 ようやく 成長加速へ早期の 積極財政・高圧経済 を、
「 消費者 経済 総研 」 が、政策提言

- ■「高圧経済」 政策 その4
2022年 8月 28日 (日) に 投稿
Vol.8 (第2部の高圧経済の 4回目)
国の借金 過去最大 の発表を 丸無視
この連載シリーズは、政策提言でもある
日本の 「 金融政策 」 には、変更はない
変更無いのに、金融政策や日銀の話題が、多すぎる
今の日本で、重要なのは、「 財政政策 」 だ
とても重要なのに、注目度が、低すぎる
連載シリーズ|ニッポン爆上げは、
その重要な財政政策の中の「 高圧経済 」を、連載中
-- 消費者 経済 総研 --
わかりやすく、理解するため、
1人2役の対話方式を、交えながら、解説していく
◆海外は、国の借金で、騒がない?
「 国の借金は、けしからん 」 が、日本で多い
↓
日本ではなく、「 海外 」 ではどうかを、知りたい
↓
例えば、米国では、どうなのか?
↓
米国も、国の借金問題で、騒いでいるはずだ
↓
違う。 米国は、国の借金で、騒いでない
↓
米国では、国の借金には、そもそも注目してない
米国は、国の借金に、注目してない
-- 消費者 経済 総研 --
◆米国で、国の借金は、ニュースになるか?
筆者(松田)は、毎朝、海外の経済情報を、見ている
↓
米国で、国の借金のニュースは、まず無い
↓
米国経済を、毎日チェックしてる人なら、知ってる
↓
米国で、「国の借金額」は、話題にならないのだ
↓
日本だけが、「国の借金問題」で、騒ぐのか?
↓
そうだ。 日本は「国の借金問題」で、過剰に騒ぐ
国の 借金問題 で、
過剰に、日本は騒ぐ
-- 消費者 経済 総研 --
◆米国で注目されるのは、「 物価 」と「 雇用 」?
では米国では、何に、注目しているのか?
↓
「 インフレ率 」 (物価上昇率)と、 「 雇用の動向 」だ
↓
「物価」の安定と、「雇用」の拡大が、関心の対象だ
↓
具体的には、何を目指すのか?
↓
「物価」では、 安定的な「2%の物価上昇」を、目指す
↓
「雇用」では、 失業率の低下と、賃金UPを、目指す
↓
物価上昇率を超える、賃金上昇率を、目指すのだ
米国で、注目されるのは、
「物価」 と 「雇用」 の指標
-- 消費者 経済 総研 --
◆先進国での 重要な 経済指標は?
こうして経済政策は、「雇用」と「物価」を、重視する
↓
「インフレ率」と「失業率・賃金UP率」が重要指標だ
↓
それは、米国だけの話か?
↓
違う。 米国に限らず、先進国は同じだ
↓
「 国の借金の金額 」 は、重要指標ではない
↓
「国の借金の額」は、下位・低位の指標である
↓
借金増加は、インフレの原因の1つでしかない
↓
インフレ(物価高)の原因は、何があるか?
↓
需要、供給、税率、金利、マネーストック等、様々だ
↓
これらの指標は、借金増加よりも、物価に影響する
↓
借金増加は、インフレの原因の1つでしかない
↓
しかも借金増加は、インフレへの影響度は、小さい
先進国では、 借金の額は、
低位・下位の 指標
-- 消費者 経済 総研 --
◆最近の米国は、インフレ率に注目?
「雇用」と「物価」の指標が、重要なのは、理解した
↓
最近の米国で、「特に、注目される指標」は、何か?
↓
米国雇用は堅調なので、雇用指標の注目度は低い
↓
最大の注目指標は、物価上昇率(インフレ率)だ
↓
物価上昇率は、CPI(消費者物価指数)の指標で見る
↓
2022年の夏は、8%~9%台ものインフレになった
↓
この急激な物価高から、米国では、CPIに注目する
米国で、最大の 注目指標は、
CPI ( 消費者 物価 指数 )
-- 消費者 経済 総研 --
◆FRBが 物価を、金利で 制御?
そこで物価高を、抑制するため、金利を上げる
↓
「 金利を上げる 」 と、「 物価が下がる 」 のだな
↓
このメカニズムを、知りたい
↓
「 金利 政策 とは? 」 の解説を、ご覧頂きたい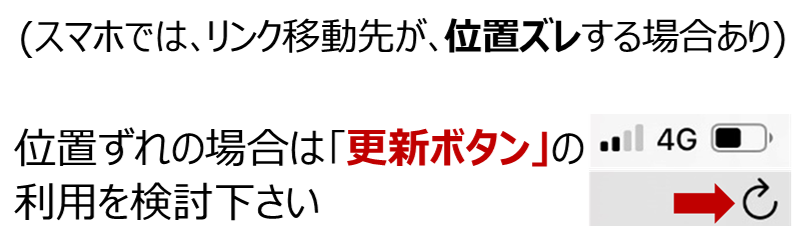 ↓
↓
米国の金利を、コントロールするのは、どこか?
↓
米国の中央銀行のFRBだ
↓
FRBが、金利の上げ・下げ等で、物価を制御する
↓
米国の経済ニュースは、FRBの話で、持ち切りだ
↓
FRBのニュースとは、具体的には、何か?
↓
「 政策金利の 次の利上げは、 何%?」 などだ
FRBの 利上げに 大きな注目
-- 消費者 経済 総研 --
◆FRBは、CPIを、注視?
最近のFRBの 最大の仕事は、インフレ退治だ
↓
CPIに応じて、FRBは、政策金利を変える
↓
政策金利が、上がれば、どうなるのか?
↓
市場金利も、(先回りしながら) 連動して、上がるのだ
↓
市場金利とは、具体的には、何か?
↓
例えば、住宅ローンや、マイカーローン などだ
↓
金利の上昇で、住宅ローン等の金利も、上がる
↓
家・車を買う際の「本体価格+ローン支払」が増える
↓
購入を、見送る人も増えて、家・車の需要が、減る
↓
需要が減るのは、家・車の需要だけ ではない
↓
それらの部品・部材・資材・原材料の需要も、減る
↓
こうして、需要の減少は、幅広い業界におよぶ
↓
需要が減れば、価格は下がるので、物価低下になる
↓
こうして、政策金利UPで、需要減・物価低下になる
↓
最近のFRBの 最大の仕事は、インフレ退治だ
↓
FRBは、物価の指標のCPIを、注視しているのだ
↓
金利水準を、決める要素は、「CPI」だ
↓
CPIが、米国での最大注目の 経済の指標だ
米国で、最大の 注目指標は、
CPI ( 消費者 物価 指数 )
-- 消費者 経済 総研 --
◆金利UPで、ドル高・円安 へ?
米国の金利が、上がれば、ドル高・円安になる
↓
米国金利の上昇で、「ドル高・円安」 になる理由は?
↓
米国金利が上がると、米国での利息は、多く貰える
↓
日本での利息より、米国での利息の方が、多くなる
↓
よって、円からドルに、換える人が、増える
↓
つまり、円を売って、ドルを買う人が、増える
↓
こうして米国金利の上昇で、「ドル高・円安」 になる
-- 消費者 経済 総研 --
◆金利UPで、株安 へ?
金利が上がると、「 株価 」 は、下がる
↓
なぜ、株価は、下がるのか?
↓
金利が上がると、企業の支払利子が、増える
↓
支払利子が増えると、その分、企業の利益が減る
↓
よって、企業の株価は、下がるのだ
-- 消費者 経済 総研 --
◆金利しだいで、金融市場が動く?
こうして、政策金利によって、金融市場は変動する
↓
金融の市場参加者・投資家は、金利に大注目なのだ
投資家は、政策金利に、大注目
-- 消費者 経済 総研 --
◆米国CPIは、日本でも、大注目?
政策金利を決める時、CPIを考慮するのは理解した
↓
だが、米国のCPIで、そこまで騒ぐとは、思えない
↓
違う。 日本でも、ものすごく注目を、集めるのだ
↓
テレビ東京は、米CPIの緊急ライブ特番を配信した
↓
筆者(松田)も、21時15分から、観ていた
↓
米国のCPIは、8/10(水)の21:30に、発表された
↓
テレビ東京はその15分前からライブ放送を始めた
↓
発表まで、100分の1秒のカウント・ダウンをした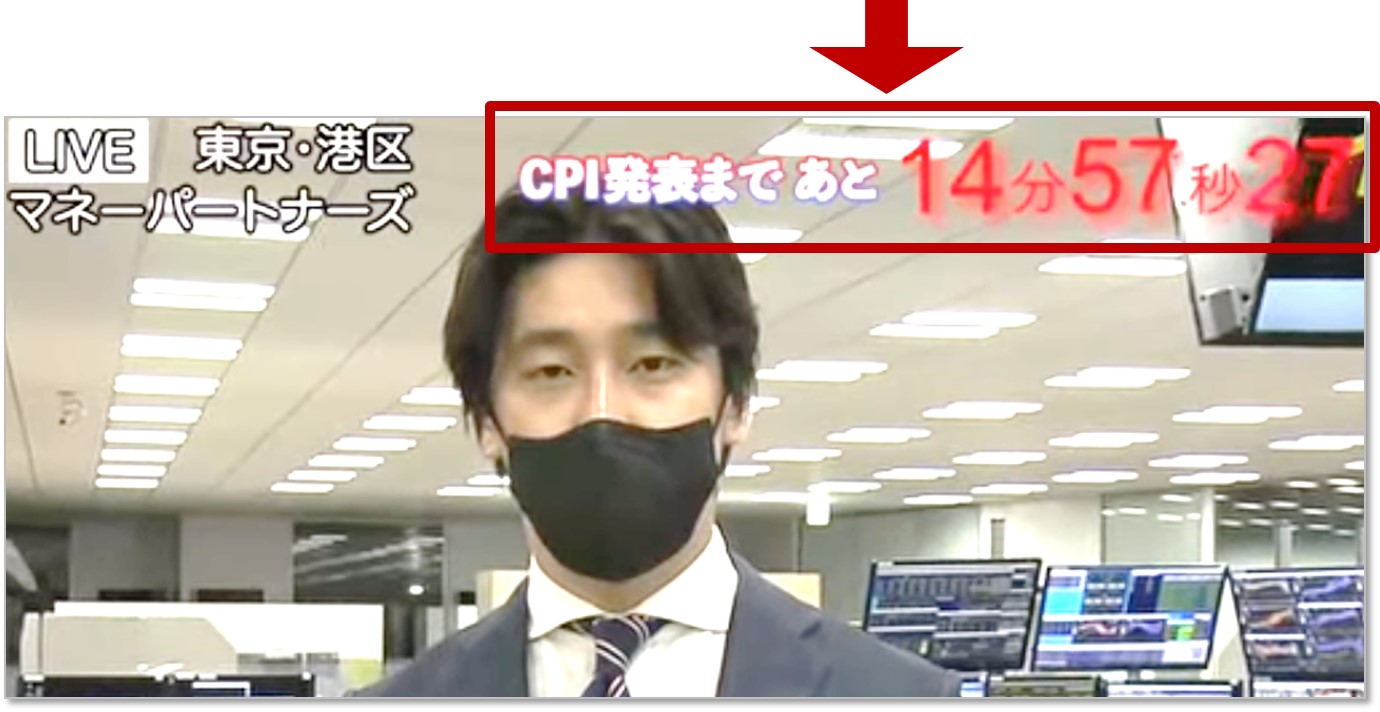
CPIは、21:30に、前年比8.5%上昇と、発表された
↓
為替(ドル円)は、その瞬間から、急落 した
↓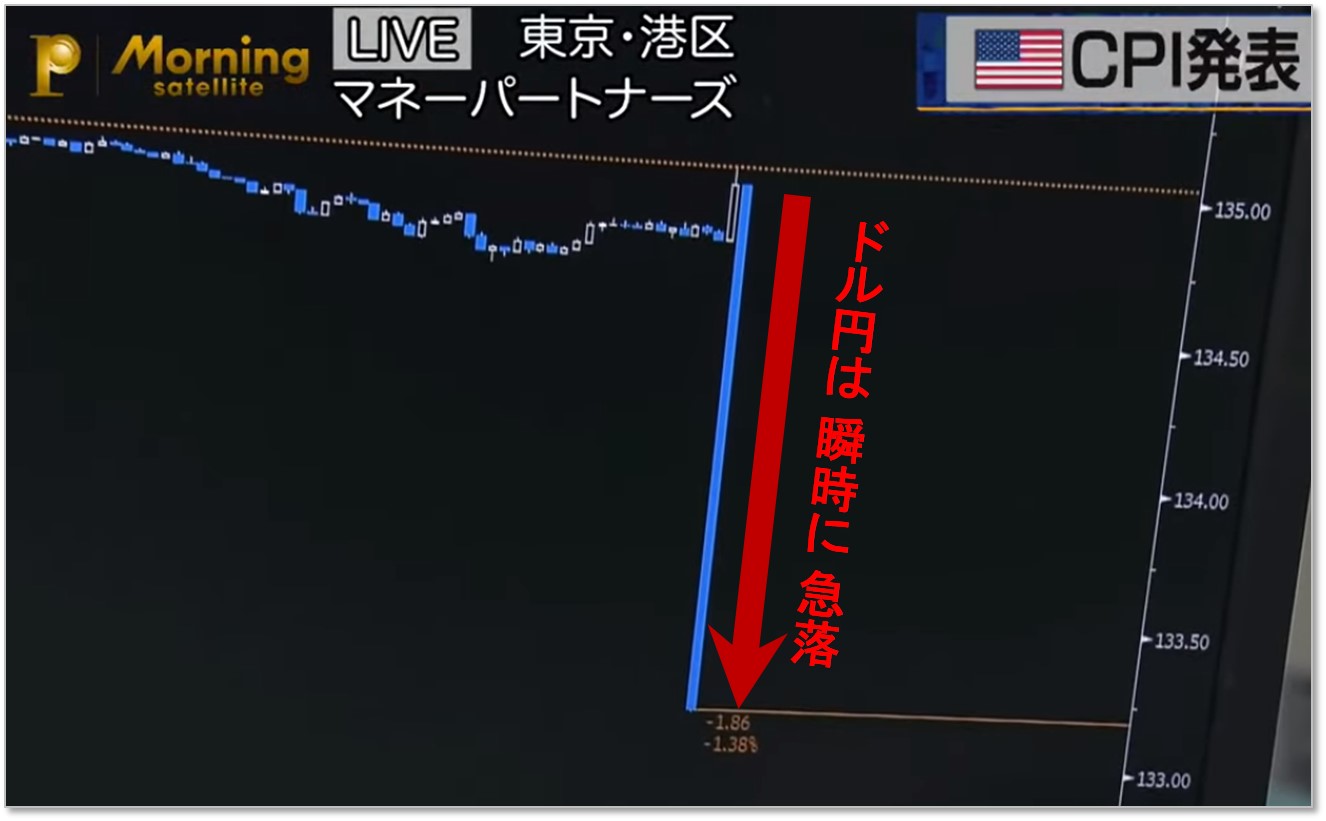
※赤矢印・赤枠は、筆者が加入
※画像出典:テレ東BIZ|【緊急ライブ】米CPI発表の瞬間
下記に、テレビ東京の公式動画がある
↓
関心が非常に高いことを、感じてもらえるだろう
↓
また、秒刻みの緊迫感も、感じてもらえるだろう
↓
テレ東BIZ|【緊急ライブ】米CPI発表の瞬間
-- 消費者 経済 総研 --日本でも、 米国CPIに、 大注目
◆まとめ|米国の注目の 経済指標
インフレ率のCPI、そして金利が、注目される
↓
米国の国の借金のニュースは、取り上げられない
↓
日本だけが、国の借金の額で、大騒ぎしている
国の借金で 騒ぐのは、日本だけ
米国では、話題にならない
-- 消費者 経済 総研 --
◆「日本の借金が、過去最高」 発表で、暴落?
金融関係者は、日本の借金額に、どう反応したか?
↓
22年8/10(水)14時に、「国の借金額」が発表された
↓
日本国の借金は、1255兆円で、過去最大となった
↓
日本の金融の市場は、暴落したか?
↓
違う。 株価は、上昇した
↓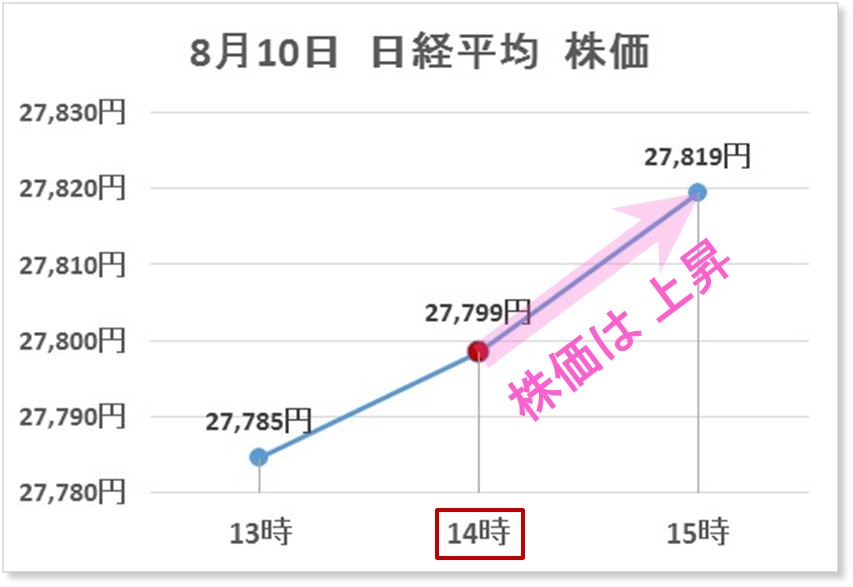
日本の借金 過去最高で、
株は、下落どころか 上昇
-- 消費者 経済 総研 --
◆株よりも 「金利」 が、借金に 反応?
前項では、「 株価 」 について、述べた
↓
借金の増減は、株よりも、「 金利 」の方に、影響する
↓
金利の高・低の原因を、わかりやすく解説してみる
↓
A お金を、返さなそうな人 ( 破綻しそうな人 )
B お金を、しっかり返す人 ( 健全な人 )
↓
Aに貸すのは不安だ。 金利が低いなら貸さない
Bに貸すのは安心だから、金利が低くても貸す
↓
借金大国・日本は、財政破綻の寸前と言う人がいる
↓
その借金大国の日本が、更に借金が増えたら?
↓
「 破綻リスクが、より高まる 」 と言う人がいる
↓
リスクが高まれば、低金利では、貸し借りできない
↓
よって、リスクが高まれば、金利は上昇する
↓
つまり、借金増加の発表で、金利は上昇するはずだ
↓
国の借金で、直接的に影響を受ける指標は、何か?
↓
それは、国債の「金利」だ
↓
「 国の借金 」と 「 国 債」 の関係を、知りたい
↓
「 そもそも 国債 とは? 」 を、ご覧頂きたい
↓
借金の増加で、「 国債の金利は 上昇 」 するはずだ
借金増加が リスクなら、
国債の金利は 上昇 するはず
-- 消費者 経済 総研 --
◆金利は、急騰したか?
借金の発表で、日本国債の金利は、どうなったか?
↓
8月10日14時の借金額の発表で、金利急騰だろう
↓
違う。 日本の国債の金利は、低下した
↓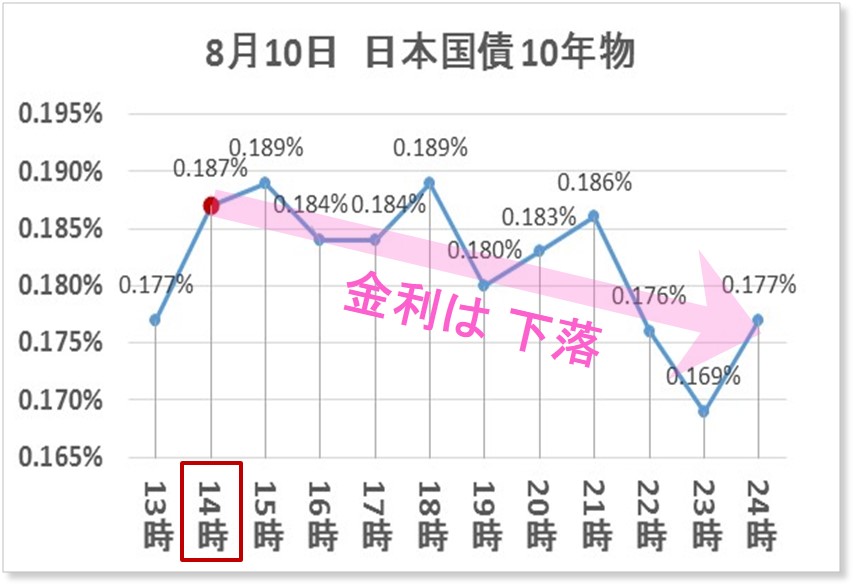
過去最大に、借金増加しても、
金利は、上昇どころか、下落した
-- 消費者 経済 総研 --
◆借金増加でも、 「 日本円 」 は、不変?
「 国の借金 のせいで、日本円の 信頼が、下がる 」
「 よって、円は暴落する リスクがある 」
↓
こんなことを、言う人がいる
↓
では、過去最大の国の借金の発表で、円は暴落か?
↓
違う。14時の発表後、円は下がらず、横ばいだった
↓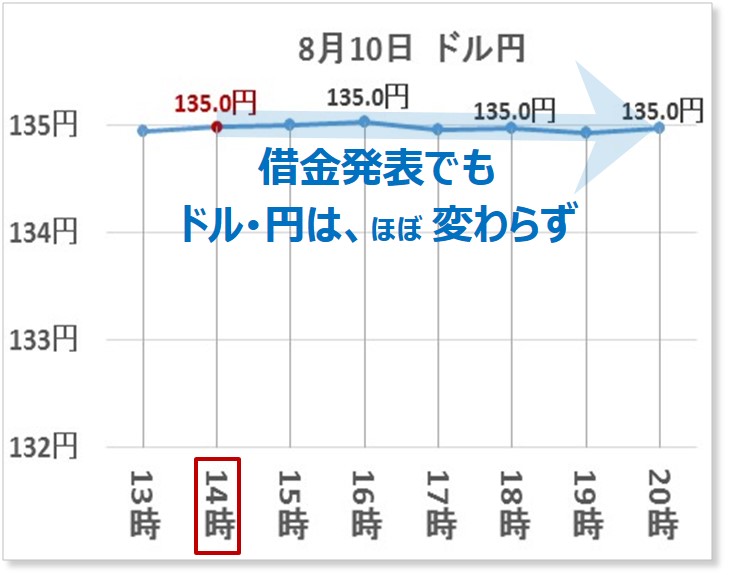
米国CPI発表と日本の借金発表は、8月10日だった
↓
たまたま、同じ日だった
↓
14時に日本の借金発表で、21:30に米国CPI発表だ
↓
日本の借金発表では、円は反応せず、横ばいだった
↓
だが21:30、米CPI発表で、急激な円高へ(ドル急落)
↓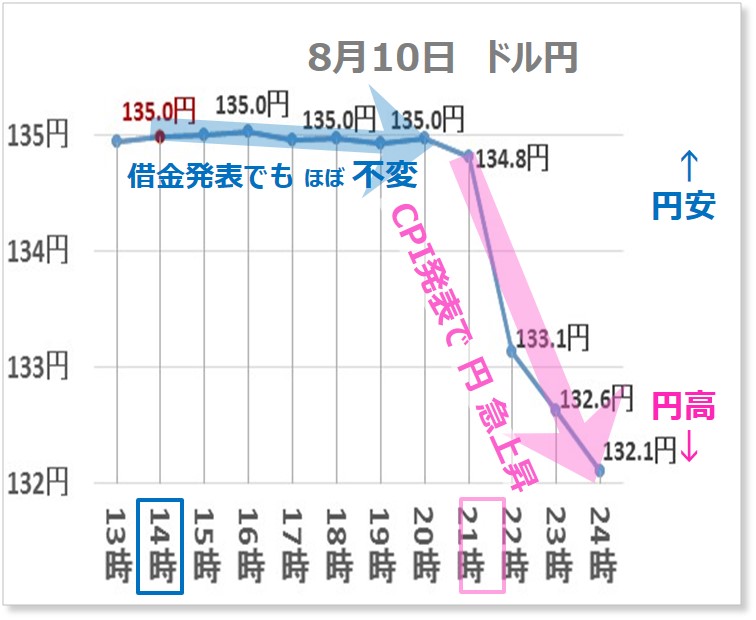
日本円は、借金に無反応で、米CPIに強く反応した
↓
日本の国の借金増加で、日本円の信頼は落ちない
借金増加でも、円の信頼は不変
米国CPIの方が、はるかに重要
金融市場の参加者は、多数いるが、
彼らは、借金の増加を、無視した
-- 消費者 経済 総研 --
◆個人投資家は、国の借金を、無視する?
日本人は、預貯金が多く、株等への投資は少ない
↓
少ないながらも、成人の約2割が、投資経験者だ※
※出典:日本証券業協会|中間層の資産所得拡大に向けて
成人の約2割とは、人数では、約2000万人だ
↓
日本での割合が小さくても、人数では、結構いる
↓
これだけ多くの人は、借金額の発表で、どうした?
↓
過去最大になった借金の増加に、反応しなかった
↓
金融の理解者は、「国の借金 問題無い」だからだ
国の借金を、
個人投資家は、無視している
-- 消費者 経済 総研 --
◆プロの 機関投資家は、どうした?
前項は、日本の 「 個人投資家 」 に、ついてだった
↓
「プロの機関投資家」は、国の借金を、どう考える?
↓
筆者(松田)は、プロ機関投資家と、交流をしている
↓
債権、株、為替のトレーダーに、調査した事がある
↓
日本で 「何が、重要指標か?」とのアンケートをした
↓
1位 GDP
2位 日銀短観
3位 CPI
4位 鉱工業指数
5位 機械受注
6位 設備投資
7位 小売売上高
8位 有効求人倍率
9位 景気動向指数
10位 景気ウォッチャー調査
↓
上から順番に、重要度が高い
↓
国の借金を、プロの機関投資家は、無視している
プロの 機関投資家 は、
国の借金を、無視 している
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本も海外も、投資家は、無視?
外人の投資家も、日本の金融市場に、参加する
↓
世界中で、多くの投資家が、日本金融市場に参加だ
↓
これだけ多くの人が、借金増加発表に、反応しない
↓
金融がわかる人は、「 国の借金 問題無し 」だからだ
金融に詳しい人は、
日本も、海外も、
日本の借金額を、無視する
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本で 「借金は問題」 と、言う理由は?
[1] そう言った方が、自分が、得をする
[2] そう言わざるを 得ない立場にある
[3] 単純に 情報不足
[1]と[2]は、ポジショントーク だ。
有名な肩書きを、持つ人でも、言う人がいる
-- 消費者 経済 総研 --
◆続編は?
▼なぜ、ポジショントークが、出て来る?
▼金融界は、意図的にポジショントークだらけ?
▼報道界は、なぜ、借金NGか?
▼ポジショントークや、セールストークから、
自分の身を守るには?
これらを、続編で、取り上げたい
-- 消費者 経済 総研 --
- ◆本ページを、リンク等で広めて、頂きたい
- 日本には、将来に不安を、持つ方も多い
↓
「 借金は、将来世代へ、付け回し される 」
「 日本の将来は、借金で、破綻する 」
↓
このように、言われたからだ
↓
既述の通り、日本の国の借金は、問題ない
↓
過度な不安を、持たなくて良い。 楽観してよい
↓
将来不安に、おびえると、日本は、一層低迷する
↓
若者が夢や希望を、持たなく なってしまう
↓
明るい未来のために、本ページを、広めて欲しい
↓
本ページへのリンク設定の協力を、お願いしたい
松田からのお願いです。リンクをお願いします 消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸
消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸

- ■MMT理論とは?|高圧経済 その5
- 2022年 9月 4日 (日) に 投稿
Vol.9 (第2部の高圧経済の 5回目)
令和1年から急激注目の「MMT理論」とは?
◆「3分でわかる MMT」 の簡単解説
今回は「要約・ポイント編」で、3分でわかる MMT
MMT 理論 とは? 一体何者か?
令和から 急に注目が 集まった MMTを、簡単解説
◆メリット・デメリットは?
MMT理論では、財政赤字も、肯定される。
MMT理論では、国の借金も、肯定される。
だが、MMTには、問題点が、指摘される事がある。
「MMTは間違いだ」との批判が、される事もある。
MMT理論の反対派からは
「嘘だ、おかしい」とも言われる事もある。
机上の空論か? 危険な理論なのか?
逆に、MMTを評価するリフレ派の賛成派もいる。
はたしてMMTは、正しいのか? 正しくないのか?
こうして、賛否あるなか、MMTの概要と
デメリット(欠点)と、メリット(利点)を、見ていく。
日本の国の借金は、MMT理論で、どうなる?

- ■東京新聞に掲載
- 「 日本は 借金大国 とは言えない 」
筆者(松田)が、取材を受け、
準全国紙・東京新聞に、掲載された。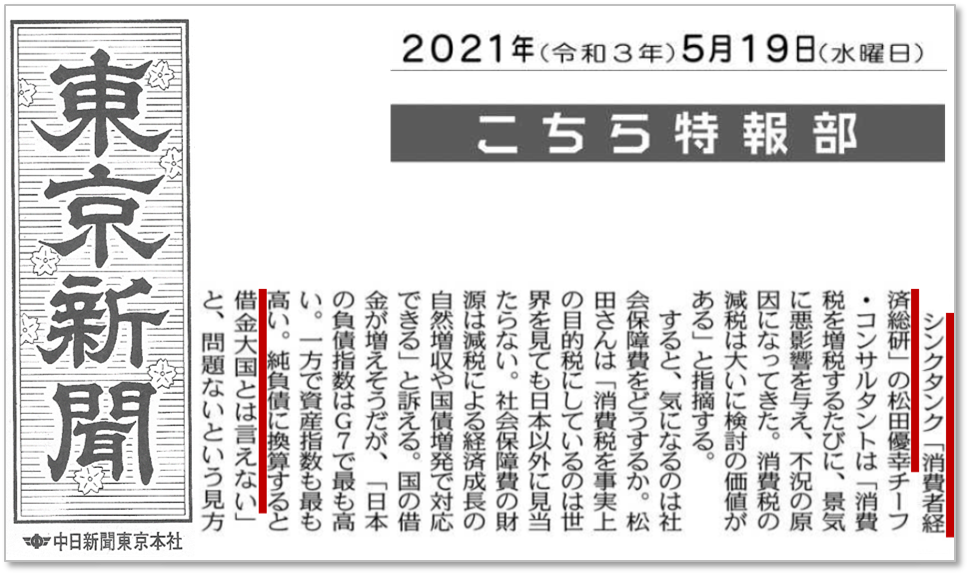
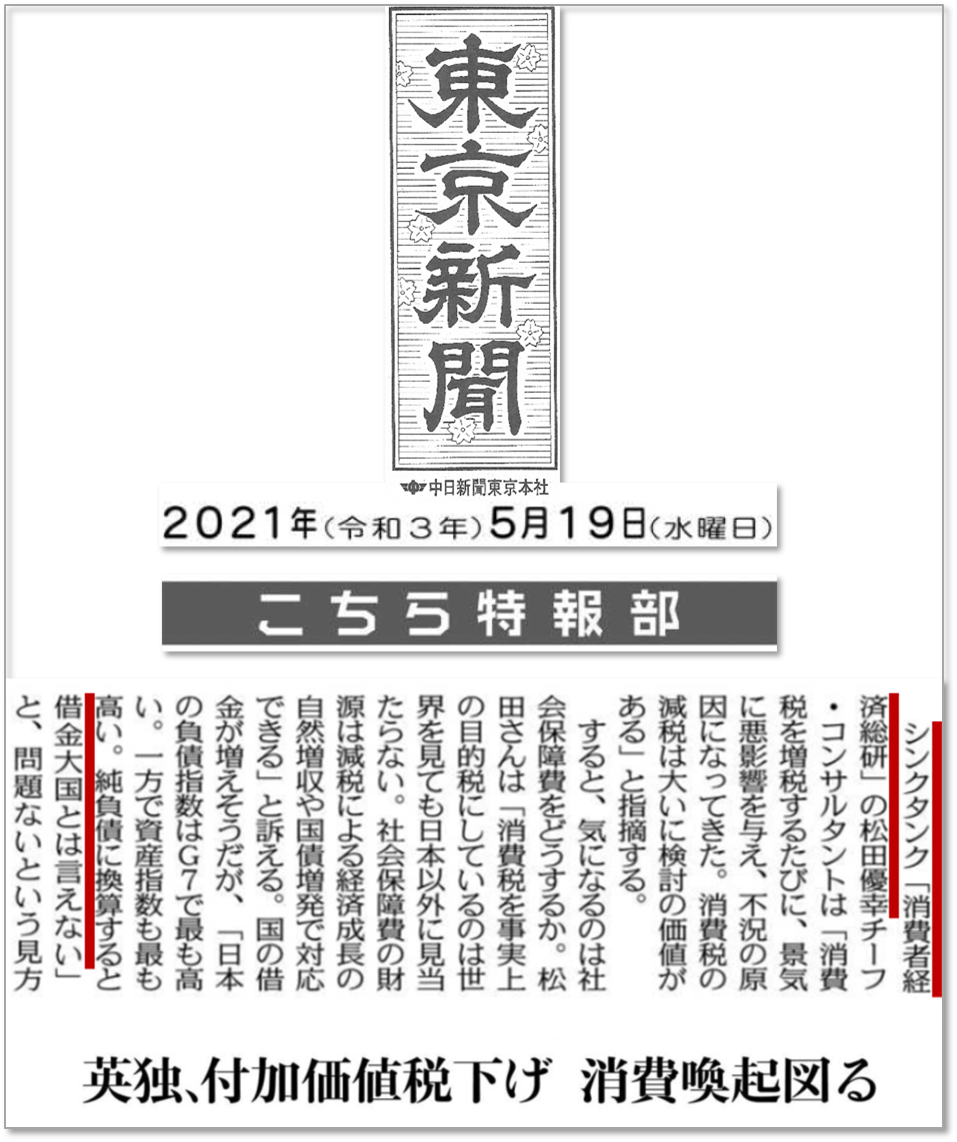

- ■MMT理論の 要約・ポイント編
- MMT 理論 とは?
MMTの メリット・デメリット は?
令和から 急に注目が 集まった MMTに迫る
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「 MMT 理論 」 とは、何か?
簡単に、わかりやすく、知りたい
↓
A:政府がお金を、集める手段は、
「 税金 」 でも、「 国の借金 」 でもない。
政府が、自らお札を刷って、
お金を生み出す、という理論だ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「財源が、税金ではない」 ならば、
政府の支出で、政府は財政赤字に、なるか?
↓
A:そうだ。 政府は、財政赤字になる
-- 消費者 経済 総研 --
Q:政府の赤字は、何で埋め合わせを、するのか?
↓
A:日本も含め、今までの先進諸国は、
「国の借金」を増やして、赤字に対応した
-- 消費者 経済 総研 --
Q:MMTは、国の赤字と借金を、どう評価するか?
↓
A:国の 「 財政赤字も、借金も、問題なし 」 だ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「 財政の赤字額 」 が、増えると、
その赤字額の分だけ、「 国の借金 」が増える。
なぜ、国の借金は、問題ないのか?
↓
A:麻生元首相の説明が、わかりやすい。
それは、次の有名なフレーズだ
「 国の借金?
お金を刷って、返せばいい。 簡単だろ? 」
-- 消費者 経済 総研 --
Q:MMTのメリットは、何か?
↓
A:「 財政赤字は、OK 」 になる
「 国の借金も、OK 」 になる
政府は、多くのお金を使って、よいのだ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:増えたお金を手にした政府は、何をするのか?
↓
A:政府は、財政支出を、拡大できる。
それによって、景気を拡大できる
赤字でも、借金増加しても、問題なく、
政府は、支出を増やせるのだ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:政府の財政支出で、具体的に、何をやるのか?
↓
A:災害予防の工事や、教育予算を増やしたり、
幼稚園・保育園の充実、福祉の充実や、
AIなどへの未来投資・・など、様々ある。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:国民に、役立つモノが、増えるのだな?
↓
A:そうだ。 国民のメリットは、とても大きい。
さらに、企業にも、メリットがある
-- 消費者 経済 総研 --
Q:企業のメリット とは、何か?
↓
A:政府が、工事を始め、様々な発注をする。
その仕事を、受注するのは、民間企業だ。
政府の発注 (政府の支出) の増加で、
企業の売上が、増えるのだ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:企業の売上が増えると、私たちの賃金は?
↓
A:売上増で、賃金UPの原資が、増える
-- 消費者 経済 総研 --
Q:ということは、それも国民のメリットだな?
↓
A:そうだ。 下記2つの国民へのメリットがある
① 防災・教育・福祉・未来投資などの充実等
② 賃金UPの原資が 増える
-- 消費者 経済 総研 --
Q:他に、日本の国民のメリットは、あるか?
↓
A:税は主財源ではないので、重税感がなくなる
-- 消費者 経済 総研 --
Q:MMTは景気にも、企業にも、国民にもプラスで
メリットが、多いのだな?
↓
A:そうだ。 MMTには、メリットが多い
-- 消費者 経済 総研 --
Q:MMTのメリットは、わかった。
では、デメリットは、何か?
↓
A:MMTのデメリットは 「 インフレ圧力 」 だ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:なぜ 「インフレ圧力」 に、なるのか?
↓
A:MMTでは、お金を増やせる。
お金が増えれば、インフレ率は高まる
-- 消費者 経済 総研 --
Q:お金が増えると、インフレ圧力との仕組みは?
↓
A:増えたお金で、政府は、様々な支出をする。
つまり、政府の 「 需要が、増える 」
「 需要 > 供給 」は、価格を上げる作用がある
また、別のロジックでも、簡単解説している
「ミカンの例で、簡単3分解説」をご覧頂きたい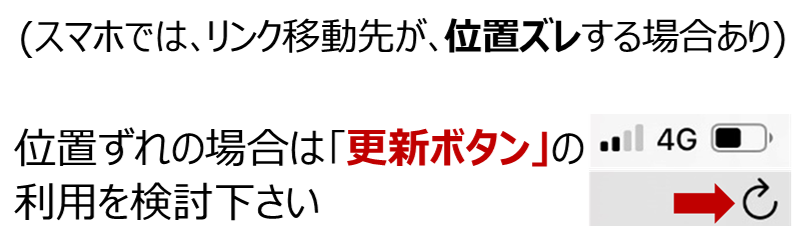
-- 消費者 経済 総研 --
Q:日本は、インフレになっても、よいのか?
2022年は、値上げラッシュが、続いているぞ
↓
A:2022年の値上げは、
悪天候、コロナ、戦争の一時的な要因による。
「 一時的な 値上げ 」 であって、
日本は、まだ 「 デフレ脱却 」 していない
-- 消費者 経済 総研 --
Q:デフレ脱却が未完なら、インフレは良いのか?
↓
A:そうだ。 デフレの日本には、
インフレ圧力は、逆に好都合なのだ
お金の増加で、インフレ圧力が、かかり、
日本は、デフレ脱却できる
-- 消費者 経済 総研 --
Q:でも、インフレが、過剰になったら、心配だ
↓
A:心配ない。
その時は、政府はブレーキを、かけるからだ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:どうやって、ブレーキを、かけるのか?
↓
A:「 増税 」 を、するのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:増税すると、なぜ物価が、冷えるのか?
↓
A:増税すると、民間部門のお金が減る。
お金の量が減れば、需要も減る
需要減で、「供給>需要」となり、物価は下がる
-- 消費者 経済 総研 --
Q:ということは、MMTでの税金は「調整機能」か?
↓
A:そうだ。 MMTでの税金は、
「 財源 機能 」ではなく、「 調整 機能 」だ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:政治家は、MMTを、導入しないのか?
↓
A:政界でも、令和元年から、急激に、
MMT側に、傾いてきた
-- 消費者 経済 総研 --
Q:「 MMT側に、傾く 」 とは?
↓
A:MMTを、標榜するのは、まだ一部の政党だ
MMT的な路線の理解が、増えたという段階だ
-- 消費者 経済 総研 --
Q:自民党や野党は、どう考えるのか?
↓
A:本ページのこの先に、進んで頂きたい
-- 消費者 経済 総研 --

- ■自民党・野党と、MMTは?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆MMTや、財政姿勢 への 分類
MMTに 遠い側と、MMTに 近い側 の分類では、
国の借金や、財政収支 への姿勢なども分類できる。
-- 消費者 経済 総研 --
◆政党別では、どうか?
MMTに近い政党と、MMTに遠い政党は、どこか?
↓
21衆院選・22参院選の公約からは、下図であろう
↓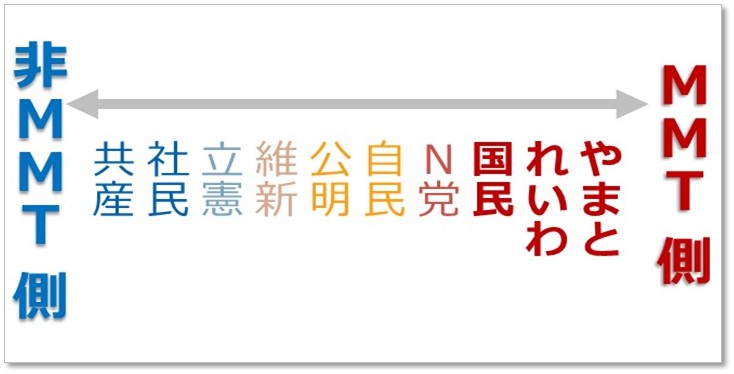 ※消費者 経済 総研が、上図を作成
※消費者 経済 総研が、上図を作成
「 新党やまと 」 は、
政策公約に、「 MMT 」 を、明記し標榜した。
「 れいわ新選組 」 と 「 国民民主党 」 は、
MMTの言葉は、使わないが、かなり「 MMT側 」だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆自民党内 の 温度差 は?
同じ自民党の中でも、スタンスは違うのか?
↓
そうだ。 かなり違う
↓
故安倍元首相や、高市氏は、「MMT側」だ
↓
岸田首相や、麻生元首相は、「非 MMT側」だ
↓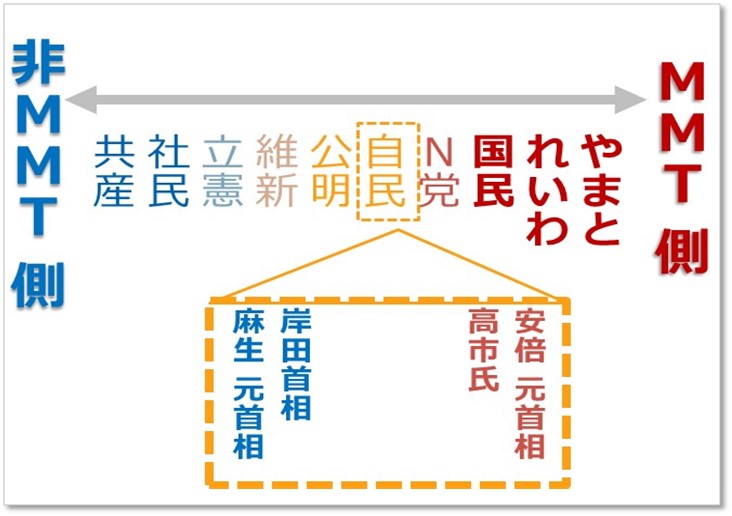 ※消費者 経済 総研が、上図を作成
※消費者 経済 総研が、上図を作成
※自民党の 「MMT側 」 には、
高市氏の直轄の 「財政政策 検討本部」がある。
安倍元首相が、最高顧問を、務めていた。
※自民党の 「非 MMT側 」 には、
岸田総裁直属の「 財政健全化 推進本部 」がある。
麻生元首相が、最高顧問を務める
この2つの本部は、下記ページで、解説している。
「 政策本部 vs 健全化本部 とは? 」-- 消費者 経済 総研 --※安倍氏、高市氏をはじめ借金肯定派であっても、
「借金は善」のような明確な表現は避けて、
回りくどいが、借金は悪ではない趣旨を言っている。
◆ 「MMT側」 が、増えた?
政治家は、 「 MMT側 」 が、増えたのか?
↓
そうだ。 与党も野党も、MMT側が、近年増加した
↓
自民党は、近年は、どのように変化したか?
↓
自民党は、令和元年から、MMT側が急増だ
↓
令和から、急増したのは、なぜか?
↓
令和元年の講演が、影響したのだろう。
この元年の講演の件は、次回以降で、解説する

- ■連載|日本は借金大国ではない?
- 「 日本は 借金大国ではない 理由 」 を、
過去2回、連載してきた。
その前編2つは、下記をご覧頂きたい。
*Vol.1【バランスシート編】日本借金大国は嘘?
負債だけではなく資産も含めた純負債で優等生
*Vol.2【日銀・政府編】なぜ借金大国ではない?
国の借金は、親子関係にある日銀が、担う
今回の本ページは、その続編 Vol.3 に相当し、
「 MMT理論 」と「 MMT的な理論 」の解説だ
本ページは「ニッポン 爆上げ作戦 その9」でもある

- ■「借金は悪」と、言われる理由とは?
- 「次世代への、借金の先送りは、ダメ」
「日本は借金大国なので、増税が必要だ」
「日本の財政支出を、減らす必要がある」
上記のフレーズが、しばしば聞かれる。
しかしいずれも、問題視する必要はない。
なぜ「先送りはダメ」等のフレーズを言うのか?
その理由は、下記3つの、いずれかだ。
[1] そう言った方が、自分が、得をする
[2] そう言わざるを得ない立場にある
[3] 単純に情報不足
[3]は、知識の習得で解消する。
[1]と[2]は、ポジショントーク だ。
消費者経済総研は、財務を預る役所でもなく、
特定政党の支援を、する立場でもない。
つまり、当方のポジションは、ニュートラルだ。
「わかりやすく解説する」との立場に、いるだけだ。
※なお「ポジショントークは直ちにNG」
というわけではない。
先送りダメと言う人は、「だいぶ減った」と感じる。
知識の習得(情報の共有・伸展)が、進んだのだろう。
筆者(松田)は、35年以上前に、慶応大学 経済学部
に入学以来、経済を研究している。
しかし本稿は、経済学の知識なしでも
わかるような簡単解説としている。
MMTは、筆者(松田)の解説が、
「 とことん わかりやすい 」 と、思っている。

- ■MMT続編|高圧経済6|爆上げVol.10
- 2022年 9月 10日 (土) に 投稿
Vol.10 (第2部の高圧経済の 6回目)
MMT-2:なぜ、日本円なら、借金OKか?
今回号は、MMTの続編で、
高圧経済その6|ニッポン爆上げVol.10 に、相当
-- 消費者 経済 総研 --
◆積極財政で、高圧経済へ?
「連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦」
の第2部は、「景気 UP 編」だ。
「 積極財政 」で「 高圧経済 」の実現
このテーマを、現在、継続中。
さて、日本の 「 金融政策 」 には、変更はない。
変更無いのに、金融政策・日銀の話題が、多すぎる。
今の日本で、重要なのは、「 財政政策 」 だ。金融政策よりも、財政政策が重要
とても重要なのに、注目度が、低すぎる
「 その 大変重要な 財政政策 」 に、
「 高圧経済 」 の政策がある。
高圧経済という 財政政策を、提言
積極財政で、高圧経済を、実現へ
-- 消費者 経済 総研 --
◆財源は?
高圧経済のために、「 政府の支出 」を、増やす。財源は、 税金 or 国の借金 ?
すると 「 財源は、何? 」 となる。
従来までの財源は、「 税金 or 国の借金 」 だった。
今注目される 「 MMT 」 での財源は、何か?
「 政府が自ら、お札を印刷して、お金を増やす 」
これが、MMTの財源である。
前回号は、「 要約編 」として、簡単解説だった。
MMTの利点と、欠点の両方を、簡単解説した。
今回号は、より詳しく、解説する。

- ■政府支出は、国民と、景気のため?
- 「高圧経済」にするために、「政府の支出」を増やす。
では、近年の「政府の支出」の「額・内容」は、どうか?
-- 消費者 経済 総研 --
◆GDPと政府の支出
日本のGDPの内訳は、次の通りだ。
① 60%が、個人の消費
+
② 25%が、政府の支出・投資
+
③ 15%が、企業の設備投資
+
④ 純輸出は、1%未満
※上の %の値は、近年での概数
-- 消費者 経済 総研 --
◆政府支出は、国民と企業に、プラス?
GDPでの政府の支出・投資の額は、どのくらいか?
近年(直近10年平均)は、年間約135兆円だ。
※「 政府の支出・投資 」は、以降 「 政府の支出 」 と略す
そもそも、「政府の支出」は、何のためか?
-- 消費者 経済 総研 --
◆国民の便益 のため?
②の政府の支出では、何をするか?
建設工事や、社会福祉、防衛など様々だ。
つまり、国民の役に立つ、物事への支出だ。
その政府の支出の予算が、増えれば、どうか?
災害予防の工事や、教育予算を増やしたり、
幼稚園・保育園の充実、福祉の充実や、
AIなどへの未来投資・・など、様々できる。
政府の支出が、増えれば、
国民の役に立つ便益が、増えるのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆景気拡大 のため?
また同時に、「 景気拡大 」の意味もある。
政府の支出(発注)で、民間企業が、受注する。
それで、民間企業の売上は、増加する。
民間企業部門の「売上増加」で、景気拡大する。
売上増えれば「 私達の賃金UPの原資 」も、増える。
企業にも、そして、働き手(消費者)にも、プラスだ。
国民の便益のため、景気拡大のための政府支出だ。
これは、海外の先進諸国でも、同じである。
政府の支出は、国民の便益のため
政府の支出は、景気拡大のため
-- 消費者 経済 総研 --
◆目的を、再確認する
「 ①景気UP ②企業売上UP ③賃金UP 」
本連載は、上記3つを、目的としている
「 ③ 私たちの 給料を 増やす 」
本連載は、その③までが、目的だ。
そのための 「 積極財政 による 高圧経済 」 だ。高圧経済で、私たちの給料も UP
お金を増やして、政府の支出を、増やすのだ。
それで 「 景気UP・企業売上UP・賃金UP 」 にする。
この目的の実現のために、MMTの理解が需要だ。
※政府の支出の増加で、
景気・売上・賃金が、UPする 仕組みは、下記参照
「過去号・その1|なぜ「高圧経済」なのか?」

- ■財源は、どうなる?
- 高圧経済・積極財政では、政府の支出を、増やす。
では、「 政府の支出を、増やす 」 と、どうなるか?
↓
「増税 無し」 なら、財政赤字が、増える
↓
その赤字の分だけ、国の借金が、増える
-- 消費者 経済 総研 --財源は、どうなる?
・政府の支出が、増える
↓
・財政赤字が、増える
↓
・国の借金が、増える
◆財源問題が、課題?
高圧経済のための積極財政では、
「 財源 」 が、課題になる。

- ■借金が悪なら、 増税?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆借金が悪なら、 増税しかない?
日本では、「 国の借金は、けしからん 」と言われる。
借金がダメなら、 「 財源は、 増税 」 だ。
-- 消費者 経済 総研 --借金ダメなら、 増税か ?
◆国民は、 増税を、求めてない?
ならば、日本国民は、「 増税を、求めている 」 のか?
「 増税希望! 」 なんて言う人は、少数派だ。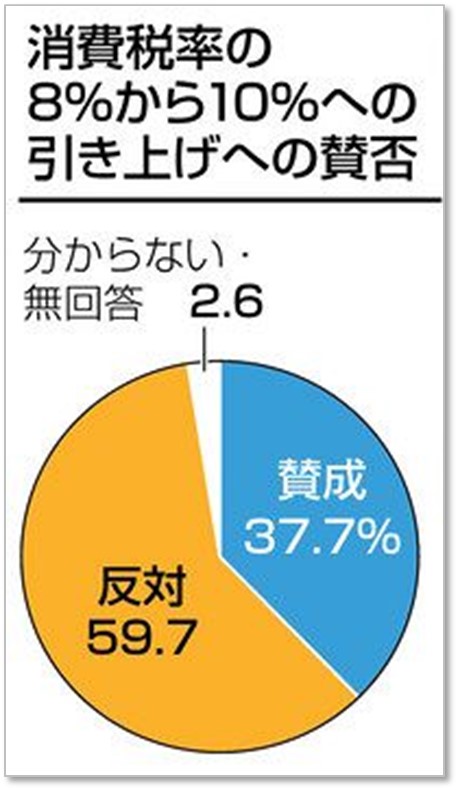 ※出典:東京新聞TOKYO Web|消費増税、反対60% 全国世論調査
※出典:東京新聞TOKYO Web|消費増税、反対60% 全国世論調査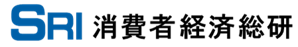
◆増税では、日本は、低迷する?
消費税の増税で、
失われた20年が、起きたことを、知っている。
消費増税 ( 1997年 )で、私たちの賃金は下落した
↓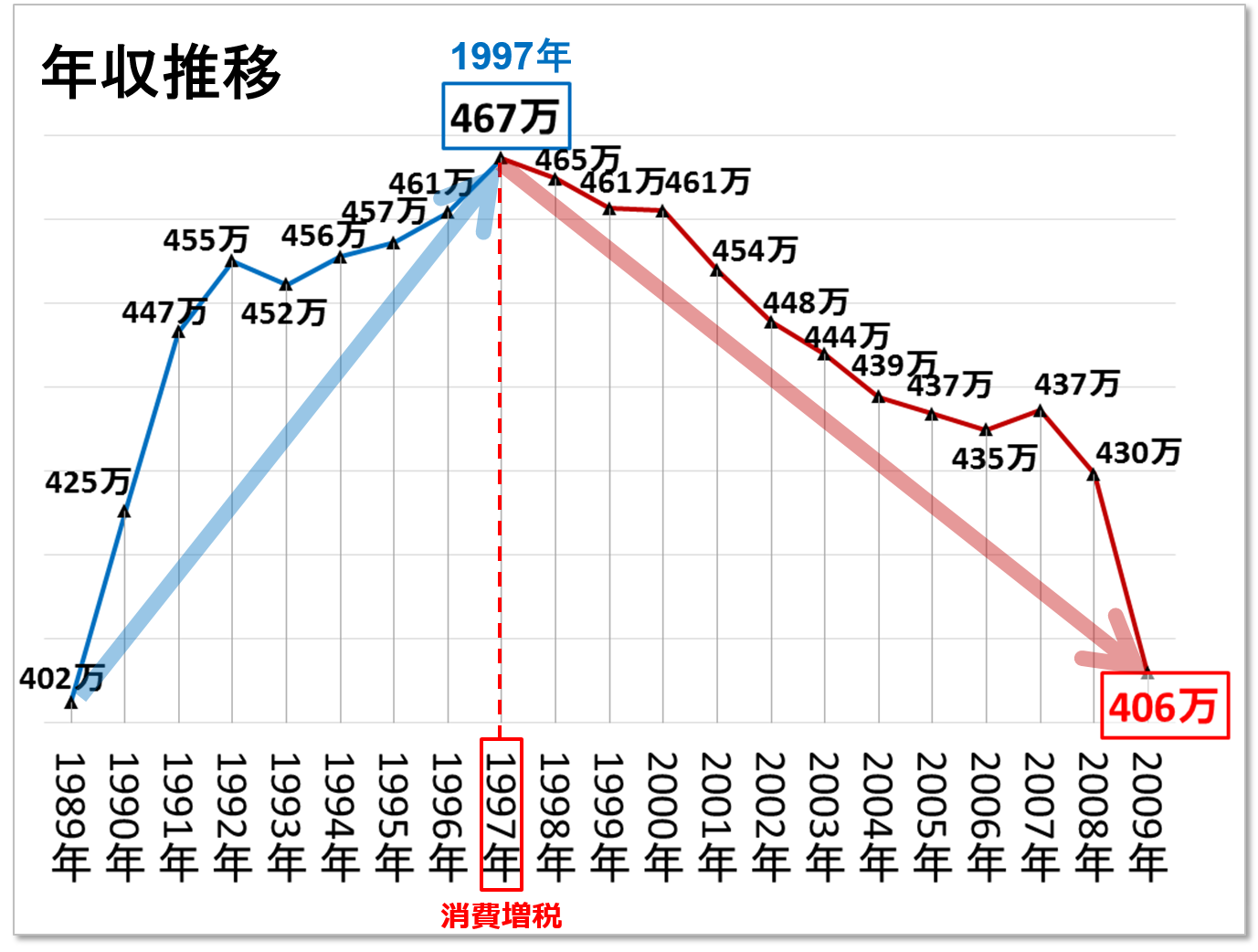 1997年に消費税の増税
1997年に消費税の増税
増税で、日本の低迷 スタート
増税は、私たちの給料を、下げる
-- 消費者 経済 総研 --
◆増税以外の選択肢が、必要?
本連載は、下記3つを、目的としている
「 ①景気UP ②企業売上UP ③賃金UP 」
「 ③ 私たちの 給料を 増やす 」
本連載は、その③までが、目的だ。
「 増税以外 の 財源 」 を、選択するのだ。
増税以外 の 財源 を、選択

- ■なぜ、 「 MMT 」 なのか?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆MMTを理解し、財源を理解
連載シリーズで、MMTを解説する目的は、何か?
それは、 「 財源 」 への理解の促進だ。
日本では、「 財源問題 」への「 誤解 」が、多すぎる。
それは、なぜか?
原因は、不十分な義務教育である。
金融・経済の義務教育が、少なすぎる。
よって金融・経済のリテラシーが、不足してしまう。
日本人の金融・経済のリテラシーが、低いことが、
既に、指摘されていた。
自分の国の財政の状態が、わからないのは、問題だ。
小中の義務教育から、高校までで、
金融・経済の教育を、拡充すべきである。
そうしないと、日本は、どうなる?
誤った判断や、誤った決定を、してしまう。
日本国と、日本国民が、誤った道を、進んでしまう。
というより、誤解によって、
既に、誤った道を、歩いてきた。
世界の各国に比べて、日本は、低迷している。
早く、改める必要が、あるのだ。

- ■3つの目の 財源 とは?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆3つの目の 財源を、選択?
政府の支出を、増やすための、財源は何か?
今までの財源は、下記の2つだ。
[1] 増税、または、[2] 国の借金
では、MMTの財源は、何か?
MMTの財源は、 「 政府が自ら、お札を印刷 」 だ。
MMTの最大の特徴は、
「 財源は、政府が自ら、お札を印刷 」 である。
MMTの 最大の特徴 は、
財源は、政府が自ら、お札を印刷
-- 消費者 経済 総研 --
◆3つの目の 財源は、政府の発行?
[1] 増税、[2] 国の借金 でもない。
[3] 政府が自ら、お札を印刷 が、3つ目の財源だ。

- ■用語の解説
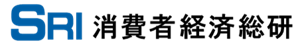
◆用語の解説
後で、出てくる用語を、先に解説する。
「 自国通貨 」とは、
日本国の通貨で、つまり「 円 」のこと
「 債務 」とは、
お金を支払う義務
「 政府債務 」とは、
日本政府の、借金を返す義務
「 債務残高 」とは、
返すべき借金の、合計額のこと
「 デフォルト 」 とは、
債務不履行のこと。
債務(義務) を、 履行(実行)できない。
つまり「 借金を返す義務が、実行できない 」こと
「 国債 」とは、
国の借金は、大半が、国債の売買で、なされる。
詳しくは「そもそも「国債」 とは?」を参照

- ■MMT とは?
- ◆MMTとは、何の略?
MMTとは、「 Modern Monetary Theory 」の略で、
「 現代貨幣理論 」 と、訳される。
-- 消費者 経済 総研 --
◆MMTでの、財源とは?
MMTを完全導入したら、政府支出の財源が変わる。
政府の財源として、「 税金は、不要 」 だ。
政府の財源として、「 借金(国債)も、不要 」 だ。
政府の財源は、税でも、国債(国の借金)でもない。
政府は、通貨(お金)を、自ら発行 するのだ。
「 政府が 通貨を 発行 」 とは、
政府自身が、お札を刷ったり硬貨を製造する事だ。
それが、政府の財源だ。 財源を、自ら生み出すのだ。
「政府が生んだ通貨」で、国民のための支出をする。
公共事業、防衛費、社会保障などの財源は、
税や国の借金ではなく、政府が発行した通貨だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆MMTの最大の特徴は?
再掲するが、MMTの最大の特徴は、
「 財源は、政府が自ら、お札を印刷 」 である。
この点を強調しないと、次項以降、混乱を招く。
再度、このMMTの最大の特徴を、再確認頂きたい。
MMTの 最大の特徴 は、
財源は、政府が自ら、お札を印刷
-- 消費者 経済 総研 --
◆「MMT」のポイントを、まとめると?
消費者経済総研が、わかりやすく要点を整理する。
↓
政府の財源は、通貨を自ら発行して、まかなう
↓
その通貨で、政府は、積極的に、財政支出をする
↓
それにより、需要が拡大し、景気は良くなる
↓
同時に、国民の役に立つ物が、作られ、増える
↓
財源は、「 新たな通貨発行 」で、税も国債も不要
↓
税と国債は、調整弁として使い、主な財源ではない
↓
お金の増やし方は「増税」や「借金」ではない
↓
国が、お金を「新たに発行」するのだ
-- 消費者 経済 総研 --
◆MMT の メリット ・ デメリット は?
▼メリットは?
政府の支出の拡大で、国民の便益UP・景気拡大へ。
財源は、増税や借金でなく、政府が自ら、通貨発行。
MMTによって、政府の支出の財源が、豊富になる。
▼デメリットは?
MMTのデメリットは、 「インフレ圧力」だ。
デメリットの詳細は、追って、解説する。

- ■日銀と財務省の見解は?
- ◆日銀の黒田総裁は?
日銀の黒田総裁は、MMTを、次のように述べた。
「自国通貨建て政府債務はデフォルトしないため
財政政策は、財政赤字や債務残高等を考慮せずに
景気安定化に専念すべき 」 という理論
※各用語の解説は、上段の「用語の解説」を参照
上記を、日本に当てはめて、簡単にすると、下記だ。
「日本円での返済義務は、果たせるので、
国の赤字や、国の借金額を、気にせずに、
景気を良くするための財政政策に、専念すべき」
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本は デフォルト するか?
上の黒田氏の発言の中に、「デフォルト」があった。
日本国は、デフォルトするのか?
-- 消費者 経済 総研 --
◆デフォルトに関する 財務省の見解は?
▼財務省 個人発言では?
氷山(借金の塊)に衝突し、タイタニック(日本)が沈む
上記のような趣旨を、財務省 事務次官が発言した。
これを、上司の鈴木財務相は「個人的発言」 とした。
▼財務省 公式見解では?
財務省の公式サイトの中には、下記の記載がある。
「日・米など 先進国の自国通貨建て 国債の
デフォルトは 考えられない。」
財務省は、「 日本は、デフォルトしない 」と言う。
これが、財務省の公式見解だ。
※出典:財務省 公式サイト
-- 消費者 経済 総研 --
◆デフォルトした 外国の事例は?
▼アルゼンチン政府では?
アルゼンチンの自国の通貨は、「ペソ」だ。
「ドル」は、他国の通貨で、自国の通貨ではない。
アルゼンチンは、「自国通貨 ペソ」を発行できても、
「他国の通貨 ドル 」の発行は、当然できない。
アルゼンチン政府は、外国から「ドル」で借金した。
それが返済不能になったので、デフォルトした。
アルゼンチンの2001年デフォルトでは
アルゼンチンは、世界金融市場から締め出された。
▼日本円は、日本の自国通貨?
日本の「円」は、日本の自国の通貨だ。
ドルでの借金ではなく「円」での借金ならどうか?
円建て借金が、返せないなら、日本は、どうする?
「円のお札を、刷って、借金を返せばいい 」のだ。

- ■MMTの解説は、様々あり
- ◆MMT理論 の解説 とは?
MMTは、確立された理論ではなく、
様々な人が、様々な解説を、している。
その中では、概ね下記の内容である。
「 自国通貨の発行権 を、持つ国家は、
国の財政が、赤字でも、問題ない。
国の借金も、問題ない。
財政破綻する リスクも ない。」
上記を、もっと簡単に、理解するには、、
「国の借金は、国がお札を刷って、返せばよい」
と、とらえれば、よい。
-- 消費者 経済 総研 --
◆「 非・MMT の 日本 」 に、MMTを適用?
・MMTの財源は、「政府が発行する通貨」
・今の日本の財源は、「税金+国の借金」
今の日本は、「MMT」ではない。
今の日本の財源は、
「政府発行通貨」ではなく、「税+借金」だからだ。
「国の借金は、国がお札を刷って、返せばよい」 は、
非・MMT の日本に、MMTを、援用した話である。
-- 消費者 経済 総研 --
◆MMTを、今の日本に、援用すると?
MMTの考えを、今の日本に、あてはめてみる
↓
今の日本のお金の集め方は、「増税」や「借金」だ
↓
なお、借金は増加を、続けている
↓
そのお金で、政府は積極的に、財政支出をする
↓
それにより、需要が拡大し、景気は良くなる
↓
同時に、国民の役に立つ物が、作られ、増える
↓
日本の借金残高は、千兆円超だが、破綻しない。
↓
国の「借金」があっても、さらに増えても、問題ない
↓
お金を、新たに作って、借金を返せば良いからだ
↓
よって、借金を気にせずに、お金を増やして使おう
↓
政府の支出を増やして、景気に貢献すべきである

- ■ MMTを、実行する国 とは?
- MMTを、実施している国は、どこか?
あるいは、それに近いことを、行う国はどこか?
ここまで読んで、気づいた方も、いるだろう。
実は日本は、MMT的な事を、既にやっているのだ。
また日本だけでなく、海外の先進7か国も、同じだ。
-- 消費者 経済 総研 --日本は、「 MMT 」 ではない
先進7か国も、 「 MMT 」 ではない
だが、「 MMT的」な事は、実施済み
◆次回・続編は?
実は日本は、MMT的な事を、既にやっている?
先進7か国も、MMT的な事を、既にやっている?
「既にMMT的な事を実行」とは、具体的には、何か?
これらを、次回の続編で、解説していきたい。

- ■MMT -3|高圧経済7|爆上げVol.11
- 2022年 9月 14日 に 新規投稿
Vol.11 (第2部の高圧経済の 7回目)
MMT-3:なぜ、親子合計なら、借金ゼロか?
「純粋MMT」と、「MMT的 理論」 の違いは?
今回号は、MMTの3回目で、
高圧経済その7|ニッポン爆上げVol.11 に、相当
-- 消費者 経済 総研 --
◆積極財政で、高圧経済へ?
「連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦」
の第2部は、「景気 UP 編」だ。
「 積極財政 」 で、「 高圧経済 」 を実現
このテーマを、現在、継続中。
-- 消費者 経済 総研 --
◆今回号は?
日本は、MMT ではない。
しかし、「 MMT的 な事 」は、日本は、実施済み?
上記を、前回号の文末で、述べた。
「 純粋MMT 」と、「 MMT的 理論 」 の違いは、何か?
日本は、「 MMT的 理論 」を、実施済み なのか?
「 純粋MMT 」と、「 MMT的理論 」を、解説していく

- ■純MMT と MMT的 の違いは?
- 日本は、、まだ「 MMT 」を、やっていない。
だが、「 MMT的 理論 」 を、既にやっている。
では「 純MMT 」と「 MMT 的 理論 」 の違いは何か?
▼両者の 違う点は?(財源)
まずは、「 財源 」に、注目して、解説する。
・純粋MMT は、 「 通貨の 新規発行 」 が、財源
・MMT的 の方は、 「 税+借金 」 が、財源
政府の財源は、
・純MMTは、 「 通貨の 新規発行 」
・MMT的は、 「 税 + 借金 」
▼両者の 違う点は?(通貨の発行者)
続いて、「通貨は、誰が発行?」 を、解説する。
・純MMTは、「 政府が、通貨を発行 」 する
・MMT的 では、「 中銀が、紙幣を供給 」 する
純MMTの方は、中銀の役割は、かなり小さくなる。
※「 中銀 」 とは、中央銀行の略で、
日本なら日銀、米国ならFRB
※「 通貨 」 とは、
狭義では、「 紙幣(お札) + 硬貨(コイン)」
広義では、「 紙幣+ 硬貨+預金 」
通貨の中の「 預金 」を、深入りすると、横道にそれる。
まずは、「 通貨とは、お札のこと 」 と、理解しても良い。
「通貨」、 「マネー」、 「お金」 は、
いずれも 「 お札 (紙幣) 」 と理解しても、まずは、よい。
・純MMT:政府が、自ら通貨を発行
・MMT的:中銀が、紙幣を供給
▼共通点は、「 財政赤字の肯定 」
前項では、「 違い 」 についてだった。
続いて、「 共通点 」 についてだ。
純MMTと、MMT的の共通点は、何か?
共通点は、「 財政赤字 の 肯定 」 だ。
両方とも、「 政府の支出を、増やす 」からだ。
政府の財源のお金を、増やす
↓
その増えたお金で、政府の支出を、増やす
↓
それにより、景気を拡大させる
↓
同時に、国民の役に立つ物を、作り・増やす
↓
政府の支出の増加で、赤字が増えても良い
↓
財政赤字は、肯定される
純MMTと、MMT的の 共通点は、
・財政赤字を肯定
・政府の支出 を 増やす

- ■3つの財源とは?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆3つの財源 とは?
財源を、増やして、政府の支出を、増やす。
その財源を、増やす方法は、何か?
それは、下記の3つの、どれかだ。
[1] 増税 [2] 国の借金 [3] 政府通貨発行
-- 消費者 経済 総研 --
◆3つのうち、どれが良い?
[1] 増税は、
景気を、良くするどころか、悪くする。
下記の2つの、どちらかを、選択するのだ。
[2] 国の借金 or [3] 政府通貨発行
財源は、[1]増税 ではなく、
[2]国の借金 or [3]政府通貨発行
-- 消費者 経済 総研 --
◆[1] 「 増税 」 は、良くない?
[1] 増税は、財源として、どうか?
「 増税 」 では、民間からお金を、国が吸い上げる。
よって、民間部門のお金が、減ってしまう。
お金が減れば、民間需要も、減ってしまう。
需要を減らしたら、経済は縮小する。
経済が縮小したら、景気は、良くならない。
増税は、景気へ、プラスではない。
増税は、景気へ、マイナスに働く。
-- 消費者 経済 総研 --増税したら、
民間の お金・需要 を、
減らして しまう
◆[2] 「 国の借金 」 は、どうか?
[1] 増税 では、民間のお金が、減ってしまう。
[2] 国の借金型では、民間のお金は、減らない。
だが国の借金型でも、民間のお金は、最初は減る。
しかし民間へ、お金は、後に戻る。
よって、民間のお金は、減らないのだ。
▼ 「減って、戻る」 とは?
民間のお金が「減って、戻る」とは、どいう事か?
国の借金は、「国債の発行」によるのが、大半だ。
国債を、政府が販売し、民間の銀行等が買う。
この国債の販売額を、仮に、2兆円とする。
民間の銀行等が、購入代金(2兆円)を、支払う。
政府が、販売代金(2兆円)を、受け取る。
この時点 (前半) では、
国債の購入代金(2兆円)が、民間から減る。
前半は、民間から、2兆円が減る
その後(後半)、民間の銀行等は、日銀へ国債を売る。
日銀が、購入代金(2兆円)を、支払う。
民間の銀行等が、販売代金(2兆円)を、受け取る。
この時点 (後半) では、2兆円が、民間へ戻る。
後半は、民間へ、2兆円が戻る
国債の売買代金は、
前半:民間から→政府へ。 後半:日銀から→民間へ
前半: 民間から、2兆円が 減る
↓
後半: 民間へ、2兆円が 戻る
こうして、民間のお金は、「 減って、戻る 」のだ。
つまり、「 借金 」型では、民間のお金は、減らない。
民間の需要は、減らずに、維持される。
借金型では、
民間の お金・需要 は、
減らない
※「そもそも国債とは?」も参照
-- 消費者 経済 総研 --
◆[3] 「 政府通貨発行 」 は、どうか?
[3] 政府通貨発行も、民間のお金は、減らない。
政府通貨発行では、単純に、新たに、お金を作る。
お金は、増えるだけで、減るタイミングは無い。
-- 消費者 経済 総研 --[2]国の借金と、[3]政府通貨発行は、
民間の お金と需要 を、減らさない
◆なぜ、増税では、ないのか?
純MMTの財源は、増税ではなく「政府通貨発行」だ。
MMT的の財源は、増税ではなく、「借金の増加」だ。
なぜ、両方ともに、「 増税を、選択しない 」 のか?
理由は、増税すると、景気は悪くなるからだ。
過去の増税で、失われた20年が、始まった。
過去の増税で、私たちの給料の下落が、始まった。
増税で景気悪化は、下記過去号で解説した通りだ。過去の 増税で、
失われた20年 スタート
「増税では、日本は、低迷する?」

- ■MMT的での、国の借金は?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆MMT的では、国の借金はOK?
積極財政では、政府の支出を、増やす。
その「財源」のお金も、増やすことが、必要だった。
MMT的理論の財源は、
増税ではなく、「 国の借金の 増加 」 だ。
MMT的理論では、国の借金の増加は、肯定される。
-- 消費者 経済 総研 --
◆国の借金 今も、今後も OK?
▼国の借金 今は、問題なし
「日本は資産大国なので、国の借金は問題ない」と、
消費者経済総研の、複数の過去号で、解説した。
日本の国の借金は、現時点は、問題ない。
▼国の借金 今後の増加も、問題なし?
・借金は、現在、問題なしで、今後も、問題なしか?
・借金は、現在、問題ないが、今後は、問題ありか?
答えは「 今後の、更なる借金増加も、問題なし 」だ。
今後、さらに増えてもOK の理由 とは?
-- 消費者 経済 総研 --
◆今後、増えてもOK の2つの理由
▼① 国の借金 引受け者は、日銀
政府の借金の 最終の引受け者は 子会社の日銀
▼② 新たに、通貨を、発行
返済必要でも、お札を刷って、返せばよい
上記の①②を根拠とし、「借金増えても、問題なし」
とするのが、MMT的理論である。
借金増加は、今後も、OKの理由
① 政府は、日銀(子)から、借金
② 新たに、通貨を、発行
(お札を刷って、返せばよい)
なお、「純MMT」での財源は、「政府の発行通貨」だ。
借金は、主な財源ではない。
よって、国の借金の問題は、
MMT的で登場するが、純MMTでは、登場しない。
-- 消費者 経済 総研 --
◆① 国の借金 引受者は 子会社の日銀
▼連結会計 とは?
上場企業には、「連結会計」をする義務がある。
連結会計とは、
親会社・子会社等を、合体させ、
「 全体を、1つの会社 」 とみなす会計だ。
親・子に、貸し・借りが、ある場合は、どうするか?
つまり、親子間の「 債権・債務の処理 」である。
次のケースで、見ていく。
親会社は、子会社から借金した「債務」がある。
子会社は、親会社へ貸し付けた「債権」がある。
連結会計では、親会社と子会社を、連結させる。
債権・債務は、親と子の、合わせた値で、発表する。
連結会計で、親子間の債権・債務は、相殺される。
連結会計で、
親子間の 「 債権・債務は、相殺 」
▼日銀に、当てはめて、みると?
日銀は、役所ではなく、会社である。
東京証券取引所に、上場している上場企業だ。
だが、日銀は、上場企業ではあるものの、
一般の上場企業とは、異なる点はある。
ここでは日銀を、一般の上場企業と、
同じ視点で、見た場合の解説を、してみる。
財政赤字で、政府の借金が、増加してもよい。
↓
新たな借金増加も、(間接だが) 日銀が、引き受ける
↓
つまり、「 政府が日銀から、借りたお金 」 が、増える
↓
政府は、日銀の株の55%を、保有している(出資証券)
↓
つまり、「日銀は、政府の子会社」だ
↓
政府(親)は、日銀から借金した「債務」がある
↓
日銀(子)は、政府へ貸し付けた「債権」がある
↓
連結会計では、親会社と子会社を、合算させる
↓
連結会計で、親子間の債権・債務は、相殺される
↓
親の債務530兆円と、子の債権530兆円は、相殺だ
↓
親と子の合計では、「借金は無い」になる
・政府(親)の 債務 530兆円
・日銀(子)の 債権 530兆円
上の2つは、相殺で、借金ゼロ
▼「統合政府」 とは?
上記の連結の見方は、新たに登場のものではない。統合政府 =政府 + 日銀
前から「 統合政府 」の見方として、言われてきた。
22/5/9に、安倍元首相は、下記趣旨の解説をした。
「 日銀は、政府の子会社 」
「 返済期限が来たら、
返さないで、借り換えて構わない。 」
安倍氏の解説は、この「統合政府」の視点に基づく。
▼統合政府を、親子の例で、簡単解説
統合政府を、親子の例で、簡単な解説をする。
山田さんが、銀行から、借金した。
その借金を、返さないと、問題である。
山田花子(親)が、山田太郎(子)に、千円を貸した。
この親子の貸し借りは、他人には、無関係だ。
山田親子の貸し借りは、山田家だけの問題だ。
銀行を始め、他人には、何の問題もない。
だが、山田花子が、銀行からの借金を、返さないと?
既述の通り、それは、問題になる。
政府(親)が、日銀(子)に、返さない事で、困る人は?
親子の問題であって、他人で困る人は、いない。
親子の 貸し借りは、
親子以外には、無関係
▼統合政府の視点で、借金増加も、OK
国の借金の引受者は、子会社の日銀
↓
借金は、問題ではないので、増加してもよい
↓
財政赤字でも、積極的に財政支出をする
MMT的理論 では、国の借金を、
子会社・日銀が、引受けるからOK
-- 消費者 経済 総研 --
◆② 返済となっても、お札を刷ればよい
政府は、日銀から返済を、迫られるか?
↓
仮に、返すことに、なったとしたら、どうする?
↓
お札を刷って、返せば良い のである
仮に、返すことに、なっても、
お札を刷って、返せば良い
▼MMT的理論の支柱は、通貨発行
MMT的理論での「 借金増加 OK 」の根拠の一つが、
「 借金は、お札刷って、返せばいい 」 だ。
「 お札を刷る 」とは、
「 政府が、通貨を、発行する 」 ということだ。
「 政府通貨発行が、財源 」は、純MMTの特徴だった。
MMT的理論は、
純MMTの財源理論を、援用して説明されるのだ。
-- 消費者 経済 総研 --MMT的理論で、返済する場合は、
お札刷って、返せばよい

- ■目的を、再確認する
- 「 ①景気UP ②企業売上UP ③賃金UP 」
本連載は、上記3つを、目的としている
「 ③ 私たちの 給料を 増やす 」
本連載は、その③までが、目的だ。
そのための 「 積極財政 による 高圧経済 」 だ。
お金を増やして、政府の支出を、増やすのだ。高圧経済で、私たちの給料も UP
それで 「 景気UP・企業売上UP・賃金UP 」 にする。
この目的の実現のために、MMTの理解が需要だ。
なぜMMTを、考えるかの意義を、再確認だ。
積極財政のために、政府の支出を増やす。
そのために、財源を、増やすのだ。
財源の理解のために、MMTに注目なのだ。
-- 消費者 経済 総研 --財源の理解 のために、MMT
◆国民の便益 のため?
政府の支出では、何をするか?
建設工事や、社会福祉、防衛など様々だ。
つまり、国民の役に立つ、物事への支出だ。
その政府の支出の予算が、増えれば、どうか?
災害予防の工事や、教育予算を増やしたり、
幼稚園・保育園の充実、福祉の充実や、
AIなどへの未来投資・・など、様々できる。
「 保育園落ちた 日本 ■ね!」 の話が以前あった。
政府支出が、増えれば、待機児童問題も、解消へ。
政府の支出が、増えれば、
国民の役に立つ便益が、増えるのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆景気拡大 のため?
また同時に、「 景気拡大 」の意味もある。
政府の支出(発注)で、民間企業が、受注する。
それで、民間企業の売上は、増加する。
民間企業部門の「売上増加」で、景気拡大する。
売上増えれば「 私達の賃金UPの原資 」も、増える。
企業にも、そして、働き手(消費者)にも、プラスだ。
国民の便益のため、景気拡大のための政府支出だ。
これは、海外の先進諸国でも、同じである。
政府の支出は、国民の便益のため
政府の支出は、景気拡大のため
※政府の支出の増加で、
景気・売上・賃金が、UPする 仕組みは、下記参照
「過去号・その1|なぜ「高圧経済」なのか?」
次回号は、「MMT的理論」の
日本、米国、先進国での、導入状況を、解説予定。

- ■MMT -4|高圧経済8|爆上げVol.12
- 2022年 9月 18日 (日) に 新規投稿
Vol.12 (第2部の高圧経済の 8回目)
MMT-4:日本低迷の理由は、少ない借金?
今回号は、MMTの続編で、
高圧経済その8|ニッポン爆上げVol.12 に、相当
-- 消費者 経済 総研 --
◆積極財政で、高圧経済へ?
「 連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦 」
の第2部は、「景気 UP 編」だ。
「 積極財政 」 で、「 高圧経済 」 を実現
このテーマを、現在、継続中。
-- 消費者 経済 総研 --
◆前回号と、今回号は?
▼前回号は?
前回号で、純MMTと、MMT的の「違い」を解説した。
「 財源 」 は、下記の様に、違いがあった
・ 純MMT:政府が、自ら通貨を発行
・ MMT的:中銀が、紙幣を供給
一方で、2つの 「共通点」は、
「財政赤字を、肯定」と「政府支出を、増やす」だった
▼今回号は?
日本も、米国も、先進7か国も、MMT ではない。
しかし、「 MMT的 な事 」は、実施済み?
今回号は、日本・米国・先進国の
「 MMT的 理論 」 の導入の現状を、解説していく

- ■日本では、どうか?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆日本は、 「政府の支出」を、増やした?
日本は、「政府の支出」を、増やしてきた。
下図は、2005年支出を100%とした場合の推移だ。
↓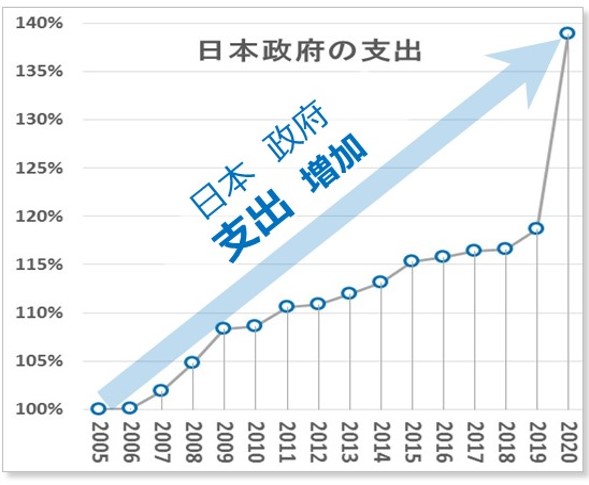 なお2020年に、大幅増加したのは、
なお2020年に、大幅増加したのは、※JPN. G.G. Expense
※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成
※出典 :IMF| Statement of Operations -IMF Data
コロナ対策の支出が、増えたからだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本は、 「国の借金」も、増やした?
前項の通り日本は、「政府の支出」を、増やした。
それにより、日本の「国の借金」は、どうなった?
日本は、「 国の借金 」 を、増やしてきた。
下図は、2005年借金を100%とした場合の推移だ。
↓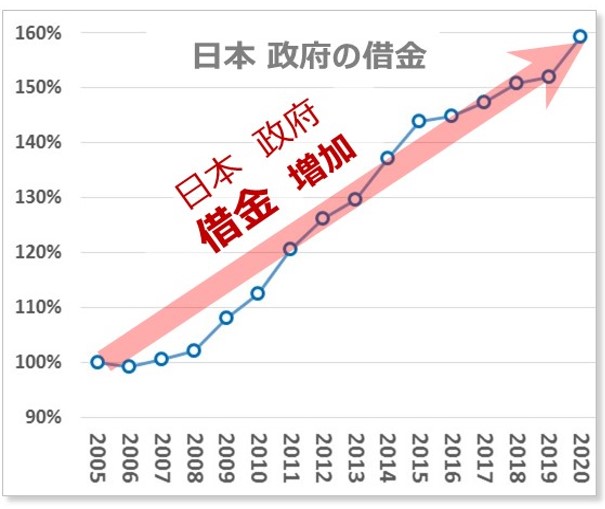 政府支出を増やし、財政赤字で、借金も増えた。
政府支出を増やし、財政赤字で、借金も増えた。※JPN. G.G. Liabilities
※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成
※出典 :IMF| Balance Sheet -IMF Data
よって、日本は、「 MMT的 」なのだ。
日本は、「 MMT 」 ではない
だが、「 MMT的」な事は、実施済み

- ■米国では、どうか?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆米国は 「政府の支出」を、増やした?
米国は、「政府の支出」を、増やしてきた。
下図の通り、「 大幅に 増やした 」 のである。
↓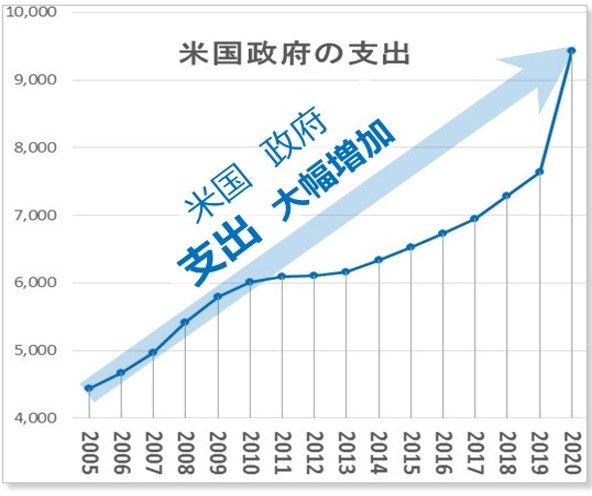 -- 消費者 経済 総研 --
-- 消費者 経済 総研 --※金額は、 単位$、Scale: Billions
※※対象は、U.S. G.G. Expense
※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成
※出典 :IMF| Statement of Operations -IMF Data
◆政府の支出の 財源は?
政府支出を増やすには、財源も増やす必要がある。
では、財源は、何か? 下記の3つのどれかだ。
① 「 増税 」
② 「 国の借金増加 」
(増税無しでは、借金は増加する)
③ 「 政府が通貨発行 」
(政府が、自らお札を、印刷する)
米国は、上記 ① ② ③ の、どれか?
-- 消費者 経済 総研 --
◆米国は 「国の借金」も、増やした?
前項の通り米国は、「政府の支出」を、増やした。
それにより、米国の「国の借金」は、どうなったか?
米国は、「 国の借金 」 を、増やしてきた。
下図の通り、「 大幅に 増やした 」 のである。
↓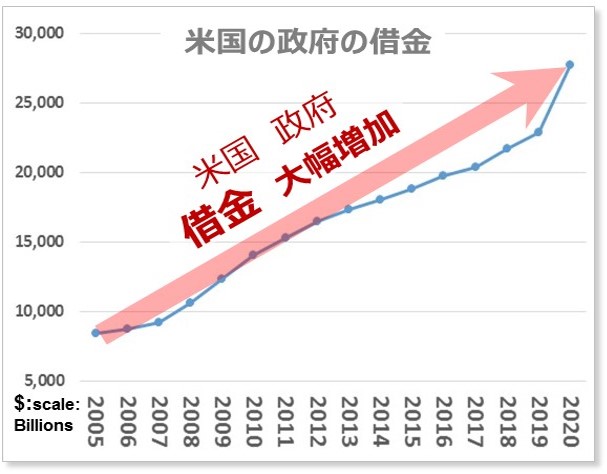
※金額は、 単位$、Scale: Billions
※対象は、U.S. G.G.Liabilities (IPSGS(年金等) を除く)
※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成
※出典 :IMF| Balance Sheet -IMF Data
あなたの わからない を
わかるに 変える
- 消費者 経済 総研 -

- ■日米比較は?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆日本と、米国を、比較すると?
前項の米国のグラフは、ドルベースの金額推移だ。
続いてここでは、「日米の比較」を、してみる。
2005年の額を、100とした場合の推移の比較だ。
▼政府の支出の日米比較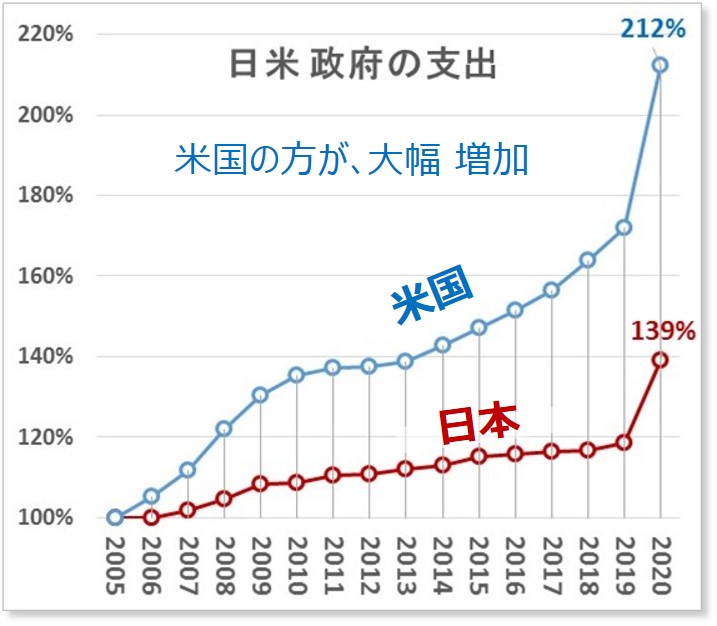
▼政府の借金の日米比較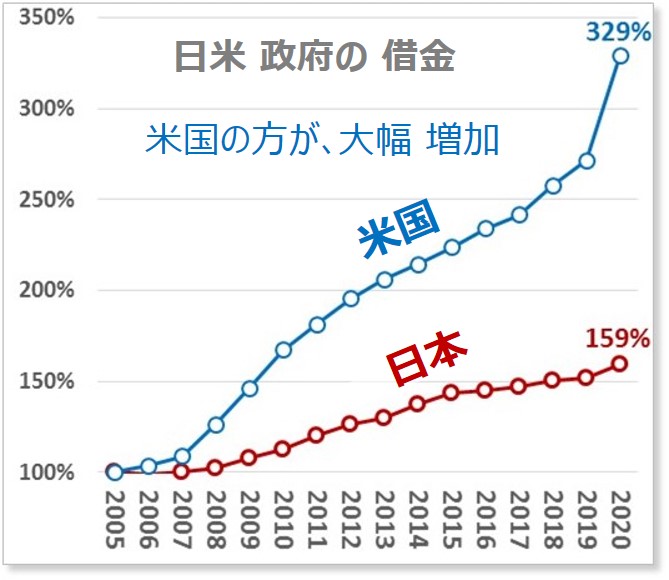
政府の 「 支出 」 も 「 借金 」 も、
日本より、米国の方が
はるかに、増やしている

- ■海外と日本の MMT的理論
-- 消費者 経済 総研 --あなたの わからない を
わかるに 変える
- 消費者 経済 総研 -
◆海外は、赤字で、借金増加?
財政赤字は、日本、米国だけではない。
2020年のG7(先進7国)では、7か国は、全て赤字だ。
コロナ前の2019年でも、大半が赤字国だ。
財政赤字は、何も特別なことではない。
赤字なら、その赤字分は、「国の借金」で、調達する。
つまり先進諸国は、国の借金を、増加させている。
先進7か国は、
・政府支出を、増やした
↓
・財政は、赤字
↓
・国の借金も、増加した
外国は、借金増加で、政府支出の財源を、増やした。
それで、「 需要 > 供給 」 にして、景気UPさせた。
また同時に、政府支出の増加によって、
国民に役に立つ便益を、増やした。
政府の支出の増加も、国の借金の増加も、
景気拡大のため、国民の便益のためだ。
国民のための、政府の借金増加
-- 消費者 経済 総研 --借金の増加は、国民のため
「 景気拡大+国民の便益 」 のため
◆先進国は、MMT的なのか?
政府の「支出」を増やし、「借金」も、増やしたので、
先進7国は、MMT的理論を、実践中なのだ。
先進7国は 「 純MMT 」 ではない
だが、「 MMT的」な事は、実施済み
-- 消費者 経済 総研 --
◆先進7国の 借金は?
G7(先進7ヵ国)の 借金は、どう増えたか?
↓
2005年を100とした場合の、2020年の増加率だ
↓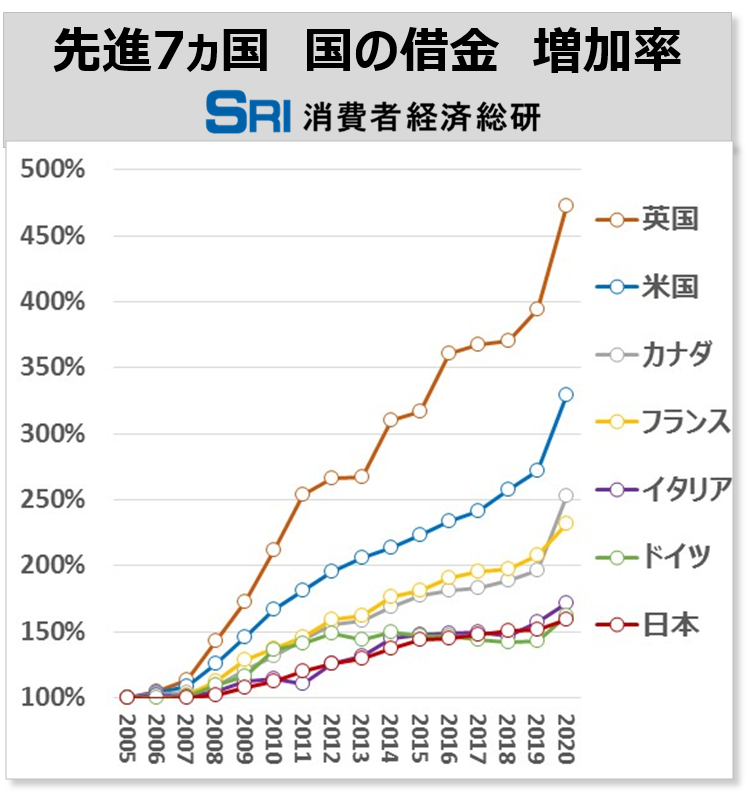 ↓
↓
英 国 473%
米 国 329%
カナダ 253%
フランス 232%
イタリア 172%
ドイツ 162%
日 本 159%
↓
日本が、最も借金の増加が、少ない
-- 消費者 経済 総研 --
※上のグラフの対象は、Liabilities
(IPSGS(年金等)ある場合は、それを除く)
※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成
※出典 :IMF | Balance Sheet-IMF Data
◆日本の 借金の増加 は、少なすぎる?
「 国の借金の増加 」 は、先進諸国では共通だ。
日本では、「 国の借金は ダメ 」と、言う人がいる。
国の借金は、問題ないのだ。
それどころこか、日本の借金増加は、少なすぎる
-- 消費者 経済 総研 --日本の 借金の増加 は、
少なすぎる
◆日本の政府の支出は、少なすぎ?
日本の 「 借金の増加が、少ない 」 のは、なぜか?
日本の 「 政府支出が、少ない 」 からだ。
下図がその証拠だ。
↓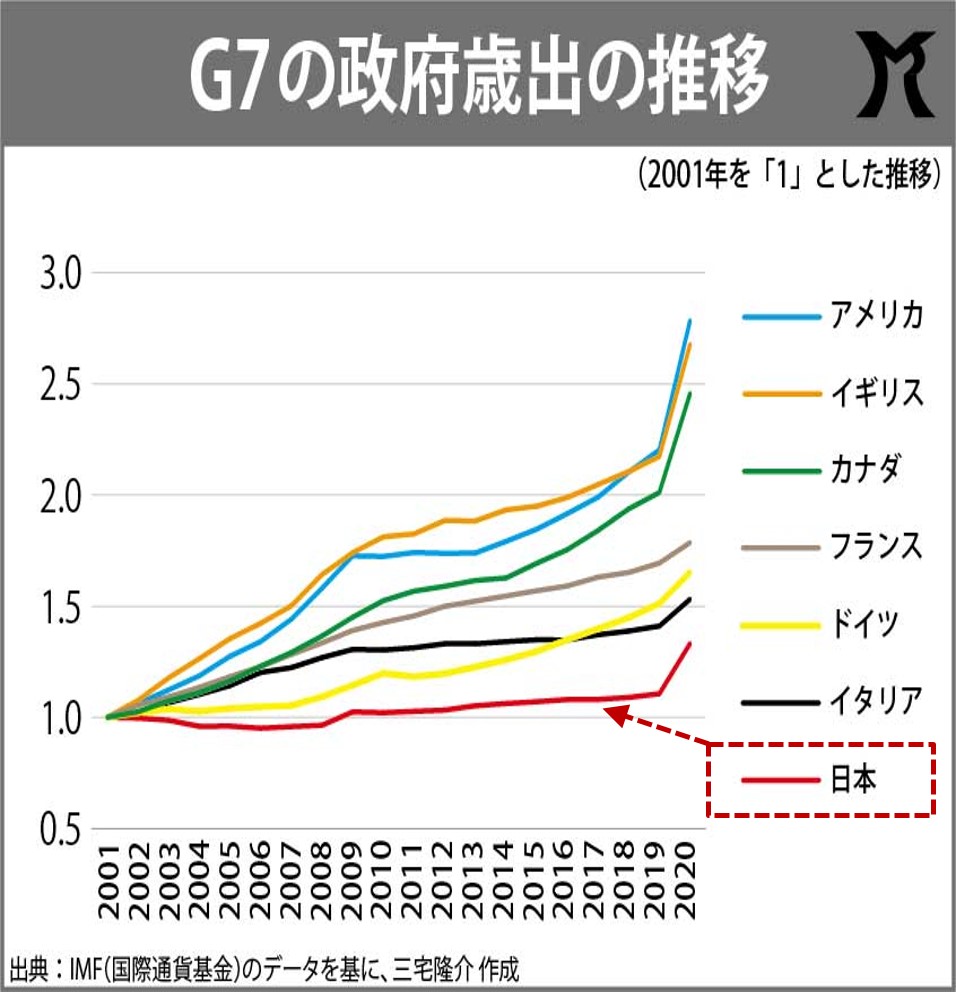
※グラフ出典:川崎市議会議員 三宅隆介氏
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本は、消極財政?
上のグラフからは、何が、わかるか?
↓
日本は、政府支出の増額幅が、小さすぎる
政府の支出の増加は、
日本は、少なすぎる
日本は、「積極財政」ではなく、「消極財政」なのだ
↓
これでは、日本のGDPは、低迷してしまう
↓
しかも、国民に役立つ便益も、増えない
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本だけが低迷 その原因は?
国の借金が増えたのは、日本だけではない。
先進諸国は、軒並み、借金を、増やしてきた。
その中でも、日本の借金の増加率は、低いのだ。
外国は、借金を増やして、政府予算を増やした。
借金増は、景気UPと、国民の便益UPのためだ。
日本低迷の理由の1つは、借金増が少ないからだ。
日本経済が弱いから、借金を増やした のではない。
借金増加が少ないから、日本経済が低迷したのだ。
世間の常識とは違うが、これが真実である。
この真実に、与党も野党も、気づき始めた。
日本が低迷から、脱出するために、
このページ内容は、広がって欲しい。
ぜひ、このページへリンク設定、をお願いしたい。
日本は、外国よりも、
・借金増加が、少なすぎる
・政府の支出が、少なすぎる
借金と支出が、少なすぎるのが、
日本低迷の 原因の1つだ

- ■日本政府と自民党の 見解は?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆日本は、肯定しないが、実行中?
MMT的なら、財政赤字は、積極的に肯定される。
だが、日本政府は、「赤字の肯定」は、していない。
財政赤字を、肯定しないが、実行中の状態なのだ。
さらに、自民党と政府には、
財政スタンスの変化が、みられる。
自民党も政府も「赤字の肯定」の側に、近づいた。
つまり、MMT側に、近づいたのだ。
では、「 日本が、どう変化したか 」で、
「政府の変化」、続いて「自民党の変化」を見ていく。
-- 消費者 経済 総研 --
◆「 日本政府 」 は、どうか?
日本も、「 MMT的理論の 実行国 」だ。
では、赤字・借金・MMTへの、政府の見解はどうか?
下記は、元財務大臣の麻生氏の発言だ。
「 国の借金? お金を刷って返せばいい。簡単だろ?」
麻生氏は、上記 の発言とは別に、次も発言した。
「 日本を、MMTの実験場に、する気はない 」
では、政府の公式見解は、どうか?
-- 消費者 経済 総研 --
◆政府の公式見解は?
政府は、純MMTも、MMT的理論も、肯定してない。
政府の公式見解は、
「 財政健全化への旗を、降ろさない 」である。
日本政府は、財政の黒字化の道を、捨てていない。
日本政府は、
「 黒字化 」 の姿勢を維持
-- 消費者 経済 総研 --
◆政府の公式見解の 推移(財政の黒字・赤字)
黒字化を目指すと言う政府にも、変化がある。
政府は、どう変化したか?
徐々に、MMT側へ、近づいたのか?
▼2017年 12月8日|閣議決定
「2020年度での黒字化目標の達成は困難。
ただし、財政健全化の旗は、決して降ろさず、
黒字化を、目指すという目標自体は、堅持する。」
▼2018年 6月15 日|閣議決定
「財政健全化に着実に取り組み、
" 2025 年度の 黒字化 " を、目指す。」
▼ 2022年 6月7 日|閣議決定
「財政健全化の「旗」を下ろさず、
これまでの財政健全化目標に取り組む。」
しかし、骨太方針2018で掲げた
" 2025年度の黒字化 " は、削除された。
つまり、財政の健全化(黒字化)は、維持するが、
「 黒字化は、いつか 」 の時期目標は、捨てたのだ。
つまり黒字化は、トーンダウンしたのだ
「 黒字化 」 の目標年度は、
削除された
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本政府も、若干、MMT側へ
22年の骨太方針で、黒字化の目標年度が、消えた。
「黒字化が、トーンダウン」したので、
政府も、若干だが、MMT側に、寄ってきたのだ。
「 積極 財政 派 」 の勢いが、増加したからだ。
非MMT側から → MMT側へ、 若干だが接近中だ。
日本政府も、MMT側へ、若干接近
-- 消費者 経済 総研 --
◆「 政府 」 ではなく 「 自民党 」 は?
前項は、「 日本 政府 」 についてだった。
では、「 政府 」 ではなく 「 自民党 」 は、どうか?
「自民党で、借金肯定派が、急増」 と以前、解説した。
自民党は、どう変化したのか?
政府より、自民党の方が、積極的にMMT側に接近。
自民党の議連は、「 下記は、全て誤り 」 と表明した。
・日本の財政は 破綻寸前
・国民一人 900万円の 借金
・国債は、必ず返済が、必要
上記を、「 全て誤り 」 としたのだ。
これは、「過去号 その3」で、解説した。
詳細は、「 自民党も野党も、借金肯定へ 」 を参照
自民党も、MMT側へ、近づいた
-- 消費者 経済 総研 --
◆野党は、どうか?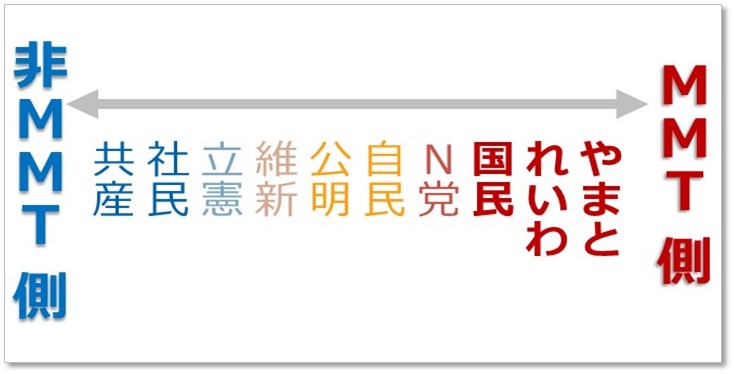
「 新党やまと 」 は、「 新党やまと 」 は、
MMTを 明記
政策公約に、「 MMT」 を、明記し標榜した。
「 MMTで 豊かな日本を! 」 が、
新党やまとのメイン・フレーズだ。
それは、下記公報の1ページ目の左上にある。
※出典:衆議院 ( 比例代表選出 ) 議員選挙広報
れいわ新選組と、国民民主党は、かなりMMT側だ。れいわと、国民民主は、
かなり MMT的
MMTの用語を使わないが、MMT経済学を、
「れいわ」と、「国民民主」は、良く理解している。
また、立憲民主党、維新の会にも、変化がみられる。
「自民党・野党も、MMT側へ変化」の詳細は下記参照野党も、MMT側へ、近づいた
過去号・高圧経済3|自民党も野党も、借金肯定へ
-- 消費者 経済 総研 --
◆MMT側が、増えたのは、いつ?
日本の国会は与党も野党も、急にMMT側に寄った。
MMT側が、増えたのは、いつからか?
令和元年 (2019年) からである。
令和元年に、ケルトン氏が、来日した。
ケルトン氏は、国会内で、MMTの講演をした。
ケルトン氏は、アメリカの経済学者で教授である。
その頃から、日本でMMT側が、増えてきたのだ。
なお令和元年よりも前から日本で、長年にわたり、
「 MMT的な 理論 」 が、議論されていた。
「お金で困るなら、自ら紙幣を、刷れば良い」
「不景気でなら、お金を国民に、配ればよい」
「ヘリコプターから、お金を、ばら撒けば良い」
このように、 MMT ではなくても、
MMT的な議論は、以前から、あったのだ。
それが、令和元年から、増えたのだ。
-- 消費者 経済 総研 --令和元年から、自民党も野党も、
MMT側へ、近づいた
党内変化で、政府も若干変化
◆どこまで、MMT側へ?
こうして、令和元年から、急にMMT側へ、接近した。
では、どこまで「 MMT側に、接近 」 してよいのか?
MMT側に、政策が寄っていくと、どうなる?
MMTのデメリットは、〇〇か?
次回号は、これらを、解説していきたい。
とことん
わかりやすい 解説
- 消費者 経済 総研 -
-- 消費者 経済 総研 --
■関連ページは?
◆日本は、借金大国では、ない
日本の国の借金は、問題ではない。もともと 日本は、
借金大国では、なかった
現状は、日本は、借金大国ではなく、優等生だ
理由は、借金も多いが、財産も多いからだ。
日本は、資産も多く「資産大国」でもある。
負債だけでなく、資産も見る必要がある。
日本は、純負債・純資産で、G7で上位の優等生だ
これは、過去号で、わかりやすく解説してある。
下記の号を、ご覧頂きたい。
*Vol.1「 純負債編|なぜ 日本借金大国は 嘘? 」
-- 消費者 経済 総研 --
◆借金増えても、日銀が対応する
親会社の債務と、子会社の債権は、連結で相殺
更なる借金の増加も、問題ない
国の借金は、子会社である日銀が、担うからだ
これは、過去号で、わかりやすく解説してある。
下記の号を、ご覧頂きたい。
*Vol.2 「 日銀・政府編|なぜ借金大国ではない? 」
-- 消費者 経済 総研 --
◆自民党・野党の MMT側への 変化は?
「自民党も野党も赤字肯定の開始」は、下記を参照
「 「高圧経済」 政策 その3 」

- ■MMT-5|高圧経済9|爆上げVol.13
- 2022年 9月 25日 (日) に 新規投稿
Vol.13 (第2部の高圧経済の 9回目)
MMT-5:デメリットは、ハイパーインフレ?
-- 消費者 経済 総研 --
◆積極財政で、高圧経済へ?
「 連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦 」
の第2部は、「景気 UP 編」だ。
「 積極財政 」 で、「 高圧経済 」 を実現
このテーマを、現在、継続中。
-- 消費者 経済 総研 --
◆前回号と、今回号は?
▼前回号は?
日本も、米国も、先進7か国も、MMT ではない。
しかし、「 MMT的 な事 」は、実施済み。
日本・米国・先進国の「 MMT的 理論 」 の
導入の現状を、前回号で解説した。
▼今回号は?
今まで、MMTのメリットを、解説してきた。
今回号は、MMTのデメリットを、解説していく。
-- 消費者 経済 総研 --

- ■MMTの デメリット とは?
- 前回号まで、MMTのメリットを、解説してきた。
では、「 MMTの デメリット 」 は、何か?
先に結論を言うと、
MMTのデメリットは、「 インフレ圧力 」 だ。
MMTでは、物価上昇の力が、働くのだ。
MMTの デメリットは、
「 インフレ圧力 」
-- 消費者 経済 総研 --
◆MMTのメリットは?(再確認)
財政赤字になっても、政府の支出を、増やす。
政府の支出の増加で、下記①と②が、実現できる。
① 景気の拡大
② 国民に役立つ便益の増加
純MMTでも、MMT的でも、上記がメリットだった。
-- 消費者 経済 総研 --
◆財源は?
政府支出の増加の際の「 財源 」は、下記だった
純MMTでは、政府の通貨発行
MMT的では、国の借金の増加
-- 消費者 経済 総研 --
◆民間の需要は、不足?
景気拡大の手段は、様々な方法が、ある。
様々ある中で、「 政府支出の増大 」の役割は、何か?
それは、「 需要強化 」 だ。
日本経済は、「 供給 > 需要 」 である。
需給ギャップ(GDPギャップ)は、現在、マイナスだ。
そのマイナスの需給ギャップを、政府が埋める。
需要 = 民間部門の需要 + 政府部門の需要だ。
日本経済は、民間部門が、弱い。
つまり「民間部門の需要が、少ない」ということだ。
日本は、民間の需要が、少ない
-- 消費者 経済 総研 --
◆民間の不足を、政府が、埋める?
民間の需要不足分を、政府部門がうめる。
そのための 「 政府支出の増加 」 なのだ。
それによって、「 供給 < 需要 」 にするのだ。
民間の需要不足を、政府がうめる
そのために、政府支出を、増やす
それで 「 供給 < 需要 」 に
-- 消費者 経済 総研 --
◆価格は、「需・給」で、決まる?
そもそも 「 価格 」 は、何で決まるのか?
「需要」 と 「供給」 のバランスで、価格が、決まる。
需要が弱い、つまり「供給>需要」だと、価格下落。
需要が強い、つまり「供給<需要」だと、価格上昇。
政府支出の増加で、政府部門の需要が、高まる。
総需要(民間需要+政府需要)が、強くなる。
総需要の大きさで、価格水準が決まる。
総需要の増加で、物価は上昇するのだ。
政府支出の増加で、需要が増えれば、
「インフレ圧力」が、かかる。
この「 インフレ圧力 」 が、「 MMTの 副反応 」 だ。
▼副反応が過剰なら、デメリットへ
「政府の支出の増加→需要増加」が、過剰になれば、
「望まぬインフレ」に、なる可能性がある。
-- 消費者 経済 総研 --政府支出 増加
↓
需要 増加
↓
インフレ圧力

- ■インフレは好都合?
- 純MMTや、MMT的な理論を、実行すると、
インフレになる可能性がある。
MMTのデメリットは、インフレ圧力だ。
しかし日本は、長年デフレに、悩まされてきた。
日本のデフレ脱却は、未完である。
よってインフレ圧力は、「 逆に好都合 」 なのだ。
▼2022年の値上げラッシュは?
2022年は、値上げが続くが、それは一時的だ。
悪天候、コロナ、戦争という一時的な原因による。
「 一時的 」ではなく、「 安定的・継続的 」な2%上昇
まで、政府支出を、増やすのだ。
-- 消費者 経済 総研 --日本は、デフレ脱却 未完
インフレは、逆に好都合

- ■ なぜ、デフレは、だめなのか?
- 日本は、デフレ脱却が、未完の状態にある。
そもそも、なぜインフレ(脱デフレ)を、目指すのか?
-- 消費者 経済 総研 --
◆デフレス・パイラル とは?
デフレ・スパイラルは、下落が、更なる下落を呼ぶ。
そのデフレ・スパイラルを、解説する。
※スパイラルとは、「 らせん 」 のこと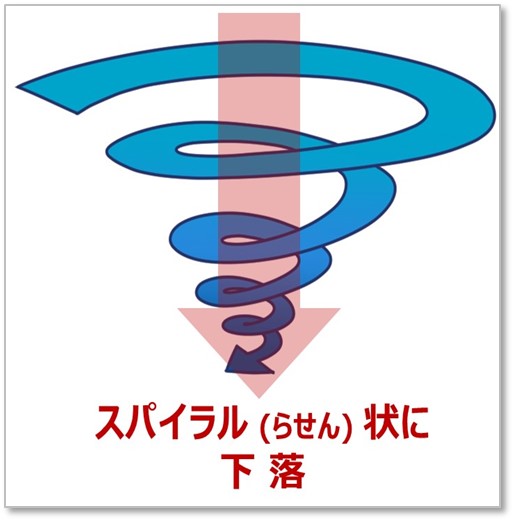
企業の売上が、下がると?
↓
企業の利益が減り、社員の給料も下がる
↓
給料が下がれば、消費支出も減る
↓
消費が減れば、企業の売上も、再度、減る
↓
売上が減った企業は、「取引先」への発注額が、減る
↓
その取引先の企業は、どうなる?
↓
取引先の売上も減り、取引先社員の給料も下がる
↓
こうしてマイナスが、さらなるマイナスを、呼ぶ
↓
これが 「 デフレ・スパイラル 」 である
-- 消費者 経済 総研 --
◆デフレ脱却と、インフレ・スパイラル
デフレ脱却と、インフレ・スパイラルを、解説する。
「物価上昇の目標」を設定し、達成すると?
↓
モノの値段が、上がる
↓
企業の売上額が、上がる
↓
社員の給料も、上がる
↓
中でも国民に、直接に影響するのは「給料UP」だ。
↓
適度なインフレで、プラスがプラスを呼ぶ
インフレは、プラスがプラスを呼ぶ
適度なインフレが良い

- ■適度な「良いインフレ」 とは?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆適度な「インフレ率」 とは?
「適度なインフレ率」は、2%だ。
先進国の安定的な物価目標は、2%である。
英国、カナダ、ニュージーランドなどは、
インフレ・ターゲットを、2%としている。
米国も、長期的な物価安定のゴールは2%だ。
日本も、2%目標としていて、同じだ。
つまり2%は、適度なインフレの「 世界標準 」だ。
適度なインフレ率は、2%
2%は、世界標準
-- 消費者 経済 総研 --
◆なぜ、2% なのか?
日本の目標が、2%なのは、
世界標準に、あわせるためだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆物価(モノの価値)と、通貨の価値
物価(モノの価値)と、通貨価値(カネの価値)
この2つは、天秤のシーソーの関係にある。
片方が上がれば、反対側は下がる。
物価が上がれば、通貨価値は下がる。
通貨価値が上がれば、物価は下がる。
▼ミカンの例で、簡単解説をする。
ミカン1個が、100円だった
↓
インフレで、110円に、値上がりした
↓
これは、「 物価の 10%上昇 」 だ
↓
逆の見方では、どうか?
↓
ミカンという「モノ」ではなく、「お金」に注目では?
↓
値上げ後は、100円玉で、ミカンは、何個買えるか?
↓
100円玉では、「 0.91個 」 しか買えない
※110円なら、1個 → 100円なら、0.91個
0.91個 × ( 110円 ÷ 100円 ) = 1個
100円玉の価値が、「1 → 0.91 」へ、下落したのだ
↓
つまり、「通貨の価値」が、「1→0.91」へ下落
↓
物価の上昇で、「通貨の価値」が下がった
-- 消費者 経済 総研 --物価↑ ならば 通貨価値↓
物価↓ ならば 通貨価値↑
◆2%より低いと、どうなる?
次の仮定では、どうなるか?
「米国は、2%物価上昇で、日本は、1%物価上昇」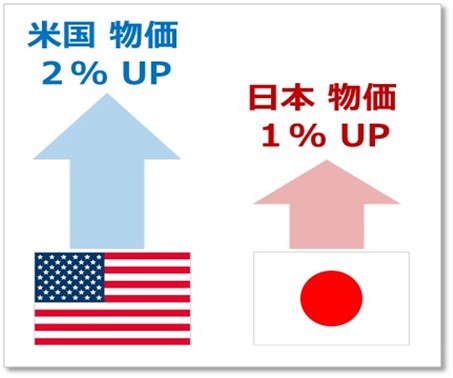
物価水準は、米国が、日本より、1%分高い。
ならば、「通貨水準」の方は、はどうか?
米国通貨(ドル)より、日本の通貨(円)は、1%分高い
これは「 円高 」 ということだ。
円高だと、日本企業の輸出に、ダメージを与える。
よって、海外の水準に追従する必要があるのだ。
-- 消費者 経済 総研 --世界標準2%より、低いと、
輸出にダメージ
◆円安は、損ではなく、得 の理由は?
最近は、「 円安は悪だ 」 との論調が、増えた。
しかし日本の経済全体には、「円安は得」である。
日銀はそれを、当然に、わかっている。
政府も、円安が有利だと、わかっている。
日銀も政府も、計量モデル式で、それを確認済み。
- 日銀・政府の 円安 「 計量モデル 」は、下記参照
②は、内閣府HPの直リンクで、14p目を参照 - ◆①日銀|Var計量モデル|悪い円安は嘘?
◆② 内閣府|日本経済 マクロ計量 モデル(14P)
9月22日の為替介入は、「円安の是正」ではない。
投機筋による、急激な円売りの排除が、目的だ。
▼かつては、円高で騒動に
かつては「円高」で、悩まされた時代が、あった。
その時、「円高は悪」との円高騒動が、激しかった。
当時の「円高騒動」は、今の「円安騒動」とは、
比較になら無いほどの「騒動」だった。
▼貿易収支と、損・得 のまとめ
貿易収支が、黒字なら、円安が得だ。
貿易収支が、赤字なら、円安が損だ。
最近は、貿易赤字だから、円安は損だ。
この「まとめ」では、「 円安は損 」だ。
では、 「 なぜ 円安は 得」 なのか?
貿易収支では損だが、経常収支で得だからだ。
経常収支は後述するが、まずは貿易収支から見る。
-- 消費者 経済 総研 --
◆貿易赤字なら、円安が損の計算は?
貿易収支が赤字(収入<支出)の簡単式を解説する。
※金額は、仮の数字で実際とは違う (切りのいい値)
▼収入 1兆 > 支出 1.1兆 で、赤字の計算
収入1兆ドル-支出1.1兆ドル=0.1兆ドルの赤字
① 1ドル 100円の場合は、
収入: 1兆 ドル = 100兆円
支出: 1.1兆ドル = 110兆円
② 1ドル 140円 の場合は、
収入: 1兆 ドル = 140兆円
支出: 1.1兆ドル = 154兆円※
※154兆円=1.1兆ドル×140円
① 円高 (1ドル 100円 ) の場合は、
収入100兆円 - 支出110兆円 = 10兆円の赤字
② 円安 (1ドル 140円 ) の場合は、
収入140兆円 - 支出154兆円※ =14兆円赤字
① 円高では、10兆円の赤字 → お得
② 円安では、14兆円の赤字 → 損
②円安 の方が、日本は 損 をする。
-- 消費者 経済 総研 --赤字なら、円安は 損
◆貿易(部分的)ではなく、経常(全体)では?
しかし、[1]モノの貿易 以外に、
[2]サービス収支 や、[3]所得収支 がある。
これら全部を合計したのが、「経常収支」だ。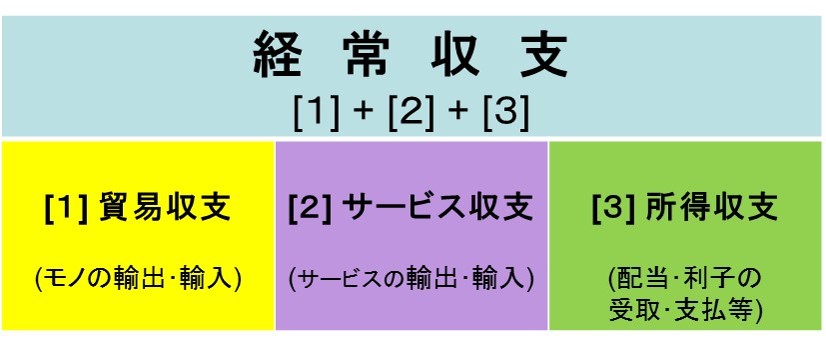
部分的な「 貿易収支 」ではなく、
全体を示す「 経常収支 」で、見ないとダメだ。
「 経常収支 」 は、2022年も、黒字である。× 部分的な 「 貿易収支 」 ×
〇 全体的な 「 経常収支 」 〇
つまり 経常収支は、「 収入 > 支出 」 だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆経常黒字なら、円安がお得 の計算は?
経常収支が黒字(収入>支出)の簡単式を解説する。
※金額は、仮の数字で実際とは違う (切りのいい値)
▼収入 1.1兆 > 支出 1兆 で、黒字の計算
収入1.1兆ドル-支出1兆ドル=0.1兆ドルの黒字
①円高 (1ドル 100円) の場合は、
収入110兆円 - 支出100兆円 = 10兆円の黒字
②円安 (1ドル 140円) の場合は、
収入154兆円 - 支出140兆円※=14兆円黒字
①円高では、10兆円の黒字
②円安では、14兆円の黒字
②円安の方が、日本は得をする。
※所得収支では、「海外現地で、再投資に回るから、
円安効果は、無い 」 と、言う人がいる。
だが、経常収支から、「再投資分」を、引いても黒字だ。
よって、「 経常収支で、円安は得 」なのは,変わらない。
-- 消費者 経済 総研 --日本は、経常黒字
よって、円安が得で、円高は損
◆実際に、円安で、得したのか?
円安効果もあって、2021年4~2022年3月の期は、
トヨタ自動車は、「 過去 最高利益 」を、出した。
2021年4月~2022年3月の期は、
上場企業の 約3割 もが、最高益を出した。
最高益が3割にも至ったのは、30年ぶりだ。※1
理由は、主に「 円安効果 」だ。
その後も、2022年4~6月期・法人企業統計では、
「 全産業の 経常利益の額は、過去最高 」 だ。
(金融・保険除く)※2
※1出典:日本経済新聞 電子版|2022年5月14日
※2出典:日本経済新聞 電子版|2022年9月1日
-- 消費者 経済 総研 --
◆悪いのは、円安ではなく、〇〇だった?
円安で、企業は、過去最高に、儲かっている。
一方、円安で、輸入物価が上がった。
消費者には、値上げラッシュが、きつい。
それでも、結論は、「円安は、悪くない」のだ
問題の源は、円安ではない。
十分な賃上げをしない企業方針が、問題だ。
充分な賃上げにならない政策方針が、問題だ。
「賃上げ税制」の更なる強化が、必要である。
それで、企業の内部留保を、賃金に回すのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆日銀の 2%目標の 論拠は?
物価目標2%の日銀の根拠は、「 世界標準論 」だ。
なお「世界標準論」以外に、下記2件でも、説明する。
「 CPI 上方バイアス論 」
「 金利引き下げ のりしろ論 」
バイアス論の解説は、複雑になり、
のりしろ論は、感覚論的で説得力に欠く。
よって「世界標準論」で理解するので、良いと思う。
※出典:日本銀行 講演|なぜ「2%」の物価上昇を目指すのか
-- 消費者 経済 総研 --
◆失業率と、インフレ率の関係では?
失業率とインフレ率は、経済政策の最重要対象だ。
失業率もインフレ率も、低い方が良い。
景気が良いと、失業率は、下がる。
景気が良いと、インフレ率は、上がる。
よって、失業率とインフレ率は、逆相関の関係だ。
失業率とインフレ率のバランスが、いいのは?
それは、インフレ率が2%程度の時とされる。
失業率とインフレ率のバランスからも、
CPIは2%が、適度なインフレ水準なのだ。

- 日銀・政府の 円安 「 計量モデル 」は、下記参照
- ■日本のインフレ率は、何%?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆日本のインフレ率は、どの程度か?
インフレ率 (物価上昇率) の指標は、
CPI ( 消費者 物価 指数 ) だ。
2022年の日本は、値上げが続いた。
日本のCPIは、2%を、超えた。
しかし、それは一時的なインフレだ。
悪天候、コロナ、戦争という一時的な原因による。
「一時的」 であって、 「 安定的・継続的 」 ではない。
▼20年間のCPIは?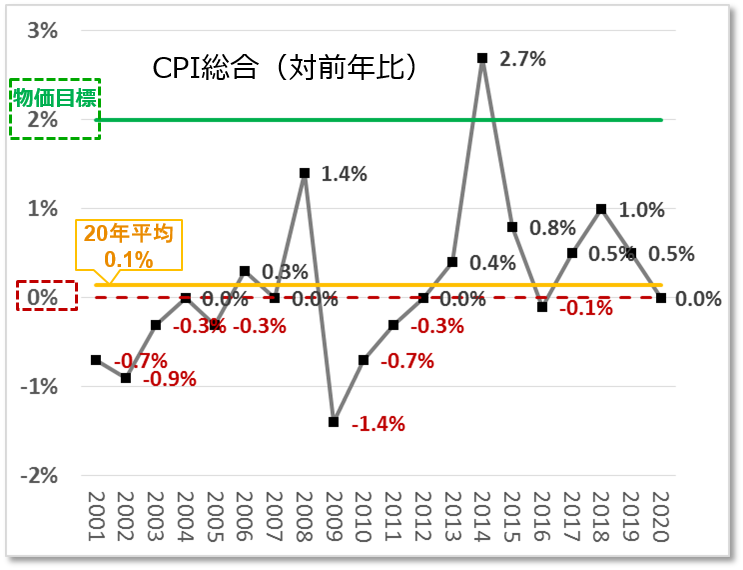
2001~2020年の20年間の
日本のCPIの平均は、0.1%しかない。
2001~2020年のCPIは、マイナスの年が多い。
物価目標2%に、達したのは、2014年だけだ。
しかも2014年は、消費増税の強制値上げによる。
消費税の影響を除くと、20年平均はマイナスだ。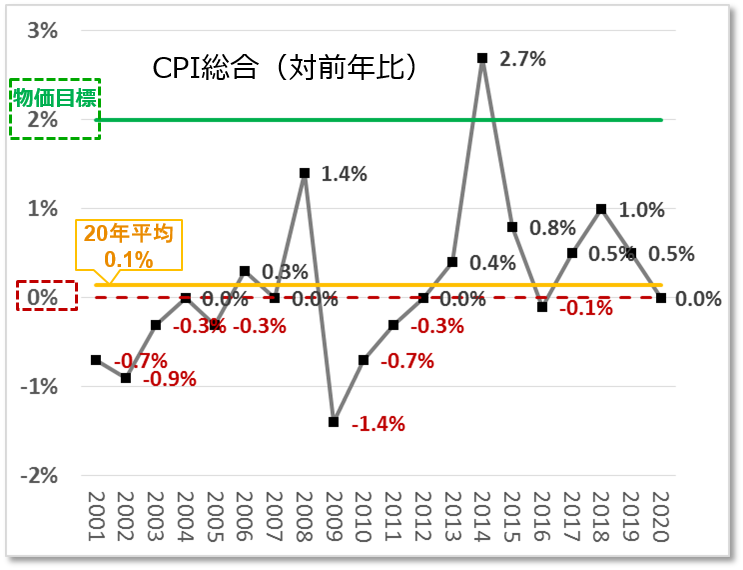 ※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成
※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成
※出典:総務省統計局|消費者物価指数
CPIが、安定的・継続的に、2%超になるまでは、
お金と政府の支出を、増やしてOKなのだ。
-- 消費者 経済 総研 --日本の物価は、0.1%UPしかない

- ■いくら増やすと、物価は何%UP?
- ◆物価2%上昇には、どのくらいのお金?
お金が、いくら増えると、物価は、何%上昇か?
お金を、〇兆円増やすと、物価は、◇%上昇?
この点に関して、参議院が実施した試算値がある。
国民全員に、毎月10万円を、配った場合の試算だ。
つまり、毎年144兆円を、国が借金し増やして配る。
毎年のインフレ率の試算値は、どうか?
1年目1.2%、 2年目1.4%、 3・4年目1.8% だ。
現在の借金水準に、144兆円もプラスオンしても、
物価は、2%上昇に届かない。
※出典:
・年間144兆円国債を発行してもインフレにならない
・日テレニュース2021/10/16
-- 消費者 経済 総研 --
◆インフレ率が、2%超に、なったら?
2%になるまで、お金を増やしてOKと述べた。
なお、2%を超えたら、直ちにNGでもない。
2%を超えた後、過剰なインフレに、なったら?
その場合は、「政府支出を減少」すればいいだけだ。
他にも、物価を下げる政策は、色々ある。過剰なインフレに、なったら
政府支出を、減らせばいい だけ
それらのマクロ政策で、冷やせばよいのだ。
「増税」も、物価を下げる政策の一つだ。
税制では、「インフレ後に、税率をUP」ではなく、
最初から「 効果的な 累進課税 」に、しておく。
そうすれば、自動的にブレーキが、効いてくる
効果的な累進課税ならば、
不況の時は、低い税率が効き、景気を冷やさない。
一方で、好況の時は、高い税率が効き、
「景気の過熱を冷やす」という働きが効く。
これを「ビルト・イン・スタビライザー」と言う。
あらかじめ、組み込まれた 「 安定化の機能 」だ。
また、日銀による
「利上げ」や「量的・質的な金融引き締め」もある。
インフレが過熱しても、様々な方法で制御でき、
心配しなくても、大丈夫なのだ。
インフレ過熱しても、
様々な制御で、問題なし

- ■MMT-6| 高圧経済10| 爆上げVol.14
- 2022年 10月 1日 (土) に 新規投稿
Vol.14 (第2部の高圧経済の10回目)
MMT-6:ハイパーインフレは、いつ・どこで?
-- 消費者 経済 総研 --
◆積極財政で、高圧経済へ?
「 連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦 」
の第2部は、「景気 UP 編」だ。
「 積極財政 」 で、「 高圧経済 」 を実現
このテーマを、現在、継続中。
-- 消費者 経済 総研 --
◆前回号と、今回号は?
▼前回号は?
MMTの副反応は、インフレ圧力。
インフレが、望まぬほど進めば、デメリット。
上記を、前回号で解説した。
▼今回号は?
MMTで、「 ハイパーインフレ 」に、なるか?
ハイパーインフレは、過去、いつどこで、起きたか?
今回号は、これらを、解説していく。
-- 消費者 経済 総研 --

- ■悪性のインフレは、起きたのか?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆MMTで、ハイパー・インフレ?
MMTの副反応は、「インフレ圧力」だった。
インフレが過剰になったら、デメリットになる。
「 ハイパー・インフレになるから、MMTはダメ 」
このように、言う人がいる
そもそも、ハイパー・インフレとは何か?
ハイパーインフレとは、
異常なほどまで、インフレが進行することである。
経済学者のフィリップ・D・ケーガンの定義では、
「 インフレ率が、毎月50%超 」としている。
年間換算では、「1年で、約130倍超の物価上昇」だ。
-- 消費者 経済 総研 --ハイパー・インフレは、
1年で 130倍 超の 物価上昇
◆ハイパーインフレは、いつ起きた?
ハイパーインフレは、大規模な戦争で、発生した。
20世紀までは、大規模な戦争が、しばしば起きた。
巨額のお金が動き、ハイパーインフレが発生した。
▼需要が、増大?
巨額のマネーが、武器を製造する企業等へ行く。
巨額の軍事費が、政府の支出として、使われた。
平時とは比較にならない「 巨大な政府の需要 」だ。
下図は、戦時の日本の国家予算の推移だ。
1938年予算を100とすると、1944年は1109だ。
数年間で11倍に、政府の支出が増えた。 ※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成
※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成
※関野満夫氏|アジア太平洋戦争期日本の戦争財政
なおGDP比は、(一般会計+純軍事費)÷GDPの値
大規模な戦争では、
巨大な 需要が 発生
▼供給が、減少
また戦争では、工場等は、破壊される。
生産能力は、激減し、供給も激減する。
▼需・給の バランスは?
大規模の戦争では、
需要は、巨大化し、供給は、壊滅的に減少する。
つまり 「 供給 < 需要 」 になる。
その需給バランスは、平時とは、比較にならない。
世界大戦は、ハイパーインフレの原因になりうる。
しかし21世紀は、大規模戦争は、起きていない。
ハイパー・インフレは、
世界大戦等で、発生

- ■ハイパーインフレの事例は?
- - 消費者 経済 総研 --
◆19世紀~20世紀の 先進国では?
19世紀~20世紀の 「 先進国 」での事例は、どうか?
19世紀では、南北戦争の後のアメリカ
20世紀では、1次世界大戦の後のドイツ帝国
このように、大規模な戦争で、
ハイパーインフレが、発生した。
-- 消費者 経済 総研 --19世紀:南北戦争の後の米国
20世紀:1次大戦後のドイツ帝国
先進国のハイパーは、大戦で発生
◆21世紀では、どうか?
ベネズエラや、ジンバブエで、発生した。
21世紀のハイパーインフレは、途上国で、起きた。
21世紀の「先進国」に、ハイパーインフレは、無い。
▼ジンバブエでは?
独裁政権による、極端な政策で、発生した。
白人を国外追放し、外資も撤退した。
それによって、生産が落ち、「供給不足」になった。
「 供給< 需要 」 である。
2008年7月のインフレ率は、2億3100万%だ。
▼ベネズエラは?
2019年1月のインフレ率は、年率268万8670%。
ベネズエラは、石油大国である。
よって経済は、石油の輸出に、頼っていた。
石油を売るだけで、儲かるから、産業は育たない。
よって、国内産業の供給能力は、少ない。
それゆえ、物資は輸入に、頼っていた。
経済制裁も加わり、石油の輸出が減った。
輸出の減少で、外貨も減り、輸入も困難になった。
国内での生産・供給は、元々少なかった。
さらに、外国からの物資の輸入も、減った。
つまり、モノの供給は、不足した。
「 供給 < 需要 」 である。
※出典:ジンバブエ・ドル| wikipedia |
※出典:ベネズエラ、1月のインフレ率が268万%に
日本経済新聞|2019年2月8日||
ハイパーインフレは、
21世紀は、途上国で、発生
▼先進国は?
前項のベネズエラ、ジンバブエは、途上国である。
21世紀の先進国では、ハイパーインフレはない。
2つの途上国も「かなり特殊な政治や環境」である。
例外と捉えても、いいだろう。
20世紀までの先進国のハイパーインフレは、
大規模な戦争が、原因だった。
巨額の軍事需要と、工場生産のダウンが原因だ。
21世紀の先進国には、大規模な戦争は、ない。
▼ウクライナ戦争では?
ロシアもウクライナは、先進国ではなく途上国だ。
2022年8月のインフレ率は、
ロシア14.3%、ウクライナ23.8%だ。
※出典:経済指標 |JA | TRADINGECONOMICS.COM
ハイパー・インフレは、
21世紀の先進国は、無縁

- ■日本の ハイパー・インフレ は?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆日本|2次 世界大戦 では?
日本も、第2次世界大戦の影響があった。
45年10月から3年半で、CPIは約100倍になった。
前段で定義した通り、
ハイパーインフレは、年間130倍超の物価上昇だ。
よって、焼野原となった戦後の日本でも
ハイパーインフレではない。
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本| オイルショック後 では?
1973年オイルショックで、日本はどうなったか?
翌74年、日本のCPI(消費者物価指数)は、23%上昇した。
ハイパーインフレではないが、狂乱物価とされた。
74年のインフレは、73年の中東戦争が原因だ。
戦争当事国に産油国が多く、原油高騰したからだ。
「戦争→原油高騰」は、ウクライナ戦争も同じだ。
「 供給 < 需要 」 ではなく、
コスト・プッシュによるインフレである。
-- 消費者 経済 総研 --
日本は、
ハイパーインフレは、なかった

- ■明治維新の後の 日本は?
- 日本も、20~21世紀で、高インフレが起きた。
既述の通り、「大戦後」と、「オイルショック後」だ。
では、19世紀の日本では、どうか?
明治維新の後の西南戦争で、高インフレが起きた。
西南戦争は、明治10年(1877年)に、発生。
政府 vs 反乱軍(西郷隆盛が率いる旧武士)の内戦だ。
戦費を補うため、政府は紙幣を、大量発行した。
その結果、高インフレが起きた。
当時は、明治10年で、今日のようなデータは無い。
よって、インフレ率の値は、見当たらない。
だが、下記のコメの価格が、参考になる。
4年間で、約2倍に上昇した。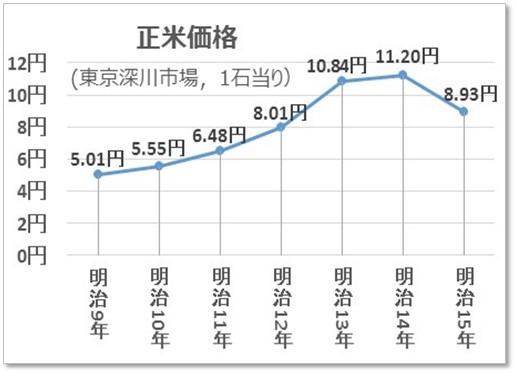 ※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成
※下記出典から、消費者経済総研が、グラフを作成
※出典:ADEAC|デジタルアーカイブシステム
西南戦争の後のインフレの特徴は、
「 政府が、紙幣を、大量発行 」した点にある。
▼20世紀の 日本の 高インフレは?
・太平洋戦争後のインフレは、「 供給 < 需要 」
・オイルショック後は、コストプッシュ・インフレ
▼19世紀の 日本の 高インフレは?
西南戦争の後の高インフレは、
「 政府による 紙幣の大量発行 」 が、原因だった。
さて「純MMT」の特徴は、政府の紙幣発行だった。
つまり西南戦争の頃の日本は、「純MMT」であった。
その反省から、日銀が、誕生することになる。
-- 消費者 経済 総研 --
◆MMTで、高インフレ?
-リスクは、高インフレ、ハイパーインフレ?-
▼明治の純MMT
明治の日本は 「 純MMTで、高インフレ 」 が発生。
やはり、 「 純MMT 」 は、危険なのか?
▼令和の MMT的
令和の日本は、 「 MMT的理論を、実行中 」 だ。
だが、デフレ脱却未完なので、インフレ懸念無い。
では、MMT的なら、OKで、純MMTは、NG か?
▼なぜ、発行者が違う?
皆さんのお財布の中のお金を、見て頂きたい。
500円玉には、「 日本国 」と、書いてある。
1万円札には、「 日本銀行 」と、書いてある。
硬貨(コイン)の発行者は、日本国つまり政府。
紙幣(お札)の発行者は、日銀。
なぜ、発行者が、違うのか?
政府が、お金を発行した方が、良いのか?
日銀が、お金を発行した方が、良いのか?
これらの疑問について、
続編・次回号で、解説したい。
-- 消費者 経済 総研 --

- ■MMT-7| 高圧経済11| 爆上げVol.15
- 2022年 10月 8日 (土) に 新規投稿
Vol.15 (第2部の高圧経済の11回目)
MMT-7:なぜ、お札は日銀で、コインは政府?
-- 消費者 経済 総研 --
◆積極財政で、高圧経済へ?
「 連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦 」
の第2部は、「 景気 UP 編 」だ。
「 積極財政 」 で、「 高圧経済 」 を実現し、
日本が、長い低迷から、脱出へ。
このテーマを、現在、継続中。
-- 消費者 経済 総研 --
◆前回号は?
MMTで、「 ハイパーインフレ 」 に、なるか?
ハイパーインフレは、過去、いつどこで、起きたか?
上記を、前回号で解説した。
-- 消費者 経済 総研 --
◆今回号は?
▼MMT的 は OKで、 純MMT は NG?
明治の日本は、純MMTを行い、高インフレが発生。
やはり、 「 純MMT 」 は、危険なのか?
令和の日本は、 「 MMT的理論を、実行中 」 だ。
では、MMT的なら、OKで、 純MMTは、NG か?
▼なぜ、発行者が違う?
硬貨(コイン)の 発行者は、政府。
紙幣(お札)の 発行者は、日銀。
なぜ、発行者が、違うのか?
政府が、お金を発行した方が、良いのか?
日銀が、お金を発行した方が、良いのか?
今回号は、これらを、解説していく。
-- 消費者 経済 総研 --

- ■通貨,貨幣,紙幣,硬貨,銀行券の違い
- 通貨, 貨幣, 紙幣, 硬貨, 銀行券
これらの違いを、皆さん、考えて頂きたい。
-- 消費者 経済 総研 --
◆「 通貨 」、 「 貨幣 」、 「 紙幣 」 とは?
日本での 通貨、貨幣、紙幣 などを、解説する。
その他に、硬貨、銀行券と、様々な呼び方がある。
法律での名称は、「通貨」、 「貨幣」、 「銀行券」 だ。
「 通貨 」 とは、
「 貨幣 」 (コイン) + 「 銀行券 」 (お札)だ。
(通貨法※2条3項にて、定義されている)
「 貨幣 」 は、
「 コイン 」 の他に、「 硬貨 」 とも言う。
「 銀行券 」 は、
「 お札 」 の他に、 「 紙幣 」 とも言う。
「 貨幣 = コイン 」 は、少々、馴染みが薄い。
馴染みある言葉のほうが、混乱しなくて良い。
よって本稿では、
コインを、「 貨幣 」 ではなく 「 硬貨 」 と呼ぶ。
通貨 (お金) =
硬貨 (コイン)
+
銀行券 (お札)

- ■お金は、どこが、発行している?
- 1万円札には、「 日本銀行 」 と書いてある。
500円玉には、「 日本国 」 と書いてある。
この違いの謎とは?
-- 消費者 経済 総研 --
◆紙幣は?
銀行券(紙幣) は、「日銀が発行」する。
(日本銀行法 46条)
日銀は、下記の種類を、発行している。
一万円券、五千円券、二千円券、千円券の4種類
-- 消費者 経済 総研 --
◆一方、 「硬貨」 は?
硬貨は、日銀ではなく、「政府」が、発行している。
(通貨法 4条1項)
政府は、下記の六種類の通常硬貨を、発行する。
五百円、百円、五十円、十円、五円、1円
(通貨法 5条1項)
皆さんの財布の中のお札とコインを、見て欲しい。
発行主体が、書いてある。
「紙幣」は、せっかくだから、千円札ではなく、
1万円札を、見て頂きたい(笑)
「 日本銀行券 壱萬円 日本銀行 」と書いてある。
次に、「硬貨」を、見て頂きたい。
(これも、せっかくだから、五百円玉で)
「 五百円 日本国 」と、刻印されている。
発行主体は、
硬貨は、日本国(政府)で、紙幣は、日銀なのだ。
※出典:通貨法(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律)
硬貨 (コイン) は、 政府が 発行
紙幣 ( お 札 ) は、 日銀が 発行

- ■お札の誕生と、銀行の誕生
- -- 消費者 経済 総研 --
◆コインから、 お札へ、 進化 ?
「 硬貨・紙幣の歴史 」 は、国によって異なる。
よって、世界の概ねの流れを、解説する。
紙幣(お札)よりも、硬貨(コイン)が、先に登場だ。
経済活動の発展で、お金は、どうなっていくか?
当然に、硬貨のやり取りが、増えていく。
すると、硬貨の重さや、盗難リスクが、課題になる。
そこで、両替商人や金庫商人へ、硬貨を預ける。
預けた人は、「 硬貨を預けた 証拠の紙 」 を、
もらって帰る。
預けた証拠の紙は、「 預り証 」のことだ。
この「 預り証 」 の紙が、「 銀行券 」 の始まりだ。
「 コインの預り証 」 の紙が、
「 お札 」 の始まり
-- 消費者 経済 総研 --
◆両替・金庫の商人が、銀行へ進化?
そして両替金庫の商人は、銀行業者になっていく。
買い物の際、硬貨が必要な時は、どうするか?
預けた人が、両替・金庫の商人の所へ行く。
そして、預り証を提出し、硬貨を引き出す。
その硬貨を使って、買い物をする。
しかし、やはり硬貨は、重くて不便だ。
両替・金庫の商人の所へ、出かけるのも、面倒だ。
「 最初から、預り証で、支払う 」
この方が、便利だと、気付く。
こうして、預り証の紙は、「お金」として、普及した。
預り証の紙が、お札 (紙幣) である。
世界の歴史を見ても、
様々な「硬貨」を、様々な「政府等※」が、発行した。
※政府等とは、政府、王様、殿様などを含む
一方、預り証から発展した「紙幣」は、
「銀行」(前身は両替・金庫の商人)が、発行したのだ。
硬貨は、政府や王様が、発行
紙幣は、(金庫商人だった)銀行が、発行

- ■日本のお金は?
- ここから、日本のお金の話に、移したい。
-- 消費者 経済 総研 --
◆明治時代は、お金は、政府が発行?
明治維新以降の日本のお金は、どうだったか?
硬貨も紙幣も、明治政府が、発行していた。
明治10年(1877年)に、西南戦争が、発生。
戦費を補うため、政府は紙幣を、大量発行した。
「西南戦争で、高インフレ発生」は、前回号の通り。
この高インフレの原因は、
「 政府が、お札を、刷りすぎた 」 からだ。
明治の 高インフレの 原因は、
政府が、お札を、刷りすぎたから
この反省から、お札は、「 政府が発行 」ではなく、
「 中央銀行が発行 」に、変更した。
中央銀行が発行に、変更した理由は何か?
「 政府が、自らお札を、刷る 」仕組みだと、どうか?
政府が、「 無節操に 大量発行 」 する懸念がある。
戦時ではなく、平時でも、大量発行の懸念は残る。
よって、政府とは別の組織が発行と、なったのだ。
高インフレの反省から、
政府ではなく、日銀が、発行へ
-- 消費者 経済 総研 --
◆中央銀行の日銀が、誕生
明治10年に、西南戦争が、発生し、インフレへ
明治14年に、物価は、明治10年の2倍(生米価格2倍)
明治15年に、日本銀行が、設立
明治18年に、最初の日本銀行券が、発行
こうして、近代日本では、
「 お札は、日銀が発行 」 するとなった。
-- 消費者 経済 総研 --
◆硬貨の発行は、政府のまま?
「 硬貨は、政府が、発行 」 の方は、継続した。
「 お札を大量印刷 or コインを大量鋳造 」
巨額のお金を、作り出すには、前者が選択される。
大量のお金を、作るには、「お札」の方が早い。
「硬貨」では、非効率だ。
「 硬貨で、お金の大量発行 」を、する懸念は薄い。
硬貨の発行は、政府のままでも、問題なしなのだ。
硬貨の発行は、 政府のまま
▼参考
参考までに、 「お札」と「硬貨」 の現在の割合は、
お札:96%、硬貨:4%だ。(2022年8月)
日本銀行券発行高:120兆4343億円 (96%)
貨幣流通高 : 4兆 8959億円 ( 4%)
※出典:日本銀行|統計別検索
-- 消費者 経済 総研 --
◆政府が、高額のコインを、発行?
日本政府は、高額の硬貨の発行を、時々実施した。
それは、「 記念硬貨 」である。
天皇在位記念や、五輪記念などでの記念事業だ。
政府は、様々、高額の記念硬貨を、発行してきた。
額面での最高額は、「 10万円 」 の記念硬貨だ。※
※1991年発行:「天皇陛下御即位記念」
政府は、10万円硬貨 を、発行した
▼記念硬貨の 歴史は ?
1964年(昭和39年)に、
日本で最初の記念硬貨を、政府が発行した。
東京オリンピックの記念硬貨である。
2022年(令和4年)は、
「沖縄復帰50周年記念」(1万円玉)等を、発行した。
▼高額コインの発行は、内閣が決める?
政府が発行する 「 硬貨 」 とは、
通常硬貨(1円~500円) + 記念硬貨(1万円まで) だ。
記念硬貨の金額上限は、現行法では、1万円玉だ。
1万円玉なら、閣議決定で、発行できる。
発行枚数は、政令で定める。
(政令で定める = 「閣議で決定」と、ほぼ同じ意味)
言い換えて、まとめると、
1万円玉・記念硬貨は、内閣の会議で決められる。
内閣(総理大臣+各大臣)で、総額を、決められる。
1万円玉の 発行も、
その総額も、内閣が 決める
-- 消費者 経済 総研 --
◆政府も日銀も、上限1万円を、発行?
過去号で既述の通り、純と的の違いは下記だった。
・純MMT の財源は、政府が、お金を発行
・MMT的 の財源は、日銀が、お金を発行
日銀が、発行するお札は、最高額は1万円。
政府が、発行するコインも、最高額は1万円。
日本は、「MMT的理論」を、実施中だが、
「純MMT」も、実施可能なのか?
積極財政で高圧経済のためには、
結局、純MMTと、MMT的、どちらが良いのか?
これらを、今後解説したい。
-- 消費者 経済 総研 --

- ■MMT-8| 高圧経済12| 爆上げVol.16
- ◆2022年 10月 10日 (月) に 新規投稿
(第2部の高圧経済の12回目)
MMT-8:MMTは、純と的 結局どちらが良い?
-- 消費者 経済 総研 --
◆積極財政で、高圧経済へ?
「 連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦 」
の第2部は、「 景気 UP 編 」だ。
「 積極財政 」 で、「 高圧経済 」 を実現し、
日本の長い低迷から、脱出へ。
このテーマを、現在、継続中。
-- 消費者 経済 総研 --
◆前回号は?
▼MMT的 は OKで、 純MMT は NG?
明治の日本は、純MMTを行い、高インフレが発生。
やはり、 「 純MMT 」 は、危険なのか?
令和の日本は、 「 MMT的理論を、実行中 」 だ。
では、MMT的なら、OKで、 純MMTは、NG か?
▼なぜ、発行者が違う?
硬貨(コイン)の 発行者は、政府。
紙幣(お札)の 発行者は、日銀。
なぜ、発行者が、違うのか?
政府が、お金を発行した方が、良いのか?
日銀が、お金を発行した方が、良いのか?
上記を、前回号で解説した。
-- 消費者 経済 総研 --
◆今回号は?
過去号で既述の通り、純と的の違いは下記だった。
・純MMT では、政府が、お金を発行
・MMT的 では、日銀が、お金を発行
日銀が、発行するお札は、最高額は1万円。
政府が、発行するコインも、最高額は1万円。
日本は、「MMT的理論」を、実施中だが、
「純MMT」も、実施可能なのか?
「積極財政で、高圧経済」の実現には、
結局、純MMTと、MMT的、どちらが良いのか?
今回号は、これらを、解説していく。

- ■純MMTと、MMT的理論
- この連載シリーズの過去号では、
純MMTと、MMT的理論の比較を、してきた。
-- 消費者 経済 総研 --
◆2つの共通項は?
純MMTと、MMT的理論の共通点は、何だったか?
「政府のお金を増やし、政府の支出を増やす」だ。
つまり、財政の赤字を肯定し、
積極財政で、高圧経済の実現が、共通の目的だ。
純MMTと、MMT的の共通メリットは、下記だった。
・景気を 良くする ことができる
・国民の 役に立つ便益を 増やせる
共通メリットは、
・景気を 良くする ことができる
・国民の 役に立つ便益を 増やせる
-- 消費者 経済 総研 --
◆2つの相違点は、財源?
純MMTと、MMT的も、政府のお金を、増やす。
違うのは、お金の増やし方だ。
下記が、その違いだ。
・純MMT:政府が自ら紙幣を発行し、お金を増やす
・MMT的:国が借金を増やし、お金を増やす
・純MMT:政府が自ら紙幣を発行
・MMT的:借金で、お金を増やす
-- 消費者 経済 総研 --
◆MMT的の 増やし方の 流れとは?
MMT的の方は、日本を始め先進国で、実施中だ。
MMT的の流れを、下記で、再確認する。
国の借金は、大半が、国債の発行による
↓
国債の販売額を、仮に、2兆円とする
↓
政府が、民間の銀行等へ、国債(2兆円)を、販売する
↓
政府は、その販売代金(2兆円)を、手に入れる
↓
これで、政府のお金は、2兆円増えた
↓
その後、その国債(2兆円)を、
民間銀行は、日銀へ売却する
↓
最終的に、国債(2兆円)は、日銀が保有する
↓
国債は、借用証書の性格を持つ
↓
2兆円の国債を持つ日銀は、
政府へ、2兆円のお金を、貸している状態だ
↓
国債の販売を続けることで、政府のお金は増える
※わかりやすさのため、国債価格は2兆円で固定とした
-- 消費者 経済 総研 --
◆的は、複雑で、純なら簡単?
前項が、MMT的での、政府のお金の増やし方だ。
民間の銀行等が、「中継役」に、なっている。
「政府」、「民間銀行等」、「日銀」の3者が、登場する。
このややこしい流れ(MMT的)より、
政府がお札を自ら刷る(純MMT)の方が、簡単だ。
▼純MMTの 増やし方の 流れとは?
純MMTでは、
2兆円のお札を、政府が自ら刷って、お金を増やす。
お金の増やし方は、
MMT的よりも、純MMTの方が、容易なのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
お金を 増やすには、
的よりも、純の方が、容易

- ■今でも政府は、お金を発行中?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆500円玉の増発は、どうか?
前回号の通り、政府は、現在、硬貨を発行している。
現制度で、純MMTを、実行するには、
硬貨の発行量を、増やせばいい。
だが、硬貨増発で、政府予算を作るのは、非効率だ。
「1円玉作るのに、3円かかるって、知ってる?」
これは、東急リバブルのテレビCMでの会話だ。
一番高額の500円玉でも、効率よくない。
万円単位以上の高額の硬貨なら、効率的だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本政府が、高額の通貨を、発行?
日本政府は、高額の硬貨の発行を、時々実施した。
「記念硬貨」である。
額面での最高額は、「10万円」の記念硬貨だ。
現行法では、記念硬貨の金額上限は、1万円玉だ。
「1万円札」を、政府は発行できない。
一方、「 1万円玉 記念硬貨 」は、
閣議決定だけで、政府は発行できる。
だが記念硬貨は「国家的な記念事業」に限定だ。
(※通貨法5条に、規定)
あなたの わからない を
わかるに 変える
- 消費者 経済 総研 -

- ■お金の 増やし方 <まとめ>
- ① 中央銀行が、お札を、発行
② 政府が、お札を、発行
③ 政府が、高額な硬貨を、発行
-- 消費者 経済 総研 --
◆海外や、過去の日本では?
①中央銀行が、お札を、発行
先進国は、多くが、中銀の発行による。
現在の日本も、そうだ。
①政府が、お札を、発行
近代日本は、明治初期に、実施した。
シンガポールは、現在も実施している。
③政府が、高額な硬貨を、発行
日本は、1万円玉までなら、今でも継続中。
しかし国家的な記念事業に限定される。
-- 消費者 経済 総研 --

- ■発行は、政府と日銀、よいのは?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆西南戦争で、政府発行で、高インフレ?
現在のお札・硬貨の割合は、お札96%、硬貨4%だ。
現在のお札は、日銀が供給している。
政府の紙幣発行をやめたのは、西南戦争の反省だ。
政府の紙幣発行を、やめたので、
以降、高インフレは、無くなったか?
-- 消費者 経済 総研 --
◆日銀発行でも、戦争で、高インフレ?
太平洋戦争後にも、日本は、高インフレになった。
つまり政府発行でなくても、高インフレが発生だ。
お札の発行者が、日銀でも、政府でも、
戦争になったら、高インフレだ。
「日銀発行なら、インフレ起きない」ではないのだ。
太平洋戦争では、政府が直接増刷ではない。
政府が、国債(借金)を増やして、
日銀に、多くのお金を、供給させたのだ。
政府でなく、日銀の発行でも、
戦争で、高インフレ
-- 消費者 経済 総研 --
◆平時なら、政府発行でもよい?
前項で見た通り、戦争では、
日銀でも政府でも、高インフレが、発生した。
では、戦争がなければ、政府発行でもいいか?
確かに、よさそうに思える。
だが、政権が人気取りのために、
お金をバラマキすぎるリスクは、ある。
戦時ではなく、平時の21世紀では、どうか?
▼乱暴な政権では?
乱暴な政権だと、
高インフレ→ハイパーインフレのリスクはある。
21世紀でも、独裁政権のジンバブエは、
乱暴な政策で、ハイパーインフレになった。
▼通常の政権なら、どちらでも同じ?
ちゃんとした政権なら、政府発行でもよいとなる。
一方、乱暴な政権なら、中央銀行の発行でも、
高インフレになりうる。
結局、お札の発行者が、政府でも日銀でも、両方、
高インフレのリスクは、あるのだ。
政府でも、日銀でも、
両方、高インフレのリスクある
▼どちらもインフレ懸念あるなら、政府でよい?
政府でも日銀でも、どちらもリスクあるなら、
政府発行で、よいではないか?
「政府→民間銀行等→日銀を経由」という
現在の面倒な仕組みでなくても、よいではないか?
両方、リスクあるなら、
政府の方が、簡単でよい
-- 消費者 経済 総研 --
◆先進諸国は、どうしている?
多くの先進国が、中銀発行の制度を採用する。
その理由は、何か?
政府が紙幣発行だと、すぐに増刷できてしまう。
中銀が紙幣発行なら、クッションが入る。
このクッションが、ブレーキ役になりうるのだ。
政権の恣意的・乱暴な財政政策を、避けやすい。
しかしながら、繰り返しだが、
中銀の発行でも、お金を増やせてしまう。
結局、どっちが、よいのか?
-- 消費者 経済 総研 --
あなたの わからない を
わかるに 変える
- 消費者 経済 総研 -

- ■純MMTと、MMT的 のまとめ
- -- 消費者 経済 総研 --
◆純MMTと、MMT的の 共通項は?
既述の通り、純MMTと、MMT的の共通点は、
「政府のお金を増やし、政府の支出を増やす」だ。
つまり、財政の赤字を肯定し、
積極財政によって、高圧経済が実現できるのだ。
純MMTと、MMT的の共通のメリットは、下記だ。
・景気を良くすることができる
・国民の役に立つ便益を増やせる
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本と、他国との、違いは?
日本と、他の先進国の違いを、
過去号Vol.12(MMT-4|高圧経済8)で、見てきた。
比較した結果、明確になったのは、下記2点だった。
・日本政府の支出が、小さすぎる
・日本の借金の増加が、少なすぎる
日本と 他の先進国の 違いは、
・日本の 政府支出 が、小さい
・日本の 借金の増加 が、少ない
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本の低迷の原因は?
先進諸国は、国の借金を、増やしながら、
政府の支出を、増やしてきた。
-- 消費者 経済 総研 --
◆他国は、政府の支出を、増やした?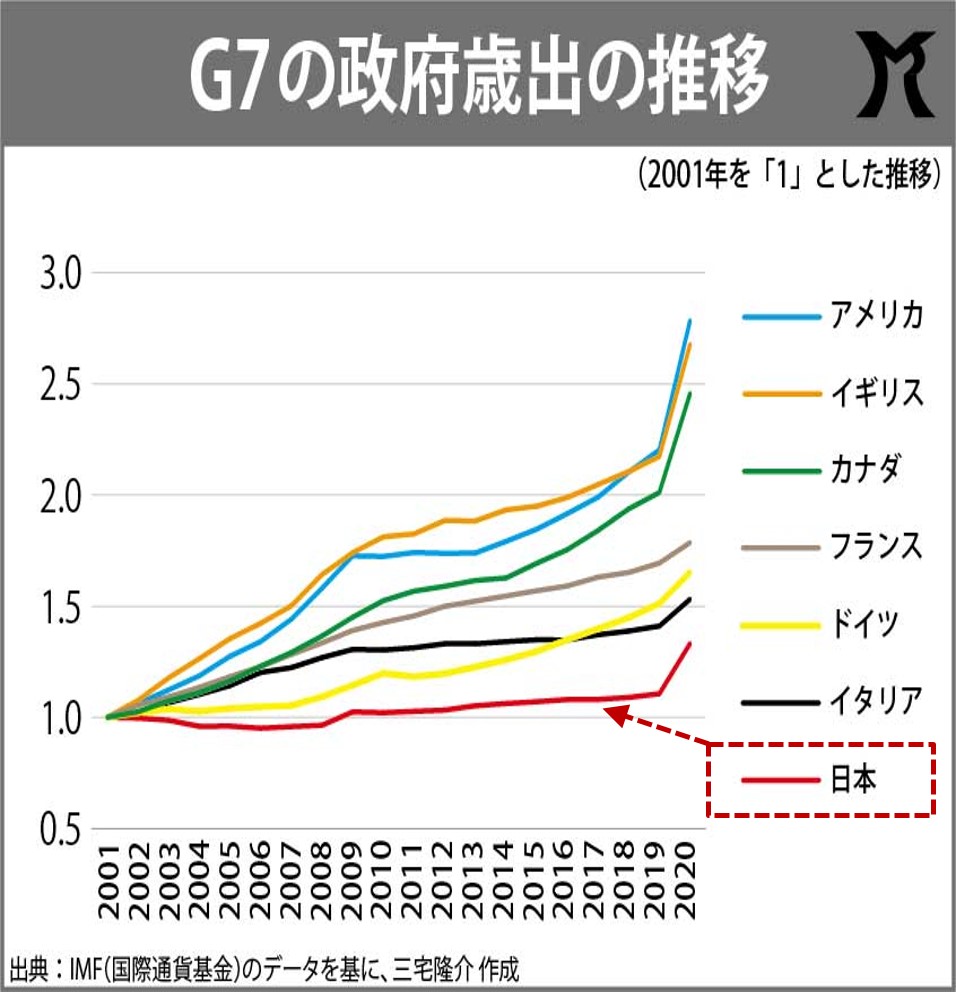 政府の支出の増加は、日本が、最も、少ない
政府の支出の増加は、日本が、最も、少ない※グラフ出典:川崎市議会議員 三宅隆介氏
日本の 政府支出は、少なすぎる
-- 消費者 経済 総研 --
◆他国は、国の借金を、増やした?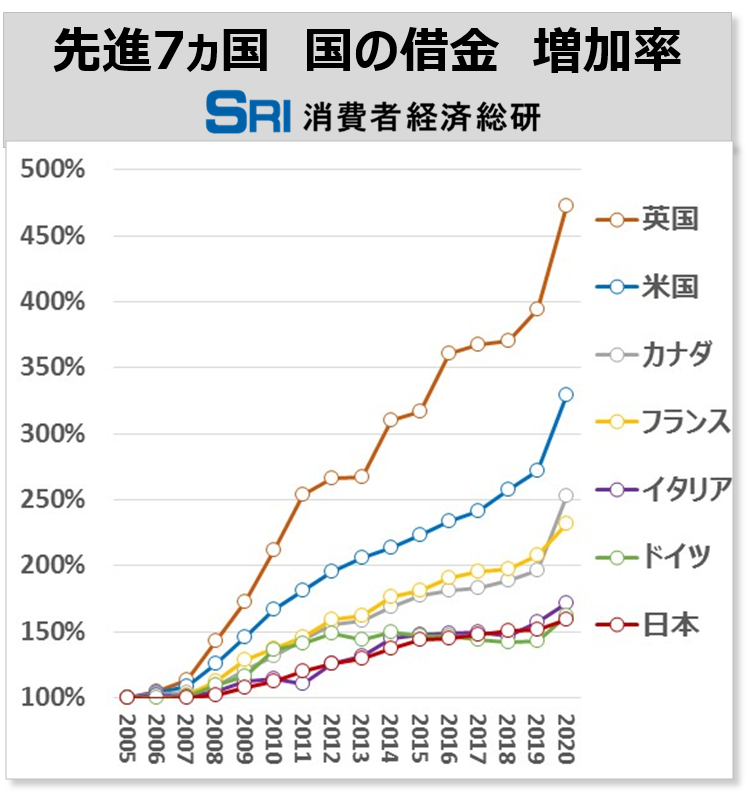 ↓
↓
英 国 473%
米 国 329%
カナダ 253%
フランス 232%
イタリア 172%
ドイツ 162%
日 本 159%
↓
日本が、最も借金の増加が、少ない
※上のグラフの対象は、Liabilities
(IPSGS(年金等)ある場合は、それを除く)
※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成
※出典 :IMF | Balance Sheet-IMF Data日本の借金の増加が、少なすぎる
「 日本の 借金増加は、ダメ 」 ではなかった。
「 日本の 借金増加が少ない のが、ダメ 」 なのだ。
本件は「 Vol.12(過去号MMT-4|高圧経済8 )」参照
以前も指摘した通り、「借金 けしからん」は、
下記のいずれかだった。
- ◆日本で 借金が批判される 理由 とは?
- なぜ、財政赤字と借金は、日本で批判されるのか?
↓
下記のいずれかだ
[1] そう言った方が、自分が、得をする
[2] そう言わざるを 得ない立場にある
[3] 単純に 情報不足
[3]は、知識の習得で解消する。
[1]と[2]は、ポジショントーク だ。
消費者経済総研は、財務を預る役所でもなく、
特定政党の支援を、する立場でもない。
つまり、当方のポジションは、中立・客観 だ。
「わかりやすく解説する」との立場に、いるだけだ。
※なお「ポジショントークは直ちにNG」
というわけではない。
借金はダメ と言う人は、「だいぶ減った」と感じる。
知識の習得(情報の共有・伸展)が、進んだのだろう。
-- 消費者 経済 総研 --とことん
わかりやすい 解説
- 消費者 経済 総研 -
◆日本に、需給ギャップが、あるから?
需給ギャップ(潜在GDP-実際のGDP)は、いくらか?
最近は、20兆円前後のマイナスで、推移している。
潜在GDPと、実際のGDPは、どのくらいの金額か?
時期によって、値は異なるが、概数は下記だ。
潜在GDP558兆 -GDP537兆 =需給ギャップ 21兆
558兆円供給できるが、需要が537兆円しかない。
「供給」よりも、「需要」が、21兆円分、弱いのだ。
マイナスの需給ギャップが、日本経済の課題だ。
現状は、民間部門の需要(個人消費+企業投資)が弱い。
「 供給 > 需要 」で、需要が20兆円不足している
「 供給 >需要」では、日本は、デフレ脱却できない。
需要不足の解消には、どうするか?
不足分を 「政府の支出の拡大」 で、埋めるのだ。
弱い民間部門の需要を、
政府の需要増で、埋める
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本が、低迷脱出する方法 とは?
日本が、低迷脱出する策を、連載で解説してきた。
それは 「 積極財政で、高圧経済 」 の実現だった。
高圧経済の実現の方法は、純MMTか、MMT的だ。
純MMTか、MMT的で、政府の支出を増やすのだ。

- ■結局、どっちがよい? 純と的
- -- 消費者 経済 総研 --
◆純MMTと、MMT的 相違点は、財源?
純MMTと、MMT的も、政府のお金を増やす。
違うのは、お金の増やし方だ。
MMT的は、 「国の借金」を起点とし、
民間銀等が中継し、「日銀がお金を供給」だった。
純MMTは、 「政府が自ら 紙幣を発行」だった。
▼今後の日本は、どっちを、選べばよい?
MMT的の方は、日本を始め先進国で、実施中だ。
今後の日本は、
純MMTと、MMT的のどちらを選ぶべきか?
-- 消費者 経済 総研 --
◆純と的のメリット・デメリットは?
▼MMT的
MMT的の メリット:
現在実行中なので、新た制度設計は不要
MMT的の デメリット:
「借金けしからん」との誤った意見を招きやすい
▼純MMT
純MMTの メリット:
スキームがシンプルなので、機動的
純MMTの デメリット:
新たな制度設計や法整備が必要
-- 消費者 経済 総研 --
◆早く、強化できるのは、MMT的?
純MMTと、MMT的の共通の目的は、
積極財政で、高圧経済の実現だ。
目的が同じなら、すぐ強化できる方を選べばよい。
純MMTの開始には、時間がかかるので、
MMT的のままで、良いだろう。
MMTを連載してきたが、この連載でのポイントは、
・日本は、借金大国ではない
・今後さらに、借金が増えても、問題ない
・借金増がNGではなく、逆に借金が少ないのがNG
・仮に、借金返済となっても、有名なフレーズの
「 お札刷って返せばいい。 簡単だろ? 」である。
-- 消費者 経済 総研 --とことん
わかりやすい 解説
- 消費者 経済 総研 -
◆結論と、政策提言
現在、日本は、MMT的を実行中だ。
「現在のMMT的を、より強化する」ことを提言する。
先進諸国(G7)並みに、国の借金を増やす
↓
増えたお金で、先進諸国並に、政府の支出を増やす
とにかく、これを強化すべきである。
G7なみに、国の借金を、増やす
↓
増えたお金で、政府の支出を増やす
とにかく、これを強化すべき
-- 消費者 経済 総研 --
◆皆が知らない 日本の借金の真実?
▼借金原則NG の 法律の謎
「 借金は、原則NG 」 は、法律に書いてある?
その法律は、75年前、戦後の進駐軍が、定めた?
その理由は、「 借金すると、〇〇できる 」 から?
▼借金しないと、給料払えない?
借金して、お金の量を、増やさないと、
日本人の給料の支払いが、できない?
これらの謎を、今後、解説していきたい。
今回は、中一日で、連続投稿した。
「10月8日: なぜ、お札は日銀で、コインは政府? 」
を、この下(次項)にて、記載済み。
-- 消費者 経済 総研 --

- ■MMT-9| 高圧経済13| 爆上げVol.17
- 2022年 10月 15日 (土) に 新規投稿
Vol.17 (第2部の高圧経済の13回目)
MMT-9:借金NGは、〇〇の回避 のため?
-- 消費者 経済 総研 --
◆積極財政で、高圧経済へ?
「 連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦 」
の第2部は、「 景気 UP 編 」だ。
「 積極財政 」 で、「 高圧経済 」 を実現し、
日本の長い低迷から、脱出へ。
このテーマを、現在、継続中。
-- 消費者 経済 総研 --
◆前回号は?
・純MMT では、政府が、お金を発行
・MMT的 では、日銀が、お金を発行
日銀が、発行するお札は、最高額は1万円。
政府が、発行するコインも、最高額は1万円。
日本は、「MMT的理論」を、実施中だが、
「純MMT」も、実施可能なのか?
「積極財政で、高圧経済」の実現には、
結局、純MMTと、MMT的、どちらが良いのか?
上記を、前回号で解説した。
-- 消費者 経済 総研 --
◆今回号は?
「 借金NG の 法律 」 の 謎 とは?
先だって、クイズ。
皆さんに、下の「〇〇は何か」を、お考え頂きたい。
「 借金は、NG 」 は、法律に書いてある?
その法律は、〇〇〇が、定めた?
その理由は、「 借金すると、〇〇できる 」 から?
つまり、借金NGの法律が、生まれた理由は、
「 財政の赤字の回避 」 ではなかった?
「 財政の破綻の回避 」 でもなかった?
実は、「 〇〇の回避 」 のためだった?
今回号は、これらを、解説していく。

- ■「純」と「的」の 共通点と、相違点
- この連載シリーズの過去号では、
純MMTと、MMT的理論の比較を、してきた。
-- 消費者 経済 総研 --
◆2つの共通点は?
純MMTと、MMT的理論の共通点は、何だったか?
「政府のお金を増やし、政府の支出を増やす」だ。
つまり、財政の赤字を肯定し、
積極財政によって、高圧経済を、実現する。
純MMTと、MMT的の共通メリットは、下記だった。
・景気を良くすることができる
・国民の役に立つ便益を増やせる
-- 消費者 経済 総研 --
◆2つの違いは?
過去号で既述の通り、純と的の違いは下記だった。
・純MMT では、政府が、お金を発行
・MMT的 では、日銀が、お金を発行
「過去号」を、読むには、「目次のリンク」から。

- ■ 借金はNGは、〇〇回避のため?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆借金はNGの 法的根拠は?
「 借金はNG 」 の法的根拠は、
昭和22年制定の 「 財政法 」 による。
なぜ昭和22年に、借金NGになったかを、
知らない人は、結構多い模様だ。
昭和22年に、借金NGに、なった理由は、
「 〇〇回避 」 のためだった?
「 財政の、赤字・破綻の 回避 」 ではないのだ。
▼財政法 4条1項は?
財政法4条1項の条文は、下記である。
( ..のドットは、省略箇所を示す。 以下同じ )
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、
その財源としなければならない。
但し、公共事業費..の財源については.
公債を発行し又は借入金をなすことができる。
※出典:財政法
※「 公債 」 とは、「 国債 + 地方債 」のこと。
国債は、国が発行し、地方債は、地方自治体が発行
4条:国の財源は、借金等はNG
公共事業等は、借金等でもOK
▼財政法 第5条は?
財政法5条の条文は、下記である。
..公債の発行については、
日本銀行に..引き受けさせ、
又、借入金については、
日本銀行から..借り入れてはならない。
但し、特別の事由がある場合において、
国会の議決を経た金額の範囲内では、
この限りでない。
5条:日銀からの借金等は、NG
-- 消費者 経済 総研 --
◆4条で、赤字国債は、NG?
▼ 「公債」+「借入金」 = 「借金」
財政法4、5条で「公債」と「借入金」の用語が出たが、
ここからは、まとめて、「借金」と表記する。
国債 ÷ 国の借金 = 84%
国の借金のうち、国債によるものが、84%だ。
※なお、借金や公債には、様々な種類がある。
その種類の詳細や、84%の計算等は、下記を参照
「日本の借金の 範囲・定義とは?」
▼赤字国債は、ダメ?
政府の支出の財源は、借金(国債等)では、NGだ。
つまり、税収が主な財源となる。
「歳入 < 歳出 」の赤字では、借金することになる。
歳入(税収等) ≧ 歳出(政府の支出) にする
ということだ。
しかし、実際には、
その都度、特例法を制定し、国債を発行してきた。
財政の赤字分を、国債で調達するので、
「赤字国債」と、呼ばれる。
とことん
わかりやすい 解説
- 消費者 経済 総研 -
▼建設国債なら、OK?
一方、公共事業の財源は、借金(国債等)でもよい。
公共事業の一つの例は、「幹線道路の建設」だ。
幹線道路の開通で、消費者の利便性は、UPする。
物資の輸送にも貢献し、産業発展にも貢献する。
公共事業で生れたものは、国の資産として残り、
将来にわたり、国民が利益を、受ける。
つまり、建設国債は、先行投資の位置づけだ。
後で、役に立つから、借金しても良いという事だ。
国の借金は、
公共事業等のための借金に、限定されていた。
この国債を、「 建設国債 」と呼ぶ。
国の借金は、
建設国債は、OK
赤字国債は、NG
-- 消費者 経済 総研 --
◆5条で、日銀からの直接借金は、ダメ?
▼直接引き受けの 禁止 とは?
第5条の趣旨は、
政府は、日銀から、直接の借金をしては、NGだ。
直接の借金とは、
「政府が日銀へ、国債等の直接の発行」も、含む。
これを、「 日銀 直接引受の 禁止 」 と言う。
なお、「日銀 直接引受け」を、
「 財政ファイナンス 」 とも言う。
日銀からの、直接の借金は、NG
▼間接の引き受けなら、OK?
直接ではなく、間接の引き受けなら、OKだ。
よって、過去号で、解説の通り、
次の①-④の流れで、「 間接引受け 」をやっている。
※「過去号」を、読むには、「目次のリンク」から。
① 政府が、国債発行
↓
② 民間銀行等 (中継役)が、国債を購入
↓
③ 民間銀行等 (中継役)が、日銀へ国債を売却
↓
④ 日銀が、国債保有
政府と日銀とで、「直接」ではなく、
民間銀行等を「中継役」としての「間接引受け」だ。
※但し、借金返済の期限が来て、借り換える際は、
政府と日銀の直接やり取りでよい、との例外ある。
日銀からの、間接の借金は、OK
▼間接はOK、直接はNGの 理由とは?
「 間接はOKで、直接はNG 」 なのは、なぜか?
「 節操なく、国が借金する 」 のを防ぐ趣旨だ。
そのために、クッションを、挟むのだ。
一番、簡単なお金の増やし方は、
「政府が自らお札を刷る」だった。
これは、過去号での解説の通りだ。
① 政府が、自ら、お札を刷る
② 中継なしで、日銀が、政府から、直接引受け
③ 民間銀行等が中継し、日銀が、間接引受け
①が、一番簡単だ。
②の方が煩雑で、さらに③の方が、煩雑だ。
煩雑であれば、お金を、簡単には増やせない。
乱暴な政権による、稚拙で恣意的な増刷を防げる。
「 間接 引き受け 」 の方が、
お金を、増やしにくい
-- 消費者 経済 総研 --
◆なぜ、借金NGに、なったか?
「 日本で国の借金はNG 」 となったのは、いつか?
太平洋戦争後の占領下の昭和22年だ。
日本が再び戦争しないように、
戦争の資金源を、GHQが、止めたのだ。
憲法9条の戦争放棄を、
資金面で保証する規定が、財政法4条だったのだ。
日本国憲法と財政法は、同じ頃に、施行された。
(憲法は昭和22年の5月、財政法は4月に施行)
▼GHQ覚書 昭和20年、21年
①昭和20年 「 戦争利得の除去 及び 財政の再建 」
②昭和21年 「 政府借入及び政府支出の 削減 」
2件の覚書の指示が、GHQから日本政府にあった。
「 戦争のために、政府借入するな 」 であった。
「借金はNG 」との財政法の条文は、
上記のGHQの覚書の趣旨を、立法化したものだ。
※参考文献: 日本銀行百年史|日銀
▼「財政法 逐条 解説」1947年 とは?
「 財政法 逐条解説 」 にて、
財政法4条の趣旨が、解説されている。
「戦争危険の防止については、
戦争と公債がいかに密接不離の関係にあるかは、
各国の歴史を紐解く迄もなく、我国の歴史をみても
公債なくして戦争の計画遂行の不可能であった事
を考察すれば明らかである。
..公債のない所に戦争はないと断言しうる..
従って、本条(財政法第4条)は、
..憲法の戦争放棄の規定を裏書き保証せんとする
ものであるとも言いうる。」
※出典:平井平治氏「財政法逐条解説」1947年
あなたの わからない を
わかるに 変える
- 消費者 経済 総研 -
-- 消費者 経済 総研 --
◆太平洋戦争で、借金 どう増えた?
下図の通り、
日本の国の借金は、太平洋戦争で、急増した。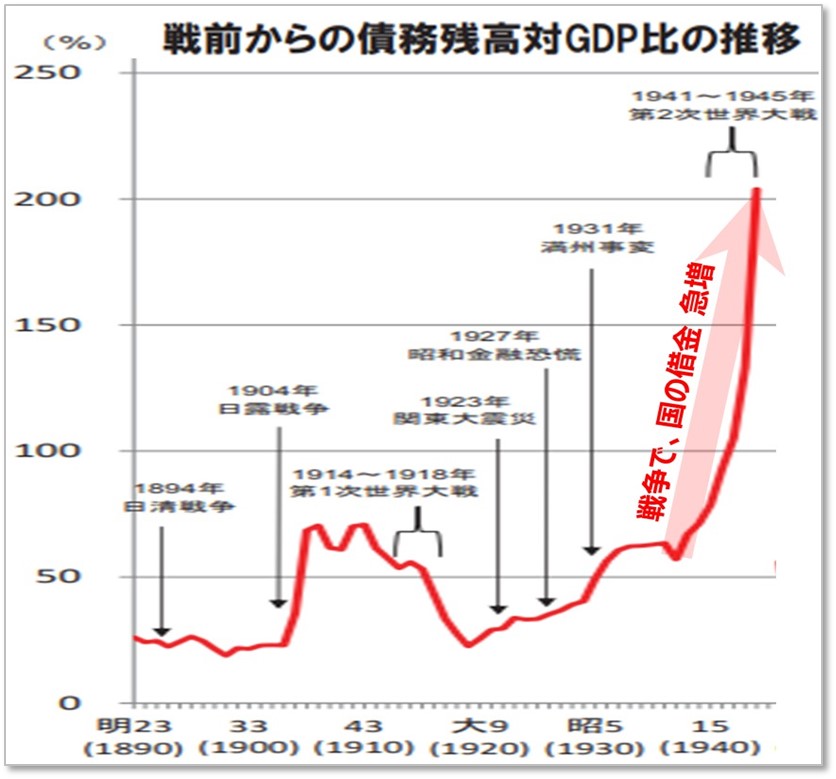 ※下記出典の中の図に、一部可加筆等した
※下記出典の中の図に、一部可加筆等した
※出典: 日本の財政関係資料|財務省|
巨額の戦費のために、巨額の借金をしたのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆借金 けしからん?
借金NGの理由は、下記だった。
「 財政破綻の回避 」ではなく、「 戦争の回避」
借金NGの理由は、
「 財政破綻の 回避 」 ではなく、
「 戦争の 回避 」
-- 消費者 経済 総研 --
◆借金NGの他に、航空もNG?
既述の通り、「 借金NGで、戦争回避 」だった。
戦費回避とは、
「 日本から米国への、攻撃力の無力化 」 でもある。
「 攻撃力の無力化 」は、
戦後の航空行政でも、行われた。
開戦時の真珠湾攻撃では、艦隊砲撃ではなく、
航空戦力による銃撃、爆撃、雷撃だった。
戦艦大和、戦艦武蔵も、開戦後に、誕生したが、
既に戦力貢献度は、小さかった。
攻撃能力は、陸上武装、艦砲攻撃より、
圧倒的に航空攻撃が、上回っていた。
戦後のGHQは、数年間、
日本の航空機の製造や飛行を、完全に停止させた。
(誤解だったが)模型飛行機まで自粛した時もあった。
軍用機も民間機も、全てを供出する命令があった。
ガソリンをかけて、日本の航空機は、燃やされた。
戦中までの航空産業の技師たちは、
戦後は、他の業界へ、転職していった。
※参考文献: ㈶日本航空協会|民間航空再開50年座談会

- ■令和は、同盟国に、国防予算UPを
- 太平洋戦争では、日本は、米国の敵国だった。
敗戦後の日本は、連合軍の占領下にあった。
米国は、昭和21年に「戦争回避で借金NG」とした。
昭和27年のサンフランシスコ平和条約で、
日本の主権は回復し、GHQの進駐は終了した。
そして時代は、変わり、敵国ではなく、
日本は、米国の同盟国だ。
米国は、日本を含む同盟国に、国防費を、
GDP比 2%以上に、増加するように、要請した。
2022年度の防衛費は、GDP比 1% 弱だ。
2023年度はGDP比 1% を、若干超える見通しだ。
戦争の回避のため、昭和21年、借金はNGになった。
だが、「 戦争の予算 」と、「 防衛の予算 」は、違う。
昨今の世界情勢を見れば、
日本の防衛強化の重要度は、増している。
防衛力の強化は、喫緊の課題である。
防衛予算の増加の財源は、
増税ではなく、国債発行を、財源とすべきだ。
増税では、
日本の防衛力がUPしても、日本の経済力を失う。
昭和21年と令和時代は、大きく事情が異なる。
本連載の過去号で、「 国の借金は、問題ない 」を、
様々な角度から、解説してきた。
さらに昨今の世界情勢からも、防衛の視点からも、
「国の借金はNG」と言っている場合ではない。
※出典:国防費はGDP比2%以上に|2020/9/18|日経新聞電子版

- ■MMT-10| 高圧経済14| 爆上げVol.18
- 2022年 10月 22日 (土) に 新規投稿
Vol.18 (第2部の高圧経済の14回目)
MMT-10:日本や世界の「お金の 増やし方」
-- 消費者 経済 総研 --
◆積極財政で、高圧経済へ?
「 連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦 」
の第2部は、「 景気 UP 編 」だ。
「 積極財政 」 で、「 高圧経済 」 を実現し、
日本の長い低迷から、脱出へ。
このテーマを、現在、継続中。
-- 消費者 経済 総研 --
◆前回号は?
「 借金NG の 法律 」 の 謎 とは?
「 借金は、NG 」 は、法律に書いてある?
その法律は、〇〇〇が、定めた?
その理由は、「 借金すると、〇〇できる 」 から?
つまり、借金NGの法律が、生まれた理由は、
「 財政の赤字の回避 」 ではなかった?
「 財政の破綻の回避 」 でもなかった?
実は、「 〇〇の回避 」 のためだった?
上記を、前回号で解説した。
-- 消費者 経済 総研 --
◆今回号は?
日本と世界は、
どうやって、お札を、発行したか?
どうやって、お札を、増やしたか?
お札の歴史を、見ると、
「 国の借金は、悪 」ではない事が、わかってくる。
お札を増やさないと、給料も増えない?
金本位制 とは、何か?
兌換・不換 とは、何か?
今回号は、これらを、解説していく。

- ■お札を 増やすのは、けしからん?
- 「純MMTで、政府がお札発行なんて、とんでもない」
「MMT的で、借金を増やすなんて、けしからん」
「純MMTだろうが、MMT的だろうが、
お金を増やすなんて、けしからん」
こう思う人も、いるだろう。
では、「 お札が増えるのは、悪なのか? 」
それは違う。 悪ではない。
お札が増えないと、給料が、増えないからだ。
この件は、後に、詳細を解説する。
その前に「お札の作り方・増やし方」の推移を見る。
先に、「お札の 作り方」の推移、
続いて「お札の 増やし方」の推移を、解説する。
「 お札の 作り方・増やし方 」 の歴史を見れば、
「 国の借金は、悪ではない 」 がわかる。
なので、ぜひ、お読み頂きたい。
また、お金の作り方・増やし方は、
読者の皆さんは、後述の①~⑤のどれを選ぶ?
もし自分が首相なら、と思って、お読み頂きたい。
お札が増えるのは、 悪ではない
お札 増えないと、給料 増えない自分が、総理大臣なら、
選ぶのは、〇〇?

- ■価値ない お札、価値ある お札?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆ゲームのお札では、買い物できない?
「人生ゲーム」は、タカラトミーが販売する。
50年以上の歴史がある人気ゲームだ。
人生ゲームでは、お金を払ったり、貰ったりする。
付属品に「ゲーム用のお札」が、付いている。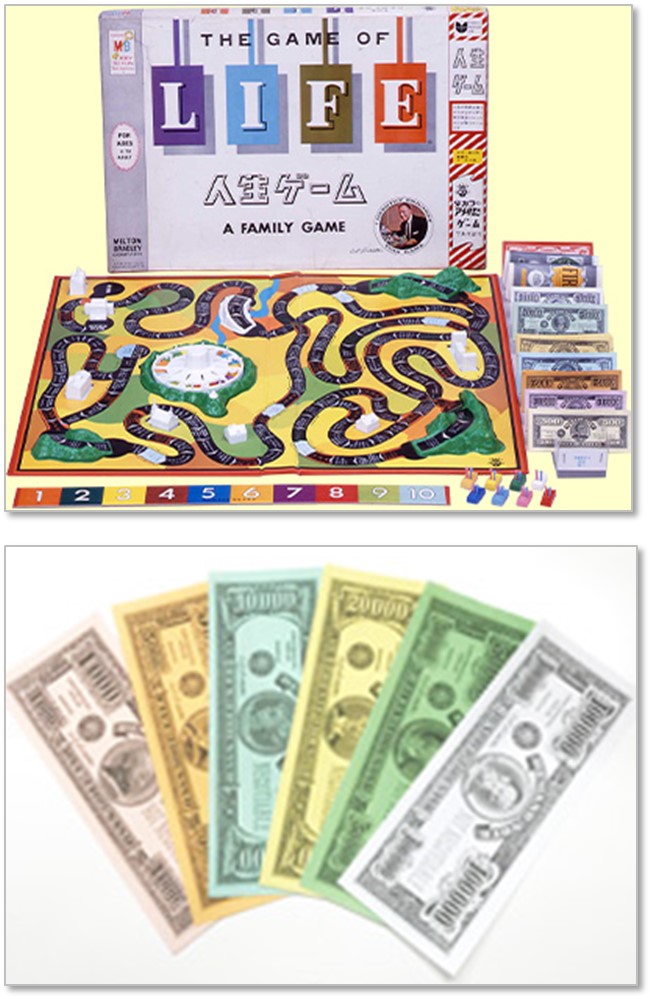 ※写真上:初代商品。写真下:現在のゲームお札
※写真上:初代商品。写真下:現在のゲームお札
※画像出典:商品情報|人生ゲーム|タカラトミー
「ゲーム用のお札」は、街中のお店で、使えるか?
当然だが、実際のお店での支払いには、使えない。
-- 消費者 経済 総研 --
◆日銀のお札で、買い物できる理由は?
一方で、「日銀が発行したお札」は、支払に使える。
・ゲームのお札は、使えない。
・日銀のお札は、使える。
この違い生まれる理由は、〇〇だ。
〇〇に何が、入るか、お考え頂きたい。
・ゲームお札で、買い物 できない
・日銀のお札で、買い物 できる
この違いの 理由は、〇〇?

- ■兌換と不換、金本位制 とは?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆ダカンと、フカン とは?
兌換(ダカン)と、不換(フカン) とは?
兌換(ダカン)は、交換できる事を、意味する。
不換(フカン)は、交換できない事を、意味する。
とことん
わかりやすい 経済解説
- 消費者 経済 総研 -
-- 消費者 経済 総研 --
◆兌換紙幣 とは?
では、なぜ、中央銀行のお札は、使えるのか?
中銀のお札に、「 価値 」を、与えたからだ。
どのような「価値」が、与えられたのか?
世界の歴史を、見ていく。
1816年から、イギリスのお札は、
「 金 (ゴールド) 」と、交換できる制度とした。
価値が高い金(ゴールド)と、
交換できるお札は、価値があるということ。
こうして、お札は、価値があるとなった。
金(ゴールド)と、交換できる紙幣を、
「 兌換 紙幣 」 ( だかん しへい )と言う。
-- 消費者 経済 総研 --
◆不換紙幣 とは?
ゴールドと、交換できる兌換紙幣は、価値がある。
つまり、兌換紙幣は、「単なる紙切れ」ではない。
一方、不換紙幣の方は、
「 単なる紙切れ 」とも言える。
不換紙幣は、金と、交換できないからだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆金本位制 とは?
お札が、金(ゴールド)と、交換できる制度を、
「 金本位制 」 と言う。
金本位制での紙幣は、兌換紙幣で、
非・金本位制での紙幣は、不換紙幣だ。
「兌換紙幣」 「不換紙幣」 「金本位制」 のコトバは、
これからも、登場するので、覚えて頂きたい。
「 兌換紙幣 」 とは 〇〇
「 不換紙幣 」 とは 〇〇
「 金本位制 」 とは 〇〇
あなたの わからない経済 を
わかる経済に 変える
- 消費者 経済 総研 -

- ■お札の供給・流通の歴史は?
- お札の供給・流通の歴史は、日本は、どうだったか?
明治以降の日本のお札の歴史を、解説していく。
-- 消費者 経済 総研 --
◆明治初期は、政府紙幣?
明治の初期は、日本政府が、自ら紙幣を発行した。
これは、金と交換できない「不換紙幣」だった。
この時は、日銀は、まだ誕生していなかった。
明治初期は、
政府が自ら、不換紙幣を、発行
-- 消費者 経済 総研 --
◆明治18年から、銀本位制?
上の政府紙幣の大量発行で、高インフレとなった。
この高インフレを、政府は反省した。
そこで、「 裏付けと制限のあるお札 」へ、変更した。
裏付けと制限のあるお札とは、「兌換紙幣」の事だ。
▼裏付け とは?
お札が、「単なる紙切れ」ではなく、
「価値の裏付け」が、ある紙にした。
「価値の裏付け」のために、「銀(シルバー)」を用いた。
「銀」と交換できる「兌換紙幣」を、
明治18年に、日銀が、発行を開始した。
銀を裏付けとした紙幣(銀兌換券)だ。
紙幣は、銀と交換できるから「価値あり」となった。
▼銀本位制 とは?
価値の裏付けは、「金」ではなく「銀」であった。
その理由は、何か?
当時の日本は、「金」が、不足していたからだ。
つまりこの時点の日本は、
「 金本位制 」 ではなく 「 銀本位制 」 だった。
▼制限 とは?
「 裏付けと、制限のあるお札 」と述べたが、
「 制限 」とは、何か?
この兌換紙幣は、銀と交換できる。
お札の発行量は、銀の獲得量までに制限される。
裏付け・制限のある「兌換紙幣」で
高インフレを回避
「銀本位制」の開始
-- 消費者 経済 総研 --
◆明治30年に、銀から金へ
明治30年に、銀本位制→金本位制へ、移行した。
銀兌換を、金兌換に、変更したのだ。
日清戦争後に、日本は、多額の賠償金を獲得した。
それによって、日本の金の保有量は、増えた。
日本は、金本位制を、開始できたのだ。
▼金本位制のメリットは?
金本位制に、変更した理由は、何か?
金本位制が、世界の標準で、便利だからだ。
輸出国Aと、輸入国Bが、貿易をした場合はどうか?
あるモノを、A国から、B国へ、売るとする。
▼B国のお札では不安?
支払の時に、
売主A国は、買主B国から、お札を受け取る。
「買主B国のお札」は、価値が、あるのか? 無いのか?
受け取る売主A国は、不安だ。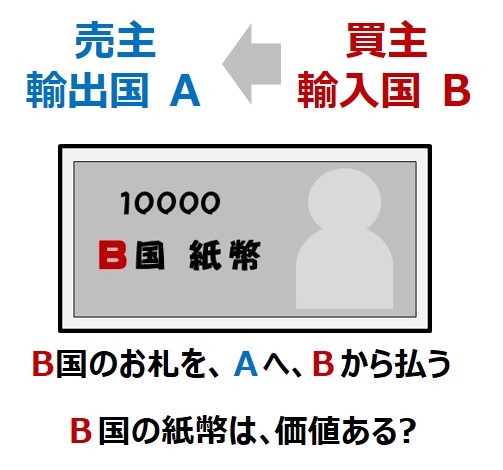
B国のお札がゴールドと、交換できるなら、安心だ。
貿易相手国が、金本位制なら、安心して貿易できる。
英国発の金本位制は、世界に広まっていく。
▼日本は?
日本も、金本位制の導入によって、
外国との貿易が、便利になった。
紙幣の裏付けは、「銀」から「金」になった。
紙幣は、金と交換できるから、価値がある。
銀 から 金 へ
海外貿易に、便利な「金本位制」へ
-- 消費者 経済 総研 --
◆大正3年(1914年)から、大量のお札が必要?
1914年に、第1次世界大戦が、発生した。
戦時では、平時よりも、遥かに多いお札が必要だ。
金本位制では、お札の量が、金の量に制限される。
制限があるから、お札を増やしにくい。
第1次世界大戦から、
世界各国は、金本位制のデメリットに、直面した。
制限ある金本位制は、不便
-- 消費者 経済 総研 --
◆昭和6年(1931年) 金本位制の停止へ
日本では、金本位制が、事実上、停止された。
金の裏付け無しで、紙幣を発行するようになった。
理由は、既述の通り、
「お札が、金の量に制約」では、不便だからだ。
日銀が発行するお札は、「不換紙幣」になった。
日本で、金本位制が、事実上、停止
-- 消費者 経済 総研 --
◆昭和17年(1942年) 金本位制の完全停止
前項の「事実上の停止」から「完全停止」になった。
「不換紙幣」の制度へ、法律も変え、完全移行した。
昭和17年、日本は「 兌換紙幣の 金本位制 」から、
「 不換紙幣の 非・金本位制 」に、完全に変わった。
日本で、金本位制が、完全停止
-- 消費者 経済 総研 --
◆世界各国は?
大戦が終わった後の平時でも、お札が必要だ。
経済発展で、お札への需要は、増える一方だ。
国によって、時期は違うが、
金本位制を、昭和の時代に、各国は終了した。
終了した理由は、既述の通り、金本位制では、
金の量に応じたお札しか、作れないからだ。
金と交換できる兌換紙幣による金本位制を、
世界各国も、続々と、やめていった。
1971年に、世界の金本位制は、終了した。
不便な金本位制は、世界で終了

- ■裏付けない 不換紙幣で 良いか?
- 既述の通り、「ゲーム用のお札」では、
実際の店での支払いは、できない。
中央銀行の発行であっても、
不換紙幣は、金銀の裏付けが、ないお札だ。
では、不換紙幣の支払いを、お店が、拒否できるか?
日本では、日銀発行のお札の受取りを、
お店は、拒否できない。
日銀発行のお札(日本銀行券)には、
強制通用力が、あるからだ。
*日本銀行法46条:
日本銀行が発行する銀行券(日本銀行券)は、
法貨として無制限に通用する。
*支払いに関する質問主意書・答弁書(参議院):
支払方法に関する事前の特別の合意がない場合
法貨の強制通用力により、現金での支払いも
有効であり、店側は受け取りを拒めない。
※出典:
・日本銀行法46条
・支払いに関する質問主意書:質問本文:参議院
・同上答弁書:答弁本文:参議院
日銀が発行した お札には、
法律で、強制通用力 がある

- ■日本のお金の増やし方は?
- 前項までは、「お札の 作り方」を、解説した。
ここからは、日本の「お札の増やし方」を解説する。
-- 消費者 経済 総研 --
◆明治初期の 政府紙幣 では?
日本政府の都合で、お札を増やしたのだ。
増やし方は、お札の印刷枚数を、増やすだけだ。
金銀の裏付けの無い「不換紙幣」を、増やした。
(だがその結果、高インフレ発生で、後にやめた)
・増やし方:印刷枚数を、増やす
・発 行 者 :政府
・制 約 : 政府の望む枚数まで
-- 消費者 経済 総研 --
◆明治18年からの 金銀本位制 では?
明治18年からの金・銀本位制の開始で、
金・銀と交換できる兌換紙幣になった。
裏付けとなる金銀の量に応じて、紙幣を増やした。
・増やし方: 裏付けの金銀を増やす
・発行者 : 日銀
・制 約 : 獲得した金銀の量まで
-- 消費者 経済 総研 --
◆太平洋戦争では、直接引き受け?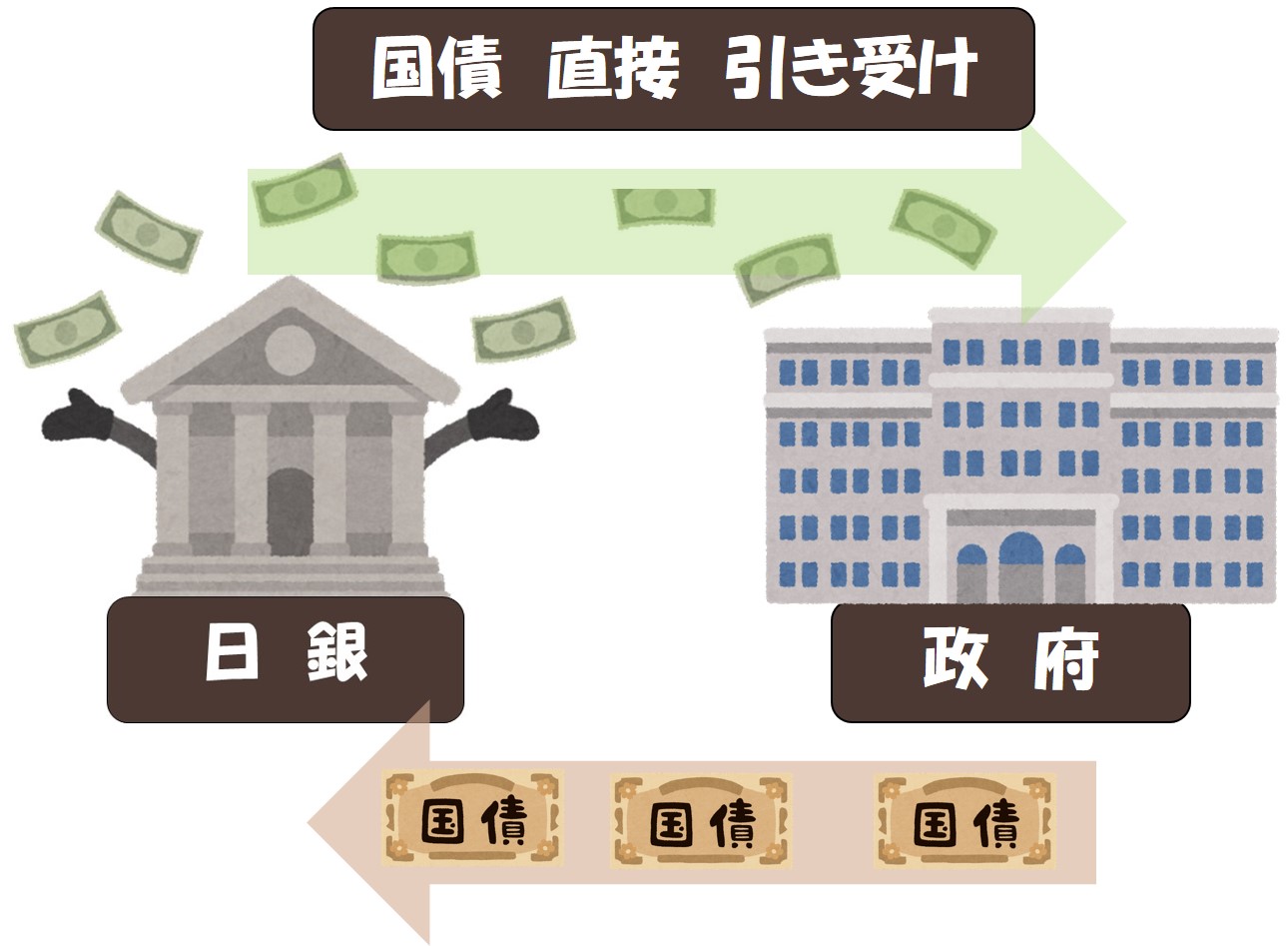
▼国債の大量発行+日銀の直接引受け
昭和6年に、日本は、兌換紙幣を、停止した。
その後、太平洋戦争の巨額の戦費のため、
日本政府は、莫大なお札を、必要とした。
そこで政府は、大量の国債を、販売した。
売買代金として、政府は巨額資金を、手に入れた。
国債の大半は、日銀が、直接に、引き受けをした。
政府が日銀へ、国債を、直接売ることは、
政府が日銀から、直接に借金する事を、意味する。
日銀は、国債を買うたびに、お札を政府へ渡す。
よって、金(ゴールド)の量の制約なしで、
日銀は、お札を大量に、供給したのだ。
お札の発行者は、政府ではなく、日銀だ。
増やし方は、国債の増発による。
・増やし方:
国債の増発 (国の借金が起点)
・発行者:日銀
・国 債:政府・日銀での 直接引受け
-- 消費者 経済 総研 --
◆現在は、間接引き受け?
昭和22年の財政法の登場で、
日銀からの直接の借金等は、原則禁止になった。
よって政府が発行する国債は、
「直接引受け」から「間接引受け」に、変更された。
直接:中継なしで、日銀が、政府から、直接引受け
間接:民間銀行等が中継し、日銀が、間接引受け
後者の「間接」の方が、煩雑だ。
煩雑であれば、お札を、簡単には増やせない。
よって、間接よりも、前者の「直接」の方が、
お札の供給に対し、ブレーキ効果がある。
直接引き受けの原則禁止を、GHQが法制化させた。
(詳細は、過去号を参照)
こうして、政府が国債を、販売する相手は、
日銀から、民間銀行等に、変わった。
「 間接 引受け 」では、下記手順による。
政府が、民間銀行等へ、国債を販売
↓
政府は、その販売代金を、手に入れる
↓
民間銀行等が、日銀へ国債を売却
↓
日銀の国債保有の額が、増えていく
現在の日本は、金本位制ではない。
よって、日銀発行のお札は、不換紙幣だ。
金本位制では、
金の量に応じて、お札の量が決まった。
現行制度では、お金の必要度に、応じて供給する。
つまり、政府や日銀の考えで、
マネーの供給量が決まる。
・お札の発行者:日銀
・増やし方:国債増発(国の借金増)
・国債:政府→民間銀行等→日銀
での間接引受け

- ■お金の増やし方 まとめ
- ▼① 政府紙幣
政府が望む量まで、お札を、自ら増刷
↓
▼② 銀本位制で、銀の兌換紙幣
日銀が、銀の量に応じて、お札を発行
↓
▼③ 金本位制で、金の兌換紙幣
日銀が、金の量に応じて、お札を発行
↓
▼④ 脱・金本位制で、不換紙幣
日銀が、増発国債の直接引受けで、お札を増刷
↓
▼⑤ 現在:国債を、間接引受け
日銀が、増発国債の間接引受けで、お札を増刷
-- 消費者 経済 総研 --
◆お札を増やさないと、給料増えない?
「MMT的で、借金を増やすなんて、けしからん」
「純MMTで、政府がお札発行なんて、とんでもない」
「純MMTだろうが、MMT的だろうが、
お金を増やすなんて、けしからん」
こう思う人も、いるだろう。
では、「 お札が増えるのは、悪なのか? 」
それは違う。 悪ではない。
お札が増えないと、給料が、増えないからだ。
先進諸国は、お金を増やしてきた。
各国とも「国の借金」は、給料を増やすツール?
これらを、次回号で、解説していきたい。
とことん
わかりやすい 経済解説
- 消費者 経済 総研 -あなたの わからない経済 を
わかる経済に 変える
- 消費者 経済 総研 -

- ■MMT-11| 高圧経済15| 爆上げVol.19
- 2022年 10月 29日 (土) に 新規投稿
Vol.19 (第2部の高圧経済の15回目)
MMT-11:借金増えないと、給料が〇〇に?
-- 消費者 経済 総研 --
◆積極財政で、高圧経済へ?
「 連載シリーズ|ニッポン 爆上げ 作戦 」
の第2部は、「 景気 UP 編 」だ。
「 積極財政 」 で、「 高圧経済 」 を実現し、
日本の長い低迷から、脱出へ。
このテーマを、現在、継続中。
-- 消費者 経済 総研 --
◆前回号は?
日本と世界は、
どうやって、お札を、「発行した」のか?
どうやって、お札を、「増やした」のか?
お札の歴史 とは?
金本位制 とは、何か?
兌換・不換 とは、何か?
上記を、前回号で解説した。
-- 消費者 経済 総研 --
◆今回号は?
純MMTでも、MMT的でも、お金を増やす。
そもそも、「お金を増やす必要」は、あるのか?
お札が増えないと、給料が〇〇に なる?
〇〇に、何が入るか?お考え頂きたい。
今回号は、これらを、解説していきたい。

- ■お札 増えないと、〇〇が増えない?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆お札が増えるのは、けしからん?
「MMT的で、借金増やすなんて、けしからん」
「純MMTで、政府がお札発行なんて、とんでもない」
「純MMTだろうが、MMT的だろうが、
お金を増やすなんて、けしからん」
こう思う人も、いるだろう。
では、「 お札が、増えるのは、 悪なのか? 」
それは違う。 悪ではない。
お札が増えないと、「 給料 増やせない 」からだ。
お札が増えないと、
給料 増やせない
-- 消費者 経済 総研 --
◆昭和の給料は、現金(お札)を、手渡し?
昭和は、サラリーマンの給料は、現金渡しだった。
現金を、封筒に入れて、社員に手渡しした。
芸能人の報酬も、現金の手渡しだった。
山田邦子は、昭和の人気タレントだ。
人気絶頂期は、
買い物袋2つに、大量の1万円札が、あったと言う。
なお有吉弘行や、指原莉乃も所属する太田プロは、
最近まで(コロナ前まで)、現金渡しだった。
※出典:太田プロの給料は最近まで手渡し|
伝説は山田邦子..スポニチSponichi Annex
-- 消費者 経済 総研 --
◆お札が、増えないと、給料が払えない?
ここでは、理解のしやすさから、まずは、
「 給料は、お札の手渡しで、貰う 」として説明する。
日本の大卒の初任給(月給)は、どう推移したか?
・1965年(昭和40年)は、約2.3万円
↓
・2021年(令和3年)は、約23万円だ。
つまり、56年間で給料は、10倍に、上昇したのだ。
なおラーメンは、同56年で、9倍上昇(60円→540円)
※出典:明治~令和 値段史
給料が10倍に、増えたのに、
お札の量が、増えなかったら、どうなるか?
お札不足で、適正な給料が、払えない。
経済の拡大に応じて、
お札の量も、増やす必要が、あるのだ。
これは、日本のみならず、他国でも同じだ。
お札を増やすのは、悪でも何でもない。
お札を増やす必要性が、あるから、そうするのだ。
時代と共に、お札の量が増えるのは、当然の事だ。
お札の量が増えないと、
給料UPしても、お札不足で、払えないとなる。
お札の量が増えないと、
給料UPしても、
お札不足で、払えない
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本のお札は、どれだけ増えた?
下図は、日本のお札(紙幣)の量の推移だ。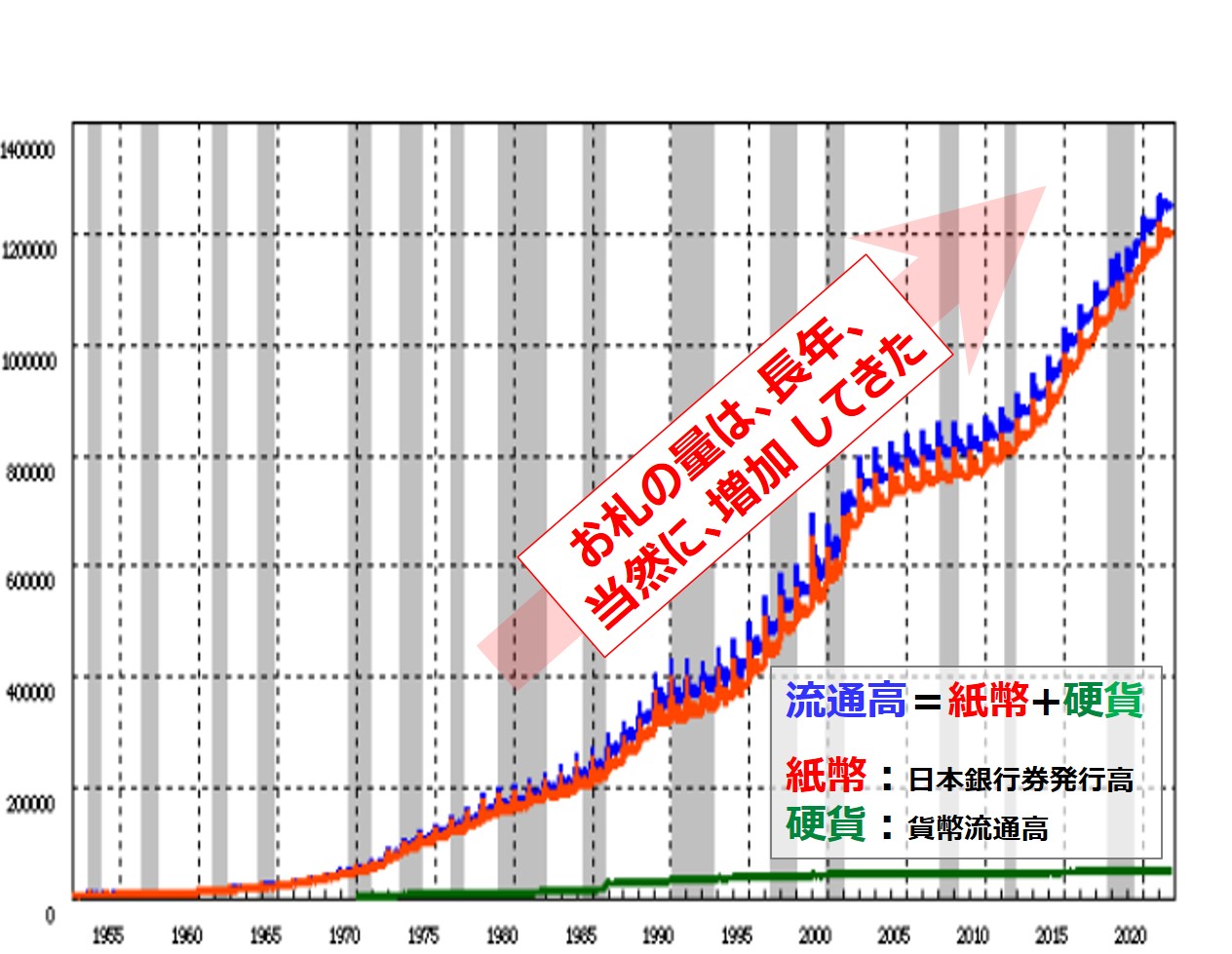 ※出典: 統計別検索|日本銀行
※出典: 統計別検索|日本銀行

- ■ 通貨には、「預金」もある?
- わかりやすさのため、
ここまでは、給料を「お札」で、受取るとしてきた。
お金 (通貨) は、
「 お札 」 の他に、「 硬貨 」と「 預金 」もある。
とことん
わかりやすい 経済解説
- 消費者 経済 総研 -
-- 消費者 経済 総研 --
◆法律では?
法律では、「お金」=「お札」+「コイン」だ。
次の条文での
「 銀行券 」 は お札、 「 貨幣 」 は コイン のこと。
「..通貨とは、貨幣及び日本銀行法..の規定により
日本銀行が発行する銀行券をいう。」
このように、通貨法 第2条 ※に、定義されている。
※通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第2条
※..は詳細箇所。 以下同じ
▼本連載での表記は?
なじみのある言葉の方が、わかりやすい。
よって、本連載では、下記の表記としてきた。
「 通貨 」を、 お金
「 貨幣 」を、 コイン 又は 硬貨
「 日本銀行が発行する銀行券 」を、 お札 又は 紙幣
-- 消費者 経済 総研 --
◆経済学では?
経済学では、
「 通貨 」 = 「 紙幣 」+「 硬貨 」+「 預金 」だ。
経済学では、
通貨 = 紙幣 + 硬貨 + 預金
-- 消費者 経済 総研 --
◆「 預金 」 の重要性が、高まった?
昭和の時代は、「現金」でのやり取りが、多かった。
例えば、下記のような、やり取りだ。
給料を、毎月25日に、現金手渡しで、受け取る
家賃を、毎月27日に、現金手渡しで、大家に渡す
しかし徐々に、現金渡しは、減っていった。
給料の支払いは、振込みに、変わっていた。
会社の預金口座から、社員の預金口座への振込だ。
家賃も、振込みや、引き落としに、変わっていった。
こうして、「現金のお札」が、移動するのではなく、
「デジタルデータ」が、移動して行った。
Aさんが、現金を、Bさんに、手渡し
↓
預金口座Aから、預金口座Bへ、振り込み
預金通帳に、印字された数値も、お金である。
この印字されたお金を、経済学では「預金」という。
経済学では、
「通貨」=「紙幣」+「硬貨」 に加え +「預金」なのだ。
法律では、通貨=紙幣+硬貨
経済学は、通貨=紙幣+硬貨+預金
こうして日銀が供給するお金の内訳も、変化した。
「お札」よりも、「預金」の割合が、高まっていった。
2012年7月まで「 預金の量 < お札の量 」で、
2013年8月から「 預金の量 > お札の量 」だ。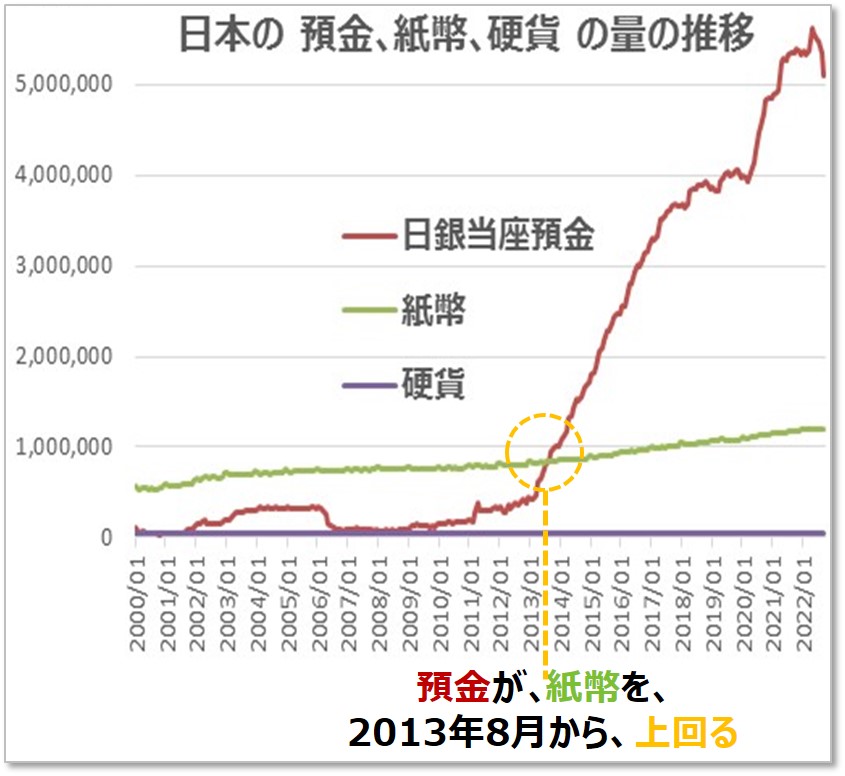
※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成
※出典:マネタリーベース|日本銀行
-- 消費者 経済 総研 --
◆なぜ、「お札」を中心に、解説してきたか?
再掲するが、わかりやすさのために、
「お札で、やり取り」を中心に、表現してきた。
早い段階で、「預金」の話をすると、
混乱させてしまうことが、あるからだ。
「通貨を発行する」と言うと、ピンと来ない。
だが、「お札を刷る」なら、イメージが湧きやすい。
-- 消費者 経済 総研 --
◆今後の表記は?
これからは、「お札不足で、給料払えない」は、
「通貨(お金)不足で、給料払えない」と読み替える。
また、「お札を、刷る」を
「通貨(お金)を、発行する」として、表記していく。
あなたの
わからない経済 を
わかる経済に 変える
- 消費者 経済 総研 -

- ■国の借金は、お金を 増やす方法?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆お金の 供給と流通 の仕組み とは?
本連載では、純MMT・MMT的理論を解説してきた。
MMT的では、
国の借金を起点に、通貨(お金)を、供給・流通させる。
純MMTでは、
政府が、通貨を発行し、世の中に供給・流通させる。
純MMTでも、MMT的でも、
通貨を、世の中に、流通させるシステムでもある。
MMTは、
お金の 供給・流通の システム
-- 消費者 経済 総研 --
◆借金起点での、お金の増やし方
▼①借金で、政府のお金を、増やす
国の借金は、大半が、国債の発行による
↓
国債の販売額を、仮に、2兆円とする
↓
政府が、国債(2兆円)を、民間の銀行等へ、販売する
↓
政府は、その販売代金(2兆円)を、手に入れる
↓
これで、政府のお金は、2兆円増えた
▼② 2兆円は、政府から、民間セクターへ、移動
この2兆円を、政府は、民間のために使う
↓
2兆円の公共事業等を、政府→民間企業へ発注する
↓
受注により、民間セクターのお金は、2兆円増加
↓
民間セクターの増えたお金は、給料にも使われる
▼③ 民間の銀行等は、政府と日銀の中継役
①で登場した民間銀行等は、どうする?
↓
民間銀行等は、買った国債(2兆円)を、日銀へ売る
↓
これで民間銀行等は、国債を、買って売って手放す
↓
民間銀行等は、国債の政府・日銀の中継役を終える
▼④ 最終的に、受け皿の日銀に、国債がたまる
最終的に、国債(2兆円)は、日銀が保有する
↓
この流れを繰り返すことで、民間のお金は増える
※わかりやすさのため、国債価格は、2兆円で固定とした
※注:民間銀行等の中継役について
国債売買の中継は、民間銀行等の義務ではない。
民間銀行等は、国債を買う義務もなく、
買った国債を日銀に売る義務もない(プライマリーD除く)
民間銀行等は、経済合理性(損得)で、売買をする。
-- 消費者 経済 総研 --
◆借金起点で、お金を増やすのは、日本だけ?
国の借金を、起点に、お金を、増やす。
このやり方は、日本だけか?
違う。 先進国で、大枠では、共通の仕組みだ。
現在は、日本を始め、先進国は、
中央銀行の国債の間接引受けを、採用している。
※出典:日本銀行が国債の引受けを行わないのはなぜですか|日本銀行
今の お金の 増やし方は、
中央銀行の 国債の 間接引受け
それは、日本も、先進国も同じ
-- 消費者 経済 総研 --
◆お金の増加と、借金の増加は?
▼マネタリーベースとは?
中央銀行が、供給するお金を、
「 マネタリー ベース 」 という。
マネタリー ベースは、下記3つの合計だ。
日本銀行券発行高 + 貨幣流通高 +日銀当座預金
つまり、お札+硬貨+預金である。
※出典:「マネタリーベース」とは何ですか?|日本銀行
▼日本と米国の マネタリーベースの 推移は?
日本よりも米国の方が、お金を増やしている。
下図は、お金の発行量の日米推移だ。(2005年を100)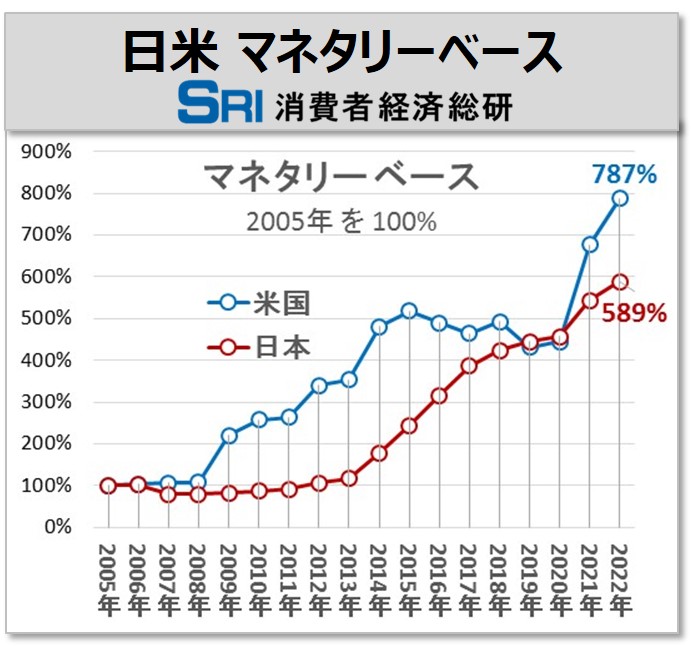
※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成
※出典:Monetary Base; Total (BOGMBASE) | FRED | St. Louis Fed
※出典:マネタリーベース|日本銀行
▼日本と米国の 借金の残高は?
借金の増加は、けしからん なら、
日本より、米国の方が、
けしからん?
日本よりも米国の方が、国の借金を増やしている。
下図は、国の借金の日米推移だ。(2005年を100) 米国は、借金の大幅増で、お金を増やしてきた。
米国は、借金の大幅増で、お金を増やしてきた。※上のグラフの対象は、Liabilities(IPSGS(年金等)を除く)
※下記出典から「 消費者 経済 総研 」がグラフ作成
※出典 :IMF | Balance Sheet-IMF Data
日本の借金増加は、少ないのだ。
日米ともに、
借金増やして、お金増やした
違うのは、
米国の方が、徹底している点

- ■借金は、悪ではなく、有益ツール?
- -- 消費者 経済 総研 --
◆クレカは、借金だから、けしからん?
日本でも、キャッシュレス比率が、増えてきた。
「クレジットカードは、借金だから、
人前で使ってるのを、見せるな。 恥ずかしい。」
だいぶ前だが、こう言う人がいて驚いた事がある。
クレジットカード(クレカ)は、
〇〇ペイや、交通系ICカードと同じく、
キャッシュレスのツールで、使われる。
A:クレカは、キャッシュレスの有益なツール
B:クレカは、借金だから、けしからん
Aの有益性を無視して、
Bのけしからんと、される事がある。
クレカは、有益なツール
しかし、借金なので、けしからん?
-- 消費者 経済 総研 --
◆けしからん では、無く、有益なツール?
「 国の借金は、けしからん 」 ではない。
借金は、
「通貨の発行+流通」のシステムも担っているのだ。
借金は、通貨の発行・流通の有益なツールなのだ。
「借金けしからん」と言うのは、筋違いなのだ。
政府が国債を発行することは、
国が借金することだ。
日本の国の借金の84%が、国債発行の方法による。
※詳細は過去号「日本の借金の範囲・定義」を参照
A:国債は、
通貨の発行・流通のための必要・有益な金融証書
B:国債は、
国の借金で、けしからんもの
日本では、後者Bの視点で、批判されることがある。
「ギャンブル三昧で、借金まみれは、けしからん」
と同じような視点で、国債が非難される。
クレカは、キャッシュレスの有益なツールだった。
国債はお金の発行・流通のための有益なツールだ。
「 有益なツール 」 として見るべきものを、
「 けしからん借金 」 と見るべきではない。
国債の増発は、
お金を増やす 有益なツール
けしからんは、筋違い
-- 消費者 経済 総研 --
◆給料UPには、お金の増加が必要?
国の借金を、増やすことで、
増える通貨へのニーズに応え、供給・流通させる。
「 借金がNG 」 だと、どうなる?
給料がUPしても、お金が足りないから、払えない。
国債増発(借金増加)で、
増加する給料のためのお金を、供給・流通する。
国債増発 (借金増加) で、
給料UPの お金を、供給・流通
-- 消費者 経済 総研 --
◆お金の増やし方 まとめ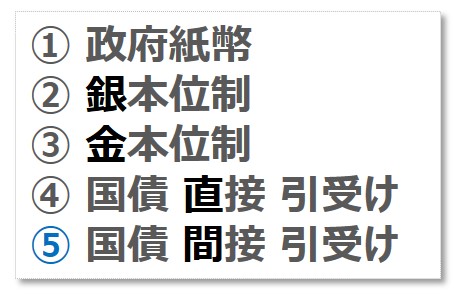
▼① 政府紙幣
政府が望む量まで、お札を、自ら増刷
↓
▼② 銀本位制で、銀の兌換紙幣
日銀が、銀の量に応じて、お札を発行
↓
▼③ 金本位制で、金の兌換紙幣
日銀が、金の量に応じて、お札を発行
↓
▼④ 脱・金本位制で、不換紙幣
日銀が、増発国債の直接引受けで、お札を増刷
↓
▼⑤現在:国債を、間接引受け
日銀が、増発国債の間接引受けで、お札を増刷
日本も先進国も、現在は、⑤を採用している。
日本は、特別ではない
先進国も、同じ方法⑤を、採用中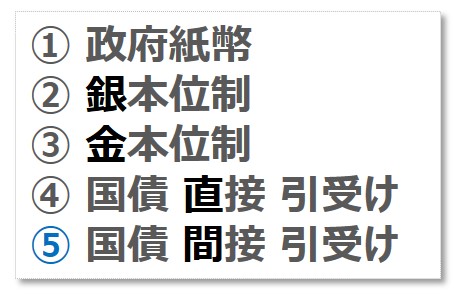

- ■ お金の増やし方は、どれがいい?
-
⑤の「国債 間接 引受」はダメと、批判する場合は、
借金 けしからん なら、
別の選択肢の 提示が 必要
⑤以外の選択肢を、対案として、提示すべきだ。
では、⑤以外の①~④の4つのうち、どれが候補か?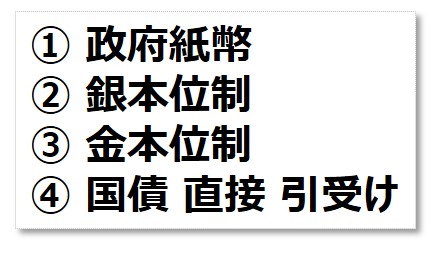
②③の金銀本位制は、
再度、選択することは、無い。
選択しない理由は、何か?
給料が10倍になったら、お札も10倍必要だ。
お札を10倍に増やすには、
10倍の量のゴールドを、採掘・獲得の必要がある。
それは、現実的ではない。
よって、日本も世界も、再度、選択することは無い。
よって残った候補は、②③を除く、下記の①④だ。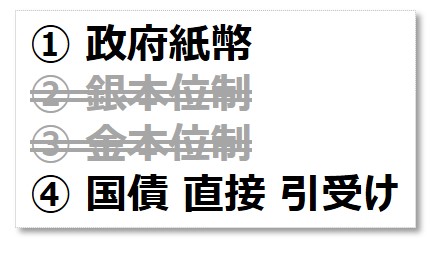
① 政府紙幣の発行
④ 国債増発を、日銀が直接引受け
①と④を、MMTの視点で、見ると、
①は、純MMTで、④は、MMT的だ。
「借金起点」なのは、④も、「現行の⑤」も、同じだ。
借金けしからんなら、④も⑤も、候補にならない。
(④と⑤の違いは、④が直接引受、⑤が間接引受)
よって、残る選択肢は、①の純MMT だけとなる。
▼現行制度⑤と、残った候補①の どちらが良い?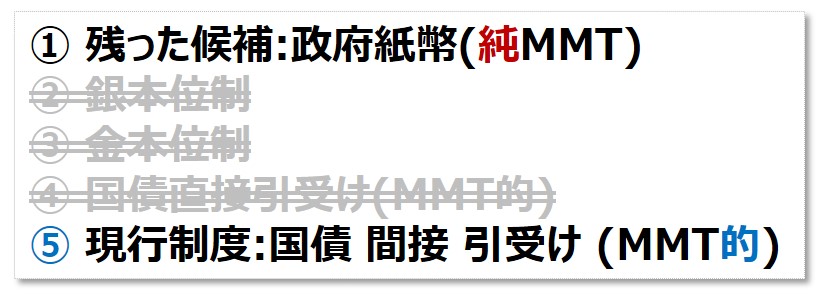
① 政府が、紙幣を発行 (純MMT)
⑤ 国債増発を、日銀が間接引受け (MMT的)
過去号で解説の通り、制度の変更は、大変だ。
よって日本は「 現行の⑤MMT的 のまま 」 でよい。
-- 消費者 経済 総研 --
◆借金は、けしからん ではない
①~⑤の中で、日本は、⑤を採用している。
繰り返しの内容になるが、重要なので、再掲する。
「国の借金増加」を、起点としての、
お金の供給・流通のシステムを、採用している。
既述の通り、給料が、10倍になったら、
お金の量も、10倍必要だ。
そのお金を増やす、システムの起点が、
「 国の借金の増加 」 なのだ。
国の借金は、下記の、システムなのだ。
「 通貨発行 通貨供給 信用創造 」
増えた給料等に、使う通貨を、発行・供給するのだ。
「国の借金増加、けしからん」と言うなら、どうなる?
借金増加が反対なら、給料増加も反対すればよい。
日本が好景気になり、給料UP傾向になっても、
「 給料 増やすな! 」と、言えばよい。
借金増加が、反対なら、
給料UPも、反対すれば よい
-- 消費者 経済 総研 --
◆お札の増やし方の歴史
日本の「お札の増やし方」の歴史を、見てきた。
明治時代以降、約150年間で、
日本は、①→②→③→④→⑤を経験してきた。
①のデメリットを解消すべく、②に変わった
②のデメリットを解消すべく、③に変わった
③のデメリットを解消すべく、④に変わった
④のデメリットを解消すべく、⑤に変わった
約150年で、①~⑤の、5つの方法があった。
日本を始め先進諸国は、最適な⑤を選択している。
⑤は国の借金を起点とした、中銀の間接引き受け
⑤を批判するならば、
①~⑤以外の新しい対案を、提示すべきだ。
では今後、より優れた
通貨の供給・流通の仕組みは、生まれるか?
実は、それが 「 純MMT 」 だったのだ。
現在の日銀の国債の間接引受けは、
中継役の民間銀行等を挟み、煩雑な仕組みだ。
お金の供給・流通量は、
政府が、大方針を定め、 日銀が、具体化する。
政府・日銀が、お金の量を決めるなら、
「政府が自ら、お金を、発行すればよい」と気づく。
ここに着目したのが、純MMTだったのだ。
純MMTは、借金を起点としないので、
「借金は悪」の誤った意見を、招かない利点もある。
だが、既述の通り、制度変更は時間がかかる。
よって、現制度のまま、積極財政の強化で、
高圧経済を、早期に実現すべきだ。
新たな選択肢は、純MMT
だが、MMT的のままで、
積極財政の強化→高圧経済でよい- ◆本ページを、リンク等で広めて、頂きたい
- 日本には、将来に不安を、持つ方も多い
↓
「 借金は、将来世代へ、付け回し される 」
「 日本の将来は、借金で、破綻する 」
↓
このように、言われたからだ
↓
既述の通り、日本の国の借金は、問題ない
↓
過度な不安を、持たなくて良い。 楽観してよい
↓
将来不安に、おびえると、日本は、一層低迷する
↓
若者が夢や希望を、持たなく なってしまう
↓
明るい未来のために、本ページを、広めて欲しい
↓
本ページへのリンク設定の協力を、お願いしたい
松田からのお願いです。リンクをお願いします 消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸
消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸

- ■ 25年 7月 12日 (土)
国債(借金)増えても 金利UPしない?
◆連載シリーズ | 誤解・誤報・誤理解 を 正す
消費者 経済 総研 の様々な連載シリーズの中に、
「連載シリーズ|誤解・誤報・誤理解 を正す」もある。
国債 ( 借金 ) の誤解や、日銀の金融政策の誤解、
消費税の利点・欠点や、 消費税の使い道の誤解など、
様々な切り口で、解説してきた。
今回号は、下記だ。
国債 ( 借金 ) が、デフォルトしなくても、
金利が、上昇して、困る?
日本の格付けが、下げられて、
金利が上昇して、国債が急落する?
↓
結論は、いずれも違う。
この件は、本項の後半に、解説してある。
-- 消費者 経済 総研 --
◆参院選の 争点 は?
参議院選挙が近い。
参院選での、最大の争点は、下記だ。
「 消費税の減税か? 給付金か? 」
自民・公明のみが、
消費減税ではなく、給付金を主張する。
なお給付金は、1回きりの給付だ。
自・公以外の、8党は、消費減税を、主張する。
減税期間は、政党によって異なるが、
1年〜2年や、恒久措置だ。
既述の通り、給付金は1回きり。
だが消費税の減税は、継続的な措置だ。
自民党は、下記と言う。
「消費税減税は、財源論を伴わないので、無責任だ」
これは、序盤戦の論戦で、出てきた話だ。
最近では、すでに各政党が、
減税にせよ給付金にせよ、財源論を提示している。
-- 消費者 経済 総研 --
◆財源は?
政党で違うが、財源は、下記等が、提示されている。
赤字国債の増発
大企業・富裕層への課税強化
直近の、税収上振れ分を、活用
今後の、自然増収 (経済成長での税収増)
積立金や、剰余金を、活用
歳出の削減 ( 防衛費、歳出改革・行政改革 )
-- 消費者 経済 総研 --
◆メディアでは?
参院選が近いので、私(松田)は、
情報系・報道系のTV番組を、いつもより多めに見た。
TVでは、
争点の消費減税に関して、批判的コメントも多い。
政党では、
10党のうち、消費減税を否定するのは、自・公だけ。
という事は、
メディアは、自民・公明の、応援団なのか?
財源や、国債( 借金 )の増加、金利の上昇懸念などで
消費税の減税が、批判される。
この批判は、
1つのTV番組ではなく、様々な番組で見た。
今回号は、
消費減税に関する「 誤解を 正す 」 視点で解説する。
特に、下記に重点を置く。
「 金利の上昇の リスクあり は 間違い 」
-- 消費者 経済 総研 --
◆赤字国債とは?
・国の収入
・国の支出
前者が、大きければ、 国は、財政黒字だ。
後者が、大きければ、 国は、財政赤字だ。
★ここで、あなたに、問いかけ
赤字の場合は、どうするか?
あなたは、1分間、考えて頂きたい。
↓
赤字を補填する、財源が必要だ。
国は、借金をして、赤字を、まかなう。
赤字で借金、つまり、「 赤字国債 」を発行する、
と言うことだ。
★では、財政の赤字は、けしからんのか?
赤字を補填する国債は、けしからんのか?
↓
どちらも、けしからん ではない。
日本だけでの問題ではない。
★では、他国では、どうか?
↓
先進7カ国は、
大半の年、大半の国で、財政は赤字だ。
よって、各国は、赤字国債を、発行している。
日本だけでは、無いのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆国債は 通貨発行の 機能
日本も、世界中の国も、
ほぼ毎年、お札の量を、増やし続けている。
★ここで、あなたに、問いかけ
お札の量が、増え続けるのは、なぜか?
あなたは、1分間、考えて頂きたい。
↓
経済の発展と共に、使うお金の量は、増えるからだ。
日本は、賃金が、低迷している。
その日本でさえ、56年間で、賃金は、10倍に伸びた。
★日本の大卒の 初任給(月給)は どう推移したか?
↓
・1965年(昭和40年)は、 約2.3万円
↓
・2021年(令和3年)は、 約23万円だ。
つまり、56年間で給料は、10倍に、上昇したのだ。
なおラーメンは、同56年で、9倍上昇(60円→540円)
※出典:明治~令和 値段史
★賃金が、10倍になったら、
お金の量は、どのくらい必要か?
↓
お金の量も、10倍、必要だ。
そうしないと、給料を、支払えない。
★お金を 発行する際の 手続きは?
↓
国債を、中央銀行が、受け入れて、
その対価として、お札を、提供する。
その流れは、下記だ。
民間の金融機関は、国債を、持っている。
↓
その国債を、中央銀行に、売却する。
↓
中銀は、国債を手に入れ、
民間は、売却代金の現金を、手に入れる
★昔から、この手続き、だったのか?
↓
違う。
通貨発行のための、交換ツールは、
以前は、「 国債 」 ではなかった。
国債ではなく、「 金 (ゴールド) 」 だった。
これは、学校で教わったが、金本位制という。
ゴールドを、中央銀行が、受け入れて、
その対価として、お札を、提供する。
★10倍に、増えた賃金を、払うために、
10倍のお金が、必要だと、言った。
では、ゴールドの量は、どれだけ必要か?
↓
10倍のお金を、供給するためには、
ゴールドの量も、10倍必要だ。
しかし、
そんなに多くのゴールドを、採掘するのは、無理だ。
そこで、1930年代から、
金本位制・金兌換制度を、各国は、やめてしまった。
通貨発行のツールは、現在は、
ゴールド、ではなく、国債だ。
国債は、
通貨発行のツールで、
通貨発行の機能
これを、知らない人や、理解できない人は、
意外と多い。
-- 消費者 経済 総研 --
◆赤字国債への 各政党の 考えは?
国民民主党は、消費減税の財源を、下記と述べた。
「 堂々と、赤字国債を、発行すれば良い 」
★その他の政党では、どうか?
↓
国民民主以外に、参政、れいわ は、
国債の増発も、財源として、主張する。
つまり、あなたのお金を、増やす政党だ。
これらの政党は、積極財政を、主張する。
★他の政党は、どうか?
↓
維新、公明、共産は、
部分的な国債の活用を、以前から主張していた。
自民と、連立を組む公明党は、
今年の序盤では、「赤字国債も 検討」 と言っていた。
だが、自・公の連立政権であるが故に、
自民党に、すり合わせをし、それは消滅した。
-- 消費者 経済 総研 --
◆破綻する?
国債は、国の借金だ。
借金まみれで、国は破綻するのか?
↓
過去号で、様々既述の通り、借金増えても問題ない。
★その理由は何か?
↓
これも、くどいようだが、下記である。
「 日・米など先進国の 自国通貨建て国債の
デフォルトは 考えられない。 」
これは、経済評論家のコメントではない。
日本国政府の財政当局の公式見解である。
まとめると下記である。
・日米等自国通貨建て国債のデフォルトは考え難い
・国の借金? お札刷って返せばいい。 簡単だろ?
前者は、日本国政府の財政当局の公式見解だ。
後者は、財務大臣時の、麻生太郎氏の解説だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆米国では どうか?
米国では、国の赤字・借金を、どう捉えているか?
▼米国の 中央銀行 では?
★米国の中央銀行・FRBは、何と言ったか?
↓
FRBの元議長のグリーン・スパン氏は、下記と解説。
「 米国は、いつでも、お金を印刷できるので、
負債を、支払うことが、できる。
よって、デフォルトの確率は、ゼロだ 」
▼米国の 政府は?
大統領・首席経済顧問のバーンスタイン氏は、
「 米国は、自分で、お金を印刷できるので、
破産する事は無い。 」
▼米国の 経済学者は?
米国のニューヨーク市立大学の、ケルトン教授は、
経済学の学問として、下記のように整理済みだ。
「 財政赤字も、赤字国債も、問題ない 」
▼米国の 経済学会 では?
ケルトン教授の、1人だけではない。
複数の学者への調査でも、同様の結果となった。
全米経済学会も、財政赤字OKと、整理している。
これも過去号で、既述の通りだが、下記の出典だ。
※出典:Geide-Stevenson and Para Prez 2021
-- 消費者 経済 総研 --
◆でも 金利は アップする?
★ここで、あなたに、問いかけ
国債(借金) の 増加で、
金利は、上がってしまう のか?
あなたは、1分間、考えて頂きたい。
↓
ほぼ、反応しない。
★では、金利の水準を、決めるのは、何か?
↓
中央銀行による政策金利だ。
国債(借金)の量ではない。
★米国の金利を 決めるのは 何か?
↓
米国の市場金利は、FF金利によって、決定される。
FF金利とは、
米国の中央銀行・FRBが、政策決定した金利である。
市場金利と、FF金利は、高い相関関係にある。
下図の通り、相関係数は、0.99で、ほぼ完全相関だ。
★日本の金利を 決めるのは 何か?
↓
日本の中央銀行である、日銀の政策金利で、決まる。
下図の通りだ。
相関係数は、0.95で、極めて高い。
日本は、マイナス金利政策の、時期が長かった。
また、政策金利の、上げ・下げの回数も、まだ少ない。
よって、米国と比べると、連動性は少し下がるが、
相関係数0.95と、極めて高い、相関関係にある。
-- 消費者 経済 総研 --
◆国債 格付け は?
★国債 (借金) の増加で、格付けが、下がるのか?
↓
実際に、格付けが、下がる事はある。
★では、格付けの低下で、金利は上昇するか?
↓
スタンダード&プアーズ社(S&P)が、
2015年9月中旬に、日本国債の格付けを、下げた。
格下げの理由は、財政赤字・政府債務の増加だった。
しかし、市場は、ほとんど反応しなかった。
一時は、下図の通り、若干の反応があった。
しかし、短期間で、元の水準に、戻った。
その後は、上がるどころか、さらに低下した。
格付けの、金利への影響度は、
とても低い
格付けの引下げは、
ほぼ、無視されているのだ
★無視する理由は、なぜか?
↓
市場参加者は、皆が、下記だと、知っているからだ。
「 金利を決める、主たる決定要因は、
財政赤字や、赤字国債ではない。
日銀の政策金利だ。 」
▼ドイツは どうか?
ドイツの国債の、格付けは、高い。
ランクは、世界最高水準の、AAA (トリプルA) だ。
日本は、 A+ ( シングルA+ ) だ。
★では、日本は、低い格付なので、高金利か?
ドイツは、高い格付なので、低金利か?
↓
違う。
日本よりも、ドイツの方が、金利が高い。
ドイツ 1.9%> 日本 0.8%
※25/7/12時点の2年債券利回り
★ドイツが、高い格付けなら、金利は低いはずだ。
日本が、低い格付けなら、金利は高いはずだ。
なぜ、日本は、ドイツより、金利が低いのか?
↓
格付けではなく、中央銀行の政策金利で決まるからだ。
デフォルト・リスクを示す格付けは、重要ではない。
★デフォルト・リスクを、示す格付けが、
重要ではないのは、なぜか?
↓
日米の自国通貨建て国債の、デフォルトは考え難い
国の借金? お札刷って返せばいい。 簡単だろ?
格付けは、民間企業の 借金(社債)に、主に使われる。
民間企業は、お金を、刷って、増やせないからだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆日本は お札 刷れる?
お札刷って 返せばいい 簡単だろ?
この元財務大臣の発言は、正確には、
「 お札刷って 」 ではなく「 お金刷って 」 だ。
★そもそも 「 お金 」 とは 何か?
↓
お金 = 通貨 だ。
通貨 = 紙幣 又は 硬貨 だ。
紙幣とは、1万円札などの、紙のお金だ。
硬貨とは、500円玉のような、コインのお金だ。
★紙幣や硬貨は どこが 発行するのか?
↓
日銀が発行すると、思っている人も、多いだろう。
だが、それは違う。 下記の通りだ。
紙幣の 発行主体:日本銀行
硬貨の 発行主体:日本国政府
これも過去号で、解説済みだ。
別ページで解説中だ。 そのページを読んで欲しい。
本稿の最下段に、URLリンクがある。
お金刷って返せば良いとは、
日本国政府が、硬貨を発行し、返済すると言う事だ。
なお、日銀が発行する、紙幣の単位の上限は、
ご存知の通り、1万円札だ。
日本国政府が発行する、硬貨の最高単元は、
今までの所では、10万円の硬貨だ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆盛り上がって みよう
私(松田)は、しばしば、言っているが、
昭和世代なので、テレビ世代だ。
なので昔から、テレビが好きだ。
オレたちひょうきん族 など、
たまらないほど、面白いテレビ番組があった。
お笑いや、バラエティー系以外では、
下記が、好きだった。
ワールド・プロレスリング
(テレビ朝日の 新日本プロレスの 番組)
プロレスは、テレビに、マッチすると、思っている。
大好きで、毎週、楽しみにしていた。
だが、プロレスでは、
正統派 vs 正統派 のバトル では、いまいちだ。
よって、悪役である、ヒール役の登場は、重要だ。
ヒール役のプロレスラーとは、
アブドーラザ・ブッチャーやタイガー・ジェットシン等
ブッチャーや、シンの登場で、
プロレス会場は、一気に「 ヒート・アップ 」 する。
ヒールの登場で ヒート・アップ する
トランプ大統領も、
ヒール・プロレスラーのような演じ方を、していた。
これも過去号で、紹介したが、下記の動画だ。
トランプさんは、プロレスラーとしても適任だ。
YouTubeは、100万回再生で、ヒットとされるが、
下記の動画の再生数は、約4千万回だ。
画像をクリックで、この動画が、YouTubeで見れる ※出典出典:WWE | The Battle of the Billionaires.. .
※出典出典:WWE | The Battle of the Billionaires.. .
プロレスでは、
リングの下で、不意打ちで、他人を襲ってはだめだ。
だが、トランプさんは、
襲いかかり、馬乗りになって、殴りかかった。
-- 消費者 経済 総研 --
◆ヒール 炎上商法 スタイル
国の借金 増えても OK
国の借金 増えたら やばい
「 増えてもOK 」 では、盛り上がらない。
「 借金増えてもOK 」 では、ヒートしないのだ。
「 借金なんて とんでもない けしからん 」
と言う方が、盛り上がる。
つまり、ヒート・アップするのだ。
▼ネット番組では?
ネットで、動画を見ると、
自分の考えを、肯定する番組が、続々と出てくる。
アルゴリズムが、視聴者の志向を認識し、
似た番組を、お勧めとして、出してくるからだ。
つまり、下記となる。
「 そうだ そうだ その通りだ いいぞ いいぞ 」
これでは、似たような番組、ばかりになっていく。
敢えて、違う番組も、見てみては?
★どこで、見られるか?
↓
オールド・メディアで、見ることができる。
★消費減税なんかダメだと、言われれば、どう思う?
↓
「 減税NGなんて、 とんでもない けしからん 」 と、
盛り上がるかもしれない。
▼盛り上がる?
ネット・ユーザーが、オールド・メディアのTVを
見れば、下記と、なるかもしれない。
「 とんでもない けしからん 間違っている
〇〇教の信者だ 」
これは、どのような効果を、生むか?
↓
盛り上がるのだ。
ヒールの登場で、
視聴者のあなたはヒートアップするかもしれない。
▼あなたも ヒートUP してみては?
正当で、正論で、正しい情報を、提供する番組は、
あなたの役に立つ。
役に立つが、盛り上がらない、かもしれない。
先ほど、プロレスの、ヒール役の登場で、
ヒートUPして、盛り上がる話をした。
「 そうだ その通りだ 」 のネット番組だけではなく、
「 とんでもない けしからん 」 のTV番組で、
盛り上がってみれば?
かつてMXTVのニュース女子、という番組があった。
出演者の女医・西川史子が、下記趣旨の発言をした。
「 ある番組を、けしからんと、思う人もいるが、
それ、ヒールを、楽しむものでしょ。
あの番組は、そうやって、楽しいむものでは? 」
▼ついつい、また 見たくなる?
ヒール炎上系の番組に、関するコメントが、
ネット (X) 上で、凄かった。
「 けしからん ので、もう、この番組は、見ません! 」
と言うコメントもあった。
でもその人は、気になって、また見るかもしれない。
私(松田)も、ヒートUPする番組を、
また、見たくなってしまった (笑)
-- 消費者 経済 総研 --
◆関連ページ・リンク集
千円札は 日銀, 1円玉は 日本国
通貨 硬貨 紙幣 の 違い・歴史

| ■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので、 「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆である事を念頭に置いて下さい。 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、 対応して下さい。また「免責事項 」をお読みください。 ■引用 皆さまに、本ページの引用や、 URLの紹介などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件をご覧下さい。 |
- 【著作者 プロフィール】
- ■松田 優幸 経歴
(消費者経済|チーフ・コンサルタント)
◆1986年 私立 武蔵高校 卒業
◆1991年 慶応大学 経済学部 卒業
*経済学部4年間で、下記を専攻
・マクロ経済学(GDP、失業率、物価、投資、貿易等)
・ミクロ経済学(家計、消費者、企業、生産者、市場)
・労働経済
*経済学科 高山研究室の2年間 にて、
・貿易経済学・環境経済学を研究
◆慶応大学を卒業後、東急不動産(株)、
東急(株)、(株)リテール エステートで勤務
*1991年、東急不動産に新卒入社し、
途中、親会社の東急(株)に、逆出向※
※親会社とは、広義・慣用句での親会社
*2005年、消費・商業・経済のコンサルティング
会社のリテールエステートに移籍
*東急グループでは、
消費経済の最前線である店舗・商業施設等を担当。
各種施設の企画開発・運営、店舗指導、接客等で、
消費の現場の最前線に立つ
*リテールエステートでは、
全国の消費経済の現場を調査・分析。
その数は、受託調査+自主調査で多岐にわたる。
商業コンサルとして、店舗企業・約5000社を、
リサーチ・分析したデータベースも構築
◆26年間の間「個人投資家」としても、活動中
株式の投資家として、
マクロ経済(金利、GDP、物価、貿易、為替)の分析や
ミクロ経済(企業動向、決算、市場)の分析にも、
注力している。
◆近年は、
消費・経済・商業・店舗・ヒットトレンド等で、
番組出演、執筆・寄稿、セミナー・講演で活動
◆現 在は、
消費者経済総研 チーフ・コンサルタント
兼、(株)リテール エステート リテール事業部長
◆資格は、
ファイナンシャル・プランナーほか
■当総研について
◆研究所概要
*名 称 : 消費者経済総研
*所在地 : 東京都新宿区新宿6-29-20
*代表者 : 松田優子
*U R L : https://retail-e.com/souken.html
*事業内容: 消費・商業・経済の、
調査・分析・予測のシンクタンク
◆会社概要
「消費者経済総研」は、
株式会社リテールエステート内の研究部署です。
従来の「(株)リテールエステート リテール事業部
消費者経済研究室」を分離・改称し設立
*会社名:株式会社リテールエステート
*所在地:東京都新宿区新宿6-29-20
*代表者:松田優子
*設立 :2000 年(平成12年)
*事業内容:商業・消費・経済のコンサルティング
■松田優幸が登壇のセミナーの様子
- ご案内・ご注意事項
- *消費者経済総研のサイト内の
情報の無断転載は禁止です。
*NET上へ「引用掲載」する場合は、
①出典明記
②当総研サイトの「該当ページに、リンク」を貼る。
上記の①②の2つを同時に満たす場合は、
事前許可も事後連絡も不要で、引用できます。
①②を同時に満たせば、引用する
文字数・情報量の制限は、特にありません。
(もっと言いますと、
①②を同時に満したうえで、拡散は歓迎です)
*テレビ局等のメディアの方は、
取材対応での情報提供となりますので、
ご連絡下さい。
*本サイト内の情報は、正確性、完全性、有効性等は、保証されません。本サイトの情報に基づき損害が生じても、当方は一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。
- 取材等のご依頼 ご連絡お待ちしています
- メール: toiawase★s-souken.jp
(★をアットマークに変えて下さい)
電 話: 03-3462-7997
(離席中が続く場合は、メール活用願います)
- チーフ・コンサルタント 松田優幸
- 松田優幸の経歴のページは「概要・経歴」をご覧下さい。