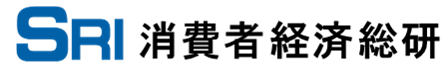消費税 減税・増税のメリット・デメリットを、わかりやすく解説
■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 リモートでの出演・取材にも、対応しています  消費者 経済 総研 チーフ・コンサルタント 松田優幸 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆であることを念頭に置いて下さい。 本ページ内容に関しては、自らの責任において対応して下さい。 また「免責事項」をお読みください ■引用 皆さまに、本ページの引用や、 リンク設定などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件 をご覧下さい。 |
- ■新聞|松田優幸の記事掲載
大手新聞から、筆者(松田)が取材を受け、
消費税の減税に、関する内容が、掲載されました。

- ■今回号の要約・ポイントは?
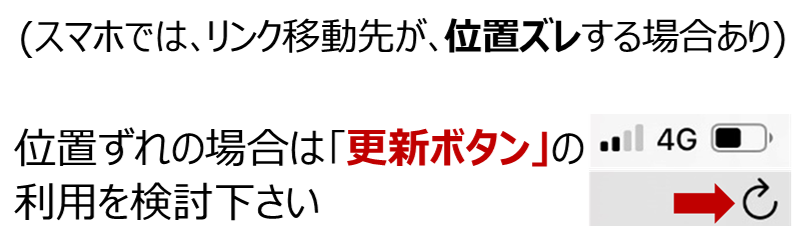 -- 消費者 経済 総研 --
-- 消費者 経済 総研 --
Q:消費税が、1989年に導入された時の
理由・必要性は、何か?
↓
A:いわゆる「クロヨン問題」が、きっかけである。
クロヨン問題は、
リンク先(クロヨン)から、ご覧頂きたい
-- 消費者 経済 総研 --
Q:過去の3回の消費税の「増税」は、いつか?
↓
A:1回目:1997年4月 ( 3% → 5% )
2回目:2014年4月 ( 5% → 8% )
3回目:2019年10月 ( 8% → 10% )
-- 消費者 経済 総研 --
Q:消費税の「メリット」は?
↓
A:
① 皆で、広く、薄く 負担。
所得税では、税の負担が、働く世代に、偏る。
一方で、消費税では、どうか?
国民の誰もが、買い物をする。
ほとんどの買い物で、消費税が発生する
消費税の税負担は、広く薄いのが、メリット
② 安定的。
法人税は、企業が赤字になれば、ゼロ円になる。
一方で、消費税では、どうか?
消費が、ゼロになる事は、あり得ないので、
「 消費税 ゼロ円 」 とはならない
消費税は、景気の変動に、左右されにくく、
税収額が安定的なのが、メリット
③ 捕捉率が良い。
前々項のクロヨン問題に対して、
消費税は捕捉率が高く、徴収漏れが少ない
-- 消費者 経済 総研 --
Q:消費税の 「 賛成派 」 は?
↓
A:企業は、法人税が減ったほうが、有利だ。
個人投資家は、金融所得税が少ない方が良い。
高額所得者は、所得税の累進税率が、気になる。
資産家の親族は、相続税が、気になる だろう。
自分に関する税金が、減ることを、
期待する人も、いるだろう。
その税金を減らすため、「薄く・広い消費税」の
増税に、賛成の人も、いるだろう。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:それは、自分勝手ではないか?
↓
A:べつに、悪いことではない。
様々な立場の人が、
様々な意見を言うのは、当然だ。
最終的には、国会での多数決で、決定される。
有権者は、選挙権を、行使すればいいのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:そもそも消費税では、誰が負担を、するのか?
↓
A:法律上:消費税は、事業者が、納付する。
実際上:消費税は、消費者が、負担する。
この件に関する解説は、後述してある
-- 消費者 経済 総研 --
Q:消費税の「デメリット」は、何か?
日本全体への影響が、大きいのではないか?
↓
A:そうだ。 全体への影響は、大きい。
GDPのメイン・エンジンの個人消費は、
消費税の増税のたびに、ダメージを受けた
下記が、近年のGDPの内訳の概数だ。
60% : 個人の消費
25% : 政府の支出・投資
15% : 企業の設備投資
個人消費へのダメージの解説は、後述する
-- 消費者 経済 総研 --
Q:消費税の 「私たちの給料」 への影響は?
↓
A:私たちの給料は、1997年まで、上昇した。
だが、97年の消費税の増税で、反転下落した。
そして、長い 「失われた20年」 が、始まった
-- 消費者 経済 総研 --
Q:消費税の減税は、いつか?
↓
A:現在の与党は「消費税の減税は無い」と言う。
野党は、政策公約に「消費税 減税」をうたう
-- 消費者 経済 総研 --
Q:与党は、消費税の減税を、なぜ、しない?
↓
A:「消費税の使い道が、決まっているからだ」と
現在の与党は、言っている
-- 消費者 経済 総研 --
Q:消費税は「使い道」は、社会保障なのか?
国の借金対策か? 法人税の穴埋めか?
「消費税の使い道」を、詳しく知りたい
↓
A:別ページで「使い道を、徹底解説」している。
ページ下段掲載のリンクから、ご覧頂きたい
-- 消費者 経済 総研 --
Q:GDP以外に、「私たちの給料」 への影響は?
↓
A:私たちの給料は、1997年まで、上昇した。
だが、97年の消費税の増税で、反転下落した。
そして、長い 「失われた20年」 が、始まった
-- 消費者 経済 総研 --
Q:2022年から、「悪いインフレ」と言われ始めた。
それは、なぜか?
↓
A:インフレで、物価が上昇しても、
それ以上に「賃金が上昇」すればokだ。
だが 「 物価UP率 > 賃金UP率 」 なので、
「悪いインフレ」である
-- 消費者 経済 総研 --
Q:値上げラッシュ・悪いインフレの対策は何か?
↓
A:「賃金UP」以外では、消費税の減税がよい。
「物価が 3% UP 」 ならば、
「消費税の 3%増税 」 と、概ね同じだ。
消費税が3%下がれば、国民の財布は傷まない
-- 消費者 経済 総研 --
Q:消費税の減税が、できなくても
せめて生活必需品だけでも、軽減されないか?
↓
A:現在は、基本税率は10%だが、
生活必需品は、8%の軽減税率だ。
中長期的な消費税の減税の議論とは別に、
軽減税率だけでも、下げるのは、検討に値する
-- 消費者 経済 総研 --
Q:消費税によって、給料、個人消費、失業率は、
どのように、変化したのか?
↓
A:次項以降の解説編をご覧頂きたい。
また 「消費税の使い道」 などの別テーマの
リンク先を、本ページの下段に掲載してある。
-- 消費者 経済 総研 --
Q:消費税に対する、各政党の考えは、どうか?
↓
A:本ページ下段を、ご覧頂きたい。

- ■過去の増税のデメリットは?
- ◆消費税で、損するのは誰?
「そもそもとして、消費税で、誰が、損をする?」
消費税の法律上の納税者は、事業者だ。
だが、実際上は、消費税は、消費者が負担している。
消費税の増税で、損をするのは、消費者だ。
この点は、本ページの最後に解説してある。
-- 消費者 経済 総研 --
◆過去の消費税の増税では、どうなったか?
順番に、消費増税の影響を見ていく。

- ■増税1回目(1997年)の影響は?
- 1回目の消費増税(3→5%)は、1997年4月だった。
増税の影響を、まずは人々の暮らしの視点で見る。
-- 消費者 経済 総研 --
◆生活者の収入は?
平成元年から、生活者の年収を、見ていく。
下図の通り、1997年まで「年収」は、上昇した。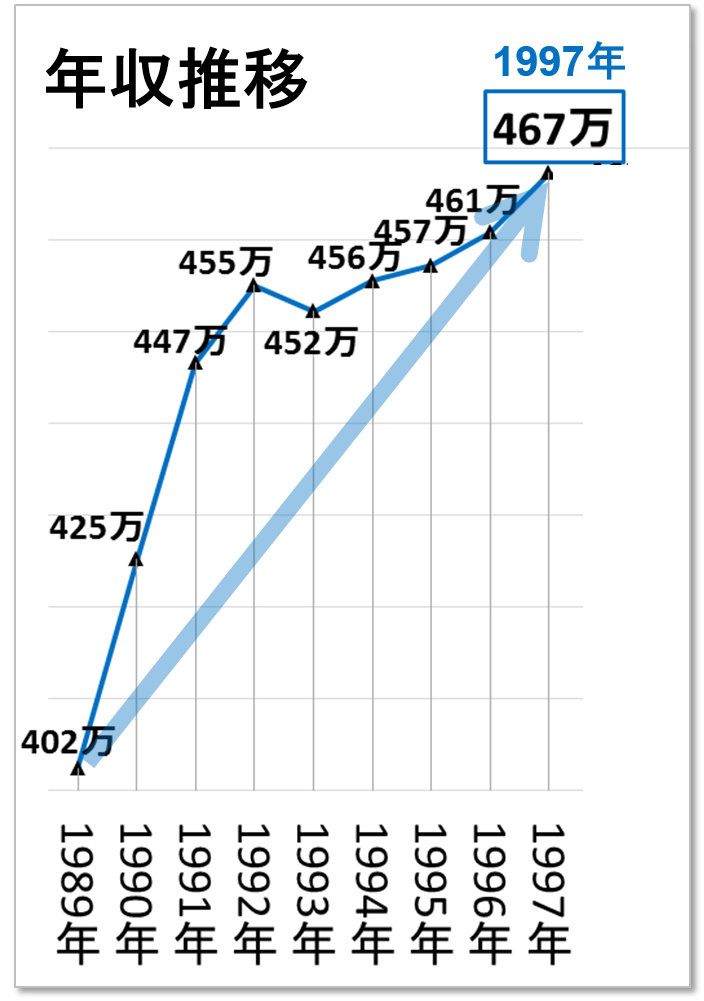 ※単位:円。年収=給料、手当及び賞与の合計
※単位:円。年収=給料、手当及び賞与の合計
※出典:国税庁給与統計データ
しかし1997年で、反転下落してしまった。
その原因 とは?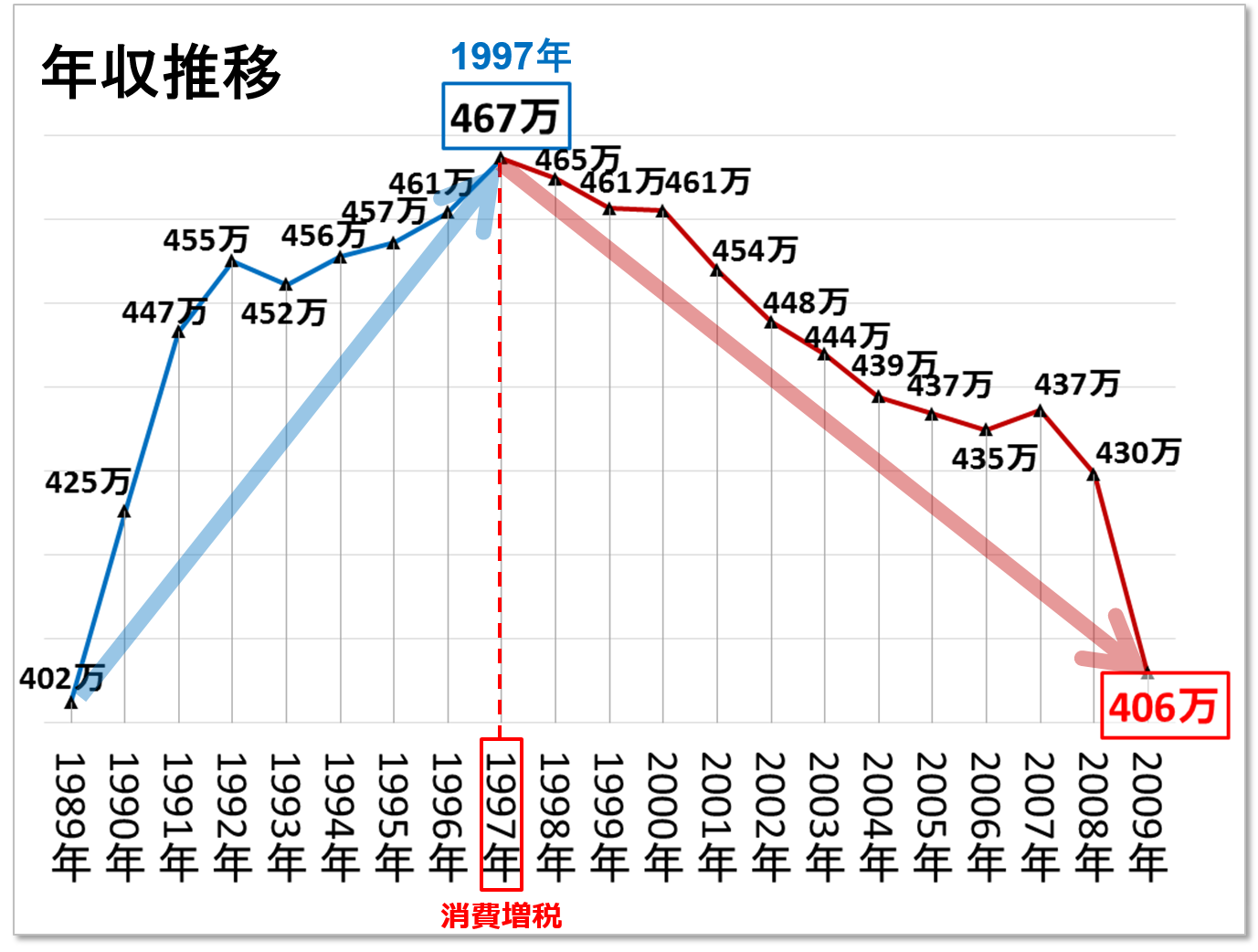
1997年の 消費税の増税で、
下落トレンドに、変わってしまったのだ。
一時的な下落では、済まなかった。
長期間も、下落が続いてしまったのだ。
つまり、第1回目の消費増税で
「失われた20年」が、始ってしまったのだ。
-- 消費者 経済 総研 --
◆失業率は?
失業率は、96年→97年は、横ばいだった
しかし消費増税で、大きく上昇していった。(下図)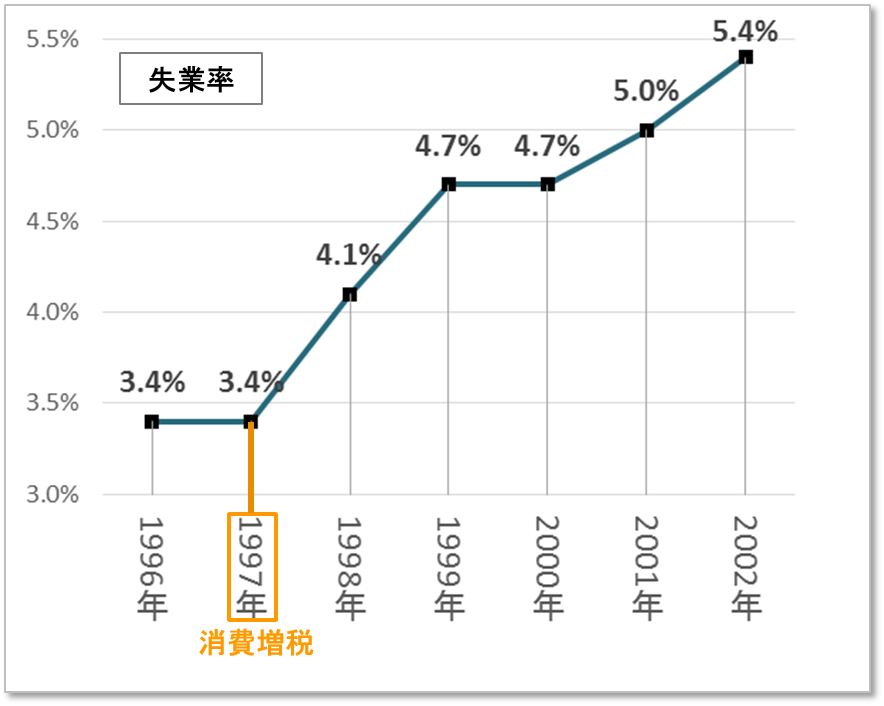

- ■増税2回目(2014年)の影響は?
- ◆実質年収は、下がった?
2012年から、第2次・安倍政権が、始まった。
複数年の期間で見れば、実質年収は上昇した。(下図)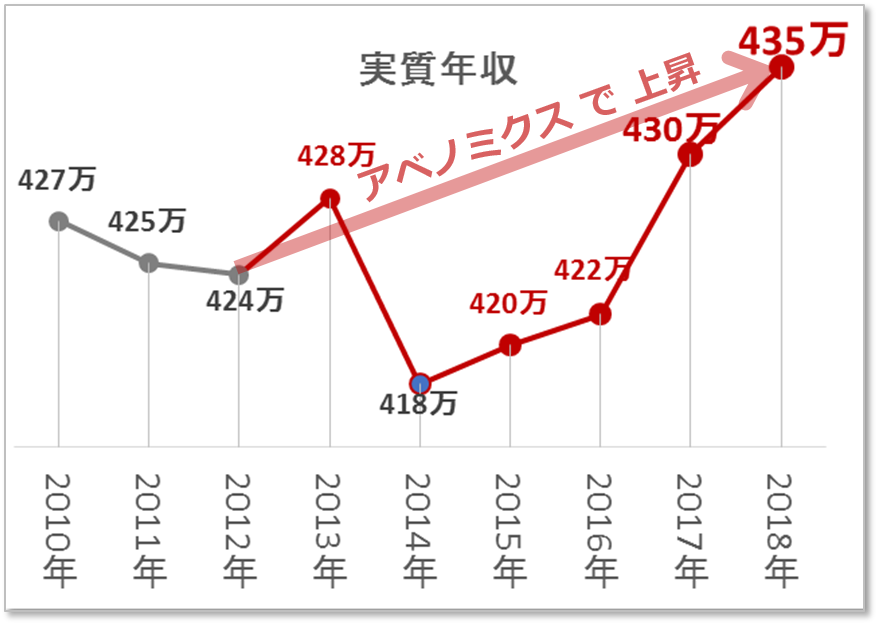
上図の中で、2014年に注目したのが、下図青線だ。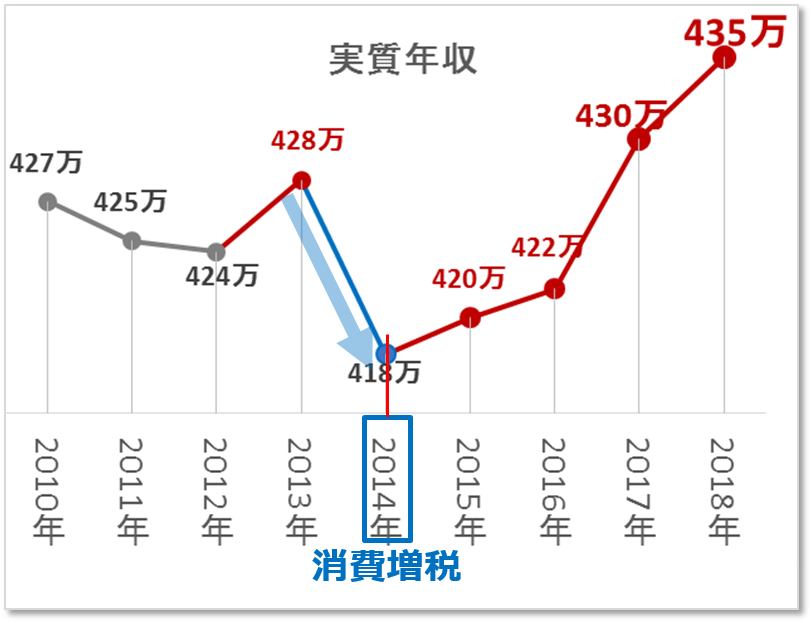 ※国税庁給与統計と総務省CPIから消費者経済総研が2つのグラフを作成
※国税庁給与統計と総務省CPIから消費者経済総研が2つのグラフを作成
消費増税が無ければ、赤線の上昇トレンドだけだ。
増税が無ければ、国民は、楽な生活であったろう。
この項の「実質年収」の詳しい解説は
本ページ下段記載のリンク先から、ご覧頂きたい。
-- 消費者 経済 総研 --
◆個人消費では、どうか?
GDPの 近年の おおまかな内訳は、下記の通りだ。
・60% が、個人の消費
・25% が、政府の支出投資
・15% が、企業の設備投資
つまり、経済のメイン・エンジンは「個人消費」だ。
そこで、GDPの内訳項目の中の
個人の「消費支出」に、注目してみる。
2013年度から、アベノミクスが、始まった。
下図の 「 緑の ➡ 」 が、アベノミクス効果である。
「黄色矢印 ➡」よりも、伸び率はアップしている。
つまりアベノミクスで、消費支出は、加速した。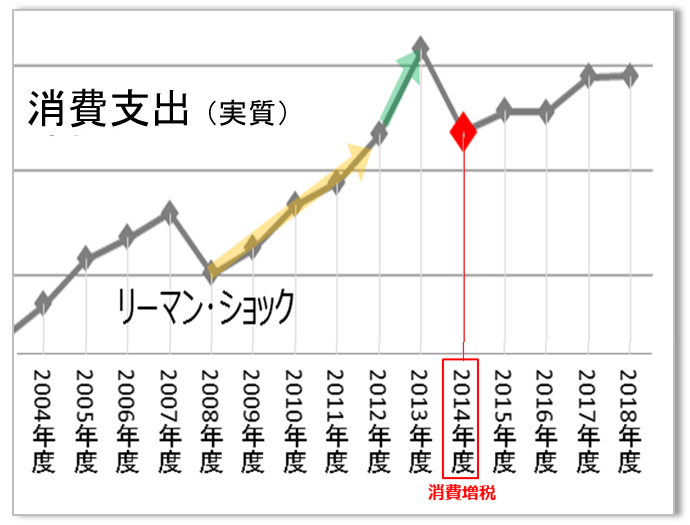
しかし、2014年の 消費税の増税で、急落した。
アベノミクスは、消費増税で、台無しとなった。

- ■増税のたびに、下落ダメージ?
- ◆3つのショックで下落
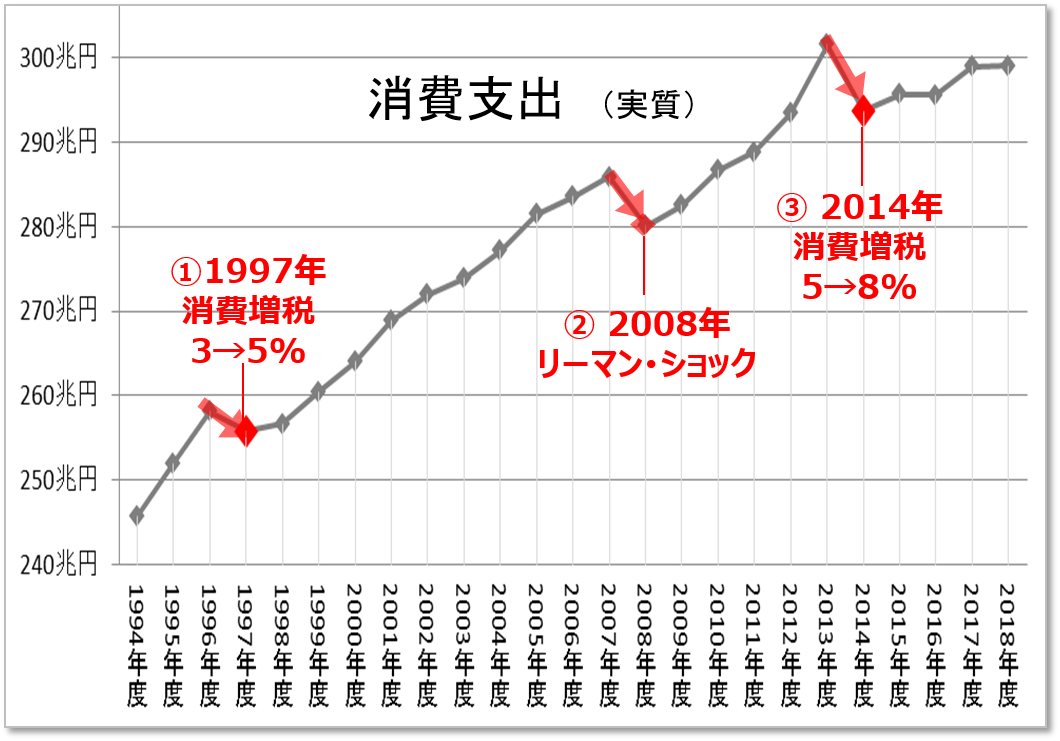
上のグラフの中で、下記の3つに注目する。
① 1997年:3→5%の 消費増税ショック
② 2008年:リーマン・ショック
③ 2014年:5→8%の 消費増税ショック
3つのショック前までは、消費支出は拡大した。
しかし、この3つのショックで、下落に転じる。
増税のたびに、経済のメインの消費は、下落だ

- ■下落から回復しても、減速?
- ◆1997年の増税の「前と後」を比較
増税前の伸び率と、増税後の伸び率はどうか?
2つ伸び率を、比較する。
増税前・赤➡ と、増税後・黄➡ では、どうか?
後者の方が、低くなってしまった。(下図)
増税で下落した後は、回復しても、元に戻らない。
消費の拡大は、「 減速 」してしまうのだ。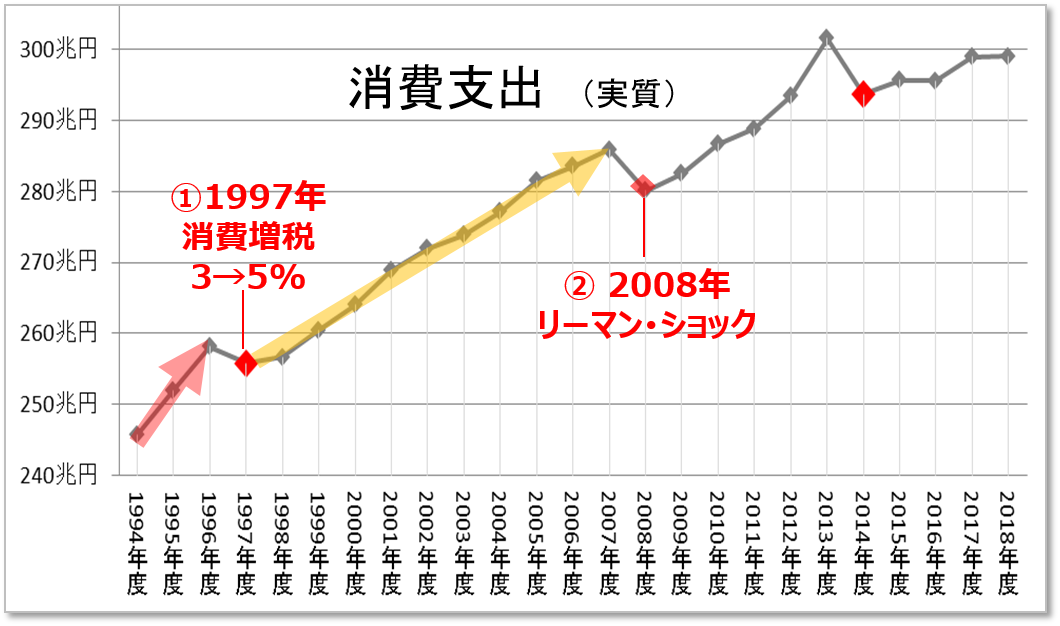
-- 消費者 経済 総研 --
◆2014年の増税の「前と後」を比較
続いて、2014年の増税の「前と後」を比較する。
増税前・緑➡ と、 増税後・青➡ では、
後者の方が、低くなった。
2回目の増税でも、消費は「減速」してしまった。
増税・下落後は、回復しても、元のペースに戻らない。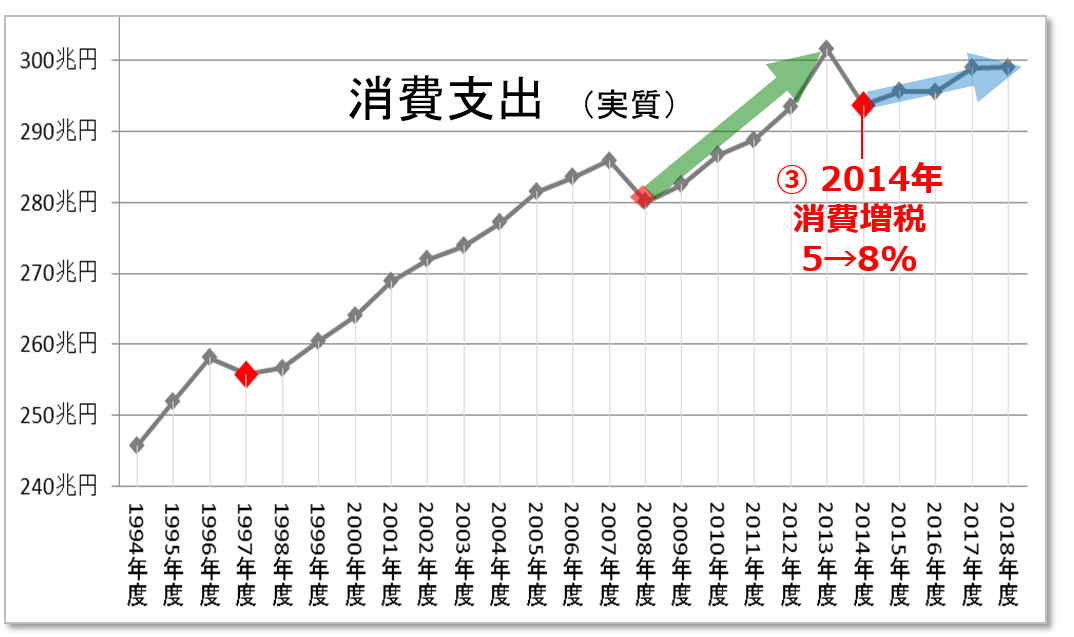
-- 消費者 経済 総研 --
◆増税のたびに、下落し、回復しても減速
下記グラフは、「3つの傾き」を、比較したものだ。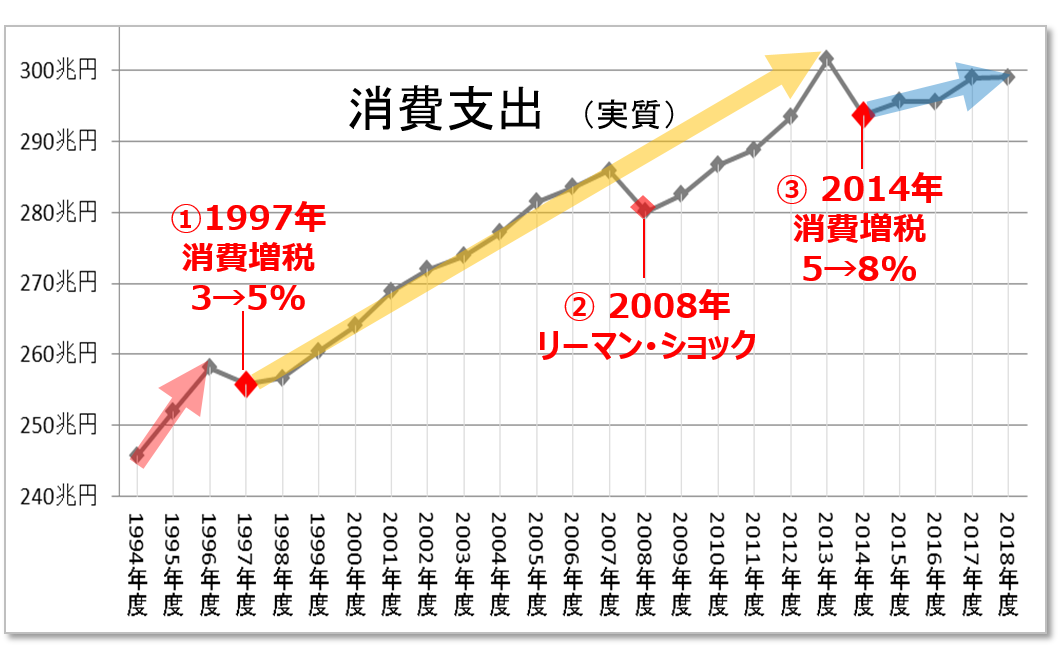
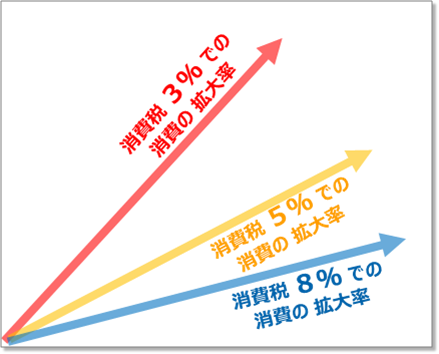
消費税を、増税するたびに 「下落」 した。
回復しても、消費者へ重しが乗っかり 「減速」する。
-- 消費者 経済 総研 --
◆リーマン・ショックでは、減速しない?
下図の黄色➡は、リーマン・ショック前までの線。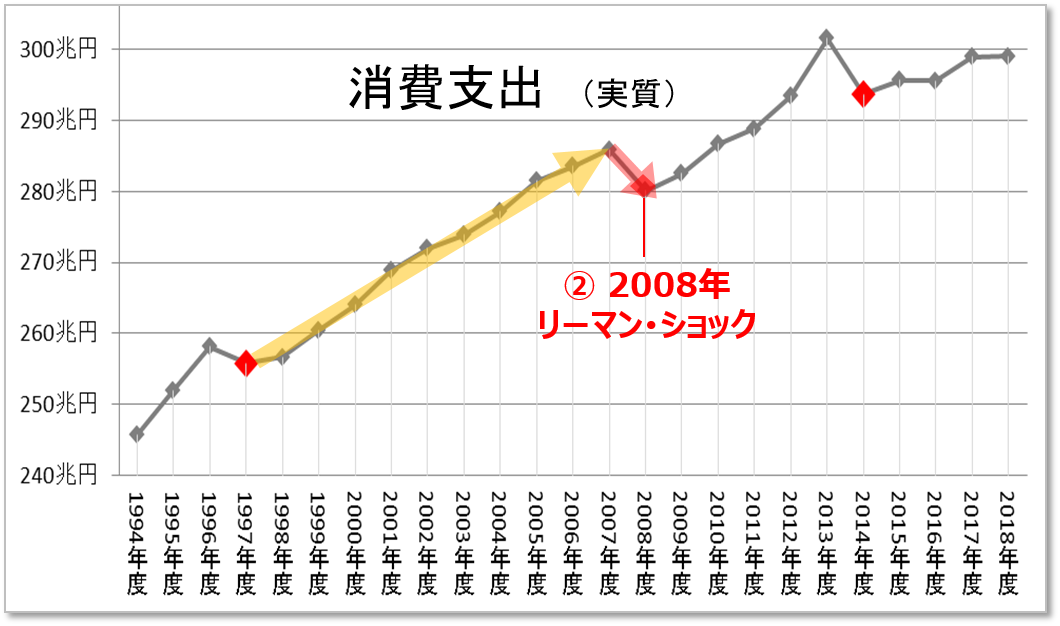
上図の黄色を、2013年まで伸ばしたのが、下図だ。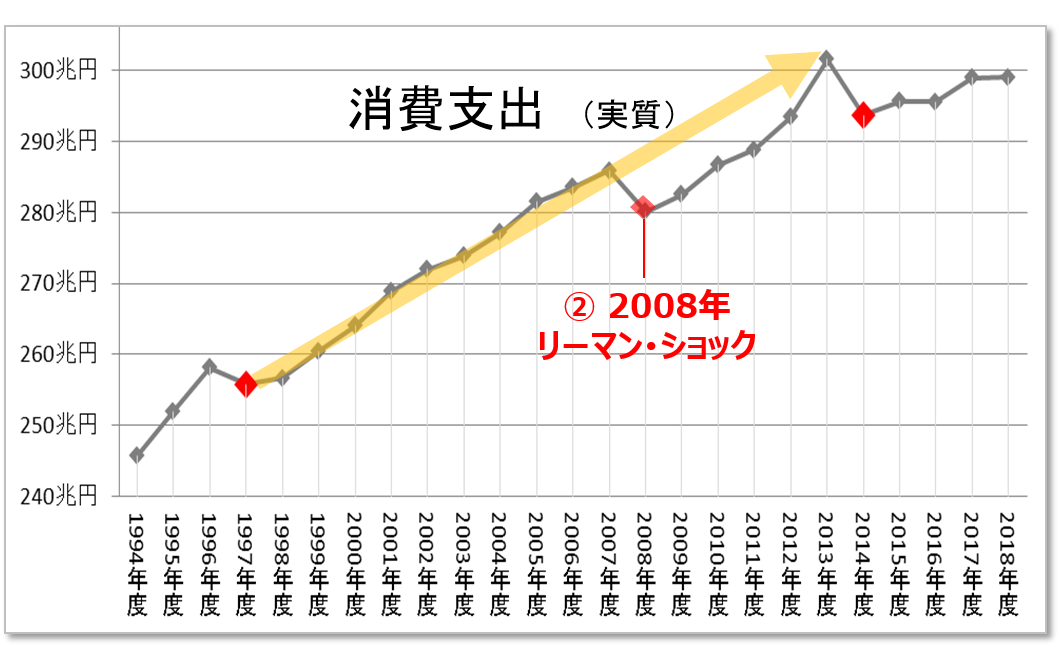
伸ばした黄色の➡で、わかることは、次のことだ。
リーマン・ショックで、消費が落ちても、復活した。
そして、「元の伸び率に、戻った」 のだ。
その理由は何か?
リーマンショックは、一時的なショックだからだ。
しかし消費増税では、毎年毎年、重しが継続する。

- ■2019年の増税(8→10%)では?
- 2019年10月に、3回目の増税(8→10%)があった。
2020年はコロナで、経済に大きな影響があった。
よって2020年は、経済指数も、激しく変動した。
そのため、「8→10%増税後」の影響については、
2020年は除外し、2019年で見てみる。
2019年10-12月期と、18年10-12月期とを
比較した減少率の矢印を、下図に挿入した。
(グレーの色の矢印)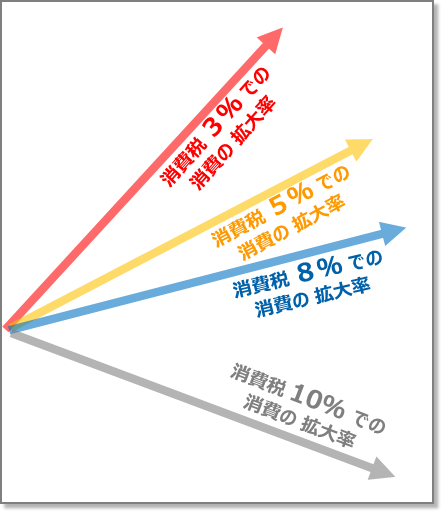
-- 消費者 経済 総研 --
◆増税のデメリット
ここまで、過去の消費税の増税を、見てきた。
増税で、生活の負担増になり、消費は落ち込んだ。
そして、個人消費は、マイナスになった。
景気悪化等の悪影響のきっかけに、なってきた。
増税は、デメリットが、多いことが、わかる。
続いて、消費税の減税のメリットを、見ていく。

- ■消費税を減税すると、どうなる?
- 消費税は、1989年に導入以来、3回も増税された。
そのたびに、消費は下落し、その後も減速継続だ。
消費税の「減税」を、日本は実施したことが無い。
そこで、減税した場合の効果を、推測してみたい。
増税の前後とも、消費グラフは、強い線形性だ。
※線形性とは、変数と変数の関係が、直線的であること
強い線形性から「税率」と「消費」の関係は単純だ。
「減税」したら、「下図の紫矢印」のように、
「消費」が戻ることは、十分に予想できるだろう。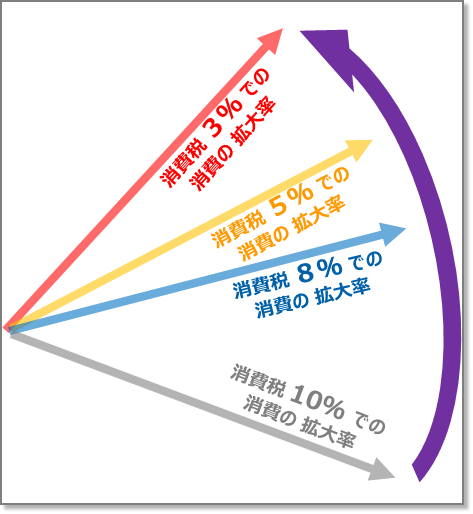
-- 消費者 経済 総研 --
◆「現金給付」と「消費税の減税」との比較は?
コロナで、経済・国民生活には、大きな影響が出た。
20年、1人10万円の特別定額給付金が支給された。
1世帯が、2人なら20万円、4人なら40万円だ。
1世帯で、年間400万円を、消費支出するとする。
その場合、消費税額は400万円×10%=40万円。
※消費税が、非課税又は軽減税率が、適用される
取引もあるが、ここではいずれも、10%課税とした。
消費税0%なら、1世帯当り、年間40万円の救済だ。
消費税5%なら、1世帯当り、年間20万円の救済だ。
「1人10万円の現金給付」と「消費税減税」どちらか?
様々なコロナ支援策は、煩雑で、時間もかかった。
消費減税なら、国民の負担は、大きく軽減だった。
-- 消費者 経済 総研 --
◆減税は野党・自民党(有志)は賛成。政府は?
野党は、消費税の増税には、反対してきた。
「消費税収を、社会保障などに充てる」
との3党合意の経緯があるため、政府は消極的だ。
しかし自民党でも、一部の有志が、
「消費税減税の緊急声明」を、2020年に出した。
与野党共に、消費税の減税の議論は、増えている。
-- 消費者 経済 総研 --
◆消費税の 使い道は?
消費税は、下記の財源となっている
・社会保障(年金、医療・介護)と
・人づくり革命(子供・子育て、教育無償)
「消費税は、社会保障のため」
と言えば、増税しやすくなる。
消費税は、普通税であって、目的税ではない。
しかし消費税を、「事実上の目的税」にしている。
「お金に色」 を、付けてしまったのだ。
「消費税が目的税」なのは、諸外国で見当たらない。
日本の消費税の使い道は、「社会保障」ではなく、
「国の借金対策」や「法人税の穴埋め」も言われる。
「消費税の使い道」は、年によって、変化してきた。
別ページに「 消費税使い道の 徹底解説 」がある。
本ページ下段掲載のリンクから、ご覧頂きたい。
-- 消費者 経済 総研 --
◆消費税の代替の財源は?
消費税の年間税収は、20兆9714億(2020年度)だ。
消費税減税の場合、21兆円の代替財源は、どうか?
消費税を減税すれば、消費が拡大しGDPが成長し、
自然増収(法人税、所得税等の税収増加)が見込める。
消費税減税→消費拡大→GDP成長→自然増収で、
まかなえば、良いのだ。
不足が生じたら、国債の増発でよい。
「国債増発は、NG」と言う人が、まだいる。
国債増発は、問題ではない。
別ページに「日本は 借金大国 ではない」がある。
本ページ下段掲載のリンクから、ご覧頂きたい。
こうして、消費税の減税は、
「 悪いインフレ での 生活支援 」
さらに「 景気対策 」 にもなる。
このスキームは、充分、検討の価値がある。
日本は減税の議論を、更に進めるべきではないか。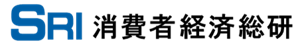
◆世界各国では、どうしている?
海外では、下記のような様々な外国が、
コロナ禍で、消費税の減税を、実施した。
アジアでは、
中国、韓国、マレーシアが、
欧州では、
イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、
スペイン、オランダ、ベルギーなど
※ここでの消費税は付加価値税を含む
-- 消費者 経済 総研 --
◆2025年 日本の 政党は?
2025年7月の参院選へ向けて、
各政党が、徐々に、政策の表明を、始めている。
その代表は、「 消費税 」 についてだ。
★2025年7月の、参院選が、近づいている。
参院選での、「 争点 」 は、何か?
↓
「 消費税 の 減税 」 は、大きな争点だ。
★減税する場合、減税で減る財源を、
まかなう代替の財源は?
↓
各党で、様々な財源が示されている。
主なものは、下記だ。
所得税・法人税の増税
大企業や富裕層への課税強化
定額減税・終了での、税収増を、活用
積立金や剰余金を、活用
防衛費の削減
歳出の削減 ( 歳出改革・行政改革 )
国債増発
自然増収 (経済成長での税収増)
★自然増収 ( 経済成長での 税収増 ) とは?
↓
下記の流れだ。
消費税の減税は、商品の値引きと一緒
↓
仮に、消費税が、10% → 0% になれば
↓
スーパー・マーケットでの、10%値引きと一緒
↓
消費者の、買い物のマインドが、高まる
↓
スーパーマーケットの、売上も、増える
↓
店舗企業の、売上・利益がUP
↓
店舗企業の、外注予算も、UP
↓
外注先の、様々な企業の、売上・利益もUP
↓
店舗企業や、様々な外注先の、企業の利益UP
↓
幅広く、企業の、賃金の支払い原資も、増える
↓
消費者の賃金が、更にUPする
↓
消費者の、買い物の意欲が、更にUP
↓
(先ほどの 繰り返しで) 様々な企業の売上・利益UP
↓
景気にプラスの、好循環サイクルが回る
これが、「 経済成長・好循環サイクル 」 だ。
企業の利益がUPすると
↓
企業の利益へ、課税する、法人税もUP
消費者の賃金が増えると
↓
所得税もUP
消費が活発になると
↓
消費税もUP
これが、「 経済成長での 自然増収 」 だ。
▼2つの どちらが 良いか?
[1] 増税で、税率を上げて、税収UP
[2] 経済成長で、自然と、税収UP
[2] が、良いに、決まっている。
これが、「 経済成長での 自然増収 」 だ。
[2] なら、下記となり、三方良しだ。
・国の 税収予算も 増え、
・消費者の お金も 増え、
・企業の 売上・利益も 増える
-- 消費者 経済 総研 --
★現在の各政党の、消費減税に、関する考えは?
↓
下記の通りだ。
消費税の、減税・廃止の考えが、強い順に、掲載する。
減税した場合、減る財源の、代替財源も、記載した。
24年と25年での、姿勢の変化も、記載した。
2024 衆院選での 政策公約
↓
2025 参院選へ向けた 方針
▼れいわ
2024年:消費税 廃止
↓
2025年:同上
れいわは、消費税の、最大の反対派。
その姿勢は、2024年も、2025年も、不変。
代替の財源は、
所得税・法人税の増税や、国債増発
▼参政
2024年:消費税を、減税
↓
2025年:消費税の、段階的廃止
参政は、「減税」 から、「段階廃止」 へ、踏み込んだ。
よって、減税・廃止志向が、より強まってきた。
代替の財源は、
国債増発、自然増収 (経済成長での税収増) や、
行政の無駄な支出の削減
▼社民
2024年:消費税を、3年間ゼロ%
↓
2025年:同上 + 食料品・消費税を、直ちに無くす
社民は、減税志向が、高まった。
代替の財源は、
大企業の内部留保・課税や、防衛費の削減も検討
▼共産
2024年:消費税廃止を目指し、当面5%に
↓
2025年:同上
代替の財源は、
共産党は、大企業や富裕層への課税強化
▼国民民主
2024年:時限的に、消費税 一律 5%
↓
2025年:時限的に、消費税 一律 5%
赤字国債を、堂々と発行
国民民主は、5%への減税は、変わらず。
財源は、
「 赤字国債 堂々と 発行 」 と、積極派の姿勢を強化
その他の財源として、
自然増収 (経済成長での税収増)、歳出改革。
▼維新
2024年:一時的に、8%に、減税
↓
2025年:2年限定で、食料品の消費税 0%
2024と、2025では、減税の対象が、変わった。
だが、減税の額は、大きくは、変わらない。
代替の財源は、
定額減税・終了での税収増、
行政改革・財政健全化、自然増収(経済成長の税収増)
▼立憲
2024年:言及無し
↓
2025年:1年・2年間の、食料品の消費税 0%
野田代表は、2012年・増税決定の「 ザ・当事者 」だ。
立憲の党内は、増税派と減税派に、別れている。
徐々に、減税派が、増えつつあり、
最新では、消費減税を、党の方針とした。
また、減税の実施までの短期の支援として給付金も。
代替の財源は、
積立金や剰余金を活用する。
▼公明
2024年:消費税の言及無し
↓
2025年:減税 + つなぎ給付金
赤字国債の検討も、ありうる。
大幅に、減税側に、シフトする可能性があった。
だが、自公連立なので、
自民の方針を配慮し、消滅する可能性も。
実際に徐々に、消費税の減税志向は、低下している。
▼自民
2024年:消費税の減税なし
↓
2025年:現金給付や、消費税の減税を、検討。
赤字国債を、出さない範囲で。
自民でも、消費税の、減税の可能性が、出た。
だが、「 結局、減税しない 」 との予想が多い。

- ■消費税で、損するのは誰?
- 「そもそもとして、消費税で、誰が、損をする?」
消費税の法律上の納税者は、事業者だ。
だが、実際上は、消費税は、消費者が負担している。
消費税の増税で、損をするのは、消費者だ。
消費税では、一般消費者の財布が痛むのだ。
これは、ややこしいので、
本稿の最後に、この点を解説しておく。
-- 消費者 経済 総研 --
◆誤解の原因 その1
誤解の原因の1つは、企業も「物品購入」の時に
「本体価格+消費税」を、支払っているからだ。
--消費者 経済 総研--
◆企業は、消費税を、どう扱う?
企業が物品を買えば、税込みの代金を支払う。
下記のAからBを引いた額を、企業は国に納める。
A 販売時:
企業が商品を、販売した時に、
本体価格とあわせて受領する消費税
B 購入時:
企業が、物品を、購入した時(仕入れをした時)に、
本体価格とあわせて支払う消費税
*消費税なしの場合は?
A販売時:
「税抜き本体価格:140円」(消費税なし)の
商品を販売した時
B購入時:
「税抜き本体価格:100円」(消費税なし)の
物品を購入(仕入れ)した時
この場合の会社の利益は
「本体価格:140円」-「本体価格:100円」=40円だ。
利益の額の40円が、会社に残る。
*消費税10%の場合は?
A販売時:
「税抜き本体価格140円」+「消費税14円」
=計154円の商品を、販売した時
↓
受領した消費税は、14円
B購入時:
「税抜き本体価格100円」+「消費税10円」
=計110円の物品を、購入した時
↓
支払った消費税は、10円
Aの14円から、Bの10円を、引いた額の4円を
この会社は、国に納める。
入金・出金の差額は、
出金154円-入金110円=44円だ。
そして上記の4円を、国へ出金する。
44円から4円が減るので、会社には40円が残る。
この場合の会社の利益は
「本体価格140円」-「本体価格100円」=40円だ。
利益の額の40円が、会社に残る。
*消費税が、「なし」と「あり」との比較では?
両方とも、40円の利益が、会社に残る。
消費税による、企業へのダメージはない。
しかし「消費税なし」なら140円の商品が、
「消費税あり」により154円になるので、
いわば「強制的な値上げ」のような状態になる。
その分は、商品は売れにくくなる。
商品の売れ行きが落ちるので、
この点において、企業もダメージを受ける。
-- 消費者 経済 総研 --
◆どの視点で、見るか? で変わる?
上記の説明は、消費税が課税される時に、
企業が、税金分を、販売価格に転嫁するケースだ。
消費税が、「 導入 or 増税 」 された時に、
価格転嫁せず「税込み価格を、据え置き」だと違う。
C 110円で販売 消費税なし
税抜・本体価格110円+消費税ゼロ
= 計 110円 で販売
D 110円で販売 消費税10%・転嫁なし
税抜・本体価格100円+消費税10円
= 計 110円 で販売
消費税10円を、企業は国に納める。
・転嫁した Cの企業 では、
手元に、110円獲得
・据え置きした Dの企業 では、
手元に、100円獲得 ( 110円販売 - 10円納税 )
Dでは、企業は、損してしまうので、
増税分は、価格転嫁し、結局、消費者が負担となる。
-- 消費者 経済 総研 --
◆どのくらい 価格転嫁 しているのか?
消費税の増税で、
大半の事業者(企業等)は、価格転嫁している。
よって、消費税で損するのは、消費者だ。
▼調査|消費税率の引上げに関する価格転嫁の状況
88.6%の事業者が、全て転嫁できている
1.8%の事業者が、全く転嫁できていない
3.8%の事業者が、一部転嫁できている
5.8%の事業者が、経営戦略上転嫁しなかった等
※出典:経済産業省|消費税の転嫁状況に関するモニタリング調査

- ■関連テーマ・別ページ リンク集
- 別ページでの、関連テーマの解説は、
下記の青色下線部のリンク先から、ご覧頂きたい。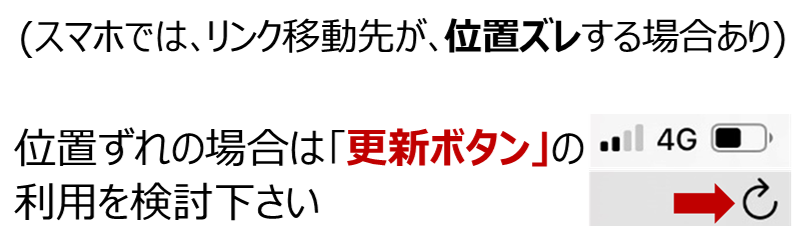
◆消費税の 使い道 歴史 の詳細
消費税 使い道 内訳をグラフで解説 | 目的,歴史も
◆日本は スウェーデンより 消費税多い
「皆が知らない消費税謎」に迫った
日本は スウェーデンより 消費税 多い国?
◆日本は 借金大国 ではない?
【なぜ日本借金大国は嘘?】国の借金は大丈夫
◆実質年収とは?
実感なき景気回復とは?|わかりやすく3分解説

| ■番組出演・執筆・講演等のご依頼は、 お電話・メールにてご連絡下さい。 ■ご注意 「○○の可能性が考えられる。」というフレーズが続くと、 読みづらくなるので、 「○○になる。」と簡略化もしています。 断定ではなく可能性の示唆である事を念頭に置いて下さい。 このテーマに関連し、なにがしかの判断をなさる際は、 自らの責任において十分にかつ慎重に検証の上、 対応して下さい。また「免責事項 」をお読みください。 ■引用 皆さまに、本ページの引用や、 URLの紹介などで、広めて頂くことを、歓迎いたします。 引用・転載の注意・条件をご覧下さい。 |
- 【著作者 プロフィール】
- ■松田 優幸 経歴
(消費者経済|チーフ・コンサルタント)
◆1986年 私立 武蔵高校 卒業
◆1991年 慶応大学 経済学部 卒業
*経済学部4年間で、下記を専攻
・マクロ経済学(GDP、失業率、物価、投資、貿易等)
・ミクロ経済学(家計、消費者、企業、生産者、市場)
・労働経済
*経済学科 高山研究室の2年間 にて、
・貿易経済学・環境経済学を研究
◆慶応大学を卒業後、東急不動産(株)、
東急(株)、(株)リテール エステートで勤務
*1991年、東急不動産に新卒入社し、
途中、親会社の東急(株)に、逆出向※
※親会社とは、広義・慣用句での親会社
*2005年、消費・商業・経済のコンサルティング
会社のリテールエステートに移籍
*東急グループでは、
消費経済の最前線である店舗・商業施設等を担当。
各種施設の企画開発・運営、店舗指導、接客等で、
消費の現場の最前線に立つ
*リテールエステートでは、
全国の消費経済の現場を調査・分析。
その数は、受託調査+自主調査で多岐にわたる。
商業コンサルとして、店舗企業・約5000社を、
リサーチ・分析したデータベースも構築
◆25年間の間「個人投資家」としても、活動中
株式の投資家として、
マクロ経済(金利、GDP、物価、貿易、為替)の分析や
ミクロ経済(企業動向、決算、市場)の分析にも、
注力している。
◆近年は、
消費・経済・商業・店舗・ヒットトレンド等で、
番組出演、執筆・寄稿、セミナー・講演で活動
◆現 在は、
消費者経済総研 チーフ・コンサルタント
兼、(株)リテール エステート リテール事業部長
◆資格は、
ファイナンシャル・プランナーほか
■当総研について
◆研究所概要
*名 称 : 消費者経済総研
*所在地 : 東京都新宿区新宿6-29-20
*代表者 : 松田優子
*U R L : https://retail-e.com/souken.html
*事業内容: 消費・商業・経済の、
調査・分析・予測のシンクタンク
◆会社概要
「消費者経済総研」は、
株式会社リテールエステート内の研究部署です。
従来の「(株)リテールエステート リテール事業部
消費者経済研究室」を分離・改称し設立
*会社名:株式会社リテールエステート
*所在地:東京都新宿区新宿6-29-20
*代表者:松田優子
*設立 :2000 年(平成12年)
*事業内容:商業・消費・経済のコンサルティング
■松田優幸が登壇のセミナーの様子
- ご案内・ご注意事項
- *消費者経済総研のサイト内の
情報の無断転載は禁止です。
*NET上へ「引用掲載」する場合は、
①出典明記
②当総研サイトの「該当ページに、リンク」を貼る。
上記の①②の2つを同時に満たす場合は、
事前許可も事後連絡も不要で、引用できます。
①②を同時に満たせば、引用する
文字数・情報量の制限は、特にありません。
(もっと言いますと、
①②を同時に満したうえで、拡散は歓迎です)
*テレビ局等のメディアの方は、
取材対応での情報提供となりますので、
ご連絡下さい。
*本サイト内の情報は、正確性、完全性、有効性等は、保証されません。本サイトの情報に基づき損害が生じても、当方は一切の責任を負いませんので、あらかじめご承知おきください。
- 取材等のご依頼 ご連絡お待ちしています
- メール: toiawase★s-souken.jp
(★をアットマークに変えて下さい)
電 話: 03-3462-7997
(離席中が続く場合は、メール活用願います)
- チーフ・コンサルタント 松田優幸
- 松田優幸の経歴のページは「概要・経歴」をご覧下さい。